<< 4:00~5:00




無骨な廃コンテナの内側にはボロ布を継ぎ接ぎしたカーペットが敷かれ、にわかに彩りがもたらされていた。
その上にはちゃぶ台が一つ。載せられたガスコンロが鍋を温め、こぽこぽと湯がわいている。
中には人参と白菜、ブナシメジ、ネギ……それから豆腐が浮かび上がってくるところだった。
「おーし、肉行くよ?」
美香は『しゃぶしゃぶ用』『2割引』とシールが張られたラップを破いて豚肉を鍋の中へ放り込む。
一方の一穂はというと、とりあえずアクを取るのだけは手伝った。
「さ、しっかり食べなさい。ずーっと家無しでいたんでしょ」
言いながら、美香は鍋から肉をつまみ上げる。
「家がなくとも生きていくことはできました。栄養状態にも今の所問題はありません」
「そういう問題じゃないでしょーよ……」
「廃棄されたコンテナに無断で住み着くのは犯罪であり、そちらのほうが問題と思われますが」
「いいのよバレなきゃ。あたしの力で壁の振動を抑えてあるから声も漏れないし。
第一犯罪ってんならこのコンテナだってきちんと処分されたもんじゃないんだし、五十歩百歩だわ」
このコンテナは、コヌマ区の森の中にぽつんと棄てられていたものだった。
「……空の下で寝てて、デビアンスに襲われたんじゃなくって」
「就寝時ではありませんがDE-317と遭遇しました。対象はこの町の住民と思しき人物に殺害されました。WSO職員規則に従えば―――」
一穂の言に、美香は二枚目の豚肉を口に含んだまましばし静止した。
「しゃーないしゃーない! 場合が場合だわ。
無事に帰れたらちゃんと報告しましょ……ってか、今はまだ、帰れるかどうかだってわかんないけどね」
「美香さんは、先ほどのDE-96の他にはなにかデビアンスに遭遇したのですか?」
DE-96―――あの波の中に潜む怪物は、今はクーラーボックスの中に収められ、南京錠つきの鎖でぐるぐる巻きにされている。
「や、あんだけ……とはいえ、他にも来てるって思うのがフツーよね。
あーもうどうすりゃいいのよったく、581とか977とか来てたらって考えると、えェい!」
美香は野菜と肉とをまとめて頬張り、しばらく噛んでから炭酸のジュースで飲み下す。
「……なんでこんなことになっちゃったんだろうね。わかんないよ、あたし」
カスミ湖では絶えず強かさを湛えていた美香の目は、今やすがるようなものに変わり、絶対の記憶力を誇る一穂へと向けられた。
が、
「僕もです」
「へ?」
「WSO研究棟からこの街へ転移する前後の記憶がありません。
なにか異常なことがあったと思われます」
美香はきょとんとしていた。
異常だなんて、そんなの言われるまでもない。
もう何もかもが異常だ。

☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆
その世界の人類は、ある時から社会に受け入れるものと除けるものを決め、選り分けるようにした。
受け入れたのは、挙動について再現性があるもの。自然科学の方法論で対応しきれるようなもの。努力と信念と敬意でもって高く積み上げられてきた人類発展の歴史を根本からひっくり返すようなまねをしないもの。
除けたのは、それらに当てはまらぬもの全て。未知なるものであり、かつ未知でなくなることを力いっぱい拒んでいるようなもの。もしも無垢なる人々に接触したならば、たちどころに世界を、現実を信じられなくさせるようなもの―――すなわち、異常なもの、逸脱したもの。『デビアンス』。
"World Standardized Organization"、縮めてWSOなる秘密組織が、この世の―――あるいはこの世ならざるものも含めて、あらゆる事物をこれら二つのカテゴリーに分ける仕事を担っていた。彼らは巨大な力と予算を駆使し、『デビアンス』を見つけ出しては社会から排除していった。
だが、かといって破壊したり殺したりしたというわけではなかった。WSOは確保したデビアンスを手元に残し、研究していたのである。
いつの日か彼らを組み伏せ、『受け入れる』ために。
☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆
WSO日本支部、普段は行くことのない部屋で一穂と出会った日のことを美香はよく覚えている。十二歳の誕生日を迎えて間もない時のことだった。
「初めまして。DE-216です。よろしくお願いいたします」
彼は足を揃えて背筋を伸ばし、ほぼ精確に四十五度のお辞儀をしてみせた。
その動きに、美香は動画共有サイトで暇つぶしに見た、二十年以上も前の人型ロボットのプレスリリースを思い出す。
「……えと、名前ってない? その、ファーストネームとセカンドネーム」
「カズホ・ミヤタです」
「……姓と名」
「宮田一穂です」
この間、一穂は全くの無表情。
美香は面食らっていた。ロボットどころじゃない。声をかければ施設の案内やコンピュータ操作の代行をしてくれる人工知能エージェントだって、今日びもうちょっと人間味があるし、融通も利く。
そういえば彼は眼に光が入っていないような気がするし、肌も赤ん坊みたいにしっとりしている。もしかして本当はアンドロイドか何かなんじゃないか、と美香が思い始めた時、
「あなたは、DE-256ですね?」
と、またも平坦な一穂の声。
「川野美香。美香でいいわ。あたしも一穂って呼ばしてもらうから。
いつまでかわかんないけど一緒にこのフロアで暮らしてくんだし、フランクにいきましょ」
「了解しました」
「よろしく」
美香が手を差し伸べる。一穂は少し遅れて反応し、握手をした。
デビアンスたちはDEという接頭詞とナンバーをつけられ、管理されている。
一穂と美香はその異能―――こちらの世界では『逸脱性』と呼ばれていたが―――ゆえに、デビアンスとして扱われていたのだが、一方で一人の人間であるとも認められてはいた。
少なくとも、この時点からは。
☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆
一穂は、時には便利で、時には厄介だった。
たとえば寝泊まりしている部屋を離れてよその研究棟に行くときには、
「美香さん、ロックをかけ忘れています」
「あ、え、なんでわかんの?」
「ドアが閉じる音の直後に、ロックの音がなかったためです」
「はあ」
たとえばWSO内のショッピング・モールへ買い出しに行ったら、
「ちょっとちょっと、一穂! どこ行くのよ!」
「必要な商品を確保してレジへ向かう最短ルートを辿っています」
「わかんの!? って、待ってよもう!!」
たとえば夕食の調理を任された時には、
「美香さん、味噌汁の塩分が多すぎます」
「えぇ!? いつもと同じくらいよ?」
「味噌の分量が普段より一割ほど多いと思われます」
「そ、そんくらい別にいいじゃんって……」
あるいは、たとえば、
「美香さん、トイレが流しきれていません。臭いが―――」
「あぁもうわかったからちょっとはデリカシー持ってよ馬鹿!!」
☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆
諸事情で生活をともにすることになったとはいえ、流石に寝る部屋は別だった。
「……はぁーあ」
シャワーを終えてパジャマに着替えた美香は、白い布団に灰色のフレームのベッドに転がり込んで、ため息をつく。
「あいつが来てからたしかに生活は効率良くなったって思うけど、なんでこんなモヤモヤすんだろ……」
ごろんと寝返りを打って、物思いに耽る。
一穂も何の前ぶりもなくやってきたわけではない。あの数日前、美香の世話をしている―――『デビアンス』たる彼女の担当者となっている研究員たちがちゃんと教えてくれていた。
感情が薄い感じがするかもしれないけど、とも伝えられてはいたのだが、さすがにこれほどとは思わなかった……
「……や、他にもあったわね、言われてたコト」
彼の『逸脱性』に関する話だ。
一穂は自らの記憶をなにかに焼き付け、それを通じて記憶を他者に伝染させることができる。ただし焼き付けられるのはあくまで記憶であり、全く経験したこともないことを想像して使うことはできない。
そして、この力は異常な記憶力によって支えられている。一穂はこれまでの十数年の人生で見た、聞いた、触れた、嗅いだ、味わった全てを記憶しており、忘れることはない―――忘れるということが彼にはできないらしい。加えて感覚の鋭さも人並み外れており、それが記憶をより鮮明なものにする。
美香は、気に入らないものはその気になればある程度退けたり逃げたりできるのだと思っていた。
彼女の『逸脱性』である、波を薙ぐ力……うまく応用すれば、壁の向こうから伝わってくる騒音を抑えたり、工事による振動を防いだり、生き物の心臓を止めてしまうことさえできる。
逸脱性を抜きにしても、嫌なものは嫌と言える、自我の力が彼女にはある。
自分を守れるだけの力と、守ってしかるべきだという確信がある。
だが、一穂はそうなのだろうか。
世界をありのまま見つめ、その全てを憶えてしまうとは、どんな気持ちなのだろう。
デビアンスだらけの場所で過ごしていると、世界には信用ならないものや恐ろしいものの方が多いのだと、どうしても思えてきてしまう。知っている人間がデビアンスの犠牲になったことだって一度や二度ではなかった。
悪いことを思い出して嫌な気分になってきた時、美香は体を動かしたり寝たりして自分を騙す。
だけど、一穂にそれは出来るのだろうか。
「……何。何あたしアイツのこと心配してんだか。
いいやもう。寝ちゃえ。明日も早い……」
美香は丸くなって目をつむった。拭いきれていない水気が布団の中に染み込んでいった。
☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆
一穂はポリタンクにためた水を少しずつ使って鍋と皿とを洗っている。スポンジに最低限の洗剤を含ませて表面をこすり、汚れを含んだ水はバケツの中にためる。動作は洗練され、ひたすらに効率的だった。
美香は手伝わせてもらえず、仕方がないので新聞を読んで過ごしている。
例の、ある日突然イバラシティの住民全員にふりかかった『侵略の報せ』についての調査はまだ行われているようだが、近いうちに打ち切りになりそうだった。どんなに衝撃的な事件でも日が経つにつれて熱は冷めていくものだ。
今はむしろ他のニュースが目立つ。誰もが異能を持つこの町ではそれを利用した犯罪も少なくないし、そのカウンターとなるようなものも多々ある―――昨日は、壁抜けの異能で銀行破りを試みた輩がいた。ところが壁の中でそいつを待ち受けていたのは広大な迷路で、彼は迷子になった挙句生き埋めになって掘り出された。壁に迷路を作り出してみせたのは最近雇われた警備員だったのだが、その後哀れなことに彼は解雇されてしまったという。コソ泥を退けた功績より、そいつを掘り出すのにかかったコストの方がずっと重かったらしい。この警備員が次なる犯罪者にならないことを美香はひっそりと祈った。
ともあれ、こういう中からイバラシティの人間ではなくデビアンスが関与しているだろう事件を抜き出さなくてはならない。
これもきっと、一穂ならもっと上手くやるのだろう。直接デビアンスについての情報を教えられておらずとも、彼らが逃げ出したりあるべき場所から離れてしまうことは時々ある。そういう時、どんな騒ぎが起きてたかだって、一穂は全て覚えているはずなのだから。
それでも、精一杯やるのだ。
デビアンスがイバラシティをうろついているのは自分にとっても問題だし、一穂には生命を救われた恩がある。
それに……少なくとも、一穂を独りきりにすることは、美香の心が許せなかった。










制約LV を 5 UP!(LV15⇒20、-5CP)
武器LV を 5 UP!(LV30⇒35、-5CP)
高速配置 を習得!
デスペラート を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



現在のパーティから離脱しました!
特に移動せずその場に留まることにしました。
体調が全回復しました!






[707 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[297 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
―― Cross+Roseに映し出される。


チャット画面にまたまたふたりの姿が映る。

ふたりの背後から突然現れる長身。
ダルそうな、面倒そうな、そんな様子の青年。
ふたりの反応を気にすることなく、
前髪を手でくしゃっとさせて、目のあたりを隠す。
そう言って、さっさと姿を消してしまう。
うーん、と悩むふたり。
白南海の姿が消える。
チャットが閉じられる――










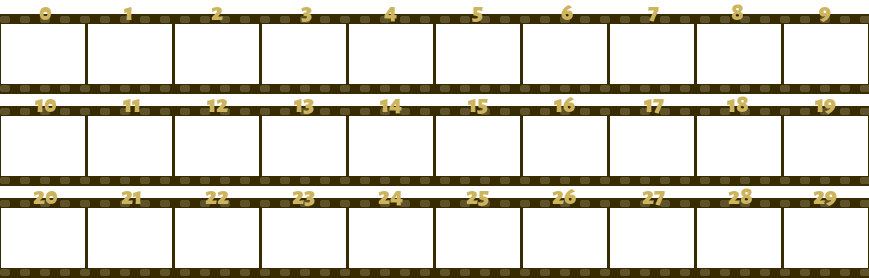







































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [スキル]OK.



無骨な廃コンテナの内側にはボロ布を継ぎ接ぎしたカーペットが敷かれ、にわかに彩りがもたらされていた。
その上にはちゃぶ台が一つ。載せられたガスコンロが鍋を温め、こぽこぽと湯がわいている。
中には人参と白菜、ブナシメジ、ネギ……それから豆腐が浮かび上がってくるところだった。
「おーし、肉行くよ?」
美香は『しゃぶしゃぶ用』『2割引』とシールが張られたラップを破いて豚肉を鍋の中へ放り込む。
一方の一穂はというと、とりあえずアクを取るのだけは手伝った。
「さ、しっかり食べなさい。ずーっと家無しでいたんでしょ」
言いながら、美香は鍋から肉をつまみ上げる。
「家がなくとも生きていくことはできました。栄養状態にも今の所問題はありません」
「そういう問題じゃないでしょーよ……」
「廃棄されたコンテナに無断で住み着くのは犯罪であり、そちらのほうが問題と思われますが」
「いいのよバレなきゃ。あたしの力で壁の振動を抑えてあるから声も漏れないし。
第一犯罪ってんならこのコンテナだってきちんと処分されたもんじゃないんだし、五十歩百歩だわ」
このコンテナは、コヌマ区の森の中にぽつんと棄てられていたものだった。
「……空の下で寝てて、デビアンスに襲われたんじゃなくって」
「就寝時ではありませんがDE-317と遭遇しました。対象はこの町の住民と思しき人物に殺害されました。WSO職員規則に従えば―――」
一穂の言に、美香は二枚目の豚肉を口に含んだまましばし静止した。
「しゃーないしゃーない! 場合が場合だわ。
無事に帰れたらちゃんと報告しましょ……ってか、今はまだ、帰れるかどうかだってわかんないけどね」
「美香さんは、先ほどのDE-96の他にはなにかデビアンスに遭遇したのですか?」
DE-96―――あの波の中に潜む怪物は、今はクーラーボックスの中に収められ、南京錠つきの鎖でぐるぐる巻きにされている。
「や、あんだけ……とはいえ、他にも来てるって思うのがフツーよね。
あーもうどうすりゃいいのよったく、581とか977とか来てたらって考えると、えェい!」
美香は野菜と肉とをまとめて頬張り、しばらく噛んでから炭酸のジュースで飲み下す。
「……なんでこんなことになっちゃったんだろうね。わかんないよ、あたし」
カスミ湖では絶えず強かさを湛えていた美香の目は、今やすがるようなものに変わり、絶対の記憶力を誇る一穂へと向けられた。
が、
「僕もです」
「へ?」
「WSO研究棟からこの街へ転移する前後の記憶がありません。
なにか異常なことがあったと思われます」
美香はきょとんとしていた。
異常だなんて、そんなの言われるまでもない。
もう何もかもが異常だ。

☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆
その世界の人類は、ある時から社会に受け入れるものと除けるものを決め、選り分けるようにした。
受け入れたのは、挙動について再現性があるもの。自然科学の方法論で対応しきれるようなもの。努力と信念と敬意でもって高く積み上げられてきた人類発展の歴史を根本からひっくり返すようなまねをしないもの。
除けたのは、それらに当てはまらぬもの全て。未知なるものであり、かつ未知でなくなることを力いっぱい拒んでいるようなもの。もしも無垢なる人々に接触したならば、たちどころに世界を、現実を信じられなくさせるようなもの―――すなわち、異常なもの、逸脱したもの。『デビアンス』。
"World Standardized Organization"、縮めてWSOなる秘密組織が、この世の―――あるいはこの世ならざるものも含めて、あらゆる事物をこれら二つのカテゴリーに分ける仕事を担っていた。彼らは巨大な力と予算を駆使し、『デビアンス』を見つけ出しては社会から排除していった。
だが、かといって破壊したり殺したりしたというわけではなかった。WSOは確保したデビアンスを手元に残し、研究していたのである。
いつの日か彼らを組み伏せ、『受け入れる』ために。
☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆
WSO日本支部、普段は行くことのない部屋で一穂と出会った日のことを美香はよく覚えている。十二歳の誕生日を迎えて間もない時のことだった。
「初めまして。DE-216です。よろしくお願いいたします」
彼は足を揃えて背筋を伸ばし、ほぼ精確に四十五度のお辞儀をしてみせた。
その動きに、美香は動画共有サイトで暇つぶしに見た、二十年以上も前の人型ロボットのプレスリリースを思い出す。
「……えと、名前ってない? その、ファーストネームとセカンドネーム」
「カズホ・ミヤタです」
「……姓と名」
「宮田一穂です」
この間、一穂は全くの無表情。
美香は面食らっていた。ロボットどころじゃない。声をかければ施設の案内やコンピュータ操作の代行をしてくれる人工知能エージェントだって、今日びもうちょっと人間味があるし、融通も利く。
そういえば彼は眼に光が入っていないような気がするし、肌も赤ん坊みたいにしっとりしている。もしかして本当はアンドロイドか何かなんじゃないか、と美香が思い始めた時、
「あなたは、DE-256ですね?」
と、またも平坦な一穂の声。
「川野美香。美香でいいわ。あたしも一穂って呼ばしてもらうから。
いつまでかわかんないけど一緒にこのフロアで暮らしてくんだし、フランクにいきましょ」
「了解しました」
「よろしく」
美香が手を差し伸べる。一穂は少し遅れて反応し、握手をした。
デビアンスたちはDEという接頭詞とナンバーをつけられ、管理されている。
一穂と美香はその異能―――こちらの世界では『逸脱性』と呼ばれていたが―――ゆえに、デビアンスとして扱われていたのだが、一方で一人の人間であるとも認められてはいた。
少なくとも、この時点からは。
☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆
一穂は、時には便利で、時には厄介だった。
たとえば寝泊まりしている部屋を離れてよその研究棟に行くときには、
「美香さん、ロックをかけ忘れています」
「あ、え、なんでわかんの?」
「ドアが閉じる音の直後に、ロックの音がなかったためです」
「はあ」
たとえばWSO内のショッピング・モールへ買い出しに行ったら、
「ちょっとちょっと、一穂! どこ行くのよ!」
「必要な商品を確保してレジへ向かう最短ルートを辿っています」
「わかんの!? って、待ってよもう!!」
たとえば夕食の調理を任された時には、
「美香さん、味噌汁の塩分が多すぎます」
「えぇ!? いつもと同じくらいよ?」
「味噌の分量が普段より一割ほど多いと思われます」
「そ、そんくらい別にいいじゃんって……」
あるいは、たとえば、
「美香さん、トイレが流しきれていません。臭いが―――」
「あぁもうわかったからちょっとはデリカシー持ってよ馬鹿!!」
☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆
諸事情で生活をともにすることになったとはいえ、流石に寝る部屋は別だった。
「……はぁーあ」
シャワーを終えてパジャマに着替えた美香は、白い布団に灰色のフレームのベッドに転がり込んで、ため息をつく。
「あいつが来てからたしかに生活は効率良くなったって思うけど、なんでこんなモヤモヤすんだろ……」
ごろんと寝返りを打って、物思いに耽る。
一穂も何の前ぶりもなくやってきたわけではない。あの数日前、美香の世話をしている―――『デビアンス』たる彼女の担当者となっている研究員たちがちゃんと教えてくれていた。
感情が薄い感じがするかもしれないけど、とも伝えられてはいたのだが、さすがにこれほどとは思わなかった……
「……や、他にもあったわね、言われてたコト」
彼の『逸脱性』に関する話だ。
一穂は自らの記憶をなにかに焼き付け、それを通じて記憶を他者に伝染させることができる。ただし焼き付けられるのはあくまで記憶であり、全く経験したこともないことを想像して使うことはできない。
そして、この力は異常な記憶力によって支えられている。一穂はこれまでの十数年の人生で見た、聞いた、触れた、嗅いだ、味わった全てを記憶しており、忘れることはない―――忘れるということが彼にはできないらしい。加えて感覚の鋭さも人並み外れており、それが記憶をより鮮明なものにする。
美香は、気に入らないものはその気になればある程度退けたり逃げたりできるのだと思っていた。
彼女の『逸脱性』である、波を薙ぐ力……うまく応用すれば、壁の向こうから伝わってくる騒音を抑えたり、工事による振動を防いだり、生き物の心臓を止めてしまうことさえできる。
逸脱性を抜きにしても、嫌なものは嫌と言える、自我の力が彼女にはある。
自分を守れるだけの力と、守ってしかるべきだという確信がある。
だが、一穂はそうなのだろうか。
世界をありのまま見つめ、その全てを憶えてしまうとは、どんな気持ちなのだろう。
デビアンスだらけの場所で過ごしていると、世界には信用ならないものや恐ろしいものの方が多いのだと、どうしても思えてきてしまう。知っている人間がデビアンスの犠牲になったことだって一度や二度ではなかった。
悪いことを思い出して嫌な気分になってきた時、美香は体を動かしたり寝たりして自分を騙す。
だけど、一穂にそれは出来るのだろうか。
「……何。何あたしアイツのこと心配してんだか。
いいやもう。寝ちゃえ。明日も早い……」
美香は丸くなって目をつむった。拭いきれていない水気が布団の中に染み込んでいった。
☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆
一穂はポリタンクにためた水を少しずつ使って鍋と皿とを洗っている。スポンジに最低限の洗剤を含ませて表面をこすり、汚れを含んだ水はバケツの中にためる。動作は洗練され、ひたすらに効率的だった。
美香は手伝わせてもらえず、仕方がないので新聞を読んで過ごしている。
例の、ある日突然イバラシティの住民全員にふりかかった『侵略の報せ』についての調査はまだ行われているようだが、近いうちに打ち切りになりそうだった。どんなに衝撃的な事件でも日が経つにつれて熱は冷めていくものだ。
今はむしろ他のニュースが目立つ。誰もが異能を持つこの町ではそれを利用した犯罪も少なくないし、そのカウンターとなるようなものも多々ある―――昨日は、壁抜けの異能で銀行破りを試みた輩がいた。ところが壁の中でそいつを待ち受けていたのは広大な迷路で、彼は迷子になった挙句生き埋めになって掘り出された。壁に迷路を作り出してみせたのは最近雇われた警備員だったのだが、その後哀れなことに彼は解雇されてしまったという。コソ泥を退けた功績より、そいつを掘り出すのにかかったコストの方がずっと重かったらしい。この警備員が次なる犯罪者にならないことを美香はひっそりと祈った。
ともあれ、こういう中からイバラシティの人間ではなくデビアンスが関与しているだろう事件を抜き出さなくてはならない。
これもきっと、一穂ならもっと上手くやるのだろう。直接デビアンスについての情報を教えられておらずとも、彼らが逃げ出したりあるべき場所から離れてしまうことは時々ある。そういう時、どんな騒ぎが起きてたかだって、一穂は全て覚えているはずなのだから。
それでも、精一杯やるのだ。
デビアンスがイバラシティをうろついているのは自分にとっても問題だし、一穂には生命を救われた恩がある。
それに……少なくとも、一穂を独りきりにすることは、美香の心が許せなかった。



 |
出したモノが武器の形になっていて虚無になっている。 防具になるかと思ったのに。 そっと異能を解除した。 |





制約LV を 5 UP!(LV15⇒20、-5CP)
武器LV を 5 UP!(LV30⇒35、-5CP)
高速配置 を習得!
デスペラート を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



現在のパーティから離脱しました!
特に移動せずその場に留まることにしました。
体調が全回復しました!






[707 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[297 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
―― Cross+Roseに映し出される。
 |
白南海 「・・・・・ぁァ?」 |
 |
エディアン 「おやおや!」 |

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
チャット画面にまたまたふたりの姿が映る。
 |
白南海 「まぁた呼び出しやがってこのアマァ・・・・・ひとりで居ろってあんだけ――」 |
 |
エディアン 「いや今回は呼んでませんって。私。」 |
 |
白南海 「チッ・・・・・今から若と入れ替わってくれませんかねぇアンタ。」 |
 |
エディアン 「若?何言ってんですか?」 |
 |
白南海 「何でもねぇっすよ・・・」 |
 |
ソージロウ 「・・・・・・ぁー、いいですか。」 |

ソージロウ
黒い瞳、黒いもじゃもじゃ頭。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。
ふたりの背後から突然現れる長身。
 |
白南海 「・・・ッ!!っちょ・・・ぅお・・・・・」 |
 |
エディアン 「わっ・・・・・びっくりしたぁ・・・・・」 |
 |
ソージロウ 「・・・・・・・・・・・・」 |
ダルそうな、面倒そうな、そんな様子の青年。
 |
エディアン 「あら貴方は!ロストのおひとりじゃないですか!!」 |
 |
白南海 「・・・・・何でこう急に出てくる奴が多いんだッ」 |
 |
ソージロウ 「・・・・・・・・・あのぅ。」 |
ふたりの反応を気にすることなく、
 |
ソージロウ 「・・・ゲーセン。ゲーセンあったら教えて。」 |
前髪を手でくしゃっとさせて、目のあたりを隠す。
 |
ソージロウ 「格ゲー、できるとこ。・・・・・・そんだけ。」 |
そう言って、さっさと姿を消してしまう。
 |
エディアン 「消えちゃった・・・・・口数の少ない、物静かな子ですねぇ。」 |
 |
白南海 「ゲーセン、ゲーセンっすか。 雀荘じゃダメかね。行きつけならたまに格闘もあるんだが。」 |
 |
エディアン 「うーん、私もあまり詳しくないですねぇ。専らスチー・・・・・あぁいや、なんでも。」 |
うーん、と悩むふたり。
 |
白南海 「・・・・・・・・・ぁ、こうすりゃよかったっけな。そういや。」 |
白南海の姿が消える。
 |
エディアン 「・・・退室の仕方は覚えたんですか。よくできました・・・っと!」 |
 |
エディアン 「お役に立てずごめんなさい。私なりにも少し探してみますね!」 |
チャットが閉じられる――

ENo.3
宮田一穂とK.M.



《宮田一穂(みやたかずほ)》
『すべてはいつの日か記号に還元されるでしょう』
・種族: 地球人(モンゴロイド)
・年齢:14歳/身長: 164cm/体重: 42kg/誕生日:10月3日
・特技:記憶すること/趣味:持たない/好物:特にない
イバラシティの片隅で路上生活を続ける少年。
言葉に抑揚が薄く、感情もほとんど示さない。ロボットのような印象を与えがちだが、優しさを見せないこともない。
赤いジャケットとニット帽を常に着用している。
その異能は『記憶』の異能。
自らの記憶を物体に焼き付けることができ、それを触れたものに記憶を『伝染』させ、自らのことのように感じさせる。代償として、焼き付けた記憶は本人の中から失われてしまう。また、記憶を焼きつけた物体は一度『伝染』させると効力を失い、再利用はできない。
異能とは別にほぼ完璧な記憶力を持ち、先述の異能の代償やなにか異常なものの影響にさらされた場合をのぞいて物事を忘れるということがない。
武器として拳銃を一丁所持している。相当に使い慣れている模様。
どこか異なる場所から来たようで、帰り方を探している。
※遭遇したものに対しメモを取る場合がございます。もし、問題がございましたら、ご一報頂ければ削除いたします。
⇒http://lisge.com/ib/talk.php?p=1821
《K.M.(クリストファ・マルムクヴィスト)》
ジャケットが青いのを除けば一穂とうりふたつの姿を持つ少年。
一穂と異なり、かなり殺傷力の強い異能を持っているようだ。また感情も普通に見せる。
PL: 切り株(@BehindForestBoy)
『すべてはいつの日か記号に還元されるでしょう』
・種族: 地球人(モンゴロイド)
・年齢:14歳/身長: 164cm/体重: 42kg/誕生日:10月3日
・特技:記憶すること/趣味:持たない/好物:特にない
イバラシティの片隅で路上生活を続ける少年。
言葉に抑揚が薄く、感情もほとんど示さない。ロボットのような印象を与えがちだが、優しさを見せないこともない。
赤いジャケットとニット帽を常に着用している。
その異能は『記憶』の異能。
自らの記憶を物体に焼き付けることができ、それを触れたものに記憶を『伝染』させ、自らのことのように感じさせる。代償として、焼き付けた記憶は本人の中から失われてしまう。また、記憶を焼きつけた物体は一度『伝染』させると効力を失い、再利用はできない。
異能とは別にほぼ完璧な記憶力を持ち、先述の異能の代償やなにか異常なものの影響にさらされた場合をのぞいて物事を忘れるということがない。
武器として拳銃を一丁所持している。相当に使い慣れている模様。
どこか異なる場所から来たようで、帰り方を探している。
※遭遇したものに対しメモを取る場合がございます。もし、問題がございましたら、ご一報頂ければ削除いたします。
⇒http://lisge.com/ib/talk.php?p=1821
《K.M.(クリストファ・マルムクヴィスト)》
ジャケットが青いのを除けば一穂とうりふたつの姿を持つ少年。
一穂と異なり、かなり殺傷力の強い異能を持っているようだ。また感情も普通に見せる。
PL: 切り株(@BehindForestBoy)
30 / 30
160 PS
チナミ区
D-2
D-2







































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | SRmkVI | 武器 | 20 | 攻撃10 | - | - | 【射程1】 |
| 5 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]防御10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) | |||
| 6 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 8 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
| 9 | SRmkVI-P | 武器 | 35 | 束縛10 | - | - | 【射程3】 |
| 10 | 甲殻 | 素材 | 15 | [武器]地纏10(LV20)[防具]防御10(LV15)[装飾]反射10(LV25) | |||
| 11 | 防刃ベスト | 防具 | 67 | 活力15 | - | - | |
| 12 | 吸い殻 | 素材 | 10 | [武器]炎上10(LV25)[防具]火纏10(LV25)[装飾]耐火10(LV20) | |||
| 13 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 20 | 身体/武器/物理 |
| 制約 | 20 | 拘束/罠/リスク |
| 響鳴 | 5 | 歌唱/音楽/振動 |
| 武器 | 35 | 武器作製に影響 |
| 付加 | 10 | 装備品への素材の付加に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 6 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 6 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 6 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 | |
| ティンダー | 5 | 0 | 50 | 敵:火撃&炎上 | |
| アサルト | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃+自:連続減 | |
| エチュード | 5 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) | |
| デアデビル | 5 | 0 | 60 | 自:HP減+敵傷4:痛撃 | |
| マーチ | 5 | 0 | 100 | 味全:AT増(4T) | |
| アリア | 5 | 2 | 0 | 自:SP・次与ダメ増 | |
| ファイアダンス | 5 | 0 | 80 | 敵:2連火領撃&炎上+領域値[火]3以上なら、火領撃&炎上 | |
| アラベスク | 5 | 0 | 50 | 味全:HP・AG増+魅了 | |
| チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 | |
| ファイアボルト | 5 | 0 | 100 | 敵貫:火痛撃 | |
| ペナルティ | 5 | 0 | 120 | 敵3:麻痺・混乱 | |
| スピアトラップ | 5 | 0 | 100 | 敵:罠《突刺》LV増 | |
| ボムトラップ | 5 | 0 | 110 | 敵:罠《爆弾》LV増 | |
| イレイザー | 5 | 0 | 100 | 敵傷:攻撃 | |
| ピットトラップ | 5 | 0 | 120 | 敵全:罠《奈落》LV増 | |
| ハードブレイク | 5 | 1 | 120 | 敵:攻撃 | |
| イグニス | 5 | 0 | 120 | 敵傷3:火領撃 | |
| デスペラート | 5 | 0 | 130 | 敵:報讐LV増+6連撃+報讐消滅 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 火の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:魔術LVが高いほど火特性・耐性増 | |
| 阿修羅 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HP減+AT・DX・LK増 | |
| 高速配置 | 5 | 4 | 0 | 【スキル使用後】自:直前に使用したスキル名に「トラップ」が含まれるなら、連続増 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
ダメージ・アブソーバー (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
|
雷鳥は頂きを目指す (インヴァージョン) |
0 | 150 | 敵全:攻撃&祝福を猛毒化 | |
|
猟犬の一撃 (イグニス) |
0 | 120 | 敵傷3:火領撃 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]イレイザー | [ 2 ]ミラージュ | [ 3 ]インパクト |
| [ 1 ]ティンダー | [ 1 ]ファイアダンス | [ 1 ]ファイアレイド |
| [ 3 ]ハードブレイク |

PL / 切り株





























