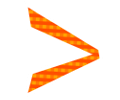<< 4:00~5:00




006.「HSP」――もしくは、実在の否定と探偵の居場所について
「中学生の頃から、一条くんと仲が良かったって聞いてるけど――」
一条燈大が、検査の名目で病院にやってきて。
その付き添いに家族を指定されたものの、イバラシティに彼の家族はいない。
彼が言えたことは唯一つだ。「一緒に暮らしてる奴はいますけど」。
そんな経緯で、小野木瞬はこの大学病院に連れてこられることになり。
検査中で燈大がいない間に、白衣を着た医師から視線を向けられていた。
「彼、君が知ってる限りでいいんだけど……どんな子かな?」
小野木瞬の顔に浮かぶのは、一筋の困惑。だがそれも今は既に鳴りを潜めていた。
“そういう奴”だと簡単に言ってしまえる程の生活をこれまでの間にこなし、
分かりきっている事実に一つ溜息をつくだけで、ただ、それまでだ。
「そう、ですね。冷めてる様に見える奴、だと思います。
何事にも夢中にならないようにしている、といいますか。諦め、なんでしょうかね。
オレの見ている限り人間関係とかもそんな感じで。
……オレから見れば、したいことがあるはずなのに理屈つけて──」
白衣を着た大人は、静かにそれを聞いていた。
淡々と電子カルテに打ち込みながら、時折曖昧な相槌を挟んで。
幾度か不思議そうな声色が続いてから、言葉を促すように口を開く。
「理屈つけて」
「はい。やっている理由って何だったのか、とか。
そこに大した理由何て必要ないと思うんですけど、あいつからしたら大事な物なのか。
やりたいから、やる。っていう単純なことが、あいつには出来ないように見えます」
言葉に首肯を返し、とつとつと言葉を連ねる。彼にはわからない、という様子はない。
ただ、トータという彼はそういう人物で、そういう物を、身近で見続けてきたという響きがあった。
そこにある響きには、“その単純な物を選べさえすれば”という信用がにじみ出ている事に、
小野木少年本人には、“そういう”自覚はあまり存在していない。
「そういう時、小野木くんは彼になにか言ったりするのかな」
医師は、一瞬だけ目を細めた。単純なことが、あいつにはできない。
その言葉に僅かに視線を落としてから、また手元のカルテへと。
そのまた次には小野木少年の顔へと医者の視線は移動する。揺らぐ。
「何も言っていなくても、そういうときにどうしてるか、教えてもらえるかな」
小野木瞬は一瞬目を伏せる。何処か後ろめたい事があるかのように。
まるでそれは幻、或いは無意識の物だったかのように、消え去っていた。
言葉は、素直に文言を連ねる。ありのままを。そこにある通りに、淡々と。
「その……、割と一緒にいたからか、売り言葉みたいなことを言ってみたりします。
“やれないんなら、やりたくないんじゃないのか”とか言って、笑ってみたり。
でも、決まってあいつ、笑うんです。“そうかもな”って。
オレは、意図は伝わってる、と思ってるんですけどね。だって、」
その先の言葉を口にすることなく、少年は口を閉ざした。
言うべきなのか、それとも本人にも言葉にするのが難しい、とでも思っているのか。
それを知ってか知らぬか、大人はやや諌めるような口調で少年に告げる。
「言いにくい話だけどね」とクッションを置いてから、少年と視線を合わせて、ゆっくりと。
「“やれないこと”と“やりたくないこと”はね、違うんだ」
少年に、できるだけ柔らかい口調と印象を保ったままに、それでいて冷ややかに。
「例えば、もし。君が陸上選手になりたかったとしよう。そういうときに、君はどうする?」
問う。
「え、ぇと。陸上に関して詳しくないんで細かくはいえないんですが……、目指します。
必要な練習があれば、それをやります。すいません、どんな練習かはわからなくて。
ともかく、なりたいんなら、それに近づける手段を試してみたいと思います」
その質問の意図が少年には分からなかったわけではない。
やれないことと、やりたくないこと。その違いは当然認識している。ただ、ただただ。
彼にとって、“トータ”という少年にとってのそれは、
間違いなく“やりたくない事などでは決してなかった”。だから──。
「もし、“そうしよう”として、“そうできなかったら”。
例えば……生まれつき、心臓に大きな病気を抱えていて、
“そうしたい”けど“そうできない”。そういうものがあるっていうのは、わかるかな?」
頷いていいのか、それとも頷かない方がいいのか。
瞬という少年は逡巡した様子を見せた後、一つ頷いた。大人びた少年でも、ここではただの高校生で。
「それは……分かります。でも、オレはそれでもやりたいなら諦めたくないです。
……それでもできる方法を探したいです。
それでも、それでも、って言って、出来ないって言われたら、無駄でも挑戦したいです」
此処まで言葉を選びながらも、少年の脳裏にはある思想が宿っている。
自分が何度、自分の脳裏に“オレなら”という単語を浮かばせていたのか、ということを。
少年は、少しだけ聡かった。でも、それによって浮かんだ答えを、うまく認める事が出来ずにいる。
医師は、静かに困ったような笑みを浮かべた。
ただただ、ゆっくりと。そして、しばらくしてから体ごと小野木少年のほうへと向きを変えて。
「……それなら、もう少しわかりやすい例えのほうがよかったね。申し訳ない。
……陸上選手になりたい男の子に、もし両足がなかったら、どうだろうか。
彼は、オリンピックに出られる?」
そう、告げて。答えなど決まりきっている。事実というのは、往々にして残酷なものだ。
先の例え話で、少年が受けるかもしれない衝撃を和らげられると思っているのかもしれない。
走り高跳びのマットのように準備されたその例え話の先にあるのは、ただの針山にほかならない。
「────……」
言葉を詰まらせる。
もし、この少年が限りなく愚かで、そのたとえ話の意味すら理解できなかったとしたら。
……何度でも、何度でも。その走り高跳びを越え続ける。
自分に用意された、そして自分が越えていきたい何かを、一生、ずっと。越え続ける。
その先に用意されている物が、何者であるかなど理解する事はなく。
だが。やはり。
この少年は……少しだけ聡かった。いや、本当なら。
予感をずっと感じ続けていた。だからこそ、認める事などできなかった。自分の思考との食い違いを。
「……あいつは、そうなんですか?」
「“そう”か“そうじゃない”かで言われれば、“そう”と言うほかない。
……ああでも、ただ。それは誰にでもあることの延長線だから、変に気にしなくてもいい。
君は、きっとそういうことはしないだろうと思うから、釈迦に説法かもしれないけれどね」
パソコンに有線で繋がれたマウスを二度クリックする。
乾いた音が響いて、カルテや検査結果の文字列を一通り医師は目で追ってから、
年老いた医師は、やはりまた小野木少年へと言葉を投げかける。
「一条くんの異能の話、聞いたことあるかな」
少年の目線は動く。手は固く握られ、呼吸はどこか浅い。
それでも、普段通りと言われれば、それまででしかない。沈黙は続き、整理などできるはずがない。
「……、はい。それと、今の話に、関係が?」
「一条くんの異能は、“それそのもの”が存在しないんだ。彼は知らないから、どうか内密に」
一条燈大の異能。一日に一度、正確な筆致で風景を「切り取る」ことができる異能。
制御できている異能ではなく、必ず発動するわけではない。
彼は、この異能で「うまく」絵を描いてきた。が、それは。そんなものはなく。
――そう「思っている」だけ。
「彼が一枚だけしか一日に『切り取れ』なかったのは、
……簡単に説明するなら、『過集中』という言葉で説明可能だ。
それも、毎日発動する異能じゃない。『集中できる日とできない日』があるだけなんだ。
本人はそれに気付いていないし、本人はそれを異能だとしか思っていない。
だから、できないのは『自分のせい』じゃなくて『異能のせい』でいられている」
即ち。「本当」は、一条燈大ができないのは「異能のせい」ではなくて、
ただ「自分のせい」でしかなく。本人がそれに気付いているか、それともどういう認識を
しているのかをこの医師は知らない。わからない。真実は、一条燈大という少年のもとにしかなく。
それでも、事実として、彼には「異能が発現していない」ということだけは他者も観測できる。
「だから、君の言葉は――」
その先を聞いていたのは、小野木少年ただ一人だ。
このイバラシティで、病院のスタッフ以外誰も知らない。
学校の級友だって、知り合った誰かも知らない。その秘密は、確かに告げられて。
「だったら」
少しだけ俯いていた視線は、真っ直ぐに医師を見つめる。
誰にも届かない言葉。この医師にしか届かない言葉。
或いはそれは、ロバ耳の王様の秘密を告げる穴のような物だったのかもしれないが、
それでも少年は、確かな意思を持って告げる。自分の犯した罪を償う意味ではなく。
求める物を、ただ手に入れる為だけに。
「オレが、誰のせいでもなくしてみせます」
医師は、笑って頷いた。
「ありがとう」と短く口添えてから、開かれていたカルテを閉じて。
別の患者のカルテをモニタ上に移し直せば、看護師が瞬の肩を軽く叩いて退出を促す。
一条燈大は。一条燈大の異能など、どこにも存在せず。
彼に与えられる診断はただ一つ。ありきたりで、どこにでもある病名で。
されど、その病は確かに身も心もを蝕む病で、身体だけは健康なのに、心の健康を損なう病。
強迫的なまでに「ルール」に苛まれること。
どうしようもないまでに、「簡単にできること」をするまでに時間がかかること。そして。
――色鮮やかに見える世界は、HSPという三文字の英字で示される単調な答えで。
それはやはり、このイバラシティにおける異能と同じようなものでしかなく。
ただ、それが「すべての人間」がそうである可能性すらもある「気質」でしかなく。
この街の「どこにでもあるもの」を持たない少年は、
この世界を見渡せば「どこにでもあるもの」でしかなく。
一つも特別になれずに、ただただ凡庸に病んでいるだけだ。
ただ、特別なのは。――それを知っている、小野木少年、ただ一人で。
HSPの属性は「DOES」という頭文字で表され、4つ全ての性質を持っているとされる。
《処理の深さ(Depth of processing)》
HSPは感覚データを通常よりはるかに深く、かつ徹底的に処理しているが、
それは神経システムにおける生物学的な差異によるものである。
《刺激を受けやすい(Overstimulated)》
感覚的に敏感である。
五感や、人の感情や雰囲気から自身の内部に入り込まれ受ける刺激が非HSPに比べ強い。
何に対して敏感かは個人差がある。説明のつかない多くの刺激を受けるため、心身ともに疲れやすい。
疲れが蓄積され不機嫌や体調不良などにつながりやすい。
嫌なことだけでなく、楽しいことでも刺激が多すぎると疲労になる。
《感情的反応性・高度な共感性(Emotional reactivity and high Empathy)》
神経細胞「ミラーニューロン」の活動が活発であることにより、共感力が高く感情移入しやすい。
HSPは生まれたときから境界を持てないケースがあり、
過剰同調性のために自身と他者との問題を自身の問題として同一視しやすい面もある。
《些細な刺激に対する感受性(Sensitivity to Subtle stimuli)》
人や環境における小さな変化や、細かい意図に気づきやすい。



ENo.720 瞬 とのやりとり




特に何もしませんでした。













六角形の柱から天に向け、赤色の光柱が立つ。
どうやら次元タクシーで行けるようになったようだ。



命術LV を 10 DOWN。(LV10⇒0、+10CP、-10FP)
呪術LV を 5 DOWN。(LV15⇒10、+5CP、-5FP)
魔術LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
響鳴LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
付加LV を 5 UP!(LV40⇒45、-5CP)
瞬(720) により ItemNo.8 アルミ缶 から射程1の武器『使いかけの鉛筆』を作製してもらいました!
⇒ 使いかけの鉛筆/武器:強さ82/[効果1]攻撃15 [効果2]- [効果3]-【射程1】
ItemNo.7 汚れたエプロン に ItemNo.10 古雑誌 を付加しました!
⇒ 汚れたエプロン/防具:強さ40/[効果1]命脈10 [効果2]鎮痛15 [効果3]-
しょぼ(781) とカードを交換しました!
どっかーん (ジャイアントキル)

サモン:サーヴァント を研究しました!(深度0⇒1)
サモン:サーヴァント を研究しました!(深度1⇒2)
ボロウライフ を研究しました!(深度1⇒2)
ティンダー を習得!
エチュード を習得!
ダークフレア を習得!
クリエイト:ダイナマイト を習得!
ファイアダンス を習得!
カースワード を習得!
クリエイト:パワードスピーカー を習得!
ファイアボルト を習得!
ビブラート を習得!
ワンオンキル を習得!
クリエイト:ファイアウェポン を習得!
バーニングチューン を習得!
ディプラヴィティ を習得!
コントラクト を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



吊るされた男(128) は 雑木 を入手!
瞬(720) は 雑木 を入手!
吊るされた男(128) は 花びら を入手!
瞬(720) は 羽 を入手!
瞬(720) は 毛 を入手!
瞬(720) は 毛 を入手!



特に移動せずその場に留まることにしました。






[707 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[297 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
―― Cross+Roseに映し出される。


チャット画面にまたまたふたりの姿が映る。

ふたりの背後から突然現れる長身。
ダルそうな、面倒そうな、そんな様子の青年。
ふたりの反応を気にすることなく、
前髪を手でくしゃっとさせて、目のあたりを隠す。
そう言って、さっさと姿を消してしまう。
うーん、と悩むふたり。
白南海の姿が消える。
チャットが閉じられる――
















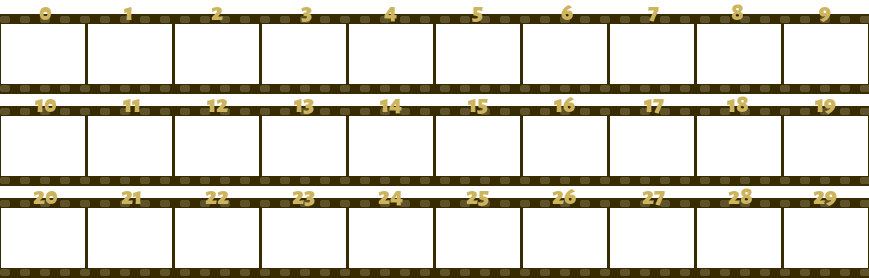







































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



006.「HSP」――もしくは、実在の否定と探偵の居場所について
「中学生の頃から、一条くんと仲が良かったって聞いてるけど――」
一条燈大が、検査の名目で病院にやってきて。
その付き添いに家族を指定されたものの、イバラシティに彼の家族はいない。
彼が言えたことは唯一つだ。「一緒に暮らしてる奴はいますけど」。
そんな経緯で、小野木瞬はこの大学病院に連れてこられることになり。
検査中で燈大がいない間に、白衣を着た医師から視線を向けられていた。
「彼、君が知ってる限りでいいんだけど……どんな子かな?」
小野木瞬の顔に浮かぶのは、一筋の困惑。だがそれも今は既に鳴りを潜めていた。
“そういう奴”だと簡単に言ってしまえる程の生活をこれまでの間にこなし、
分かりきっている事実に一つ溜息をつくだけで、ただ、それまでだ。
「そう、ですね。冷めてる様に見える奴、だと思います。
何事にも夢中にならないようにしている、といいますか。諦め、なんでしょうかね。
オレの見ている限り人間関係とかもそんな感じで。
……オレから見れば、したいことがあるはずなのに理屈つけて──」
白衣を着た大人は、静かにそれを聞いていた。
淡々と電子カルテに打ち込みながら、時折曖昧な相槌を挟んで。
幾度か不思議そうな声色が続いてから、言葉を促すように口を開く。
「理屈つけて」
「はい。やっている理由って何だったのか、とか。
そこに大した理由何て必要ないと思うんですけど、あいつからしたら大事な物なのか。
やりたいから、やる。っていう単純なことが、あいつには出来ないように見えます」
言葉に首肯を返し、とつとつと言葉を連ねる。彼にはわからない、という様子はない。
ただ、トータという彼はそういう人物で、そういう物を、身近で見続けてきたという響きがあった。
そこにある響きには、“その単純な物を選べさえすれば”という信用がにじみ出ている事に、
小野木少年本人には、“そういう”自覚はあまり存在していない。
「そういう時、小野木くんは彼になにか言ったりするのかな」
医師は、一瞬だけ目を細めた。単純なことが、あいつにはできない。
その言葉に僅かに視線を落としてから、また手元のカルテへと。
そのまた次には小野木少年の顔へと医者の視線は移動する。揺らぐ。
「何も言っていなくても、そういうときにどうしてるか、教えてもらえるかな」
小野木瞬は一瞬目を伏せる。何処か後ろめたい事があるかのように。
まるでそれは幻、或いは無意識の物だったかのように、消え去っていた。
言葉は、素直に文言を連ねる。ありのままを。そこにある通りに、淡々と。
「その……、割と一緒にいたからか、売り言葉みたいなことを言ってみたりします。
“やれないんなら、やりたくないんじゃないのか”とか言って、笑ってみたり。
でも、決まってあいつ、笑うんです。“そうかもな”って。
オレは、意図は伝わってる、と思ってるんですけどね。だって、」
その先の言葉を口にすることなく、少年は口を閉ざした。
言うべきなのか、それとも本人にも言葉にするのが難しい、とでも思っているのか。
それを知ってか知らぬか、大人はやや諌めるような口調で少年に告げる。
「言いにくい話だけどね」とクッションを置いてから、少年と視線を合わせて、ゆっくりと。
「“やれないこと”と“やりたくないこと”はね、違うんだ」
少年に、できるだけ柔らかい口調と印象を保ったままに、それでいて冷ややかに。
「例えば、もし。君が陸上選手になりたかったとしよう。そういうときに、君はどうする?」
問う。
「え、ぇと。陸上に関して詳しくないんで細かくはいえないんですが……、目指します。
必要な練習があれば、それをやります。すいません、どんな練習かはわからなくて。
ともかく、なりたいんなら、それに近づける手段を試してみたいと思います」
その質問の意図が少年には分からなかったわけではない。
やれないことと、やりたくないこと。その違いは当然認識している。ただ、ただただ。
彼にとって、“トータ”という少年にとってのそれは、
間違いなく“やりたくない事などでは決してなかった”。だから──。
「もし、“そうしよう”として、“そうできなかったら”。
例えば……生まれつき、心臓に大きな病気を抱えていて、
“そうしたい”けど“そうできない”。そういうものがあるっていうのは、わかるかな?」
頷いていいのか、それとも頷かない方がいいのか。
瞬という少年は逡巡した様子を見せた後、一つ頷いた。大人びた少年でも、ここではただの高校生で。
「それは……分かります。でも、オレはそれでもやりたいなら諦めたくないです。
……それでもできる方法を探したいです。
それでも、それでも、って言って、出来ないって言われたら、無駄でも挑戦したいです」
此処まで言葉を選びながらも、少年の脳裏にはある思想が宿っている。
自分が何度、自分の脳裏に“オレなら”という単語を浮かばせていたのか、ということを。
少年は、少しだけ聡かった。でも、それによって浮かんだ答えを、うまく認める事が出来ずにいる。
医師は、静かに困ったような笑みを浮かべた。
ただただ、ゆっくりと。そして、しばらくしてから体ごと小野木少年のほうへと向きを変えて。
「……それなら、もう少しわかりやすい例えのほうがよかったね。申し訳ない。
……陸上選手になりたい男の子に、もし両足がなかったら、どうだろうか。
彼は、オリンピックに出られる?」
そう、告げて。答えなど決まりきっている。事実というのは、往々にして残酷なものだ。
先の例え話で、少年が受けるかもしれない衝撃を和らげられると思っているのかもしれない。
走り高跳びのマットのように準備されたその例え話の先にあるのは、ただの針山にほかならない。
「────……」
言葉を詰まらせる。
もし、この少年が限りなく愚かで、そのたとえ話の意味すら理解できなかったとしたら。
……何度でも、何度でも。その走り高跳びを越え続ける。
自分に用意された、そして自分が越えていきたい何かを、一生、ずっと。越え続ける。
その先に用意されている物が、何者であるかなど理解する事はなく。
だが。やはり。
この少年は……少しだけ聡かった。いや、本当なら。
予感をずっと感じ続けていた。だからこそ、認める事などできなかった。自分の思考との食い違いを。
「……あいつは、そうなんですか?」
「“そう”か“そうじゃない”かで言われれば、“そう”と言うほかない。
……ああでも、ただ。それは誰にでもあることの延長線だから、変に気にしなくてもいい。
君は、きっとそういうことはしないだろうと思うから、釈迦に説法かもしれないけれどね」
パソコンに有線で繋がれたマウスを二度クリックする。
乾いた音が響いて、カルテや検査結果の文字列を一通り医師は目で追ってから、
年老いた医師は、やはりまた小野木少年へと言葉を投げかける。
「一条くんの異能の話、聞いたことあるかな」
少年の目線は動く。手は固く握られ、呼吸はどこか浅い。
それでも、普段通りと言われれば、それまででしかない。沈黙は続き、整理などできるはずがない。
「……、はい。それと、今の話に、関係が?」
「一条くんの異能は、“それそのもの”が存在しないんだ。彼は知らないから、どうか内密に」
一条燈大の異能。一日に一度、正確な筆致で風景を「切り取る」ことができる異能。
制御できている異能ではなく、必ず発動するわけではない。
彼は、この異能で「うまく」絵を描いてきた。が、それは。そんなものはなく。
――そう「思っている」だけ。
「彼が一枚だけしか一日に『切り取れ』なかったのは、
……簡単に説明するなら、『過集中』という言葉で説明可能だ。
それも、毎日発動する異能じゃない。『集中できる日とできない日』があるだけなんだ。
本人はそれに気付いていないし、本人はそれを異能だとしか思っていない。
だから、できないのは『自分のせい』じゃなくて『異能のせい』でいられている」
即ち。「本当」は、一条燈大ができないのは「異能のせい」ではなくて、
ただ「自分のせい」でしかなく。本人がそれに気付いているか、それともどういう認識を
しているのかをこの医師は知らない。わからない。真実は、一条燈大という少年のもとにしかなく。
それでも、事実として、彼には「異能が発現していない」ということだけは他者も観測できる。
「だから、君の言葉は――」
その先を聞いていたのは、小野木少年ただ一人だ。
このイバラシティで、病院のスタッフ以外誰も知らない。
学校の級友だって、知り合った誰かも知らない。その秘密は、確かに告げられて。
「だったら」
少しだけ俯いていた視線は、真っ直ぐに医師を見つめる。
誰にも届かない言葉。この医師にしか届かない言葉。
或いはそれは、ロバ耳の王様の秘密を告げる穴のような物だったのかもしれないが、
それでも少年は、確かな意思を持って告げる。自分の犯した罪を償う意味ではなく。
求める物を、ただ手に入れる為だけに。
「オレが、誰のせいでもなくしてみせます」
医師は、笑って頷いた。
「ありがとう」と短く口添えてから、開かれていたカルテを閉じて。
別の患者のカルテをモニタ上に移し直せば、看護師が瞬の肩を軽く叩いて退出を促す。
一条燈大は。一条燈大の異能など、どこにも存在せず。
彼に与えられる診断はただ一つ。ありきたりで、どこにでもある病名で。
されど、その病は確かに身も心もを蝕む病で、身体だけは健康なのに、心の健康を損なう病。
強迫的なまでに「ルール」に苛まれること。
どうしようもないまでに、「簡単にできること」をするまでに時間がかかること。そして。
――色鮮やかに見える世界は、HSPという三文字の英字で示される単調な答えで。
それはやはり、このイバラシティにおける異能と同じようなものでしかなく。
ただ、それが「すべての人間」がそうである可能性すらもある「気質」でしかなく。
この街の「どこにでもあるもの」を持たない少年は、
この世界を見渡せば「どこにでもあるもの」でしかなく。
一つも特別になれずに、ただただ凡庸に病んでいるだけだ。
ただ、特別なのは。――それを知っている、小野木少年、ただ一人で。
HSPの属性は「DOES」という頭文字で表され、4つ全ての性質を持っているとされる。
《処理の深さ(Depth of processing)》
HSPは感覚データを通常よりはるかに深く、かつ徹底的に処理しているが、
それは神経システムにおける生物学的な差異によるものである。
《刺激を受けやすい(Overstimulated)》
感覚的に敏感である。
五感や、人の感情や雰囲気から自身の内部に入り込まれ受ける刺激が非HSPに比べ強い。
何に対して敏感かは個人差がある。説明のつかない多くの刺激を受けるため、心身ともに疲れやすい。
疲れが蓄積され不機嫌や体調不良などにつながりやすい。
嫌なことだけでなく、楽しいことでも刺激が多すぎると疲労になる。
《感情的反応性・高度な共感性(Emotional reactivity and high Empathy)》
神経細胞「ミラーニューロン」の活動が活発であることにより、共感力が高く感情移入しやすい。
HSPは生まれたときから境界を持てないケースがあり、
過剰同調性のために自身と他者との問題を自身の問題として同一視しやすい面もある。
《些細な刺激に対する感受性(Sensitivity to Subtle stimuli)》
人や環境における小さな変化や、細かい意図に気づきやすい。



ENo.720 瞬 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||



特に何もしませんでした。







対戦相手未発見のため不戦勝!
影響力が 5 増加!
影響力が 5 増加!





チナミ区 R-7:チェックポイント《廃ビル》
守護者の姿が消え去った――六角形の柱から天に向け、赤色の光柱が立つ。
どうやら次元タクシーで行けるようになったようだ。



命術LV を 10 DOWN。(LV10⇒0、+10CP、-10FP)
呪術LV を 5 DOWN。(LV15⇒10、+5CP、-5FP)
魔術LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
響鳴LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
付加LV を 5 UP!(LV40⇒45、-5CP)
瞬(720) により ItemNo.8 アルミ缶 から射程1の武器『使いかけの鉛筆』を作製してもらいました!
⇒ 使いかけの鉛筆/武器:強さ82/[効果1]攻撃15 [効果2]- [効果3]-【射程1】
 |
瞬 「……、いや欲しいとは言ってたけど武器にするとは思わなんだ」 |
ItemNo.7 汚れたエプロン に ItemNo.10 古雑誌 を付加しました!
⇒ 汚れたエプロン/防具:強さ40/[効果1]命脈10 [効果2]鎮痛15 [効果3]-
| 燈大 「……こうして、こう」 |
しょぼ(781) とカードを交換しました!
どっかーん (ジャイアントキル)

サモン:サーヴァント を研究しました!(深度0⇒1)
サモン:サーヴァント を研究しました!(深度1⇒2)
ボロウライフ を研究しました!(深度1⇒2)
ティンダー を習得!
エチュード を習得!
ダークフレア を習得!
クリエイト:ダイナマイト を習得!
ファイアダンス を習得!
カースワード を習得!
クリエイト:パワードスピーカー を習得!
ファイアボルト を習得!
ビブラート を習得!
ワンオンキル を習得!
クリエイト:ファイアウェポン を習得!
バーニングチューン を習得!
ディプラヴィティ を習得!
コントラクト を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



吊るされた男(128) は 雑木 を入手!
瞬(720) は 雑木 を入手!
吊るされた男(128) は 花びら を入手!
瞬(720) は 羽 を入手!
瞬(720) は 毛 を入手!
瞬(720) は 毛 を入手!



特に移動せずその場に留まることにしました。






[707 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[297 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
―― Cross+Roseに映し出される。
 |
白南海 「・・・・・ぁァ?」 |
 |
エディアン 「おやおや!」 |

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
チャット画面にまたまたふたりの姿が映る。
 |
白南海 「まぁた呼び出しやがってこのアマァ・・・・・ひとりで居ろってあんだけ――」 |
 |
エディアン 「いや今回は呼んでませんって。私。」 |
 |
白南海 「チッ・・・・・今から若と入れ替わってくれませんかねぇアンタ。」 |
 |
エディアン 「若?何言ってんですか?」 |
 |
白南海 「何でもねぇっすよ・・・」 |
 |
ソージロウ 「・・・・・・ぁー、いいですか。」 |

ソージロウ
黒い瞳、黒いもじゃもじゃ頭。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。
ふたりの背後から突然現れる長身。
 |
白南海 「・・・ッ!!っちょ・・・ぅお・・・・・」 |
 |
エディアン 「わっ・・・・・びっくりしたぁ・・・・・」 |
 |
ソージロウ 「・・・・・・・・・・・・」 |
ダルそうな、面倒そうな、そんな様子の青年。
 |
エディアン 「あら貴方は!ロストのおひとりじゃないですか!!」 |
 |
白南海 「・・・・・何でこう急に出てくる奴が多いんだッ」 |
 |
ソージロウ 「・・・・・・・・・あのぅ。」 |
ふたりの反応を気にすることなく、
 |
ソージロウ 「・・・ゲーセン。ゲーセンあったら教えて。」 |
前髪を手でくしゃっとさせて、目のあたりを隠す。
 |
ソージロウ 「格ゲー、できるとこ。・・・・・・そんだけ。」 |
そう言って、さっさと姿を消してしまう。
 |
エディアン 「消えちゃった・・・・・口数の少ない、物静かな子ですねぇ。」 |
 |
白南海 「ゲーセン、ゲーセンっすか。 雀荘じゃダメかね。行きつけならたまに格闘もあるんだが。」 |
 |
エディアン 「うーん、私もあまり詳しくないですねぇ。専らスチー・・・・・あぁいや、なんでも。」 |
うーん、と悩むふたり。
 |
白南海 「・・・・・・・・・ぁ、こうすりゃよかったっけな。そういや。」 |
白南海の姿が消える。
 |
エディアン 「・・・退室の仕方は覚えたんですか。よくできました・・・っと!」 |
 |
エディアン 「お役に立てずごめんなさい。私なりにも少し探してみますね!」 |
チャットが閉じられる――







ENo.128
吊るされた男



一条 燈大(イチジョウ-トウタ)
身長 165cm 本人は170cmを自称している
相良伊橋高校2年1組 美術部
「……るせ。いま俺集中してんの」
中性的な見た目の割に口を開けば10割男子
開けば口も態度も悪めでぶっきらぼう
愛想がないのはデフォルト 本人も結構気にしている
■ 三行
背中まで伸ばした髪を三つ編みおさげに結ぶ
美術部に在籍しており、とりわけ静物画に関心が強い
職人気質で譲れるものと譲れないものの差が激しい
■ 異能
そんなものはない。
彼が誰もと同じように自分も持つと思っているだけだ。
■ 既知RPは歓迎です。
■ イラストは湯槽さんに描いていただきました!
--- ✂ --- ✂ --- ✂ --- ✂ --- ✂ --- ✂ --- ✂ --- ✂ ---
一度目の人生を自殺という形で終えている少年。
そのはずだが、まるでそれがなかったかのように、
あるはずのないあの日の「続き」を今も享受している。
一条 燈大
SIDE:ANSINITY
彼は、アンジニティを「死後の世界」と認識している。
が、実際のところはそういうわけではない。
彼は、死にながらにして死を拒んだ。
故に、彼は死を迎えることなく否定の世界へと追放された。
彼はそれに気付くことはない。
自らという一人の人間の死を「芸術」として弄び、
一人のアーティストとして「遺作」とすることを選び、
「人の記憶に残るような」劇的な死を「創った」。
故に、彼は「作品」として生き続けなくてはならない。
終わることはない物語の象徴。死を冒涜するもの。
彼の罪は、「『作者』が終わりを拒んだこと」である。
無自覚な罪人が赦されることはない。
身長 165cm 本人は170cmを自称している
相良伊橋高校2年1組 美術部
「……るせ。いま俺集中してんの」
中性的な見た目の割に口を開けば10割男子
開けば口も態度も悪めでぶっきらぼう
愛想がないのはデフォルト 本人も結構気にしている
■ 三行
背中まで伸ばした髪を三つ編みおさげに結ぶ
美術部に在籍しており、とりわけ静物画に関心が強い
職人気質で譲れるものと譲れないものの差が激しい
■ 異能
そんなものはない。
彼が誰もと同じように自分も持つと思っているだけだ。
■ 既知RPは歓迎です。
■ イラストは湯槽さんに描いていただきました!
--- ✂ --- ✂ --- ✂ --- ✂ --- ✂ --- ✂ --- ✂ --- ✂ ---
一度目の人生を自殺という形で終えている少年。
そのはずだが、まるでそれがなかったかのように、
あるはずのないあの日の「続き」を今も享受している。
一条 燈大
SIDE:ANSINITY
彼は、アンジニティを「死後の世界」と認識している。
が、実際のところはそういうわけではない。
彼は、死にながらにして死を拒んだ。
故に、彼は死を迎えることなく否定の世界へと追放された。
彼はそれに気付くことはない。
自らという一人の人間の死を「芸術」として弄び、
一人のアーティストとして「遺作」とすることを選び、
「人の記憶に残るような」劇的な死を「創った」。
故に、彼は「作品」として生き続けなくてはならない。
終わることはない物語の象徴。死を冒涜するもの。
彼の罪は、「『作者』が終わりを拒んだこと」である。
無自覚な罪人が赦されることはない。
11 / 30
352 PS
チナミ区
R-6
R-6











| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 新品の鉛筆 | 武器 | 30 | 攻撃10 | - | - | 【射程1】 |
| 5 | 油壺 | 装飾 | 30 | 幸運10 | - | - | |
| 6 | 美味しくない草 | 素材 | 10 | [武器]耐疫10(LV30)[防具]体力10(LV30)[装飾]強靭10(LV30) | |||
| 7 | 汚れたエプロン | 防具 | 40 | 命脈10 | 鎮痛15 | - | |
| 8 | 使いかけの鉛筆 | 武器 | 82 | 攻撃15 | - | - | 【射程1】 |
| 9 | 大軽石 | 素材 | 15 | [武器]幸運10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]舞護10(LV20) | |||
| 10 | 雑木 | 素材 | 15 | [武器]回復10(LV15)[防具]活力10(LV15)[装飾]体力10(LV15) | |||
| 11 | 牙 | 素材 | 15 | [武器]追撃10(LV30)[防具]奪命10(LV25)[装飾]増幅10(LV30) | |||
| 12 | 美味しい果実 | 食材 | 15 | [効果1]攻撃10(LV10)[効果2]防御10(LV15)[効果3]強靭15(LV25) | |||
| 13 | 花びら | 素材 | 10 | [武器]混乱10(LV25)[防具]舞魅10(LV10)[装飾]祝福10(LV20) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 魔術 | 10 | 破壊/詠唱/火 |
| 呪術 | 10 | 呪詛/邪気/闇 |
| 具現 | 15 | 創造/召喚 |
| 響鳴 | 10 | 歌唱/音楽/振動 |
| 付加 | 45 | 装備品への素材の付加に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 6 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ティンダー | 5 | 0 | 50 | 敵:火撃&炎上 | |
| ウォーターフォール | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |
| 決2 | カース | 5 | 0 | 50 | 敵:闇撃&束縛 |
| アサルト | 6 | 0 | 50 | 敵:痛撃+自:連続減 | |
| クリエイト:タライ | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |
| エチュード | 5 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) | |
| プリディクション | 5 | 0 | 120 | 味列:AG増(3T) | |
| ダークフレア | 5 | 0 | 60 | 敵:火撃&炎上・盲目 | |
| クリエイト:ダイナマイト | 5 | 0 | 120 | 自:道連LV増 | |
| ファイアダンス | 5 | 0 | 80 | 敵:2連火領撃&炎上+領域値[火]3以上なら、火領撃&炎上 | |
| ボロウライフ | 5 | 0 | 70 | 敵:闇撃&味傷:HP増 | |
| アクアシェル | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+火耐性増 | |
| クリエイト:スパイク | 5 | 0 | 60 | 敵貫:闇痛撃&衰弱 | |
| カースワード | 5 | 0 | 130 | 敵全:闇撃&腐食 | |
| キャプチャートラップ | 5 | 0 | 90 | 敵列:罠《捕縛》LV増 | |
| クリエイト:パワードスピーカー | 5 | 0 | 130 | 自:魅了LV増 | |
| ファイアボルト | 5 | 0 | 100 | 敵貫:火痛撃 | |
| 決1 | アクアヒール | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 |
| 決3 | ダークネス | 5 | 0 | 100 | 敵列:闇撃&盲目 |
| ペナルティ | 5 | 0 | 120 | 敵3:麻痺・混乱 | |
| ビブラート | 5 | 0 | 120 | 敵全2:粗雑SP攻撃 | |
| ブロック | 5 | 0 | 80 | 自:守護+DF増(2T)+味傷:護衛 | |
| ワンオンキル | 5 | 0 | 100 | 敵:闇撃+自:闇撃 | |
| クリエイト:ファイアウェポン | 5 | 0 | 200 | 味:炎上LV・反火LV増 | |
| バーニングチューン | 5 | 0 | 140 | 自:炎上+敵5:火撃&麻痺 | |
| ディープフリーズ | 5 | 0 | 110 | 敵:凍結 | |
| ディバウア | 5 | 0 | 80 | 自従傷:喰LV増 | |
| ディプラヴィティ | 5 | 0 | 160 | 敵列:闇撃&自堕落LV増 | |
| ジャックポット | 5 | 0 | 110 | 敵傷:粗雑痛撃+回避された場合、3D6が11以上なら粗雑痛撃 | |
| コントラクト | 5 | 0 | 80 | 自従:契LV増 | |
| ピットトラップ | 5 | 0 | 120 | 敵全:罠《奈落》LV増 | |
| サモン:サーヴァント | 6 | 5 | 300 | 自:サーヴァント召喚 | |
| リンクブレイク | 5 | 0 | 150 | 敵全:精確攻撃&従者ならDX・AG減(3T) | |
| サモン:シャドウ | 5 | 5 | 400 | 自:シャドウ召喚 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 召喚強化 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:具現LVが高いほど自身の召喚するNPCが強化 | |
| 五月雨 | 5 | 4 | 0 | 【スキル使用後】敵:3連水撃 | |
| 決3 | 闇の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:呪術LVが高いほど闇特性・耐性増 |
| 死線 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:現在HP割合が低いほど攻撃命中率増 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
雨の癒し (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
|
引き裂く爪 (チャージ) |
0 | 100 | 敵:4連鎖撃 | |
| 決1 |
ひよこのゆめ (ファーマシー) |
0 | 110 | 味傷:HP増+肉体精神変調減 |
|
コンセントレイト (ブレイドフォーム) |
0 | 160 | 自:AT増 | |
|
ヒール (リザレクション) |
0 | 150 | 味傷:HP増+瀕死ならHP増 | |
|
どっかーん (ジャイアントキル) |
0 | 250 | 敵:X連火領撃 ※X=対象の強化ターン効果の数+1 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 2 ]五月雨 | [ 3 ]キャプチャートラップ | [ 2 ]アサルト |
| [ 2 ]サモン:サーヴァント | [ 2 ]ブロック | [ 2 ]ボロウライフ |
| [ 2 ]プリディクション |

PL / .