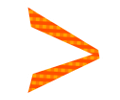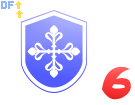<< 2:00~3:00




「あんなの、きにすることないんだからね」
そう言って、泣いている自分の手を握り隣を歩いてくれた幼馴染みの手の感触を、言祝愛夢は今でも覚えている。
「あむにはおとうさんはいないけど……おかあさんやおれだっているからね」
公園で自分より少しだけ年上の子供たちに、父親がいないことをからかわれて泣いてしまっていた自分を、助けてくれたのは幼馴染みの吉野俊彦だった。
自分たちより身体が大きな数人の子供から、自分を背に庇ってくれた。それでも怖くて泣き止めない自分の手を引いて、その場から連れ出してくれたのだ。
まだそれ程背丈も変わらないはずなのに、その背中がとても大きく頼もしく見えたのも、愛夢はしっかりと覚えている。
「トシくん」
「なに? あむ」
真っ直ぐ前を向いていた俊彦が自分を見る。優しい表情をしていた。
「ありがとう」
「うん。あむはおれがまもるからね」
にぱ、と笑った幼馴染みにようやく愛夢も笑顔を返せたのだ。
幼い日の、他愛のない約束。
なんてことはない、優しい思い出。
だけど、心の中にずっと残り続ける宝物のような思い出。
ーーそれが、幻だったなんて、想像したこともなかった。
「あー、あ」
移動中の小休憩中ちょっとだけパーティメンバーから離れて、愛夢は1人でぼんやりと朽ちかけたベンチで休んでいた。
ハザマに来ると、嫌でも考えてしまう。
――幼馴染みの、吉野俊彦のこと。
彼もワールドスワップの影響でイバラシティに紛れ込んだアンジニティの住人であり、本来の姿はくすんだ金髪の壮年の男性だ。
ワールドスワップが行なわれたのがつい数ヶ月前であることを考えると、当然吉野俊彦が実際に存在している期間も数ヶ月。
故に、当たり前のことであるが、愛夢の幼少期に吉野俊彦は存在していない。
だから、彼との思い出も何もかも、本当は幻なのだ。
その事実を愛夢は上手く受け入れられていない。彼が存在していない、それは解った。解ったが、あの大切な思い出の数々が嘘や幻だったとは、どうしても受け入れられないのだ。
――本来の姿がどうであれ、彼が大切だ。だったと過去形にはとてもじゃないが出来やしない。
偽りの日々だと解っても尚、それらはキラキラと輝いて見えるのだ。
だって、心の支えだった。
小さな頃の彼と他愛のない日々が、今の自分を形作っているという、確信がある。
でも、それすらがそもそも幻で――。
足元がおぼつかない感覚。色んな物がガラガラと崩れるような、そんな感覚。
「…………。トシくんがいなくたって、」
そう、強がってみようとするがそれ以上は出てこない。
彼がいなくても大丈夫、だなんて嘘でも言えない。
あの金髪の男性にこそ「大丈夫」だと言ったものの、実際は泣きそうで仕方がなかった。
「あーぁ」
大切な人はいなくなっていく。
母も、幼馴染も。
もしかしたら、楽しい友人たちや、愉快な先輩だって――。
「―――――――うぇ、」
喉元から酸っぱいものが込み上がるのを感じる。それを無理やり飲み下して、ギュッと眉を寄せて、深呼吸。
心臓がバクバクせわしなく動いて、嫌な汗が流れるのを感じる。
覚えがある感覚だ。母が事故にあったと、連絡を受けた時によく似ている。
その時も、支えになってくれたのは幼馴染と友人達だった。
親類のほとんどいない愛夢にとって、それはどれほど心強かったことか。
だけど、少なくともこのハザマでは、あの幼馴染はいないのだ。
何も言わず手を握ってくれた、あの自分より大きくて少しゴツゴツした手の男の子はいないのだ。
「……辛いなぁ」
言いながら、口元をマッサージする。それから人差し指で口角をキュッと上げて、笑みを作る。
笑おう。
アイドルは笑ってなんぼだ。辛くたって、悲しくたって、誰かの理想の為に笑うのが、役割だ。
以前同級生に言ったように、そこには自分の気持は関係ない。自分がどんな気持ちであろうが、自分の笑顔に、“誰か”が夢見てくれればそれでいい。“誰か”が己の理想と夢を自分に――MUAに、押し付けて、それで楽になったり、元気になってくれるなら、それでいい。
――それが、言祝愛夢の、そしてMUAの“価値”だ。
それはその同級生に地獄だとも言われたけれど。
“今は”それで構わない。
きっと笑ったほうがトシくんだった男性も安心するだろう。
彼はトシくんではない。一緒に成長を重ねてきた幼馴染ではなく、彼なりの事情のある“誰か”なのだから。
それに、「そこまでをお前にかける義理はない 」とも言っていたし。
だったら、笑おう。
“あなたがいなくても大丈夫”
そう笑おう。ステージの上に立って歌って踊るように。
もし気に病んでいるのなら、その必要はないからって。
「大丈夫」
足に力を入れる。
背筋をピンと伸ばして、まっすぐ前を見て。
指先まで神経を張る。ここで手を抜いてしまっては、素人もいい所だ。
そして、何よりも大事なのは笑顔だ。
夢を見させるに相応しい、笑顔。
――――笑え。
「まだ、笑える」
そう口元を上げて、笑った。
そして気づく。
言祝愛夢が言祝愛夢として笑えたのは、友人たちや――幼馴染がいたからだったと。
そのひとつを、喪った。



ENo.165 フェデルタ とのやりとり

ENo.1191 音々子 とのやりとり

以下の相手に送信しました














少年?(883) から 30 PS 受け取りました。
命術LV を 5 UP!(LV5⇒10、-5CP)
料理LV を 5 UP!(LV30⇒35、-5CP)
ひばり(1219) により ItemNo.9 白樺 から装飾『水色のリボン』を作製してもらいました!
⇒ 水色のリボン/装飾:強さ67/[効果1]活力10 [効果2]- [効果3]-
少年?(883) の持つ ItemNo.7 不思議な食材 から料理『ブラウニー』をつくりました!
少年?(883) の持つ ItemNo.9 美味しい果実 から料理『フルーツタルト』をつくりました!
音々子(1191) の持つ ItemNo.7 不思議な食材 から料理『不思議なアイス』をつくりました!
ニノマエ(46) とカードを交換しました!
ブランチ (ブランチ)

パワフルヒール を研究しました!(深度0⇒1)
パワフルヒール を研究しました!(深度1⇒2)
パワフルヒール を研究しました!(深度2⇒3)
アクアヒール を習得!
アクアブランド を習得!
フローズンフォーム を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





チナミ区 H-16(チェックポイント)に移動!(体調15⇒14)
チナミ区 I-16(道路)に移動!(体調14⇒13)
チナミ区 J-16(森林)に移動!(体調13⇒12)
チナミ区 J-17(森林)に移動!(体調12⇒11)
チナミ区 J-18(森林)に移動!(体調11⇒10)
採集はできませんでした。
- あかね(945) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- 仏の男(950) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
MISSION!!
チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》 が発生!
- 愛夢(912) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- あかね(945) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- 仏の男(950) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- 音々子(1191) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》






―― ハザマ時間が紡がれる。


チャット画面にふたりの姿が映る。
チャットに響く声。

画面に現れる3人目。
上目遣いでふたりに迫る。
ノイズで一部が聞き取れない。
突然現れるドライバーさん。
賑やかな雰囲気のまま、チャットが閉じられる――












仄かな光に包まれた六角形の柱が立っている。
・・・柱から滲み出るように、何かが生み出される。

それは言葉を発すると共に襲いかかる!
(初発生のイベント戦:異能FP+5!生産FP+5!)














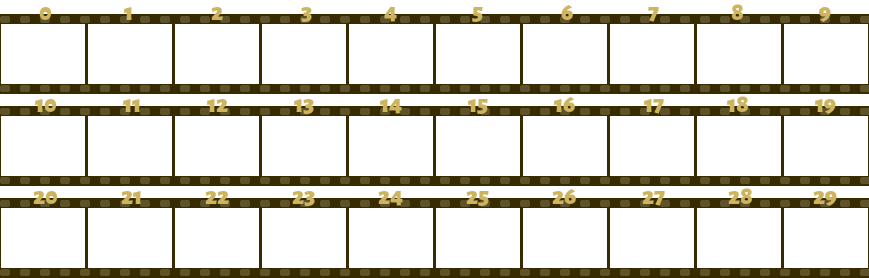







































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



「あんなの、きにすることないんだからね」
そう言って、泣いている自分の手を握り隣を歩いてくれた幼馴染みの手の感触を、言祝愛夢は今でも覚えている。
「あむにはおとうさんはいないけど……おかあさんやおれだっているからね」
公園で自分より少しだけ年上の子供たちに、父親がいないことをからかわれて泣いてしまっていた自分を、助けてくれたのは幼馴染みの吉野俊彦だった。
自分たちより身体が大きな数人の子供から、自分を背に庇ってくれた。それでも怖くて泣き止めない自分の手を引いて、その場から連れ出してくれたのだ。
まだそれ程背丈も変わらないはずなのに、その背中がとても大きく頼もしく見えたのも、愛夢はしっかりと覚えている。
「トシくん」
「なに? あむ」
真っ直ぐ前を向いていた俊彦が自分を見る。優しい表情をしていた。
「ありがとう」
「うん。あむはおれがまもるからね」
にぱ、と笑った幼馴染みにようやく愛夢も笑顔を返せたのだ。
幼い日の、他愛のない約束。
なんてことはない、優しい思い出。
だけど、心の中にずっと残り続ける宝物のような思い出。
ーーそれが、幻だったなんて、想像したこともなかった。
「あー、あ」
移動中の小休憩中ちょっとだけパーティメンバーから離れて、愛夢は1人でぼんやりと朽ちかけたベンチで休んでいた。
ハザマに来ると、嫌でも考えてしまう。
――幼馴染みの、吉野俊彦のこと。
彼もワールドスワップの影響でイバラシティに紛れ込んだアンジニティの住人であり、本来の姿はくすんだ金髪の壮年の男性だ。
ワールドスワップが行なわれたのがつい数ヶ月前であることを考えると、当然吉野俊彦が実際に存在している期間も数ヶ月。
故に、当たり前のことであるが、愛夢の幼少期に吉野俊彦は存在していない。
だから、彼との思い出も何もかも、本当は幻なのだ。
その事実を愛夢は上手く受け入れられていない。彼が存在していない、それは解った。解ったが、あの大切な思い出の数々が嘘や幻だったとは、どうしても受け入れられないのだ。
――本来の姿がどうであれ、彼が大切だ。だったと過去形にはとてもじゃないが出来やしない。
偽りの日々だと解っても尚、それらはキラキラと輝いて見えるのだ。
だって、心の支えだった。
小さな頃の彼と他愛のない日々が、今の自分を形作っているという、確信がある。
でも、それすらがそもそも幻で――。
足元がおぼつかない感覚。色んな物がガラガラと崩れるような、そんな感覚。
「…………。トシくんがいなくたって、」
そう、強がってみようとするがそれ以上は出てこない。
彼がいなくても大丈夫、だなんて嘘でも言えない。
あの金髪の男性にこそ「大丈夫」だと言ったものの、実際は泣きそうで仕方がなかった。
「あーぁ」
大切な人はいなくなっていく。
母も、幼馴染も。
もしかしたら、楽しい友人たちや、愉快な先輩だって――。
「―――――――うぇ、」
喉元から酸っぱいものが込み上がるのを感じる。それを無理やり飲み下して、ギュッと眉を寄せて、深呼吸。
心臓がバクバクせわしなく動いて、嫌な汗が流れるのを感じる。
覚えがある感覚だ。母が事故にあったと、連絡を受けた時によく似ている。
その時も、支えになってくれたのは幼馴染と友人達だった。
親類のほとんどいない愛夢にとって、それはどれほど心強かったことか。
だけど、少なくともこのハザマでは、あの幼馴染はいないのだ。
何も言わず手を握ってくれた、あの自分より大きくて少しゴツゴツした手の男の子はいないのだ。
「……辛いなぁ」
言いながら、口元をマッサージする。それから人差し指で口角をキュッと上げて、笑みを作る。
笑おう。
アイドルは笑ってなんぼだ。辛くたって、悲しくたって、誰かの理想の為に笑うのが、役割だ。
以前同級生に言ったように、そこには自分の気持は関係ない。自分がどんな気持ちであろうが、自分の笑顔に、“誰か”が夢見てくれればそれでいい。“誰か”が己の理想と夢を自分に――MUAに、押し付けて、それで楽になったり、元気になってくれるなら、それでいい。
――それが、言祝愛夢の、そしてMUAの“価値”だ。
それはその同級生に地獄だとも言われたけれど。
“今は”それで構わない。
きっと笑ったほうがトシくんだった男性も安心するだろう。
彼はトシくんではない。一緒に成長を重ねてきた幼馴染ではなく、彼なりの事情のある“誰か”なのだから。
それに、「そこまでをお前にかける義理はない 」とも言っていたし。
だったら、笑おう。
“あなたがいなくても大丈夫”
そう笑おう。ステージの上に立って歌って踊るように。
もし気に病んでいるのなら、その必要はないからって。
「大丈夫」
足に力を入れる。
背筋をピンと伸ばして、まっすぐ前を見て。
指先まで神経を張る。ここで手を抜いてしまっては、素人もいい所だ。
そして、何よりも大事なのは笑顔だ。
夢を見させるに相応しい、笑顔。
――――笑え。
「まだ、笑える」
そう口元を上げて、笑った。
そして気づく。
言祝愛夢が言祝愛夢として笑えたのは、友人たちや――幼馴染がいたからだったと。
そのひとつを、喪った。



ENo.165 フェデルタ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.1191 音々子 とのやりとり
| ▲ |
| ||
以下の相手に送信しました







チグハグラプソディ
|
 |
Un Alice+
|



対戦相手未発見のため不戦勝!
影響力が 2 増加!
影響力が 2 増加!



少年?(883) から 30 PS 受け取りました。
 |
忽然と目の前に小さな子供が現れ、てのひらの貨幣を貴女に差し出した |
命術LV を 5 UP!(LV5⇒10、-5CP)
料理LV を 5 UP!(LV30⇒35、-5CP)
ひばり(1219) により ItemNo.9 白樺 から装飾『水色のリボン』を作製してもらいました!
⇒ 水色のリボン/装飾:強さ67/[効果1]活力10 [効果2]- [効果3]-
 |
ひばり 「はい!水色のリボン、かわいくできたよ!」 |
少年?(883) の持つ ItemNo.7 不思議な食材 から料理『ブラウニー』をつくりました!
少年?(883) の持つ ItemNo.9 美味しい果実 から料理『フルーツタルト』をつくりました!
音々子(1191) の持つ ItemNo.7 不思議な食材 から料理『不思議なアイス』をつくりました!
ニノマエ(46) とカードを交換しました!
ブランチ (ブランチ)

パワフルヒール を研究しました!(深度0⇒1)
パワフルヒール を研究しました!(深度1⇒2)
パワフルヒール を研究しました!(深度2⇒3)
アクアヒール を習得!
アクアブランド を習得!
フローズンフォーム を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





チナミ区 H-16(チェックポイント)に移動!(体調15⇒14)
チナミ区 I-16(道路)に移動!(体調14⇒13)
チナミ区 J-16(森林)に移動!(体調13⇒12)
チナミ区 J-17(森林)に移動!(体調12⇒11)
チナミ区 J-18(森林)に移動!(体調11⇒10)
採集はできませんでした。
- あかね(945) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- 仏の男(950) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
MISSION!!
チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》 が発生!
- 愛夢(912) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- あかね(945) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- 仏の男(950) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- 音々子(1191) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
エディアン 「・・・・・あら?」 |
 |
白南海 「おっと、これはこれは。」 |

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
チャット画面にふたりの姿が映る。
 |
エディアン 「こんにちは白南海さん。元気そうで何より。」 |
 |
白南海 「そう尖らんでも、嬢さん。折角の美人が台無しだ。」 |
 |
エディアン 「・・・それもそうですね、私達同士がどうこうできる訳でもないですし。 それで、これは一体なんなんでしょう?」 |
 |
白南海 「招待されたとか、さっき出てましたけど。」 |
 |
「そ!お!でぇぇ―――っす☆」 |
チャットに響く声。

ミヨチン
茶色の瞳、桜色のロング巻き髪。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
画面に現れる3人目。
 |
白南海 「まぁた、うるせぇのが。・・・ってぇ、こいつァ・・・・・?」 |
 |
エディアン 「ロストじゃないですか、このこ。」 |
 |
白南海 「それとその格好・・・やっぱイバラシティの人間じゃ?あんた。」 |
 |
ミヨチン 「ロスト?イバラシティ?何のことっすかぁ??」 |
 |
ミヨチン 「それよりそれよりぃ!ミヨチンの願いを叶えてくれるって、聞いたんすけどぉー。」 |
上目遣いでふたりに迫る。
 |
白南海 「なるほど。こんな感じであっちから来るんすかねぇ、ロスト。」 |
 |
エディアン 「そっすねぇー。意外っすー。」 |
 |
ミヨチン 「聞いてるんすかぁ!?叶えてくれるんっすかぁー!!?」 |
 |
エディアン 「えぇ叶えます!叶えますともっ!!」 |
 |
白南海 「無茶なことじゃなけりゃー、ですがね。」 |
 |
ミヨチン 「やったーっ!!ミヨチンは、団子!団子が食べたいんすよぉ!! 美味しいやつ!!美味しい団子をたらふく食べたいッ!!」 |
 |
ミヨチン 「好みを言うなら―― ザザッ・・・ 堂のあんこたっぷりの―― ザザッ・・・ 団子がいいんすよねぇ! ガッコー帰りによく友達と食べてたんすよぉ!!」 |
ノイズで一部が聞き取れない。
 |
白南海 「団子だァ・・・??どんな願望かと思えばなんつぅ気の抜けた・・・」 |
 |
エディアン 「しかしこのハザマでお団子、お団子ですかぁ。」 |
 |
白南海 「イバラシティの団子屋なら、梅楽園のが絶品なんすけどねぇ。」 |
 |
エディアン 「あぁ!あそこのお団子はモッチモチで美味しかったです!! 夢のような日々の中でもあれはまた格別でしたねぇ!!」 |
 |
ミヨチン 「マジっすか!それ!それ食べれねぇんすかぁー!?」 |
 |
ドライバーさん 「食べれるぞ。」 |
突然現れるドライバーさん。
 |
白南海 「・・・び、ビビらせねぇでくれませんか?」 |
 |
ドライバーさん 「ビビったんか、そりゃすまん。」 |
 |
エディアン 「こんにちはドライバーさん。・・・お団子、食べれるんですか?」 |
 |
ドライバーさん 「おう。地図見りゃ分かるだろうが、ハザマのモデルはイバラシティだ。 そんでもって一部の名所は結構再現されてる、ハザマなりに・・・な。試しに見てくるといい。」 |
 |
エディアン 「ほんとですか!?ハザマも捨てたもんじゃないですねぇ!!」 |
 |
白南海 「いや、捨てたもんじゃって・・・なぁ・・・・・」 |
 |
ミヨチン 「んじゃんじゃその梅楽園の団子!よろしくお願いしゃーっす!!」 |
 |
白南海 「あの辺なら誰かしら丁度向かってる頃じゃねぇすかねぇ。」 |
 |
エディアン 「よろしく頼みますよぉ皆さん!私も後で行きたいなぁーっ!!」 |
 |
白南海 「・・・何か気が抜ける空気っすねぇ、やっぱ。」 |
賑やかな雰囲気のまま、チャットが閉じられる――







TeamNo.111
|
 |
ドキッ☆アイドルだらけのイバラPT~feat. 仏~
|




チナミ区 H-16
チェックポイント《瓦礫の山》
チェックポイント。チェックポイント《瓦礫の山》
仄かな光に包まれた六角形の柱が立っている。
・・・柱から滲み出るように、何かが生み出される。

守護者《DEER》
黒闇に包まれた巨大なシカのようなもの。
 |
守護者《DEER》 「――我が脳は我が姫の意思。我が力は我が主の力。」 |
それは言葉を発すると共に襲いかかる!
(初発生のイベント戦:異能FP+5!生産FP+5!)



ドキッ☆アイドルだらけのイバラPT~feat. 仏~
|
 |
立ちはだかるもの
|


ENo.912
言祝 愛夢



時間について:深夜と昼間に出現することが多いです。割と置きレスになりやすいので、置きレス歓迎。、リアルタイムで返せる時は返します。
+++++++++
言祝 愛夢(ことほぎ あむ)/15歳(12月27日)/女性/高校1年生
とあるライブハウスをメインに活動している地下アイドルの少女。小鳥遊朱音(ENo.945)と夢見音々子(ENo.1191)ユニット「アンアリス」を組む。
そのライブハウスでの認知度はあるが、メディアの露出はほぼほぼないのでイバラシティではほぼ無名。とは言え知ってる人は知ってる。
活動開始は中学卒業直後。大体のことはそつなくこなす優等生。
アイドル名は「MUA」
相良伊橋高校の1年生。クラスは4組。学校や私生活では伊達メガネをかけている。
学校ではアイドル活動のことは基本的に口にしないので、知らない人は全く知らない。
登校日数はギリギリよりやや上ライン、授業態度はまあ普通、成績は中の上。
身長153cmで小柄だが、胸の自己主張が激しい。
一年前(中学三年、14歳の秋頃)に片親であった母親が交通事故で死亡。
今は慰謝料と保険金で一人暮らし。
必要なときに書類にサインをしてくれたり、保護者が必要なときに来たりしてくれる便利な母方の叔父(NPC)の後見人がおり、かなり自由な生活を送っている。
異能:ドリームキャッチャー
祝福を与えた相手に一晩~数日の間悪夢を見せない異能。
本人曰く「運が良ければいい夢が見れる」
ただし、この異能を発動した段階で言祝本人はその晩悪夢を見ることが確定する。
また、“悪夢を溜めておく”ことが出来るらしい。
※ロールの際の異能の使用に関して
言祝が異能を使用した際の悪夢を見る/見ない、いい夢を見る/見ない等は受け手側のPLさん/PCさん側にお任せします。
悪夢を見ない確率が上がり、いい夢を見る確率が上がる(確率は不明)くらいに思ってくだされば幸いです。
※その他
既知歓迎。アイドル活動についても可。
交流歓迎です。
+++サブキャラクター++++
英 静(はなぶさ せい)/33歳/女性/ライブハウスオーナー
ライブハウス「HEAVENS FINGER」のオーナー。
ライブハウスでの愛称は「マム」
30代の女性。耳はピアスだらけで所々に刺青が見えるが悪い人ではない。
10歳(推定)までの記憶がなく、いつのまにかイバラシティにいた。その後養父に引き取られたりして今に至る。
雇っているマスター(NPC)と共に料理やドリンクを作ったり、バイトに指示をだしたり、ライブの出演者の調整などを行う。
しかしながらいないことも多いく、マスターが大体オーナー代理を行っている。
この女性の異能でこのライブハウスは騒音問題とは無縁である。
異能:静を制するものは音を制する
音を“閉じ込める”異能。
主にライブハウスから音漏れをさせないために使われる異能である。
*既知可。交流歓迎
+++++++
めちゃくちゃキュートでかわいいイラストはカミヤさんからいただきました。ありがとうございます!
+++++++++
言祝 愛夢(ことほぎ あむ)/15歳(12月27日)/女性/高校1年生
とあるライブハウスをメインに活動している地下アイドルの少女。小鳥遊朱音(ENo.945)と夢見音々子(ENo.1191)ユニット「アンアリス」を組む。
そのライブハウスでの認知度はあるが、メディアの露出はほぼほぼないのでイバラシティではほぼ無名。とは言え知ってる人は知ってる。
活動開始は中学卒業直後。大体のことはそつなくこなす優等生。
アイドル名は「MUA」
相良伊橋高校の1年生。クラスは4組。学校や私生活では伊達メガネをかけている。
学校ではアイドル活動のことは基本的に口にしないので、知らない人は全く知らない。
登校日数はギリギリよりやや上ライン、授業態度はまあ普通、成績は中の上。
身長153cmで小柄だが、胸の自己主張が激しい。
一年前(中学三年、14歳の秋頃)に片親であった母親が交通事故で死亡。
今は慰謝料と保険金で一人暮らし。
必要なときに書類にサインをしてくれたり、保護者が必要なときに来たりしてくれる便利な母方の叔父(NPC)の後見人がおり、かなり自由な生活を送っている。
異能:ドリームキャッチャー
祝福を与えた相手に一晩~数日の間悪夢を見せない異能。
本人曰く「運が良ければいい夢が見れる」
ただし、この異能を発動した段階で言祝本人はその晩悪夢を見ることが確定する。
また、“悪夢を溜めておく”ことが出来るらしい。
※ロールの際の異能の使用に関して
言祝が異能を使用した際の悪夢を見る/見ない、いい夢を見る/見ない等は受け手側のPLさん/PCさん側にお任せします。
悪夢を見ない確率が上がり、いい夢を見る確率が上がる(確率は不明)くらいに思ってくだされば幸いです。
※その他
既知歓迎。アイドル活動についても可。
交流歓迎です。
+++サブキャラクター++++
英 静(はなぶさ せい)/33歳/女性/ライブハウスオーナー
ライブハウス「HEAVENS FINGER」のオーナー。
ライブハウスでの愛称は「マム」
30代の女性。耳はピアスだらけで所々に刺青が見えるが悪い人ではない。
10歳(推定)までの記憶がなく、いつのまにかイバラシティにいた。その後養父に引き取られたりして今に至る。
雇っているマスター(NPC)と共に料理やドリンクを作ったり、バイトに指示をだしたり、ライブの出演者の調整などを行う。
しかしながらいないことも多いく、マスターが大体オーナー代理を行っている。
この女性の異能でこのライブハウスは騒音問題とは無縁である。
異能:静を制するものは音を制する
音を“閉じ込める”異能。
主にライブハウスから音漏れをさせないために使われる異能である。
*既知可。交流歓迎
+++++++
めちゃくちゃキュートでかわいいイラストはカミヤさんからいただきました。ありがとうございます!
10 / 30
107 PS
チナミ区
J-18
J-18







































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | ファンシーなマイク | 武器 | 35 | 攻撃10 | - | - | 【射程1】 |
| 5 | 白のレースワンピース | 防具 | 40 | 防御10 | - | - | |
| 6 | 不思議なお餅 | 料理 | 35 | 器用10 | 敏捷10 | 耐疫10 | |
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 8 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
| 9 | 水色のリボン | 装飾 | 67 | 活力10 | - | - | |
| 10 | 美味しくない草 | 素材 | 10 | [武器]耐疫10(LV30)[防具]体力10(LV30)[装飾]強靭10(LV30) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 10 | 身体/武器/物理 |
| 命術 | 10 | 生命/復元/水 |
| 具現 | 5 | 創造/召喚 |
| 変化 | 10 | 強化/弱化/変身 |
| 料理 | 35 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 6 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 | |
| ウォーターフォール | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |
| クリエイト:タライ | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |
| ガードフォーム | 6 | 0 | 100 | 自:DF増 | |
| 決1 | フロウライフ | 5 | 0 | 80 | 自:MHP・DF増 |
| クリエイト:シールド | 5 | 2 | 200 | 自:DF増+守護 | |
| クリーンヒット | 5 | 0 | 60 | 敵:痛撃&次与ダメ減 | |
| アクアシェル | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+火耐性増 | |
| アンダークーリング | 5 | 0 | 70 | 敵傷:水撃+自:腐食+3D6が15以上なら凍結LV増 | |
| ローバスト | 5 | 0 | 100 | 自従:MSP・AT増 | |
| チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 | |
| 決2 | アクアヒール | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 |
| ディベスト | 5 | 0 | 70 | 敵:強化奪取+痛撃 | |
| アクアブランド | 5 | 1 | 50 | 敵:水痛撃&味傷:HP増 | |
| ガーディアンフォーム | 5 | 0 | 200 | 自:DF・HL増+連続減 | |
| フローズンフォーム | 5 | 0 | 150 | 自:反水LV・放凍LV増+凍結 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
ブレイク (ブレイク) |
0 | 50 | 敵:攻撃 | |
|
蔦市民章2 (チャージ) |
0 | 100 | 敵:4連鎖撃 | |
|
呪符:誰かの怖いもの (ブレイク) |
0 | 50 | 敵:攻撃 | |
|
ブランチ (ブランチ) |
0 | 100 | 敵:地痛撃&領域値[地]3以上なら、敵傷:地領痛撃 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]アクアヒール | [ 1 ]ガードフォーム | [ 1 ]クリーンヒット |
| [ 1 ]チャージ | [ 3 ]パワフルヒール |

PL / 月影冠