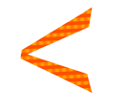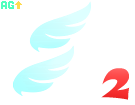<< 2:00~3:00




蝉の鳴き声が降り注ぐ、七月の終わり。
学校はもう夏休みに入っていた。
沢山の宿題と、進路のことや志望校のこと。それと、家庭のこと、家族のこと。さまざまな感情が綯い混ぜになって言葉にするのが難しい。ざわざわして、耳を塞ぎたくなる時もある。
心に抱え込んだものは色に例えるなら、限りなく黒に近い灰色かもしれない。鉛筆でぐりぐり塗り潰して、真っ黒で見えなくなった落書きのよう。
塗りつぶす前に、私は何を書いていたのだろう。
絵だったのか、単なるメモだったのか。何も覚えていない。
ほんの数秒前の出来事も、たまに思い出せなくて苛立ってしまう。これはきっと受験に対してのストレスだ。
自分は今、神経質になっているんだ。
些細なことでも苛立って、お腹がムカムカしたり、頭が痛くなったりしてしまう。悲しくなることはなかったけど、たまに自己嫌悪に陥ったりと忙しない。
ああ、いやだなぁ。こんなの。
中学生最後の夏休みは、少しだけ刺がささった痛みを感じながら始まった。
部活も、最後の大会をあと一週間後に控えている。今日は朝の涼しい時間に集まってのランニングと筋トレと、スタートダッシュの練習、いつもと代わり映えのない練習メニュー。
二時間くらいはやったのだろうか。
夏場はどうしても暑くなりがちで、外での運動は体調不良を起こすことも多い。気温が高くなるとそんなに長くやらせてもらえないのが現状だ。
それでも、朝の少しだけ涼しい空気の中を。目映い青空の下を。
思いっきり走れるのは、とても気持ち良い。
走っている時は自由で、自分を縛るものは何もなくて、ただひたすら、前にあるゴールラインを目指せばいい。
石灰で引かれた白線。青い空。生温い風。グラウンドに木霊する蝉の声。見えるもの、聞こえるものすべてが刹那の幻のよう。
ちくりと感じる刺の痛みも――今だけは、忘れることが出来る。
走れば、イヤなことから逃げられる。
ぐちゃぐちゃになったわたしの頭の中を、全部真っ白にできる。走れば。ただひたすら走ればよかった。
好きとか嫌いとか、そんなものじゃなかった。
逃げたかった。目の前にあるものすべてから。
ただ、それだけ。
だからね、遠野くん。
「……好きとか、そういうものじゃないよ。私にとって走ることは」
隣を歩く、背丈の高い少年を振り向きもせず。
少女は答えた。
「えー。じゃあ、好きじゃなかったら、キライってことですか?」
「嫌いじゃないわよ。嫌いだったらそもそも走ってないし、部活だって入らないし」
「つまり好きってことっすよね!」
少年は嬉しそうに言うと、眩しいほどの笑顔を向ける。対して少女はうんざりした面持ちだ。
「だから、好きじゃないってば。遠野くんさ、世の中には好きと嫌いの二つ以外だってあるでしょ? そういうものなの」
「そうなんですか? オレは好きとキライしかないですけど」
「それは遠野くんがそういう性格だからでしょ。君と一緒にしないで」
低い声で少年の主張を突っぱねる。明らかに不機嫌だ。少女は大きく溜め息を吐いてから足を止めた。
「遠野くんと私は違うの。君の価値観はよくわかったから、それを私に押し付けるのやめて」
「押し付けてないっすよ! だってセンパイが」
「私がなに? 走るのが好きって答えないのがそんなにおかしいの?」
語気を荒立ててしまう。そんなつもりはなかったのだが、感情を抑えることが出来なかった。
少女は、隣にいる少年を見ようとはしない。視線は真っ直ぐのまま、暗い夜道を睨み付けて。
遠野が聞きたいのは。聞きたかったのは、自分が陸上を好きだという気持ち。それを確かめたかったのだろう。
言い返した言葉から、そんな気持ちが透けて見えたかもしれない。
少女は唇を噛み締め、俯いた。
「全力で、走ることを楽しんでる遠野くんには。今の私の気持ちは、絶対にわからないよ」
息が苦しい。視界が滲んでいく感覚に、心が悲鳴をあげている。
自分にもわからない。この焦りが何なのか。
そしてこの少年にも、わかって欲しいとも思わない。そんな都合のいいことを言えるわけがない。
この少年はただ、走ることが大好きなだけ。
誰よりも速く走りたくて、誰よりも走ることが大好きで、きっと一年後も「陸上が好きだから、オレは続けますよ」と笑ってくれるのだろう。
わかっている。分かりきっていたことだ。
彼と自分は、まったく違うのだ。
「ごめん、遠野くん。これじゃあただの八つ当たりだね」
生温い風が頬を撫でて、蜩の声が夕暮れにこだまする。夏なのに心が寒さを感じるのはどうしてだろう。
少女は頭を振って。
「本当にごめんなさい。私、今はどうやっても君を傷付けることしか言えない。……前みたいに、君と一緒に笑えない。楽しめない」
早口にそう言って、大きく嘆息した。
鞄を持つ手に力が入り、そのまま逃げるように走り去ろうとする。
視界が滲む。目が熱い。胸が痛い。息が苦しい。
感情が込み上げて、どうすることも出来ない。
十五の夏。私が夏をもっと嫌いになったこの日。
生まれて初めて、身近な誰かを『否定』し『拒絶 』した。
--------------------------------------------------------
episode2:夏影
--------------------------------------------------------



ENo.356 眠 とのやりとり

ENo.412 スノウストーム とのやりとり

以下の相手に送信しました




ItemNo.1 不思議な武器 を破棄しました。
ItemNo.3 不思議な装飾 を破棄しました。








自然LV を 5 UP!(LV10⇒15、-5CP)
装飾LV を 5 UP!(LV10⇒15、-5CP)
ItemNo.8 ネジ から射程4の大砲『韋駄天』を作製しました!
⇒ 韋駄天/大砲:強さ45/[効果1]- [効果2]- [効果3]-【射程4】
地の祝福 を習得!
沙羅双樹 を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





チナミ区 J-6(沼地)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 J-7(沼地)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 K-7(森林)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 K-8(隔壁)には移動できません。
チナミ区 K-8(隔壁)には移動できません。






―― ハザマ時間が紡がれる。


チャット画面にふたりの姿が映る。
チャットに響く声。

画面に現れる3人目。
上目遣いでふたりに迫る。
ノイズで一部が聞き取れない。
突然現れるドライバーさん。
賑やかな雰囲気のまま、チャットが閉じられる――
















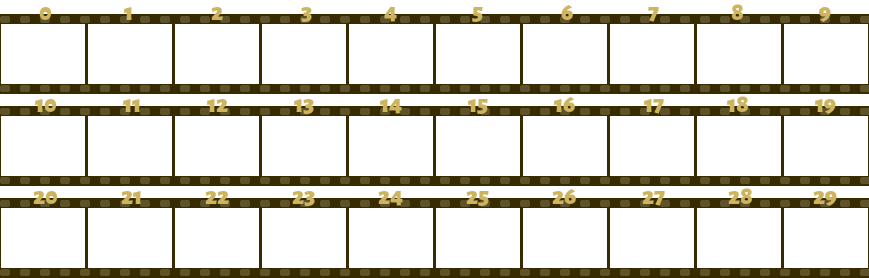





































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



蝉の鳴き声が降り注ぐ、七月の終わり。
学校はもう夏休みに入っていた。
沢山の宿題と、進路のことや志望校のこと。それと、家庭のこと、家族のこと。さまざまな感情が綯い混ぜになって言葉にするのが難しい。ざわざわして、耳を塞ぎたくなる時もある。
心に抱え込んだものは色に例えるなら、限りなく黒に近い灰色かもしれない。鉛筆でぐりぐり塗り潰して、真っ黒で見えなくなった落書きのよう。
塗りつぶす前に、私は何を書いていたのだろう。
絵だったのか、単なるメモだったのか。何も覚えていない。
ほんの数秒前の出来事も、たまに思い出せなくて苛立ってしまう。これはきっと受験に対してのストレスだ。
自分は今、神経質になっているんだ。
些細なことでも苛立って、お腹がムカムカしたり、頭が痛くなったりしてしまう。悲しくなることはなかったけど、たまに自己嫌悪に陥ったりと忙しない。
ああ、いやだなぁ。こんなの。
中学生最後の夏休みは、少しだけ刺がささった痛みを感じながら始まった。
部活も、最後の大会をあと一週間後に控えている。今日は朝の涼しい時間に集まってのランニングと筋トレと、スタートダッシュの練習、いつもと代わり映えのない練習メニュー。
二時間くらいはやったのだろうか。
夏場はどうしても暑くなりがちで、外での運動は体調不良を起こすことも多い。気温が高くなるとそんなに長くやらせてもらえないのが現状だ。
それでも、朝の少しだけ涼しい空気の中を。目映い青空の下を。
思いっきり走れるのは、とても気持ち良い。
走っている時は自由で、自分を縛るものは何もなくて、ただひたすら、前にあるゴールラインを目指せばいい。
石灰で引かれた白線。青い空。生温い風。グラウンドに木霊する蝉の声。見えるもの、聞こえるものすべてが刹那の幻のよう。
ちくりと感じる刺の痛みも――今だけは、忘れることが出来る。
走れば、イヤなことから逃げられる。
ぐちゃぐちゃになったわたしの頭の中を、全部真っ白にできる。走れば。ただひたすら走ればよかった。
好きとか嫌いとか、そんなものじゃなかった。
逃げたかった。目の前にあるものすべてから。
ただ、それだけ。
だからね、遠野くん。
「……好きとか、そういうものじゃないよ。私にとって走ることは」
隣を歩く、背丈の高い少年を振り向きもせず。
少女は答えた。
「えー。じゃあ、好きじゃなかったら、キライってことですか?」
「嫌いじゃないわよ。嫌いだったらそもそも走ってないし、部活だって入らないし」
「つまり好きってことっすよね!」
少年は嬉しそうに言うと、眩しいほどの笑顔を向ける。対して少女はうんざりした面持ちだ。
「だから、好きじゃないってば。遠野くんさ、世の中には好きと嫌いの二つ以外だってあるでしょ? そういうものなの」
「そうなんですか? オレは好きとキライしかないですけど」
「それは遠野くんがそういう性格だからでしょ。君と一緒にしないで」
低い声で少年の主張を突っぱねる。明らかに不機嫌だ。少女は大きく溜め息を吐いてから足を止めた。
「遠野くんと私は違うの。君の価値観はよくわかったから、それを私に押し付けるのやめて」
「押し付けてないっすよ! だってセンパイが」
「私がなに? 走るのが好きって答えないのがそんなにおかしいの?」
語気を荒立ててしまう。そんなつもりはなかったのだが、感情を抑えることが出来なかった。
少女は、隣にいる少年を見ようとはしない。視線は真っ直ぐのまま、暗い夜道を睨み付けて。
遠野が聞きたいのは。聞きたかったのは、自分が陸上を好きだという気持ち。それを確かめたかったのだろう。
言い返した言葉から、そんな気持ちが透けて見えたかもしれない。
少女は唇を噛み締め、俯いた。
「全力で、走ることを楽しんでる遠野くんには。今の私の気持ちは、絶対にわからないよ」
息が苦しい。視界が滲んでいく感覚に、心が悲鳴をあげている。
自分にもわからない。この焦りが何なのか。
そしてこの少年にも、わかって欲しいとも思わない。そんな都合のいいことを言えるわけがない。
この少年はただ、走ることが大好きなだけ。
誰よりも速く走りたくて、誰よりも走ることが大好きで、きっと一年後も「陸上が好きだから、オレは続けますよ」と笑ってくれるのだろう。
わかっている。分かりきっていたことだ。
彼と自分は、まったく違うのだ。
「ごめん、遠野くん。これじゃあただの八つ当たりだね」
生温い風が頬を撫でて、蜩の声が夕暮れにこだまする。夏なのに心が寒さを感じるのはどうしてだろう。
少女は頭を振って。
「本当にごめんなさい。私、今はどうやっても君を傷付けることしか言えない。……前みたいに、君と一緒に笑えない。楽しめない」
早口にそう言って、大きく嘆息した。
鞄を持つ手に力が入り、そのまま逃げるように走り去ろうとする。
視界が滲む。目が熱い。胸が痛い。息が苦しい。
感情が込み上げて、どうすることも出来ない。
十五の夏。私が夏をもっと嫌いになったこの日。
生まれて初めて、身近な誰かを『否定』し『拒絶 』した。
--------------------------------------------------------
episode2:夏影
--------------------------------------------------------



ENo.356 眠 とのやりとり
| ▲ |
| ||||||
ENo.412 スノウストーム とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
以下の相手に送信しました



ItemNo.1 不思議な武器 を破棄しました。
ItemNo.3 不思議な装飾 を破棄しました。







自然LV を 5 UP!(LV10⇒15、-5CP)
装飾LV を 5 UP!(LV10⇒15、-5CP)
ItemNo.8 ネジ から射程4の大砲『韋駄天』を作製しました!
⇒ 韋駄天/大砲:強さ45/[効果1]- [効果2]- [効果3]-【射程4】
 |
縹 「縹の計算では、これは強い武器になるはず……です!」 |
地の祝福 を習得!
沙羅双樹 を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





チナミ区 J-6(沼地)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 J-7(沼地)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 K-7(森林)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 K-8(隔壁)には移動できません。
チナミ区 K-8(隔壁)には移動できません。






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
エディアン 「・・・・・あら?」 |
 |
白南海 「おっと、これはこれは。」 |

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
チャット画面にふたりの姿が映る。
 |
エディアン 「こんにちは白南海さん。元気そうで何より。」 |
 |
白南海 「そう尖らんでも、嬢さん。折角の美人が台無しだ。」 |
 |
エディアン 「・・・それもそうですね、私達同士がどうこうできる訳でもないですし。 それで、これは一体なんなんでしょう?」 |
 |
白南海 「招待されたとか、さっき出てましたけど。」 |
 |
「そ!お!でぇぇ―――っす☆」 |
チャットに響く声。

ミヨチン
茶色の瞳、桜色のロング巻き髪。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
画面に現れる3人目。
 |
白南海 「まぁた、うるせぇのが。・・・ってぇ、こいつァ・・・・・?」 |
 |
エディアン 「ロストじゃないですか、このこ。」 |
 |
白南海 「それとその格好・・・やっぱイバラシティの人間じゃ?あんた。」 |
 |
ミヨチン 「ロスト?イバラシティ?何のことっすかぁ??」 |
 |
ミヨチン 「それよりそれよりぃ!ミヨチンの願いを叶えてくれるって、聞いたんすけどぉー。」 |
上目遣いでふたりに迫る。
 |
白南海 「なるほど。こんな感じであっちから来るんすかねぇ、ロスト。」 |
 |
エディアン 「そっすねぇー。意外っすー。」 |
 |
ミヨチン 「聞いてるんすかぁ!?叶えてくれるんっすかぁー!!?」 |
 |
エディアン 「えぇ叶えます!叶えますともっ!!」 |
 |
白南海 「無茶なことじゃなけりゃー、ですがね。」 |
 |
ミヨチン 「やったーっ!!ミヨチンは、団子!団子が食べたいんすよぉ!! 美味しいやつ!!美味しい団子をたらふく食べたいッ!!」 |
 |
ミヨチン 「好みを言うなら―― ザザッ・・・ 堂のあんこたっぷりの―― ザザッ・・・ 団子がいいんすよねぇ! ガッコー帰りによく友達と食べてたんすよぉ!!」 |
ノイズで一部が聞き取れない。
 |
白南海 「団子だァ・・・??どんな願望かと思えばなんつぅ気の抜けた・・・」 |
 |
エディアン 「しかしこのハザマでお団子、お団子ですかぁ。」 |
 |
白南海 「イバラシティの団子屋なら、梅楽園のが絶品なんすけどねぇ。」 |
 |
エディアン 「あぁ!あそこのお団子はモッチモチで美味しかったです!! 夢のような日々の中でもあれはまた格別でしたねぇ!!」 |
 |
ミヨチン 「マジっすか!それ!それ食べれねぇんすかぁー!?」 |
 |
ドライバーさん 「食べれるぞ。」 |
突然現れるドライバーさん。
 |
白南海 「・・・び、ビビらせねぇでくれませんか?」 |
 |
ドライバーさん 「ビビったんか、そりゃすまん。」 |
 |
エディアン 「こんにちはドライバーさん。・・・お団子、食べれるんですか?」 |
 |
ドライバーさん 「おう。地図見りゃ分かるだろうが、ハザマのモデルはイバラシティだ。 そんでもって一部の名所は結構再現されてる、ハザマなりに・・・な。試しに見てくるといい。」 |
 |
エディアン 「ほんとですか!?ハザマも捨てたもんじゃないですねぇ!!」 |
 |
白南海 「いや、捨てたもんじゃって・・・なぁ・・・・・」 |
 |
ミヨチン 「んじゃんじゃその梅楽園の団子!よろしくお願いしゃーっす!!」 |
 |
白南海 「あの辺なら誰かしら丁度向かってる頃じゃねぇすかねぇ。」 |
 |
エディアン 「よろしく頼みますよぉ皆さん!私も後で行きたいなぁーっ!!」 |
 |
白南海 「・・・何か気が抜ける空気っすねぇ、やっぱ。」 |
賑やかな雰囲気のまま、チャットが閉じられる――







ENo.139
縹



縹【ハナダ】
17歳/163cm
白藍色の髪に真紅の瞳。彼女は自らを縹と名乗る。
カスミ区に住んでいる17歳の女子高生だ。
物怖じしない性格でとにかく明るくて人懐っこい。
好きなものは猫。
黒羽【クロバネ】
15歳の中学三年生。152cmと小柄。
濡羽色の髪に蒼い瞳、濃紺のセーラー服を着ている少女。
夢見がちでロマンチストだが、芯は強い。
ある日を境に逢えなくなってしまった少年と、再び出会えることを夢見ている。
2/20:PL体調不良のため、RPのお返事が今まで以上に遅くなります。もしかしたら暫くお返事出来ないかもしれません。大変申し訳ございません。あったかくなる頃には戻ってこられるように頑張ります。
17歳/163cm
白藍色の髪に真紅の瞳。彼女は自らを縹と名乗る。
カスミ区に住んでいる17歳の女子高生だ。
物怖じしない性格でとにかく明るくて人懐っこい。
好きなものは猫。
黒羽【クロバネ】
15歳の中学三年生。152cmと小柄。
濡羽色の髪に蒼い瞳、濃紺のセーラー服を着ている少女。
夢見がちでロマンチストだが、芯は強い。
ある日を境に逢えなくなってしまった少年と、再び出会えることを夢見ている。
2/20:PL体調不良のため、RPのお返事が今まで以上に遅くなります。もしかしたら暫くお返事出来ないかもしれません。大変申し訳ございません。あったかくなる頃には戻ってこられるように頑張ります。
22 / 30
142 PS
チナミ区
K-7
K-7





































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | ド根性雑草 | 素材 | 15 | [武器]防狂10(LV20)[防具]反護10(LV25)[装飾]復活10(LV25) | |||
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | |||||||
| 4 | 風神 | 武器 | 30 | 攻撃10 | - | - | 【射程3】 |
| 5 | フローライト | 装飾 | 20 | 幸運10 | - | - | |
| 6 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 8 | 韋駄天 | 大砲 | 45 | - | - | - | 【射程4】 |
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 自然 | 15 | 植物/鉱物/地 |
| 領域 | 20 | 範囲/法則/結界 |
| 武器 | 20 | 武器作製に影響 |
| 装飾 | 15 | 装飾作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 6 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 6 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ストーンブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵:地撃&朦朧 | |
| リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |
| ノーマライズ | 5 | 0 | 80 | 味環:HP増+環境変調を守護化 | |
| ブルーム | 5 | 0 | 120 | 敵全:地撃&魅了・束縛 | |
| ガーディアン | 6 | 0 | 50 | 敵:攻撃+味傷:護衛 | |
| ディスターバンス | 5 | 0 | 80 | 味傷:HP増+弱化ターン効果を短縮 | |
| ツインブラスト | 5 | 0 | 220 | 敵全:攻撃&麻痺+敵全:攻撃&盲目 | |
| インヴァージョン | 6 | 0 | 150 | 敵全:攻撃&祝福を猛毒化 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 地の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:自然LVが高いほど地特性・耐性増 | |
| 沙羅双樹 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】味全:DF増(2T)+領域値[地]増 | |
| 大砲作製 | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『装備作製』で武器「大砲」を選択できる。大砲は射程が必ず4になる。 |
最大EP[20]





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]クリーンヒット | [ 3 ]レッドショック |

PL / 史郎