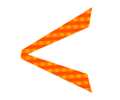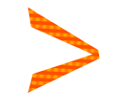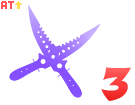<< 1:00~2:00




坂道を登る。
見下ろせば赤茶色と水色の屋根が敷き詰められ、その向こうには滑らかな曲線を描く港が日差しに煌めいている。
「すみませーん!」
明るい声に振り返ると、若い女が三人。地図を手に駆け寄ってきた。
「また始まったよ、アッキーのイケメンセンサー」
「違っ! このままだとお店につかないし!」
「どうでもいい〜、はやくごはん食べたーい」
観光客か。
まぁ、古い街並みだ。迷いやすいのはわからないでもない。
♦︎
「良い旅を」
漸くお目当ての店にありつけそうな三人と別れ、坂を登り続けると目的地に辿り着いた。英雄アイルの最期の地。訪れる者が絶えないのだろう。真新しい生花が初夏の陽光に萎れることなく石碑を彩っている。
城門跡を抜け、堀に架けられた橋を渡る。浮かぶ蓮の葉の影には鮮やかな魚達が漂い、木々が周囲を巡る塁壁を隠す。迎撃のために細く作られた道は今や藤棚に囲われて訪れる者を迎え入れる。花の季節が過ぎても、光を透かす緑は美しい。
木漏れ日を抜けると、芝生に覆われた広場。かつての城は痕跡さえなく、ただ一つ残った塔がそびえている。塔のふもとの簡素なカフェ。そのテラスに座る一人が俺を見つけて手を振っていた。
♦︎
「なんでまた待ち合わせなんて。俺の店に来れば済むことだったろ?」
パフェを器用に啄みながら彼女が答える。
「まぁ、それはそうなんだけど。ちょっと都合があって」
「都合? それにしちゃ……」
考える様子を見せたかに思われたがそれも一瞬、勢いよく残りを食べ終えると彼女は席を立った。塔を指差して俺を手招く。
「塔登ろうよ、塔。ここまできたんだし」
いや、話繋がってなくね?
流れに戸惑っていると手首を抓られた。突然の言動に、何か訳ありかと勘ぐる。
「どうしてもか?」
「そう、どうしても!」
言葉の軽さとは裏腹に、真剣な面持ちだ。
「わかった。なんかよくわからんが、多分なんかそういう設定ね……」
はしゃぐ彼女に手を引かれるまま、俺は塔へ向かった。
♦︎
昇降機を降りると展望台は人で溢れていた。
「絶対に手を離さないでほしい」
「高所恐怖症か?」
「そうなの、だから。絶対にね」
自称高所恐怖症が人混みを掻き分けながら俺の手を引いてゆく。一周して昇降機の出口にさしかかると、そこから吐き出される新たな客にまみれるように壁に寄りかかり……
消えた?
彼女が居ない。
いや手は離していない。
その感触はまだ俺を導いている。壁の向こうへ。
「手は離すな、だったな」
人々に押しやられるまま俺は壁に身を任せ、気づくと古びた螺旋階段にいた。
先程までの喧騒が嘘のように静かだ。
声が響く。
「ここは、眩ましの結界が張られているの。ここに隠れた先世によるものだけれど」
マジかよ。それで大体わかってしまった。
最悪の事態を想定しつつ無言で階段を登る。互いの足音だけが、がらんとした塔に響いてゆく。その音も止まる。最上階に辿り着いたのか。今は景色を見る余裕もない。
「緊張しなくていいよ。色々言われているけど…… これまで通りにして欲しい」
緊張? いや、その俺が思ってたのはそのスジの奴に色々バレて塔もろとも蒸し焼きにされるとかそういうアレで……。見上げると、見張り台で待つ彼女は俺を促すように柔らかな表情で頷く。
そうだ、今はわかることを。
「……眩ましの結界。声が外へ伝わらない、外からも見えない。その結界を操作できる英雄の血族のアンタは監視の目もなく本当のことを話せるって塩梅か?」
再度、彼女は頷いて、
「話が早くて助かるよ。私の本当の名前は……」
一息ついて、両手を後ろに回し。目を閉じて俯いて、こちらへ一歩。その手が髪飾りを解く。それには偽りの姿を見せる術がかけられていたのだろう。髪は青へ。顔をあげると、穏やかな顔つきは凛々しくも美しいものへと変わってゆく。
「アリス……」
「そう。私は、アリステア・シェフィールド」
アリステア。
英雄の血筋であり、この時代においては貿易で財を成した名士であるシェフィールド家。その中でも先祖返りと呼ばれる程の力を持ち、強く美しく、子供でも知っている有名人だ。早い話がアイドル。彼女を聖女として崇めるファンクラブさえ存在している。
その聖女が俺の前に。まぁ、彼女がアリステアであること自体は俺に何の影響も及ぼさない。だから今は普通に振る舞うとする。
「その……アリステア様が何でまた俺の店に注文に来て、こんなサプライズに至ったのか謎なんだが。まぁ、アリ…… いや、アンタが誰だとしても俺にとっては一人の客にしか過ぎない。ここへは、仕事の成果を渡すために来た。わけだから……」
ダメだ。全然普通じゃなかった。
どう考えてもぎこちない。
ああ、もう、なるようになれ。
俺は懐から包みを取り出した。全く。人混みでどうなるかと思ったが無事だったようだ。
「注文の品だ。開けて確かめるといい」
差し出された包みを、アリステアは慈しむように両手で受け取った。その気品溢れる所作に、目の前の人物が誰であるかを実感する。
「ありがとう。確かに受けとりました。では、お言葉に甘えて」
包みの中にはシンプルなケース。細い指が蓋を開け細工を取り出して光にかざす。途切れることのない三つの結び目。古くから伝わる意匠だ。それを小枝を象った金属が紡いでいる。控えめに埋め込まれた石が、結び目の作る複雑な形を通した光を受けて淡く煌めく。
息を飲む声が聞こえた。
頃合いを見計らって指し示す。
「そこの石に魔力を込めるんだ。ガチのに比べたらおもちゃみてぇなもんだが…… ああ、ちょっとでいい。アンタが本気でやったら壊れる!」
石に添えた指から僅かな魔力が漏れることなく注がれた。術が起動し光の羽が飛び散る。想定していたよりもずっと豊かに、それでいて繊細さを失うことなく。幾重にも、幾重にも。
俺はとんでもない思い違いをしていたのだと気づいた。本気とはこういうことだ。この女は俺の作った仕掛けに、世界に一つのアーティファクトを厳重に扱うかの如く最適な魔力を最適な量で込めたのだ。
「なんか、その、すまん……」
羽は雁の群れのようにはためきながら上空を一周し、塔の外側へ羽ばたいてゆく。俺の呟きが聞こえたかどうか。彼女は物言わず光の羽が飛び立つ先を見つめている。
アリステアという存在に抱いていた恐怖は、このひとときで殆ど敬意にすり替わったかもしれない。
最後の羽が空に溶けると、薄緑の瞳がこちらを見上げた。昼下がりの日差しが彼女の肩口を照らす。
「本当に、ありがとう。素晴らしい仕事でした」
頭を下げるアリステアを見て、はっとする。言葉は自然に出た。
「どういたしまして。期待に応えられていたら俺も嬉しい。それに、さっきのはその、俺の技術も捨てたもんじゃねぇと思えたし。ただ……」
「……うん」
「ただ、やっぱり、なんで姿を変えてまで俺の店に来て注文したのかがわからねぇ。素材も値段も一般人用だ。接点がねぇよ。それに、そもそもここでこうしてる理由をまだ聞いて無い、よな?」
風がアリステアの海の色をした髪をそよいでゆく。暫し街の方を眺めて、つぶやくように。
「私は、流浪の民に興味があって。歴史には残らず、姿でさえもはっきりとはしない」
流浪の民。久しぶりにその言葉をヒトから聞いた。流浪の民なんて使うのは彼ら自らくらいだ。少なくとも、その呼び名を使うってことは友好的、か。
「随分と…… いや、御伽噺じゃねぇのか?」
「幻想として知る人さえ、殆どはこの世を去ったはず。でも、私は知ってしまった。この塔に残されていた手記で。神聖聖絶団が何を行なっていたかを」
ジェノサイドだ。
ヒト以外のヒトに似た生き物を悪魔と称し、徹底的に文化の痕跡を消し、未来永劫蘇ることも転生することもないよう彼らが言う聖絶の炎で焼き払う。流浪の民が隠れ住み糧とした森も焼き海を汚し ”ヒトを憎ませて” 自ら滅びへと向かわせた。戦後は悪魔狩りとして各地で活動している。
アリステアは続ける。
「英雄と呼ばれはしても政治的な力を持たなかったアイルは、死地に向かう前にここで知る限りを書き残した。塔だけが焼け残ったのも恐らくそれが関係してる。けれど、万一これを読む者が現れても身を守る知識も力も無ければ消されてしまう。当然、聖絶団に見つかってはならない。だから結界を残した」
「アンタはそれを見つけて。だとして、俺に話してヤバくねぇのか?」
「あなたは、元々、真実を知っているはず」
アリステアは隠していた首飾りを外すと俺に手渡してきた。細いチェーンの先には、途切れることのない三つの結び目。
「それは、ここに残されていたの。似たような模様は各地にあるから珍くはない。でも、手記にはあなたの事もあった」
ああ、そうか。
彼がそう、姿を変えて。
そういうことか。
こいつら、やることが変わらねぇ。
面影の残る彼女に問いかける。
「アリステア、君は…… 過去を知って、どうしたいんだ? 時間をかければ変化は訪れるかもしれない。けどな、説教みたいな言い方になっちまうが、これは一面の善悪とかで急にどうこうできることじゃねぇ。俺も若い頃は勢い余ってヒトを食い殺したこともあるし、それでいて今はこの街の営みを享受している。俺達を滅ぼそうとしたヒトの作った街を、ヒトも住むこの星を、俺も失いたくないと思っている。あんたらから見たらモラルもクソもねぇかもだが、今はただ静かに平穏に生きていたいんだ」
どうしてか、言葉は堰を切ったように溢れた。言っていることもめちゃくちゃだ。驚きを隠せずにいるアリステアに続ける。
「それでも、全部をさ。ぜんぶぜんぶ無かったことにするのは、少し嫌だったのかもしれない。そんな、クソみてぇな意地で俺はこれを……」
彼女がそうしていたように、結び目を光にかざす。
「同じです」
「……同じ?」
「全てを無かったことにはしたくない。クソみてぇな意地で。あなたと同じように。抱えるものが違っても、生き方が違っても。今は何もすぐにはできなくても」
街と海と空と。光は巡って結び目を照らした。銀色の輪は無数の色を、世界を映し出している。
「トリケトラだ」
「……えっ?」
「こいつの名前だ。意味は…… 三つのなんかいい感じのなんかがぐるぐるっといい感じになるように、みたいな。もしかしたら三つでなくてもいいかもしれない」
「いい感じ……」
「人と海と星とか。そうだな、あんたらなら神とか。なんでもいいんだ」
昔同じ事を語ったのを思い出す。面倒な客だった。仕掛けのキーワードは流浪の民の古い言葉にしてくれとか。俺は半端者で、そういうのあんましらねぇのに。そうだ、キーワードだ。
「いいか、よく、聞いて見ていろ」
彼が何故知る人も殆どいない言葉をこれに刻んだのかはわからない。
けれど、今日の日の奇妙な巡り合わせがなければ、俺はこの言葉もいつか忘れていただろう。
『————、———』
込められた魔力と言葉が術を起動する。温かな光がふわりと膨らんで、一羽の鳶となり力強く羽ばたくと滑るように俺の手元から飛び立った。傾き始めた陽が薄く紅色に染める空に、光の鳶は大きな輪を描く。
アリステアは静かにそれを見つめている。
「ほら、返すからやってみ」
肩を叩いて細工を手渡そうとすると彼女は体を震わせて振り返った。あまりの無防備さにこっちが驚く。
「もう一度……」
「え?」
「もう一度お願い。あまりにも、その。もちろん、よく見て、聞いていたけど。もう一度聞かせて!」
何がそんなに心を掴んだのだろう。急に積極的になったアリステアに驚きっぱなしだ。いや、最初から積極的、だったか。
「まぁ、減るもんじゃねぇし。そのくらいなら」
「ありがとう。それにもっと話を聞きたい。言葉の意味も知りたい。嫌でなければ」
嫌なわけはない。
好きとも違うが。
この想いは。
ああ、そうだ。
『美しき、世界よ』
二羽目の鳶が飛び立つ。



ENo.17 サクマ とのやりとり




特に何もしませんでした。








変化LV を 10 DOWN。(LV25⇒15、+10CP、-10FP)
具現LV を 15 UP!(LV0⇒15、-15CP)
装飾LV を 5 UP!(LV25⇒30、-5CP)
ItemNo.7 何かの殻 から装飾『もうひとつの小さな輪』を作製しました!
⇒ もうひとつの小さな輪/装飾:強さ60/[効果1]防御15 [効果2]- [効果3]-
藍浦英里織(1034) とカードを交換しました!
悪魔の代弁者 (ドレイン)


ウォーターフォール を研究しました!(深度0⇒1)
ティンダー を研究しました!(深度0⇒1)
ストライク を研究しました!(深度0⇒1)
クリエイト:タライ を習得!
ローバスト を習得!
召喚強化 を習得!
クリエイト:バトルフラッグ を習得!
サモン:サーヴァント を習得!
☆サモン:ビーフ を習得!
☆初習得ボーナス:各FPが2増加した!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





特に移動せずその場に留まることにしました。






―― ハザマ時間が紡がれる。

Cross+Roseの音量を調整する。
Cross+Roseにロスト7名の容姿と簡単なプロフィールが映し出される。







チャットが閉じられる――






























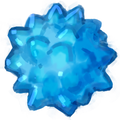























異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



坂道を登る。
見下ろせば赤茶色と水色の屋根が敷き詰められ、その向こうには滑らかな曲線を描く港が日差しに煌めいている。
「すみませーん!」
明るい声に振り返ると、若い女が三人。地図を手に駆け寄ってきた。
「また始まったよ、アッキーのイケメンセンサー」
「違っ! このままだとお店につかないし!」
「どうでもいい〜、はやくごはん食べたーい」
観光客か。
まぁ、古い街並みだ。迷いやすいのはわからないでもない。
♦︎
「良い旅を」
漸くお目当ての店にありつけそうな三人と別れ、坂を登り続けると目的地に辿り着いた。英雄アイルの最期の地。訪れる者が絶えないのだろう。真新しい生花が初夏の陽光に萎れることなく石碑を彩っている。
城門跡を抜け、堀に架けられた橋を渡る。浮かぶ蓮の葉の影には鮮やかな魚達が漂い、木々が周囲を巡る塁壁を隠す。迎撃のために細く作られた道は今や藤棚に囲われて訪れる者を迎え入れる。花の季節が過ぎても、光を透かす緑は美しい。
木漏れ日を抜けると、芝生に覆われた広場。かつての城は痕跡さえなく、ただ一つ残った塔がそびえている。塔のふもとの簡素なカフェ。そのテラスに座る一人が俺を見つけて手を振っていた。
♦︎
「なんでまた待ち合わせなんて。俺の店に来れば済むことだったろ?」
パフェを器用に啄みながら彼女が答える。
「まぁ、それはそうなんだけど。ちょっと都合があって」
「都合? それにしちゃ……」
考える様子を見せたかに思われたがそれも一瞬、勢いよく残りを食べ終えると彼女は席を立った。塔を指差して俺を手招く。
「塔登ろうよ、塔。ここまできたんだし」
いや、話繋がってなくね?
流れに戸惑っていると手首を抓られた。突然の言動に、何か訳ありかと勘ぐる。
「どうしてもか?」
「そう、どうしても!」
言葉の軽さとは裏腹に、真剣な面持ちだ。
「わかった。なんかよくわからんが、多分なんかそういう設定ね……」
はしゃぐ彼女に手を引かれるまま、俺は塔へ向かった。
♦︎
昇降機を降りると展望台は人で溢れていた。
「絶対に手を離さないでほしい」
「高所恐怖症か?」
「そうなの、だから。絶対にね」
自称高所恐怖症が人混みを掻き分けながら俺の手を引いてゆく。一周して昇降機の出口にさしかかると、そこから吐き出される新たな客にまみれるように壁に寄りかかり……
消えた?
彼女が居ない。
いや手は離していない。
その感触はまだ俺を導いている。壁の向こうへ。
「手は離すな、だったな」
人々に押しやられるまま俺は壁に身を任せ、気づくと古びた螺旋階段にいた。
先程までの喧騒が嘘のように静かだ。
声が響く。
「ここは、眩ましの結界が張られているの。ここに隠れた先世によるものだけれど」
マジかよ。それで大体わかってしまった。
最悪の事態を想定しつつ無言で階段を登る。互いの足音だけが、がらんとした塔に響いてゆく。その音も止まる。最上階に辿り着いたのか。今は景色を見る余裕もない。
「緊張しなくていいよ。色々言われているけど…… これまで通りにして欲しい」
緊張? いや、その俺が思ってたのはそのスジの奴に色々バレて塔もろとも蒸し焼きにされるとかそういうアレで……。見上げると、見張り台で待つ彼女は俺を促すように柔らかな表情で頷く。
そうだ、今はわかることを。
「……眩ましの結界。声が外へ伝わらない、外からも見えない。その結界を操作できる英雄の血族のアンタは監視の目もなく本当のことを話せるって塩梅か?」
再度、彼女は頷いて、
「話が早くて助かるよ。私の本当の名前は……」
一息ついて、両手を後ろに回し。目を閉じて俯いて、こちらへ一歩。その手が髪飾りを解く。それには偽りの姿を見せる術がかけられていたのだろう。髪は青へ。顔をあげると、穏やかな顔つきは凛々しくも美しいものへと変わってゆく。
「アリス……」
「そう。私は、アリステア・シェフィールド」
アリステア。
英雄の血筋であり、この時代においては貿易で財を成した名士であるシェフィールド家。その中でも先祖返りと呼ばれる程の力を持ち、強く美しく、子供でも知っている有名人だ。早い話がアイドル。彼女を聖女として崇めるファンクラブさえ存在している。
その聖女が俺の前に。まぁ、彼女がアリステアであること自体は俺に何の影響も及ぼさない。だから今は普通に振る舞うとする。
「その……アリステア様が何でまた俺の店に注文に来て、こんなサプライズに至ったのか謎なんだが。まぁ、アリ…… いや、アンタが誰だとしても俺にとっては一人の客にしか過ぎない。ここへは、仕事の成果を渡すために来た。わけだから……」
ダメだ。全然普通じゃなかった。
どう考えてもぎこちない。
ああ、もう、なるようになれ。
俺は懐から包みを取り出した。全く。人混みでどうなるかと思ったが無事だったようだ。
「注文の品だ。開けて確かめるといい」
差し出された包みを、アリステアは慈しむように両手で受け取った。その気品溢れる所作に、目の前の人物が誰であるかを実感する。
「ありがとう。確かに受けとりました。では、お言葉に甘えて」
包みの中にはシンプルなケース。細い指が蓋を開け細工を取り出して光にかざす。途切れることのない三つの結び目。古くから伝わる意匠だ。それを小枝を象った金属が紡いでいる。控えめに埋め込まれた石が、結び目の作る複雑な形を通した光を受けて淡く煌めく。
息を飲む声が聞こえた。
頃合いを見計らって指し示す。
「そこの石に魔力を込めるんだ。ガチのに比べたらおもちゃみてぇなもんだが…… ああ、ちょっとでいい。アンタが本気でやったら壊れる!」
石に添えた指から僅かな魔力が漏れることなく注がれた。術が起動し光の羽が飛び散る。想定していたよりもずっと豊かに、それでいて繊細さを失うことなく。幾重にも、幾重にも。
俺はとんでもない思い違いをしていたのだと気づいた。本気とはこういうことだ。この女は俺の作った仕掛けに、世界に一つのアーティファクトを厳重に扱うかの如く最適な魔力を最適な量で込めたのだ。
「なんか、その、すまん……」
羽は雁の群れのようにはためきながら上空を一周し、塔の外側へ羽ばたいてゆく。俺の呟きが聞こえたかどうか。彼女は物言わず光の羽が飛び立つ先を見つめている。
アリステアという存在に抱いていた恐怖は、このひとときで殆ど敬意にすり替わったかもしれない。
最後の羽が空に溶けると、薄緑の瞳がこちらを見上げた。昼下がりの日差しが彼女の肩口を照らす。
「本当に、ありがとう。素晴らしい仕事でした」
頭を下げるアリステアを見て、はっとする。言葉は自然に出た。
「どういたしまして。期待に応えられていたら俺も嬉しい。それに、さっきのはその、俺の技術も捨てたもんじゃねぇと思えたし。ただ……」
「……うん」
「ただ、やっぱり、なんで姿を変えてまで俺の店に来て注文したのかがわからねぇ。素材も値段も一般人用だ。接点がねぇよ。それに、そもそもここでこうしてる理由をまだ聞いて無い、よな?」
風がアリステアの海の色をした髪をそよいでゆく。暫し街の方を眺めて、つぶやくように。
「私は、流浪の民に興味があって。歴史には残らず、姿でさえもはっきりとはしない」
流浪の民。久しぶりにその言葉をヒトから聞いた。流浪の民なんて使うのは彼ら自らくらいだ。少なくとも、その呼び名を使うってことは友好的、か。
「随分と…… いや、御伽噺じゃねぇのか?」
「幻想として知る人さえ、殆どはこの世を去ったはず。でも、私は知ってしまった。この塔に残されていた手記で。神聖聖絶団が何を行なっていたかを」
ジェノサイドだ。
ヒト以外のヒトに似た生き物を悪魔と称し、徹底的に文化の痕跡を消し、未来永劫蘇ることも転生することもないよう彼らが言う聖絶の炎で焼き払う。流浪の民が隠れ住み糧とした森も焼き海を汚し ”ヒトを憎ませて” 自ら滅びへと向かわせた。戦後は悪魔狩りとして各地で活動している。
アリステアは続ける。
「英雄と呼ばれはしても政治的な力を持たなかったアイルは、死地に向かう前にここで知る限りを書き残した。塔だけが焼け残ったのも恐らくそれが関係してる。けれど、万一これを読む者が現れても身を守る知識も力も無ければ消されてしまう。当然、聖絶団に見つかってはならない。だから結界を残した」
「アンタはそれを見つけて。だとして、俺に話してヤバくねぇのか?」
「あなたは、元々、真実を知っているはず」
アリステアは隠していた首飾りを外すと俺に手渡してきた。細いチェーンの先には、途切れることのない三つの結び目。
「それは、ここに残されていたの。似たような模様は各地にあるから珍くはない。でも、手記にはあなたの事もあった」
ああ、そうか。
彼がそう、姿を変えて。
そういうことか。
こいつら、やることが変わらねぇ。
面影の残る彼女に問いかける。
「アリステア、君は…… 過去を知って、どうしたいんだ? 時間をかければ変化は訪れるかもしれない。けどな、説教みたいな言い方になっちまうが、これは一面の善悪とかで急にどうこうできることじゃねぇ。俺も若い頃は勢い余ってヒトを食い殺したこともあるし、それでいて今はこの街の営みを享受している。俺達を滅ぼそうとしたヒトの作った街を、ヒトも住むこの星を、俺も失いたくないと思っている。あんたらから見たらモラルもクソもねぇかもだが、今はただ静かに平穏に生きていたいんだ」
どうしてか、言葉は堰を切ったように溢れた。言っていることもめちゃくちゃだ。驚きを隠せずにいるアリステアに続ける。
「それでも、全部をさ。ぜんぶぜんぶ無かったことにするのは、少し嫌だったのかもしれない。そんな、クソみてぇな意地で俺はこれを……」
彼女がそうしていたように、結び目を光にかざす。
「同じです」
「……同じ?」
「全てを無かったことにはしたくない。クソみてぇな意地で。あなたと同じように。抱えるものが違っても、生き方が違っても。今は何もすぐにはできなくても」
街と海と空と。光は巡って結び目を照らした。銀色の輪は無数の色を、世界を映し出している。
「トリケトラだ」
「……えっ?」
「こいつの名前だ。意味は…… 三つのなんかいい感じのなんかがぐるぐるっといい感じになるように、みたいな。もしかしたら三つでなくてもいいかもしれない」
「いい感じ……」
「人と海と星とか。そうだな、あんたらなら神とか。なんでもいいんだ」
昔同じ事を語ったのを思い出す。面倒な客だった。仕掛けのキーワードは流浪の民の古い言葉にしてくれとか。俺は半端者で、そういうのあんましらねぇのに。そうだ、キーワードだ。
「いいか、よく、聞いて見ていろ」
彼が何故知る人も殆どいない言葉をこれに刻んだのかはわからない。
けれど、今日の日の奇妙な巡り合わせがなければ、俺はこの言葉もいつか忘れていただろう。
『————、———』
込められた魔力と言葉が術を起動する。温かな光がふわりと膨らんで、一羽の鳶となり力強く羽ばたくと滑るように俺の手元から飛び立った。傾き始めた陽が薄く紅色に染める空に、光の鳶は大きな輪を描く。
アリステアは静かにそれを見つめている。
「ほら、返すからやってみ」
肩を叩いて細工を手渡そうとすると彼女は体を震わせて振り返った。あまりの無防備さにこっちが驚く。
「もう一度……」
「え?」
「もう一度お願い。あまりにも、その。もちろん、よく見て、聞いていたけど。もう一度聞かせて!」
何がそんなに心を掴んだのだろう。急に積極的になったアリステアに驚きっぱなしだ。いや、最初から積極的、だったか。
「まぁ、減るもんじゃねぇし。そのくらいなら」
「ありがとう。それにもっと話を聞きたい。言葉の意味も知りたい。嫌でなければ」
嫌なわけはない。
好きとも違うが。
この想いは。
ああ、そうだ。
『美しき、世界よ』
二羽目の鳶が飛び立つ。



ENo.17 サクマ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||



特に何もしませんでした。







変化LV を 10 DOWN。(LV25⇒15、+10CP、-10FP)
具現LV を 15 UP!(LV0⇒15、-15CP)
装飾LV を 5 UP!(LV25⇒30、-5CP)
ItemNo.7 何かの殻 から装飾『もうひとつの小さな輪』を作製しました!
⇒ もうひとつの小さな輪/装飾:強さ60/[効果1]防御15 [効果2]- [効果3]-
 |
イツ 「今は何もできなくても、か……」 |
藍浦英里織(1034) とカードを交換しました!
悪魔の代弁者 (ドレイン)


ウォーターフォール を研究しました!(深度0⇒1)
ティンダー を研究しました!(深度0⇒1)
ストライク を研究しました!(深度0⇒1)
クリエイト:タライ を習得!
ローバスト を習得!
召喚強化 を習得!
クリエイト:バトルフラッグ を習得!
サモン:サーヴァント を習得!
☆サモン:ビーフ を習得!
☆初習得ボーナス:各FPが2増加した!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





特に移動せずその場に留まることにしました。






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
ノウレット 「またまたこんにちは―――ッ!!」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
 |
エディアン 「わぁこんにちはノウレットさーん! えーと音量音量・・・コンフィグかな?」 |
Cross+Roseの音量を調整する。
 |
エディアン 「よし。・・・・・さて、どうしました?ノウレットちゃん。」 |
 |
ノウレット 「はぁい!今回はロストに関する情報を持ってきましたッ!」 |
 |
エディアン 「おや、てっきりあのざっくりした説明だけなのかと。」 |
 |
ノウレット 「お役に立てそうで嬉しいです!!」 |
 |
エディアン 「よろしくお願いしまーす。」 |
 |
ノウレット 「ではでは・・・・・ジャーンッ!こちらがロスト情報ですよー!!」 |
Cross+Roseにロスト7名の容姿と簡単なプロフィールが映し出される。

アンドリュウ
紫の瞳、金髪ドレッドヘア。
体格の良い気さくなお兄さん。
料理好き、エプロン姿が何か似合っている。
体格の良い気さくなお兄さん。
料理好き、エプロン姿が何か似合っている。

ロジエッタ
水色の瞳、菫色の長髪。
大人しそうな小さな女の子。
黒いドレスを身につけ、男の子の人形を大事そうに抱えている。
大人しそうな小さな女の子。
黒いドレスを身につけ、男の子の人形を大事そうに抱えている。

アルメシア
金の瞳、白い短髪。褐色肌。
戦闘狂で活動的な少女。
鎧を身につけハルバードを持っている。
戦闘狂で活動的な少女。
鎧を身につけハルバードを持っている。

ソージロウ
黒い瞳、黒いもじゃもじゃ頭。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。

フレディオ
碧眼、ロマンスグレーの短髪。
彫りが深く、男前な老翁。
黒のライダースジャケットを身に着けている。
彫りが深く、男前な老翁。
黒のライダースジャケットを身に着けている。

ミヨチン
茶色の瞳、桜色のロング巻き髪。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。

マッドスマイル
乱れた長い黒緑色の髪。
両手に紅いナイフを持ち、
猟奇的な笑顔の仮面をつけている。
両手に紅いナイフを持ち、
猟奇的な笑顔の仮面をつけている。
 |
エディアン 「なるほど、いろんなかたがいますねぇ。 彼らの願望を叶えることで影響力を得て、ハザマで強くもなれるんですか。」 |
 |
エディアン 「どこにいるかとか、願望の内容とか、そういうのは分かります?」 |
 |
ノウレット 「ごめんなさい!私はCross+Roseの妖精なのでよくわかりません! Cross+Roseに送られた情報を伝えることしか・・・・・」 |
 |
エディアン 「むむむ・・・・・頑張って見つけないといけませんねぇ。 こう、ロストには頭にマークが付いてるとか・・・そういうのは?」 |
 |
ノウレット 「ごめんなさい!私はCross+Roseの妖精なのでハザマのことはよくわかりません! Cross+Roseに送られた情報を伝えることしか・・・・・」 |
 |
エディアン 「・・・・・システムメッセージなのかなこれ。 ・・・ノウレットちゃんの好きなものは?」 |
 |
ノウレット 「肉ですッ!!」 |
 |
エディアン 「・・・嫌いなものは?」 |
 |
ノウレット 「白南海さん、です・・・・・」 |
 |
エディアン 「・・・・・さては何かしましたね、彼。」 |
 |
エディアン 「では、ロスト情報もそこそこ気にしながら進めていきましょう!」 |
 |
ノウレット 「ファイトでーすッ!!」 |
チャットが閉じられる――





ENo.990
九十九 五



身長 178cm(ツノを含まない)日焼けした肌、青っぽい髪、アンバーの瞳。男性。二十歳そこそこに見える。見た目相応の普通の声。口調は粗雑で立ち振る舞いにもおよそ気品というものがない。大抵はツノの入る耳のついたフードを被っている。
— 以下、初見では不明な情報および参考資料。こちらに傷害を与えたり、異能に干渉しない限りは読む必要はない。
読み: ツクモ イツ
住処: マシカ区 T-20 (全マップの一番右下。海上)
好き: 海
ネット上で仕事をしながら、海で獲れるものや異能で生えてきたツノを食べてダラダラ生きている。[1]
マシカ浜保全ファンド [2] の発起に関わった一人。
折り畳み式の鋸を持ち歩いている。 [3]
— 異能
頭に食べられるツノを形成する。[4] 常時発動型。 [5] ツノの再生を少し早めるのと、鋸で切れるまで柔らかくする以外のコントロールは身につけていない。
ツノから切り離した欠片は香り豊かなクランチキャンディのようになり、長くても丸一日で霧散して消えてしまう。
12月 かつお出汁梅味 → 1月 干し金柑味 → 2月 胡桃の蜂蜜漬け味
食料としては濃縮された完全栄養食のようにふるまう。加えて、本人が食べた場合は、肉体をベストな状態に近づけ [6] 数日かけて小さな欠損程度は修復できる。 [7] 他者が食べた場合は個人差が大きい。[8]
ツノは本来の姿のそれと同じ大きさまで再生されるが、普段は 15cm 程度にしている。
— Ansinity
名: イツ
身長: 182cm (ツノを含まない)
特性: 生きるものの生気を奪う [5]
生気をツノに溜め込んでおり、これがなくならない限りはかなり死ににくい。
生気を奪う方法はいくつかあるが、契約や性行によるものなど相手の生死にかかわる手段は身の危険に繋がるため好まない。
普段発動しているのは ”対象である生きるものの存在を認め、その生を尊く美しいと思うこと。” この前提さえ満たすなら範囲内 [9] のあらゆる生命とパスを繋げ、対象に影響を及ぼさない程ごく僅かずつの生気を得られる。[10]
— 脚注
【イバラシティ】
1. ^ 最悪ツノさえ食ってれば生きていける。治癒にツノを回している間は人並みに飯も食う。
2. ^ マシカ区 Q-19, P-19
3. ^ 銃刀法違反
4. ^ 本体の特性が『ツノを食べることでしか生気を利用できない』形で発現したもの。
5. ^ ツノの維持自体が異能によるため、異能を消されるなどして溜めた生気が失われることを本能的に嫌っている。
6. ^ 病気の回復などよりも、デフォルトのコンディションが良くなる効果が大きい。実年齢より全盛期の肉体に近くなり、知覚能力や身体能力は普通の人間の範囲ではまぁまぁ高い。
7. ^ 部位再生は数日かけて指くらいまで。ツノが食えるなら血液の再生は迅速に行われるので外傷に対してはしぶとい。
8. ^ 本人より高い効果は出ない。大体は疲れがや二日酔いが取れて調子が良くなりお肌が少し若返る完全栄養食止まり。
【イバラシティ・アンジニティ】
9. ^ イバラシティの異能では最大でマシカ区くらい。本体の特性による全力ならイバラシティ全域くらい。
10. ^ 本体の主となる特性。イバラシティではこれのみ発現しており、海の生き物などから生気を半ば無自覚に得ている。広範囲だが非常に微弱で、対象がこの能力による干渉を生理的に受け付けない場合は互いに無意識のうちに弾かれる。
— 以下、初見では不明な情報および参考資料。こちらに傷害を与えたり、異能に干渉しない限りは読む必要はない。
読み: ツクモ イツ
住処: マシカ区 T-20 (全マップの一番右下。海上)
好き: 海
ネット上で仕事をしながら、海で獲れるものや異能で生えてきたツノを食べてダラダラ生きている。[1]
マシカ浜保全ファンド [2] の発起に関わった一人。
折り畳み式の鋸を持ち歩いている。 [3]
— 異能
頭に食べられるツノを形成する。[4] 常時発動型。 [5] ツノの再生を少し早めるのと、鋸で切れるまで柔らかくする以外のコントロールは身につけていない。
ツノから切り離した欠片は香り豊かなクランチキャンディのようになり、長くても丸一日で霧散して消えてしまう。
12月 かつお出汁梅味 → 1月 干し金柑味 → 2月 胡桃の蜂蜜漬け味
食料としては濃縮された完全栄養食のようにふるまう。加えて、本人が食べた場合は、肉体をベストな状態に近づけ [6] 数日かけて小さな欠損程度は修復できる。 [7] 他者が食べた場合は個人差が大きい。[8]
ツノは本来の姿のそれと同じ大きさまで再生されるが、普段は 15cm 程度にしている。
— Ansinity
名: イツ
身長: 182cm (ツノを含まない)
特性: 生きるものの生気を奪う [5]
生気をツノに溜め込んでおり、これがなくならない限りはかなり死ににくい。
生気を奪う方法はいくつかあるが、契約や性行によるものなど相手の生死にかかわる手段は身の危険に繋がるため好まない。
普段発動しているのは ”対象である生きるものの存在を認め、その生を尊く美しいと思うこと。” この前提さえ満たすなら範囲内 [9] のあらゆる生命とパスを繋げ、対象に影響を及ぼさない程ごく僅かずつの生気を得られる。[10]
— 脚注
【イバラシティ】
1. ^ 最悪ツノさえ食ってれば生きていける。治癒にツノを回している間は人並みに飯も食う。
2. ^ マシカ区 Q-19, P-19
3. ^ 銃刀法違反
4. ^ 本体の特性が『ツノを食べることでしか生気を利用できない』形で発現したもの。
5. ^ ツノの維持自体が異能によるため、異能を消されるなどして溜めた生気が失われることを本能的に嫌っている。
6. ^ 病気の回復などよりも、デフォルトのコンディションが良くなる効果が大きい。実年齢より全盛期の肉体に近くなり、知覚能力や身体能力は普通の人間の範囲ではまぁまぁ高い。
7. ^ 部位再生は数日かけて指くらいまで。ツノが食えるなら血液の再生は迅速に行われるので外傷に対してはしぶとい。
8. ^ 本人より高い効果は出ない。大体は疲れがや二日酔いが取れて調子が良くなりお肌が少し若返る完全栄養食止まり。
【イバラシティ・アンジニティ】
9. ^ イバラシティの異能では最大でマシカ区くらい。本体の特性による全力ならイバラシティ全域くらい。
10. ^ 本体の主となる特性。イバラシティではこれのみ発現しており、海の生き物などから生気を半ば無自覚に得ている。広範囲だが非常に微弱で、対象がこの能力による干渉を生理的に受け付けない場合は互いに無意識のうちに弾かれる。
21 / 30
111 PS
チナミ区
I-11
I-11



















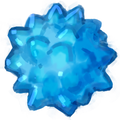



















| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 小さな輪 | 装飾 | 30 | 体力10 | - | - | |
| 5 | 銀の針 | 武器 | 30 | 回復10 | - | - | 【射程1】 |
| 6 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 7 | もうひとつの小さな輪 | 装飾 | 60 | 防御15 | - | - | |
| 8 | 美味しい果実 | 食材 | 15 | [効果1]攻撃10(LV10)[効果2]防御10(LV15)[効果3]強靭15(LV25) | |||
| 9 | 白樺 | 素材 | 15 | [武器]活力10(LV10)[防具]活力15(LV20)[装飾]活力10(LV10) | |||
| 10 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 具現 | 15 | 創造/召喚 |
| 変化 | 15 | 強化/弱化/変身 |
| 装飾 | 30 | 装飾作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| クリエイト:タライ | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |
| ガードフォーム | 5 | 0 | 100 | 自:DF増 | |
| ローバスト | 5 | 0 | 100 | 自従:MSP・AT増 | |
| ディベスト | 5 | 0 | 70 | 敵:強化奪取+痛撃 | |
| クリエイト:バトルフラッグ | 5 | 0 | 150 | 味全:DX・AG増(3T) | |
| サモン:サーヴァント | 5 | 5 | 300 | 自:サーヴァント召喚 | |
| アブソーブ | 5 | 0 | 100 | 敵全:次与ダメ減 | |
| サモン:ビーフ | 5 | 0 | 100 | 敵:連続減+アイテム「ビーフ」をドロップするようになる(遭遇戦・採集のみ) | |
| ブレイドフォーム | 6 | 0 | 160 | 自:AT増 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 召喚強化 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:具現LVが高いほど自身の召喚するNPCが強化 |
最大EP[20]





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]ストライク | [ 1 ]ティンダー | [ 1 ]ウォーターフォール |
| [ 3 ]イレイザー | [ 3 ]ハードブレイク |

PL / はっぱたそ