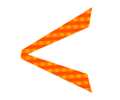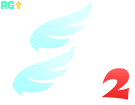<< 1:00~2:00




住処を定めてからの日々は、怒涛のごとく過ぎ去る。
ウィルヘルムがイバラシティの情報を集めて調べ上げ仕事を見つけて生活の基盤を整えていく間、クリスは日常的な交流が出来る様になる努力を積み重ね、少なくとも会話そのものと簡単な読み書きとぐらいはこなせる様になった。
その間、約一年。二人にとってはとても穏やかで静かな時間が流れていたのは確かだ。
世界間移動という、未だに慣れない旅路の疲れや新たな世界への適応の関係でクリスが体調を崩す……などと言ったトラブルもあったが、そんな細やかな問題以外は心配していた様なトラブル──例えば何らかの争いに巻き込まれたりだとか、世界に適応出来ず新たな場所を探す羽目になるとか──も無かったのがその証拠である。
この長いようで短い期間は、文明度の高い世界に慣れ親しんだウィルヘルムと違い、恐れからくる警戒心が高かったクリスにとっても良い準備期間だったらしい。
今では、簡単な家電──例えば炊飯器だとか電子レンジなど、家事に直結するものが多いのだが──程度ならば説明もなく使い方を把握している様である。スマホの様な最新鋭の機械にも自発的に使用をチャレンジをするようになった姿からして、使いこなせるようになるのも時間の問題だろう。
「そういえば学校はどんな感じだ?」
「え? どんなって?」
「いや……こう、馴染めているかなって。中途半端な学年への転入ってのもあって心配なのさ」
「あはは、ウィルは気にしすぎだよー」
冬も深まってきたある日。自室用にとウィルヘルムが買ってきて組み立てたばかりのコタツに、早速潜り込みながらクリスは苦笑を返す。保護者役を務める質問した当人はというと、畳の上に座り込んで黒猫の爪を切っている真っ最中だった。
とはいえ、ウィルヘルムの心配も当然ではあろう。この世界に移動してきて少しした頃に、一応転入手続きを行ったことで熾盛天晴学園──シジョウアマハラガクエン、という。やたら名前がややこしいので、略称であるハレ高としか呼ばないのだけれど──の正式な生徒となっていたクリスではあったが、当初は体調不良や言語がまだ完全に覚えられていない問題もあって暫く休学状態だったのだ。今はその辺りの問題も多少は緩和してきたこともあって、通学を開始している訳だが。
「そりゃあまあ、勉強はまだまだついてけてないなって所があるけど……言葉はちゃんと通じてるもん。大丈夫だよ。書いたりするのは大変だけど、ボク、その点では記憶力が良いからね。休み時間とかにちゃんと全部ノートにまとめてるからさ」
その場で質問されたりすると正直、科目によっては──例えば漢字問題とか──かなり困る場合もあるが、言語周りが不自由という事情は教師にも説明しているので多少温情をもらえている。時間はかかるが、何とか勉強はこなせている……というのがクリスの体感した現在の学生生活への評価だ。同じ学校に通っている人たちも皆、親切な人ばかりで心配するほどの事もない。
そうクリスが説明すれば、そうか……と少し安心した様子でウィルヘルムは表情を緩めた。
「勉強でわからない部分とかは俺でも教えられるやつが幾らかはあるから、その時は遠慮なく聞いてくれよ」
「でもウィルも仕事で忙しいのに」
何の仕事をしているのか知らないが、ウィルヘルムがこのイバラシティで働いているのは確かだ。偶に遅くなったり、逆にものすごく早く出掛ける事もあるのでなかなか変則的な勤務の様である。クリスとしては、ウィルヘルムだけに働かせるのは申し訳なく感じるし自分も働けたら……などと思いはするものの、どうもイバラシティというかこの世界では『子供は勉強が仕事のようなもの』という認識が一般的であるらしい。
試しに羊の放牧の見張りだとか、或いは畑の整備の手伝いだとか無いのかとウィルヘルムに聞いてみたら、苦笑しながら「そういうのは専門でやってる人がこなしていて子供だと体験学習とかそういう形になってしまうだろう」との事だった。働くとしても、そういう仕事をする人の家族とかでないと本格的には無理だろう……とも。
そんな訳で、家計を支えるという事を1人に背負わせる形となっている現状、勉強まで面倒を見させるのはさすがに……とクリスが思うのも当然といえば当然なのだった。実際、仕事で疲れている所で教師役までさせるのは申し訳ない話ではある。
が、当の本人はというとそんなことはないと穏やかに笑うのだ。
「俺もクリスが学ぶのと一緒に勉強させてもらっているのさ。この世界は俺にとっても未知だし、一応ざっくりと生活に支障がないレベルの情報は仕入れていても細かいことはわからないしな。かといって、情報端末を叩けば嫌というほどに情報は溢れている。学ぼうにもドコから摘めば良いのかもわからないくらいにな。だから、こういう教材があってそれに従って少しずつ学べる学校方式の学習ってのは丁度いいのさ」
「うー……まぁ、ウィルがそういうなら良いけど」
「ははは。とは言っても、わからないやつとかもあるからその辺りは勘弁してくれ」
特に得意なのは数学系とかかな、と言いつつウィルヘルムはパチリと爪切りを再開する。黒猫──メラン、という名前だ。ウィルヘルムの使い魔という奴らしい──が「めにゃー……」としおらしい鳴き声を上げているのがクリスからも見えた。
「ウィルは何でも出来るから凄いよねぇ……」
「そんな事も無いとは思うけどな……って、こら、メラン! 痛たッ!?」
しみじみと呟くクリスに返答する途中、黒猫に逃げられるウィルヘルムの悲鳴が響く。軽く噛まれたからか涙目な飼い主を放置して腕の中に飛び込んでくる黒猫を、仕方ないなぁと呆れつつも抱きとめた。喉元をなでてやればゴロゴロと嬉しげな音を鳴らすこのメランという猫は、飼い主であるウィルヘルムに対してはツンツンなくせをしてクリスにはやたらとデレデレなのである。
まぁ、その原因は半分ぐらい飼い主にあるのだが。ウィルヘルムはクールな見た目に反して猫大好きの猫狂い──というのは言いすぎな気もするが、他にいい表現もない──な男である。真実かどうかは不明だが、週に数回は猫カフェに通っているらしいというし、メランからすると「他所の猫にばっかりうつつを抜かして!」という気持ちになってもおかしくはない。それが飼い主に通じていないのが大問題なわけだが。
「時々思うけど……たまーにダメダメなんだよね、ウィルは」
「え? 俺が何だって?」
「何でもないー」
完璧過ぎるというのも、とっつきづらいというか、どう関われば良いのか困るものだろう。昔、もっと前、クリスがこの世界に来る前のウィルヘルムと出会ったばかりの頃、彼はもっと淡々としていて感情の発露が少ない人間だった。その頃を思えば、このぐらいのほうが愛嬌があって良いのかもしれない。
きっと、多分、『■■■■■■』もそう言う筈だ。
「……?」
クリスは首を傾げた。
『■■■■■■』って何だったろうか。
それは多分、とても、大切なものだった筈だ。
身近で、大好きで、失ってはいけないものだった筈だ。
──…でも、思い出せない。
「めにゃ!」
「わっ!?」
思考の深みに沈み込みそうだったのを引き戻すメランの声。目を瞬けば、クリスを心配げに覗き込む黒猫の顔があった。頬をペロペロと舐めてくる黒猫が安心できるように、微笑んで見せる。
「大丈夫だよ、メラン」
「……めにゃーん」
「大丈夫だってば」
不安げなその声を聞きながら、背を撫でつつクリスは静かに囁いた。
まるで、自分に言い聞かせるかのように。



ENo.847 一葉 とのやりとり

ENo.1099 コウ とのやりとり

以下の相手に送信しました












命術LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
響鳴LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
装飾LV を 5 UP!(LV25⇒30、-5CP)
目下(1345) の持つ ItemNo.8 何かの殻 から装飾『試作品のポプリ』を作製しました!
ランメイ(892) の持つ ItemNo.8 不思議な石 から装飾『燐灰石のネックレス』を作製しました!
つぐみ(894) により ItemNo.7 ボロ布 から防具『異界渡りの旅衣』を作製してもらいました!
⇒ 異界渡りの旅衣/防具:強さ40/[効果1]敏捷10 [効果2]- [効果3]-
春原とマル(159) とカードを交換しました!
なきごえ (エレジー)


ダウンフォール を研究しました!(深度0⇒1)
ダウンフォール を研究しました!(深度1⇒2)
ダウンフォール を研究しました!(深度2⇒3)
エチュード を習得!
アースタンブア を習得!
アトラクト を習得!
ビブラート を習得!
剛健 を習得!
精神変調特性 を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



クリス(62) は 白樺 を入手!
ウィル(72) は 杉 を入手!
ウィル(72) は 牙 を入手!
クリス(62) は 羽 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
ウィル(72) のもとに ウルフ がスキップしながら近づいてきます。
ウィル(72) のもとに キラービー が恥ずかしそうに近づいてきます。



ウィル(72) に移動を委ねました。
チナミ区 I-12(森林)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 I-13(道路)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 I-14(道路)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 I-15(沼地)に移動!(体調17⇒16)






―― ハザマ時間が紡がれる。

ため息をつく。
Cross+Roseにロスト7名の容姿と簡単なプロフィールが映し出される。







大きな打撃音と泣き声と共に、チャットが閉じられる――
























































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



住処を定めてからの日々は、怒涛のごとく過ぎ去る。
ウィルヘルムがイバラシティの情報を集めて調べ上げ仕事を見つけて生活の基盤を整えていく間、クリスは日常的な交流が出来る様になる努力を積み重ね、少なくとも会話そのものと簡単な読み書きとぐらいはこなせる様になった。
その間、約一年。二人にとってはとても穏やかで静かな時間が流れていたのは確かだ。
世界間移動という、未だに慣れない旅路の疲れや新たな世界への適応の関係でクリスが体調を崩す……などと言ったトラブルもあったが、そんな細やかな問題以外は心配していた様なトラブル──例えば何らかの争いに巻き込まれたりだとか、世界に適応出来ず新たな場所を探す羽目になるとか──も無かったのがその証拠である。
この長いようで短い期間は、文明度の高い世界に慣れ親しんだウィルヘルムと違い、恐れからくる警戒心が高かったクリスにとっても良い準備期間だったらしい。
今では、簡単な家電──例えば炊飯器だとか電子レンジなど、家事に直結するものが多いのだが──程度ならば説明もなく使い方を把握している様である。スマホの様な最新鋭の機械にも自発的に使用をチャレンジをするようになった姿からして、使いこなせるようになるのも時間の問題だろう。
「そういえば学校はどんな感じだ?」
「え? どんなって?」
「いや……こう、馴染めているかなって。中途半端な学年への転入ってのもあって心配なのさ」
「あはは、ウィルは気にしすぎだよー」
冬も深まってきたある日。自室用にとウィルヘルムが買ってきて組み立てたばかりのコタツに、早速潜り込みながらクリスは苦笑を返す。保護者役を務める質問した当人はというと、畳の上に座り込んで黒猫の爪を切っている真っ最中だった。
とはいえ、ウィルヘルムの心配も当然ではあろう。この世界に移動してきて少しした頃に、一応転入手続きを行ったことで熾盛天晴学園──シジョウアマハラガクエン、という。やたら名前がややこしいので、略称であるハレ高としか呼ばないのだけれど──の正式な生徒となっていたクリスではあったが、当初は体調不良や言語がまだ完全に覚えられていない問題もあって暫く休学状態だったのだ。今はその辺りの問題も多少は緩和してきたこともあって、通学を開始している訳だが。
「そりゃあまあ、勉強はまだまだついてけてないなって所があるけど……言葉はちゃんと通じてるもん。大丈夫だよ。書いたりするのは大変だけど、ボク、その点では記憶力が良いからね。休み時間とかにちゃんと全部ノートにまとめてるからさ」
その場で質問されたりすると正直、科目によっては──例えば漢字問題とか──かなり困る場合もあるが、言語周りが不自由という事情は教師にも説明しているので多少温情をもらえている。時間はかかるが、何とか勉強はこなせている……というのがクリスの体感した現在の学生生活への評価だ。同じ学校に通っている人たちも皆、親切な人ばかりで心配するほどの事もない。
そうクリスが説明すれば、そうか……と少し安心した様子でウィルヘルムは表情を緩めた。
「勉強でわからない部分とかは俺でも教えられるやつが幾らかはあるから、その時は遠慮なく聞いてくれよ」
「でもウィルも仕事で忙しいのに」
何の仕事をしているのか知らないが、ウィルヘルムがこのイバラシティで働いているのは確かだ。偶に遅くなったり、逆にものすごく早く出掛ける事もあるのでなかなか変則的な勤務の様である。クリスとしては、ウィルヘルムだけに働かせるのは申し訳なく感じるし自分も働けたら……などと思いはするものの、どうもイバラシティというかこの世界では『子供は勉強が仕事のようなもの』という認識が一般的であるらしい。
試しに羊の放牧の見張りだとか、或いは畑の整備の手伝いだとか無いのかとウィルヘルムに聞いてみたら、苦笑しながら「そういうのは専門でやってる人がこなしていて子供だと体験学習とかそういう形になってしまうだろう」との事だった。働くとしても、そういう仕事をする人の家族とかでないと本格的には無理だろう……とも。
そんな訳で、家計を支えるという事を1人に背負わせる形となっている現状、勉強まで面倒を見させるのはさすがに……とクリスが思うのも当然といえば当然なのだった。実際、仕事で疲れている所で教師役までさせるのは申し訳ない話ではある。
が、当の本人はというとそんなことはないと穏やかに笑うのだ。
「俺もクリスが学ぶのと一緒に勉強させてもらっているのさ。この世界は俺にとっても未知だし、一応ざっくりと生活に支障がないレベルの情報は仕入れていても細かいことはわからないしな。かといって、情報端末を叩けば嫌というほどに情報は溢れている。学ぼうにもドコから摘めば良いのかもわからないくらいにな。だから、こういう教材があってそれに従って少しずつ学べる学校方式の学習ってのは丁度いいのさ」
「うー……まぁ、ウィルがそういうなら良いけど」
「ははは。とは言っても、わからないやつとかもあるからその辺りは勘弁してくれ」
特に得意なのは数学系とかかな、と言いつつウィルヘルムはパチリと爪切りを再開する。黒猫──メラン、という名前だ。ウィルヘルムの使い魔という奴らしい──が「めにゃー……」としおらしい鳴き声を上げているのがクリスからも見えた。
「ウィルは何でも出来るから凄いよねぇ……」
「そんな事も無いとは思うけどな……って、こら、メラン! 痛たッ!?」
しみじみと呟くクリスに返答する途中、黒猫に逃げられるウィルヘルムの悲鳴が響く。軽く噛まれたからか涙目な飼い主を放置して腕の中に飛び込んでくる黒猫を、仕方ないなぁと呆れつつも抱きとめた。喉元をなでてやればゴロゴロと嬉しげな音を鳴らすこのメランという猫は、飼い主であるウィルヘルムに対してはツンツンなくせをしてクリスにはやたらとデレデレなのである。
まぁ、その原因は半分ぐらい飼い主にあるのだが。ウィルヘルムはクールな見た目に反して猫大好きの猫狂い──というのは言いすぎな気もするが、他にいい表現もない──な男である。真実かどうかは不明だが、週に数回は猫カフェに通っているらしいというし、メランからすると「他所の猫にばっかりうつつを抜かして!」という気持ちになってもおかしくはない。それが飼い主に通じていないのが大問題なわけだが。
「時々思うけど……たまーにダメダメなんだよね、ウィルは」
「え? 俺が何だって?」
「何でもないー」
完璧過ぎるというのも、とっつきづらいというか、どう関われば良いのか困るものだろう。昔、もっと前、クリスがこの世界に来る前のウィルヘルムと出会ったばかりの頃、彼はもっと淡々としていて感情の発露が少ない人間だった。その頃を思えば、このぐらいのほうが愛嬌があって良いのかもしれない。
きっと、多分、『■■■■■■』もそう言う筈だ。
「……?」
クリスは首を傾げた。
『■■■■■■』って何だったろうか。
それは多分、とても、大切なものだった筈だ。
身近で、大好きで、失ってはいけないものだった筈だ。
──…でも、思い出せない。
「めにゃ!」
「わっ!?」
思考の深みに沈み込みそうだったのを引き戻すメランの声。目を瞬けば、クリスを心配げに覗き込む黒猫の顔があった。頬をペロペロと舐めてくる黒猫が安心できるように、微笑んで見せる。
「大丈夫だよ、メラン」
「……めにゃーん」
「大丈夫だってば」
不安げなその声を聞きながら、背を撫でつつクリスは静かに囁いた。
まるで、自分に言い聞かせるかのように。



ENo.847 一葉 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.1099 コウ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
以下の相手に送信しました



| クリス 「ウィルとも無事に合流できたし、何とかこの争いが終わるまで乗り切りたい所……だけど。でも、負けるわけにもいかないよね。……アンジニティってどういう所か、ボクはよく知らないけど。ウィルは知ってる?」 |
 |
ウィル 「……こんな所で落ち着くほうが異常だ。 この企画の主催者はよほどいい趣味をしているようだな」 |







命術LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
響鳴LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
装飾LV を 5 UP!(LV25⇒30、-5CP)
目下(1345) の持つ ItemNo.8 何かの殻 から装飾『試作品のポプリ』を作製しました!
ランメイ(892) の持つ ItemNo.8 不思議な石 から装飾『燐灰石のネックレス』を作製しました!
つぐみ(894) により ItemNo.7 ボロ布 から防具『異界渡りの旅衣』を作製してもらいました!
⇒ 異界渡りの旅衣/防具:強さ40/[効果1]敏捷10 [効果2]- [効果3]-
| つぐみ 「こんな感じでどうだろうか。(筆で絵を描いてみせると、絵はふわりと宙に浮き、実体化した)」 |
春原とマル(159) とカードを交換しました!
なきごえ (エレジー)


ダウンフォール を研究しました!(深度0⇒1)
ダウンフォール を研究しました!(深度1⇒2)
ダウンフォール を研究しました!(深度2⇒3)
エチュード を習得!
アースタンブア を習得!
アトラクト を習得!
ビブラート を習得!
剛健 を習得!
精神変調特性 を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



クリス(62) は 白樺 を入手!
ウィル(72) は 杉 を入手!
ウィル(72) は 牙 を入手!
クリス(62) は 羽 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
ウィル(72) のもとに ウルフ がスキップしながら近づいてきます。
ウィル(72) のもとに キラービー が恥ずかしそうに近づいてきます。



ウィル(72) に移動を委ねました。
チナミ区 I-12(森林)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 I-13(道路)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 I-14(道路)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 I-15(沼地)に移動!(体調17⇒16)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
ノウレット 「またまたこんにちは―――ッ!!」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
 |
白南海 「・・・っつぅ・・・・・また貴方ですか・・・ ・・・耳が痛くなるんでフリップにでも書いてくれませんかねぇ。」 |
 |
ノウレット 「はぁい!イヤですッ!!」 |
 |
白南海 「Yesなのか、Noなのか・・・」 |
ため息をつく。
 |
白南海 「それで、自己紹介の次は何用です?」 |
 |
ノウレット 「はぁい!今回はロストに関する情報を持ってきましたよーッ!!」 |
 |
白南海 「おぉそれは感心ですね、イルカよりは性能良さそうです。褒めてあげましょう。」 |
 |
ノウレット 「やったぁぁ―――ッ!!!!」 |
 |
白南海 「だから大声やめろおぉぉぉクソ妖精ッッ!!!」 |
 |
ノウレット 「早速ですが・・・・・ジャーンッ!!こちらがロスト情報ですよー!!!!」 |
Cross+Roseにロスト7名の容姿と簡単なプロフィールが映し出される。

アンドリュウ
紫の瞳、金髪ドレッドヘア。
体格の良い気さくなお兄さん。
料理好き、エプロン姿が何か似合っている。
体格の良い気さくなお兄さん。
料理好き、エプロン姿が何か似合っている。

ロジエッタ
水色の瞳、菫色の長髪。
大人しそうな小さな女の子。
黒いドレスを身につけ、男の子の人形を大事そうに抱えている。
大人しそうな小さな女の子。
黒いドレスを身につけ、男の子の人形を大事そうに抱えている。

アルメシア
金の瞳、白い短髪。褐色肌。
戦闘狂で活動的な少女。
鎧を身につけハルバードを持っている。
戦闘狂で活動的な少女。
鎧を身につけハルバードを持っている。

ソージロウ
黒い瞳、黒いもじゃもじゃ頭。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。

フレディオ
碧眼、ロマンスグレーの短髪。
彫りが深く、男前な老翁。
黒のライダースジャケットを身に着けている。
彫りが深く、男前な老翁。
黒のライダースジャケットを身に着けている。

ミヨチン
茶色の瞳、桜色のロング巻き髪。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。

マッドスマイル
乱れた長い黒緑色の髪。
両手に紅いナイフを持ち、
猟奇的な笑顔の仮面をつけている。
両手に紅いナイフを持ち、
猟奇的な笑顔の仮面をつけている。
 |
白南海 「ほぅほぅ、みな人間・・・のような容姿ですね。ハザマの様子的に意外なようでもあり。 彼らの願望を叶えると影響力が上がり、ハザマでの力も高めてくれる・・・と。」 |
 |
白南海 「どんな願望なのやら、無茶振りされないといいんですが。 ロストに若がいたならどんな願望もソッコーで叶えに行きますがね!」 |
 |
ノウレット 「ワカは居ませんよ?」 |
 |
白南海 「・・・わかってますよ。」 |
 |
白南海 「ところで情報はこれだけっすか?クソ妖精。」 |
 |
ノウレット 「あだ名で呼ぶとか・・・・・まだ早いと思います。出会ったばかりですし私たち。」 |
 |
白南海 「ねぇーんですね。居場所くらい持ってくるもんかと。」 |
 |
白南海 「ちなみに、ロストってのは何者なんで? これもハザマのシステムって解釈でいいのかね。」 |
 |
ノウレット 「ごめんなさい!私はCross+Roseの妖精なのでハザマのことはよくわかりません!! Cross+Roseに送られた情報を伝えることしか・・・・・」 |
 |
白南海 「・・・まぁそーか。仕方ないが、どうも断片的っすねぇ。」 |
 |
白南海 「そんじゃ、チェックポイントを目指しがてらロスト探しもしていきましょうかね。」 |
 |
ノウレット 「レッツゴォォ―――ッ!!!!」 |
大きな打撃音と泣き声と共に、チャットが閉じられる――







ENo.62
クリス・ヴェスパー



[Name]クリス・ヴェスパー(Cris・Vesper)
[Height]155cm
[Weight]48kg
[Middle school]熾盛天晴学園(シジョウアマハラガクエン)
中等部3年2組
ちょっと人見知りがちの明るく元気なお子様。
体を動かす事が大好きで、得意なのは駆けっこと木登り。
反面、勉強は少々苦手(嫌いではない)で苦労している。
遠縁の親戚だという青年を保護者として一緒に暮らしている。
ペットに黒猫を飼っている様子でよく一緒に遊んでいる。
宝物で友達だというのはうさぎっぽい黒のぬいぐるみ。
生まれ育ちは異国との事。
その関係か、会話は大丈夫だが文字の読み書きは下手くそ。
電子機器系は使い慣れないらしく機械音痴な所がある。
また、まだまだイバラシティの文化や技術には不慣れな様子。
好きな事は、運動とお昼寝と散歩と星空を見るのと絵本。
好きな食べ物は、リンゴとシチューとその他諸々。
苦手な事は、勉強(主に読み書きと計算)。
苦手な食べ物は、苦いものと辛いものと匂いのキツイもの。
★連絡先★
【クリスのスマホ(既知、或いは連絡先の交換済の人向け)】
http://lisge.com/ib/talk.php?p=715
【喜久田商店(下宿先)】
http://lisge.com/ib/talk.php?s=135
★保護者★
【ウィルさん】
http://lisge.com/ib/k/now/r72.html
※RP歓迎ですが反応時間がマチマチです。あまりリアルタイム対応は難しいかもしれない事をご了承下されば幸いです。(出来る時は出来るけど)
※既知設定などもわりと柔軟に対応出来るとは思うので気楽にどうぞ。(駄目なものは駄目というし)
※一部アイコン、ヘッダ画像は「いらすとや」「写真AC」の物を加工し使用しています。
[Height]155cm
[Weight]48kg
[Middle school]熾盛天晴学園(シジョウアマハラガクエン)
中等部3年2組
ちょっと人見知りがちの明るく元気なお子様。
体を動かす事が大好きで、得意なのは駆けっこと木登り。
反面、勉強は少々苦手(嫌いではない)で苦労している。
遠縁の親戚だという青年を保護者として一緒に暮らしている。
ペットに黒猫を飼っている様子でよく一緒に遊んでいる。
宝物で友達だというのはうさぎっぽい黒のぬいぐるみ。
生まれ育ちは異国との事。
その関係か、会話は大丈夫だが文字の読み書きは下手くそ。
電子機器系は使い慣れないらしく機械音痴な所がある。
また、まだまだイバラシティの文化や技術には不慣れな様子。
好きな事は、運動とお昼寝と散歩と星空を見るのと絵本。
好きな食べ物は、リンゴとシチューとその他諸々。
苦手な事は、勉強(主に読み書きと計算)。
苦手な食べ物は、苦いものと辛いものと匂いのキツイもの。
★連絡先★
【クリスのスマホ(既知、或いは連絡先の交換済の人向け)】
http://lisge.com/ib/talk.php?p=715
【喜久田商店(下宿先)】
http://lisge.com/ib/talk.php?s=135
★保護者★
【ウィルさん】
http://lisge.com/ib/k/now/r72.html
※RP歓迎ですが反応時間がマチマチです。あまりリアルタイム対応は難しいかもしれない事をご了承下されば幸いです。(出来る時は出来るけど)
※既知設定などもわりと柔軟に対応出来るとは思うので気楽にどうぞ。(駄目なものは駄目というし)
※一部アイコン、ヘッダ画像は「いらすとや」「写真AC」の物を加工し使用しています。
16 / 30
122 PS
チナミ区
I-15
I-15














| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 光輝【棍】 | 武器 | 30 | 攻撃10 | - | - | 【射程1】 |
| 5 | 紫蝶の御守 | 装飾 | 30 | 幸運10 | - | - | |
| 6 | 救急箱 | 武器 | 35 | 治癒10 | - | - | 【射程1】 |
| 7 | 異界渡りの旅衣 | 防具 | 40 | 敏捷10 | - | - | |
| 8 | 白樺 | 素材 | 15 | [武器]活力10(LV10)[防具]活力15(LV20)[装飾]活力10(LV10) | |||
| 9 | 羽 | 素材 | 10 | [武器]風撃10(LV25)[防具]風柳10(LV20)[装飾]風纏10(LV20) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 自然 | 10 | 植物/鉱物/地 |
| 幻術 | 10 | 夢幻/精神/光 |
| 響鳴 | 10 | 歌唱/音楽/振動 |
| 装飾 | 30 | 装飾作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ウォーターフォール | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |
| 練1 | ストーンブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵:地撃&朦朧 |
| ライトニング | 5 | 0 | 50 | 敵:精確光撃 | |
| エチュード | 5 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) | |
| リフレッシュ | 5 | 0 | 50 | 味肉精3:祝福+肉体精神変調をAT化 | |
| ブレス | 5 | 0 | 100 | 味全:HP増+祝福 | |
| アマゾナイト | 5 | 0 | 100 | 自:LK・火耐性・闇耐性増 | |
| アースタンブア | 5 | 0 | 100 | 敵:地撃&自:3D6が15以上ならMHP・MSP増 | |
| アトラクト | 5 | 0 | 50 | 自:HATE・連続増 | |
| ブルーム | 5 | 0 | 120 | 敵全:地撃&魅了・束縛 | |
| 練1 | ディム | 5 | 0 | 50 | 敵:SP光撃 |
| ビブラート | 5 | 0 | 120 | 敵全2:粗雑SP攻撃 | |
| リリーフ | 5 | 0 | 70 | 味傷3:HP増+祝福 | |
| グランドクラッシャー | 5 | 0 | 160 | 敵列:地撃 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 剛健 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・MSP増 | |
| 精神変調特性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:精神変調特性増 | |
| 地の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:自然LVが高いほど地特性・耐性増 | |
| 魔晶作製 | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『装備作製』で装飾「魔晶」を選択できる。魔晶は効果3に充填LVが付加される。 |
最大EP[20]





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]ストライク | [ 3 ]デアデビル | [ 3 ]ダウンフォール |

PL / 九十九