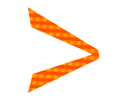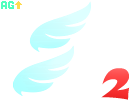<< 0:00~1:00




イバラシティはリュウジン区の一角。
駅も近い細い通りに面した場所に、その店はあった。
喜久田商店という古めかしくもシンプルな看板が目印のその店は、いわゆる駄菓子屋と呼ばれる部類の店である。軒先にはジュースの販売機やアイスの詰まった冷蔵庫が並び、店内には無数の種類の駄菓子が溢れる光景は、一昔前なら当たり前だったが昨今ともなると少々珍しくレトロとも称されてしまいかねない。実際、店そのものも歴は古いと店主は言う。今ではこのスタイルを貫く店は少ないのだ、とも。
その奥手、店舗部分より更に内側の敷地には小さな庭に面した二棟の建物があった。片方は古い平屋で、喜久田商店の主たる喜久田イマの住居。そしてもう片方はというと、二階建ての日本家屋からなる下宿である。紹介状を手に喜久田商店を訪れたウィルヘルムとクリスは、快く迎え入れられ契約書を交わした後、その下宿の一階に並ぶ二部屋をあてがわれたのであった。
「草の匂いがする……」
「タタミ、という奴だな。この土地の建築では古来からそういう床への敷物が一般的なんだそうだ」
「この扉みたいなのは横に開くんだね」
「フスマっていうんだよ。木の枠に特殊な紙を貼って作られているんだ」
「この格子が目立つ扉もフスマ?」
「そっちはショウジだ。貼ってある紙は襖より薄い。うっかり破るなよ」
「このちっちゃめのテーブル、可愛いね」
「チャブダイっていうんだよ。何かの作法ではひっくり返して見せるものだとか聞いたが……」
室内に通されたクリスは、家主が店舗の方へと戻っていったのを確認すれば物珍しげに周囲を見回す。和風、という様式らしいというのは聞いたがそういったものとは今まで縁のなかった生活をしていたもので、見るもの全てに興味津々といった感じだ。壁際の押入れの戸を開ければ、中にある布団をおずおずと突いたりしている様子は、微笑ましいものである。
ウィルヘルム──この土地では『ウィル』と名乗っているのは此処だけの話だ──はといえば、少ない手荷物を部屋の隅に置いて書類と一緒に手にしていた一枚の折りたたまれた紙を卓袱台の上に広げた所だった。紙には綺麗な印刷で大きな地図が描かれている。イバラシティの全景図だ。
「この喜久田商店はリュウジン区の此処、だったな……近くには駅もある様だし、道すがらバス停なんかも見かけた所を見ると随分と交通は発展してるらしい」
「えき? ばすてい??」
「乗り物が一時的に止まってくれる場所だよ。公共の交通機関だ。これがあるかないかで不便さが変わるからな」
特にこういった科学文明の進んだ世界では、と苦笑して見せればクリスは複雑な表情を浮かべる。
「ボク、その、かがくぶんめーってのがよくわかんないんだけど……」
「簡単に言えばそうだな……高度に発展した技術や知識を使って、人が暮らすのに便利な道具や仕組みが発明され、当たり前のように其れが普及している様な文明社会の事さ。まあ、今までの環境からすると大違いすぎて何が何やらお前にはわからないだろうが」
「……ウィルはでも、判ってるみたいだよね?」
何で、と疑問符を浮かべる子供の頭を撫でてやりつつウィルヘルムは微笑む。
「俺も昔は、そういう高度な文明が発展してた世界で暮らしていたからな。ある意味、此処の世界より俺の産まれた世界の方が技術は発展してたかもしれない」
これは嘘でもなんでもない事だ。こうして一緒にクリスと──そして此処には居ないヴィーズィーと──まるで家族のように生活をしているウィルヘルムだが、それは暫く前からの事でその前は全く異なる世界で生きていた異界人である。もうそちらの世界とは色々な理由もあって縁を切ってしまったが、実際にとても科学技術が発展していた世界でもあった──異界移動の転送技術や人造人間を製造する等、かなりレベルは高かった様である──おかげで、イバラシティのアレコレもあっさりと理解してしまった訳である。
「とはいえ、クリスもこの世界に暫く滞在するんだ。ちゃんとこういう技術の使い方だけでも学んでおくと良い。知らないままだと危ないものもあるしな」
「その前にボクは言葉と文字の勉強だよ……」
「ははは……そういえばそうだったな」
多少の拙さはあれどまだ会話可能なウィルヘルムと異なり、クリスにとっては初の文化圏。話す言葉も使う文字も未知のものである。険しい表情で座り込んで卓袱台に突っ伏すその眼前へと、ウィルヘルムは一冊の手帳のようなものを差し出した。怪訝げに視線を上げてその表紙を読み上げようとするが、やはり無理で首を横にふるクリス。
「何これ」
「ひらがなドリルだ」
「ひらがなどりる」
「この文化圏の文字の基本の基本を学ぶための学習素材だ。これが終わったら漢字ドリルもあるぞ」
「うえぇぇぇぇ……」
「まずはコミュニケーションを取れるようになるのが第一歩だ。大丈夫、見知らぬ土地でも大体笑顔で身振り手振りしてれば何となく分かる様になる」
「とっても暴論じゃないそれ!?」
「でもこれが一番手っ取り早いからな。何、暫く仕事が決まるまでは時間があるんだ。その間は俺も勉強を見てやるから安心しろ。目指すは学校に通えるようになる事……って感じか」
「本当に大丈夫かなぁ……」
呻きつつもそれでも素直にひらがなドリルを受け取るクリス。渋々とはいえ、勉強そのものに対する嫌悪の感情はその顔には浮かんでいない。純粋に、ちゃんと覚えられるかどうかが心配なだけなのだろう。実際、勉強そのものは嫌いではなかった筈だ。
ちょっと建物の中に何があるのかだけ見てくる、と断って廊下へと駆け出していくその背を微笑ましげに見送ったウィルヘルムは、例の運び屋による荷物搬入の為の準備をする。預けられた目印になるというお香を取り出せば、部屋の隅で慎重に火を付けた。専用の皿の上でチリチリと煙を真上へとたなびかせ、独特の香りが場に広がり始める頃。
《……此処か》
瞬きしたほんの刹那の合間に、目の前に人影が現れる。黒フードに黒マントという黒尽くめのその姿は、運び屋だと名乗った人物のものであった。運び屋は部屋の中を一瞥するとウィルヘルムへと顔を向ける。
《荷は何処に置くか》
「そうだな……とりあえずこの部屋と、」
言って、運び屋の後ろにある襖を開いた。そこには同じ間取りのもう一室がある。襖を隔てて左右対称に二部屋あったのだ。そちらを指差せば、
「この部屋に半分ずつ置いてもらえるか。後は、こっちで何とかするさ」
《承った。では、目を》
このイバラシティに来た転移の時も目をつぶれ、と言っていた。今回も同じだろう、と頷けばウィルヘルムは目を閉じて暫し待った。物音はほとんどしない。ほんの少しだけ、木板が軋む様な音が微かに聞こえた気がした。
《もう良いだろう》
言われ目を開けば、其処にはイバラシティに来る前の世界でまとめていた荷物の数々が、畳の上に積まれ並べられていた。一体全体どういう技術の賜物なのか、とウィルヘルムは舌を巻く。目を瞑ったままでも多少は周囲の様子はわかる。魔力が動いたならばその形跡だって逃すつもりはない。だというのに、何一つ痕跡は無いのだ。まるで、無から湧いて出てきたように自分達の預けた品は在った。
「助かったよ。……しかし、本当、あんた一体何者なんだ?」
《運び屋である。それ以上でもそれ以下でも無い》
あくまでヴィーズィーの使いであるとだけ語り、名も姿も晒すつもりの無い相手に呆れ混じりの言葉を投げるウィルヘルム。それに対して、運び屋は淡々とフードの奥から返すのみだ。その声音も、フードの奥側から届くせいかくぐもっていて相手の正体を更に謎めいたものにするだけである。
「話すつもりはない、と。まぁ良いけどな。ヴィズの紹介だっていうなら、信頼は出来る」
《納得したようならば何よりだ》
言えば、背を向ける運び屋。しかしそこで彼──或いは彼女、か?──は動きを止めた様だった。わぁすごーいなんかふるーい!……という明るい声が遠くから届く。クリスの声だ。上の方から聞こえるので、多分、この下宿の二階部分をあちこち覗いているのかもしれない。
その声に耳を澄ませていたのか、それともまた別の要因か。動きを止めていた運び屋は、何を思ったのか肩越しにウィルヘルムへと振り返り……そして、口を開いた。
《……気を付けることだ》
「……? 何の事だ?」
訝しげに問うウィルヘルム。忠告のようなその言葉の真意を尋ねる。
《お前の見ている世界は、お前の知るままの世界ではない》
「世界……? このイバラシティの事か?」
《そうだ。お前が認識しているこの世界は、お前が本来辿り着くと想定したものではない》
「意味がわからない」
《わからずとも良い。ただ、覚えておく事だ。線の異なる道の先である、その事実を忘れるな》
「いや、本当、何が言いたいんだあんた」
《心構えの話だ。覚悟が出来ていれば動揺は少なくて済む。そういう話だ》
「はぁ……」
《異なる事象にもまた意味がある。その理由を常に問う事だ》
それだけ言ってしまえば、話すことは無くなったのだろう。運び屋は今度こそ完全に背を向けた。そのまま一歩二歩と歩を進め……ウィルヘルムが瞬きした一瞬で、再び姿は消え失せていた。完全に、気配すら残さず消えてしまったのだ。現れた時と同様である。一瞬、夢か幻でも見たんじゃないかと思ってしまうウィルヘルムだったが、その心配は杞憂に消えた。
「ちゃんと荷物はある、からな」
二つの部屋に積まれた、決して少なくはない荷物。これが証拠だ。苦笑を浮かべつつもウィルヘルムは二階のクリスへと声をかけた。荷解きは一人では難しい。人員が必要だったからである。はぁい、と明るく元気な声が上から返ってくるのに笑みを深めながら、ウィルヘルムはふと、先程まで運び屋が居たはずの場所を見た。何一つ痕跡を残さず消えた運び屋が、最後に告げた言の葉を思い出す。
「俺の見ている世界は、俺の知るままの世界ではない……? 一体何の話なんだか」
反駁してみても意味はやはりわからなかった。
ただの悪戯かもしれない、と思ったがそれでも何だかやたらと気になる。もやもやとした、変な気持ち。或いは落ち着かない、ゾワゾワとした感覚。こういう気分の時はあまり良くないことが起こるものだ。……嫌な経験則だが。
「勘弁してほしいな……」
ため息交じりにそう呟きつつ。
ウィルヘルムは、荷物の片付けの為に袖をまくりあげるのだった。













自然LV を 10 DOWN。(LV20⇒10、+10CP、-10FP)
命術LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
幻術LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
装飾LV を 5 UP!(LV20⇒25、-5CP)
ランメイ(892) により ItemNo.6 不思議な食材 に ItemNo.7 不思議な食材 を合成してもらい、何か柔らかい物体 に変化させました!
⇒ 何か柔らかい物体/素材:強さ10/[武器]治癒10(LV20)[防具]命脈10(LV25)[装飾]防御10(LV20)/特殊アイテム
ランメイ(892) の持つ ItemNo.5 不思議な石 から魔晶『赤瑪瑙のネックレス』を作製しました!
つぐみ(894) の持つ ItemNo.5 不思議な石 から魔晶『スクエアメガネ』を作製しました!
ウィル(72) により ItemNo.6 何か柔らかい物体 から射程1の武器『救急箱』を作製してもらいました!
⇒ 救急箱/武器:強さ35/[効果1]治癒10 [効果2]- [効果3]-【射程1】/特殊アイテム
眞梨奈(155) とカードを交換しました!
ライフリカバー&クイックネス (キュアブリーズ)

ストライク を研究しました!(深度0⇒1)
ストライク を研究しました!(深度1⇒2)
ストライク を研究しました!(深度2⇒3)
ウォーターフォール を習得!
ライトニング を習得!
リフレッシュ を習得!
ブレス を習得!
アマゾナイト を習得!
ディム を習得!
リリーフ を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



クリス(62) は ぬめぬめ を入手!
ウィル(72) は 何かの殻 を入手!
ウィル(72) は 不思議な雫 を入手!
ウィル(72) は 何か柔らかい物体 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
ウィル(72) のもとに ピクシー がスキップしながら近づいてきます。
ウィル(72) のもとに ホシイモくん が空を見上げなから近づいてきます。



ウィル(72) に移動を委ねました。
チナミ区 G-9(沼地)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 H-9(沼地)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 I-9(沼地)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 I-10(森林)に移動!(体調22⇒21)
チナミ区 I-11(森林)に移動!(体調21⇒20)
採集はできませんでした。
- クリス(62) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- ウィル(72) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。
元気よく両手両足を伸ばし空間を飛びまわる!
・・・姿を現すことなく、女性のような声が伝わる。
ため息のような音が漏れる。
声はそこで終わる。
チャットが閉じられる――






















































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



イバラシティはリュウジン区の一角。
駅も近い細い通りに面した場所に、その店はあった。
喜久田商店という古めかしくもシンプルな看板が目印のその店は、いわゆる駄菓子屋と呼ばれる部類の店である。軒先にはジュースの販売機やアイスの詰まった冷蔵庫が並び、店内には無数の種類の駄菓子が溢れる光景は、一昔前なら当たり前だったが昨今ともなると少々珍しくレトロとも称されてしまいかねない。実際、店そのものも歴は古いと店主は言う。今ではこのスタイルを貫く店は少ないのだ、とも。
その奥手、店舗部分より更に内側の敷地には小さな庭に面した二棟の建物があった。片方は古い平屋で、喜久田商店の主たる喜久田イマの住居。そしてもう片方はというと、二階建ての日本家屋からなる下宿である。紹介状を手に喜久田商店を訪れたウィルヘルムとクリスは、快く迎え入れられ契約書を交わした後、その下宿の一階に並ぶ二部屋をあてがわれたのであった。
「草の匂いがする……」
「タタミ、という奴だな。この土地の建築では古来からそういう床への敷物が一般的なんだそうだ」
「この扉みたいなのは横に開くんだね」
「フスマっていうんだよ。木の枠に特殊な紙を貼って作られているんだ」
「この格子が目立つ扉もフスマ?」
「そっちはショウジだ。貼ってある紙は襖より薄い。うっかり破るなよ」
「このちっちゃめのテーブル、可愛いね」
「チャブダイっていうんだよ。何かの作法ではひっくり返して見せるものだとか聞いたが……」
室内に通されたクリスは、家主が店舗の方へと戻っていったのを確認すれば物珍しげに周囲を見回す。和風、という様式らしいというのは聞いたがそういったものとは今まで縁のなかった生活をしていたもので、見るもの全てに興味津々といった感じだ。壁際の押入れの戸を開ければ、中にある布団をおずおずと突いたりしている様子は、微笑ましいものである。
ウィルヘルム──この土地では『ウィル』と名乗っているのは此処だけの話だ──はといえば、少ない手荷物を部屋の隅に置いて書類と一緒に手にしていた一枚の折りたたまれた紙を卓袱台の上に広げた所だった。紙には綺麗な印刷で大きな地図が描かれている。イバラシティの全景図だ。
「この喜久田商店はリュウジン区の此処、だったな……近くには駅もある様だし、道すがらバス停なんかも見かけた所を見ると随分と交通は発展してるらしい」
「えき? ばすてい??」
「乗り物が一時的に止まってくれる場所だよ。公共の交通機関だ。これがあるかないかで不便さが変わるからな」
特にこういった科学文明の進んだ世界では、と苦笑して見せればクリスは複雑な表情を浮かべる。
「ボク、その、かがくぶんめーってのがよくわかんないんだけど……」
「簡単に言えばそうだな……高度に発展した技術や知識を使って、人が暮らすのに便利な道具や仕組みが発明され、当たり前のように其れが普及している様な文明社会の事さ。まあ、今までの環境からすると大違いすぎて何が何やらお前にはわからないだろうが」
「……ウィルはでも、判ってるみたいだよね?」
何で、と疑問符を浮かべる子供の頭を撫でてやりつつウィルヘルムは微笑む。
「俺も昔は、そういう高度な文明が発展してた世界で暮らしていたからな。ある意味、此処の世界より俺の産まれた世界の方が技術は発展してたかもしれない」
これは嘘でもなんでもない事だ。こうして一緒にクリスと──そして此処には居ないヴィーズィーと──まるで家族のように生活をしているウィルヘルムだが、それは暫く前からの事でその前は全く異なる世界で生きていた異界人である。もうそちらの世界とは色々な理由もあって縁を切ってしまったが、実際にとても科学技術が発展していた世界でもあった──異界移動の転送技術や人造人間を製造する等、かなりレベルは高かった様である──おかげで、イバラシティのアレコレもあっさりと理解してしまった訳である。
「とはいえ、クリスもこの世界に暫く滞在するんだ。ちゃんとこういう技術の使い方だけでも学んでおくと良い。知らないままだと危ないものもあるしな」
「その前にボクは言葉と文字の勉強だよ……」
「ははは……そういえばそうだったな」
多少の拙さはあれどまだ会話可能なウィルヘルムと異なり、クリスにとっては初の文化圏。話す言葉も使う文字も未知のものである。険しい表情で座り込んで卓袱台に突っ伏すその眼前へと、ウィルヘルムは一冊の手帳のようなものを差し出した。怪訝げに視線を上げてその表紙を読み上げようとするが、やはり無理で首を横にふるクリス。
「何これ」
「ひらがなドリルだ」
「ひらがなどりる」
「この文化圏の文字の基本の基本を学ぶための学習素材だ。これが終わったら漢字ドリルもあるぞ」
「うえぇぇぇぇ……」
「まずはコミュニケーションを取れるようになるのが第一歩だ。大丈夫、見知らぬ土地でも大体笑顔で身振り手振りしてれば何となく分かる様になる」
「とっても暴論じゃないそれ!?」
「でもこれが一番手っ取り早いからな。何、暫く仕事が決まるまでは時間があるんだ。その間は俺も勉強を見てやるから安心しろ。目指すは学校に通えるようになる事……って感じか」
「本当に大丈夫かなぁ……」
呻きつつもそれでも素直にひらがなドリルを受け取るクリス。渋々とはいえ、勉強そのものに対する嫌悪の感情はその顔には浮かんでいない。純粋に、ちゃんと覚えられるかどうかが心配なだけなのだろう。実際、勉強そのものは嫌いではなかった筈だ。
ちょっと建物の中に何があるのかだけ見てくる、と断って廊下へと駆け出していくその背を微笑ましげに見送ったウィルヘルムは、例の運び屋による荷物搬入の為の準備をする。預けられた目印になるというお香を取り出せば、部屋の隅で慎重に火を付けた。専用の皿の上でチリチリと煙を真上へとたなびかせ、独特の香りが場に広がり始める頃。
《……此処か》
瞬きしたほんの刹那の合間に、目の前に人影が現れる。黒フードに黒マントという黒尽くめのその姿は、運び屋だと名乗った人物のものであった。運び屋は部屋の中を一瞥するとウィルヘルムへと顔を向ける。
《荷は何処に置くか》
「そうだな……とりあえずこの部屋と、」
言って、運び屋の後ろにある襖を開いた。そこには同じ間取りのもう一室がある。襖を隔てて左右対称に二部屋あったのだ。そちらを指差せば、
「この部屋に半分ずつ置いてもらえるか。後は、こっちで何とかするさ」
《承った。では、目を》
このイバラシティに来た転移の時も目をつぶれ、と言っていた。今回も同じだろう、と頷けばウィルヘルムは目を閉じて暫し待った。物音はほとんどしない。ほんの少しだけ、木板が軋む様な音が微かに聞こえた気がした。
《もう良いだろう》
言われ目を開けば、其処にはイバラシティに来る前の世界でまとめていた荷物の数々が、畳の上に積まれ並べられていた。一体全体どういう技術の賜物なのか、とウィルヘルムは舌を巻く。目を瞑ったままでも多少は周囲の様子はわかる。魔力が動いたならばその形跡だって逃すつもりはない。だというのに、何一つ痕跡は無いのだ。まるで、無から湧いて出てきたように自分達の預けた品は在った。
「助かったよ。……しかし、本当、あんた一体何者なんだ?」
《運び屋である。それ以上でもそれ以下でも無い》
あくまでヴィーズィーの使いであるとだけ語り、名も姿も晒すつもりの無い相手に呆れ混じりの言葉を投げるウィルヘルム。それに対して、運び屋は淡々とフードの奥から返すのみだ。その声音も、フードの奥側から届くせいかくぐもっていて相手の正体を更に謎めいたものにするだけである。
「話すつもりはない、と。まぁ良いけどな。ヴィズの紹介だっていうなら、信頼は出来る」
《納得したようならば何よりだ》
言えば、背を向ける運び屋。しかしそこで彼──或いは彼女、か?──は動きを止めた様だった。わぁすごーいなんかふるーい!……という明るい声が遠くから届く。クリスの声だ。上の方から聞こえるので、多分、この下宿の二階部分をあちこち覗いているのかもしれない。
その声に耳を澄ませていたのか、それともまた別の要因か。動きを止めていた運び屋は、何を思ったのか肩越しにウィルヘルムへと振り返り……そして、口を開いた。
《……気を付けることだ》
「……? 何の事だ?」
訝しげに問うウィルヘルム。忠告のようなその言葉の真意を尋ねる。
《お前の見ている世界は、お前の知るままの世界ではない》
「世界……? このイバラシティの事か?」
《そうだ。お前が認識しているこの世界は、お前が本来辿り着くと想定したものではない》
「意味がわからない」
《わからずとも良い。ただ、覚えておく事だ。線の異なる道の先である、その事実を忘れるな》
「いや、本当、何が言いたいんだあんた」
《心構えの話だ。覚悟が出来ていれば動揺は少なくて済む。そういう話だ》
「はぁ……」
《異なる事象にもまた意味がある。その理由を常に問う事だ》
それだけ言ってしまえば、話すことは無くなったのだろう。運び屋は今度こそ完全に背を向けた。そのまま一歩二歩と歩を進め……ウィルヘルムが瞬きした一瞬で、再び姿は消え失せていた。完全に、気配すら残さず消えてしまったのだ。現れた時と同様である。一瞬、夢か幻でも見たんじゃないかと思ってしまうウィルヘルムだったが、その心配は杞憂に消えた。
「ちゃんと荷物はある、からな」
二つの部屋に積まれた、決して少なくはない荷物。これが証拠だ。苦笑を浮かべつつもウィルヘルムは二階のクリスへと声をかけた。荷解きは一人では難しい。人員が必要だったからである。はぁい、と明るく元気な声が上から返ってくるのに笑みを深めながら、ウィルヘルムはふと、先程まで運び屋が居たはずの場所を見た。何一つ痕跡を残さず消えた運び屋が、最後に告げた言の葉を思い出す。
「俺の見ている世界は、俺の知るままの世界ではない……? 一体何の話なんだか」
反駁してみても意味はやはりわからなかった。
ただの悪戯かもしれない、と思ったがそれでも何だかやたらと気になる。もやもやとした、変な気持ち。或いは落ち着かない、ゾワゾワとした感覚。こういう気分の時はあまり良くないことが起こるものだ。……嫌な経験則だが。
「勘弁してほしいな……」
ため息交じりにそう呟きつつ。
ウィルヘルムは、荷物の片付けの為に袖をまくりあげるのだった。





| クリス 「落ち着かないな……こっちの世界。凄い、ザワザワする……。」 |
 |
ウィル 「……クリス!無事か?」 |







自然LV を 10 DOWN。(LV20⇒10、+10CP、-10FP)
命術LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
幻術LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
装飾LV を 5 UP!(LV20⇒25、-5CP)
ランメイ(892) により ItemNo.6 不思議な食材 に ItemNo.7 不思議な食材 を合成してもらい、何か柔らかい物体 に変化させました!
⇒ 何か柔らかい物体/素材:強さ10/[武器]治癒10(LV20)[防具]命脈10(LV25)[装飾]防御10(LV20)/特殊アイテム
| ランメイ 「おや、可愛らしい嬢ちゃんだねえ。昔のあたしを思い出すよ」 |
ランメイ(892) の持つ ItemNo.5 不思議な石 から魔晶『赤瑪瑙のネックレス』を作製しました!
つぐみ(894) の持つ ItemNo.5 不思議な石 から魔晶『スクエアメガネ』を作製しました!
ウィル(72) により ItemNo.6 何か柔らかい物体 から射程1の武器『救急箱』を作製してもらいました!
⇒ 救急箱/武器:強さ35/[効果1]治癒10 [効果2]- [効果3]-【射程1】/特殊アイテム
 |
ウィル 「武器……?武器なのかこれは?」 |
眞梨奈(155) とカードを交換しました!
ライフリカバー&クイックネス (キュアブリーズ)

ストライク を研究しました!(深度0⇒1)
ストライク を研究しました!(深度1⇒2)
ストライク を研究しました!(深度2⇒3)
ウォーターフォール を習得!
ライトニング を習得!
リフレッシュ を習得!
ブレス を習得!
アマゾナイト を習得!
ディム を習得!
リリーフ を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



クリス(62) は ぬめぬめ を入手!
ウィル(72) は 何かの殻 を入手!
ウィル(72) は 不思議な雫 を入手!
ウィル(72) は 何か柔らかい物体 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
ウィル(72) のもとに ピクシー がスキップしながら近づいてきます。
ウィル(72) のもとに ホシイモくん が空を見上げなから近づいてきます。



ウィル(72) に移動を委ねました。
チナミ区 G-9(沼地)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 H-9(沼地)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 I-9(沼地)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 I-10(森林)に移動!(体調22⇒21)
チナミ区 I-11(森林)に移動!(体調21⇒20)
採集はできませんでした。
- クリス(62) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- ウィル(72) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
「おっくれまして―――ッ!!」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
 |
ノウレット 「はぁい!はじめましてーッ!!私はここCross+Roseの管・・・妖精! ノウレットでーっす!!皆さんよろしくおねがいしまぁーっす!!」 |
チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。
 |
白南海 「・・・・・。管理用アバター・・・ですかね。」 |
 |
ノウレット 「元気ないですねーッ!!死んでるんですかーッ!!!!」 |
 |
白南海 「貴方よりは生物的かと思いますよ。 ドライバーさんと同じく、ハザマの機能ってやつですか。」 |
 |
ノウレット 「機能なんて言わないでください!妖精です!!妖精なんですッ!!」 |
 |
ノウレット 「Cross+Roseのことで分からないことは何でも聞いてくださいねーっ!!」 |
 |
白南海 「あぁ、どっちかというとアレですか。"お前を消す方法"・・・みたいな。」 |
 |
ノウレット 「よくご存知でーっ!!そうです!多分それでーっす!!!!」 |
元気よく両手両足を伸ばし空間を飛びまわる!
 |
ノウレット 「えーっとそれでですねーッ!!」 |
 |
ノウレット 「・・・・・あれっ 創造主さまからメッセージが!」 |
 |
白南海 「おや、なんでしょうね。」 |
・・・姿を現すことなく、女性のような声が伝わる。
 |
声 「――お疲れ様です御二方。役目を担ってくれて、感謝しています。」 |
 |
白南海 「担うも何も、強制ですけどね。報酬でも頂きたいくらいで。」 |
 |
声 「そしてハザマに招かれた方々、申し訳ありません。」 |
 |
声 「・・・・・・・・・」 |
 |
声 「このワールドスワップという能力は、招かれた方々全員が――ザザッ・・・」 |
 |
声 「――失われ、そう――ザザッ・・・――周期的に発動する、能力というより・・・」 |
 |
声 「制御不能な・・・呪いのよう。今までに発動した数度、自分への利は・・・ない。」 |
 |
声 「・・・・・・・・・」 |
ため息のような音が漏れる。
 |
声 「どうか、自らが自らであ―― ザザッ・・・」 |
 |
白南海 「・・・・・?」 |
 |
声 「――ザザッ・・・・・・・・己の世界のために、争え。」 |
声はそこで終わる。
 |
白南海 「何だか変なふうに終わりましたねぇ。」 |
 |
ノウレット 「そうですかーっ!!?そうでもないですよーっ!!!?」 |
 |
白南海 「どーも、嫌な予感が・・・ ・・・いや、十分嫌な状況ではありますがね。」 |
 |
白南海 「・・・・・ま、とりあえずやれることやるだけっすね。」 |
チャットが閉じられる――





ENo.62
クリス・ヴェスパー



[Name]クリス・ヴェスパー(Cris・Vesper)
[Height]155cm
[Weight]48kg
[Middle school]熾盛天晴学園(シジョウアマハラガクエン)
中等部3年2組
ちょっと人見知りがちの明るく元気なお子様。
体を動かす事が大好きで、得意なのは駆けっこと木登り。
反面、勉強は少々苦手(嫌いではない)で苦労している。
遠縁の親戚だという青年を保護者として一緒に暮らしている。
ペットに黒猫を飼っている様子でよく一緒に遊んでいる。
宝物で友達だというのはうさぎっぽい黒のぬいぐるみ。
生まれ育ちは異国との事。
その関係か、会話は大丈夫だが文字の読み書きは下手くそ。
電子機器系は使い慣れないらしく機械音痴な所がある。
また、まだまだイバラシティの文化や技術には不慣れな様子。
好きな事は、運動とお昼寝と散歩と星空を見るのと絵本。
好きな食べ物は、リンゴとシチューとその他諸々。
苦手な事は、勉強(主に読み書きと計算)。
苦手な食べ物は、苦いものと辛いものと匂いのキツイもの。
★連絡先★
【クリスのスマホ(既知、或いは連絡先の交換済の人向け)】
http://lisge.com/ib/talk.php?p=715
【喜久田商店(下宿先)】
http://lisge.com/ib/talk.php?s=135
★保護者★
【ウィルさん】
http://lisge.com/ib/k/now/r72.html
※RP歓迎ですが反応時間がマチマチです。あまりリアルタイム対応は難しいかもしれない事をご了承下されば幸いです。(出来る時は出来るけど)
※既知設定などもわりと柔軟に対応出来るとは思うので気楽にどうぞ。(駄目なものは駄目というし)
※一部アイコン、ヘッダ画像は「いらすとや」「写真AC」の物を加工し使用しています。
[Height]155cm
[Weight]48kg
[Middle school]熾盛天晴学園(シジョウアマハラガクエン)
中等部3年2組
ちょっと人見知りがちの明るく元気なお子様。
体を動かす事が大好きで、得意なのは駆けっこと木登り。
反面、勉強は少々苦手(嫌いではない)で苦労している。
遠縁の親戚だという青年を保護者として一緒に暮らしている。
ペットに黒猫を飼っている様子でよく一緒に遊んでいる。
宝物で友達だというのはうさぎっぽい黒のぬいぐるみ。
生まれ育ちは異国との事。
その関係か、会話は大丈夫だが文字の読み書きは下手くそ。
電子機器系は使い慣れないらしく機械音痴な所がある。
また、まだまだイバラシティの文化や技術には不慣れな様子。
好きな事は、運動とお昼寝と散歩と星空を見るのと絵本。
好きな食べ物は、リンゴとシチューとその他諸々。
苦手な事は、勉強(主に読み書きと計算)。
苦手な食べ物は、苦いものと辛いものと匂いのキツイもの。
★連絡先★
【クリスのスマホ(既知、或いは連絡先の交換済の人向け)】
http://lisge.com/ib/talk.php?p=715
【喜久田商店(下宿先)】
http://lisge.com/ib/talk.php?s=135
★保護者★
【ウィルさん】
http://lisge.com/ib/k/now/r72.html
※RP歓迎ですが反応時間がマチマチです。あまりリアルタイム対応は難しいかもしれない事をご了承下されば幸いです。(出来る時は出来るけど)
※既知設定などもわりと柔軟に対応出来るとは思うので気楽にどうぞ。(駄目なものは駄目というし)
※一部アイコン、ヘッダ画像は「いらすとや」「写真AC」の物を加工し使用しています。
20 / 30
44 PS
チナミ区
I-11
I-11














| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 光輝【棍】 | 武器 | 30 | 攻撃10 | - | - | 【射程1】 |
| 5 | 紫蝶の御守 | 装飾 | 30 | 幸運10 | - | - | |
| 6 | 救急箱 | 武器 | 35 | 治癒10 | - | - | 【射程1】 |
| 7 | ぬめぬめ | 素材 | 10 | [武器]列撃10(LV25)[防具]舞反10(LV25)[装飾]幸運10(LV10) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 命術 | 5 | 生命/復元/水 |
| 自然 | 10 | 植物/鉱物/地 |
| 幻術 | 10 | 夢幻/精神/光 |
| 装飾 | 25 | 装飾作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ウォーターフォール | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |
| ストーンブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵:地撃&朦朧 | |
| 練1 | ライトニング | 5 | 0 | 50 | 敵:精確光撃 |
| リフレッシュ | 5 | 0 | 50 | 味肉精3:祝福+肉体精神変調をAT化 | |
| ブレス | 5 | 0 | 100 | 味全:HP増+祝福 | |
| アマゾナイト | 5 | 0 | 100 | 自:LK・火耐性・闇耐性増 | |
| ブルーム | 5 | 0 | 120 | 敵全:地撃&魅了・束縛 | |
| 練1 | ディム | 5 | 0 | 50 | 敵:SP光撃 |
| リリーフ | 5 | 0 | 70 | 味傷3:HP増+祝福 | |
| グランドクラッシャー | 5 | 0 | 160 | 敵列:地撃 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 地の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:自然LVが高いほど地特性・耐性増 | |
| 魔晶作製 | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『装備作製』で装飾「魔晶」を選択できる。魔晶は効果3に充填LVが付加される。 |
最大EP[20]





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]ストライク | [ 3 ]デアデビル |

PL / 九十九