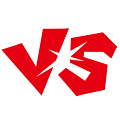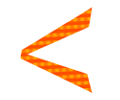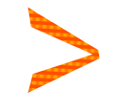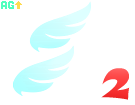<< 0:00~0:00




【此処につながる前の話はコチラ:https://privatter.net/p/5197939】
今から遡ること一年前。
「ここが、イバラシティ?」
「らしいな。しかし……話には聞いていたが随分と栄えた場所の様だ」
金髪に翡翠の瞳をした子供──クリスが首を傾げつつ問えば、隣の保護者は頭をかきつつため息をついた。その視線を追いかけてクリスもまた周囲を見回す。いま自分たちがいるのはこの土地の南の方にあるという港だが、その港にしたって規模が大きい様だ。事前情報では異国ともやり取りするらしい話を聞いている。鉄の船が悠々と水面に浮く光景は、今まで木造船しか見たことの無いクリスには酷く衝撃だった。
※ ※ ※ ※ ※
イバラシティという場所に赴いて欲しい、と話があったのは一週間程前の事だ。連絡をよこしたのは淡く紫に輝く蝶だった。クリスの義理の母に当たるヴィーズィーがよく扱う使い魔で、主の声やら何やらを届けてくれる便利な存在である。
ヴィーズィーは暫く前からクリスの側を離れて行商の旅に出ていた。行商といっても普通の旅ではない。それは、数多存在する異界を渡り歩いて行われるものだ。とはいえ、それ自体は珍しい話ではない。違う世界で定住していた頃も、時折そうしてヴィーズィーは旅に出て長い時間を留守にしていた事があったからだ。
そんな旅の最中でも、留守番をする側に心配をかけないようにヴィーズィーは良く連絡を寄越した。その為に使われていたのがこの光の蝶で、普段は何処かに潜んでいるのだが必要な時にふらりと現れてこうして声を届けてくれるのである。
「イバラシティ……?」
『今おぬしらがおる【《蒼穹の世界》シルフェルディア】からすると、幾分離れた場所に存在する異界の一つじゃな。【《響奏の世界》イバラシティ】というのが正式な名称となる』
「……そこが次の目的地になるのか?」
横から顔を出したのは銀の髪と赤い目をした整った顔立ちの青年……ウィルヘルムだ。彼はクリスの隣へとくれば、ゆっくりと羽ばたく光蝶を見据えつつ眉根を寄せる。
「まだ移動には正直速い気がするが。あと数年は居ても問題ないだろうに」
『それも正論ではあるのじゃがな』
苦笑の気配が声音に滲む。
『あまりそちらの世界に長居しすぎると情が移りすぎて辛いのではないか、と思案してな』
「む……それは、まぁ……そうか……」
事情があって一所になかなか留まることの出来ない身──これはヴィーズィーだけではなく、クリスもウィルヘルムも同様だ──からすると適切なタイミングでの異界渡りは必須となる。情が移りすぎて云々にはウィルヘルムとしても思い当たる節があるからか複雑そうな顔で黙り込んだ。実際、既に今暮らしている街の人達との交流はそれなりに深まってきた事もあって、後ろ髪を引かれる思いが現状ですらそれなりにあるのは確かだ。
「じゃあ、……お引越しするの?」
『そうなるかの。おぬしからすると、ちと寂しいかもしれんが……』
「そう……だね。せっかく友達とかも出来たのに……」
淋しげな表情でポツリとクリスは呟く。
『すまぬな……悲しい思いをさせる』
「ううん。良いんだ。仕方ないのは分かってるから」
慣れてるから大丈夫だよ、とそれでも淋しげに笑うクリスの頭を、慰めるように撫でてやりつつウィルヘルムが口を開く。
「移動のタイミングはどうする」
『迎えを寄越そう。迷って違う世界に行かれても面倒じゃしな。それに、今丁度、そういう異界移動に適した輩が来ておるのじゃ。こういう時とばかりに使いっぱしりさせてやらねばな』
蝶の向こう側でカラカラと笑う声がする。それに対して何か抗議をする様な声がした気がするが、よく聞こえはしなかった。ただ、ヴィーズィーの知り合いが側にいるという事なのだろう。異界渡りの旅人歴がやたら長い人物である。人脈もまた言うまでもなくやたらと広く、それなりに側で暮らして長いクリスやウィルヘルムをしても把握しきれていない部分は多い。
『とりあえず、迎えは一週間後におぬしらの所に行くようにしておくでな。準備を宜しゅう頼むわい』
「了解だ」
「はーい」
『……ではの』
いつもの簡潔な挨拶を返してヴィーズィーからの通信は途切れた。どこかへとパタパタ飛んでいってしまった光蝶を見送って、荷造りをどう進めるべきだろうかと頭を悩ませることになったのは、また別のお話である。
※ ※ ※ ※ ※
「しかし……世界間移動を一瞬で終わらせてしまうとは。恐ろしいもんだな」
「ウィルのやつだと半日がかりだもんね」
「事前準備が必要だからな。慣れてないのもあるし、まあこれは仕方ないだろ」
二人で顔を見合わせ苦笑いを交わす。実際、連絡から一週間後の今朝方に迎えは来たのだ。ただの運び屋だと言う黒フードに黒マント姿の人物──顔も見えない徹底ぶりだった──はヴィーズィーの使いだと答え、こき使われる身の不憫さを愚痴るように嘆きつつも事前に運ぶべき荷物と住居が決まってから運ぶべき荷物、そして移動する人員を確認したあと、二人に眼をつぶるようにと促したのである。
「次に目を開けた時には目的地だ、って言ってたけど本当にそうなんだもん。ビックリしちゃった」
「俺もだよ。まさか体に何ひとつ感じさせず転移可能な技術を持つ奴がいるとは」
必要最低限の荷物だけを手元に残してイバラシティの片隅に立っているのだから、先の出来事は夢幻ではないのだろう。運び屋の姿は無い。目立つので自分は入らず『世界』の外側から荷物はまた届けるので決まり次第に目印──小さなお香の様な三角コーンを預かった──を立てろとは言われたので、心配はないが。
潮の香りを感じながらウィルヘルムは小脇に抱えていた自分の使い魔である黒猫を地面に下ろす。めにゃー、と特徴的な鳴き声をあげて周囲をうろつき始めるのを横目に、さて、とポケットから紙切れを取り出した。使いっぱしりだった人物がヴィーズィーから預かっていたというもの一つで、イバラシティに関する簡易情報が書き込まれているメモだ。
「住処にできそうな場所の情報を色々仕入れておいてくれたのは助かるよな」
「一番候補はドコなの?」
「キクタ商店……店っぽいな。下宿をしているとかで、そこは安いし家主も親切そう……とか」
「他にも色々載ってるね……ボクには読めないけど」
「クリスは平仮名や漢字はまだ覚えてないもんな……これから勉強するしか無いか」
「えううぅぅぅ……」
「ま、これから慣れていけば良い」
何せまだ到着したばかりなのだ。生活が始まるのはこれからなのだし焦ることはない。
そうクリスに言い聞かせながらウィルヘルムは一路歩き始める。
まずは住居を確保しなければいけない。
そのために。



ENo.847 一葉 とのやりとり

ENo.1099 コウ とのやりとり










駄木(50 PS)を購入しようとしましたが、PSが足りませんでした。
自然LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)
装飾LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)
ItemNo.5 不思議な石 から装飾『紫蝶の御守』を作製しました!
⇒ 紫蝶の御守/装飾:強さ30/[効果1]幸運10 [効果2]- [効果3]-/特殊アイテム
ウィル(72) の持つ ItemNo.5 不思議な石 から装飾『Lucky Sigil』を作製しました!
アイリ(893) の持つ ItemNo.4 不思議な牙 から装飾『シャルドネのワイン』を作製しました!
ウィル(72) により ItemNo.4 不思議な牙 から射程1の武器『光輝【棍】』を作製してもらいました!
⇒ 光輝【棍】/武器:強さ30/[効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程1】/特殊アイテム
イブキ(1310) とカードを交換しました!
ヒール (ブレイク)

デアデビル を研究しました!(深度0⇒1)
デアデビル を研究しました!(深度1⇒2)
デアデビル を研究しました!(深度2⇒3)
ストーンブラスト を習得!
ブルーム を習得!
☆地の祝福 を習得!
☆グランドクラッシャー を習得!
☆魔晶作製 を習得!
☆初習得ボーナス:各FPが6増加した!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





次元タクシーに乗り チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》 に転送されました!
チナミ区 F-5(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 F-6(道路)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 F-7(草原)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 F-8(草原)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 F-9(沼地)に移動!(体調26⇒25)
ウィル(72) をパーティに勧誘しました!
採集はできませんでした。
- クリス(62) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- ウィル(72) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャットで時間が伝えられる。
グチャッとなったどこかのナレハテの映像をまじまじと見つめる白南海。
その背後から、突然タクシーが現れる!!
白南海のすぐ横を走り抜け、止まる。
タクシーの窓が開く。

帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。
窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。
白南海からのチャットが閉じられる――














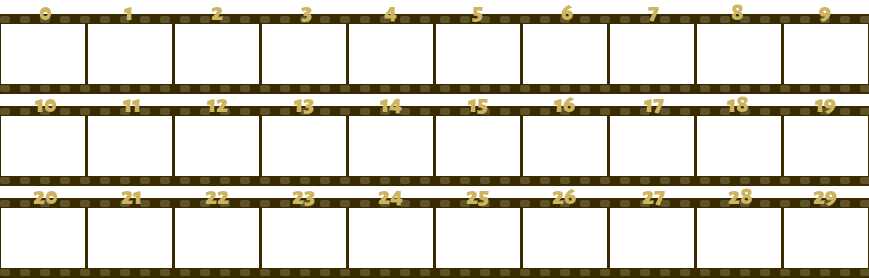







































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



【此処につながる前の話はコチラ:https://privatter.net/p/5197939】
今から遡ること一年前。
「ここが、イバラシティ?」
「らしいな。しかし……話には聞いていたが随分と栄えた場所の様だ」
金髪に翡翠の瞳をした子供──クリスが首を傾げつつ問えば、隣の保護者は頭をかきつつため息をついた。その視線を追いかけてクリスもまた周囲を見回す。いま自分たちがいるのはこの土地の南の方にあるという港だが、その港にしたって規模が大きい様だ。事前情報では異国ともやり取りするらしい話を聞いている。鉄の船が悠々と水面に浮く光景は、今まで木造船しか見たことの無いクリスには酷く衝撃だった。
※ ※ ※ ※ ※
イバラシティという場所に赴いて欲しい、と話があったのは一週間程前の事だ。連絡をよこしたのは淡く紫に輝く蝶だった。クリスの義理の母に当たるヴィーズィーがよく扱う使い魔で、主の声やら何やらを届けてくれる便利な存在である。
ヴィーズィーは暫く前からクリスの側を離れて行商の旅に出ていた。行商といっても普通の旅ではない。それは、数多存在する異界を渡り歩いて行われるものだ。とはいえ、それ自体は珍しい話ではない。違う世界で定住していた頃も、時折そうしてヴィーズィーは旅に出て長い時間を留守にしていた事があったからだ。
そんな旅の最中でも、留守番をする側に心配をかけないようにヴィーズィーは良く連絡を寄越した。その為に使われていたのがこの光の蝶で、普段は何処かに潜んでいるのだが必要な時にふらりと現れてこうして声を届けてくれるのである。
「イバラシティ……?」
『今おぬしらがおる【《蒼穹の世界》シルフェルディア】からすると、幾分離れた場所に存在する異界の一つじゃな。【《響奏の世界》イバラシティ】というのが正式な名称となる』
「……そこが次の目的地になるのか?」
横から顔を出したのは銀の髪と赤い目をした整った顔立ちの青年……ウィルヘルムだ。彼はクリスの隣へとくれば、ゆっくりと羽ばたく光蝶を見据えつつ眉根を寄せる。
「まだ移動には正直速い気がするが。あと数年は居ても問題ないだろうに」
『それも正論ではあるのじゃがな』
苦笑の気配が声音に滲む。
『あまりそちらの世界に長居しすぎると情が移りすぎて辛いのではないか、と思案してな』
「む……それは、まぁ……そうか……」
事情があって一所になかなか留まることの出来ない身──これはヴィーズィーだけではなく、クリスもウィルヘルムも同様だ──からすると適切なタイミングでの異界渡りは必須となる。情が移りすぎて云々にはウィルヘルムとしても思い当たる節があるからか複雑そうな顔で黙り込んだ。実際、既に今暮らしている街の人達との交流はそれなりに深まってきた事もあって、後ろ髪を引かれる思いが現状ですらそれなりにあるのは確かだ。
「じゃあ、……お引越しするの?」
『そうなるかの。おぬしからすると、ちと寂しいかもしれんが……』
「そう……だね。せっかく友達とかも出来たのに……」
淋しげな表情でポツリとクリスは呟く。
『すまぬな……悲しい思いをさせる』
「ううん。良いんだ。仕方ないのは分かってるから」
慣れてるから大丈夫だよ、とそれでも淋しげに笑うクリスの頭を、慰めるように撫でてやりつつウィルヘルムが口を開く。
「移動のタイミングはどうする」
『迎えを寄越そう。迷って違う世界に行かれても面倒じゃしな。それに、今丁度、そういう異界移動に適した輩が来ておるのじゃ。こういう時とばかりに使いっぱしりさせてやらねばな』
蝶の向こう側でカラカラと笑う声がする。それに対して何か抗議をする様な声がした気がするが、よく聞こえはしなかった。ただ、ヴィーズィーの知り合いが側にいるという事なのだろう。異界渡りの旅人歴がやたら長い人物である。人脈もまた言うまでもなくやたらと広く、それなりに側で暮らして長いクリスやウィルヘルムをしても把握しきれていない部分は多い。
『とりあえず、迎えは一週間後におぬしらの所に行くようにしておくでな。準備を宜しゅう頼むわい』
「了解だ」
「はーい」
『……ではの』
いつもの簡潔な挨拶を返してヴィーズィーからの通信は途切れた。どこかへとパタパタ飛んでいってしまった光蝶を見送って、荷造りをどう進めるべきだろうかと頭を悩ませることになったのは、また別のお話である。
※ ※ ※ ※ ※
「しかし……世界間移動を一瞬で終わらせてしまうとは。恐ろしいもんだな」
「ウィルのやつだと半日がかりだもんね」
「事前準備が必要だからな。慣れてないのもあるし、まあこれは仕方ないだろ」
二人で顔を見合わせ苦笑いを交わす。実際、連絡から一週間後の今朝方に迎えは来たのだ。ただの運び屋だと言う黒フードに黒マント姿の人物──顔も見えない徹底ぶりだった──はヴィーズィーの使いだと答え、こき使われる身の不憫さを愚痴るように嘆きつつも事前に運ぶべき荷物と住居が決まってから運ぶべき荷物、そして移動する人員を確認したあと、二人に眼をつぶるようにと促したのである。
「次に目を開けた時には目的地だ、って言ってたけど本当にそうなんだもん。ビックリしちゃった」
「俺もだよ。まさか体に何ひとつ感じさせず転移可能な技術を持つ奴がいるとは」
必要最低限の荷物だけを手元に残してイバラシティの片隅に立っているのだから、先の出来事は夢幻ではないのだろう。運び屋の姿は無い。目立つので自分は入らず『世界』の外側から荷物はまた届けるので決まり次第に目印──小さなお香の様な三角コーンを預かった──を立てろとは言われたので、心配はないが。
潮の香りを感じながらウィルヘルムは小脇に抱えていた自分の使い魔である黒猫を地面に下ろす。めにゃー、と特徴的な鳴き声をあげて周囲をうろつき始めるのを横目に、さて、とポケットから紙切れを取り出した。使いっぱしりだった人物がヴィーズィーから預かっていたというもの一つで、イバラシティに関する簡易情報が書き込まれているメモだ。
「住処にできそうな場所の情報を色々仕入れておいてくれたのは助かるよな」
「一番候補はドコなの?」
「キクタ商店……店っぽいな。下宿をしているとかで、そこは安いし家主も親切そう……とか」
「他にも色々載ってるね……ボクには読めないけど」
「クリスは平仮名や漢字はまだ覚えてないもんな……これから勉強するしか無いか」
「えううぅぅぅ……」
「ま、これから慣れていけば良い」
何せまだ到着したばかりなのだ。生活が始まるのはこれからなのだし焦ることはない。
そうクリスに言い聞かせながらウィルヘルムは一路歩き始める。
まずは住居を確保しなければいけない。
そのために。



ENo.847 一葉 とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.1099 コウ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||



| クリス 「……何だか変な雰囲気の場所だね。」 |





駄木(50 PS)を購入しようとしましたが、PSが足りませんでした。
自然LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)
装飾LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)
ItemNo.5 不思議な石 から装飾『紫蝶の御守』を作製しました!
⇒ 紫蝶の御守/装飾:強さ30/[効果1]幸運10 [効果2]- [効果3]-/特殊アイテム
ウィル(72) の持つ ItemNo.5 不思議な石 から装飾『Lucky Sigil』を作製しました!
アイリ(893) の持つ ItemNo.4 不思議な牙 から装飾『シャルドネのワイン』を作製しました!
ウィル(72) により ItemNo.4 不思議な牙 から射程1の武器『光輝【棍】』を作製してもらいました!
⇒ 光輝【棍】/武器:強さ30/[効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程1】/特殊アイテム
 |
ウィル 「これでお前の武器も強くなるはずだ。」 |
イブキ(1310) とカードを交換しました!
ヒール (ブレイク)

デアデビル を研究しました!(深度0⇒1)
デアデビル を研究しました!(深度1⇒2)
デアデビル を研究しました!(深度2⇒3)
ストーンブラスト を習得!
ブルーム を習得!
☆地の祝福 を習得!
☆グランドクラッシャー を習得!
☆魔晶作製 を習得!
☆初習得ボーナス:各FPが6増加した!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





次元タクシーに乗り チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》 に転送されました!
 |
ドライバーさん 「はいお疲れさん。サービスの飴ちゃん持ってきな。」 |
チナミ区 F-5(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 F-6(道路)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 F-7(草原)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 F-8(草原)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 F-9(沼地)に移動!(体調26⇒25)
ウィル(72) をパーティに勧誘しました!
採集はできませんでした。
- クリス(62) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- ウィル(72) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
白南海 「長針一周・・・っと。丁度1時間っすね。」 |

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
チャットで時間が伝えられる。
 |
白南海 「ケンカは無事済みましたかね。 こてんぱんにすりゃいいってわけですかい。」 |
グチャッとなったどこかのナレハテの映像をまじまじと見つめる白南海。
その背後から、突然タクシーが現れる!!
白南海のすぐ横を走り抜け、止まる。
 |
白南海 「・・・・・こ、殺す気ですかね。」 |
タクシーの窓が開く。

ドライバーさん
次元タクシーの運転手。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。初老くらいに見える。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。初老くらいに見える。
 |
ドライバーさん 「すまんすまん、出口の座標を少し間違えた。 挨拶に来たぜ。『次元タクシー』の運転役だ。」 |
帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。
 |
白南海 「イバラシティ側を潰そうってんじゃねぇでしょーね。・・・ぶっ殺しますよ?」 |
 |
ドライバーさん 「安心しな、どっちにも加勢するさ。俺らはそういう役割の・・・ハザマの機能ってとこだ。」 |
 |
ドライバーさん 「チェックポイントとかの行き来の際にゃ、へいタクシーの一声を。 俺もタクシーも同じのが沢山"在る"んでな、待たしゃしない。・・・そんじゃ。」 |
窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。
 |
白南海 「ひとを轢きかけといてあの態度・・・後で営業妨害でもしてやろうか。」 |
 |
白南海 「さて、それでは私は・・・のんびり傍観させてもらいますかね。この役も悪くない。」 |
白南海からのチャットが閉じられる――





ENo.62
クリス・ヴェスパー



[Name]クリス・ヴェスパー(Cris・Vesper)
[Height]155cm
[Weight]48kg
[Middle school]熾盛天晴学園(シジョウアマハラガクエン)
中等部3年2組
ちょっと人見知りがちの明るく元気なお子様。
体を動かす事が大好きで、得意なのは駆けっこと木登り。
反面、勉強は少々苦手(嫌いではない)で苦労している。
遠縁の親戚だという青年を保護者として一緒に暮らしている。
ペットに黒猫を飼っている様子でよく一緒に遊んでいる。
宝物で友達だというのはうさぎっぽい黒のぬいぐるみ。
生まれ育ちは異国との事。
その関係か、会話は大丈夫だが文字の読み書きは下手くそ。
電子機器系は使い慣れないらしく機械音痴な所がある。
また、まだまだイバラシティの文化や技術には不慣れな様子。
好きな事は、運動とお昼寝と散歩と星空を見るのと絵本。
好きな食べ物は、リンゴとシチューとその他諸々。
苦手な事は、勉強(主に読み書きと計算)。
苦手な食べ物は、苦いものと辛いものと匂いのキツイもの。
★連絡先★
【クリスのスマホ(既知、或いは連絡先の交換済の人向け)】
http://lisge.com/ib/talk.php?p=715
【喜久田商店(下宿先)】
http://lisge.com/ib/talk.php?s=135
★保護者★
【ウィルさん】
http://lisge.com/ib/k/now/r72.html
※RP歓迎ですが反応時間がマチマチです。あまりリアルタイム対応は難しいかもしれない事をご了承下されば幸いです。(出来る時は出来るけど)
※既知設定などもわりと柔軟に対応出来るとは思うので気楽にどうぞ。(駄目なものは駄目というし)
※一部アイコン、ヘッダ画像は「いらすとや」「写真AC」の物を加工し使用しています。
[Height]155cm
[Weight]48kg
[Middle school]熾盛天晴学園(シジョウアマハラガクエン)
中等部3年2組
ちょっと人見知りがちの明るく元気なお子様。
体を動かす事が大好きで、得意なのは駆けっこと木登り。
反面、勉強は少々苦手(嫌いではない)で苦労している。
遠縁の親戚だという青年を保護者として一緒に暮らしている。
ペットに黒猫を飼っている様子でよく一緒に遊んでいる。
宝物で友達だというのはうさぎっぽい黒のぬいぐるみ。
生まれ育ちは異国との事。
その関係か、会話は大丈夫だが文字の読み書きは下手くそ。
電子機器系は使い慣れないらしく機械音痴な所がある。
また、まだまだイバラシティの文化や技術には不慣れな様子。
好きな事は、運動とお昼寝と散歩と星空を見るのと絵本。
好きな食べ物は、リンゴとシチューとその他諸々。
苦手な事は、勉強(主に読み書きと計算)。
苦手な食べ物は、苦いものと辛いものと匂いのキツイもの。
★連絡先★
【クリスのスマホ(既知、或いは連絡先の交換済の人向け)】
http://lisge.com/ib/talk.php?p=715
【喜久田商店(下宿先)】
http://lisge.com/ib/talk.php?s=135
★保護者★
【ウィルさん】
http://lisge.com/ib/k/now/r72.html
※RP歓迎ですが反応時間がマチマチです。あまりリアルタイム対応は難しいかもしれない事をご了承下されば幸いです。(出来る時は出来るけど)
※既知設定などもわりと柔軟に対応出来るとは思うので気楽にどうぞ。(駄目なものは駄目というし)
※一部アイコン、ヘッダ画像は「いらすとや」「写真AC」の物を加工し使用しています。
25 / 30
5 PS
チナミ区
F-9
F-9














| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 光輝【棍】 | 武器 | 30 | 攻撃10 | - | - | 【射程1】 |
| 5 | 紫蝶の御守 | 装飾 | 30 | 幸運10 | - | - | |
| 6 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 自然 | 20 | 植物/鉱物/地 |
| 装飾 | 20 | 装飾作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ストーンブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵:地撃&朦朧 | |
| ブルーム | 5 | 0 | 120 | 敵全:地撃&魅了・束縛 | |
| グランドクラッシャー | 5 | 0 | 160 | 敵列:地撃 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 地の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:自然LVが高いほど地特性・耐性増 | |
| 魔晶作製 | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『装備作製』で装飾「魔晶」を選択できる。魔晶は効果3に充填LVが付加される。 |
最大EP[20]





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]デアデビル |

PL / 九十九