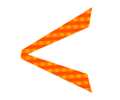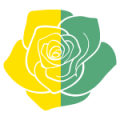<< 1:00~2:00




意識が散漫になる。
数百の人間が叫び、逃げ惑っている様な。
無数の声が阿鼻叫喚の如く余の頭の中で木霊していた。
ああ、意識が。。。気を確かに持たなければ。
そう思考している筈なのに、何処か夢を見ている様な浮遊感が抜けない。
こんな思考に没頭してる暇は無いのだ。余は、護らなければならないのだから。
・・・・・・誰を?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
その子供は両親と共に在った。
イルハザーク・オブリビエント。何故かこれが子供の名前だと余には分かった。
ある日、両親はとても幸せそうに子供を抱きしめ言った。
「生れて来てくれてありがとう」
子供は一瞬不思議そうな顔をしながらも、心から嬉しそうに笑った。
そこで余は理解した。ああ、この子供は生まれて初めて親からの愛されたのだと。
そして同時に理解する。彼らは、今から子供を売るのだと。
子供は複数の男に手を引かれ両親の元を後にした。
子供は振り返った。しかし既に両親の姿は無く
子供は、生涯両親と再会する事は無かった。

子供は特異な体質をしていた。透き通る程に白い髪、そして同様に白く陶器の様に滑らかな肌。
宝石の様に紅い瞳に体内に複数の遺伝子を所有していたのだ。
それ故に彼とその親は、生きる事に必死だった。
子供もそれらを心得ていたので、両親の事は「二人が幸せに生きてくれているのならそれで良い」
心からそう思っていた。
男達は子供の心の清らかさに「ああ、やはり我らの神だ」と囃し立てもてなした。
そこは、所謂カルト教団の施設だった。教団には信仰が有り、崇拝する対象が在る。
男達は子供の特異な体質と色素を持たない美しい容姿から、子供に自分達の神を見出したのだった。
子供は最初数人の同年代の子供達と同じ空間で過ごした。
子供達は子供の容姿に臆する事無く、仲間として迎え入れた。
子供はその束の間本来の年頃の子の様に笑い、駆け回り、毎日を楽しんだ。
しかし暫くして、子供達は姿を消した。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・・・・・・・・・・・・・・・・・。
・・・・・・・・・・。
・・・・。
余は、何を見ていた?
現在行動を共にしている仲間、結乃に手当を施しながら唇を噛み締める。
恐らくは自身に関わりの有る人間の記憶か虚妄だろう。
長い間意識が混濁していた為、正直今の自分には何が記憶で何が虚妄なのか判別が出来なかった。
しかし目の前に居る仲間とこの状況は真実であり現実なのだ。呆けている場合ではない。
幸い結乃は致命傷という傷でも無く、自分達は勝利を収める事が出来た。しかし・・・
今回余は同郷の者。つまりはアンジニティ、侵略者と対峙する事となった。
事前に知っていた事では有るし、相応の覚悟を決めてこの場に立った。
今でもそれに相違ない。
しかし、それでも。余は彼らを前にし、その考えに触れ、共感してしまった。
共感してしまったのだ。
混在した記憶の根底に有る感情。
もっと生きたかった。
もっと楽しい記憶を、生きた証を刻みたかった。
取り戻せるものならば取り戻したい。
生きる事が許される世界が有るのなら、自分もそこで当たり前の生を享受したい。
しかし、それは出来ない。してはならない。
アンジニティに堕ちた者は最早本来の“人”では無いのだ。
どれだけ悲壮な死を遂げた者でも、どれだけ理不尽な生の果てに迫害された者だとしても。
今現在“人”として在る目前の彼らの、当たり前に訪れるはずの日々を踏み台にして良いという
免罪符に成り得はしないのだ。決して。
今回の決闘で恐らく彼らは余の想像に及ばない辛い選択をした事だろう。
護ると決め、その様に動き結果仲間の友に止め一撃を見舞ったのは余だ。
これで良かったのかと問われると、分からない。
守護者と言うには些か空虚であるが、それでも余は彼らをこの力有る限り護らねばと思う。
ただの道理や情としてだけでは無く、それが余自身の為であると感じたからだ。
何故なのか、それがどうしてなのか、余自身が分かりはしない現状ではあるが
これは余自身が生きた証を残す為の戦でも有るのだと、そう強く感じた。



ENo.612 チホ とのやりとり

ENo.664 レウ・コンアス とのやりとり













チホ(612) から 10 PS 受け取りました。
魔術LV を 5 UP!(LV5⇒10、-5CP)
武器LV を 5 UP!(LV25⇒30、-5CP)
チホ(612) の持つ ItemNo.8 毛 から射程1の武器『あんしんスタンガン』を作製しました!
晴(428) により ItemNo.8 花びら から防具『紅い腰帯』を作製してもらいました!
⇒ 紅い腰帯/防具:強さ40/[効果1]舞魅10 [効果2]- [効果3]-
産姫(885) とカードを交換しました!
花より団子 (ヒール)


デストロイ を研究しました!(深度0⇒1)
デストロイ を研究しました!(深度1⇒2)
デストロイ を研究しました!(深度2⇒3)
ファイアボルト を習得!
デストロイ を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



泥蘇光悪渡(150) は 韮 を入手!
イルハ(324) は 花びら を入手!
ユイノ(388) は 韮 を入手!
晴(428) は 白石 を入手!
ユイノ(388) は 不思議な雫 を入手!
泥蘇光悪渡(150) は 不思議な雫 を入手!
泥蘇光悪渡(150) は 毛 を入手!
イルハ(324) は 毛 を入手!



ユイノ(388) に移動を委ねました。
チナミ区 E-13(草原)に移動!(体調21⇒20)
チナミ区 F-13(山岳)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 G-13(山岳)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 H-13(草原)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 I-13(道路)に移動!(体調17⇒16)






―― ハザマ時間が紡がれる。

ため息をつく。
Cross+Roseにロスト7名の容姿と簡単なプロフィールが映し出される。







大きな打撃音と泣き声と共に、チャットが閉じられる――


























































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



意識が散漫になる。
数百の人間が叫び、逃げ惑っている様な。
無数の声が阿鼻叫喚の如く余の頭の中で木霊していた。
ああ、意識が。。。気を確かに持たなければ。
そう思考している筈なのに、何処か夢を見ている様な浮遊感が抜けない。
こんな思考に没頭してる暇は無いのだ。余は、護らなければならないのだから。
・・・・・・誰を?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
その子供は両親と共に在った。
ある日、両親はとても幸せそうに子供を抱きしめ言った。
「生れて来てくれてありがとう」
子供は一瞬不思議そうな顔をしながらも、心から嬉しそうに笑った。
そこで余は理解した。ああ、この子供は生まれて初めて親からの愛されたのだと。
そして同時に理解する。彼らは、今から子供を売るのだと。
子供は複数の男に手を引かれ両親の元を後にした。
子供は振り返った。しかし既に両親の姿は無く
子供は、生涯両親と再会する事は無かった。

子供は特異な体質をしていた。透き通る程に白い髪、そして同様に白く陶器の様に滑らかな肌。
宝石の様に紅い瞳に体内に複数の遺伝子を所有していたのだ。
それ故に彼とその親は、生きる事に必死だった。
子供もそれらを心得ていたので、両親の事は「二人が幸せに生きてくれているのならそれで良い」
心からそう思っていた。
男達は子供の心の清らかさに「ああ、やはり我らの神だ」と囃し立てもてなした。
そこは、所謂カルト教団の施設だった。教団には信仰が有り、崇拝する対象が在る。
男達は子供の特異な体質と色素を持たない美しい容姿から、子供に自分達の神を見出したのだった。
子供は最初数人の同年代の子供達と同じ空間で過ごした。
子供達は子供の容姿に臆する事無く、仲間として迎え入れた。
子供はその束の間本来の年頃の子の様に笑い、駆け回り、毎日を楽しんだ。
しかし暫くして、子供達は姿を消した。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・・・・・・・・・・・・・・・・・。
・・・・・・・・・・。
・・・・。
余は、何を見ていた?
現在行動を共にしている仲間、結乃に手当を施しながら唇を噛み締める。
恐らくは自身に関わりの有る人間の記憶か虚妄だろう。
長い間意識が混濁していた為、正直今の自分には何が記憶で何が虚妄なのか判別が出来なかった。
しかし目の前に居る仲間とこの状況は真実であり現実なのだ。呆けている場合ではない。
幸い結乃は致命傷という傷でも無く、自分達は勝利を収める事が出来た。しかし・・・
今回余は同郷の者。つまりはアンジニティ、侵略者と対峙する事となった。
事前に知っていた事では有るし、相応の覚悟を決めてこの場に立った。
今でもそれに相違ない。
しかし、それでも。余は彼らを前にし、その考えに触れ、共感してしまった。
共感してしまったのだ。
混在した記憶の根底に有る感情。
もっと生きたかった。
もっと楽しい記憶を、生きた証を刻みたかった。
取り戻せるものならば取り戻したい。
生きる事が許される世界が有るのなら、自分もそこで当たり前の生を享受したい。
しかし、それは出来ない。してはならない。
アンジニティに堕ちた者は最早本来の“人”では無いのだ。
どれだけ悲壮な死を遂げた者でも、どれだけ理不尽な生の果てに迫害された者だとしても。
今現在“人”として在る目前の彼らの、当たり前に訪れるはずの日々を踏み台にして良いという
免罪符に成り得はしないのだ。決して。
今回の決闘で恐らく彼らは余の想像に及ばない辛い選択をした事だろう。
護ると決め、その様に動き結果仲間の友に止め一撃を見舞ったのは余だ。
これで良かったのかと問われると、分からない。
守護者と言うには些か空虚であるが、それでも余は彼らをこの力有る限り護らねばと思う。
ただの道理や情としてだけでは無く、それが余自身の為であると感じたからだ。
何故なのか、それがどうしてなのか、余自身が分かりはしない現状ではあるが
これは余自身が生きた証を残す為の戦でも有るのだと、そう強く感じた。



ENo.612 チホ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.664 レウ・コンアス とのやりとり
| ▲ |
| ||||



| 泥蘇光悪渡 「岬、伊藤君、イーサン。 俺もやっと覚悟決めたぜ。」 |
| 泥蘇光悪渡 「俺にはコレしか脳がねェ… なら」 |
| 泥蘇光悪渡 「ヤる事ァ最初から決まってンだ!!」 |
| 泥蘇光悪渡 「俺の名前は外道ヒーロー『泥蘇光悪渡・悪漢(ディスコード・バッドガイ)』 回復上等!!! テメェらの命全力で預かってやるぜ!!!」 |
 |
(ガーゼだったり、ぐるぐる巻きの白い布だったり。 ……それらのほとんどは寒さを凌ぐための厚い生地の下に隠れて見えない。 かろうじてスカートとハイソックスの間の肌に貼られた絆創膏が目立つくらいだ。) |
 |
結乃 「お待たせぇ~。アゲハくんが作ってくれた唐揚げのおかげで、 ケガしたとこもあっという間に治ってばっちり元気だよぅ~」 ――それはまるで、遊びに出掛ける待ち合わせに合流したときのような朗らかな笑顔で。 |
 |
晴 「ごめん。離れてしまって。/1/もう大丈夫だからさ!みんなでアンジニティどうにかしようぜ!!」 |





【問】iまでの距離を求めよ
|
 |
TeamNo.322
|



チホ(612) から 10 PS 受け取りました。
 |
チホ 「スタンガン、あざまーす!コレ、お礼っす!」 |
魔術LV を 5 UP!(LV5⇒10、-5CP)
武器LV を 5 UP!(LV25⇒30、-5CP)
チホ(612) の持つ ItemNo.8 毛 から射程1の武器『あんしんスタンガン』を作製しました!
晴(428) により ItemNo.8 花びら から防具『紅い腰帯』を作製してもらいました!
⇒ 紅い腰帯/防具:強さ40/[効果1]舞魅10 [効果2]- [効果3]-
 |
晴 「イーサンならほんとこういうの似合いそうだよな。」 |
産姫(885) とカードを交換しました!
花より団子 (ヒール)


デストロイ を研究しました!(深度0⇒1)
デストロイ を研究しました!(深度1⇒2)
デストロイ を研究しました!(深度2⇒3)
ファイアボルト を習得!
デストロイ を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



泥蘇光悪渡(150) は 韮 を入手!
イルハ(324) は 花びら を入手!
ユイノ(388) は 韮 を入手!
晴(428) は 白石 を入手!
ユイノ(388) は 不思議な雫 を入手!
泥蘇光悪渡(150) は 不思議な雫 を入手!
泥蘇光悪渡(150) は 毛 を入手!
イルハ(324) は 毛 を入手!



ユイノ(388) に移動を委ねました。
チナミ区 E-13(草原)に移動!(体調21⇒20)
チナミ区 F-13(山岳)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 G-13(山岳)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 H-13(草原)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 I-13(道路)に移動!(体調17⇒16)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
ノウレット 「またまたこんにちは―――ッ!!」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
 |
白南海 「・・・っつぅ・・・・・また貴方ですか・・・ ・・・耳が痛くなるんでフリップにでも書いてくれませんかねぇ。」 |
 |
ノウレット 「はぁい!イヤですッ!!」 |
 |
白南海 「Yesなのか、Noなのか・・・」 |
ため息をつく。
 |
白南海 「それで、自己紹介の次は何用です?」 |
 |
ノウレット 「はぁい!今回はロストに関する情報を持ってきましたよーッ!!」 |
 |
白南海 「おぉそれは感心ですね、イルカよりは性能良さそうです。褒めてあげましょう。」 |
 |
ノウレット 「やったぁぁ―――ッ!!!!」 |
 |
白南海 「だから大声やめろおぉぉぉクソ妖精ッッ!!!」 |
 |
ノウレット 「早速ですが・・・・・ジャーンッ!!こちらがロスト情報ですよー!!!!」 |
Cross+Roseにロスト7名の容姿と簡単なプロフィールが映し出される。

アンドリュウ
紫の瞳、金髪ドレッドヘア。
体格の良い気さくなお兄さん。
料理好き、エプロン姿が何か似合っている。
体格の良い気さくなお兄さん。
料理好き、エプロン姿が何か似合っている。

ロジエッタ
水色の瞳、菫色の長髪。
大人しそうな小さな女の子。
黒いドレスを身につけ、男の子の人形を大事そうに抱えている。
大人しそうな小さな女の子。
黒いドレスを身につけ、男の子の人形を大事そうに抱えている。

アルメシア
金の瞳、白い短髪。褐色肌。
戦闘狂で活動的な少女。
鎧を身につけハルバードを持っている。
戦闘狂で活動的な少女。
鎧を身につけハルバードを持っている。

ソージロウ
黒い瞳、黒いもじゃもじゃ頭。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。

フレディオ
碧眼、ロマンスグレーの短髪。
彫りが深く、男前な老翁。
黒のライダースジャケットを身に着けている。
彫りが深く、男前な老翁。
黒のライダースジャケットを身に着けている。

ミヨチン
茶色の瞳、桜色のロング巻き髪。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。

マッドスマイル
乱れた長い黒緑色の髪。
両手に紅いナイフを持ち、
猟奇的な笑顔の仮面をつけている。
両手に紅いナイフを持ち、
猟奇的な笑顔の仮面をつけている。
 |
白南海 「ほぅほぅ、みな人間・・・のような容姿ですね。ハザマの様子的に意外なようでもあり。 彼らの願望を叶えると影響力が上がり、ハザマでの力も高めてくれる・・・と。」 |
 |
白南海 「どんな願望なのやら、無茶振りされないといいんですが。 ロストに若がいたならどんな願望もソッコーで叶えに行きますがね!」 |
 |
ノウレット 「ワカは居ませんよ?」 |
 |
白南海 「・・・わかってますよ。」 |
 |
白南海 「ところで情報はこれだけっすか?クソ妖精。」 |
 |
ノウレット 「あだ名で呼ぶとか・・・・・まだ早いと思います。出会ったばかりですし私たち。」 |
 |
白南海 「ねぇーんですね。居場所くらい持ってくるもんかと。」 |
 |
白南海 「ちなみに、ロストってのは何者なんで? これもハザマのシステムって解釈でいいのかね。」 |
 |
ノウレット 「ごめんなさい!私はCross+Roseの妖精なのでハザマのことはよくわかりません!! Cross+Roseに送られた情報を伝えることしか・・・・・」 |
 |
白南海 「・・・まぁそーか。仕方ないが、どうも断片的っすねぇ。」 |
 |
白南海 「そんじゃ、チェックポイントを目指しがてらロスト探しもしていきましょうかね。」 |
 |
ノウレット 「レッツゴォォ―――ッ!!!!」 |
大きな打撃音と泣き声と共に、チャットが閉じられる――







ヒーローと愉快な仲間たち~オバケもいるよ~
|
 |
神も仏もあるもんか
|


ENo.324
イーサン/イーちゃん



姫神イーサン(姫園でも可)
つい最近まで親戚の苗字を間違って使ってたので引っ込みがつかなくなってる所有る思春期男子。
名前で呼ぶと喜ぶぞ!イーさんでも良いらしい。
「余は美しく、そして愛らしいのだ!!!」
身長177cm(ヒール込み+15cm) 体型:筋肉質
一人称:余 二人称:お前、貴様
好きな物:肉、食べ放題、ジャンクフード、お洒落
嫌いな物:質素な食べ物、地味な物、小賢しい奴
イバラ所属のアンジ。
ハザマでは多腕に6枚羽根を有する巨躯な怪人だが比較的理知的。
戦闘時は反転目になる。羽根と腕は収納可。
顔だけ見ると美少女。しかし低音イケメンボイスの持ち主。
そして声がめっちゃデカい。
背格好からよく年長者に間違われるが、満更でも無い様子。
自己肯定感ゴリラなナルシスト。
普段は自信満々の振る舞いを見せるが、実の所割とポンコツ。
しかし本人はそれもまた個性なのだと気にしていない。
双子の妹にだけは頭が上がらず、塩対応に凹む様子も見られる。
養父母の元で暮らしており、姫園の性も引き取られてから名乗っている。が、実は姫神だった。姫園は分家の名前。良い所のおぼっちゃま。
仲は良好で、家の中では年相応な素直さを見せたり見せなかったり。
一転妹は絶賛反抗期中で、余り家に帰らない為イーサンがよく探しに出掛けたりもしている。
つい最近まで親戚の苗字を間違って使ってたので引っ込みがつかなくなってる所有る思春期男子。
名前で呼ぶと喜ぶぞ!イーさんでも良いらしい。
「余は美しく、そして愛らしいのだ!!!」
身長177cm(ヒール込み+15cm) 体型:筋肉質
一人称:余 二人称:お前、貴様
好きな物:肉、食べ放題、ジャンクフード、お洒落
嫌いな物:質素な食べ物、地味な物、小賢しい奴
イバラ所属のアンジ。
ハザマでは多腕に6枚羽根を有する巨躯な怪人だが比較的理知的。
戦闘時は反転目になる。羽根と腕は収納可。
顔だけ見ると美少女。しかし低音イケメンボイスの持ち主。
そして声がめっちゃデカい。
背格好からよく年長者に間違われるが、満更でも無い様子。
自己肯定感ゴリラなナルシスト。
普段は自信満々の振る舞いを見せるが、実の所割とポンコツ。
しかし本人はそれもまた個性なのだと気にしていない。
双子の妹にだけは頭が上がらず、塩対応に凹む様子も見られる。
養父母の元で暮らしており、姫園の性も引き取られてから名乗っている。が、実は姫神だった。姫園は分家の名前。良い所のおぼっちゃま。
仲は良好で、家の中では年相応な素直さを見せたり見せなかったり。
一転妹は絶賛反抗期中で、余り家に帰らない為イーサンがよく探しに出掛けたりもしている。
16 / 30
91 PS
チナミ区
I-13
I-13






































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | goddamn finger | 武器 | 30 | 攻撃10 | - | - | 【射程1】 |
| 5 | 金の首飾り | 装飾 | 30 | 幸運10 | - | - | |
| 6 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 8 | 紅い腰帯 | 防具 | 40 | 舞魅10 | - | - | |
| 9 | 美味しい果実 | 食材 | 15 | [効果1]攻撃10(LV10)[効果2]防御10(LV15)[効果3]強靭15(LV25) | |||
| 10 | 不思議な雫 | 素材 | 10 | [武器]水纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV10)[装飾]耐水10(LV20) | |||
| 11 | 花びら | 素材 | 10 | [武器]混乱10(LV25)[防具]舞魅10(LV10)[装飾]祝福10(LV20) | |||
| 12 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 15 | 身体/武器/物理 |
| 魔術 | 10 | 破壊/詠唱/火 |
| 制約 | 5 | 拘束/罠/リスク |
| 武器 | 30 | 武器作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| 練3 | ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 |
| ティンダー | 5 | 0 | 50 | 敵:火撃&炎上 | |
| アサルト | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃+自:連続減 | |
| レッドショック | 5 | 0 | 80 | 敵:3連鎖火撃 | |
| 練3 | デアデビル | 5 | 0 | 60 | 自:HP減+敵傷4:痛撃 |
| アリア | 5 | 2 | 0 | 自:SP・次与ダメ増 | |
| 練3 | チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 |
| ファイアボルト | 5 | 0 | 100 | 敵貫:火痛撃 | |
| デストロイ | 5 | 0 | 100 | 敵:守護減+火痛撃 | |
| 練3 | イレイザー | 5 | 0 | 100 | 敵傷:攻撃 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 |
最大EP[20]





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]ガードフォーム | [ 1 ]アリア | [ 1 ]スコーピオン |
| [ 3 ]デストロイ |

PL / 大介