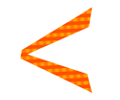<< 0:00~1:00





かつて、人は海を畏れていた。
嵐や高波は海の怒りであり、海沿いの町で頻発する水難事故は海の怪異の仕業であった。
言い伝えが骨となり、人々の畏怖が肉となり、幻想が形を成して海を跋扈していた、今は失われた時代。
そんな怪異のひとつ、馬の姿で人を誘い、海中に引き込んで喰い殺す魔物。
それが俺だった。仲間もたくさんいた。
人の肉が大好物だった。そう言い伝えられていたから。
内臓だけは受け付けず、水面に放り出すのが常だった。そう噂されていたから。
怪異にとっての死とは、忘れ去られること。語られなくなること。畏れられなくなること。
人が知恵をつける度に、あれだけいた同胞達は一頭、また一頭と姿を消していった。
ある者は馬の頭に似た奇妙な形の岩に。
ある者は足を取られやすい藻の茂みに。
人の言葉で説明がつくような何か。
最早怪異でも何でもない、何の変哲もないありふれた事物に貶められて、彼等は消えた。
俺は長く暮らした海辺を捨てて、人が船の墓場と呼ぶ難所、魔の海域と呼ばれる海へ泳いでいった。
未だ船乗り達が様々な魔除けやまじないを携えて航海に臨む、海の秘境。
そこにはまだ神秘があった。畏怖があった。
語られる幻想。囁かれる遭難譚。
そこにはまだ、怪異の生きる余地があった。
……最後に船を沈めたのは、いつだったろうか。
この揺蕩い絡む鬣で船足を止め、波濤と蹄でマストを叩き折ったのは。
震え慄く船乗り達を昏い海に引きずり込み、この歯で柔らかい肉を裂いたのは。
――それから数世紀が経ち。
遂に、世界中の海域は開拓され尽くした。
船の墓場も、魔の海域も、攻略法を見出した人間達にとっては最早畏れの対象ではなくなった。
俺は深い深い海の底、知の光を以てなお照らされぬ暗がりに逃げ込むしかなかった。
もう海に引きずり込まれる船はない。
美しい人魚の歌に惑わされる船乗りも、海辺に佇む人慣れした馬に騙される子供もいない。
巨大なウミユリや奇妙な鰭を持つ魚、単眼の鮫。そういった深海の神秘の残滓に囲まれて、ただ故郷の海辺と肉の味を懐かしみながら微睡むだけの日々。
首をもたげて僅かな光の差す水面を睨みつけるだけの気力も、最後には失せていたが。
それでも俺はただ、そこに存在していた。
――消えたくなかった。
ある日、いつものように光の届かぬ澱みを漂っていた俺の身体に、人間の髪のような細いものが絡みついた。袋のように俺を包んだそれはどんどん上へと昇ってゆき、俺は巻き込まれた深海魚達と共に為す術なく海面へと引き上げられていった。
そして俺は、気がついてしまった。
脚も首も、耳の片方ですら、視線のひとつでさえも。
自分の意思で何一つ動かすことができなくなっているということに。
潮の流れに揺蕩っていた鬣も固められたように体に張りつき、薄っぺらい青緑や赤褐色のひらひらしたものが体中に絡みついている。
――ああ。
「こりゃあ大物だぞ」
声がした。
俺は袋状のものごと海面を突き破り、どうやら空気の中にいるらしかった。
飛び出した単眼を晒して事切れた鮫が、袋の隙間から落ちていった。ぼたぼたと水を垂らす俺の下で、慌ただしく何人かの人間が動き回っている。
そのうちの一人が俺を見上げて、隣の人間に言った。
「馬鹿、よく見ろ。どっかの見世物小屋か、廃業した遊園地から流れてきたんだろ。全く脅かしやがる」
男達が見上げる先、吊るされた網の中には。
大量の海藻が絡まった、大きな古い回転木馬があった。
長い間海に漬かっていたような色をした馬は、木彫りの歯で口惜しげに海藻を噛んでいた。
――斯くして。
俺という"怪異"は、世界から"否定"された。



ENo.93 Eva とのやりとり

ENo.273 闇 とのやりとり

以下の相手に送信しました




ItemNo.6 不思議な食材 を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(25⇒26)
今回の全戦闘において 器用10 が発揮されます。








領域LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
具現LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
防具LV を 5 UP!(LV20⇒25、-5CP)
九郎(357) とカードを交換しました!
とある新聞 (カース)

マナポーション を研究しました!(深度0⇒1)
マナポーション を研究しました!(深度1⇒2)
マナポーション を研究しました!(深度2⇒3)
クリエイト:タライ を習得!
クリエイト:シールド を習得!
アクアシェル を習得!
クリエイト:スパイク を習得!
召喚強化 を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





チナミ区 D-10(道路)に移動!(体調26⇒25)
チナミ区 D-11(草原)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 D-12(草原)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 D-13(草原)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 E-13(草原)に移動!(体調22⇒21)






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。
そう言ってフロントダブルバイセップス。
・・・姿を現すことなく、女性のような声が伝わる。
ため息のような音が漏れる。
声はそこで終わる。
チャットが閉じられる――


























































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [スキル]OK.




アハ・イシュケ
馬のかたちをした海の魔物。
人慣れした美しい馬の姿で現れるが、本性は獰猛な捕食者である。
人慣れした美しい馬の姿で現れるが、本性は獰猛な捕食者である。
かつて、人は海を畏れていた。
嵐や高波は海の怒りであり、海沿いの町で頻発する水難事故は海の怪異の仕業であった。
言い伝えが骨となり、人々の畏怖が肉となり、幻想が形を成して海を跋扈していた、今は失われた時代。
そんな怪異のひとつ、馬の姿で人を誘い、海中に引き込んで喰い殺す魔物。
それが俺だった。仲間もたくさんいた。
人の肉が大好物だった。そう言い伝えられていたから。
内臓だけは受け付けず、水面に放り出すのが常だった。そう噂されていたから。
怪異にとっての死とは、忘れ去られること。語られなくなること。畏れられなくなること。
人が知恵をつける度に、あれだけいた同胞達は一頭、また一頭と姿を消していった。
ある者は馬の頭に似た奇妙な形の岩に。
ある者は足を取られやすい藻の茂みに。
人の言葉で説明がつくような何か。
最早怪異でも何でもない、何の変哲もないありふれた事物に貶められて、彼等は消えた。
俺は長く暮らした海辺を捨てて、人が船の墓場と呼ぶ難所、魔の海域と呼ばれる海へ泳いでいった。
未だ船乗り達が様々な魔除けやまじないを携えて航海に臨む、海の秘境。
そこにはまだ神秘があった。畏怖があった。
語られる幻想。囁かれる遭難譚。
そこにはまだ、怪異の生きる余地があった。
……最後に船を沈めたのは、いつだったろうか。
この揺蕩い絡む鬣で船足を止め、波濤と蹄でマストを叩き折ったのは。
震え慄く船乗り達を昏い海に引きずり込み、この歯で柔らかい肉を裂いたのは。
――それから数世紀が経ち。
遂に、世界中の海域は開拓され尽くした。
船の墓場も、魔の海域も、攻略法を見出した人間達にとっては最早畏れの対象ではなくなった。
俺は深い深い海の底、知の光を以てなお照らされぬ暗がりに逃げ込むしかなかった。
もう海に引きずり込まれる船はない。
美しい人魚の歌に惑わされる船乗りも、海辺に佇む人慣れした馬に騙される子供もいない。
巨大なウミユリや奇妙な鰭を持つ魚、単眼の鮫。そういった深海の神秘の残滓に囲まれて、ただ故郷の海辺と肉の味を懐かしみながら微睡むだけの日々。
首をもたげて僅かな光の差す水面を睨みつけるだけの気力も、最後には失せていたが。
それでも俺はただ、そこに存在していた。
――消えたくなかった。
ある日、いつものように光の届かぬ澱みを漂っていた俺の身体に、人間の髪のような細いものが絡みついた。袋のように俺を包んだそれはどんどん上へと昇ってゆき、俺は巻き込まれた深海魚達と共に為す術なく海面へと引き上げられていった。
そして俺は、気がついてしまった。
脚も首も、耳の片方ですら、視線のひとつでさえも。
自分の意思で何一つ動かすことができなくなっているということに。
潮の流れに揺蕩っていた鬣も固められたように体に張りつき、薄っぺらい青緑や赤褐色のひらひらしたものが体中に絡みついている。
――ああ。
「こりゃあ大物だぞ」
声がした。
俺は袋状のものごと海面を突き破り、どうやら空気の中にいるらしかった。
飛び出した単眼を晒して事切れた鮫が、袋の隙間から落ちていった。ぼたぼたと水を垂らす俺の下で、慌ただしく何人かの人間が動き回っている。
そのうちの一人が俺を見上げて、隣の人間に言った。
「馬鹿、よく見ろ。どっかの見世物小屋か、廃業した遊園地から流れてきたんだろ。全く脅かしやがる」
男達が見上げる先、吊るされた網の中には。
大量の海藻が絡まった、大きな古い回転木馬があった。
長い間海に漬かっていたような色をした馬は、木彫りの歯で口惜しげに海藻を噛んでいた。
――斯くして。
俺という"怪異"は、世界から"否定"された。



ENo.93 Eva とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.273 闇 とのやりとり
| ▲ |
| ||||||
以下の相手に送信しました



 |
タウラシアス 「俺の邪魔をするなよ?」 |
| ナックラヴィ― 「撒いた? くく、そう簡単に置いていってもらっては困るな。 今度ともよろしく、"安藤さん"……ああいや、こう呼ぶんだったな。タウラシアス」 |
ItemNo.6 不思議な食材 を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(25⇒26)
今回の全戦闘において 器用10 が発揮されます。







領域LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
具現LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
防具LV を 5 UP!(LV20⇒25、-5CP)
九郎(357) とカードを交換しました!
とある新聞 (カース)

マナポーション を研究しました!(深度0⇒1)
マナポーション を研究しました!(深度1⇒2)
マナポーション を研究しました!(深度2⇒3)
クリエイト:タライ を習得!
クリエイト:シールド を習得!
アクアシェル を習得!
クリエイト:スパイク を習得!
召喚強化 を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





チナミ区 D-10(道路)に移動!(体調26⇒25)
チナミ区 D-11(草原)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 D-12(草原)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 D-13(草原)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 E-13(草原)に移動!(体調22⇒21)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
「おっくれまして―――ッ!!」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
 |
ノウレット 「はぁい!はじめましてーッ!!私はここCross+Roseの管・・・妖精! ノウレットでーっす!!皆さんよろしくおねがいしまぁーっす!!」 |
チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。
 |
エディアン 「初めまして初めまして! 私はエディアンといいます、便利な機能をありがとうございます!」 |
 |
ノウレット 「わぁい!どーいたしましてーっ!!」 |
 |
エディアン 「ノウレットさんもドライバーさんと同じ、ハザマを司る方なんですね。」 |
 |
ノウレット 「司る!なんかそれかっこいいですね!!そうです!司ってますよぉ!!」 |
 |
ノウレット 「Cross+Roseのことで分からないことは何でも聞いてくださいねーっ!!」 |
 |
エディアン 「仄暗いハザマの中でマスコットみたいな方に会えて、何だか和みます! ワールドスワップの能力者はマスコットまで創るんですねー。」 |
 |
ノウレット 「マスコット!妖精ですけどマスコットもいいですねぇーっ!! エディアンさんは言葉の天才ですか!?すごい!すごい!!」 |
そう言ってフロントダブルバイセップス。
 |
ノウレット 「えーっとそれでですねーッ!!」 |
 |
ノウレット 「・・・・・あれっ 創造主さまからメッセージが!」 |
 |
エディアン 「むむむ、要チェックですね。」 |
・・・姿を現すことなく、女性のような声が伝わる。
 |
声 「――お疲れ様です御二方。役目を担ってくれて、感謝しています。」 |
 |
エディアン 「方法はどうあれ、こちらも機会を与えてくれて感謝していますよ?」 |
 |
声 「そしてハザマに招かれた方々、申し訳ありません。」 |
 |
声 「・・・・・・・・・」 |
 |
声 「このワールドスワップという能力は、招かれた方々全員が――ザザッ・・・」 |
 |
声 「――失われ、そう――ザザッ・・・――周期的に発動する、能力というより・・・」 |
 |
声 「制御不能な・・・呪いのよう。今までに発動した数度、自分への利は・・・ない。」 |
 |
声 「・・・・・・・・・」 |
ため息のような音が漏れる。
 |
声 「どうか、自らが自らであ―― ザザッ・・・」 |
 |
エディアン 「・・・・・雑音が酷いですねぇ。」 |
 |
声 「――ザザッ・・・・・・・・己の世界のために、争え。」 |
声はそこで終わる。
 |
エディアン 「ノウレットさん、何か通信おかしくないです?」 |
 |
ノウレット 「そうですかーっ!!?そうでもないですよーっ!!!?」 |
 |
エディアン 「むぅ。・・・大した情報は得られませんでしたね。」 |
 |
エディアン 「・・・さ、それじゃこの1時間も頑張っていきましょう!!」 |
チャットが閉じられる――









ENo.502
藻噛 叢馬



藻噛 叢馬(もがみ そうま)
一人称:俺
二人称:お前、君
25歳/身長190cm/体重85kg
創峰大学の院生。D1。
生物学専攻で、興味の対象は専ら海洋生物。斑目研究室に所属。
海の幻想譚や怪談に登場する生物に憧憬を抱いており、奇形や突然変異の海洋生物を蒐集している。研究に没頭して寝食を忘れがち。
大柄で表情に乏しいため周囲に威圧感を与えていることも儘あるようだが、本人はあまり気にしていない。
嫌いなものは馬肉とホルモン。
好きなものは上記以外の肉全般と酒(特にビールと麦焼酎)。
趣味は海水浴・潜水・遠泳。着衣水泳も難なくこなすが、真水・淡水では泳げない。
異能:"微睡む藻屑の幻想海"(ドリーミング・サルガッソー)
海水を粘度のある液体に変化させ、自在に操る。粘度はとろみがつく程度から人が上を歩ける程度まで調節可能。
ただし自分で水を発生させることはできず、かつ対象は海水でなければならないため、常に試験管に入れた海水を持ち歩いている。
『アンディの骨董屋』をよく訪れ、海で拾った漂着物を買い取ってもらったり荷運びを手伝ったりしている。
故あって懐事情はかなり寒い。
■ハザマでの姿
体高2m(耳の先までで約3m)/体重1t
海藻のように揺蕩う鬣を持ち、言葉巧みに人を海に引きずり込む蒼馬《アハ・イシュケ》。または、長い腕の膂力で暴れ回る、赤く剥けたような肌の半人半馬《ナックラヴィー》。
どちらも元の世界では忘れ去られた海に棲む水妖の一種であり、人を喰う怪異である。
全身図︰http://file.gespenst.en-grey.com/mogami_hazama.png
■サブキャラ
斑目 水緒(まだらめ みずお)
一人称:ぼく
二人称:君、あなた
47歳/身長168cm/体重56kg
創峰大学第二学部海洋生物学専攻斑目研究室のゆるふわ教授。
異能:"一滴の愛"(ラスト・ギフト)
生物由来の毒を無効化するらしいが、詳細は不明。
酒に強いのは異能とは特に関係がないようだ。
---
大曲 晴人(おおまが はるひと)
28歳/身長180cm/体重65kg
黒峰総研製薬部門営業部に所属する営業マン。
異能:"未観測運命理論・不在の黒猫"(シュレーディンガー・ブラックキャット)
詳細不明。
***
テストプレイの記憶を引き継いでいます。
テストプレイ時に交流のあった方にはそのように接しますが、不都合ありましたら連絡頂ければ訂正します。
現在プロフ絵2種。
ほぼほぼ置きレスですが交流歓迎です。お気軽にどうぞ!
■ログまとめプレイス『微睡む藻屑の幻想海』
http://lisge.com/ib/talk.php?p=757
■外部ログ置き場(テストプレイ時含)
http://niwatori.kuchinawa.com/dreaming_salgasso/index.html
■自重しないついった
@yaneura_coqua
一人称:俺
二人称:お前、君
25歳/身長190cm/体重85kg
創峰大学の院生。D1。
生物学専攻で、興味の対象は専ら海洋生物。斑目研究室に所属。
海の幻想譚や怪談に登場する生物に憧憬を抱いており、奇形や突然変異の海洋生物を蒐集している。研究に没頭して寝食を忘れがち。
大柄で表情に乏しいため周囲に威圧感を与えていることも儘あるようだが、本人はあまり気にしていない。
嫌いなものは馬肉とホルモン。
好きなものは上記以外の肉全般と酒(特にビールと麦焼酎)。
趣味は海水浴・潜水・遠泳。着衣水泳も難なくこなすが、真水・淡水では泳げない。
異能:"微睡む藻屑の幻想海"(ドリーミング・サルガッソー)
海水を粘度のある液体に変化させ、自在に操る。粘度はとろみがつく程度から人が上を歩ける程度まで調節可能。
ただし自分で水を発生させることはできず、かつ対象は海水でなければならないため、常に試験管に入れた海水を持ち歩いている。
『アンディの骨董屋』をよく訪れ、海で拾った漂着物を買い取ってもらったり荷運びを手伝ったりしている。
故あって懐事情はかなり寒い。
■ハザマでの姿
体高2m(耳の先までで約3m)/体重1t
海藻のように揺蕩う鬣を持ち、言葉巧みに人を海に引きずり込む蒼馬《アハ・イシュケ》。または、長い腕の膂力で暴れ回る、赤く剥けたような肌の半人半馬《ナックラヴィー》。
どちらも元の世界では忘れ去られた海に棲む水妖の一種であり、人を喰う怪異である。
全身図︰http://file.gespenst.en-grey.com/mogami_hazama.png
■サブキャラ
斑目 水緒(まだらめ みずお)
一人称:ぼく
二人称:君、あなた
47歳/身長168cm/体重56kg
創峰大学第二学部海洋生物学専攻斑目研究室のゆるふわ教授。
異能:"一滴の愛"(ラスト・ギフト)
生物由来の毒を無効化するらしいが、詳細は不明。
酒に強いのは異能とは特に関係がないようだ。
---
大曲 晴人(おおまが はるひと)
28歳/身長180cm/体重65kg
黒峰総研製薬部門営業部に所属する営業マン。
異能:"未観測運命理論・不在の黒猫"(シュレーディンガー・ブラックキャット)
詳細不明。
***
テストプレイの記憶を引き継いでいます。
テストプレイ時に交流のあった方にはそのように接しますが、不都合ありましたら連絡頂ければ訂正します。
現在プロフ絵2種。
ほぼほぼ置きレスですが交流歓迎です。お気軽にどうぞ!
■ログまとめプレイス『微睡む藻屑の幻想海』
http://lisge.com/ib/talk.php?p=757
■外部ログ置き場(テストプレイ時含)
http://niwatori.kuchinawa.com/dreaming_salgasso/index.html
■自重しないついった
@yaneura_coqua
21 / 30
37 PS
チナミ区
E-13
E-13




















| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 海棲馬の蹄 | 武器 | 30 | 攻撃10 | - | - | 【射程1】 |
| 5 | 幻想藻の鬣 | 防具 | 30 | 防御10 | - | - | |
| 6 | 花びら | 素材 | 10 | [武器]混乱10(LV25)[防具]舞魅10(LV10)[装飾]祝福10(LV20) | |||
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 8 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
| 9 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]防御10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 5 | 身体/武器/物理 |
| 命術 | 5 | 生命/復元/水 |
| 呪術 | 5 | 呪詛/邪気/闇 |
| 具現 | 10 | 創造/召喚 |
| 防具 | 25 | 防具作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 | |
| ウォーターフォール | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |
| カース | 5 | 0 | 50 | 敵:闇撃&束縛 | |
| 決1 | クリエイト:タライ | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 |
| リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |
| フロウライフ | 5 | 0 | 80 | 自:MHP・DF増 | |
| ブラックバンド | 5 | 0 | 80 | 敵貫:闇撃&盲目 | |
| クリエイト:シールド | 5 | 2 | 200 | 自:DF増+守護 | |
| コンテイン | 5 | 0 | 50 | 敵列:精確攻撃&次与ダメ減 | |
| ボロウライフ | 5 | 0 | 70 | 敵:闇撃&味傷:HP増 | |
| アクアシェル | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+火耐性増 | |
| ヘイルカード | 5 | 0 | 100 | 敵5:粗雑水領撃 | |
| クリエイト:スパイク | 5 | 0 | 60 | 敵貫:闇痛撃&衰弱 | |
| デッドライン | 5 | 0 | 100 | 敵列:闇痛撃 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 異形の膂力 (猛攻) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 否定への憤怒 (攻勢) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 召喚強化 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:具現LVが高いほど自身の召喚するNPCが強化 |
最大EP[20]





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]ノーマライズ | [ 3 ]マナポーション |

PL / こか