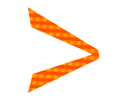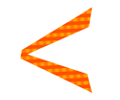<< 0:00~1:00




002.「Placebo」――もしくは、とうに効かない痛み止めについて
もし、耐えられないほどの痛みを味わったとして。
その痛みが物理的な痛みであれば、それを取り除く手段はいくらかある。
そのために現代医学は進歩してるのだろうし、骨折したときも、体調を崩したときも。
わかりやすく「痛み」は取り除くことができた。
歯の治療のときだって、麻酔をすればそこに痛みは感じずに済む。
だから、偏頭痛持ちの俺はいつも病院で処方されるよく効く頭痛薬を持ち歩いていたし、
それなしに日々を過ごすわけにはいかなかった。というよりも、過ごせなかった。
父親は「痛み止めがないと耐えられないようじゃいかん」と俺に強く当たったけど、
母親は「痛い思いを続けるよりはそっちのほうがずっといい」と微笑んだ。
俺は、どっちが正しいのかなんて少しもわからなかったけど、
痛みで何もできなくなるよりは、ずっと薬を頼るほうがいいと思っていた。
無理に耐えようとすれば、どうせトイレに駆け込んで胃の中身を戻すことになる。
それよりは、ずっとマシだ。俺は、今もそう思っている。
痛みというのは、目を向けるだけで惨めになる最悪の隣人だ。
どれだけ寂しくても、どれだけ孤独でも。そんな隣人は、誰も求めていないだろう。
――そんな隣人は、俺には必要ない。
「……はい。前も、処方されてて」
「なるほど。一条くんは……中学生の頃から偏頭痛がひどいわけだ。
苦労したろうね。今はどうかな。発作はどのくらいの頻度で起きてるのかな。
そうだね……、イバラシティに来てからどのくらい起きてるかを教えてくれればいい」
「……ひとつきに、大体二回あるかないか。吐くほどどうしようもないのは、そのくらいです」
「ふむ」と、初老の医者は頷く。
消毒薬の匂いのする白い診察室。申し訳程度に添えられた暖色の色味。
カタカタと音を立てて、汚れ一つない真っ白な白衣を羽織ってタイピングをする彼は、
書き割りのように「医者」という役割を務めているようで、なんだか退屈だった。
それに、どうにも病院は得意じゃなかった。
患者の目の前で電子カルテに打ち込んでいる文章が気になるか気にならないかといえば気になるし、
気になったところでそれを見たっていいことがないことはわかっている。
だから、意識的に視線をよそに向けなければいけないから余計居心地が悪い。
カルテはドイツ語で書く、なんて話は俺の知る「病院」という存在にはなかった。
日本語でそこには正直に自分の知らない自分のことが書いてあるのだと思うと、どうにも。
瞬にこの話をしたときは、瞬は笑っていた。「トータさんは偉いな~」なんていって。
……いや、偉いもなにもないだろ。なんか、盗み見してるみたいでちょっと、違うだろ。
確か、そんなことを言ったのを覚えている。
相手が伝えたくないことが書いてあったときにそれを見たあとに、同じ顔をできるかといえば、
決してそんなことはないだろうし、隠し事も嘘も苦手だったから見ないという選択をした。
別にそれだけの話で、自分がそういうところで大人になれないだけだと思っている。
だから、まあ。瞬が言ってるのが全部本気かなんてわかんないけど、
またきっとこれはからかわれているんだろうな、くらいにしか思わなかった。確かこれも中学の頃。
「前もらった薬は残ってるかな」
「残ってません」
医師は、不思議そうな顔をして首を傾げた。
そりゃそうだ。月に二回くらいしかひどい発作はないって言っているのに、
頓服薬がもう残っていない。矛盾する。逃げられないかと視線を彷徨わせてから、諦める。
「すいません、その、……ストレスで。
ちょっと痛んでも、ひどくなる前に飲んでおこう、って思っちゃって、ああ、でも。
効かないわけじゃなくて、全然。普通に効いてるし、痛みもひどくないしで、大丈夫です」
「一条くん」と、低い声がした。そりゃあそうだろう。
怒られて当然のことをやっているわけで、頓服薬を常飲していると聞いて怒らない医者はいない。
顔を上げて、返事をしようとしたところで医者がまた電子カルテを打ち始めたのを見て視線を逸らす。
何を書かれるかなんてだいたいわかっているけれど、それはそれとして見たくないものは見たくない。
だから、見ることはしない。
「どういう時に、『ちょっと痛む』かい」
「……?」
予想外の問いかけに、幾度か瞬いた。
てっきり、というよりも、この流れだったら怒られて当然だったろう。
俺は怒られると思ったから、謝る準備はしているつもりだった。でも、そうじゃなかった。
「え、えっと……」
口籠っても、医者は笑顔を浮かべたまま視線を合わせてくる。
何を言っても怒られないんじゃないか、と錯覚してしまうくらいには、なんだか。
自分の柔らかいところにすっと立ち入られたような気がした。
彼は、自分が何を言ったところで赦しを与えてくれるんじゃないかと思った。
だから。つい、口を滑らせて。
「色が」
「……色?」
口を押さえても遅かった。既にもう、自分の口からは言葉が落ちた。
だから、もう誤魔化したりすることもできない。
その時の感覚を思い出して、こめかみを強く押す。痛くない。それに、ここは病院だ。
目の前にいるのも医者。だから、痛くないはず。ここにはなにもない。ここは白い部屋だ。
「急にチカチカして、全部の色が極彩色に見えるっていうか、作った色と違う色に見えたり。
一瞬のはずなんですけど、なんか、全然一瞬じゃなくて。色々眩しくなっちゃって……。
デッサンとかしてると、急に距離感狂ったりとかして、わけわかんなくなっちゃって。
それで、それが、そうなるっていうか……。すいません、あの、上手く言えなくて」
医者は何も言わない。
黙って、カルテに何も打ち込まずにただただ目の前の患者のことを見ている。
口を挟むこともしない。だから、まだ話せ、ということなのかと思った。
「だから、いつこうなるかわかんなくて、まあ、結構ストレスで。
画面がぐにゃっとするっていうか、貧血かなんかだと思うんですけど。
三時間くらいかと思ってるんですけど、実際には十五分くらいだったりして……」
「前の病院でそういう話は先生にしたかい?」
「……いや、その、してないです。こんな、頭おかしいこと言って親に迷惑掛けたくないし」
「一条くん」
肩を掴まれた。自分よりずっと年上の、目尻と口元に皺の目立つ男。
書き割りに見えていたはずの、退屈でなんでもなかったはずの医者。ベージュの肌。
マルスブラウンとバーントシェンナの間の子みたいな色の目が、じっと見つめてくる。
視界の端にはベールコンポーゼとミストグリーンに近いカーテンの色がちらつく。
チタニウムジンクホワイトで整えたみたいな色をグレーズっぽく誂えた無機質な病室。
壁には申し訳程度のピンクベージュがドライブラシで軽く擦ったみたいに置かれている。
そう、――そう! この、頭の奥が弾けるような感覚!
一気に汗が噴き出して、足の指先が冷たくなって、肩のあたりがぞわりとする、この!!
この、全部が見えた瞬間みたいな、どれがどうやって描かれてるのかがわかったような!
そっくりそのまま、同じものを「描ける」と確信するこの「感じ」が、そう。
これが、そう。こうやって、世界を「捉え直し」て、「組み直す」、この!!
「――一条くん!! 一条くん、大丈夫かい。聞こえてるかい。
運ぶぞ! そこの担架持って! そっち側……頭は最大限動かさないように、……」
そう思ったときには、もう、意識はそこになかった。
異能診断科:所感(当人には内科と説明)
日常の風景、イメージを組み合わせて、現実と人工が交錯して造り出されるものが彼の絵だ。
現実の風景を「切り取る」虚構の画は、いつしか生々しい現実感を手に入れることができる。
虚構と現実の境界すら曖昧になり、現実も虚構と大差がなくなってしまう。
絵を描けば描くほど、そこに存在していた「光、形、触感、匂い、距離感」といった、
そこにあったはずの現実を一つの虚構に閉じ込めてしまう。
カメラといった「誰かの目」を使うのではなく、自分の見たままの「現実」を切り取る異能は、
そこにあったはずの現実を虚構に貶め、特有の離人感を発生させる。
追記: 彼の絵を見ても第三者が彼ほど心を動かすことはない。
彼の描く絵は、彼の見ている現実そのものと言えるだろう。
俺が、こうしてぼんやりと世界をマスキングして見ている分には痛み止めは要らない。
ただ、それを正確に、正しく、そこにあるものを正確に理解したいのであれば。
その覆いを外して、俺の目で世界を見る必要がある。
そのためには対価がいることもわかるし、だからこそ、それを誰かが代わりに担ってくれるなら。
ありがたいことに、医学は痛み止めを発明できた。
俺の「ほんとうの」症状を解決する処方箋はまだ存在しなくても、慰めにはなる。
だから、これがある限りは絵を描ける。鮮やかすぎるこの世界で生きていける。
だから、隣人を今日も殺して、見ないふりをして。
こうでもしないと、俺が。
世界に存在していたという爪痕を、どこにも残せない。
絵を描けない俺に、価値なんてないんだから。
――筆を。
――薬を。
願うならば、どうか、
赦しを。



ENo.720 瞬 とのやりとり




ItemNo.6 不思議な食材 を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(25⇒26)
今回の全戦闘において 器用10 が発揮されます。








制約LV を 5 UP!(LV10⇒15、-5CP)
杉乃(1139) とカードを交換しました!
マーチ (マーチ)

キャプチャートラップ を研究しました!(深度0⇒1)
キャプチャートラップ を研究しました!(深度1⇒2)
キャプチャートラップ を研究しました!(深度2⇒3)
ピットトラップ を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





チナミ区 K-5(隔壁)には移動できません。
チナミ区 K-5(隔壁)には移動できません。
チナミ区 J-6(沼地)に移動!(体調26⇒25)
チナミ区 J-7(沼地)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 J-8(隔壁)には移動できません。
瞬(720) をパーティに勧誘しようとしましたが既に背後にいました。
採集はできませんでした。
- 瞬(720) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。
そう言ってフロントダブルバイセップス。
・・・姿を現すことなく、女性のような声が伝わる。
ため息のような音が漏れる。
声はそこで終わる。
チャットが閉じられる――






















































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [スキル]OK.



002.「Placebo」――もしくは、とうに効かない痛み止めについて
もし、耐えられないほどの痛みを味わったとして。
その痛みが物理的な痛みであれば、それを取り除く手段はいくらかある。
そのために現代医学は進歩してるのだろうし、骨折したときも、体調を崩したときも。
わかりやすく「痛み」は取り除くことができた。
歯の治療のときだって、麻酔をすればそこに痛みは感じずに済む。
だから、偏頭痛持ちの俺はいつも病院で処方されるよく効く頭痛薬を持ち歩いていたし、
それなしに日々を過ごすわけにはいかなかった。というよりも、過ごせなかった。
父親は「痛み止めがないと耐えられないようじゃいかん」と俺に強く当たったけど、
母親は「痛い思いを続けるよりはそっちのほうがずっといい」と微笑んだ。
俺は、どっちが正しいのかなんて少しもわからなかったけど、
痛みで何もできなくなるよりは、ずっと薬を頼るほうがいいと思っていた。
無理に耐えようとすれば、どうせトイレに駆け込んで胃の中身を戻すことになる。
それよりは、ずっとマシだ。俺は、今もそう思っている。
痛みというのは、目を向けるだけで惨めになる最悪の隣人だ。
どれだけ寂しくても、どれだけ孤独でも。そんな隣人は、誰も求めていないだろう。
――そんな隣人は、俺には必要ない。
「……はい。前も、処方されてて」
「なるほど。一条くんは……中学生の頃から偏頭痛がひどいわけだ。
苦労したろうね。今はどうかな。発作はどのくらいの頻度で起きてるのかな。
そうだね……、イバラシティに来てからどのくらい起きてるかを教えてくれればいい」
「……ひとつきに、大体二回あるかないか。吐くほどどうしようもないのは、そのくらいです」
「ふむ」と、初老の医者は頷く。
消毒薬の匂いのする白い診察室。申し訳程度に添えられた暖色の色味。
カタカタと音を立てて、汚れ一つない真っ白な白衣を羽織ってタイピングをする彼は、
書き割りのように「医者」という役割を務めているようで、なんだか退屈だった。
それに、どうにも病院は得意じゃなかった。
患者の目の前で電子カルテに打ち込んでいる文章が気になるか気にならないかといえば気になるし、
気になったところでそれを見たっていいことがないことはわかっている。
だから、意識的に視線をよそに向けなければいけないから余計居心地が悪い。
カルテはドイツ語で書く、なんて話は俺の知る「病院」という存在にはなかった。
日本語でそこには正直に自分の知らない自分のことが書いてあるのだと思うと、どうにも。
瞬にこの話をしたときは、瞬は笑っていた。「トータさんは偉いな~」なんていって。
……いや、偉いもなにもないだろ。なんか、盗み見してるみたいでちょっと、違うだろ。
確か、そんなことを言ったのを覚えている。
相手が伝えたくないことが書いてあったときにそれを見たあとに、同じ顔をできるかといえば、
決してそんなことはないだろうし、隠し事も嘘も苦手だったから見ないという選択をした。
別にそれだけの話で、自分がそういうところで大人になれないだけだと思っている。
だから、まあ。瞬が言ってるのが全部本気かなんてわかんないけど、
またきっとこれはからかわれているんだろうな、くらいにしか思わなかった。確かこれも中学の頃。
「前もらった薬は残ってるかな」
「残ってません」
医師は、不思議そうな顔をして首を傾げた。
そりゃそうだ。月に二回くらいしかひどい発作はないって言っているのに、
頓服薬がもう残っていない。矛盾する。逃げられないかと視線を彷徨わせてから、諦める。
「すいません、その、……ストレスで。
ちょっと痛んでも、ひどくなる前に飲んでおこう、って思っちゃって、ああ、でも。
効かないわけじゃなくて、全然。普通に効いてるし、痛みもひどくないしで、大丈夫です」
「一条くん」と、低い声がした。そりゃあそうだろう。
怒られて当然のことをやっているわけで、頓服薬を常飲していると聞いて怒らない医者はいない。
顔を上げて、返事をしようとしたところで医者がまた電子カルテを打ち始めたのを見て視線を逸らす。
何を書かれるかなんてだいたいわかっているけれど、それはそれとして見たくないものは見たくない。
だから、見ることはしない。
「どういう時に、『ちょっと痛む』かい」
「……?」
予想外の問いかけに、幾度か瞬いた。
てっきり、というよりも、この流れだったら怒られて当然だったろう。
俺は怒られると思ったから、謝る準備はしているつもりだった。でも、そうじゃなかった。
「え、えっと……」
口籠っても、医者は笑顔を浮かべたまま視線を合わせてくる。
何を言っても怒られないんじゃないか、と錯覚してしまうくらいには、なんだか。
自分の柔らかいところにすっと立ち入られたような気がした。
彼は、自分が何を言ったところで赦しを与えてくれるんじゃないかと思った。
だから。つい、口を滑らせて。
「色が」
「……色?」
口を押さえても遅かった。既にもう、自分の口からは言葉が落ちた。
だから、もう誤魔化したりすることもできない。
その時の感覚を思い出して、こめかみを強く押す。痛くない。それに、ここは病院だ。
目の前にいるのも医者。だから、痛くないはず。ここにはなにもない。ここは白い部屋だ。
「急にチカチカして、全部の色が極彩色に見えるっていうか、作った色と違う色に見えたり。
一瞬のはずなんですけど、なんか、全然一瞬じゃなくて。色々眩しくなっちゃって……。
デッサンとかしてると、急に距離感狂ったりとかして、わけわかんなくなっちゃって。
それで、それが、そうなるっていうか……。すいません、あの、上手く言えなくて」
医者は何も言わない。
黙って、カルテに何も打ち込まずにただただ目の前の患者のことを見ている。
口を挟むこともしない。だから、まだ話せ、ということなのかと思った。
「だから、いつこうなるかわかんなくて、まあ、結構ストレスで。
画面がぐにゃっとするっていうか、貧血かなんかだと思うんですけど。
三時間くらいかと思ってるんですけど、実際には十五分くらいだったりして……」
「前の病院でそういう話は先生にしたかい?」
「……いや、その、してないです。こんな、頭おかしいこと言って親に迷惑掛けたくないし」
「一条くん」
肩を掴まれた。自分よりずっと年上の、目尻と口元に皺の目立つ男。
書き割りに見えていたはずの、退屈でなんでもなかったはずの医者。ベージュの肌。
マルスブラウンとバーントシェンナの間の子みたいな色の目が、じっと見つめてくる。
視界の端にはベールコンポーゼとミストグリーンに近いカーテンの色がちらつく。
チタニウムジンクホワイトで整えたみたいな色をグレーズっぽく誂えた無機質な病室。
壁には申し訳程度のピンクベージュがドライブラシで軽く擦ったみたいに置かれている。
そう、――そう! この、頭の奥が弾けるような感覚!
一気に汗が噴き出して、足の指先が冷たくなって、肩のあたりがぞわりとする、この!!
この、全部が見えた瞬間みたいな、どれがどうやって描かれてるのかがわかったような!
そっくりそのまま、同じものを「描ける」と確信するこの「感じ」が、そう。
これが、そう。こうやって、世界を「捉え直し」て、「組み直す」、この!!
「――一条くん!! 一条くん、大丈夫かい。聞こえてるかい。
運ぶぞ! そこの担架持って! そっち側……頭は最大限動かさないように、……」
そう思ったときには、もう、意識はそこになかった。
異能診断科:所感(当人には内科と説明)
日常の風景、イメージを組み合わせて、現実と人工が交錯して造り出されるものが彼の絵だ。
現実の風景を「切り取る」虚構の画は、いつしか生々しい現実感を手に入れることができる。
虚構と現実の境界すら曖昧になり、現実も虚構と大差がなくなってしまう。
絵を描けば描くほど、そこに存在していた「光、形、触感、匂い、距離感」といった、
そこにあったはずの現実を一つの虚構に閉じ込めてしまう。
カメラといった「誰かの目」を使うのではなく、自分の見たままの「現実」を切り取る異能は、
そこにあったはずの現実を虚構に貶め、特有の離人感を発生させる。
追記: 彼の絵を見ても第三者が彼ほど心を動かすことはない。
彼の描く絵は、彼の見ている現実そのものと言えるだろう。
俺が、こうしてぼんやりと世界をマスキングして見ている分には痛み止めは要らない。
ただ、それを正確に、正しく、そこにあるものを正確に理解したいのであれば。
その覆いを外して、俺の目で世界を見る必要がある。
そのためには対価がいることもわかるし、だからこそ、それを誰かが代わりに担ってくれるなら。
ありがたいことに、医学は痛み止めを発明できた。
俺の「ほんとうの」症状を解決する処方箋はまだ存在しなくても、慰めにはなる。
だから、これがある限りは絵を描ける。鮮やかすぎるこの世界で生きていける。
だから、隣人を今日も殺して、見ないふりをして。
こうでもしないと、俺が。
世界に存在していたという爪痕を、どこにも残せない。
絵を描けない俺に、価値なんてないんだから。
――筆を。
――薬を。
願うならば、どうか、
赦しを。



ENo.720 瞬 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||



ItemNo.6 不思議な食材 を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(25⇒26)
今回の全戦闘において 器用10 が発揮されます。







制約LV を 5 UP!(LV10⇒15、-5CP)
杉乃(1139) とカードを交換しました!
マーチ (マーチ)

キャプチャートラップ を研究しました!(深度0⇒1)
キャプチャートラップ を研究しました!(深度1⇒2)
キャプチャートラップ を研究しました!(深度2⇒3)
ピットトラップ を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





チナミ区 K-5(隔壁)には移動できません。
チナミ区 K-5(隔壁)には移動できません。
チナミ区 J-6(沼地)に移動!(体調26⇒25)
チナミ区 J-7(沼地)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 J-8(隔壁)には移動できません。
瞬(720) をパーティに勧誘しようとしましたが既に背後にいました。
採集はできませんでした。
- 瞬(720) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
「おっくれまして―――ッ!!」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
 |
ノウレット 「はぁい!はじめましてーッ!!私はここCross+Roseの管・・・妖精! ノウレットでーっす!!皆さんよろしくおねがいしまぁーっす!!」 |
チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。
 |
エディアン 「初めまして初めまして! 私はエディアンといいます、便利な機能をありがとうございます!」 |
 |
ノウレット 「わぁい!どーいたしましてーっ!!」 |
 |
エディアン 「ノウレットさんもドライバーさんと同じ、ハザマを司る方なんですね。」 |
 |
ノウレット 「司る!なんかそれかっこいいですね!!そうです!司ってますよぉ!!」 |
 |
ノウレット 「Cross+Roseのことで分からないことは何でも聞いてくださいねーっ!!」 |
 |
エディアン 「仄暗いハザマの中でマスコットみたいな方に会えて、何だか和みます! ワールドスワップの能力者はマスコットまで創るんですねー。」 |
 |
ノウレット 「マスコット!妖精ですけどマスコットもいいですねぇーっ!! エディアンさんは言葉の天才ですか!?すごい!すごい!!」 |
そう言ってフロントダブルバイセップス。
 |
ノウレット 「えーっとそれでですねーッ!!」 |
 |
ノウレット 「・・・・・あれっ 創造主さまからメッセージが!」 |
 |
エディアン 「むむむ、要チェックですね。」 |
・・・姿を現すことなく、女性のような声が伝わる。
 |
声 「――お疲れ様です御二方。役目を担ってくれて、感謝しています。」 |
 |
エディアン 「方法はどうあれ、こちらも機会を与えてくれて感謝していますよ?」 |
 |
声 「そしてハザマに招かれた方々、申し訳ありません。」 |
 |
声 「・・・・・・・・・」 |
 |
声 「このワールドスワップという能力は、招かれた方々全員が――ザザッ・・・」 |
 |
声 「――失われ、そう――ザザッ・・・――周期的に発動する、能力というより・・・」 |
 |
声 「制御不能な・・・呪いのよう。今までに発動した数度、自分への利は・・・ない。」 |
 |
声 「・・・・・・・・・」 |
ため息のような音が漏れる。
 |
声 「どうか、自らが自らであ―― ザザッ・・・」 |
 |
エディアン 「・・・・・雑音が酷いですねぇ。」 |
 |
声 「――ザザッ・・・・・・・・己の世界のために、争え。」 |
声はそこで終わる。
 |
エディアン 「ノウレットさん、何か通信おかしくないです?」 |
 |
ノウレット 「そうですかーっ!!?そうでもないですよーっ!!!?」 |
 |
エディアン 「むぅ。・・・大した情報は得られませんでしたね。」 |
 |
エディアン 「・・・さ、それじゃこの1時間も頑張っていきましょう!!」 |
チャットが閉じられる――





ENo.128
吊るされた男



一条 燈大(イチジョウ-トウタ)
身長 164cm 本人は170cmを自称している
相良伊橋高校1年1組 美術部
「……るせ。いま俺集中してんの」
中性的な見た目の割に口を開けば10割男子
開けば口も態度も悪めでぶっきらぼう
愛想がないのはデフォルト 本人も結構気にしている
■ 三行
背中まで伸ばした髪を三つ編みおさげに結ぶ
美術部に在籍しており、とりわけ静物画に関心が強い
職人気質で譲れるものと譲れないものの差が激しい
■ 異能
一日に一度、正確な筆致で風景を「切り取る」ことができる
制御できている異能ではなく、必ず発動するわけではない
最初は「数撃ちゃ当たる」で発動するまで描き続けていたが、
今はあまり気にせずに絵を描き続けている
「数撃ちゃ当たる」時代の名残で、それなりに絵は上手い
■ 既知RPは歓迎です。
■ イラストは湯槽さんに描いていただきました!
--- ✂ --- ✂ --- ✂ --- ✂ --- ✂ --- ✂ --- ✂ --- ✂ ---
一度目の人生を自殺という形で終えている少年。
そのはずだが、まるでそれがなかったかのように、
あるはずのないあの日の「続き」を今も享受している。
一条 燈大
SIDE:ANSINITY
彼は、アンジニティを「死後の世界」と認識している。
が、実際のところはそういうわけではない。
彼は、死にながらにして死を拒んだ。
故に、彼は死を迎えることなく否定の世界へと追放された。
彼はそれに気付くことはない。
自らという一人の人間の死を「芸術」として弄び、
一人のアーティストとして「遺作」とすることを選び、
「人の記憶に残るような」劇的な死を「創った」。
故に、彼は「作品」として生き続けなくてはならない。
終わることはない物語の象徴。死を冒涜するもの。
彼の罪は、「『作者』が終わりを拒んだこと」である。
無自覚な罪人が赦されることはない。
身長 164cm 本人は170cmを自称している
相良伊橋高校1年1組 美術部
「……るせ。いま俺集中してんの」
中性的な見た目の割に口を開けば10割男子
開けば口も態度も悪めでぶっきらぼう
愛想がないのはデフォルト 本人も結構気にしている
■ 三行
背中まで伸ばした髪を三つ編みおさげに結ぶ
美術部に在籍しており、とりわけ静物画に関心が強い
職人気質で譲れるものと譲れないものの差が激しい
■ 異能
一日に一度、正確な筆致で風景を「切り取る」ことができる
制御できている異能ではなく、必ず発動するわけではない
最初は「数撃ちゃ当たる」で発動するまで描き続けていたが、
今はあまり気にせずに絵を描き続けている
「数撃ちゃ当たる」時代の名残で、それなりに絵は上手い
■ 既知RPは歓迎です。
■ イラストは湯槽さんに描いていただきました!
--- ✂ --- ✂ --- ✂ --- ✂ --- ✂ --- ✂ --- ✂ --- ✂ ---
一度目の人生を自殺という形で終えている少年。
そのはずだが、まるでそれがなかったかのように、
あるはずのないあの日の「続き」を今も享受している。
一条 燈大
SIDE:ANSINITY
彼は、アンジニティを「死後の世界」と認識している。
が、実際のところはそういうわけではない。
彼は、死にながらにして死を拒んだ。
故に、彼は死を迎えることなく否定の世界へと追放された。
彼はそれに気付くことはない。
自らという一人の人間の死を「芸術」として弄び、
一人のアーティストとして「遺作」とすることを選び、
「人の記憶に残るような」劇的な死を「創った」。
故に、彼は「作品」として生き続けなくてはならない。
終わることはない物語の象徴。死を冒涜するもの。
彼の罪は、「『作者』が終わりを拒んだこと」である。
無自覚な罪人が赦されることはない。
24 / 30
41 PS
チナミ区
J-7
J-7






















| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 新品の鉛筆 | 武器 | 30 | 攻撃10 | - | - | 【射程1】 |
| 5 | 油壺 | 装飾 | 30 | 幸運10 | - | - | |
| 6 | 吸い殻 | 素材 | 10 | [武器]炎上10(LV25)[防具]火纏10(LV25)[装飾]耐火10(LV20) | |||
| 7 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 制約 | 15 | 拘束/罠/リスク |
| 解析 | 10 | 精確/対策/装置 |
| 防具 | 20 | 防具作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| アサルト | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃+自:連続減 | |
| プリディクション | 5 | 0 | 120 | 味列:AG増(3T) | |
| キャプチャートラップ | 5 | 0 | 90 | 敵列:罠《捕縛》LV増 | |
| ペナルティ | 5 | 0 | 120 | 敵3:麻痺・混乱 | |
| ブロック | 5 | 0 | 80 | 自:守護+DF増(2T)+味傷:護衛 | |
| ジャックポット | 5 | 0 | 110 | 敵傷:粗雑痛撃+回避された場合、3D6が11以上なら粗雑痛撃 | |
| ピットトラップ | 5 | 0 | 120 | 敵全:罠《奈落》LV増 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 |
最大EP[20]





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]キャプチャートラップ |

PL / .