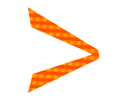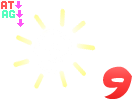<< 0:00~1:00




邪魔だ、とは思ったけれど、それで何ができたということはなかった。
異能で戦えばいい。そんなことを言われたけれど、わたしは自分の異能のことなんてこれっぽっちも覚えてない。
戦い方だってわからない。この途中で途切れた腕では、殴り飛ばすことだってできないし、そもそも拳があったとしてもきっとわたしには大した力もない。
だから何をどういう風にわたしがその赤いどろどろと戦ったかなんてことも、全然覚えてない。
でも気がついたらそれはめちゃくちゃに飛び散っていて。
わたしはそれに驚いて、わけもわからないままに地面を転がって天を仰いでいた。
赤くて昏い。
気分の悪くなるような空。
それを遮って、あの人がわたしを覗き込む。
「なんだ」
笑う。
「思いの外、根性のある娘じゃあないか」
ドアはわたしを助け起こすようなことはしなかった。ただ立ちぼうけのままわたしを見下ろしていた。
わたしはそれが、それで、きっと正しいんだと思った。
わたしは助けを求めていないし。彼がわたしを助ける義理はない。
でも、だからこそ不思議だったのが、
「……先に行ってしまったと思ってた」
「よく分かっている」
腰を下ろす。横たわるわたしを眺めて、立てた膝に頬杖をつく。
「そのつもりだった」
「ならどうして?」
「思い出したことがあってな」
視線で次を促したわたしに、彼は目を眇めてみせた。
「子供は嫌いじゃない」
「…………。じゃあ、わたしは幸運ね」
「殺されかけたのに?」
そういえばそうだった。
「ほんとうに幸運な子供であれば、もっと優しい保護者に巡り会ったのではないかね」
「……誰にも顧みられないよりは、いいんじゃないかしら」
「違いない」
くつくつと笑う彼が、立ち上がる。
赤みのかかった琥珀の瞳。燃えるようなその色彩が、なぜか空の色と被って見えた。
「私にとってはどうでも構わないことだが」
彼は最初にそう前置いた。
「イバラシティでの記憶はあるか? 私と別れて、再びこうして巡り逢うまでの間。途中に意識が途切れて、他の場所で過ごした記憶は?」
不思議なことを訊くものだと思った。そんなものあるはずがない。
わたしはずっとここにいるのに。
なのにわたしの否定は彼にとっては意外に思われたようだった。そうか、と小さく呟くのが、わたしにはやっぱり不思議に思えて、
「……なにか、おかしいの?」
「いや。そういう結果になるのかと思った、というだけだ」
「?」
再び、小さく溜め息。
その後に彼は口を開く。
「私にはその間にイバラシティで過ごした記憶がある」
「……?」
よく分からない。わたしが彼を見失った少しの間、彼はイバラシティにいた?
「この空間が特殊なのだろうな。……だがお前にはそれがない」
「……よく分からないわ」
「何。言ってしまえば、簡単なことだ」
「——やはりお前は死んでいるのかもしれない、という話さ」
◆
ワールドスワップ、という異能によって、イバラシティにアンジニティの住人が紛れ込んだ。
ただしそれは"仮の姿"でもってだ。明らかな異邦人とは分からないように、最初からそこにいたものとして、イバラシティで仮初の日々を過ごす。
本人たちすら侵略者の自覚を持たぬままに。
そして定期的に訪れるハザマ時間。
その度に彼らは自分たちの本分を思い出す。
自分たちは侵略者であることを。イバラシティを乗っ取るための戦いに身を投じるものだということを。
イバラシティの民ももちろん無抵抗ではない。
強化されたという異能で、アンジニティの住民に抵抗する。戦う。自分たちの生活を守るために。
イバラシティの日々を胸に懐きながら、自分たちの生活を守るために。
でも。
「イバラシティでのお前は死んでいる。そうでなければ意識のない昏睡状態になる」
「だから、ずっとハザマ時間にいる……?」
「分からんがな。私はお前のことを知らん」
煙草の煙を吹かしながらドアは他人事のように言う。
違う。ほんとうに他人事なのだろうと思う。
「……でも、わたし、ひとつだけ覚えていて」
「なんだ」
「わたしが殺された、ってこと」
それだけは最初から、なんだか確信があって。
だからきっと、昏睡状態だとかではなくて、わたしはほんとうに死んでいるんだろうって。
理屈ではなく、理由もなく、わたしはそう信じている。
「……ふうん」
ドアが煙草を捨てて踏み躙る。品の良い仕草ではない、とそれをわたしは受け止めていた。
「ならばお前には復讐の権利がある」
「——え?」
復讐。
脈略のない響きに、わたしは目を瞬いた。
「イバラシティの誰かがお前を殺した。お前は死んだが、そいつはおそらく生きている」
「…………」
「であればお前はそのイバラシティの人間に復讐する権利がある。違うか」
「……そんな、ことを言われても」
「殺されたことを、恨まないと?」
「そういうわけじゃない、けど、……でも、そもそも無理だわ。わたし、誰に殺されたか覚えてないし、……覚えてても、ここからじゃあ、どうしたって」
「簡単なことを言わせるなよ」
彼は呆れ果てたように溜め息を吐いた。
「そいつをアンジニティに追いやることができれば、十分な復讐にはなるのではないか」
「……それは」
「まあ、復讐は不毛なものだ、という論は認めるが。それを言い出したら人間の人生そのものがそれなりに不毛だ」
「…………」
「やりたいようにやる。人生などそれでいいものと思うがね」
腰を上げて、彼はわたしに背を向けた。いつまでも一緒にいてくれる気はないのだろう。少なくともわたしに合わせる気は。
「言い忘れていたが、このハザマ時間での闘争。一時間を三十六回繰り返して、それで蹴りがつくらしい」
「……?」
「既に私にとっては二回目だから、まあ一時間は食ったな。……要するに」
「お前の残り時間はあと三十四時間と少しだ、ということだ」





特に何もしませんでした。






領域LV を 5 UP!(LV20⇒25、-5CP)
武器LV を 5 UP!(LV20⇒25、-5CP)
ItemNo.4 不思議な牙 から射程4の大砲『戦う力』を作製しました!
⇒ 戦う力/大砲:強さ35/[効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程4】/特殊アイテム
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





チナミ区 I-5(山岳)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 J-5(道路)に移動!(体調26⇒25)
チナミ区 J-6(沼地)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 K-6(沼地)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 L-6(森林)に移動!(体調23⇒22)






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。
そう言ってフロントダブルバイセップス。
・・・姿を現すことなく、女性のような声が伝わる。
ため息のような音が漏れる。
声はそこで終わる。
チャットが閉じられる――


















































異能・生産
アクティブ
パッシブ





[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



邪魔だ、とは思ったけれど、それで何ができたということはなかった。
異能で戦えばいい。そんなことを言われたけれど、わたしは自分の異能のことなんてこれっぽっちも覚えてない。
戦い方だってわからない。この途中で途切れた腕では、殴り飛ばすことだってできないし、そもそも拳があったとしてもきっとわたしには大した力もない。
だから何をどういう風にわたしがその赤いどろどろと戦ったかなんてことも、全然覚えてない。
でも気がついたらそれはめちゃくちゃに飛び散っていて。
わたしはそれに驚いて、わけもわからないままに地面を転がって天を仰いでいた。
赤くて昏い。
気分の悪くなるような空。
それを遮って、あの人がわたしを覗き込む。
「なんだ」
笑う。
「思いの外、根性のある娘じゃあないか」
ドアはわたしを助け起こすようなことはしなかった。ただ立ちぼうけのままわたしを見下ろしていた。
わたしはそれが、それで、きっと正しいんだと思った。
わたしは助けを求めていないし。彼がわたしを助ける義理はない。
でも、だからこそ不思議だったのが、
「……先に行ってしまったと思ってた」
「よく分かっている」
腰を下ろす。横たわるわたしを眺めて、立てた膝に頬杖をつく。
「そのつもりだった」
「ならどうして?」
「思い出したことがあってな」
視線で次を促したわたしに、彼は目を眇めてみせた。
「子供は嫌いじゃない」
「…………。じゃあ、わたしは幸運ね」
「殺されかけたのに?」
そういえばそうだった。
「ほんとうに幸運な子供であれば、もっと優しい保護者に巡り会ったのではないかね」
「……誰にも顧みられないよりは、いいんじゃないかしら」
「違いない」
くつくつと笑う彼が、立ち上がる。
赤みのかかった琥珀の瞳。燃えるようなその色彩が、なぜか空の色と被って見えた。
「私にとってはどうでも構わないことだが」
彼は最初にそう前置いた。
「イバラシティでの記憶はあるか? 私と別れて、再びこうして巡り逢うまでの間。途中に意識が途切れて、他の場所で過ごした記憶は?」
不思議なことを訊くものだと思った。そんなものあるはずがない。
わたしはずっとここにいるのに。
なのにわたしの否定は彼にとっては意外に思われたようだった。そうか、と小さく呟くのが、わたしにはやっぱり不思議に思えて、
「……なにか、おかしいの?」
「いや。そういう結果になるのかと思った、というだけだ」
「?」
再び、小さく溜め息。
その後に彼は口を開く。
「私にはその間にイバラシティで過ごした記憶がある」
「……?」
よく分からない。わたしが彼を見失った少しの間、彼はイバラシティにいた?
「この空間が特殊なのだろうな。……だがお前にはそれがない」
「……よく分からないわ」
「何。言ってしまえば、簡単なことだ」
「——やはりお前は死んでいるのかもしれない、という話さ」
◆
ワールドスワップ、という異能によって、イバラシティにアンジニティの住人が紛れ込んだ。
ただしそれは"仮の姿"でもってだ。明らかな異邦人とは分からないように、最初からそこにいたものとして、イバラシティで仮初の日々を過ごす。
本人たちすら侵略者の自覚を持たぬままに。
そして定期的に訪れるハザマ時間。
その度に彼らは自分たちの本分を思い出す。
自分たちは侵略者であることを。イバラシティを乗っ取るための戦いに身を投じるものだということを。
イバラシティの民ももちろん無抵抗ではない。
強化されたという異能で、アンジニティの住民に抵抗する。戦う。自分たちの生活を守るために。
イバラシティの日々を胸に懐きながら、自分たちの生活を守るために。
でも。
「イバラシティでのお前は死んでいる。そうでなければ意識のない昏睡状態になる」
「だから、ずっとハザマ時間にいる……?」
「分からんがな。私はお前のことを知らん」
煙草の煙を吹かしながらドアは他人事のように言う。
違う。ほんとうに他人事なのだろうと思う。
「……でも、わたし、ひとつだけ覚えていて」
「なんだ」
「わたしが殺された、ってこと」
それだけは最初から、なんだか確信があって。
だからきっと、昏睡状態だとかではなくて、わたしはほんとうに死んでいるんだろうって。
理屈ではなく、理由もなく、わたしはそう信じている。
「……ふうん」
ドアが煙草を捨てて踏み躙る。品の良い仕草ではない、とそれをわたしは受け止めていた。
「ならばお前には復讐の権利がある」
「——え?」
復讐。
脈略のない響きに、わたしは目を瞬いた。
「イバラシティの誰かがお前を殺した。お前は死んだが、そいつはおそらく生きている」
「…………」
「であればお前はそのイバラシティの人間に復讐する権利がある。違うか」
「……そんな、ことを言われても」
「殺されたことを、恨まないと?」
「そういうわけじゃない、けど、……でも、そもそも無理だわ。わたし、誰に殺されたか覚えてないし、……覚えてても、ここからじゃあ、どうしたって」
「簡単なことを言わせるなよ」
彼は呆れ果てたように溜め息を吐いた。
「そいつをアンジニティに追いやることができれば、十分な復讐にはなるのではないか」
「……それは」
「まあ、復讐は不毛なものだ、という論は認めるが。それを言い出したら人間の人生そのものがそれなりに不毛だ」
「…………」
「やりたいようにやる。人生などそれでいいものと思うがね」
腰を上げて、彼はわたしに背を向けた。いつまでも一緒にいてくれる気はないのだろう。少なくともわたしに合わせる気は。
「言い忘れていたが、このハザマ時間での闘争。一時間を三十六回繰り返して、それで蹴りがつくらしい」
「……?」
「既に私にとっては二回目だから、まあ一時間は食ったな。……要するに」
「お前の残り時間はあと三十四時間と少しだ、ということだ」





特に何もしませんでした。





領域LV を 5 UP!(LV20⇒25、-5CP)
武器LV を 5 UP!(LV20⇒25、-5CP)
ItemNo.4 不思議な牙 から射程4の大砲『戦う力』を作製しました!
⇒ 戦う力/大砲:強さ35/[効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程4】/特殊アイテム
| ドア 「餞別にもならんな」 |
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





チナミ区 I-5(山岳)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 J-5(道路)に移動!(体調26⇒25)
チナミ区 J-6(沼地)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 K-6(沼地)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 L-6(森林)に移動!(体調23⇒22)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
「おっくれまして―――ッ!!」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
 |
ノウレット 「はぁい!はじめましてーッ!!私はここCross+Roseの管・・・妖精! ノウレットでーっす!!皆さんよろしくおねがいしまぁーっす!!」 |
チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。
 |
エディアン 「初めまして初めまして! 私はエディアンといいます、便利な機能をありがとうございます!」 |
 |
ノウレット 「わぁい!どーいたしましてーっ!!」 |
 |
エディアン 「ノウレットさんもドライバーさんと同じ、ハザマを司る方なんですね。」 |
 |
ノウレット 「司る!なんかそれかっこいいですね!!そうです!司ってますよぉ!!」 |
 |
ノウレット 「Cross+Roseのことで分からないことは何でも聞いてくださいねーっ!!」 |
 |
エディアン 「仄暗いハザマの中でマスコットみたいな方に会えて、何だか和みます! ワールドスワップの能力者はマスコットまで創るんですねー。」 |
 |
ノウレット 「マスコット!妖精ですけどマスコットもいいですねぇーっ!! エディアンさんは言葉の天才ですか!?すごい!すごい!!」 |
そう言ってフロントダブルバイセップス。
 |
ノウレット 「えーっとそれでですねーッ!!」 |
 |
ノウレット 「・・・・・あれっ 創造主さまからメッセージが!」 |
 |
エディアン 「むむむ、要チェックですね。」 |
・・・姿を現すことなく、女性のような声が伝わる。
 |
声 「――お疲れ様です御二方。役目を担ってくれて、感謝しています。」 |
 |
エディアン 「方法はどうあれ、こちらも機会を与えてくれて感謝していますよ?」 |
 |
声 「そしてハザマに招かれた方々、申し訳ありません。」 |
 |
声 「・・・・・・・・・」 |
 |
声 「このワールドスワップという能力は、招かれた方々全員が――ザザッ・・・」 |
 |
声 「――失われ、そう――ザザッ・・・――周期的に発動する、能力というより・・・」 |
 |
声 「制御不能な・・・呪いのよう。今までに発動した数度、自分への利は・・・ない。」 |
 |
声 「・・・・・・・・・」 |
ため息のような音が漏れる。
 |
声 「どうか、自らが自らであ―― ザザッ・・・」 |
 |
エディアン 「・・・・・雑音が酷いですねぇ。」 |
 |
声 「――ザザッ・・・・・・・・己の世界のために、争え。」 |
声はそこで終わる。
 |
エディアン 「ノウレットさん、何か通信おかしくないです?」 |
 |
ノウレット 「そうですかーっ!!?そうでもないですよーっ!!!?」 |
 |
エディアン 「むぅ。・・・大した情報は得られませんでしたね。」 |
 |
エディアン 「・・・さ、それじゃこの1時間も頑張っていきましょう!!」 |
チャットが閉じられる――



ENo.1001
******



倫理観が絶滅している。
その全てはあの街に残された。
愛も慈しみも優しさも温もりも、
全ては掌をすり抜けて零れ落ち、
ハザマの彼女には何一つ届かない。
殺された、という事実だけが、彼女の中には残されている。
誰に? 分からない。
どうして? 知る由もない。
自分が殺された事実だけを確かなものと覚えている。
◆少女
小学生くらいの少女。
半ばで断ち切られた両腕。色の抜けた長い髪。
フリルのついた黒いワンピース。腹部を染める赤すぎる血。
身長130cmほど。
何もかもを、思い出せずに彷徨っている。
◆ドア・アッシュクロフト(アイコン28)
アンジニティの罪人。
傭兵。人殺し。黒い髪に赤みがかったアンバーの瞳。
スカーフェイス。上半身を覆うミリタリーマント。
少女を見守るが庇護はしない。
身長175cm。
◆小出エリカ(アイコン29)
イバラシティの女子高生。
茶色のショートカット。泣き黒子。
身長160cmほど。
*なんかまあ何かしらを載せたりなどする場所
http://santyome.blog135.fc2.com/
*まったり交流歓迎PLです よろしくお願いします
*CHATは基本的に少女の方が対応しますがドアも対応可能です
その全てはあの街に残された。
愛も慈しみも優しさも温もりも、
全ては掌をすり抜けて零れ落ち、
ハザマの彼女には何一つ届かない。
殺された、という事実だけが、彼女の中には残されている。
誰に? 分からない。
どうして? 知る由もない。
自分が殺された事実だけを確かなものと覚えている。
◆少女
小学生くらいの少女。
半ばで断ち切られた両腕。色の抜けた長い髪。
フリルのついた黒いワンピース。腹部を染める赤すぎる血。
身長130cmほど。
何もかもを、思い出せずに彷徨っている。
◆ドア・アッシュクロフト(アイコン28)
アンジニティの罪人。
傭兵。人殺し。黒い髪に赤みがかったアンバーの瞳。
スカーフェイス。上半身を覆うミリタリーマント。
少女を見守るが庇護はしない。
身長175cm。
◆小出エリカ(アイコン29)
イバラシティの女子高生。
茶色のショートカット。泣き黒子。
身長160cmほど。
*なんかまあ何かしらを載せたりなどする場所
http://santyome.blog135.fc2.com/
*まったり交流歓迎PLです よろしくお願いします
*CHATは基本的に少女の方が対応しますがドアも対応可能です
22 / 30
5 PS
チナミ区
L-6
L-6




























| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 戦う力 | 大砲 | 35 | 攻撃10 | - | - | 【射程4】 |
| 5 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]防御10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) | |||
| 6 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 8 | 黄鉄鉱 | 素材 | 15 | [武器]麻痺10(LV20)[防具]反光10(LV25)[装飾]光纏10(LV20) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 領域 | 25 | 範囲/法則/結界 |
| 武器 | 25 | 武器作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |
| ガーディアン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+味傷:護衛 | |
| ツインブラスト | 5 | 0 | 220 | 敵全:攻撃&麻痺+敵全:攻撃&盲目 | |
| インヴァージョン | 5 | 0 | 150 | 敵全:攻撃&祝福を猛毒化 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 大砲作製 | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『装備作製』で武器「大砲」を選択できる。大砲は射程が必ず4になる。 |
最大EP[20]



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |

PL / さかな