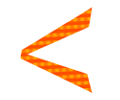<< 0:00~0:00




視界に光が差し込む。ゆっくりと身体を起こす。
息を吐いて見回して、そしてそこにある現実に、もう一度息を吐いた。
山間にひっそりと在るこの家の住人は僕と、飼い慣らした鳥しか居ない。
壁に掛けたカレンダーを見て目を細める。
今日という日は、僕にとって辛い一日だ。決定打となってしまう一日。
僕の師匠が失踪して、七年になる。
出かけて来ると言ったきり、帰って来なくなった師。
彼女はとても優しくて、とても聡明で、とても強い人だった。
病を患ってからはあまり外に出る事も無くなったけれど、
それでも笑顔を絶やさぬ人であった。
僕は幼い頃彼女に拾われ、この小屋で育った。
山の中に捨てられていたのだと、後に教えられた。
故に彼女は僕の母親代わりでもあった。
物心ついた頃には、自然と彼女に書を学んでいた。
彼女の書く字は、どれも力強く、病に伏せた女性が書く物とは思えなかった。
気の弱かった僕には真似出来ずに悔しがっていると、
彼女はそっと肩に手を置いて、僕に言った。
「御前の字はとても優しい字だ」と。
其れから、ガサツな私には真似出来ないよ、と、笑った。
僕はそんな師が大好きだった。
けれど、もう七年。七年である。
普通、世間では失踪から七年が経過すると、死亡と見なされる。
とりわけ病を抱えた彼女である。生きている可能性は、皆無に等しい。
それでも何処かで生きているような気がして、僕は育ったこの小屋で彼女を待ち続けている。
そんな想いも今日で打ち砕かれるわけだ。
そうして僕は気だるげに、彼女の私物を整理し始めた。
押し入れの奥にある箱には書術士としての書物が、大量に収められている。
彼女は短い人生で、これだけの物を書いた。
筆を進める度に、彼女は何をおもったのだろう。
呆としながら、ふと見たことの無い物に気付く。
数々の巻物や掛け軸の上に、乱雑に折り畳まれた半紙があった。
「嗚呼、とうとう、この日が来てしまった。
私は知っている。此度の命が何であるかを。
此度の命を終えた時、私の命も尽きる事を。
彼等はあくまでも、私を使い切ってしまいたいのだろう。
これは私への最期の通告なのだ。
嘗ての私であれば心残りなど無かったというに、今ではこの命が情けない程に惜しい。
できる事ならば裏切りたいものだ。
だがしかし、それが何を意味するかも、私は知っている。
こうなってしまった以上は、形式上従う他は無いだろう。
故に私は赴こう。彼の大地へ。
けれど奴等の命を聞く気など毛頭無い。」
急いで書き殴ったのだろう。あちこちに墨が飛び散っていた。
書術士である師匠にしては、らしくない。
“作品”とは、到底言い難いものであった。
命。奴等。それ等は一体、何だ?
僕は記憶を掘り返す。少なくともそんな事、彼女は口に出していない。
七年の時を経て、何かを掴んだような気がした。
彼女は何かに使われていた人間なのだという事。
そして嘗ては、それに従順に従っていたという事。
知らなかった。頭に何かの衝撃を喰らった様な痛みが走った。
即ち、僕は師匠である彼女に、とんでもない隠し事をされていたわけだった。
そりゃあ、誰だって隠したい過去はあるだろうが、それでも言い様の無い悲しみが僕を襲った。
けれど、僕はその先を見て、更に深く悲しんだ。
「その上で、私に課せられた命は、奴等の命ではない。
私の命は、我が弟子を死なせてはならない。それのみに尽きる。」
紙を握る手が震えた。
それは、
つまり。
あの日、いつもの様に笑って家を出た師の胸中は、どの様なものであったのだろうか。
その苦しみは計り知れない。否、知れて良いものではない。
七年。もう師匠は生きてはいないだろう。
だけど、僕は思ったのだ。
我が師が誰に何を言われ、何処へ赴き、何をして、何をおもって、その生涯を終えたのか。
知りたい。扉を閉めた笑顔の続きは、如何なるものであったのか。
だから僕は、箱の蓋を閉じた。



ENo.895 マサキ とのやりとり

ENo.1099 コウ とのやりとり




特に何もしませんでした。






駄木(50 PS)を購入しようとしましたが、PSが足りませんでした。
駄木(50 PS)を購入しようとしましたが、PSが足りませんでした。
駄石(50 PS)を購入しようとしましたが、PSが足りませんでした。
幻術LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
呪術LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
防具LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)
ランメイ(892) の持つ ItemNo.4 不思議な牙 から防具『古びたジュストコール』を作製しました!
マサキ(895) の持つ ItemNo.5 不思議な石 から防具『きらきら星』を作製しました!
リン(1283) の持つ ItemNo.5 不思議な石 から防具『多重積層装甲(プラ製)』を作製しました!
新田(1390) とカードを交換しました!
break (ブレイク)

カタルシス を研究しました!(深度0⇒1)
カタルシス を研究しました!(深度1⇒2)
カタルシス を研究しました!(深度2⇒3)
ライトニング を習得!
カース を習得!
カタルシス を習得!
ディム を習得!
ダークネス を習得!
マインドブレイク を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





次元タクシーに乗り チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》 に転送されました!
現在のパーティから離脱しました!
チナミ区 F-5(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 F-6(道路)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 F-7(草原)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 F-8(草原)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 F-9(沼地)に移動!(体調26⇒25)
ランメイ(892) からパーティに勧誘されました!
採集はできませんでした。
- ランメイ(892) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- つぐみ(894) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- マサキ(895) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャットで時間が伝えられる。
グチャッとなったどこかのナレハテの映像をまじまじと見つめる白南海。
その背後から、突然タクシーが現れる!!
白南海のすぐ横を走り抜け、止まる。
タクシーの窓が開く。

帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。
窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。
白南海からのチャットが閉じられる――





















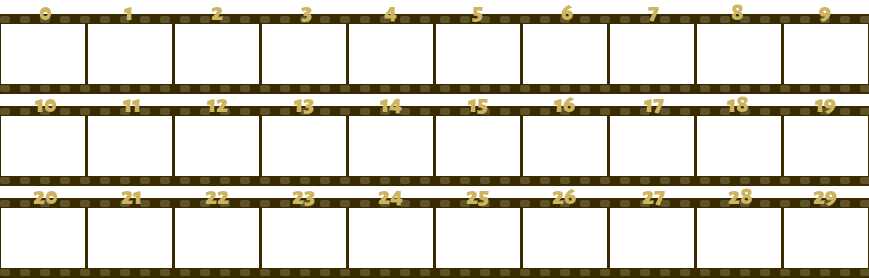







































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



視界に光が差し込む。ゆっくりと身体を起こす。
息を吐いて見回して、そしてそこにある現実に、もう一度息を吐いた。
山間にひっそりと在るこの家の住人は僕と、飼い慣らした鳥しか居ない。
壁に掛けたカレンダーを見て目を細める。
今日という日は、僕にとって辛い一日だ。決定打となってしまう一日。
僕の師匠が失踪して、七年になる。
出かけて来ると言ったきり、帰って来なくなった師。
彼女はとても優しくて、とても聡明で、とても強い人だった。
病を患ってからはあまり外に出る事も無くなったけれど、
それでも笑顔を絶やさぬ人であった。
僕は幼い頃彼女に拾われ、この小屋で育った。
山の中に捨てられていたのだと、後に教えられた。
故に彼女は僕の母親代わりでもあった。
物心ついた頃には、自然と彼女に書を学んでいた。
彼女の書く字は、どれも力強く、病に伏せた女性が書く物とは思えなかった。
気の弱かった僕には真似出来ずに悔しがっていると、
彼女はそっと肩に手を置いて、僕に言った。
「御前の字はとても優しい字だ」と。
其れから、ガサツな私には真似出来ないよ、と、笑った。
僕はそんな師が大好きだった。
けれど、もう七年。七年である。
普通、世間では失踪から七年が経過すると、死亡と見なされる。
とりわけ病を抱えた彼女である。生きている可能性は、皆無に等しい。
それでも何処かで生きているような気がして、僕は育ったこの小屋で彼女を待ち続けている。
そんな想いも今日で打ち砕かれるわけだ。
そうして僕は気だるげに、彼女の私物を整理し始めた。
押し入れの奥にある箱には書術士としての書物が、大量に収められている。
彼女は短い人生で、これだけの物を書いた。
筆を進める度に、彼女は何をおもったのだろう。
呆としながら、ふと見たことの無い物に気付く。
数々の巻物や掛け軸の上に、乱雑に折り畳まれた半紙があった。
「嗚呼、とうとう、この日が来てしまった。
私は知っている。此度の命が何であるかを。
此度の命を終えた時、私の命も尽きる事を。
彼等はあくまでも、私を使い切ってしまいたいのだろう。
これは私への最期の通告なのだ。
嘗ての私であれば心残りなど無かったというに、今ではこの命が情けない程に惜しい。
できる事ならば裏切りたいものだ。
だがしかし、それが何を意味するかも、私は知っている。
こうなってしまった以上は、形式上従う他は無いだろう。
故に私は赴こう。彼の大地へ。
けれど奴等の命を聞く気など毛頭無い。」
急いで書き殴ったのだろう。あちこちに墨が飛び散っていた。
書術士である師匠にしては、らしくない。
“作品”とは、到底言い難いものであった。
命。奴等。それ等は一体、何だ?
僕は記憶を掘り返す。少なくともそんな事、彼女は口に出していない。
七年の時を経て、何かを掴んだような気がした。
彼女は何かに使われていた人間なのだという事。
そして嘗ては、それに従順に従っていたという事。
知らなかった。頭に何かの衝撃を喰らった様な痛みが走った。
即ち、僕は師匠である彼女に、とんでもない隠し事をされていたわけだった。
そりゃあ、誰だって隠したい過去はあるだろうが、それでも言い様の無い悲しみが僕を襲った。
けれど、僕はその先を見て、更に深く悲しんだ。
「その上で、私に課せられた命は、奴等の命ではない。
私の命は、我が弟子を死なせてはならない。それのみに尽きる。」
紙を握る手が震えた。
それは、
つまり。
あの日、いつもの様に笑って家を出た師の胸中は、どの様なものであったのだろうか。
その苦しみは計り知れない。否、知れて良いものではない。
七年。もう師匠は生きてはいないだろう。
だけど、僕は思ったのだ。
我が師が誰に何を言われ、何処へ赴き、何をして、何をおもって、その生涯を終えたのか。
知りたい。扉を閉めた笑顔の続きは、如何なるものであったのか。
だから僕は、箱の蓋を閉じた。



ENo.895 マサキ とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.1099 コウ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||



特に何もしませんでした。





駄木(50 PS)を購入しようとしましたが、PSが足りませんでした。
駄木(50 PS)を購入しようとしましたが、PSが足りませんでした。
駄石(50 PS)を購入しようとしましたが、PSが足りませんでした。
幻術LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
呪術LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
防具LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)
ランメイ(892) の持つ ItemNo.4 不思議な牙 から防具『古びたジュストコール』を作製しました!
マサキ(895) の持つ ItemNo.5 不思議な石 から防具『きらきら星』を作製しました!
リン(1283) の持つ ItemNo.5 不思議な石 から防具『多重積層装甲(プラ製)』を作製しました!
新田(1390) とカードを交換しました!
break (ブレイク)

カタルシス を研究しました!(深度0⇒1)
カタルシス を研究しました!(深度1⇒2)
カタルシス を研究しました!(深度2⇒3)
ライトニング を習得!
カース を習得!
カタルシス を習得!
ディム を習得!
ダークネス を習得!
マインドブレイク を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





次元タクシーに乗り チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》 に転送されました!
 |
ドライバーさん 「ほれ、着いたぜ。お代は土産話でよろしく。」 |
現在のパーティから離脱しました!
チナミ区 F-5(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 F-6(道路)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 F-7(草原)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 F-8(草原)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 F-9(沼地)に移動!(体調26⇒25)
ランメイ(892) からパーティに勧誘されました!
採集はできませんでした。
- ランメイ(892) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- つぐみ(894) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- マサキ(895) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
白南海 「長針一周・・・っと。丁度1時間っすね。」 |

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
チャットで時間が伝えられる。
 |
白南海 「ケンカは無事済みましたかね。 こてんぱんにすりゃいいってわけですかい。」 |
グチャッとなったどこかのナレハテの映像をまじまじと見つめる白南海。
その背後から、突然タクシーが現れる!!
白南海のすぐ横を走り抜け、止まる。
 |
白南海 「・・・・・こ、殺す気ですかね。」 |
タクシーの窓が開く。

ドライバーさん
次元タクシーの運転手。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。初老くらいに見える。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。初老くらいに見える。
 |
ドライバーさん 「すまんすまん、出口の座標を少し間違えた。 挨拶に来たぜ。『次元タクシー』の運転役だ。」 |
帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。
 |
白南海 「イバラシティ側を潰そうってんじゃねぇでしょーね。・・・ぶっ殺しますよ?」 |
 |
ドライバーさん 「安心しな、どっちにも加勢するさ。俺らはそういう役割の・・・ハザマの機能ってとこだ。」 |
 |
ドライバーさん 「チェックポイントとかの行き来の際にゃ、へいタクシーの一声を。 俺もタクシーも同じのが沢山"在る"んでな、待たしゃしない。・・・そんじゃ。」 |
窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。
 |
白南海 「ひとを轢きかけといてあの態度・・・後で営業妨害でもしてやろうか。」 |
 |
白南海 「さて、それでは私は・・・のんびり傍観させてもらいますかね。この役も悪くない。」 |
白南海からのチャットが閉じられる――







決闘不成立!
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。



崎に囲まれるお嬢様
|
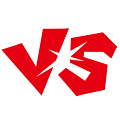 |
放課後探検クラブ
|


ENo.894
哘崎つぐみ



「晩御飯までには帰って来て下さいね」
哘崎つぐみ(さそざき つぐみ)
男性 28歳
173cm/56kg
普段は書道教室の先生をしているが、その実態は書術士という、墨痕を操る魔法使いである。
性格は温厚だがいささか穏やかに過ぎ、達観した何かがある。あるいはそれは諦観かもしれない。
元は山中に捨てられた子供であった。親の顔は知らず、〝哘崎いま〟という名の若い女性に拾われて育つ。書術士としてのノウハウもそこで学んだため、彼女は母であり師でもあった。
だが、つぐみが7つの時、突如として彼女は姿を消す。何やら後ろ暗い過去があった、ということくらいしか知らなかった。
7年経っても帰ってこなかったため、山を降り、人里に紛れて暮らしていた。
イバラシティとは別の地で生まれ育った者ではあるが、今ではすっかりこの土地に馴染んでいる。
筆を持つ時は双鉤法(人指、中、親指で筆を支える方法をいう)が主体。好きな書家は褚遂良(スッキリとした字風)だが、自分の書風には似合わないというのを自覚している。
草書を最も得意とする。
---
『今ではこの命が情けない程に惜しい』
哘崎いま
22歳没。とあるギルドの処刑人だったが、方針に嫌気がさして脱退した。山中に若くして隠者のように暮らしていたところ、つぐみを拾う。
やがてつぐみが7つの頃、ギルドの者に居場所を掴まれ、更につぐみを殺すと脅されてしまい、意を決してギルドに従った。
だが、異郷の地で病死する。
このことをつぐみは知らない。しかし、魔手は着実につぐみへ迫っている。
哘崎つぐみ(さそざき つぐみ)
男性 28歳
173cm/56kg
普段は書道教室の先生をしているが、その実態は書術士という、墨痕を操る魔法使いである。
性格は温厚だがいささか穏やかに過ぎ、達観した何かがある。あるいはそれは諦観かもしれない。
元は山中に捨てられた子供であった。親の顔は知らず、〝哘崎いま〟という名の若い女性に拾われて育つ。書術士としてのノウハウもそこで学んだため、彼女は母であり師でもあった。
だが、つぐみが7つの時、突如として彼女は姿を消す。何やら後ろ暗い過去があった、ということくらいしか知らなかった。
7年経っても帰ってこなかったため、山を降り、人里に紛れて暮らしていた。
イバラシティとは別の地で生まれ育った者ではあるが、今ではすっかりこの土地に馴染んでいる。
筆を持つ時は双鉤法(人指、中、親指で筆を支える方法をいう)が主体。好きな書家は褚遂良(スッキリとした字風)だが、自分の書風には似合わないというのを自覚している。
草書を最も得意とする。
---
『今ではこの命が情けない程に惜しい』
哘崎いま
22歳没。とあるギルドの処刑人だったが、方針に嫌気がさして脱退した。山中に若くして隠者のように暮らしていたところ、つぐみを拾う。
やがてつぐみが7つの頃、ギルドの者に居場所を掴まれ、更につぐみを殺すと脅されてしまい、意を決してギルドに従った。
だが、異郷の地で病死する。
このことをつぐみは知らない。しかし、魔手は着実につぐみへ迫っている。
25 / 30
5 PS
チナミ区
F-9
F-9







| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 不思議な牙 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV5)[防具]活力10(LV5)[装飾]体力10(LV5) | |||
| 5 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]防御10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) | |||
| 6 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 幻術 | 10 | 夢幻/精神/光 |
| 呪術 | 10 | 呪詛/邪気/闇 |
| 防具 | 20 | 防具作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ライトニング | 5 | 0 | 50 | 敵:精確光撃 | |
| カース | 5 | 0 | 50 | 敵:闇撃&束縛 | |
| カタルシス | 5 | 0 | 60 | 敵強:SP光撃&強化を腐食化 | |
| ディム | 5 | 0 | 50 | 敵:SP光撃 | |
| ダークネス | 5 | 0 | 100 | 敵列:闇撃&盲目 | |
| マインドブレイク | 5 | 0 | 80 | 敵:SP闇撃&混乱 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 |
最大EP[20]





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]カタルシス |

PL / 秋原句外