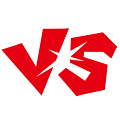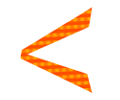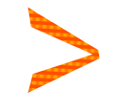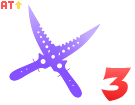<< 0:00~0:00




――薄暗い路地。
どこかの排水パイプが冷やした水が結露となり、泥の水溜まりに滴る不快な音。
土臭い、黴臭い匂いが周囲に充満していて、鼻が曲がりそうだ。
体中に纏わりつく粘つくような湿気に嫌気が差す。
倦怠感の中、若宮線引は人間の"死体"と向き合っている。
自分が何をしていたのか、唐突に思い出したように意識が覚醒する。
……惚けていた。早く処置を終わらせないと、それを運び出す別の役割の人間が来てしまう。
そうなる前に、俺は俺のための行為を行わなければならない。
指先に、"線"が躍る。
俺の異能。
――【指線引き】(ラインズマン)による、線が指先から形を成して抜けていく。
いくつも種類がある俺の異能は、この線がどの指から抜けていくかによって、効果が変わる。
思ったときに思った線が引けない自分が、紐づけをするために自分の異能に課した誓約でもある。
左手の人差し指から出たその線は、斜線の入った線。
……俺は縫い跡のようなこれを『縫合線』と呼んでいる。
指先から出た線でなぞった物同士を、物体の性質を無視して縫合する線だ。
ただ、他の線と同様、性質や法則を無視できるものは俺が"接続可能だと認識しているもの"に限るらしく、
恐る恐る試したものについてはすべて接合が離れてしまった。
要は、俺が世界を目でどう見ているか、どう感じているか、どう認識しているかに、
俺の異能は強く影響を受けるモノであるらしい。
逆に言えば。
結ぶことができる確証さえあれば、結べるということだ。
――で、あれば。
俺は今、確実にそれを、結ぶことができる。
この、堅気ではない家業を手伝う中、俺はそれを何度も見てきて、
そして自分の身体でも試し、確実にそれを結べるようになってきていた。
今では、並行して、複数個所同時にですら。
指先から出た『縫合線』は枝分かれし、男の"死体"の腹腔に吸い込まれていく。
今まで生きていた人間の熱い腸の中を、震える指先と鳴る歯の根を抑えながら、抉っていく。
出血はすでに止まっている。心臓が鼓動を止めているから、さらなる出血はない。
だから『縫合線』は簡単にそれを見つけ出し、そして本来繋がっている場所に向けてそれを動かしていく。
すなわち、それは『血管』であり、そして『神経』である。
綺麗に骨を避けてその男の身体を貫いた銃弾は、綺麗に臓器と心臓を避けて動脈だけを破壊したようで、
であればこの作業は、今までの二年間で、何度も何度も何度も繰り返してきた作業だ。
死体損壊という言葉が、実感なく両肩に乗っかる音がした。
この行為に意味はない。
だが、俺に死体を、弄ぶ趣味もない。
恐らく、組にバレれば何らかの咎めを受けるであろうそれを行う理由は一つだ。
いずれ、この技術が、生者相手にも使えるように。
今度は手遅れにならなかったときのために、俺は死体を弄んでいる。
人の死とは何だろうと、この作業をして思う。
今しがた凶弾によって命を奪われたこの男が喋るところを、俺は見ていた。
止めることはできなかったし、防ぐこともできなかった。
その銃弾に殺意がなかったことは知っていたし、それを撃った者も威嚇か、足止めのために発砲したことも知っていた。
今回、俺と組員はこの"死体"の男の捕縛を命じられていたからだ。
目の前のこの"死体"は、俺たちの組の同業他社の人間である。つまり、堅気の人間ではない。
こちらの組の――赤笠組の人間を一人殺している。
その後組を抜けたと聞いているため、切り捨てられたか、逃げたかのどちらかだ。
だからこそ、生きた状態でこの男を捕まえる必要があった。捕まえた後に、どうなるかは、さておいて、だ。
恐らく、この男は逃げようとしていた。
俺と行動を共にしていた組員が、逃すまいと脅しをかけ逃げ足を封じようと足に向けて発砲した銃弾が反れ、
路地裏を跳ね、腹から入り、胸を穿ち、背中から抜けた。
それは発砲した方にとっても、発砲された方にとってもただの不幸で、不運な事故でしかない。
路地から出た先で、発砲した組員が何やら大声で怒鳴る声がしている。
組への連絡か、或いは他の誰かに連絡しているのかもしれない。
俺は、意識を目の前の死体に戻す。
指先が触れる熱い"死体"の熱が、徐々に失われて行っていることに、気づいた。
修復は終わっている。
血管も、神経も、もしこれが骨が折れていたとしても。
その構造さえ理解していれば、俺は治すことができる。
学習を重ね理解し、いくつもの死体で実験し、自分の腕を切り裂いてみて確かめ、実践してきた。
医者が途方もない研鑽で技術を学び、可能にしていることを、自分の異能は可能にする。
世の中が、異能によって不公平になったことを、努力した者は嘆くだろうと思う。
そうだな。
世の中が不公平であることは。
俺も良く知っている。
そして、どれだけ傷を縫合しても、どれだけ体を治したとしても。
一度失われてしまった命は、戻らない。
生命の存在がどこにあるのかはわからないが、さっきまで生きていた人間も、
それが抜けてしまった後はもう、取り返しがつかない。
それが、人の死であり。
この世界が俺たちに課す、法則である。
死に触れ、感傷的にもなったのかもしれない。
その死体から失われていく熱を、
そしてその顔を、せめて俺だけは、
最期を看取った俺だけは忘れず覚えていようと思い、目を瞑ろうとした瞬間。
"死体"の手が動き。
腹腔に触れている俺の左手を掴んだ。
………え。

「どうして、センパイがそんな顔をしているんですか……?」
"死体"が喋った。
――"死体"は、風凪マナカだった
腹腔から、鮮血が溢れている。
視力のない俺の右目から血が滴る。
恐怖と混乱で歯の根が鳴った。

「……笑えますね、その顔」
一瞬の間を置いて。
俺の喉から、裂ける程の絶叫が迸る。
☆ ★ ☆ ★ ☆

――眠りからの覚醒は一瞬だ。
寮のベッドの上、寝汗でべとべとになった寝巻の胸をつかんだまま。
俺は無力に見慣れた天井を眺める。
息が荒い。心臓の鼓動が耳元で聞こえる。
それが、"悪夢"であったこと。
それが、"悪夢"でしかなかったことを理解し、安堵と苦悶の長い長い息が吐きだされた。
熱い、臓腑から熱を逃がすような吐息が吐き出されて、喉が焼ける。
荒い息を整えるようにしばらくそうしていると、視界に持ち上げた右手の上で、点線の刺青が這い回る。
親から線引なんて名前をもらったこと自体、呪いみたいなもんだ。俺はこれを、"制御"していかないといけない。
母親の腹の中に居たころから自分の異能は判明していて、それで親がつけた名前が線引だったという。
『名前に異能を記すのは、恐らく家系に於いて、紐づけが楽だからだろう。
何せ俺らは、数え切れぬ程ばら撒かれた枝葉の一節だろうからな』
俺と同じように異能の名をつけられた実兄は皮肉にそう笑って言ったのを覚えている。
思考が暴れる。考えるな。意味もないことを。
普段考えないようにしていたことまで頭の中に浮かんでは消え、心臓が鼓動を早める。
……落ち着け。
落ち着けよ自分。
何度も祈るように念じると、腕や手の上を這い回っていた線は徐々に這う速度を落としていく。
同時に呼吸と心臓の鼓動も徐々に落ち着き始める。
乾いていく寝汗によって、寒さを感じ、俺は掛け布団を胸元まで引き上げた。
……なんて、悪夢だよ。
有り得ない符丁が線を成すように繋がったその極上の悪夢は、
夢からの覚醒で霧散してくれるほど優しいものではなかった。
まるで現実であったかのように、失われていく熱も、鮮血の色も、はっきりと覚えている。
所詮夢だと思考を即座に切り替えられないくらい、それは現実感を帯びた夢だった。
恐らく。
ここ数日、風凪と行動することが多く。
色々と、自分の出自についても考えさせられることが多かったため。
そんな夢を見たんだと思う。
にしても。
「……それは、ねえだろ」
誰かに訴えかけるように、負け犬は乾いた笑いとともに右手で顔を覆った。
情けなすぎて、笑いが出る。
いつまでも過去を引きずって、それをあろうことか風凪と繋げてしまう自分の脳の構造を疑う。
そこにあるのは罪悪感であり、大切なことを秘匿している後ろめたさであり、
そして、高一の夏の日。
――嘘の告白をしたあの時からずっと引きずっている。
"風凪への負い目"から見てしまった夢だと考えれば、なんて情けない理由なんだと思った。
右手で顔を覆い。
そこで、違和感に気づいた。
ああ、成程。
悪夢を見るはずだ。
寝ている間に、器用に外してしまっていた右目の眼帯 ―― 拘束帯が外れてしまっている。
正しい手順を踏まなければ外れないようになっているので、恐らく寝ている間に自分で外したのだろう。
これを着け始めてからしばらく経つが、唯一、寝ている間意識を手放している間は、
未だに不快感があるせいかこうして外してしまうことも多い。
無意識だけはどうしようもない。要は、そうなるときに周囲に誰も居なければいいだけだ。
目覚めてすぐは気づかなかった。
俺は、眼帯の有無を『視界の違和感』によって気づくことができない。
右目は、眼帯があろうがなかろうが、今はもう『何も映していない』。
ある日を境に、俺の右目の視力は永遠に失われた。
両目を開いているはずの俺の視界の右側は、左目の視界のみで円形に区切られ、闇を映している。
かろうじて明るさだけは判別できるので、完全に死んだわけではないらしいが、それでも状態は『半盲』らしい。
原因は強烈な眼精疲労。医者はその原因を問うたが俺は答えられなかった。
ヤクザの稼業に於いて、己の目を酷使して異能を使用していることが原因だとわかっていたし、
それが原因だからといって、そこに処方する薬は医者にだって出せないだろうから。
それも、今考えてみれば、あの夢の中のように、
助けうる人間を助けられなかったときや、自分の心を守るための献身によって失われはじめたのだから、
医者だってそんな馬鹿につける薬は処方してくれないだろうと思う。
そんな馬鹿が、誰かを救おうと抗い、そして救いきれなかった無力が、俺の右目に『失明』という傷を刻んでいた。
思考が、面白くない方に進んでいく。
俺は、やはり、皮肉気に笑い、そのどうしようもないことを、寝しなに笑い飛ばした。
今更、何を後悔したって遅い。自分の正体が何であれ、今誰かに何かを必要とされるのなら。
許される間だけでも。俺は迷わず手を伸ばすだけだ。
エンドラインはもう引かれている。それが自分の引いた線ならば尚更。
――俺はどんな結末が訪れようと、後悔だけはしないと決めている。
「………」
今日もまた、いつもの日常が始まる。
それだけで十分で。それだけが必要な。
俺の大切な一日が始まる。



ENo.223 あかり とのやりとり




特に何もしませんでした。






制約LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)
防具LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)
マナカ(507) の持つ ItemNo.5 不思議な石 から防具『制服』を作製しました!
ItemNo.5 不思議な石 から防具『制服』を作製しました!
⇒ 制服/防具:強さ30/[効果1]防御10 [効果2]- [効果3]-/特殊アイテム
フタバ(515) により ItemNo.4 不思議な牙 から射程1の武器『点線』を作製してもらいました!
⇒ 点線/武器:強さ30/[効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程1】/特殊アイテム
アクト(1017) とカードを交換しました!
ヒール (ヒール)

ファイアボルト を研究しました!(深度0⇒1)
ファイアボルト を研究しました!(深度1⇒2)
ファイアボルト を研究しました!(深度2⇒3)
アサルト を習得!
ペナルティ を習得!
☆ピットトラップ を習得!
☆高速配置 を習得!
☆初習得ボーナス:各FPが4増加した!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





次元タクシーに乗り チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》 に転送されました!
チナミ区 E-6(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 E-7(道路)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 E-8(道路)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 E-9(草原)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 F-9(沼地)に移動!(体調26⇒25)
マナカ(507) からパーティに勧誘されました!






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャットで時間が伝えられる。
グチャッとなったどこかのナレハテの映像をまじまじと見つめる白南海。
その背後から、突然タクシーが現れる!!
白南海のすぐ横を走り抜け、止まる。
タクシーの窓が開く。

帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。
窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。
白南海からのチャットが閉じられる――














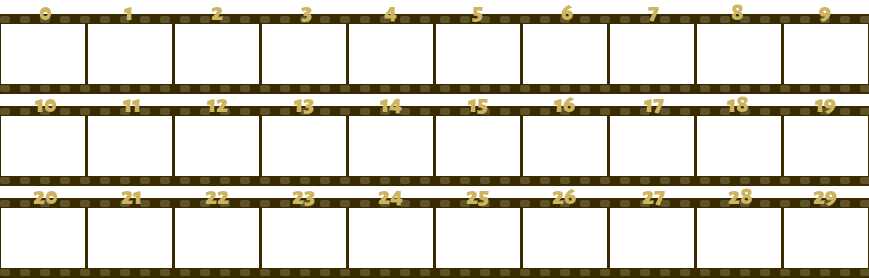





































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



――薄暗い路地。
どこかの排水パイプが冷やした水が結露となり、泥の水溜まりに滴る不快な音。
土臭い、黴臭い匂いが周囲に充満していて、鼻が曲がりそうだ。
体中に纏わりつく粘つくような湿気に嫌気が差す。
倦怠感の中、若宮線引は人間の"死体"と向き合っている。
自分が何をしていたのか、唐突に思い出したように意識が覚醒する。
……惚けていた。早く処置を終わらせないと、それを運び出す別の役割の人間が来てしまう。
そうなる前に、俺は俺のための行為を行わなければならない。
指先に、"線"が躍る。
俺の異能。
――【指線引き】(ラインズマン)による、線が指先から形を成して抜けていく。
いくつも種類がある俺の異能は、この線がどの指から抜けていくかによって、効果が変わる。
思ったときに思った線が引けない自分が、紐づけをするために自分の異能に課した誓約でもある。
左手の人差し指から出たその線は、斜線の入った線。
……俺は縫い跡のようなこれを『縫合線』と呼んでいる。
指先から出た線でなぞった物同士を、物体の性質を無視して縫合する線だ。
ただ、他の線と同様、性質や法則を無視できるものは俺が"接続可能だと認識しているもの"に限るらしく、
恐る恐る試したものについてはすべて接合が離れてしまった。
要は、俺が世界を目でどう見ているか、どう感じているか、どう認識しているかに、
俺の異能は強く影響を受けるモノであるらしい。
逆に言えば。
結ぶことができる確証さえあれば、結べるということだ。
――で、あれば。
俺は今、確実にそれを、結ぶことができる。
この、堅気ではない家業を手伝う中、俺はそれを何度も見てきて、
そして自分の身体でも試し、確実にそれを結べるようになってきていた。
今では、並行して、複数個所同時にですら。
指先から出た『縫合線』は枝分かれし、男の"死体"の腹腔に吸い込まれていく。
今まで生きていた人間の熱い腸の中を、震える指先と鳴る歯の根を抑えながら、抉っていく。
出血はすでに止まっている。心臓が鼓動を止めているから、さらなる出血はない。
だから『縫合線』は簡単にそれを見つけ出し、そして本来繋がっている場所に向けてそれを動かしていく。
すなわち、それは『血管』であり、そして『神経』である。
綺麗に骨を避けてその男の身体を貫いた銃弾は、綺麗に臓器と心臓を避けて動脈だけを破壊したようで、
であればこの作業は、今までの二年間で、何度も何度も何度も繰り返してきた作業だ。
死体損壊という言葉が、実感なく両肩に乗っかる音がした。
この行為に意味はない。
だが、俺に死体を、弄ぶ趣味もない。
恐らく、組にバレれば何らかの咎めを受けるであろうそれを行う理由は一つだ。
いずれ、この技術が、生者相手にも使えるように。
今度は手遅れにならなかったときのために、俺は死体を弄んでいる。
人の死とは何だろうと、この作業をして思う。
今しがた凶弾によって命を奪われたこの男が喋るところを、俺は見ていた。
止めることはできなかったし、防ぐこともできなかった。
その銃弾に殺意がなかったことは知っていたし、それを撃った者も威嚇か、足止めのために発砲したことも知っていた。
今回、俺と組員はこの"死体"の男の捕縛を命じられていたからだ。
目の前のこの"死体"は、俺たちの組の同業他社の人間である。つまり、堅気の人間ではない。
こちらの組の――赤笠組の人間を一人殺している。
その後組を抜けたと聞いているため、切り捨てられたか、逃げたかのどちらかだ。
だからこそ、生きた状態でこの男を捕まえる必要があった。捕まえた後に、どうなるかは、さておいて、だ。
恐らく、この男は逃げようとしていた。
俺と行動を共にしていた組員が、逃すまいと脅しをかけ逃げ足を封じようと足に向けて発砲した銃弾が反れ、
路地裏を跳ね、腹から入り、胸を穿ち、背中から抜けた。
それは発砲した方にとっても、発砲された方にとってもただの不幸で、不運な事故でしかない。
路地から出た先で、発砲した組員が何やら大声で怒鳴る声がしている。
組への連絡か、或いは他の誰かに連絡しているのかもしれない。
俺は、意識を目の前の死体に戻す。
指先が触れる熱い"死体"の熱が、徐々に失われて行っていることに、気づいた。
修復は終わっている。
血管も、神経も、もしこれが骨が折れていたとしても。
その構造さえ理解していれば、俺は治すことができる。
学習を重ね理解し、いくつもの死体で実験し、自分の腕を切り裂いてみて確かめ、実践してきた。
医者が途方もない研鑽で技術を学び、可能にしていることを、自分の異能は可能にする。
世の中が、異能によって不公平になったことを、努力した者は嘆くだろうと思う。
そうだな。
世の中が不公平であることは。
俺も良く知っている。
そして、どれだけ傷を縫合しても、どれだけ体を治したとしても。
一度失われてしまった命は、戻らない。
生命の存在がどこにあるのかはわからないが、さっきまで生きていた人間も、
それが抜けてしまった後はもう、取り返しがつかない。
それが、人の死であり。
この世界が俺たちに課す、法則である。
死に触れ、感傷的にもなったのかもしれない。
その死体から失われていく熱を、
そしてその顔を、せめて俺だけは、
最期を看取った俺だけは忘れず覚えていようと思い、目を瞑ろうとした瞬間。
"死体"の手が動き。
腹腔に触れている俺の左手を掴んだ。
………え。

「どうして、センパイがそんな顔をしているんですか……?」
"死体"が喋った。
――"死体"は、風凪マナカだった
腹腔から、鮮血が溢れている。
視力のない俺の右目から血が滴る。
恐怖と混乱で歯の根が鳴った。

「……笑えますね、その顔」
一瞬の間を置いて。
俺の喉から、裂ける程の絶叫が迸る。
☆ ★ ☆ ★ ☆

――眠りからの覚醒は一瞬だ。
寮のベッドの上、寝汗でべとべとになった寝巻の胸をつかんだまま。
俺は無力に見慣れた天井を眺める。
息が荒い。心臓の鼓動が耳元で聞こえる。
それが、"悪夢"であったこと。
それが、"悪夢"でしかなかったことを理解し、安堵と苦悶の長い長い息が吐きだされた。
熱い、臓腑から熱を逃がすような吐息が吐き出されて、喉が焼ける。
荒い息を整えるようにしばらくそうしていると、視界に持ち上げた右手の上で、点線の刺青が這い回る。
親から線引なんて名前をもらったこと自体、呪いみたいなもんだ。俺はこれを、"制御"していかないといけない。
母親の腹の中に居たころから自分の異能は判明していて、それで親がつけた名前が線引だったという。
『名前に異能を記すのは、恐らく家系に於いて、紐づけが楽だからだろう。
何せ俺らは、数え切れぬ程ばら撒かれた枝葉の一節だろうからな』
俺と同じように異能の名をつけられた実兄は皮肉にそう笑って言ったのを覚えている。
思考が暴れる。考えるな。意味もないことを。
普段考えないようにしていたことまで頭の中に浮かんでは消え、心臓が鼓動を早める。
……落ち着け。
落ち着けよ自分。
何度も祈るように念じると、腕や手の上を這い回っていた線は徐々に這う速度を落としていく。
同時に呼吸と心臓の鼓動も徐々に落ち着き始める。
乾いていく寝汗によって、寒さを感じ、俺は掛け布団を胸元まで引き上げた。
……なんて、悪夢だよ。
有り得ない符丁が線を成すように繋がったその極上の悪夢は、
夢からの覚醒で霧散してくれるほど優しいものではなかった。
まるで現実であったかのように、失われていく熱も、鮮血の色も、はっきりと覚えている。
所詮夢だと思考を即座に切り替えられないくらい、それは現実感を帯びた夢だった。
恐らく。
ここ数日、風凪と行動することが多く。
色々と、自分の出自についても考えさせられることが多かったため。
そんな夢を見たんだと思う。
にしても。
「……それは、ねえだろ」
誰かに訴えかけるように、負け犬は乾いた笑いとともに右手で顔を覆った。
情けなすぎて、笑いが出る。
いつまでも過去を引きずって、それをあろうことか風凪と繋げてしまう自分の脳の構造を疑う。
そこにあるのは罪悪感であり、大切なことを秘匿している後ろめたさであり、
そして、高一の夏の日。
――嘘の告白をしたあの時からずっと引きずっている。
"風凪への負い目"から見てしまった夢だと考えれば、なんて情けない理由なんだと思った。
右手で顔を覆い。
そこで、違和感に気づいた。
ああ、成程。
悪夢を見るはずだ。
寝ている間に、器用に外してしまっていた右目の眼帯 ―― 拘束帯が外れてしまっている。
正しい手順を踏まなければ外れないようになっているので、恐らく寝ている間に自分で外したのだろう。
これを着け始めてからしばらく経つが、唯一、寝ている間意識を手放している間は、
未だに不快感があるせいかこうして外してしまうことも多い。
無意識だけはどうしようもない。要は、そうなるときに周囲に誰も居なければいいだけだ。
目覚めてすぐは気づかなかった。
俺は、眼帯の有無を『視界の違和感』によって気づくことができない。
右目は、眼帯があろうがなかろうが、今はもう『何も映していない』。
ある日を境に、俺の右目の視力は永遠に失われた。
両目を開いているはずの俺の視界の右側は、左目の視界のみで円形に区切られ、闇を映している。
かろうじて明るさだけは判別できるので、完全に死んだわけではないらしいが、それでも状態は『半盲』らしい。
原因は強烈な眼精疲労。医者はその原因を問うたが俺は答えられなかった。
ヤクザの稼業に於いて、己の目を酷使して異能を使用していることが原因だとわかっていたし、
それが原因だからといって、そこに処方する薬は医者にだって出せないだろうから。
それも、今考えてみれば、あの夢の中のように、
助けうる人間を助けられなかったときや、自分の心を守るための献身によって失われはじめたのだから、
医者だってそんな馬鹿につける薬は処方してくれないだろうと思う。
そんな馬鹿が、誰かを救おうと抗い、そして救いきれなかった無力が、俺の右目に『失明』という傷を刻んでいた。
思考が、面白くない方に進んでいく。
俺は、やはり、皮肉気に笑い、そのどうしようもないことを、寝しなに笑い飛ばした。
今更、何を後悔したって遅い。自分の正体が何であれ、今誰かに何かを必要とされるのなら。
許される間だけでも。俺は迷わず手を伸ばすだけだ。
エンドラインはもう引かれている。それが自分の引いた線ならば尚更。
――俺はどんな結末が訪れようと、後悔だけはしないと決めている。
「………」
今日もまた、いつもの日常が始まる。
それだけで十分で。それだけが必要な。
俺の大切な一日が始まる。



ENo.223 あかり とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||



特に何もしませんでした。





制約LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)
防具LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)
マナカ(507) の持つ ItemNo.5 不思議な石 から防具『制服』を作製しました!
ItemNo.5 不思議な石 から防具『制服』を作製しました!
⇒ 制服/防具:強さ30/[効果1]防御10 [効果2]- [効果3]-/特殊アイテム
フタバ(515) により ItemNo.4 不思議な牙 から射程1の武器『点線』を作製してもらいました!
⇒ 点線/武器:強さ30/[効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程1】/特殊アイテム
アクト(1017) とカードを交換しました!
ヒール (ヒール)

ファイアボルト を研究しました!(深度0⇒1)
ファイアボルト を研究しました!(深度1⇒2)
ファイアボルト を研究しました!(深度2⇒3)
アサルト を習得!
ペナルティ を習得!
☆ピットトラップ を習得!
☆高速配置 を習得!
☆初習得ボーナス:各FPが4増加した!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





次元タクシーに乗り チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》 に転送されました!
 |
ドライバーさん 「ほら降りた降りた。次の客が待ってんだわ。」 |
チナミ区 E-6(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 E-7(道路)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 E-8(道路)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 E-9(草原)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 F-9(沼地)に移動!(体調26⇒25)
マナカ(507) からパーティに勧誘されました!






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
白南海 「長針一周・・・っと。丁度1時間っすね。」 |

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
チャットで時間が伝えられる。
 |
白南海 「ケンカは無事済みましたかね。 こてんぱんにすりゃいいってわけですかい。」 |
グチャッとなったどこかのナレハテの映像をまじまじと見つめる白南海。
その背後から、突然タクシーが現れる!!
白南海のすぐ横を走り抜け、止まる。
 |
白南海 「・・・・・こ、殺す気ですかね。」 |
タクシーの窓が開く。

ドライバーさん
次元タクシーの運転手。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。初老くらいに見える。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。初老くらいに見える。
 |
ドライバーさん 「すまんすまん、出口の座標を少し間違えた。 挨拶に来たぜ。『次元タクシー』の運転役だ。」 |
帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。
 |
白南海 「イバラシティ側を潰そうってんじゃねぇでしょーね。・・・ぶっ殺しますよ?」 |
 |
ドライバーさん 「安心しな、どっちにも加勢するさ。俺らはそういう役割の・・・ハザマの機能ってとこだ。」 |
 |
ドライバーさん 「チェックポイントとかの行き来の際にゃ、へいタクシーの一声を。 俺もタクシーも同じのが沢山"在る"んでな、待たしゃしない。・・・そんじゃ。」 |
窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。
 |
白南海 「ひとを轢きかけといてあの態度・・・後で営業妨害でもしてやろうか。」 |
 |
白南海 「さて、それでは私は・・・のんびり傍観させてもらいますかね。この役も悪くない。」 |
白南海からのチャットが閉じられる――





ENo.506
若宮線引



◆若宮 線引(ワカミヤ センビキ)
相良伊橋高校 2年1組 特進クラス
8/15生まれ 身長177cm
交友関係は広く浅い。
悪友と呼べる人間は多いが、親友と呼べる人間は少ない。
表面上は明るいがある一定のラインを引いて、交友を遠ざける癖がある。
生家の商売がカタギではない自由業を営んでいることに起因している。
彼を軽く「ワカ」「ワカ君」と呼ぶ相手は割と親しい。
好きな物はシンプルな物と当たり前の物
苦手な物は辛い物と風凪マナカ
右目に赤い眼帯をしており、
それは手順を踏まなければ拘束具のように外れることはない。
学校側には説明済みで、曰く
『右目を完全に失明しているので雑菌が入らないように』
と届けている。
実際に、彼の右目に視力はない。
◆【指線引き】(ラインズマン)
意識した視界の中に"線"を引く異能。
引く線によって効果が違う。
線の種類は即座に使用可能なものでも20種類以上ある。
普段"線"は点線として生き物のように線引の体の見えないところを
這いまわっており、動く刺青のように見える。
代表的な線は
『切取線』(キリトリ線)
『導火線』(ドウカ線)
『停止線』(テイシ線)
『縫合線』(ホウゴウ線)など
◇既知フリーです
相良伊橋高校 2年1組 特進クラス
8/15生まれ 身長177cm
交友関係は広く浅い。
悪友と呼べる人間は多いが、親友と呼べる人間は少ない。
表面上は明るいがある一定のラインを引いて、交友を遠ざける癖がある。
生家の商売がカタギではない自由業を営んでいることに起因している。
彼を軽く「ワカ」「ワカ君」と呼ぶ相手は割と親しい。
好きな物はシンプルな物と当たり前の物
苦手な物は辛い物と風凪マナカ
右目に赤い眼帯をしており、
それは手順を踏まなければ拘束具のように外れることはない。
学校側には説明済みで、曰く
『右目を完全に失明しているので雑菌が入らないように』
と届けている。
実際に、彼の右目に視力はない。
◆【指線引き】(ラインズマン)
意識した視界の中に"線"を引く異能。
引く線によって効果が違う。
線の種類は即座に使用可能なものでも20種類以上ある。
普段"線"は点線として生き物のように線引の体の見えないところを
這いまわっており、動く刺青のように見える。
代表的な線は
『切取線』(キリトリ線)
『導火線』(ドウカ線)
『停止線』(テイシ線)
『縫合線』(ホウゴウ線)など
◇既知フリーです
25 / 30
5 PS
チナミ区
F-9
F-9


























| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 点線 | 武器 | 30 | 攻撃10 | - | - | 【射程1】 |
| 5 | 制服 | 防具 | 30 | 防御10 | - | - | |
| 6 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 制約 | 20 | 拘束/罠/リスク |
| 防具 | 20 | 防具作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| アサルト | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃+自:連続減 | |
| ペナルティ | 5 | 0 | 120 | 敵3:麻痺・混乱 | |
| ピットトラップ | 5 | 0 | 120 | 敵全:罠《奈落》LV増 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 高速配置 | 5 | 4 | 0 | 【スキル使用後】自:直前に使用したスキル名に「トラップ」が含まれるなら、連続増 |
最大EP[20]





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]ファイアボルト |

PL / れじにてぃ