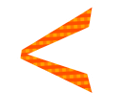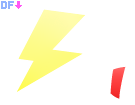<< 4:00>> 6:00




さもありなん、といった様子でその場を陣取っている。
不敵、と言うよりは不敬と表した方が正しい態度。危うく異能に誑かされる所であり、その事が思ったより男を不機嫌にさせている。平時、誰かを異能で誑かす男は自身がいざそうなれば、我慢ならぬ質だ。子供の様だ、と語るのはさておいて――店主はいらっしゃるか。その言葉が、ゆんゆんと屋敷の中を通る。失われなかった左階段を背に。見た目は大理石だが、このごつごつとした感覚が尻に伝わる以上、この床も恐らく幻。整備されていない地面だとか、そういう類を想起させられる。実の所、この屋敷そのものが虚構で、実際は襤褸小屋ではないかとすら、この男は考えている。挙げた声へのリアクションを期待して、顎を撫でて待つ事暫し。
かつ、と段を踏む音。背後の左階段。お出ましになった。徐に、首を捻って振り向く。のっぺりとした印象を受ける階段を降りる人影は、想像していたよりも小さい。身長にして、150㎝にも満たない非常に小柄な体格。腕、脚も相応に小さく、丸みを帯びた――子供を想起させるシルエット。【神】を宿す者を、そういった見目で判断するのは無為な事だと分かっていても、僅かな驚きは隠せない。仮にも、それなりの規模に干渉する幻術使いと見立てていた物だから。男の思索を知ってか知らずか、その影は悪童めいた笑みを浮かべていた。段を一つ下るにつれて、姿がはっきりと映る。子供のよう、ではなく本当に子供だ。悪童めいた、ではなく本当に悪童だ。無造作に伸ばされたブロンド色が床を引き摺り、髪は悪童の背を覆っている。喪服の様な黒を纏い、上下は存外きちりと揃えられていた。バンリの洞めいた赤を受け止める瞳の色は、これ亦形容のしようがない。獣、だとか、爬虫類だとか――既存のそれに当て嵌める事自体が不適切な色と貌。辛うじて、例えられるなら玉虫色。それから、褐色の肌と。
「なあ、小童」
それは、口角に皺寄せて語る。その一言で、これが"幼く"はないと分かった。
小首を傾げ、ブロンドを揺らす。そんな動作さえ、何処か白々しい物に見えるのだ。
思わず、男は肩を寄せ竦めていただろう。単なる不快感ではなく、ともすれば同族嫌悪に等しい感覚を。同じ匂いがした。とびきり異質な第一印象から。男女の境界が曖昧なそれは、自らに向けられた感情を身に受け、舌を出す。幼くはないが、しかし子供だ。その場に座すまま、男は動かない。言外に、お前が店主か――と語り掛けながら。
「つまらんな、小童」
すると、最後の段を下った悪童は口をへの字に曲げる。
さして目に見えた、或いはそれらしい驚きを露わにしていない事に対して。
そこに「それも幻か」――と、疑って掛かる言葉を向けたのは、男の方からだった。
きょとり、と異様な色をした目を丸めて、二度悪童は瞬きをする。そのまま、男の背に向かって歩み寄りながらくつくつと笑った。今一、よく分からないと云うのが男の抱く印象。半ほど距離を詰めた所で、悪童を膝を曲げて胡坐を掻く男に視線を合わせる。横に広げた口からは八重歯が覗き、何時の間にか片手にはシガー(葉巻たばこ)を握っていた。
「おまえがしたのと同じよう、私にも蹴り付けてみるか、小童?
けれど、それは趣味に非ずとおまえは笑うかな。でもな、小童。私はおまえの右頬を打った」
「――だから、いっそそれで左頬を差し出してみなさい、と云うならば貴方には好感が持てる」
「いいや、私は生憎とも敬虔なクリスチャンではないのでな。
ハンムラビ法典の通り、目には目を歯には歯を。こちらで宜しくしてもらおうか、小童」
「それは残念だ。バベルはとうに崩れているのに。 ――それでも、郷に入っては郷に従えと云う」
胡坐を解いて立ち上がる。バンリなる男には、呵責が無い。残った半を歩み寄り、目下から見上げる悪童の眼球が舐める様にして、自身を観察している事は余程気に入らなかったのか。郷に従い、雑に突き上げた膝が悪童の鳩尾を打つ。瞬きをする間の事だった。派手な音を立てるでもなく、悪童の胃の中身が揺らされる感覚と、生理的に呻く音が上がっただけ。蹲る事もせず、膝の入った悪童はよろめく。床に垂れる髪を踏んで、幾本かを引き抜く――引き千切ってしまっていたが、それを気にも留めず、変わらず玉虫色は洞を射抜いていた。
「満足したか」 ――いやに挑発的な声音で、"そういう"手合いの見せかけを通す悪童。
付き合えた物ではない、とは男に在る言。同族嫌悪の気を感じつつ、彼らの様な手合いは、同じもの同士では埒が明かない。それに、膝を入れた悪童の姿は已然としてそのまま。強固な幻術が術者自身に展開されているならばさておき、先程の幻に依る法則に従えば、是はありのままの姿なのだろう。呻くのも束の間、悪童は片手のシガーを咥え込んで男の返事を待っている。
「――……貴方がそこにいる事を切に願うばかりかな」
満足した、とは一言も応えないまま。そう応えてしまえば、向こうの掌で踊らされている様な気がして。結局、舌からぽろりと落ちたのは皮肉交じりで、ジョークの一つも効かぬ言葉。是に所用が無ければ、面の皮を剥いでやるだとか、そういった事も男は厭わない。然し、生憎とも今日は明確な目的あっての事。決して、遊びに来た訳ではないのだ。だから、改めて悪童に目を向ける。まさか、全くの無関係でない筈だ。
「それに、そう。そうだ、己の問いを保留したまま。貴方に、答えて戴かねば。
店主はいらっしゃるか――と聞いたのだ。ここは、骨董店だと聞き及んでいるので」
何でもない様に、問い掛ける。対して、ぷ、と如何にも嘲った声を出すのが眼前の悪童。不愉快とまで行かずとも、向けられて決して気持ちの良い対応ではない。同類、同族の気はあるが――真面目か、不真面目か。そこの二人に、それぐらいの違いは有るだろう。ふるりと口角を釣る悪童は手をひらひら振って、すっかり玉虫色の瞳を細めた目の向こうに覗かせていた。
「――は。 呼ばれたから、出てきたのだぞ。私だ、私。もっと大仰な格好をすれば小童にも伝わったか?」
シガーに火を点けず、唯々八重歯で噛み潰して言い放つ様は、一転して不機嫌であるらしい。使いや店員でなく、店主本人であるのは、妙に自信ありげな態度から疑いようも無い。小柄、かつ華奢な見目からは想像が及ばない程にハスキーな声で凄む、悪童改め店主。最初からそう言えば、妙なやり取りもせずに済んだと考えるのは無粋かもしれない。
「まぁ、良いわ」 ――今時珍しいまでに不遜な態度は、客に何か余計な口を挟ませる気も無く言葉を切って、空気の転換。一瞬、その面に並ぶパーツが失せて、のっぺりとした顔で笑う様に思えたのは大方気のせいか、この店主が幻術使いであるからか。鳩尾の埃を払いながら、漸くらしい事を口にする――いらっしゃいませ、とこの上なく厭味を込めて。何処か他人事の様に、立地を含めて碌に客も来ないだろう、なんて男は眉を僅かに寄せた。いやしかし、バンリなる男は骨董店を訪れはしたが、骨董を求めてではない。或いは、その求む手掛かりこそが一種の骨董と言われれば納得もしようが。故に、どう切り出すべきか――振り出しめいて、そう考えた。決して、無策で及んだ訳でもない。そも、ただ店先に向かうと云うお題目がこうなるとは思わなかった事が総てだ。こうして無用に考える事の、何とつまらない事か。
「ひとまず、"案内"して戴きたい」
どちらかと言えば、慇懃無礼として落とされる言葉。見回せど、この殺風景な玄関ホールには骨董店を思わしき要素が見当たらない、と思い。それこそ、適当に取ってつけた様な扉が幾らでもあるが、どうにも腑に落ちない。本人に聴く方が、余程早かろう。案の定と言うべきか、店主は片瞼を閉じて反応を見せる。それがつまらない、と言外に語っているのは目に見えた事だ。
「…何と冒険心の無い。そこな、立ち並ぶ扉があろうよ。物珍しげであろうよ。
不用意に近付いて開いて見る、と言う気持ちのひとつも起こらんと言うのか、つまらん」
「猿であるまいし、さもありなんと並べられた物に態々触る様な真似はしたくないので――。
ああ、貴方は矢張り幼子ではなかろうか。自らを屋敷の主だと嘯きたい、年頃の小童でなかろうか」
茶番。舞台めいた返しを吐き捨て、厭味の返戻。事実、その様な単純さで脚を引こうとしているのは、幼子の所業か――頭が足りていないかのどちらか。だが、店主はそれ以上乗らない。それ以上、その言葉で刺す事を行わない。引き際を弁えているのは、同類だからか。鼻に掛かる前髪を鬱陶しげに横へ寄せた後背を翻し、無言で踏み出す――店主が向かう先と言えば、どの扉でも、ましてや階段でもなく、玄関先。外へ出て往くつもりらしい。
「二階は生活圏。一階(ここ)は……遊び場、」
そして、男が疑問を呈する前に、翻す小さな背から語る。何たる無駄遣い。
或いは、決してこの悪童独りで暮らしている訳でもないのかもしれない。如何にも、と言った口調を借りて語り、実年齢が見目にそぐわないとしても、是のやる事は見た目からの連想で然程変わりない。髪を引き摺ったまま、身長との対比が目立つ屋敷の扉を押し開ければ、二度目の幻は無く。さ、と扉の隙間から拡散する陽光とのコントラストが、屋敷の中の薄暗さを示し出す。
玄関先の風景は、立ち入った時と変わらず。大規模な幻と改めて認識した今は、これらの風景の幾つが幻なのだろうか、と男は考えるばかり。草木を踏み締める音、小さな背を追えば、玄関先から左折して――屋敷の外壁と、石垣の間に出来た隙間に店主は入って行く。成人男性の身で、その小さな隙間を通り抜けるのは何とも苦労しそうな構図だ。なので、すいすいと進む店主に対して、バンリは身を縮めて恐る恐る通り抜ける羽目になった。先を往く店主と言えば、それがさも当然であると言う態度が背からありありと感じ取れて、背後を省みる。それを一切する筈も無かった。
随分と長く感じた細道も、確かな光――終わりを目にすれば、安堵。先に出た店主を追い、服を石垣を擦りながら、少々の早足で――抜けた。丁度、そこは屋敷の裏手。屋敷のある敷地へ向かう路地裏からは想像がつかぬ程、路地の内に広がった空間は広大だ。そして、裏手の空間にぽつりと建っている物は――粗末な小屋。この光景こそ、取って付けた様で。衣服の埃を払いながら、男の向けた疑念の目。それも一瞥する事なく流され、店主は小屋へ。立て付けの悪い引き戸に手を掛け、両手で開け放てば木々が擦れ、或いは折れる音。お世辞にも、それに邪魔したいとは思わない――
「店は、こっち。 ――腑抜けた面をしてくれるなよ、小童」
のに、現実が思い通りに行く筈もなく。告げられた事実は、聳える屋敷とはかけ離れた襤褸小屋こそが、本命であった事。確かに一度、その屋敷は虚構で、襤褸小屋かもしれない――抱きはしたが、近い事実がより不可解な形であると知れば、内心肩を落とした。引き返す、と言う選択肢はハナから頭に無いが、代わりに頭痛がする、とでも言えばいいか。
だが、冗長なそれを乗り越えて漸く、本分に入れそうなのだ。要らぬ躊躇いは横に退けておくが吉。しかして、溜息を舌で転がしつつ、身体を捻ってちらと己の洞を見つめる玉虫色に誘われるよう【骨董店】へと向かうのであった――。



shadow(159) に ItemNo.8 美味しい果実 を手渡ししました。
ItemNo.11 サンドイッチのバスケット を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(10⇒11)
今回の全戦闘において 治癒10 活力10 鎮痛10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!












チェックポイントから天に向け、赤色の光柱が立つ。
次元タクシーで行けるようになったようだ。



shadow(159) は ネジ を入手!
バンリ(296) は ネジ を入手!
色蝕の塊(676) は ド根性雑草 を入手!
ソースケ(681) は ネジ を入手!
ソースケ(681) は 花びら を入手!
バンリ(296) は 毛 を入手!
色蝕の塊(676) は 毛 を入手!
shadow(159) は 毛 を入手!
色蝕の塊(676) は 何か柔らかい物体 を入手!
shadow(159) は 何か柔らかい物体 を入手!
色蝕の塊(676) は 何か柔らかい物体 を入手!



合成LV を 1 DOWN。(LV1⇒0、+1CP、-1FP)
命術LV を 1 UP!(LV9⇒10、-1CP)
幻術LV を 2 UP!(LV0⇒2、-2CP)
装飾LV を 4 UP!(LV28⇒32、-4CP)
シキ(1568) とカードを交換しました!
滅の四番 (エナジードレイン)

ブラッドシェド を研究しました!(深度1⇒2)
ブラッドシェド を研究しました!(深度2⇒3)
ミラージュ を研究しました!(深度0⇒1)
水特性回復 を習得!
リップル を習得!
氷水避け を習得!



shadow(159) に移動を委ねました。
チナミ区 H-15(チェックポイント)に移動!(体調11⇒10)
採集はできませんでした。
- shadow(159) の選択は チナミ区 H-15:釣り堀(ベースキャンプ外のため無効)
- バンリ(296) の選択は チナミ区 H-15:釣り堀(ベースキャンプ外のため無効)
- 色蝕の塊(676) の選択は チナミ区 E-5:出発地(ベースキャンプ外のため無効)
- ソースケ(681) の選択は チナミ区 H-15:釣り堀(ベースキャンプ外のため無効)
MISSION - 未発生:
- バンリ(296) の選択は チナミ区 H-15:釣り堀(ベースキャンプ外のため無効)
- 色蝕の塊(676) の選択は チナミ区 H-15:釣り堀(ベースキャンプ外のため無効)
- ソースケ(681) の選択は チナミ区 H-15:釣り堀(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。

時計台の前でタバコをふかす、ドライバーさん。
時計台をぼーっと見上げる。
自分の腕時計を確認する。
・・・とても嫌そうな表情になる。


















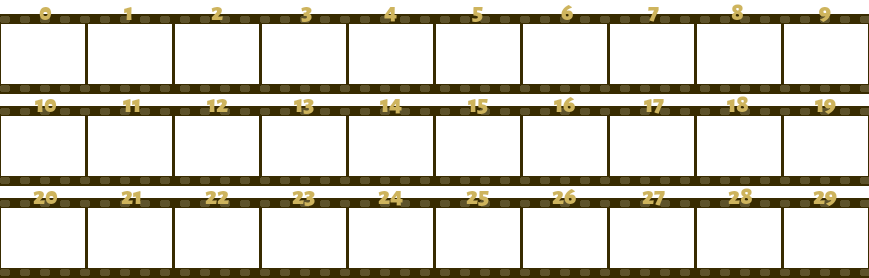





































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



⇒ 【#5 Phantom】
幻影。虚像。――例えば、あの世界。この世界。些細なこと。
眼前に在る景色の真偽。偽り、欺きのいろ。掻き乱す現実。お前の観る世界の正しさとは、何か――。
幻影。虚像。――例えば、あの世界。この世界。些細なこと。
眼前に在る景色の真偽。偽り、欺きのいろ。掻き乱す現実。お前の観る世界の正しさとは、何か――。
さもありなん、といった様子でその場を陣取っている。
不敵、と言うよりは不敬と表した方が正しい態度。危うく異能に誑かされる所であり、その事が思ったより男を不機嫌にさせている。平時、誰かを異能で誑かす男は自身がいざそうなれば、我慢ならぬ質だ。子供の様だ、と語るのはさておいて――店主はいらっしゃるか。その言葉が、ゆんゆんと屋敷の中を通る。失われなかった左階段を背に。見た目は大理石だが、このごつごつとした感覚が尻に伝わる以上、この床も恐らく幻。整備されていない地面だとか、そういう類を想起させられる。実の所、この屋敷そのものが虚構で、実際は襤褸小屋ではないかとすら、この男は考えている。挙げた声へのリアクションを期待して、顎を撫でて待つ事暫し。
かつ、と段を踏む音。背後の左階段。お出ましになった。徐に、首を捻って振り向く。のっぺりとした印象を受ける階段を降りる人影は、想像していたよりも小さい。身長にして、150㎝にも満たない非常に小柄な体格。腕、脚も相応に小さく、丸みを帯びた――子供を想起させるシルエット。【神】を宿す者を、そういった見目で判断するのは無為な事だと分かっていても、僅かな驚きは隠せない。仮にも、それなりの規模に干渉する幻術使いと見立てていた物だから。男の思索を知ってか知らずか、その影は悪童めいた笑みを浮かべていた。段を一つ下るにつれて、姿がはっきりと映る。子供のよう、ではなく本当に子供だ。悪童めいた、ではなく本当に悪童だ。無造作に伸ばされたブロンド色が床を引き摺り、髪は悪童の背を覆っている。喪服の様な黒を纏い、上下は存外きちりと揃えられていた。バンリの洞めいた赤を受け止める瞳の色は、これ亦形容のしようがない。獣、だとか、爬虫類だとか――既存のそれに当て嵌める事自体が不適切な色と貌。辛うじて、例えられるなら玉虫色。それから、褐色の肌と。
「なあ、小童」
それは、口角に皺寄せて語る。その一言で、これが"幼く"はないと分かった。
小首を傾げ、ブロンドを揺らす。そんな動作さえ、何処か白々しい物に見えるのだ。
思わず、男は肩を寄せ竦めていただろう。単なる不快感ではなく、ともすれば同族嫌悪に等しい感覚を。同じ匂いがした。とびきり異質な第一印象から。男女の境界が曖昧なそれは、自らに向けられた感情を身に受け、舌を出す。幼くはないが、しかし子供だ。その場に座すまま、男は動かない。言外に、お前が店主か――と語り掛けながら。
「つまらんな、小童」
すると、最後の段を下った悪童は口をへの字に曲げる。
さして目に見えた、或いはそれらしい驚きを露わにしていない事に対して。
そこに「それも幻か」――と、疑って掛かる言葉を向けたのは、男の方からだった。
きょとり、と異様な色をした目を丸めて、二度悪童は瞬きをする。そのまま、男の背に向かって歩み寄りながらくつくつと笑った。今一、よく分からないと云うのが男の抱く印象。半ほど距離を詰めた所で、悪童を膝を曲げて胡坐を掻く男に視線を合わせる。横に広げた口からは八重歯が覗き、何時の間にか片手にはシガー(葉巻たばこ)を握っていた。
「おまえがしたのと同じよう、私にも蹴り付けてみるか、小童?
けれど、それは趣味に非ずとおまえは笑うかな。でもな、小童。私はおまえの右頬を打った」
「――だから、いっそそれで左頬を差し出してみなさい、と云うならば貴方には好感が持てる」
「いいや、私は生憎とも敬虔なクリスチャンではないのでな。
ハンムラビ法典の通り、目には目を歯には歯を。こちらで宜しくしてもらおうか、小童」
「それは残念だ。バベルはとうに崩れているのに。 ――それでも、郷に入っては郷に従えと云う」
胡坐を解いて立ち上がる。バンリなる男には、呵責が無い。残った半を歩み寄り、目下から見上げる悪童の眼球が舐める様にして、自身を観察している事は余程気に入らなかったのか。郷に従い、雑に突き上げた膝が悪童の鳩尾を打つ。瞬きをする間の事だった。派手な音を立てるでもなく、悪童の胃の中身が揺らされる感覚と、生理的に呻く音が上がっただけ。蹲る事もせず、膝の入った悪童はよろめく。床に垂れる髪を踏んで、幾本かを引き抜く――引き千切ってしまっていたが、それを気にも留めず、変わらず玉虫色は洞を射抜いていた。
「満足したか」 ――いやに挑発的な声音で、"そういう"手合いの見せかけを通す悪童。
付き合えた物ではない、とは男に在る言。同族嫌悪の気を感じつつ、彼らの様な手合いは、同じもの同士では埒が明かない。それに、膝を入れた悪童の姿は已然としてそのまま。強固な幻術が術者自身に展開されているならばさておき、先程の幻に依る法則に従えば、是はありのままの姿なのだろう。呻くのも束の間、悪童は片手のシガーを咥え込んで男の返事を待っている。
「――……貴方がそこにいる事を切に願うばかりかな」
満足した、とは一言も応えないまま。そう応えてしまえば、向こうの掌で踊らされている様な気がして。結局、舌からぽろりと落ちたのは皮肉交じりで、ジョークの一つも効かぬ言葉。是に所用が無ければ、面の皮を剥いでやるだとか、そういった事も男は厭わない。然し、生憎とも今日は明確な目的あっての事。決して、遊びに来た訳ではないのだ。だから、改めて悪童に目を向ける。まさか、全くの無関係でない筈だ。
「それに、そう。そうだ、己の問いを保留したまま。貴方に、答えて戴かねば。
店主はいらっしゃるか――と聞いたのだ。ここは、骨董店だと聞き及んでいるので」
何でもない様に、問い掛ける。対して、ぷ、と如何にも嘲った声を出すのが眼前の悪童。不愉快とまで行かずとも、向けられて決して気持ちの良い対応ではない。同類、同族の気はあるが――真面目か、不真面目か。そこの二人に、それぐらいの違いは有るだろう。ふるりと口角を釣る悪童は手をひらひら振って、すっかり玉虫色の瞳を細めた目の向こうに覗かせていた。
「――は。 呼ばれたから、出てきたのだぞ。私だ、私。もっと大仰な格好をすれば小童にも伝わったか?」
シガーに火を点けず、唯々八重歯で噛み潰して言い放つ様は、一転して不機嫌であるらしい。使いや店員でなく、店主本人であるのは、妙に自信ありげな態度から疑いようも無い。小柄、かつ華奢な見目からは想像が及ばない程にハスキーな声で凄む、悪童改め店主。最初からそう言えば、妙なやり取りもせずに済んだと考えるのは無粋かもしれない。
「まぁ、良いわ」 ――今時珍しいまでに不遜な態度は、客に何か余計な口を挟ませる気も無く言葉を切って、空気の転換。一瞬、その面に並ぶパーツが失せて、のっぺりとした顔で笑う様に思えたのは大方気のせいか、この店主が幻術使いであるからか。鳩尾の埃を払いながら、漸くらしい事を口にする――いらっしゃいませ、とこの上なく厭味を込めて。何処か他人事の様に、立地を含めて碌に客も来ないだろう、なんて男は眉を僅かに寄せた。いやしかし、バンリなる男は骨董店を訪れはしたが、骨董を求めてではない。或いは、その求む手掛かりこそが一種の骨董と言われれば納得もしようが。故に、どう切り出すべきか――振り出しめいて、そう考えた。決して、無策で及んだ訳でもない。そも、ただ店先に向かうと云うお題目がこうなるとは思わなかった事が総てだ。こうして無用に考える事の、何とつまらない事か。
「ひとまず、"案内"して戴きたい」
どちらかと言えば、慇懃無礼として落とされる言葉。見回せど、この殺風景な玄関ホールには骨董店を思わしき要素が見当たらない、と思い。それこそ、適当に取ってつけた様な扉が幾らでもあるが、どうにも腑に落ちない。本人に聴く方が、余程早かろう。案の定と言うべきか、店主は片瞼を閉じて反応を見せる。それがつまらない、と言外に語っているのは目に見えた事だ。
「…何と冒険心の無い。そこな、立ち並ぶ扉があろうよ。物珍しげであろうよ。
不用意に近付いて開いて見る、と言う気持ちのひとつも起こらんと言うのか、つまらん」
「猿であるまいし、さもありなんと並べられた物に態々触る様な真似はしたくないので――。
ああ、貴方は矢張り幼子ではなかろうか。自らを屋敷の主だと嘯きたい、年頃の小童でなかろうか」
茶番。舞台めいた返しを吐き捨て、厭味の返戻。事実、その様な単純さで脚を引こうとしているのは、幼子の所業か――頭が足りていないかのどちらか。だが、店主はそれ以上乗らない。それ以上、その言葉で刺す事を行わない。引き際を弁えているのは、同類だからか。鼻に掛かる前髪を鬱陶しげに横へ寄せた後背を翻し、無言で踏み出す――店主が向かう先と言えば、どの扉でも、ましてや階段でもなく、玄関先。外へ出て往くつもりらしい。
「二階は生活圏。一階(ここ)は……遊び場、」
そして、男が疑問を呈する前に、翻す小さな背から語る。何たる無駄遣い。
或いは、決してこの悪童独りで暮らしている訳でもないのかもしれない。如何にも、と言った口調を借りて語り、実年齢が見目にそぐわないとしても、是のやる事は見た目からの連想で然程変わりない。髪を引き摺ったまま、身長との対比が目立つ屋敷の扉を押し開ければ、二度目の幻は無く。さ、と扉の隙間から拡散する陽光とのコントラストが、屋敷の中の薄暗さを示し出す。
玄関先の風景は、立ち入った時と変わらず。大規模な幻と改めて認識した今は、これらの風景の幾つが幻なのだろうか、と男は考えるばかり。草木を踏み締める音、小さな背を追えば、玄関先から左折して――屋敷の外壁と、石垣の間に出来た隙間に店主は入って行く。成人男性の身で、その小さな隙間を通り抜けるのは何とも苦労しそうな構図だ。なので、すいすいと進む店主に対して、バンリは身を縮めて恐る恐る通り抜ける羽目になった。先を往く店主と言えば、それがさも当然であると言う態度が背からありありと感じ取れて、背後を省みる。それを一切する筈も無かった。
随分と長く感じた細道も、確かな光――終わりを目にすれば、安堵。先に出た店主を追い、服を石垣を擦りながら、少々の早足で――抜けた。丁度、そこは屋敷の裏手。屋敷のある敷地へ向かう路地裏からは想像がつかぬ程、路地の内に広がった空間は広大だ。そして、裏手の空間にぽつりと建っている物は――粗末な小屋。この光景こそ、取って付けた様で。衣服の埃を払いながら、男の向けた疑念の目。それも一瞥する事なく流され、店主は小屋へ。立て付けの悪い引き戸に手を掛け、両手で開け放てば木々が擦れ、或いは折れる音。お世辞にも、それに邪魔したいとは思わない――
「店は、こっち。 ――腑抜けた面をしてくれるなよ、小童」
のに、現実が思い通りに行く筈もなく。告げられた事実は、聳える屋敷とはかけ離れた襤褸小屋こそが、本命であった事。確かに一度、その屋敷は虚構で、襤褸小屋かもしれない――抱きはしたが、近い事実がより不可解な形であると知れば、内心肩を落とした。引き返す、と言う選択肢はハナから頭に無いが、代わりに頭痛がする、とでも言えばいいか。
だが、冗長なそれを乗り越えて漸く、本分に入れそうなのだ。要らぬ躊躇いは横に退けておくが吉。しかして、溜息を舌で転がしつつ、身体を捻ってちらと己の洞を見つめる玉虫色に誘われるよう【骨董店】へと向かうのであった――。



 |
shadow 「ようやく見晴らしのいい場所に出られたか――おーい、弁当食うぞ弁当」 |
 |
バンリ 「いい加減慣れて来たが―― 貴方だけは幾度も踏んでしまう。 …そこな影、足元の貴方の事だ。足蹴にしてすまないね。」 |
shadow(159) に ItemNo.8 美味しい果実 を手渡ししました。
ItemNo.11 サンドイッチのバスケット を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(10⇒11)
今回の全戦闘において 治癒10 活力10 鎮痛10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!





†炎色めく漆黒の怒り†
|
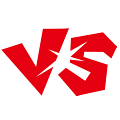 |
イバラ部特別捜査隊さっちゃんず
|



チナミ区 H-15:釣り堀
†炎色めく漆黒の怒り†
|
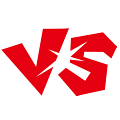 |
立ちはだかるもの
|



チナミ区 H-15:釣り堀
 |
マイケル 「上出来ですね。それでは、どうぞどうぞ。」 |
チェックポイントから天に向け、赤色の光柱が立つ。
次元タクシーで行けるようになったようだ。



shadow(159) は ネジ を入手!
バンリ(296) は ネジ を入手!
色蝕の塊(676) は ド根性雑草 を入手!
ソースケ(681) は ネジ を入手!
ソースケ(681) は 花びら を入手!
バンリ(296) は 毛 を入手!
色蝕の塊(676) は 毛 を入手!
shadow(159) は 毛 を入手!
色蝕の塊(676) は 何か柔らかい物体 を入手!
shadow(159) は 何か柔らかい物体 を入手!
色蝕の塊(676) は 何か柔らかい物体 を入手!



合成LV を 1 DOWN。(LV1⇒0、+1CP、-1FP)
命術LV を 1 UP!(LV9⇒10、-1CP)
幻術LV を 2 UP!(LV0⇒2、-2CP)
装飾LV を 4 UP!(LV28⇒32、-4CP)
シキ(1568) とカードを交換しました!
滅の四番 (エナジードレイン)

ブラッドシェド を研究しました!(深度1⇒2)
ブラッドシェド を研究しました!(深度2⇒3)
ミラージュ を研究しました!(深度0⇒1)
水特性回復 を習得!
リップル を習得!
氷水避け を習得!



shadow(159) に移動を委ねました。
チナミ区 H-15(チェックポイント)に移動!(体調11⇒10)
採集はできませんでした。
- shadow(159) の選択は チナミ区 H-15:釣り堀(ベースキャンプ外のため無効)
- バンリ(296) の選択は チナミ区 H-15:釣り堀(ベースキャンプ外のため無効)
- 色蝕の塊(676) の選択は チナミ区 E-5:出発地(ベースキャンプ外のため無効)
- ソースケ(681) の選択は チナミ区 H-15:釣り堀(ベースキャンプ外のため無効)
MISSION - 未発生:
- バンリ(296) の選択は チナミ区 H-15:釣り堀(ベースキャンプ外のため無効)
- 色蝕の塊(676) の選択は チナミ区 H-15:釣り堀(ベースキャンプ外のため無効)
- ソースケ(681) の選択は チナミ区 H-15:釣り堀(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
ドライバーさん 「・・・・・ふー。」 |

ドライバーさん
次元タクシーの運転手。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。
時計台の前でタバコをふかす、ドライバーさん。
 |
ドライバーさん 「・・・・・。」 |
時計台をぼーっと見上げる。
 |
ドライバーさん 「・・・・・。」 |
自分の腕時計を確認する。
 |
ドライバーさん 「・・・・・。」 |
・・・とても嫌そうな表情になる。
 |
ドライバーさん 「・・・・・狂ってんじゃねーか。」 |
 |
ドライバーさん 「早出手当は出・・・ ・・・ねぇよなぁ。あー・・・・・ ・・・・・面倒だが、社長に報告かね。あー、めんでぇー・・・」 |







TeamNo.1324
|
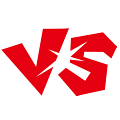 |
†炎色めく漆黒の怒り†
|


ENo.296
バンリ



――神よ。己(おれ)は裁かれるべきものです。
――神よ。自分は在らぬ罪こそを被りたく思う。
――神よ。人々の憤りに焼かれ、それを嗤いたい。
――神よ。是なる業にて実在を今此処に降ろそう。
*その男を観ていると、君達は"これ"に憤りを示すだろう*
●Name:バンリ(本名不明)
●Age:22
●Sex:Male
●Height:168cm
●Weight:70㎏前後
●Alignment:混沌-悪
【異能】- [無意味に苛立ちを与える程度の能力]
名の通り。ただ、人に苛立ちを与えるだけの、乏しい力。
付随して、苛立ちを得た対象は身体能力・異能などが強化されるこの異能による苛立ちは無差別であり、特に発動者に対して矛先が向けられる。物理的に被害を与えなければ済まないと感じる。苛立ちの制御など不可能であるため、発動者は殆ど得をしない。
――神よ。自分は在らぬ罪こそを被りたく思う。
――神よ。人々の憤りに焼かれ、それを嗤いたい。
――神よ。是なる業にて実在を今此処に降ろそう。
*その男を観ていると、君達は"これ"に憤りを示すだろう*
●Name:バンリ(本名不明)
●Age:22
●Sex:Male
●Height:168cm
●Weight:70㎏前後
●Alignment:混沌-悪
【異能】- [無意味に苛立ちを与える程度の能力]
名の通り。ただ、人に苛立ちを与えるだけの、乏しい力。
付随して、苛立ちを得た対象は身体能力・異能などが強化されるこの異能による苛立ちは無差別であり、特に発動者に対して矛先が向けられる。物理的に被害を与えなければ済まないと感じる。苛立ちの制御など不可能であるため、発動者は殆ど得をしない。
10 / 30
285 PS
チナミ区
H-15
H-15





































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材・消耗の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | どうでもよさげな物体 | 素材 | 10 | [武器]器用10(LV2)[防具]治癒10(LV2)[装飾]回復10(LV2) | |||
| 4 | パンの耳 | 食材 | 10 | [効果1]防御10(LV10)[効果2]治癒10(LV20)[効果3]攻撃10(LV30) | |||
| 5 | ■■■■著作の小説 | 装飾 | 20 | 幸運10 | - | - | |
| 6 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV5)[効果2]活力10(LV10)[効果3]鎮痛10(LV15) | |||
| 7 | ネジ | 素材 | 15 | [武器]混乱10(LV25)[防具]追撃10(LV25)[装飾]貫通10(LV25) | |||
| 8 | ネジ | 素材 | 15 | [武器]混乱10(LV25)[防具]追撃10(LV25)[装飾]貫通10(LV25) | |||
| 9 | 苛立ちの弓 | 武器 | 39 | 衰弱10 | - | - | 【射程5】 |
| 10 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]加速10(LV25)[装飾]敏捷10(LV10) | |||
| 11 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]加速10(LV25)[装飾]敏捷10(LV10) | |||
| 12 | 吸い殻 | 素材 | 10 | [武器]炎上10(LV25)[防具]道連10(LV20)[装飾]火纏10(LV25) | |||
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 命術 | 10 | 生命/復元/水 |
| 幻術 | 2 | 夢幻/精神/光 |
| 響鳴 | 10 | 歌唱/音楽/振動 |
| 領域 | 10 | 範囲/法則/結界 |
| 装飾 | 32 | 装飾作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 6 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| 練3 | アクアヒール | 5 | 0 | 40 | 味傷:HP増+炎上・麻痺防御 |
| ビブラート | 5 | 0 | 60 | 敵:SP攻撃 | |
| 練3 | Standoff (プロテクション) | 6 | 0 | 60 | 味傷:守護 |
| ヒーリングソング | 5 | 0 | 70 | 味精2:HP増&精神変調減 | |
| フリーズ | 5 | 0 | 130 | 敵全:凍結 | |
| アトラクト | 5 | 0 | 40 | 自:HATE・連続増 | |
| 練3 | Rile Up (バトルソング) | 6 | 0 | 180 | 味列:AT・LK増(3T) |
| Get Hyped Up (テリトリー) | 5 | 0 | 160 | 味列:DX増 | |
| リップル | 5 | 0 | 150 | 敵全:水痛撃(対象の領域値[水]が高いほど威力増) | |
| FrustRation (エンドレスノイズ) | 5 | 0 | 180 | 敵全2:SP攻撃+味全:SP攻撃 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| A-postplus (器用) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| V-icinus (敏捷) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| O-raculum (活力) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 体力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 治癒 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| O-ratio (幸運) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 | |
| 水特性回復 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:水属性スキルのHP増効果に水特性が影響 | |
| 氷水避け | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:水耐性・凍結耐性増+凍結によるHP・SP減少量減 |



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
| 練3 |
【X】【赤】 (ファイアボール) |
0 | 180 | 敵全:火撃 |
|
巨乳への憎しみ (チャージ) |
0 | 60 | 敵:4連鎖撃 | |
| 練3 |
勇士の歌 (バトルソング) |
0 | 180 | 味列:AT・LK増(3T) |
| 練3 |
滅の四番 (エナジードレイン) |
0 | 160 | 敵:闇撃&DF奪取 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]ライトセイバー | [ 3 ]レイ | [ 1 ]ウィークポイント |
| [ 1 ]ミラージュ | [ 1 ]レッドインペイル | [ 3 ]ブラッドシェド |
| [ 3 ]イバラ |

PL / KSINSNG