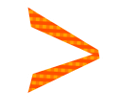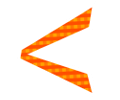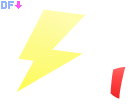<< 3:00>> 5:00




――そして、男は物々しい西洋屋敷の前に立つ。
怖い物など無い、と今時の若者にある稚拙な自負は確かに誇っていた。それでも、眼前に聳える屋敷の威容さは、求める物を求めるに来たとしても、一瞬の尻込み。片隅に住まわせた冷静な自分が、何を馬鹿なと発破を掛けて、漸く一歩踏み出すのであった。一言で言うならば、よくある外観。例えば、こうして何かを説明する事も出来るのだけど――それすら躊躇う程の、態とらしいと思うまで。繰り返す、よくある外観。薄っぺらいテンプレート、ただ見本を組み立てたかの様な、薄気味悪さ。加えて、周囲に意識を反らせば驚く程静かであったから――曲りなりにも進んで来た路地には草木を踏む音ぐらいはあったのに――余計、視界に在る物の質の悪さを感じるばかりだ。
此処は確かに、シモヨメ区の筈だ。剰りに静まり返ったそこは―― これではまるで、異界に迷い込んだ様ではないか。不意に、腰ポケットに手を突っ込んで取り出す端末。電源を入れれば――成程、とことん質の悪い…チープな環境な物で、端末は圏外を指し示していた。悪態をつく気すら起きない、と云うのがバンリの実情である。足踏みをしてみるが、やはり草木の擦れる音はしない。虚しく、堅い物を叩く靴底の音が響くだけ。如何にも怪しいこの屋敷が、尋ねるつもりであった骨董店だとすれば、いよいよB級ホラーの世界だろうか。頬を抓れど、目は醒めない。洞めいた瞳は、大変訝しげに屋敷の玄関を見詰めて数秒、観念した様に吐息を溢すしかなかった。
かつ。かつ。規則正しく、靴底が踏む。一歩一歩、屋敷に近付いて。父の真相を追って、唯一母の譫言から導き出された場所。不確かであっても、引き返す理由には大凡ならない。ポケットへ無造作に仕舞われた写真に触れながら、深呼吸。玄関先に立てば、相変わらず仰々しい。両開きの扉の真ん中――取っ手にあたる部分には、漆黒たる蝶があしらわれている。この両翅を分かち、捥ぎ取る様に扉を引けと云う事らしい。他ならぬバンリは、趣味が悪いと口許に皺を寄せる。誰ぞと知らぬ趣味に言えた物では、決してないが。視線だけを動かして観察するも、呼び鈴が見当たらない。仮にも店舗(だと、想っている)だ。ノックをして伺うのも、それはそれで可笑しい。だから、逡巡も程々に取っ手の蝶に手を掛ける。ぐ、と扉を両手で引くが思った以上に重量を感じた。身体は丈夫でも、生憎と筋力に聊かの不足がある身に囁かな苛立ち、それをばねにもう一度、強く扉を引く――と。
びしゃり。放たれる中心、裂かれる蝶の両翅から何かが飛び出す。咄嗟に取っ手から手を離し、片腕がそれを受け止め――れば、濡れた感覚。湿る袖。然し、手から離した扉は以降も一人でに動いて客人を歓迎する。是ほど思い扉だ、重量が仕事をしたのだろうけれど。瞬く間の事で、それが何かを判断は出来ない。全開になった扉の軋む音で漸く我に返り、恐る恐る受け止めた側――左腕の袖を見遣る。重く湿った袖は、朱く、黒く。伝う鉄の様な生臭さは、詳しく見ずともそれが何かを判断出来るけれど。ここまでチープな演出で出迎えられては、いっそ馬鹿にされている様にさえ思う。かと言って、濡れた袖をそのままにする程鈍くもない。扉の先へ目をやる前に、無造作に上着を脱ぎ捨てた。玄関先へ放り出すのは、行儀が悪いが是非も無い。帰り道に回収すれば良いだろう。そして、幾度か背伸びを繰り返して――ようやっと、放たれた扉の先。骨董店を名乗る、陳腐なお化け屋敷の中に意を向け、躊躇い無く立ち入るのである。
………とかく、生々しかった。バンリなる男にとって非日常よりも、自己の人生は。価値観を培った幼少期は。
或いは、どんなホラーチックな物よりも、余程。産まれ、育ち、その前に居た狂った人間。母と謂う、廃人。
それは恐怖の象徴であったか? 否、それは好奇。そういった目で観るバンリを、母は恐れていたのだろう。
洞めいた目の赫も、好奇を向け続ける目も、母は叫ぶ――あなたはあのひとに似ている。見たくもない。
居ない父に重ね、ヒステリックに叫ぶ。益々、幼い男は好奇の眼を向け続け、そのまま今日に至った。
二十有余年、言葉と掌による鉄槌を受け続けて、その上で母の世話を「心から」続けてきたのだが。
人は、それを洗脳と謂うだろうか。狂気と云うだろうか。全く以て、それは彼を表せる言葉ではない。
バンリは正気だ。大変健全な精神の下、自己の価値観を確立し、望むままに生きて。幸せな人間である。
彼の視点から観て、ではなく。第三者に下される元において。 ――彼は、決してソシオパスではない。
人格と価値観の形成に、母が一役買ったとて―― 何れは、こうなる。元々、そう成る物。それは、先天的。
故に、是は幸せだ。好奇を満たし、或いは追い求められる星の下に産まれたのだから。 ――幸福だ。
だから。今も。 ――踏み入った屋敷の中、先ず一歩。ご丁寧に、大理石のタイルが出迎えてくれた。
上着を脱ぎ捨てたお蔭か、身軽だ。平時は、ちょっかいをかけた相手の苛立ちを受け止める際、威力を殺す為に着用している――ので、あの上着はちと分厚い。それを、室内以外で着ないというのは久しい。身軽になるのも当然か。首を徐に振って、ぐるりと一瞥して判る事は、骨董屋と称される屋敷の中は殺風景である事。屋敷という体を取っている以上、豪勢に展示品の一つや二つ在っても良かろう、と言う念。代わりに、左右両側の二手に分かれた階段。そこから迎える階上の先には無駄に広々とした廊下と幾つも並べられた扉。雑だ、無駄な間取りだと言葉が漏れそうな物だ。階下には、二手の階段以外に――…… 見回す前に、背筋が跳ねる。首筋を這われる感覚、多足の虫が無遠慮に闊歩する時と、そっくりそのまま。思わず片手を首の後ろに回し、生理的な嫌悪と共に、掴んだであろう物を大理石へ叩き付ける。
うぞ、と百足にも似た多足を見せて引っ繰り返る虫。然し、頭部はクワガタにも似た鋏を持ち、その頭部に生やすは蛾の両翅。細長い胴には蜻蛉にも似た翅を付けているではないか。極め付けは、頭部より巨大な――尾、蠍の。冗談の様な継ぎ接ぎ、一目見て歪だと解る。それは、扉の取っ手に模された蝶と同じく漆黒の身体を持ち、気味悪く蠢く脚は嘲笑の意すら感じかねない。この様に気持ちの悪い物は踏み潰してしまおうか――そう至るまで、思考は僅か。何でもない物を潰す様、脚を振り上げて……下ろす。靴越しに感じるのは、殻を引き潰す感触。確かに、手応えはあった。下手げに生命力が在っても後で困るとばかり、そのまま靴底で詰って。
路地を通って来た時も確か、見覚えの無い虫を見掛けた気がする。その類か。詰りながら描く空想と共に、適当な所で詰る脚を離してやり、そう大きな虫ではなかったから、これだけ引き潰せば原型も無いだろうと、足元を見――たのに。最初から、居なかった。詰った靴底だけが擦り減り、磨かれた大理石の床だけが鈍く光っている。狐に化かされた、とはこの事かもしれない。それでも、首を這われる感覚も、詰った殻が砕ける音も、確かに記憶している。生々しさを以て、直前に焼き付いているのに――事実は、擦り減った靴底だけ。奇ッ怪な出来事が、立て続けに。
【神】を宿す物が数多居る街では、別に珍しい事ではないのかもしれない。それを加味しても、この屋敷は薄気味悪い。暫く、顎を指で掴んだまま茫然としていた。現象が、屋敷そのものに付随した何かか――或いは、何者かによる仕業なのかは測りかねる。そも、父の手がかりを求めて「骨董店」に来た結果が、この有様だ。利器に頼って来たのが災いしたか。目先の事どころか、眼前の事実すら不明瞭な状況は、いっその事笑い飛ばせるかもしれない。有限実行、即続行――俯いたままのバンリは、生理的嫌悪ではなく、面白可笑しさから肩を震わせて笑い始めた。掠れた笑い声であった事は否めないが、とかく笑う。中途咳き込むまで、笑っていた。ぴたり、とそれが止めば何も無い床を、もう一度詰った。すると、そこから舞い上がるは蝶。漆黒の蝶。細やかな物が数匹、逃げる様に飛び去って――それすらも、不意に消えた。
それを見て、目を瞬かせる。何か思いついた、と言いたげな面持ちは、そのまま二手に分かれた階段の方へと歩んでゆく。向かって左、辿り着いて何をするかと言えば――亦、脚を振り上げる。そのまま。一段目を蹴飛ばし、脚を置いたままそこから動かない。傍から見れば、先程からの奇ッ怪なそれで軽く気が触れたと見える突飛さ。当然……何も起こらない。片足だけを段に乗せ、ままよと静止する格好は滑稽ですらある。意味無し、と見たのは本人もそうあってか、時間にして五分。そこで脚を下ろす。宙でふら、と脚を振った辺り、思い切り蹴飛ばし踏み付けたせいで痛がっている。次は、加減しよう。そう思うに易い。
かつり、かつり。変わらず、大理石を踏む。だが、よくよく考えれば大理石の床を踏む感覚では決してない。滑りもしなければ、寧ろ粗雑な感覚の伝う靴底。確信に到るとすれば、大変稚拙。向かい、右階段。左右反転の鏡のよう、寸分違わぬ見目。ちら、と左階段を見遣りながら今度こそ、と脚を振り上げ――落とす。蹴飛ばす、と言うよりは小突く。また、片足を段に乗せたまま、暫し。一体何をしているのだろうか?それでも、動かぬ阿呆より動く馬鹿。とうとう、片足をふらつかせて転ぶ様子。バランスを崩した――ではない。いい歳した大人が脚を放り出したまま尻餅を付いて、口角に皺寄せて笑った。そのまま腕を組み、階上を臨む。それはそれは、大きな溜息と共に。
「―― 如何なものだろう、騙されてはしまったが、剰りにお粗末ではないか」
誰に向かってかは、知れず。組んだ腕を解き、床に掌を付ける。視界の端、右階段が――何時の間にか、消えてなくなっている。「正解」だったらしい。奇妙な虫の、あの様子を見ての試行。馬鹿が思い付く様な仮説が、想いも依らぬ場所に当たった結末。下手げに智慧の回る人間は、袋小路に陥りかねない、とも。
「【神】にも派閥がある。貴方は、そうだな――"幻術"だろうか。規模は確かに大きかった。然し、貴方は疎かだった。触れる感覚は再現出来ても、匂いや音までは騙せないし、何より一定以上の衝撃を与えれば雲散する――チープ・トリックだよ。己の【神】に降りて戴くまでもない。或いは、もう少し規模が小さく力が集中していれば騙されたかな――」
愉しさと、こんな稚拙な物に驚かされた僅かな苛立ち。幻術とは、得てして強力な物が揃っているが、穴が見え易い物で助かった。もう少し、至る物であった場合は――今頃、幻に踊らされていた。扉を放った時、血臭が漂っていなかったから、そこで既に疑ってはいたのだが。胡坐を掻いたまま、誰となく語り掛け、バンリは待つ――誰が、弄んだのかと。それから。溜息でなく、深呼吸をひとつ。
「―― 己は、貴方のお客様だ。 店主は、いらっしゃるか――」
そもそも、これが目的だ。 即座に切り替え、そう語る辺りは―― 矢張り、どうあっても図太い神経をしている。










shadow(159) は ド根性雑草 を入手!
バンリ(296) は 吸い殻 を入手!
色蝕の塊(676) は ド根性雑草 を入手!
ソースケ(681) は ド根性雑草 を入手!
色蝕の塊(676) は 毛 を入手!
色蝕の塊(676) は ボロ布 を入手!
ソースケ(681) は ボロ布 を入手!
色蝕の塊(676) は 毛 を入手!



合成LV を 10 DOWN。(LV11⇒1、+10CP、-10FP)
命術LV を 3 UP!(LV6⇒9、-3CP)
装飾LV を 13 UP!(LV15⇒28、-13CP)
ソースケ(681) により ItemNo.9 ボロ布 から射程5の武器『苛立ちの弓』を作製してもらいました!
⇒ 苛立ちの弓/武器:強さ39/[効果1]衰弱10 [効果2]- [効果3]-【射程5】
六華(33) とカードを交換しました!
勇士の歌 (バトルソング)

イバラ を研究しました!(深度1⇒2)
イバラ を研究しました!(深度2⇒3)
ブラッドシェド を研究しました!(深度0⇒1)



shadow(159) に移動を委ねました。
チナミ区 K-15(道路)に移動!(体調15⇒14)
チナミ区 J-15(道路)に移動!(体調14⇒13)
チナミ区 I-15(道路)に移動!(体調13⇒12)
チナミ区 H-15(チェックポイント)に移動!(体調12⇒11)
チナミ区 G-15(道路)に移動!(体調11⇒10)






―― ハザマ時間が紡がれる。

時計台の正面に立ち、怪訝な顔をしている。
一定のリズムで指を鳴らし、口笛を吹く――











棒のような何かが釣りを楽しんでいる。

元気なエビをもらったが、元気すぎて空高くジャンプして見えなくなる。
地面からマイケルと同じようなものがボコッと現れる。
(初発生のイベント戦:異能FP+5!生産FP+5!)




















































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [スキル]OK.



⇒ 【#4 Puzzled】
困惑。幻惑。――例えば、あの世界。この世界。些細なこと。
人の目は易く、いい加減である。智慧の先は、破滅の路。それを身躱すは、盲目の愚か人か――。
困惑。幻惑。――例えば、あの世界。この世界。些細なこと。
人の目は易く、いい加減である。智慧の先は、破滅の路。それを身躱すは、盲目の愚か人か――。
――そして、男は物々しい西洋屋敷の前に立つ。
怖い物など無い、と今時の若者にある稚拙な自負は確かに誇っていた。それでも、眼前に聳える屋敷の威容さは、求める物を求めるに来たとしても、一瞬の尻込み。片隅に住まわせた冷静な自分が、何を馬鹿なと発破を掛けて、漸く一歩踏み出すのであった。一言で言うならば、よくある外観。例えば、こうして何かを説明する事も出来るのだけど――それすら躊躇う程の、態とらしいと思うまで。繰り返す、よくある外観。薄っぺらいテンプレート、ただ見本を組み立てたかの様な、薄気味悪さ。加えて、周囲に意識を反らせば驚く程静かであったから――曲りなりにも進んで来た路地には草木を踏む音ぐらいはあったのに――余計、視界に在る物の質の悪さを感じるばかりだ。
此処は確かに、シモヨメ区の筈だ。剰りに静まり返ったそこは―― これではまるで、異界に迷い込んだ様ではないか。不意に、腰ポケットに手を突っ込んで取り出す端末。電源を入れれば――成程、とことん質の悪い…チープな環境な物で、端末は圏外を指し示していた。悪態をつく気すら起きない、と云うのがバンリの実情である。足踏みをしてみるが、やはり草木の擦れる音はしない。虚しく、堅い物を叩く靴底の音が響くだけ。如何にも怪しいこの屋敷が、尋ねるつもりであった骨董店だとすれば、いよいよB級ホラーの世界だろうか。頬を抓れど、目は醒めない。洞めいた瞳は、大変訝しげに屋敷の玄関を見詰めて数秒、観念した様に吐息を溢すしかなかった。
かつ。かつ。規則正しく、靴底が踏む。一歩一歩、屋敷に近付いて。父の真相を追って、唯一母の譫言から導き出された場所。不確かであっても、引き返す理由には大凡ならない。ポケットへ無造作に仕舞われた写真に触れながら、深呼吸。玄関先に立てば、相変わらず仰々しい。両開きの扉の真ん中――取っ手にあたる部分には、漆黒たる蝶があしらわれている。この両翅を分かち、捥ぎ取る様に扉を引けと云う事らしい。他ならぬバンリは、趣味が悪いと口許に皺を寄せる。誰ぞと知らぬ趣味に言えた物では、決してないが。視線だけを動かして観察するも、呼び鈴が見当たらない。仮にも店舗(だと、想っている)だ。ノックをして伺うのも、それはそれで可笑しい。だから、逡巡も程々に取っ手の蝶に手を掛ける。ぐ、と扉を両手で引くが思った以上に重量を感じた。身体は丈夫でも、生憎と筋力に聊かの不足がある身に囁かな苛立ち、それをばねにもう一度、強く扉を引く――と。
びしゃり。放たれる中心、裂かれる蝶の両翅から何かが飛び出す。咄嗟に取っ手から手を離し、片腕がそれを受け止め――れば、濡れた感覚。湿る袖。然し、手から離した扉は以降も一人でに動いて客人を歓迎する。是ほど思い扉だ、重量が仕事をしたのだろうけれど。瞬く間の事で、それが何かを判断は出来ない。全開になった扉の軋む音で漸く我に返り、恐る恐る受け止めた側――左腕の袖を見遣る。重く湿った袖は、朱く、黒く。伝う鉄の様な生臭さは、詳しく見ずともそれが何かを判断出来るけれど。ここまでチープな演出で出迎えられては、いっそ馬鹿にされている様にさえ思う。かと言って、濡れた袖をそのままにする程鈍くもない。扉の先へ目をやる前に、無造作に上着を脱ぎ捨てた。玄関先へ放り出すのは、行儀が悪いが是非も無い。帰り道に回収すれば良いだろう。そして、幾度か背伸びを繰り返して――ようやっと、放たれた扉の先。骨董店を名乗る、陳腐なお化け屋敷の中に意を向け、躊躇い無く立ち入るのである。
………とかく、生々しかった。バンリなる男にとって非日常よりも、自己の人生は。価値観を培った幼少期は。
或いは、どんなホラーチックな物よりも、余程。産まれ、育ち、その前に居た狂った人間。母と謂う、廃人。
それは恐怖の象徴であったか? 否、それは好奇。そういった目で観るバンリを、母は恐れていたのだろう。
洞めいた目の赫も、好奇を向け続ける目も、母は叫ぶ――あなたはあのひとに似ている。見たくもない。
居ない父に重ね、ヒステリックに叫ぶ。益々、幼い男は好奇の眼を向け続け、そのまま今日に至った。
二十有余年、言葉と掌による鉄槌を受け続けて、その上で母の世話を「心から」続けてきたのだが。
人は、それを洗脳と謂うだろうか。狂気と云うだろうか。全く以て、それは彼を表せる言葉ではない。
バンリは正気だ。大変健全な精神の下、自己の価値観を確立し、望むままに生きて。幸せな人間である。
彼の視点から観て、ではなく。第三者に下される元において。 ――彼は、決してソシオパスではない。
人格と価値観の形成に、母が一役買ったとて―― 何れは、こうなる。元々、そう成る物。それは、先天的。
故に、是は幸せだ。好奇を満たし、或いは追い求められる星の下に産まれたのだから。 ――幸福だ。
だから。今も。 ――踏み入った屋敷の中、先ず一歩。ご丁寧に、大理石のタイルが出迎えてくれた。
上着を脱ぎ捨てたお蔭か、身軽だ。平時は、ちょっかいをかけた相手の苛立ちを受け止める際、威力を殺す為に着用している――ので、あの上着はちと分厚い。それを、室内以外で着ないというのは久しい。身軽になるのも当然か。首を徐に振って、ぐるりと一瞥して判る事は、骨董屋と称される屋敷の中は殺風景である事。屋敷という体を取っている以上、豪勢に展示品の一つや二つ在っても良かろう、と言う念。代わりに、左右両側の二手に分かれた階段。そこから迎える階上の先には無駄に広々とした廊下と幾つも並べられた扉。雑だ、無駄な間取りだと言葉が漏れそうな物だ。階下には、二手の階段以外に――…… 見回す前に、背筋が跳ねる。首筋を這われる感覚、多足の虫が無遠慮に闊歩する時と、そっくりそのまま。思わず片手を首の後ろに回し、生理的な嫌悪と共に、掴んだであろう物を大理石へ叩き付ける。
うぞ、と百足にも似た多足を見せて引っ繰り返る虫。然し、頭部はクワガタにも似た鋏を持ち、その頭部に生やすは蛾の両翅。細長い胴には蜻蛉にも似た翅を付けているではないか。極め付けは、頭部より巨大な――尾、蠍の。冗談の様な継ぎ接ぎ、一目見て歪だと解る。それは、扉の取っ手に模された蝶と同じく漆黒の身体を持ち、気味悪く蠢く脚は嘲笑の意すら感じかねない。この様に気持ちの悪い物は踏み潰してしまおうか――そう至るまで、思考は僅か。何でもない物を潰す様、脚を振り上げて……下ろす。靴越しに感じるのは、殻を引き潰す感触。確かに、手応えはあった。下手げに生命力が在っても後で困るとばかり、そのまま靴底で詰って。
路地を通って来た時も確か、見覚えの無い虫を見掛けた気がする。その類か。詰りながら描く空想と共に、適当な所で詰る脚を離してやり、そう大きな虫ではなかったから、これだけ引き潰せば原型も無いだろうと、足元を見――たのに。最初から、居なかった。詰った靴底だけが擦り減り、磨かれた大理石の床だけが鈍く光っている。狐に化かされた、とはこの事かもしれない。それでも、首を這われる感覚も、詰った殻が砕ける音も、確かに記憶している。生々しさを以て、直前に焼き付いているのに――事実は、擦り減った靴底だけ。奇ッ怪な出来事が、立て続けに。
【神】を宿す物が数多居る街では、別に珍しい事ではないのかもしれない。それを加味しても、この屋敷は薄気味悪い。暫く、顎を指で掴んだまま茫然としていた。現象が、屋敷そのものに付随した何かか――或いは、何者かによる仕業なのかは測りかねる。そも、父の手がかりを求めて「骨董店」に来た結果が、この有様だ。利器に頼って来たのが災いしたか。目先の事どころか、眼前の事実すら不明瞭な状況は、いっその事笑い飛ばせるかもしれない。有限実行、即続行――俯いたままのバンリは、生理的嫌悪ではなく、面白可笑しさから肩を震わせて笑い始めた。掠れた笑い声であった事は否めないが、とかく笑う。中途咳き込むまで、笑っていた。ぴたり、とそれが止めば何も無い床を、もう一度詰った。すると、そこから舞い上がるは蝶。漆黒の蝶。細やかな物が数匹、逃げる様に飛び去って――それすらも、不意に消えた。
それを見て、目を瞬かせる。何か思いついた、と言いたげな面持ちは、そのまま二手に分かれた階段の方へと歩んでゆく。向かって左、辿り着いて何をするかと言えば――亦、脚を振り上げる。そのまま。一段目を蹴飛ばし、脚を置いたままそこから動かない。傍から見れば、先程からの奇ッ怪なそれで軽く気が触れたと見える突飛さ。当然……何も起こらない。片足だけを段に乗せ、ままよと静止する格好は滑稽ですらある。意味無し、と見たのは本人もそうあってか、時間にして五分。そこで脚を下ろす。宙でふら、と脚を振った辺り、思い切り蹴飛ばし踏み付けたせいで痛がっている。次は、加減しよう。そう思うに易い。
かつり、かつり。変わらず、大理石を踏む。だが、よくよく考えれば大理石の床を踏む感覚では決してない。滑りもしなければ、寧ろ粗雑な感覚の伝う靴底。確信に到るとすれば、大変稚拙。向かい、右階段。左右反転の鏡のよう、寸分違わぬ見目。ちら、と左階段を見遣りながら今度こそ、と脚を振り上げ――落とす。蹴飛ばす、と言うよりは小突く。また、片足を段に乗せたまま、暫し。一体何をしているのだろうか?それでも、動かぬ阿呆より動く馬鹿。とうとう、片足をふらつかせて転ぶ様子。バランスを崩した――ではない。いい歳した大人が脚を放り出したまま尻餅を付いて、口角に皺寄せて笑った。そのまま腕を組み、階上を臨む。それはそれは、大きな溜息と共に。
「―― 如何なものだろう、騙されてはしまったが、剰りにお粗末ではないか」
誰に向かってかは、知れず。組んだ腕を解き、床に掌を付ける。視界の端、右階段が――何時の間にか、消えてなくなっている。「正解」だったらしい。奇妙な虫の、あの様子を見ての試行。馬鹿が思い付く様な仮説が、想いも依らぬ場所に当たった結末。下手げに智慧の回る人間は、袋小路に陥りかねない、とも。
「【神】にも派閥がある。貴方は、そうだな――"幻術"だろうか。規模は確かに大きかった。然し、貴方は疎かだった。触れる感覚は再現出来ても、匂いや音までは騙せないし、何より一定以上の衝撃を与えれば雲散する――チープ・トリックだよ。己の【神】に降りて戴くまでもない。或いは、もう少し規模が小さく力が集中していれば騙されたかな――」
愉しさと、こんな稚拙な物に驚かされた僅かな苛立ち。幻術とは、得てして強力な物が揃っているが、穴が見え易い物で助かった。もう少し、至る物であった場合は――今頃、幻に踊らされていた。扉を放った時、血臭が漂っていなかったから、そこで既に疑ってはいたのだが。胡坐を掻いたまま、誰となく語り掛け、バンリは待つ――誰が、弄んだのかと。それから。溜息でなく、深呼吸をひとつ。
「―― 己は、貴方のお客様だ。 店主は、いらっしゃるか――」
そもそも、これが目的だ。 即座に切り替え、そう語る辺りは―― 矢張り、どうあっても図太い神経をしている。







鋼響戦隊
|
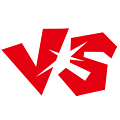 |
†炎色めく漆黒の怒り†
|



shadow(159) は ド根性雑草 を入手!
バンリ(296) は 吸い殻 を入手!
色蝕の塊(676) は ド根性雑草 を入手!
ソースケ(681) は ド根性雑草 を入手!
色蝕の塊(676) は 毛 を入手!
色蝕の塊(676) は ボロ布 を入手!
ソースケ(681) は ボロ布 を入手!
色蝕の塊(676) は 毛 を入手!



合成LV を 10 DOWN。(LV11⇒1、+10CP、-10FP)
命術LV を 3 UP!(LV6⇒9、-3CP)
装飾LV を 13 UP!(LV15⇒28、-13CP)
ソースケ(681) により ItemNo.9 ボロ布 から射程5の武器『苛立ちの弓』を作製してもらいました!
⇒ 苛立ちの弓/武器:強さ39/[効果1]衰弱10 [効果2]- [効果3]-【射程5】
 |
ソースケ 「こ、こんな感じでよかった???」 |
六華(33) とカードを交換しました!
勇士の歌 (バトルソング)

イバラ を研究しました!(深度1⇒2)
イバラ を研究しました!(深度2⇒3)
ブラッドシェド を研究しました!(深度0⇒1)



shadow(159) に移動を委ねました。
チナミ区 K-15(道路)に移動!(体調15⇒14)
チナミ区 J-15(道路)に移動!(体調14⇒13)
チナミ区 I-15(道路)に移動!(体調13⇒12)
チナミ区 H-15(チェックポイント)に移動!(体調12⇒11)
チナミ区 G-15(道路)に移動!(体調11⇒10)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
榊 「・・・・・?」 |

榊
黒髪に蒼い瞳、黒スーツ。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
時計台の正面に立ち、怪訝な顔をしている。
 |
榊 「・・・この世界でオカシイも何も無いと言えば、無いのですが。 どうしましょうかねぇ。・・・どうしましょうねぇ。」 |
一定のリズムで指を鳴らし、口笛を吹く――







†炎色めく漆黒の怒り†
|
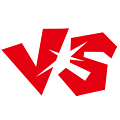 |
イバラ部特別捜査隊さっちゃんず
|



 |
マイケル 「あ、ようこそチェックポイントへ。 いまエビが釣れそうなので少々お待ちを……。」 |
棒のような何かが釣りを楽しんでいる。

マイケル
陽気な棒形人工生命体。
マイケル以外にもいろんな種類があるんだZE☆
マイケル以外にもいろんな種類があるんだZE☆
 |
マイケル 「よくぞここまで。私はマイケルといいます。 出会いの記念にこちらをどうぞ。」 |
元気なエビをもらったが、元気すぎて空高くジャンプして見えなくなる。
 |
マイケル 「……戻ってきませんねぇ、エビさん。」 |
 |
マイケル 「まぁいいです。始めるとしましょうか。」 |
地面からマイケルと同じようなものがボコッと現れる。
 |
マイケル 「私達に勝利できればこのチェックポイントを利用できるようになります。 何人で来ようと手加減はしませんので、そちらも本気でどうぞ。」 |
(初発生のイベント戦:異能FP+5!生産FP+5!)





ENo.296
バンリ



――神よ。己(おれ)は裁かれるべきものです。
――神よ。自分は在らぬ罪こそを被りたく思う。
――神よ。人々の憤りに焼かれ、それを嗤いたい。
――神よ。是なる業にて実在を今此処に降ろそう。
*その男を観ていると、君達は"これ"に憤りを示すだろう*
●Name:バンリ(本名不明)
●Age:22
●Sex:Male
●Height:168cm
●Weight:70㎏前後
●Alignment:混沌-悪
【異能】- [無意味に苛立ちを与える程度の能力]
名の通り。ただ、人に苛立ちを与えるだけの、乏しい力。
付随して、苛立ちを得た対象は身体能力・異能などが強化されるこの異能による苛立ちは無差別であり、特に発動者に対して矛先が向けられる。物理的に被害を与えなければ済まないと感じる。苛立ちの制御など不可能であるため、発動者は殆ど得をしない。
――神よ。自分は在らぬ罪こそを被りたく思う。
――神よ。人々の憤りに焼かれ、それを嗤いたい。
――神よ。是なる業にて実在を今此処に降ろそう。
*その男を観ていると、君達は"これ"に憤りを示すだろう*
●Name:バンリ(本名不明)
●Age:22
●Sex:Male
●Height:168cm
●Weight:70㎏前後
●Alignment:混沌-悪
【異能】- [無意味に苛立ちを与える程度の能力]
名の通り。ただ、人に苛立ちを与えるだけの、乏しい力。
付随して、苛立ちを得た対象は身体能力・異能などが強化されるこの異能による苛立ちは無差別であり、特に発動者に対して矛先が向けられる。物理的に被害を与えなければ済まないと感じる。苛立ちの制御など不可能であるため、発動者は殆ど得をしない。
10 / 30
162 PS
チナミ区
G-15
G-15





































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材・消耗の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | どうでもよさげな物体 | 素材 | 10 | [武器]器用10(LV2)[防具]治癒10(LV2)[装飾]回復10(LV2) | |||
| 4 | パンの耳 | 食材 | 10 | [効果1]防御10(LV10)[効果2]治癒10(LV20)[効果3]攻撃10(LV30) | |||
| 5 | ■■■■著作の小説 | 装飾 | 20 | 幸運10 | - | - | |
| 6 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV5)[効果2]活力10(LV10)[効果3]鎮痛10(LV15) | |||
| 7 | ネジ | 素材 | 15 | [武器]混乱10(LV25)[防具]追撃10(LV25)[装飾]貫通10(LV25) | |||
| 8 | 美味しい果実 | 食材 | 15 | [効果1]敏捷10(LV10)[効果2]復活10(LV10)[効果3]体力15(LV25) | |||
| 9 | 苛立ちの弓 | 武器 | 39 | 衰弱10 | - | - | 【射程5】 |
| 10 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]加速10(LV25)[装飾]敏捷10(LV10) | |||
| 11 | サンドイッチのバスケット | 料理 | 25 | 治癒10 | 活力10 | 鎮痛10 | |
| 12 | 吸い殻 | 素材 | 10 | [武器]炎上10(LV25)[防具]道連10(LV20)[装飾]火纏10(LV25) | |||
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 命術 | 9 | 生命/復元/水 |
| 響鳴 | 10 | 歌唱/音楽/振動 |
| 領域 | 10 | 範囲/法則/結界 |
| 装飾 | 28 | 装飾作製に影響 |
| 合成 | 1 | 合成に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 6 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| 練1 | アクアヒール | 5 | 0 | 40 | 味傷:HP増+炎上・麻痺防御 |
| ビブラート | 5 | 0 | 60 | 敵:SP攻撃 | |
| Standoff (プロテクション) | 5 | 0 | 60 | 味傷:守護 | |
| ヒーリングソング | 5 | 0 | 70 | 味精2:HP増&精神変調減 | |
| フリーズ | 5 | 0 | 130 | 敵全:凍結 | |
| アトラクト | 5 | 0 | 40 | 自:HATE・連続増 | |
| Rile Up (バトルソング) | 5 | 0 | 180 | 味列:AT・LK増(3T) | |
| 練1 | Get Hyped Up (テリトリー) | 5 | 0 | 160 | 味列:DX増 |
| FrustRation (エンドレスノイズ) | 5 | 0 | 180 | 敵全2:SP攻撃+味全:SP攻撃 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| A-postplus (器用) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| V-icinus (敏捷) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| O-raculum (活力) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 体力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 治癒 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| O-ratio (幸運) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 |





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]ライトセイバー | [ 3 ]レイ | [ 1 ]ウィークポイント |
| [ 1 ]レッドインペイル | [ 1 ]ブラッドシェド | [ 3 ]イバラ |

PL / KSINSNG