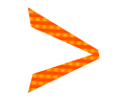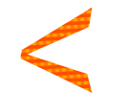<< 0:00>> 2:00





ラーメン屋の匂いだとか、車の排気音だとか、交差点に立ち止まる人だとか。そういった、普段気にも留めないような、数歩も歩けば気にしなくなる小さな事柄のいちいちが、どうしようもなく街の死を突き刺してくる。
「……侵略、マジだったかぁ」
見慣れた土地の見知らぬ姿の中、一人頭を掻く。
状況からするに、例の男──榊だったか、彼の言に偽りはなく、この殺風景な世界で俺たちと侵略者どもの戦争が始まることに間違いは無さそうだ。
自身の記憶に違和感はない。要するに、俺は『守る側』だということらしい。
破滅主義の奇特な連中は記憶がどうだろうと侵略者ことアンジニティに付くのかもしれないが、俺はそういう気分にはならなかった。
この世界、クソつまらないことが目に見えて分かる。ここに死ぬまで閉じ込められるなんて、それこそ死んでも御免だ。
現時点で問題はいくつか。砕けたコンクリートを踏み締めながら口許を右手で覆う。
一つはシンプルに敵勢力の不明瞭さ。さっきぶっ飛ばした血色の化け物ばかりでもなかろうし、何よりも榊は『潜伏している』と言った。つまり、もっと馴染んだ連中が戦争を吹っかけてきた相手という可能性は当たり前のようにある。
見知った相手を斃す──殺す気概が、今の今まで騒がしくも平和な日々を送って来たであろう『住人』たちにそれが出来るのかという懸念。相手はそもそも侵略する気であるというのなら、その点において躊躇いはあるまい。殺傷への迷いの無さ、その差はどうしようもなく大きい。
俺はまあ、別にいい。国家権力を気にせず暴れられる機会を、これ幸いと思っているくらいだ。暴れる様だけ見て勘違いさえされなければ一切合切問題はない。
二つ目、手持ちの心許なさ。急に飛ばされたもんだから、あるものと言えば制服にパーカー、まだ熱を持つカイロにほとんど用をなさないであろう携帯と財布。以上。我ながら舐め腐った装備だ。
この戦争がどれほど続くかは知らないが、食事類はどうにかしておきたかった。同じくらいに武器も欲しいが、幸いにも鉄筋に溢れた街並みだ、一旦は後回しで良い。最悪拳骨でも多少は大丈夫だろうし。
最後、仲間が欲しい。これが一番早急か。ランダムで飛ばされたならもちろんだし、ある程度固まって飛ばされたにしても味方かどうかの判断が非常に面倒くさい。さりとて向こうが徒党を組むなら此方だってもちろんチームプレイを用いざるを得なくなるわけである。数に勝る武器はない。
取り敢えず知ってる連中とあって逐一勢力確認かあ、などとそれはもう深いため息が出た。この喧嘩、本当に旨みがない。攻めるだけ攻めて撃退してもご褒美も無しとはどういう了見だ。
「…………」
何とはなしに立ち止まる。
例えば、ウチの部員とかが敵だった場合。殴るのは全く躊躇いなく出来るだろう。骨折だ何だも特に気にしない筈だ。
では、その先はどうなんだろう。今更のように振り返り、また足を適当に進め始めた。
疑問の余地なんて何もない。──俺はやる。そうでなければ、俺は一栄斗ではいられない。
我ながらどうしようもない結論に独り笑いを漏らし、伸びを一つ。やはりどこまで行っても正義の味方には向いていないらしい。
「──さァてと。世界を守りに行くか」
勇者の剣の代わりに錆びた鉄パイプを片手に、ただそれだけを宣誓した。



ENo.58 "葬儀屋" とのやりとり

ENo.413 伊上 司 とのやりとり




特に何もしませんでした。








武術LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
自然LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
具現LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
解析LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
武器LV を 15 UP!(LV0⇒15、-15CP)
防具LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
ItemNo.4 不思議な牙 から射程1の武器『謹製鉄パイプ』を作製しました!
⇒ 謹製鉄パイプ/武器:強さ25/[効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程1】/特殊アイテム
寧々(267) の持つ ItemNo.4 不思議な牙 から射程4の武器『モデル/ベレッタ92FS』を作製しました!
ション(195) の持つ ItemNo.4 不思議な牙 から射程1の武器『スタンガン』を作製しました!
アミナとゾード(109) とカードを交換しました!
生ける死神の大鎌 (ブラスト)


エキサイト を習得!
ストーンブラスト を習得!
クリエイト:タライ を習得!
プリディクション を習得!
クラッシュ を習得!
クリエイト:ウェポン を習得!
アキュラシィ を習得!
クリエイト:ホーネット を習得!
トランキュリティ を習得!
クリエイト:ガトリング を習得!



次元タクシーに乗り『チナミ区 E-5:出発地』に転送されました!
チナミ区 F-5(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 G-5(草原)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 H-5(草原)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 I-5(道路)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 J-5(道路)に移動!(体調26⇒25)
寧々(267) からパーティに勧誘されました!






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャットで時間が伝えられる。
榊の前に1台のタクシーが止まり、窓が開く。

帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。
窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。
榊からのチャットが閉じられる――
























































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.




ラーメン屋の匂いだとか、車の排気音だとか、交差点に立ち止まる人だとか。そういった、普段気にも留めないような、数歩も歩けば気にしなくなる小さな事柄のいちいちが、どうしようもなく街の死を突き刺してくる。
「……侵略、マジだったかぁ」
見慣れた土地の見知らぬ姿の中、一人頭を掻く。
状況からするに、例の男──榊だったか、彼の言に偽りはなく、この殺風景な世界で俺たちと侵略者どもの戦争が始まることに間違いは無さそうだ。
自身の記憶に違和感はない。要するに、俺は『守る側』だということらしい。
破滅主義の奇特な連中は記憶がどうだろうと侵略者ことアンジニティに付くのかもしれないが、俺はそういう気分にはならなかった。
この世界、クソつまらないことが目に見えて分かる。ここに死ぬまで閉じ込められるなんて、それこそ死んでも御免だ。
現時点で問題はいくつか。砕けたコンクリートを踏み締めながら口許を右手で覆う。
一つはシンプルに敵勢力の不明瞭さ。さっきぶっ飛ばした血色の化け物ばかりでもなかろうし、何よりも榊は『潜伏している』と言った。つまり、もっと馴染んだ連中が戦争を吹っかけてきた相手という可能性は当たり前のようにある。
見知った相手を斃す──殺す気概が、今の今まで騒がしくも平和な日々を送って来たであろう『住人』たちにそれが出来るのかという懸念。相手はそもそも侵略する気であるというのなら、その点において躊躇いはあるまい。殺傷への迷いの無さ、その差はどうしようもなく大きい。
俺はまあ、別にいい。国家権力を気にせず暴れられる機会を、これ幸いと思っているくらいだ。暴れる様だけ見て勘違いさえされなければ一切合切問題はない。
二つ目、手持ちの心許なさ。急に飛ばされたもんだから、あるものと言えば制服にパーカー、まだ熱を持つカイロにほとんど用をなさないであろう携帯と財布。以上。我ながら舐め腐った装備だ。
この戦争がどれほど続くかは知らないが、食事類はどうにかしておきたかった。同じくらいに武器も欲しいが、幸いにも鉄筋に溢れた街並みだ、一旦は後回しで良い。最悪拳骨でも多少は大丈夫だろうし。
最後、仲間が欲しい。これが一番早急か。ランダムで飛ばされたならもちろんだし、ある程度固まって飛ばされたにしても味方かどうかの判断が非常に面倒くさい。さりとて向こうが徒党を組むなら此方だってもちろんチームプレイを用いざるを得なくなるわけである。数に勝る武器はない。
取り敢えず知ってる連中とあって逐一勢力確認かあ、などとそれはもう深いため息が出た。この喧嘩、本当に旨みがない。攻めるだけ攻めて撃退してもご褒美も無しとはどういう了見だ。
「…………」
何とはなしに立ち止まる。
例えば、ウチの部員とかが敵だった場合。殴るのは全く躊躇いなく出来るだろう。骨折だ何だも特に気にしない筈だ。
では、その先はどうなんだろう。今更のように振り返り、また足を適当に進め始めた。
疑問の余地なんて何もない。──俺はやる。そうでなければ、俺は一栄斗ではいられない。
我ながらどうしようもない結論に独り笑いを漏らし、伸びを一つ。やはりどこまで行っても正義の味方には向いていないらしい。
「──さァてと。世界を守りに行くか」
勇者の剣の代わりに錆びた鉄パイプを片手に、ただそれだけを宣誓した。



ENo.58 "葬儀屋" とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.413 伊上 司 とのやりとり
| ▲ |
| ||



特に何もしませんでした。







武術LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
自然LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
具現LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
解析LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
武器LV を 15 UP!(LV0⇒15、-15CP)
防具LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
ItemNo.4 不思議な牙 から射程1の武器『謹製鉄パイプ』を作製しました!
⇒ 謹製鉄パイプ/武器:強さ25/[効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程1】/特殊アイテム
 |
ニノマエ 「……取り敢えず適当でいいか。」 |
寧々(267) の持つ ItemNo.4 不思議な牙 から射程4の武器『モデル/ベレッタ92FS』を作製しました!
ション(195) の持つ ItemNo.4 不思議な牙 から射程1の武器『スタンガン』を作製しました!
アミナとゾード(109) とカードを交換しました!
生ける死神の大鎌 (ブラスト)


エキサイト を習得!
ストーンブラスト を習得!
クリエイト:タライ を習得!
プリディクション を習得!
クラッシュ を習得!
クリエイト:ウェポン を習得!
アキュラシィ を習得!
クリエイト:ホーネット を習得!
トランキュリティ を習得!
クリエイト:ガトリング を習得!



次元タクシーに乗り『チナミ区 E-5:出発地』に転送されました!
チナミ区 F-5(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 G-5(草原)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 H-5(草原)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 I-5(道路)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 J-5(道路)に移動!(体調26⇒25)
寧々(267) からパーティに勧誘されました!






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
榊 「・・・60分!区切り目ですねぇッ!!」 |

榊
黒髪に蒼い瞳、黒スーツ。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
チャットで時間が伝えられる。
 |
榊 「先程の戦闘、観察させていただきました。 ざっくりと戦闘不能を目指せば良いようで。」 |
 |
榊 「・・・おっと、お呼びしていた方が来たようです。 我々が今後お世話になる方をご紹介しましょう!」 |
榊の前に1台のタクシーが止まり、窓が開く。

ドライバーさん
次元タクシーの運転手。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。
 |
ドライバーさん 「どーも、『次元タクシー』の運転役だ。よろしく。」 |
帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。
 |
榊 「こちら、中立に位置する方のようでして。 陣営に関係なくお手伝いいただけるとのこと。」 |
 |
ドライバーさん 「中立っつーかなぁ・・・。俺もタクシーも同じのが沢山"在る"んでな。 面倒なんで人と思わずハザマの機能の一部とでも思ってくれ。」 |
 |
ドライバーさん 「ま・・・チェックポイントとかの行き来の際にゃ、へいタクシーの一声を。じゃあな。」 |
窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。
 |
榊 「何だか似た雰囲気の方が身近にいたような・・・ あの方もタクシー運転手が似合いそうです。」 |
 |
榊 「ともあれ開幕ですねぇぇッ!!!! じゃんじゃん打倒していくとしましょうッ!!!!」 |
榊からのチャットが閉じられる――









ENo.91
一栄斗



「さーてと。今日はどう人生を楽しく彩ってやろうかなァ?」
──終業のチャイムに身を起こし、眼帯はそう歯を剥いた。
刹那主義にして快楽主義、今さえ楽しければ何でも良い16歳児。
考えなしという訳ではなさそうなのだが、常日頃の軽妙で軽率で軽薄な態度がどうしたって信用信頼の類を勝ち得ない。
父子家庭の育ちであり、母の顔は知らない。父親は土木業従事者で、似たモノ親子なのだがそれが却って小競り合いを起こす。主に彼から一方的に。
相良伊橋高校2-1組所属、生徒会副会長。全般的に成績は悪くないが態度は悪い。授業中にはしばしばチョークを額に喰らう彼の姿が目撃される。
『何をやってるか分からない』民俗文化研究部の設立者にして部長であり、特に引き締めるとか全国大会出場などは気にせず持ち込んだ菓子を貪りテレビゲームに熱中し漫画を読み耽る。部室にはベッドも完備の至れり尽くせり具合。
そもそもにして創部の動機が「校内に部屋が欲しい」からなため、堅苦しい部名は単なる方便にしか過ぎない。部室には彼に巻き込まれる、ないしは暇を持て余した相良伊橋学生たちがたむろしてたりしてなかったり。たまに外部の学生すら見受けられる。
花折美織(1089)の幼馴染。
高梁司生徒会長(413)ととある協定を締結中。
プロフィールイラストBは高梁司会長をお借りしました
──終業のチャイムに身を起こし、眼帯はそう歯を剥いた。
刹那主義にして快楽主義、今さえ楽しければ何でも良い16歳児。
考えなしという訳ではなさそうなのだが、常日頃の軽妙で軽率で軽薄な態度がどうしたって信用信頼の類を勝ち得ない。
父子家庭の育ちであり、母の顔は知らない。父親は土木業従事者で、似たモノ親子なのだがそれが却って小競り合いを起こす。主に彼から一方的に。
相良伊橋高校2-1組所属、生徒会副会長。全般的に成績は悪くないが態度は悪い。授業中にはしばしばチョークを額に喰らう彼の姿が目撃される。
『何をやってるか分からない』民俗文化研究部の設立者にして部長であり、特に引き締めるとか全国大会出場などは気にせず持ち込んだ菓子を貪りテレビゲームに熱中し漫画を読み耽る。部室にはベッドも完備の至れり尽くせり具合。
そもそもにして創部の動機が「校内に部屋が欲しい」からなため、堅苦しい部名は単なる方便にしか過ぎない。部室には彼に巻き込まれる、ないしは暇を持て余した相良伊橋学生たちがたむろしてたりしてなかったり。たまに外部の学生すら見受けられる。
花折美織(1089)の幼馴染。
高梁司生徒会長(413)ととある協定を締結中。
プロフィールイラストBは高梁司会長をお借りしました
25 / 30
50 PS
チナミ区
J-5
J-5





































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果等 |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]-【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |
| 4 | 謹製鉄パイプ | 武器 | 25 | [効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程1】 |
| 5 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]敏捷10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) |
| 6 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV5)[効果2]活力10(LV10)[効果3]鎮痛10(LV15) |
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV5)[効果2]活力10(LV10)[効果3]鎮痛10(LV15) |
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 5 | 身体/武器/物理 |
| 自然 | 5 | 植物/鉱物/地 |
| 具現 | 5 | 創造/召喚 |
| 解析 | 5 | 精確/対策/装置 |
| 武器 | 15 | 武器作製と、武器への素材の付加に影響。 |
| 防具 | 5 | 防具作製と、防具への素材の付加に影響。 |
アクティブ
| スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 |
| ピンポイント | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 |
| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 |
| ヒール | 5 | 0 | 20 | 味傷:HP増 |
| エキサイト | 5 | 0 | 40 | 敵:攻撃+自:AT増(1T) |
| ストーンブラスト | 5 | 0 | 40 | 敵:地撃 |
| クリエイト:タライ | 5 | 0 | 40 | 敵:攻撃&朦朧・混乱 |
| プリディクション | 5 | 0 | 60 | 味列:AG増(3T) |
| クラッシュ | 5 | 0 | 80 | 敵列:地撃 |
| クリエイト:ウェポン | 5 | 0 | 60 | 味:追撃LV・次与ダメ増 |
| アキュラシィ | 5 | 0 | 80 | 自:連続減+敵:精確攻撃 |
| クリエイト:ホーネット | 5 | 0 | 100 | 敵:痛撃&(猛毒or麻痺) |
| トランキュリティ | 5 | 0 | 60 | 味環:HP増&環境変調減 |
| クリエイト:ガトリング | 5 | 0 | 110 | 味:貫撃LV増 |
パッシブ
| スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 |
| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 |
| 活力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 |
| 体力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 |
| 治癒 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 |
| 幸運 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:運増 |





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |

PL / 空気頭の蛞蝓