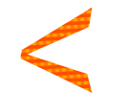<< 0:00>> 2:00




そのとき、神無月は初めての風俗に挑戦しようと決意を固めていたところだった。2月の肌寒い、ミナト区の大橋前での決断であった。
この世に生を受けて24年、しがないサラリーマン生活をして1年が過ぎようとしている平凡な男だ。大学を卒業したにも関わらず在学中はこれといった女をえり好みした所為で合コンのチャンスも逃し、異性の感触を理解できないまま生きてきた。
元々、女に興味が無かったわけではなくましてやゲイでもない。彼にとって経験すること自体の好機すら棒に振ったことを何となく尾を引いたことが起因する。
酒の席で童貞であること話題されて同僚にからかわれ、先輩から経験したらどうだと焚きつけられたのが三日前。意地になった男は月給の四分の一を予算にして特殊浴場に向かう事にした。
二時間後には一皮むけた大人の男になるんだと不安を8割胸に残し、胸中は決して快晴とは言えない気分の儘に夕暮れに泥む欲望の街へと赴いた。
マガサ駅から南に移動し、歓楽街で知られるヨシバラへと足を運ぶと目に優しくない色でチカつくネオンに視界を奪われる。
神無月はこれ、といった店を予約して行くことをしなかった。そういう店に電話を掛けるのも気恥ずかしくて、システムも理解できないから適当に練り歩く程度に見て回ろうと考えたのだ。
しかし決め打ちしてかかるには情報が足りなさ過ぎた。倒錯的な性愛者向けの店や、みるからにぼったくりする気満々の個人経営の酒場、特殊なカフェに喧しく宣伝するボーイのキンキン声が鬱陶しいとすら感じる。
あるいは現代において穢れとされる異形が跋扈するいかにもな店が嫌でも目に付いたくらいで、有体に言えば男は立ち往生していた。ポケットに手を突っ込んで定期入れの感触を指先で確かめながらため息をつく。
「出直すべきかなァ」
そこで男はべこんと軽快な衝突音を耳にした。剥き出しになったパイプがちらつく喧騒から離れた路地裏からだった。生き物の呻き声が遅れて聞こえてきたものだから、路地の入口でそれとなくスマホを開きながら聞き耳を立てる。
今度は明確だった。やはり何か生物の声がする。続けて壁に何かをこすりつけるような音。加えて、鉄板がぶつかったような重々しい音ではなく日常的に耳にする……咄嗟に出力するには少々時間がかかり具体的な言葉を出すまでに数秒程要した異音が一つ。
「なんだ、酔っぱらい同士が小競り合いか?」
路地裏の近場には青色のカラーリングが特徴的な円筒状のプラスチックのゴミ箱がある。隣接するビルが風俗店を営んでいることからそこが所有しているものだろう。
ゴミ箱の口から花のように開く黒色でコーティングされたビニールは、中身を見せないための工夫が施されている――有体に言えば生ゴミを世間一般の眼に晒さないようにするための措置である。
酔っぱらいが転倒して転がしたのかと思ったが、ポリバケツの中身はぶちまけられてはいなかった。
恐る恐る男が覗き込むと、斜陽の差し込まない暗がりに点々と赤黒い飛沫が見えた。ともあればただの模様とでも認識できる程度の誤差だが、乾ききっていないそれが今しがた噴き出したものであると認識できたのは数分してからのことだった。
今、目の前で起こっている状況を把握するので手一杯だったのだ。
大腿部を大きく露出したデニムのホットパンツが眩しく、対して真っ白なリブ生地のニットで白い柔肌を覆う女だった。横顔しか確認できないものの年端もいかない少女風貌といった華奢な女性で、成人すらしていないであろうことが窺える。
この路地はバカスカと建築したせいで通行することが出来ない行き止まりの場所である。専ら近隣の店のボーイが隠れて煙草を吸ったり、胃袋を中身をぶちまけるためにあるような袋小路という最低な環境にあった。
壁に向けてポリバケツの蓋をぐっと押し込むさまは傍から見ると間抜け甚だしい――と考えたのは一瞬。
「せっかくの相談は嬉しいけど、その前に質問ね」
こういったアンダーな場所で交わされる会話というのは、当然ながらロクなものではない。風営法にひっかかる内容以前に、法的に引っかかる内容が語られることも大して珍しいことではない。
そんな現場をこの目で見るのがあまりにもレアケースなのだが、つまるところ今はヤバい現場を眼にしている、ということに他ならない。
援助交際の申し出相手が奥にいるのか、逆ナンで買って貰おうとくいっぱぐれている家出少女の可能性もある。
恐怖と好奇の儘に神無月が眼を凝らすと、ポリバケツの蓋の中には人の頭があった。目で追いかけると胴部はきちんとあって生きた人間であることが認識できた。人間はいかにもといったヤクザ者だ。鼻ピアスやサングラス、派手な色のコートに身を包んでいて、そのくせ手指に付けている装飾品だけはいっちょ前な若いながらも明らかにそういう手合いの人間だった。
但しサングラスで威厳を出そうとした顔は醜くぼこぼこにされていて、ポリバケツの蓋を押し付けられていることもあって現在進行形でひどい変顔を晒していた。長年使い続けているであろう様々な掃き溜めの臭いがこびりついた蓋の面を躊躇なく押し付けられている。
「あなたはアンジニティ?」
「待ッ……なん、なんなんだってんだいきなり!」
「答えなさい」
一度壁に強く押し込んでから離すと、男は鯉のように口をパクパクと開きながら悲痛に呻いて地面に崩れ落ちた。血液と風俗店の水道から零れた不衛生的な地面に両手を汚して肩で息をしている。
「"あっち"と"こっち"ではいられる体感時間が違うの。あなたは榊の声を聞いた人ね。はやく今の内に答えておいた方が良い」
「さ……な、んで俺がこんな目に……」
「答えろ」
舌打ちと共にうずくまるヤクザ者の腹を蹴り上げた。一度大きくバウンドした男はえづく声を吐き捨てたが、女がバウンドした男の首根っこを掴み上げたことで中身はぶちまけずに済んだ。間髪入れず女はポリバケツの蓋で男の顔を殴りつけ、壁とのラリーを再開した。
「……とりあえず聞いて。キミはワールドスワップの影響を受けて『今』ハザマにいる。一時間しかいられない世界だから早い所、見極める手段が欲しい」
「は、は?」
「エディアンという名に聞き覚えは?」
「し、知らない! そんなやつ聞いたことない! あのイカれた榊ってヤツくらいしか」
「どれくらい情報を把握しているの? 10日前に侵略云々で放送していた人っていうのは周知済みね」
「それは、そう。そうだ、俺ァラジオ越しに聞こえて……」
再び蓋が割れんばかりの殴打が響く。そろそろ限界を超えてひび割れてきた蓋の心配をすることもなく、蹴りと殴打を繰り返す。平たい物体に何度も当てつけられた顔面は青くはれ上がっており、傷口から蓋裏にこびり付く病原菌でも貰いかねないほどに血塗れになっている。
ヤクザはそれでも何とか這い出して逃げようとしたが、それが女の癪に障ったのか、みっともなく動き回る蠅を叩き落とすかのように膝蹴りを相手の腰に打ち当てる。自然に手足がひどくばたついて抵抗が激しくなるものの、その細腕のどこに力があるのかと疑問に思う力で男の体をねじ伏せている。
「あなたはイバラシティ陣営ね」
「う、生まれも育ちも俺ァイバラシティだ。だから同郷だろ?」
「他に結託している人は? このあたりをシマにしている人に、信用ある人物。あとこの10日で動向がおかしい人物を教えて」
「流石に俺もそこまでは分からねェよ!」
「少しは理解があるのね。詳しく教えて」
店の壁が壊れるくらいギリギリと白い腕に力が込められる。ヤクザが女に手を離せと涙声で懇願されてもだんだんと不機嫌になるばかりで、ついに地面へと体を押し付け、マウントを取ってタコ殴りするに至った。これまでずっとそうしてきたように顔だけを的確に殴っていく。
一連の流れを見ていた神無月は底冷えするような恐怖と意味不明な熱に浮かされて硬直していた。駅前で見るような普通の喧嘩であればただ流し見だけして通り過ぎることだろう。しかしこれはあまりにも行き過ぎた暴力だった。集団で囲むリンチでもなければ、金をせびる情婦の淫行でもない。ましてやただの強盗でも恫喝でもない。
「これ、ヤバいやつじゃ……ッ!?」
神無月はとっさに口をついて出た言葉を反芻してから即座に口を閉じた。唇をかみ切らん勢いで防がれたものの、声は表通りの繁華街の喧騒に消えてくれることは無かった。アングラな場所で行われた燦燦たる現場にはよく通っていた。これが酒で焼けた喉なら通りが悪くて聞こえなかったかもしれないのに。男は若い内に死期を悟った。
生き物の生存本能に則るなら今からこの場を逃げ出して、人通りの多い場所へと逃げるべきだった。しかし足がすくんで動かすことが出来ない。
顔はまだ見られていないから足が掬われることはない。だから振り向くべきではないのに後ろでポリバケツの蓋を閉める音が大きく反響したものだから、咄嗟に視線を向けてしまった。
横を見ると先ほどの女がいた。ぼぅっとした胡乱な眼で汚いものを払うように手を払い、陰鬱とした空気を循環させるために胸を膨らませる。そこで神無月はようやく気付いた。女の右側頭部から紫色の角が生えていた。異形の者、異邦者らしい存在であることに。悪魔か何かと見紛うほどの毒々しい見た目のそれは決して人に良い印象を与えない。先端が鋭く尖っていることから殺傷性も十分にあると見て良い。暴力団に近しい海外から派遣されたエージェントかミュータントか。そんな詮無い考えが脳内を駆け巡る。
路地と路地の隙間から入り込んで来た日差しに眼を細め、女は碧眼をやおら細める。長い銀髪を手櫛で梳いてから、視線を向けた儘硬直している男と目が合った。睫の長い、ぱっちりとした形の碧眼だった。年齢は未成年で10代後半と見受けられるあどけなさを残しているものの、女性としての魅力を自負している――そんな印象を与える自信家の眼をしていた。
さっきの男は物音ひとつ立てていないが、死んだのだろうか。先ほどの男と同様に、現場を見た己も路地に引き込まれて半殺しにされた後、無様に次のニュースで死亡の報が流れるのかもしれない。見てはいけないものを見たとはいえ、巻き添えを食らって死ぬというのはあまりにも納得がいかなかった。
何をトチ狂ってヨシバラで死亡した訃報を会社の同僚や、ましてや実家の家族に伝えようものか。そういう目的で来訪した挙句死ぬなどあまりにも情けなくて、これから起こる事象の想像と相まって男は震え、涙を流した。
覚悟は未だ決まらず、うじうじと考える。あれがしたかった、これがしたかったと神無月は走馬燈を見ていると、横顔だけ見えていた片角の少女が真正面に立っていた。笑顔をはりつけて、気恥ずかしそうな少女の風に。
「――他言無用ね」
――嗚呼、まるで天使が舞い降りたような笑顔なのに、その宣告は悪魔からの余命宣告にも聞こえた。
女はウインクと共に人差し指を立てて口元に寄せ、『静かに』のジェスチャーを繰り出すと、何事もなかったかのように繁華街の人ごみの中へと消えて行った。
滂沱の涙を流しながら立ち尽くすサラリーマンに、しかし手を差し伸べてくれる人は誰もいない。この周囲の処世術として困っていても誰も手助けをしてはくれない。利用されれば利用されるだけ使い棄てられる、そんな世界なのだ。
神無月は袖で涙を拭い、横向き以上に顔を振り返ることはしなかった。とりあえずこのまま地元の駅まで戻って、帰りにレンタルDVDでも借りて予定の時間を有意義に使おう。
彼は背中に冷たいものを感じながらも、きびきびとした足取りでヨシバラを後にするのだった。











駄石(50 PS)を購入しました。
武術LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
幻術LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
使役LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
料理LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)
エネ(14) により ItemNo.5 不思議な石 から装飾『【一周目】』を作製してもらいました!
⇒ 【一周目】/装飾:強さ30/[効果1]幸運10 [効果2]- [効果3]-/特殊アイテム
レーコとピース(713) により ItemNo.4 不思議な牙 から射程1の武器『羨望と希望の心』を作製してもらいました!
⇒ 羨望と希望の心/武器:強さ30/[効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程1】/特殊アイテム
ItemNo.6 不思議な食材 から料理『デトックス・ハーブティ』をつくりました!
⇒ デトックス・ハーブティ/料理:強さ30/[効果1]治癒10 [効果2]活力10 [効果3]鎮痛10/特殊アイテム
レッド(151) とカードを交換しました!
ブレイク (ブレイク)

エキサイト を習得!
シャイン を習得!
ラッシュ を習得!
リフレクション を習得!
リフレックス を習得!
チャーム を習得!
魅惑 を習得!



次元タクシーに乗り『チナミ区 E-5:出発地』に転送されました!
チナミ区 E-6(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 E-7(道路)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 E-8(道路)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 D-8(道路)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 D-9(道路)に移動!(体調26⇒25)
レーコとピース(713) をパーティに勧誘しました!
ルリ(1507) をパーティに勧誘しました!
エネ(14) をパーティに勧誘しました!






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャットで時間が伝えられる。
エディアンの前に1台のタクシーが止まり、窓が開く。

帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。
窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。
エディアンからのチャットが閉じられる――




















































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



そのとき、神無月は初めての風俗に挑戦しようと決意を固めていたところだった。2月の肌寒い、ミナト区の大橋前での決断であった。
この世に生を受けて24年、しがないサラリーマン生活をして1年が過ぎようとしている平凡な男だ。大学を卒業したにも関わらず在学中はこれといった女をえり好みした所為で合コンのチャンスも逃し、異性の感触を理解できないまま生きてきた。
元々、女に興味が無かったわけではなくましてやゲイでもない。彼にとって経験すること自体の好機すら棒に振ったことを何となく尾を引いたことが起因する。
酒の席で童貞であること話題されて同僚にからかわれ、先輩から経験したらどうだと焚きつけられたのが三日前。意地になった男は月給の四分の一を予算にして特殊浴場に向かう事にした。
二時間後には一皮むけた大人の男になるんだと不安を8割胸に残し、胸中は決して快晴とは言えない気分の儘に夕暮れに泥む欲望の街へと赴いた。
マガサ駅から南に移動し、歓楽街で知られるヨシバラへと足を運ぶと目に優しくない色でチカつくネオンに視界を奪われる。
神無月はこれ、といった店を予約して行くことをしなかった。そういう店に電話を掛けるのも気恥ずかしくて、システムも理解できないから適当に練り歩く程度に見て回ろうと考えたのだ。
しかし決め打ちしてかかるには情報が足りなさ過ぎた。倒錯的な性愛者向けの店や、みるからにぼったくりする気満々の個人経営の酒場、特殊なカフェに喧しく宣伝するボーイのキンキン声が鬱陶しいとすら感じる。
あるいは現代において穢れとされる異形が跋扈するいかにもな店が嫌でも目に付いたくらいで、有体に言えば男は立ち往生していた。ポケットに手を突っ込んで定期入れの感触を指先で確かめながらため息をつく。
「出直すべきかなァ」
そこで男はべこんと軽快な衝突音を耳にした。剥き出しになったパイプがちらつく喧騒から離れた路地裏からだった。生き物の呻き声が遅れて聞こえてきたものだから、路地の入口でそれとなくスマホを開きながら聞き耳を立てる。
今度は明確だった。やはり何か生物の声がする。続けて壁に何かをこすりつけるような音。加えて、鉄板がぶつかったような重々しい音ではなく日常的に耳にする……咄嗟に出力するには少々時間がかかり具体的な言葉を出すまでに数秒程要した異音が一つ。
「なんだ、酔っぱらい同士が小競り合いか?」
路地裏の近場には青色のカラーリングが特徴的な円筒状のプラスチックのゴミ箱がある。隣接するビルが風俗店を営んでいることからそこが所有しているものだろう。
ゴミ箱の口から花のように開く黒色でコーティングされたビニールは、中身を見せないための工夫が施されている――有体に言えば生ゴミを世間一般の眼に晒さないようにするための措置である。
酔っぱらいが転倒して転がしたのかと思ったが、ポリバケツの中身はぶちまけられてはいなかった。
恐る恐る男が覗き込むと、斜陽の差し込まない暗がりに点々と赤黒い飛沫が見えた。ともあればただの模様とでも認識できる程度の誤差だが、乾ききっていないそれが今しがた噴き出したものであると認識できたのは数分してからのことだった。
今、目の前で起こっている状況を把握するので手一杯だったのだ。
大腿部を大きく露出したデニムのホットパンツが眩しく、対して真っ白なリブ生地のニットで白い柔肌を覆う女だった。横顔しか確認できないものの年端もいかない少女風貌といった華奢な女性で、成人すらしていないであろうことが窺える。
この路地はバカスカと建築したせいで通行することが出来ない行き止まりの場所である。専ら近隣の店のボーイが隠れて煙草を吸ったり、胃袋を中身をぶちまけるためにあるような袋小路という最低な環境にあった。
壁に向けてポリバケツの蓋をぐっと押し込むさまは傍から見ると間抜け甚だしい――と考えたのは一瞬。
「せっかくの相談は嬉しいけど、その前に質問ね」
こういったアンダーな場所で交わされる会話というのは、当然ながらロクなものではない。風営法にひっかかる内容以前に、法的に引っかかる内容が語られることも大して珍しいことではない。
そんな現場をこの目で見るのがあまりにもレアケースなのだが、つまるところ今はヤバい現場を眼にしている、ということに他ならない。
援助交際の申し出相手が奥にいるのか、逆ナンで買って貰おうとくいっぱぐれている家出少女の可能性もある。
恐怖と好奇の儘に神無月が眼を凝らすと、ポリバケツの蓋の中には人の頭があった。目で追いかけると胴部はきちんとあって生きた人間であることが認識できた。人間はいかにもといったヤクザ者だ。鼻ピアスやサングラス、派手な色のコートに身を包んでいて、そのくせ手指に付けている装飾品だけはいっちょ前な若いながらも明らかにそういう手合いの人間だった。
但しサングラスで威厳を出そうとした顔は醜くぼこぼこにされていて、ポリバケツの蓋を押し付けられていることもあって現在進行形でひどい変顔を晒していた。長年使い続けているであろう様々な掃き溜めの臭いがこびりついた蓋の面を躊躇なく押し付けられている。
「あなたはアンジニティ?」
「待ッ……なん、なんなんだってんだいきなり!」
「答えなさい」
一度壁に強く押し込んでから離すと、男は鯉のように口をパクパクと開きながら悲痛に呻いて地面に崩れ落ちた。血液と風俗店の水道から零れた不衛生的な地面に両手を汚して肩で息をしている。
「"あっち"と"こっち"ではいられる体感時間が違うの。あなたは榊の声を聞いた人ね。はやく今の内に答えておいた方が良い」
「さ……な、んで俺がこんな目に……」
「答えろ」
舌打ちと共にうずくまるヤクザ者の腹を蹴り上げた。一度大きくバウンドした男はえづく声を吐き捨てたが、女がバウンドした男の首根っこを掴み上げたことで中身はぶちまけずに済んだ。間髪入れず女はポリバケツの蓋で男の顔を殴りつけ、壁とのラリーを再開した。
「……とりあえず聞いて。キミはワールドスワップの影響を受けて『今』ハザマにいる。一時間しかいられない世界だから早い所、見極める手段が欲しい」
「は、は?」
「エディアンという名に聞き覚えは?」
「し、知らない! そんなやつ聞いたことない! あのイカれた榊ってヤツくらいしか」
「どれくらい情報を把握しているの? 10日前に侵略云々で放送していた人っていうのは周知済みね」
「それは、そう。そうだ、俺ァラジオ越しに聞こえて……」
再び蓋が割れんばかりの殴打が響く。そろそろ限界を超えてひび割れてきた蓋の心配をすることもなく、蹴りと殴打を繰り返す。平たい物体に何度も当てつけられた顔面は青くはれ上がっており、傷口から蓋裏にこびり付く病原菌でも貰いかねないほどに血塗れになっている。
ヤクザはそれでも何とか這い出して逃げようとしたが、それが女の癪に障ったのか、みっともなく動き回る蠅を叩き落とすかのように膝蹴りを相手の腰に打ち当てる。自然に手足がひどくばたついて抵抗が激しくなるものの、その細腕のどこに力があるのかと疑問に思う力で男の体をねじ伏せている。
「あなたはイバラシティ陣営ね」
「う、生まれも育ちも俺ァイバラシティだ。だから同郷だろ?」
「他に結託している人は? このあたりをシマにしている人に、信用ある人物。あとこの10日で動向がおかしい人物を教えて」
「流石に俺もそこまでは分からねェよ!」
「少しは理解があるのね。詳しく教えて」
店の壁が壊れるくらいギリギリと白い腕に力が込められる。ヤクザが女に手を離せと涙声で懇願されてもだんだんと不機嫌になるばかりで、ついに地面へと体を押し付け、マウントを取ってタコ殴りするに至った。これまでずっとそうしてきたように顔だけを的確に殴っていく。
一連の流れを見ていた神無月は底冷えするような恐怖と意味不明な熱に浮かされて硬直していた。駅前で見るような普通の喧嘩であればただ流し見だけして通り過ぎることだろう。しかしこれはあまりにも行き過ぎた暴力だった。集団で囲むリンチでもなければ、金をせびる情婦の淫行でもない。ましてやただの強盗でも恫喝でもない。
「これ、ヤバいやつじゃ……ッ!?」
神無月はとっさに口をついて出た言葉を反芻してから即座に口を閉じた。唇をかみ切らん勢いで防がれたものの、声は表通りの繁華街の喧騒に消えてくれることは無かった。アングラな場所で行われた燦燦たる現場にはよく通っていた。これが酒で焼けた喉なら通りが悪くて聞こえなかったかもしれないのに。男は若い内に死期を悟った。
生き物の生存本能に則るなら今からこの場を逃げ出して、人通りの多い場所へと逃げるべきだった。しかし足がすくんで動かすことが出来ない。
顔はまだ見られていないから足が掬われることはない。だから振り向くべきではないのに後ろでポリバケツの蓋を閉める音が大きく反響したものだから、咄嗟に視線を向けてしまった。
横を見ると先ほどの女がいた。ぼぅっとした胡乱な眼で汚いものを払うように手を払い、陰鬱とした空気を循環させるために胸を膨らませる。そこで神無月はようやく気付いた。女の右側頭部から紫色の角が生えていた。異形の者、異邦者らしい存在であることに。悪魔か何かと見紛うほどの毒々しい見た目のそれは決して人に良い印象を与えない。先端が鋭く尖っていることから殺傷性も十分にあると見て良い。暴力団に近しい海外から派遣されたエージェントかミュータントか。そんな詮無い考えが脳内を駆け巡る。
路地と路地の隙間から入り込んで来た日差しに眼を細め、女は碧眼をやおら細める。長い銀髪を手櫛で梳いてから、視線を向けた儘硬直している男と目が合った。睫の長い、ぱっちりとした形の碧眼だった。年齢は未成年で10代後半と見受けられるあどけなさを残しているものの、女性としての魅力を自負している――そんな印象を与える自信家の眼をしていた。
さっきの男は物音ひとつ立てていないが、死んだのだろうか。先ほどの男と同様に、現場を見た己も路地に引き込まれて半殺しにされた後、無様に次のニュースで死亡の報が流れるのかもしれない。見てはいけないものを見たとはいえ、巻き添えを食らって死ぬというのはあまりにも納得がいかなかった。
何をトチ狂ってヨシバラで死亡した訃報を会社の同僚や、ましてや実家の家族に伝えようものか。そういう目的で来訪した挙句死ぬなどあまりにも情けなくて、これから起こる事象の想像と相まって男は震え、涙を流した。
覚悟は未だ決まらず、うじうじと考える。あれがしたかった、これがしたかったと神無月は走馬燈を見ていると、横顔だけ見えていた片角の少女が真正面に立っていた。笑顔をはりつけて、気恥ずかしそうな少女の風に。
「――他言無用ね」
――嗚呼、まるで天使が舞い降りたような笑顔なのに、その宣告は悪魔からの余命宣告にも聞こえた。
女はウインクと共に人差し指を立てて口元に寄せ、『静かに』のジェスチャーを繰り出すと、何事もなかったかのように繁華街の人ごみの中へと消えて行った。
滂沱の涙を流しながら立ち尽くすサラリーマンに、しかし手を差し伸べてくれる人は誰もいない。この周囲の処世術として困っていても誰も手助けをしてはくれない。利用されれば利用されるだけ使い棄てられる、そんな世界なのだ。
神無月は袖で涙を拭い、横向き以上に顔を振り返ることはしなかった。とりあえずこのまま地元の駅まで戻って、帰りにレンタルDVDでも借りて予定の時間を有意義に使おう。
彼は背中に冷たいものを感じながらも、きびきびとした足取りでヨシバラを後にするのだった。



 |
ヒトミ 「勇者……そう、ヒトミは本物の勇者なんだ。世界を救ってあげないと」 |







駄石(50 PS)を購入しました。
武術LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
幻術LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
使役LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
料理LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)
エネ(14) により ItemNo.5 不思議な石 から装飾『【一周目】』を作製してもらいました!
⇒ 【一周目】/装飾:強さ30/[効果1]幸運10 [効果2]- [効果3]-/特殊アイテム
| ギイ 「マズハ挨拶ガワリの一仕事トイキマショウ。‥‥シカシナンデスカネ、コレハ。」 |
レーコとピース(713) により ItemNo.4 不思議な牙 から射程1の武器『羨望と希望の心』を作製してもらいました!
⇒ 羨望と希望の心/武器:強さ30/[効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程1】/特殊アイテム
 |
いっパい殺ソうネ |
ItemNo.6 不思議な食材 から料理『デトックス・ハーブティ』をつくりました!
⇒ デトックス・ハーブティ/料理:強さ30/[効果1]治癒10 [効果2]活力10 [効果3]鎮痛10/特殊アイテム
 |
ヒトミ 「……飲める薬草」 |
レッド(151) とカードを交換しました!
ブレイク (ブレイク)

エキサイト を習得!
シャイン を習得!
ラッシュ を習得!
リフレクション を習得!
リフレックス を習得!
チャーム を習得!
魅惑 を習得!



次元タクシーに乗り『チナミ区 E-5:出発地』に転送されました!
チナミ区 E-6(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 E-7(道路)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 E-8(道路)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 D-8(道路)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 D-9(道路)に移動!(体調26⇒25)
レーコとピース(713) をパーティに勧誘しました!
ルリ(1507) をパーティに勧誘しました!
エネ(14) をパーティに勧誘しました!






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
エディアン 「1時間が経過しましたね。」 |

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
チャットで時間が伝えられる。
 |
エディアン 「ナレハテとの戦闘、お疲れ様でした! 相手を戦闘不能にすればいいようですねぇ。」 |
 |
エディアン 「さてさて。皆さんにご紹介したい方がいるんです。 ――はぁい、こちらです!こちらでーっす!!」 |
エディアンの前に1台のタクシーが止まり、窓が開く。

ドライバーさん
次元タクシーの運転手。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。
 |
ドライバーさん 「どーも、『次元タクシー』の運転役だ。よろしく。」 |
帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。
 |
エディアン 「陣営に関わらず連れて行ってくれるようですのでどんどん利用しましょー!! ドライバーさんは中立ってことですよね?」 |
 |
ドライバーさん 「中立っつーかなぁ・・・。俺もタクシーも同じのが沢山"在る"んでな。 面倒なんで人と思わずハザマの機能の一部とでも思ってくれ。」 |
 |
ドライバーさん 「ま・・・チェックポイントとかの行き来の際にゃ、へいタクシーの一声を。じゃあな。」 |
窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。
 |
エディアン 「たくさん・・・ 同じ顔がいっぱいいるんですかねぇ・・・。 ここはまだ、分からないことだらけです。」 |
 |
エディアン 「それでは再びの1時間、頑張りましょう! 新情報を得たらご連絡しますね。ファイトー!!オーッ!!」 |
エディアンからのチャットが閉じられる――



ワンワンらんどのヤバいやつら
|
 |
ハザマに生きるもの
|


ENo.283
黙し告げぬ天津風



【イバラシティ】
イバラシティで『勇者』を自称する不良娘。
本名は「天津風ヒトミ」。黙し告げぬとは彼女の異名。
正義の名の下に悪を討ち、わるい人達に喧嘩を吹っ掛けて治安を守っている。
公認された治安部隊ではなく個人活動なのでただの喧嘩になっており、よく警察のお世話になっている。
座右の銘は『諦めなければ道は開く』
異能は『不撓不屈』
精神の発心。自他問わず心を前進させ、叱咤激励を与える。
要約すると、並外れた気合と根性で意志を強める異能。
気合で外れた関節を戻す、足が砕けても腕だけで前進するという「諦めなければ前に進める」「だから絶対に負けない」「最後は必ず自分が勝つ」を文句にした根性論を現実に引き起こす。
よく夕暮れ時の駅前や歓楽街の路地裏を徘徊している。
ストイックで挑発的な性格。口調は軽いが強い信念を持つ。
一人称は『ヒトミ』。たまにちゃん付けする。
【基本情報】
18歳女性。165cm
右側頭部から紫色の悪魔の角が生えている。山羊に近い形状で非常に堅牢、とても鋭い。生え変わりや脱皮はしない上、神経も通っていないので冷たい。
白髪のロングヘア。碧眼に白い肌と異邦人らしい容姿。
人ならざる容姿をしているものの『勇者』だから違うらしい。
「悪魔でも天使でもなく、ヒトミはヒトミ」とは当人の弁。
性格は『てきとう』。その場の状況によってノリが変動し、空気を読まない者がいれば無遠慮に舌打ちする。上下関係、親しさの有無に関わらず暴言を吐く。自分がその対象だった際も素直に謝ったり流したりと、かなりの気分屋。
義憤に駆られやすく、困っている人物がいれば助けたりもする。どのような手であれ利用するものは使い尽くすと公言して憚らないので非常識な行動も取りやすい。
全体的に軽率でチャラい言葉遣いが多く、今風の若者らしさ溢れる。
逆に誰が相手だろうと平等に接することを心掛けており、総合すれば表裏のない人物像と言える。
【ハザマ】
頭の両側頭部から角を生やした悪魔のような影を持つ片角の少女。影は『黙し告げぬ天津風』に沈み込み、時に這い出ては非対称的な姿を浮かび上がらせる。
彼女の正体は紛れもない『勇者』
『無間の世界』で魔王を討伐し、本物の勇者となった存在。
その世界では魔王が打倒されると、勇者以外の記録や情報の全てを更地にし、同じ人物で魔王に挑ませるという運命を科す。
悪魔の角は魔王の角。魔王を討伐した証として『勇者』が生まれ持つ実績。片角を持った少女は二周目での姿。影はいずれ訪れる成れの果てが『不撓不屈』で無理やり留まっている。
最強のボスを打倒し、あらゆる叡智と世界を踏破し、見慣れた結末を幾度も繰り返した末にアンジニティに堕とされた。
『二周目』と『成れの果て』は互いに意思疎通が可能。
容姿は影を除いてイバラシティと変化がないものの、こちらでの精神性はより強固になる。
どんな人物にも分け隔てなく対応し、諦めずに立ち向かい、理解させるために拳を振るうことも厭わない。
進むことを止めなければ、困難は踏破できると信じる限り。
イバラシティで『勇者』を自称する不良娘。
本名は「天津風ヒトミ」。黙し告げぬとは彼女の異名。
正義の名の下に悪を討ち、わるい人達に喧嘩を吹っ掛けて治安を守っている。
公認された治安部隊ではなく個人活動なのでただの喧嘩になっており、よく警察のお世話になっている。
座右の銘は『諦めなければ道は開く』
異能は『不撓不屈』
精神の発心。自他問わず心を前進させ、叱咤激励を与える。
要約すると、並外れた気合と根性で意志を強める異能。
気合で外れた関節を戻す、足が砕けても腕だけで前進するという「諦めなければ前に進める」「だから絶対に負けない」「最後は必ず自分が勝つ」を文句にした根性論を現実に引き起こす。
よく夕暮れ時の駅前や歓楽街の路地裏を徘徊している。
ストイックで挑発的な性格。口調は軽いが強い信念を持つ。
一人称は『ヒトミ』。たまにちゃん付けする。
【基本情報】
18歳女性。165cm
右側頭部から紫色の悪魔の角が生えている。山羊に近い形状で非常に堅牢、とても鋭い。生え変わりや脱皮はしない上、神経も通っていないので冷たい。
白髪のロングヘア。碧眼に白い肌と異邦人らしい容姿。
人ならざる容姿をしているものの『勇者』だから違うらしい。
「悪魔でも天使でもなく、ヒトミはヒトミ」とは当人の弁。
性格は『てきとう』。その場の状況によってノリが変動し、空気を読まない者がいれば無遠慮に舌打ちする。上下関係、親しさの有無に関わらず暴言を吐く。自分がその対象だった際も素直に謝ったり流したりと、かなりの気分屋。
義憤に駆られやすく、困っている人物がいれば助けたりもする。どのような手であれ利用するものは使い尽くすと公言して憚らないので非常識な行動も取りやすい。
全体的に軽率でチャラい言葉遣いが多く、今風の若者らしさ溢れる。
逆に誰が相手だろうと平等に接することを心掛けており、総合すれば表裏のない人物像と言える。
【ハザマ】
頭の両側頭部から角を生やした悪魔のような影を持つ片角の少女。影は『黙し告げぬ天津風』に沈み込み、時に這い出ては非対称的な姿を浮かび上がらせる。
彼女の正体は紛れもない『勇者』
『無間の世界』で魔王を討伐し、本物の勇者となった存在。
その世界では魔王が打倒されると、勇者以外の記録や情報の全てを更地にし、同じ人物で魔王に挑ませるという運命を科す。
悪魔の角は魔王の角。魔王を討伐した証として『勇者』が生まれ持つ実績。片角を持った少女は二周目での姿。影はいずれ訪れる成れの果てが『不撓不屈』で無理やり留まっている。
最強のボスを打倒し、あらゆる叡智と世界を踏破し、見慣れた結末を幾度も繰り返した末にアンジニティに堕とされた。
『二周目』と『成れの果て』は互いに意思疎通が可能。
容姿は影を除いてイバラシティと変化がないものの、こちらでの精神性はより強固になる。
どんな人物にも分け隔てなく対応し、諦めずに立ち向かい、理解させるために拳を振るうことも厭わない。
進むことを止めなければ、困難は踏破できると信じる限り。
25 / 30
0 PS
チナミ区
D-9
D-9




































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果等 |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]-【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |
| 4 | 羨望と希望の心 | 武器 | 30 | [効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程1】 |
| 5 | 【一周目】 | 装飾 | 30 | [効果1]幸運10 [効果2]- [効果3]- |
| 6 | デトックス・ハーブティ | 料理 | 30 | [効果1]治癒10 [効果2]活力10 [効果3]鎮痛10 |
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV5)[効果2]活力10(LV10)[効果3]鎮痛10(LV15) |
| 8 | 駄石 | 素材 | 10 | [武器]活力10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]器用10(LV20) |
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 5 | 身体/武器/物理 |
| 幻術 | 5 | 夢幻/精神/光 |
| 使役 | 10 | エイド/援護 |
| 料理 | 20 | 料理に影響。 |
アクティブ
| スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| バッシュ (ブレイク) | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 |
| ポイント (ピンポイント) | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 |
| クリック (クイック) | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 |
| ボール (ブラスト) | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 |
| ビンタ (ヒール) | 5 | 0 | 20 | 味傷:HP増 |
| エキサイト | 5 | 0 | 40 | 敵:攻撃+自:AT増(1T) |
| シャイン | 5 | 0 | 60 | 敵貫:SP光撃&朦朧 |
| ラッシュ | 5 | 0 | 60 | 味全:連続増 |
| リフレクション | 5 | 0 | 60 | 自:反射 |
| リフレックス | 5 | 0 | 80 | 味:AT・DX増(4T) |
| チャーム | 5 | 0 | 40 | 敵:SP光撃&魅了・混乱 |
パッシブ
| スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 |
| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 |
| 活力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 |
| 体力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 |
| 治癒 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 |
| 幸運 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:運増 |
| 魅惑 | 5 | 5 | 0 | 【常時】異能『使役』のLVに応じて、戦闘勝利時に敵をエイドにできる確率が上昇 |





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |

PL / えーや