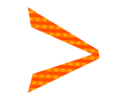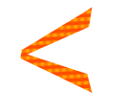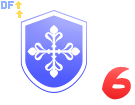<< 10:00~11:00




//side:イバラシティ
その日は、雪が降りそうな曇天だった。
来る者を遠ざけるような厳しい門を通り抜けると、重厚さを醸し出す日本家屋が見えた。
広い庭には番犬として黒い犬が多頭放し飼いにされていて、いかにも高そうな鯉の泳ぐ池もあれば、手入れの行き届いた日本庭園まである。
実際、今は庭師が植木を剪定しているところだった。
(相変わらず金かかってんなあ)
そんなことを思いながら、男は砂利の敷き詰められた一角を進む。
じゃり、ざり、と音を響かせて歩けば番犬がひょいと顔を出して、一瞬で興味を無くして去っていった。
広すぎる庭をゆったりと横切った先には、敷地の端も端に建てられた離れがあった。
一般家庭からすれば十二分に広い家だ。
けれど、喧騒から切り離されたような、しんと静かな空気だけがそこにあった。
離れはこの敷地内ではまだ新しい部類の建物であるはずなのに、どこか陰鬱とした雰囲気がある。
「おう、何見てんだ?」
男は、離れの前庭に向かって声を掛けた。
赤い椿の生け垣の影に、もそりと動くものがいた。
それは返事もせずに、視線だけをこちらに向けた。
椿のような、血のような赤色が男を映す。
「……返事しろよー」
男はため息とともに数歩の距離を詰めると、それを見下ろした。
灰とも銀とも言える髪をした、外国の血を感じさせる子供だ。
椿の生け垣の影に屈み込んでいる所為で、一層小さく見える。
その小さな手や、まろい頬は、赤黒く変色していた。
痛そうなそれらに一瞬顔をしかめかけてから、へらりと笑った。
「まぁた、こんな怪我こさえてからに」
「早く治せよ、各務」
「へえへえ」
わかりましたあ、と逆撫でする返事をしながら、男――各務は隣に屈み込んだ。
手に、頬に、あとは左足。
どこから治すべきかと考えながら、手を伸ばす。
この狂った家の中で、さらに一等狂った女の腹から生まれた子供は、こうして日々痛めつけられている。
そしてそれを治し、再び送り出すのが各務の役目だ。
(胸糞悪い。あーやだやだ)
分家も分家で、尚且椿坂家を母体とする組に所属する各務家としては、この役目を辞退する手段は持たない。
この子供自身が振り切る力を持って初めて、それは叶うだろう。
ただしその時、各務はまた別の役割を与えられるに違いない。
各務自身もまだ成人して間もないせいで、逃げる展望を思い描けないでいるのだから。
「はい、出来上がり。表面上はな。痛みが激しいところはあるか?」
「平気」
「本当にー?」
「ウザい、おっさん」
「おっ……! 俺まだ二十三なんだけど! ピッチピチの医学生だよ!?」
「十も違えば十分おっさんでしょ。あと学歴マウントは嫌われるからやめたほうがいい」
そこで初めて、目の前の子供が笑った。
内心でほっとしつつ、いっそ撫でてやろうかと手を伸ばせば、今度はすげなく避けられた。
「ガキは大人しく撫でられていろよなあ」
「そのガキより無力な大人が何言ってんだよ」
「あ゛~、可愛くねえ!」
今度こそ避けられないように、子供の頭をがしがしと撫でた。
やめろ、離せ、と言いながら撫でられる子供の首は細い。
ぐりんぐりんと揺れる頭に合わせて、ぽきりと折れそうだった。
「やめ、ろよ! 大体!」
「お」
片手で振り払われて、やや肩で息をする子供が眼光鋭く睨んできた。
降参の形で手を離しながら合わせた視線の、その瞳の中に、思わず『あの日』の色を探す。
『これは、治癒の異能を持っているのよ』
赤い唇をにぃっと上げた主家の女が言ったのは、今より数年前のことだ。
これ、と紹介と言うよりは説明された各務は、向き合う形で立っている小さな子供に礼をした。
事前に聞いた情報では、この女の息子らしい。
海外のマフィアの男との間に出来たらしいが、件の男はこの女を歯牙にも掛けず捨て置いたらしい。
らしいらしいと、伝聞の多い情報だったけれど、間違いではなかったことをこの時知った。
女はその子供に各務の異能についてを説明して、おもむろに子供に近寄った。
『え』
思わず声が出た。
女が笑みを貼り付けたまま、子供の腹にナイフを突き立てたのだ。
なんで、と呟いた子供の声は、寸分違わず各務の心の声だった。
それからのことは、もはや記憶が薄い。
子供が刺されて、自分が癒やして、それを繰り返す。
情けないことに、命ぜられたこと以外何も出来なかった。
繰り返される狂気の中、立ち込める鉄さびの臭気は子供の命がこぼれていく証跡そのものだったのに、その場で止められるのは自分だけだったのに、木偶のように突っ立っていた。
『ごめ、なさい、次、は……うまく、やり、ます』
もはや立っていられない子供が謝って、今日はこれで終いだと女はその場を後にした。
心配することもなく、一度も振り返ることなく。
傷を癒やしながらも、各務はこの空間では路傍の石でしかなかった。
その石が、子供を見下ろす。
子供の赤いビー玉のような目からころりと涙が落ちて、各務は人の心が死ぬ瞬間を見た。
あの暗さは、染みのように子供の目の奥に宿ったままだ。
ただ、浮き沈みがあるようで、今はその色が遠い。
「……大体、お前はその顔で助かっているんだ。 僕よりはマシだろ」
「…………ああもう、そう言うとこだぞー」
「何が」
「クウィリーノ坊ちゃんの悪くて良いところ」
「はあ?」
一瞬で陰りを見せる目が、ゆらゆらと揺れる。
顔が血縁上の父親によく似て『可愛い』せいで構われている子供。
きっとクウィリーノは、可愛くないほうが生きやすかったに違いない。
相変わらず人気のない庭の隅で、各務は無理矢理に笑った。
「やっぱりお前は可愛くねえなあ」
「そう」
「そうそう」
再び手を伸ばそうとして、ぱしりと躊躇いのない強さではたき落とされながら、今度は自然に笑う。
と、その可愛くない顔が、悪そうな顔に歪んだ。
「ん? 何だ急に。お兄さんぞっとしたんだけど」
「……十三だ。その年に僕は家を出る。お前もついて来い」
「は……」
「ついでに便利そうな者数人も引っ張っていく」
「おい」
「その日までお前は僕で異能を高めろ。家に従順でいろ。逆らわず、手駒を演じろ」
「ちょ」
矢継ぎ早に言われる言葉はどれも小さく早口で、子供らしからぬ平坦さだった。
口をぱくぱくとしていれば、間抜け面、と悪態を挟まれる。
本当に可愛くない顔だった。
「だから、もう個人的にはここには来るな。治癒は『あの場』だけでギリギリまで使え」
もはや声も出ず、子供を凝視する。
闇に揺らめいていた目が、ぎらぎらと輝いていた。
子供の戯言と言い切れない熱が、それにはある。
「え、何、いきなりすぎてこわ……」
「椿組に飼われるのは嫌なんだろ? 今度は僕が飼ってやるよ、『お兄ちゃん』?」
「うわあ……」
飼い殺される未来を悲観していたことを、十歳を少し超えた程度の子供に見抜かれていた。
しかもどうやら、正しく各務の『上』の立場でいるらしい。
あの悪夢が始まる前は、それでも子供の範疇にいただろうに、いつの間にか随分と酷い進化をしていたようだ。
「あ、裏切るなら覚悟してやって」
「普通に何か出来る力があるのが怖ぇ……」
「だって、気付いたんだよ。この僕が、ここの奴らに使い潰されるなんて。損失でしょ?」
「うわああ……」
今度はころりと天使のような笑顔で笑うものだから、各務は戦慄した。
これに騙される人間は多いに違いない。
各務だって、数秒前の悪人顔や悪口を目撃していなければ騙されただろう。
けれどその姿の影に、この子供に課されたもの、強制された日々が見えた気がして喉奥で呻いた。
「……しくじるなよ」
「各務もな」
ふん、と笑って、子供は背伸びをしてから家に歩を進めた。
寒々しい家に向かう姿は、やはり子供の頼りなさがあった。
「……とりあえず、そのクッソ似合わねえ悪そうな口調はやめておけよ! 人当たり良くしとけ」
「はあい」
ひらりと手を振って、子供は家に戻って行った。
その閉ざされた扉を見ていると、冬らしい寒風がびゅうと強く吹いた。
「っぶしゅっ、……あ゛ー……さっむ」
すんと鼻をすすって、両手をすり合わせる。
風邪を引いてはたまらないと、各務は帰ることにした。
赤い椿、赤い目の子供、自分の今後の身の振り方。
(やべえ……思ったより大変なことになった……)
途方に暮れて見上げた空は、雪を降らせることもなく、ただただ曇って暗かった。
//
「はい、治して」
「うわ出た」
カメリアの医務室に、クウィリーノはひょいと顔を出した。
先程ねこと格闘した傷を目の前の男に見せれば、いててて、と相手が痛がった。
いい歳したおっさんの演技は無視に限る。
「まぁた、こんな怪我こさえてからに。何、マゾなの?」
「違うけど?」
「知ってるけど!」
ぶつぶつ言いながら、男――各務は異能で治してくれた。
少しの傷くらいは自己治癒に任せるけれど、これはさすがに深すぎると判断されたらしい。
その異能を行使するスピードは、長年の経験からか素早く滑らかだ。
実に使える人間になったなと、クウィリーノは内心だけで褒めた。
口に出すと調子に乗るから、褒め時を見誤ってはならない。
「ねー、今度大きめの仕事があるからさ。車待機していてくれる?」
「おお、わかった。力の使い過ぎには気をつけろよ」
「はあい」
「うわあ……」
愛想よく笑ったはずなのに、各務は嫌そうな顔をするのが面白い。
口調はなるべく柔らかく、を意識してこうなって久しいのに、未だ慣れないらしい。
厳しい口調のほうがいいのならば、各務こそがマゾだろう。
「まあ、詳細は阿左見……いや、雲右に持ってこさせるよ」
「おお」
わかったわかったと手を振って、クウィリーノの電子カルテに打ち込むのを見る。
その声が少し嬉しそうなのは、あの家を出る時に引っ張ってきた人のうちに雲右も含まれるからだ。
兄よりも父のほうが近い関わりをした相手には、やはり愛着が湧くようだ。
「各務」
「んー?」
「ここ、白髪すごいある」
「はっ!?」
バッと振り返った顔は、嘘だろ、という表情だった。
手鏡を手に、ざかざかと後頭部を搔いている。
「うっそー✩」
「おまっ……いやそれ本当だろうな? と言うか白髪が増えたら絶対お前の所為だからな!?」
「あは」
苦労を掛けているのは自覚している。
これでもある程度は自重をしているのだけれど、やはり仕事に傷はつきものであるので、なくすことは難しい。
ただ、ほんの少しだけ、本当にもう少しだけ自重をしてもいいなと、ふと思った。
「それじゃ、また来るねー」
「怪我して来んなよ」
つまりは、遊びには来ていいらしい。
お人好し、と心の中で舌を出しつつ、クウィリーノは医務室を後にした。
寒い家、赤い椿、雪の降りそうな曇天の日。
ばれたら自分が危うくなると言うのに、わざわざ関わりの薄い子供を癒やしに来た男を思い出す。
あの日家の中に戻って、何故だか鼻の奥がツンとしたことは、クウィリーノだけの思い出だった。












お肉(50 PS)を購入しました。
お肉(50 PS)を購入しました。
すごい木材(400 PS)を購入しました。
解析LV を 5 UP!(LV15⇒20、-5CP)
合成LV を 5 UP!(LV70⇒75、-5CP)
ItemNo.1 不思議な武器 に ItemNo.2 不思議な防具 を合成し、駄物 に変化させました!
⇒ 駄物/素材:強さ10/[武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50)/特殊アイテム
⇒ 駄物発生!駄物 を入手!
ItemNo.18 花びら に ItemNo.19 不思議な雫 を合成し、何か柔らかい物体 に変化させました!
⇒ 何か柔らかい物体/素材:強さ10/[武器]治癒10(LV20)[防具]命脈10(LV25)[装飾]防御10(LV20)
ItemNo.30 何かの骨 に ItemNo.24 紅小石 を合成実験し、白い塊 に変化することが判明しました!
⇒ 白い塊/素材:強さ20/[武器]閃光10(LV20)[防具]治癒10(LV10)[装飾]気合10(LV20)
チュイ(1519) により ItemNo.20 翌檜 から魔晶『ハーフリムの眼鏡』を作製してもらいました!
⇒ ハーフリムの眼鏡/魔晶:強さ106/[効果1]幸運25 [効果2]- [効果3]充填15
雪里(1373) により ItemNo.28 お肉 から料理『さっぱり冷しゃぶ』をつくってもらいました!
⇒ さっぱり冷しゃぶ/料理:強さ85/[効果1]攻撃10 [効果2]防御10 [効果3]増幅10
山田(198) とカードを交換しました!
カルコサ聖帰団の名刺 (アウデンティア)
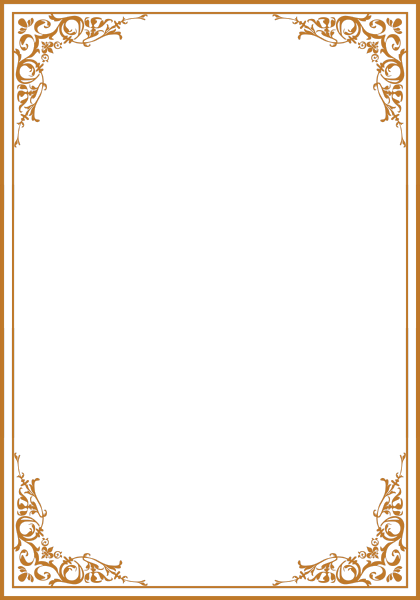
超過適応 を研究しました!(深度0⇒1)
超過適応 を研究しました!(深度1⇒2)
超過適応 を研究しました!(深度2⇒3)
ウィークサーチ を習得!
クリエイト:マシンガン を習得!
機知奇策 を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



クゥ(1372) は 腐肉 を入手!
チュイ(1519) は 腐肉 を入手!
チュイ(1519) は 何かの骨 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
クゥ(1372) のもとに ホブゴブリン が恥ずかしそうに近づいてきます。
クゥ(1372) のもとに 沼ペンギン が空を見上げなから近づいてきます。
クゥ(1372) のもとに 骨ウルフ が口笛を吹きながらこちらをチラチラと見ています。



次元タクシーで カミセイ区 S-13:チェックポイント《鰻屋》 に行こうとしましたが、チェックポイントが開放されていません。
チナミ区 E-2(水地)には移動できません。
チナミ区 E-2(水地)には移動できません。
チナミ区 E-2(水地)には移動できません。
チナミ区 E-2(水地)には移動できません。
チナミ区 D-3(隔壁)には移動できません。
体調が全回復しました!
採集はできませんでした。
- クゥ(1372) の選択は カミセイ区 S-13:チェックポイント《鰻屋》(未開放のため無効)
- 雪里(1373) の選択は カミセイ区 S-13:チェックポイント《鰻屋》(未開放のため無効)
- チュイ(1519) の選択は カミセイ区 S-13:チェックポイント《鰻屋》(未開放のため無効)
MISSION!!
ウシ区 R-4:チェックポイント《古寺》 を選択!
- クゥ(1372) の選択は ウシ区 R-4:チェックポイント《古寺》





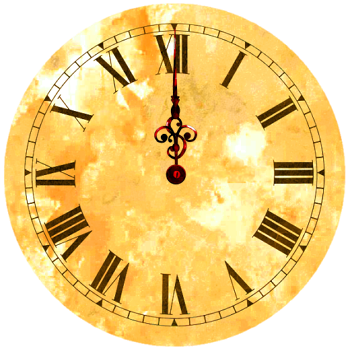
[843 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[396 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[440 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[138 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
[272 / 500] ―― 《大通り》より堅固な戦型
[125 / 500] ―― 《商店街》より安定な戦型
[125 / 500] ―― 《鰻屋》より俊敏な戦型
[24 / 500] ―― 《古寺》戦型不利の緩和
―― Cross+Roseに映し出される。




ロストのふたりがチャットに入り込んできた。
軽蔑の眼差しを向けるエディアン。
ミヨチンを制止する。
フレディオの胸倉をつかみ強く睨みつける!
――ザザッ
チャットが閉じられる――








仄かな光に包まれた六角形の柱が立っている。
・・・柱から滲み出るように、何かが生み出される。

それは言葉を発すると共に襲いかかる!






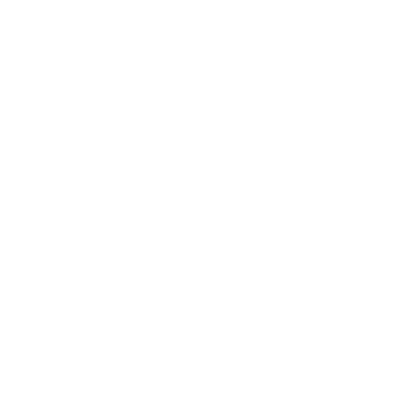
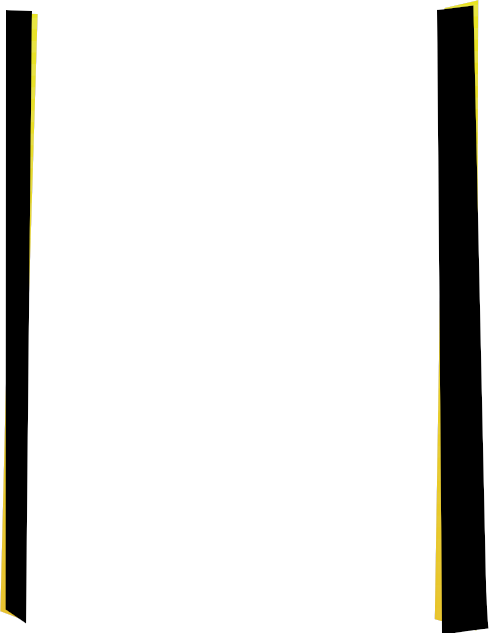
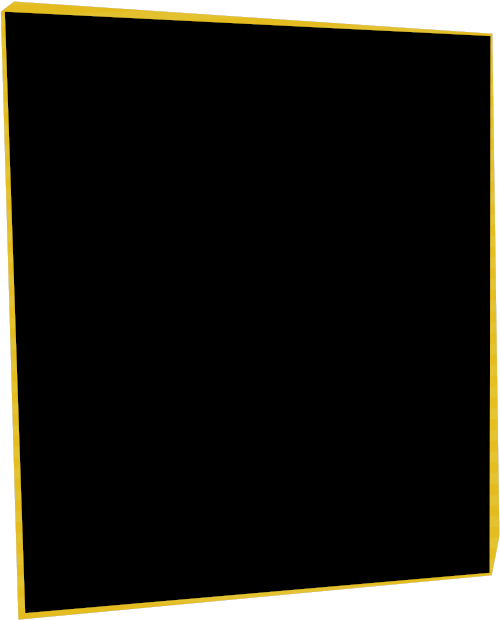





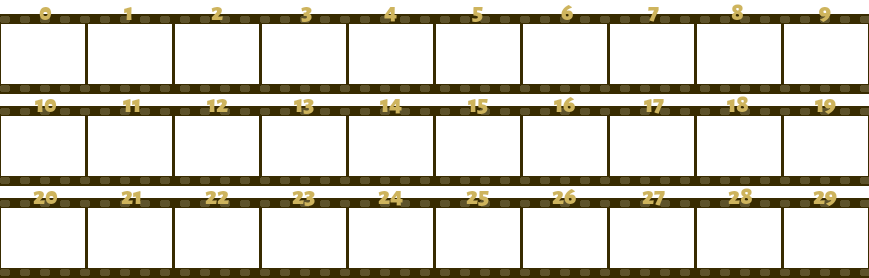




































No.1 こぐま (種族:こぐま)






異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [戦闘:エイド1]OK. [戦闘:エイド2]OK. [戦闘:エイド3]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



//side:イバラシティ
その日は、雪が降りそうな曇天だった。
来る者を遠ざけるような厳しい門を通り抜けると、重厚さを醸し出す日本家屋が見えた。
広い庭には番犬として黒い犬が多頭放し飼いにされていて、いかにも高そうな鯉の泳ぐ池もあれば、手入れの行き届いた日本庭園まである。
実際、今は庭師が植木を剪定しているところだった。
(相変わらず金かかってんなあ)
そんなことを思いながら、男は砂利の敷き詰められた一角を進む。
じゃり、ざり、と音を響かせて歩けば番犬がひょいと顔を出して、一瞬で興味を無くして去っていった。
広すぎる庭をゆったりと横切った先には、敷地の端も端に建てられた離れがあった。
一般家庭からすれば十二分に広い家だ。
けれど、喧騒から切り離されたような、しんと静かな空気だけがそこにあった。
離れはこの敷地内ではまだ新しい部類の建物であるはずなのに、どこか陰鬱とした雰囲気がある。
「おう、何見てんだ?」
男は、離れの前庭に向かって声を掛けた。
赤い椿の生け垣の影に、もそりと動くものがいた。
それは返事もせずに、視線だけをこちらに向けた。
椿のような、血のような赤色が男を映す。
「……返事しろよー」
男はため息とともに数歩の距離を詰めると、それを見下ろした。
灰とも銀とも言える髪をした、外国の血を感じさせる子供だ。
椿の生け垣の影に屈み込んでいる所為で、一層小さく見える。
その小さな手や、まろい頬は、赤黒く変色していた。
痛そうなそれらに一瞬顔をしかめかけてから、へらりと笑った。
「まぁた、こんな怪我こさえてからに」
「早く治せよ、各務」
「へえへえ」
わかりましたあ、と逆撫でする返事をしながら、男――各務は隣に屈み込んだ。
手に、頬に、あとは左足。
どこから治すべきかと考えながら、手を伸ばす。
この狂った家の中で、さらに一等狂った女の腹から生まれた子供は、こうして日々痛めつけられている。
そしてそれを治し、再び送り出すのが各務の役目だ。
(胸糞悪い。あーやだやだ)
分家も分家で、尚且椿坂家を母体とする組に所属する各務家としては、この役目を辞退する手段は持たない。
この子供自身が振り切る力を持って初めて、それは叶うだろう。
ただしその時、各務はまた別の役割を与えられるに違いない。
各務自身もまだ成人して間もないせいで、逃げる展望を思い描けないでいるのだから。
「はい、出来上がり。表面上はな。痛みが激しいところはあるか?」
「平気」
「本当にー?」
「ウザい、おっさん」
「おっ……! 俺まだ二十三なんだけど! ピッチピチの医学生だよ!?」
「十も違えば十分おっさんでしょ。あと学歴マウントは嫌われるからやめたほうがいい」
そこで初めて、目の前の子供が笑った。
内心でほっとしつつ、いっそ撫でてやろうかと手を伸ばせば、今度はすげなく避けられた。
「ガキは大人しく撫でられていろよなあ」
「そのガキより無力な大人が何言ってんだよ」
「あ゛~、可愛くねえ!」
今度こそ避けられないように、子供の頭をがしがしと撫でた。
やめろ、離せ、と言いながら撫でられる子供の首は細い。
ぐりんぐりんと揺れる頭に合わせて、ぽきりと折れそうだった。
「やめ、ろよ! 大体!」
「お」
片手で振り払われて、やや肩で息をする子供が眼光鋭く睨んできた。
降参の形で手を離しながら合わせた視線の、その瞳の中に、思わず『あの日』の色を探す。
『これは、治癒の異能を持っているのよ』
赤い唇をにぃっと上げた主家の女が言ったのは、今より数年前のことだ。
これ、と紹介と言うよりは説明された各務は、向き合う形で立っている小さな子供に礼をした。
事前に聞いた情報では、この女の息子らしい。
海外のマフィアの男との間に出来たらしいが、件の男はこの女を歯牙にも掛けず捨て置いたらしい。
らしいらしいと、伝聞の多い情報だったけれど、間違いではなかったことをこの時知った。
女はその子供に各務の異能についてを説明して、おもむろに子供に近寄った。
『え』
思わず声が出た。
女が笑みを貼り付けたまま、子供の腹にナイフを突き立てたのだ。
なんで、と呟いた子供の声は、寸分違わず各務の心の声だった。
それからのことは、もはや記憶が薄い。
子供が刺されて、自分が癒やして、それを繰り返す。
情けないことに、命ぜられたこと以外何も出来なかった。
繰り返される狂気の中、立ち込める鉄さびの臭気は子供の命がこぼれていく証跡そのものだったのに、その場で止められるのは自分だけだったのに、木偶のように突っ立っていた。
『ごめ、なさい、次、は……うまく、やり、ます』
もはや立っていられない子供が謝って、今日はこれで終いだと女はその場を後にした。
心配することもなく、一度も振り返ることなく。
傷を癒やしながらも、各務はこの空間では路傍の石でしかなかった。
その石が、子供を見下ろす。
子供の赤いビー玉のような目からころりと涙が落ちて、各務は人の心が死ぬ瞬間を見た。
あの暗さは、染みのように子供の目の奥に宿ったままだ。
ただ、浮き沈みがあるようで、今はその色が遠い。
「……大体、お前はその顔で助かっているんだ。 僕よりはマシだろ」
「…………ああもう、そう言うとこだぞー」
「何が」
「クウィリーノ坊ちゃんの悪くて良いところ」
「はあ?」
一瞬で陰りを見せる目が、ゆらゆらと揺れる。
顔が血縁上の父親によく似て『可愛い』せいで構われている子供。
きっとクウィリーノは、可愛くないほうが生きやすかったに違いない。
相変わらず人気のない庭の隅で、各務は無理矢理に笑った。
「やっぱりお前は可愛くねえなあ」
「そう」
「そうそう」
再び手を伸ばそうとして、ぱしりと躊躇いのない強さではたき落とされながら、今度は自然に笑う。
と、その可愛くない顔が、悪そうな顔に歪んだ。
「ん? 何だ急に。お兄さんぞっとしたんだけど」
「……十三だ。その年に僕は家を出る。お前もついて来い」
「は……」
「ついでに便利そうな者数人も引っ張っていく」
「おい」
「その日までお前は僕で異能を高めろ。家に従順でいろ。逆らわず、手駒を演じろ」
「ちょ」
矢継ぎ早に言われる言葉はどれも小さく早口で、子供らしからぬ平坦さだった。
口をぱくぱくとしていれば、間抜け面、と悪態を挟まれる。
本当に可愛くない顔だった。
「だから、もう個人的にはここには来るな。治癒は『あの場』だけでギリギリまで使え」
もはや声も出ず、子供を凝視する。
闇に揺らめいていた目が、ぎらぎらと輝いていた。
子供の戯言と言い切れない熱が、それにはある。
「え、何、いきなりすぎてこわ……」
「椿組に飼われるのは嫌なんだろ? 今度は僕が飼ってやるよ、『お兄ちゃん』?」
「うわあ……」
飼い殺される未来を悲観していたことを、十歳を少し超えた程度の子供に見抜かれていた。
しかもどうやら、正しく各務の『上』の立場でいるらしい。
あの悪夢が始まる前は、それでも子供の範疇にいただろうに、いつの間にか随分と酷い進化をしていたようだ。
「あ、裏切るなら覚悟してやって」
「普通に何か出来る力があるのが怖ぇ……」
「だって、気付いたんだよ。この僕が、ここの奴らに使い潰されるなんて。損失でしょ?」
「うわああ……」
今度はころりと天使のような笑顔で笑うものだから、各務は戦慄した。
これに騙される人間は多いに違いない。
各務だって、数秒前の悪人顔や悪口を目撃していなければ騙されただろう。
けれどその姿の影に、この子供に課されたもの、強制された日々が見えた気がして喉奥で呻いた。
「……しくじるなよ」
「各務もな」
ふん、と笑って、子供は背伸びをしてから家に歩を進めた。
寒々しい家に向かう姿は、やはり子供の頼りなさがあった。
「……とりあえず、そのクッソ似合わねえ悪そうな口調はやめておけよ! 人当たり良くしとけ」
「はあい」
ひらりと手を振って、子供は家に戻って行った。
その閉ざされた扉を見ていると、冬らしい寒風がびゅうと強く吹いた。
「っぶしゅっ、……あ゛ー……さっむ」
すんと鼻をすすって、両手をすり合わせる。
風邪を引いてはたまらないと、各務は帰ることにした。
赤い椿、赤い目の子供、自分の今後の身の振り方。
(やべえ……思ったより大変なことになった……)
途方に暮れて見上げた空は、雪を降らせることもなく、ただただ曇って暗かった。
//
「はい、治して」
「うわ出た」
カメリアの医務室に、クウィリーノはひょいと顔を出した。
先程ねこと格闘した傷を目の前の男に見せれば、いててて、と相手が痛がった。
いい歳したおっさんの演技は無視に限る。
「まぁた、こんな怪我こさえてからに。何、マゾなの?」
「違うけど?」
「知ってるけど!」
ぶつぶつ言いながら、男――各務は異能で治してくれた。
少しの傷くらいは自己治癒に任せるけれど、これはさすがに深すぎると判断されたらしい。
その異能を行使するスピードは、長年の経験からか素早く滑らかだ。
実に使える人間になったなと、クウィリーノは内心だけで褒めた。
口に出すと調子に乗るから、褒め時を見誤ってはならない。
「ねー、今度大きめの仕事があるからさ。車待機していてくれる?」
「おお、わかった。力の使い過ぎには気をつけろよ」
「はあい」
「うわあ……」
愛想よく笑ったはずなのに、各務は嫌そうな顔をするのが面白い。
口調はなるべく柔らかく、を意識してこうなって久しいのに、未だ慣れないらしい。
厳しい口調のほうがいいのならば、各務こそがマゾだろう。
「まあ、詳細は阿左見……いや、雲右に持ってこさせるよ」
「おお」
わかったわかったと手を振って、クウィリーノの電子カルテに打ち込むのを見る。
その声が少し嬉しそうなのは、あの家を出る時に引っ張ってきた人のうちに雲右も含まれるからだ。
兄よりも父のほうが近い関わりをした相手には、やはり愛着が湧くようだ。
「各務」
「んー?」
「ここ、白髪すごいある」
「はっ!?」
バッと振り返った顔は、嘘だろ、という表情だった。
手鏡を手に、ざかざかと後頭部を搔いている。
「うっそー✩」
「おまっ……いやそれ本当だろうな? と言うか白髪が増えたら絶対お前の所為だからな!?」
「あは」
苦労を掛けているのは自覚している。
これでもある程度は自重をしているのだけれど、やはり仕事に傷はつきものであるので、なくすことは難しい。
ただ、ほんの少しだけ、本当にもう少しだけ自重をしてもいいなと、ふと思った。
「それじゃ、また来るねー」
「怪我して来んなよ」
つまりは、遊びには来ていいらしい。
お人好し、と心の中で舌を出しつつ、クウィリーノは医務室を後にした。
寒い家、赤い椿、雪の降りそうな曇天の日。
ばれたら自分が危うくなると言うのに、わざわざ関わりの薄い子供を癒やしに来た男を思い出す。
あの日家の中に戻って、何故だか鼻の奥がツンとしたことは、クウィリーノだけの思い出だった。









カミセイ区 S-13:チェックポイント《鰻屋》
カメリア清掃会社の昼飯は中華
|
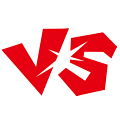 |
立ちはだかるもの
|



お肉(50 PS)を購入しました。
お肉(50 PS)を購入しました。
すごい木材(400 PS)を購入しました。
解析LV を 5 UP!(LV15⇒20、-5CP)
合成LV を 5 UP!(LV70⇒75、-5CP)
ItemNo.1 不思議な武器 に ItemNo.2 不思議な防具 を合成し、駄物 に変化させました!
⇒ 駄物/素材:強さ10/[武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50)/特殊アイテム
⇒ 駄物発生!駄物 を入手!
ItemNo.18 花びら に ItemNo.19 不思議な雫 を合成し、何か柔らかい物体 に変化させました!
⇒ 何か柔らかい物体/素材:強さ10/[武器]治癒10(LV20)[防具]命脈10(LV25)[装飾]防御10(LV20)
ItemNo.30 何かの骨 に ItemNo.24 紅小石 を合成実験し、白い塊 に変化することが判明しました!
⇒ 白い塊/素材:強さ20/[武器]閃光10(LV20)[防具]治癒10(LV10)[装飾]気合10(LV20)
チュイ(1519) により ItemNo.20 翌檜 から魔晶『ハーフリムの眼鏡』を作製してもらいました!
⇒ ハーフリムの眼鏡/魔晶:強さ106/[効果1]幸運25 [効果2]- [効果3]充填15
 |
チュイ 「新たなメガネ〜!ピカピカ!」 |
雪里(1373) により ItemNo.28 お肉 から料理『さっぱり冷しゃぶ』をつくってもらいました!
⇒ さっぱり冷しゃぶ/料理:強さ85/[効果1]攻撃10 [効果2]防御10 [効果3]増幅10
 |
雪里 「料理にも、ちょっとだけ慣れてきました」 |
山田(198) とカードを交換しました!
カルコサ聖帰団の名刺 (アウデンティア)
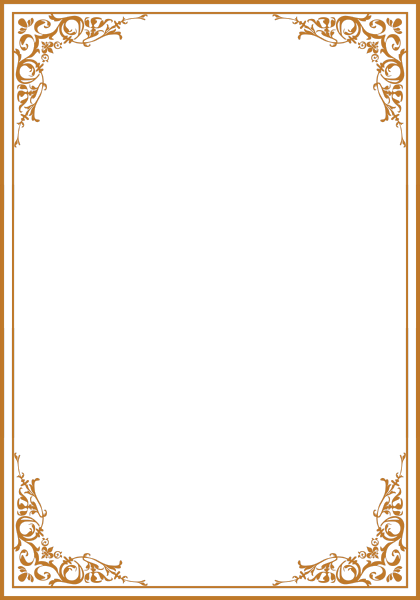
超過適応 を研究しました!(深度0⇒1)
超過適応 を研究しました!(深度1⇒2)
超過適応 を研究しました!(深度2⇒3)
ウィークサーチ を習得!
クリエイト:マシンガン を習得!
機知奇策 を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



クゥ(1372) は 腐肉 を入手!
チュイ(1519) は 腐肉 を入手!
チュイ(1519) は 何かの骨 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
クゥ(1372) のもとに ホブゴブリン が恥ずかしそうに近づいてきます。
クゥ(1372) のもとに 沼ペンギン が空を見上げなから近づいてきます。
クゥ(1372) のもとに 骨ウルフ が口笛を吹きながらこちらをチラチラと見ています。



次元タクシーで カミセイ区 S-13:チェックポイント《鰻屋》 に行こうとしましたが、チェックポイントが開放されていません。
チナミ区 E-2(水地)には移動できません。
チナミ区 E-2(水地)には移動できません。
チナミ区 E-2(水地)には移動できません。
チナミ区 E-2(水地)には移動できません。
チナミ区 D-3(隔壁)には移動できません。
体調が全回復しました!
採集はできませんでした。
- クゥ(1372) の選択は カミセイ区 S-13:チェックポイント《鰻屋》(未開放のため無効)
- 雪里(1373) の選択は カミセイ区 S-13:チェックポイント《鰻屋》(未開放のため無効)
- チュイ(1519) の選択は カミセイ区 S-13:チェックポイント《鰻屋》(未開放のため無効)
MISSION!!
ウシ区 R-4:チェックポイント《古寺》 を選択!
- クゥ(1372) の選択は ウシ区 R-4:チェックポイント《古寺》





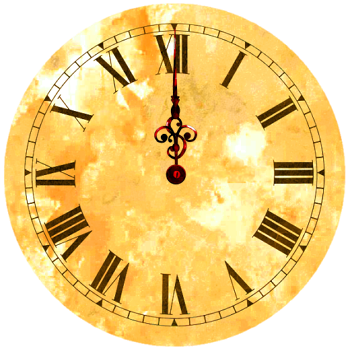
[843 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[396 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[440 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[138 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
[272 / 500] ―― 《大通り》より堅固な戦型
[125 / 500] ―― 《商店街》より安定な戦型
[125 / 500] ―― 《鰻屋》より俊敏な戦型
[24 / 500] ―― 《古寺》戦型不利の緩和
―― Cross+Roseに映し出される。

フレディオ
碧眼、ロマンスグレーの短髪。
彫りが深く、男前な老翁。
黒のライダースジャケットを身に着けている。
彫りが深く、男前な老翁。
黒のライダースジャケットを身に着けている。

ミヨチン
茶色の瞳、桜色のロング巻き髪。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
 |
フレディオ 「いよぉ!なるほどこう入んのか、ようやく使えそうだぜ。」 |
 |
ミヨチン 「にゃー!遊びに来たっすよぉ!!」 |
 |
エディアン 「にゃー!いらっしゃいませー!!」 |
 |
白南海 「毎度毎度うっせぇなぁ・・・いやこれ俺絶対この役向いてねぇわ。」 |
ロストのふたりがチャットに入り込んできた。
 |
ミヨチン 「・・・・・?おっさん誰?」 |
 |
フレディオ 「フレディオにゃー。ピッチピチ小娘も大好きにゃん!」 |
 |
ミヨチン 「・・・・・」 |
 |
エディアン 「・・・・・」 |
 |
フレディオ 「・・・いやジョークだろジョーク、そんな反応すんなっつーの。」 |
 |
ミヨチン 「大好きなのは嬉しーけど、そのナリでにゃんは痛いっすよぉ! なんすかそれ口癖っすかぁ??まじウケるんですけど。」 |
 |
フレディオ 「え、あぁそっち?・・・ジョークだジョーク。」 |
 |
エディアン 「私はそっちじゃないほうですね。顔がいいだけに残念です。」 |
軽蔑の眼差しを向けるエディアン。
 |
白南海 「・・・別にいいだろーよ。若い女が好きな男なんてむしろ普通だ普通。」 |
 |
フレディオ 「おうおうそうだそうだ!話の分かる兄ちゃんがいて助かるわッ」 |
 |
フレディオ 「・・・っつーわけで、みんなで初めましてのハグしようや!!!!」 |
 |
ミヨチン 「ハグハグー!!」 |
 |
エディアン 「ダメダメやめなさいミヨちゃん、確実にろくでもないおっさんですよあれ。」 |
ミヨチンを制止する。
 |
フレディオ 「・・・ハグしたがってる者を止める権利がお前にはあるのか?」 |
 |
エディアン 「真面目な顔して何言ってんですかフレディオさ・・・・・フレディオ。おい。」 |
 |
白南海 「お堅いねぇ。ハグぐらいしてやりゃえぇでしょうに。」 |
 |
フレディオ 「そうだそうだ!枯れたおっさんのちょっとした願望・・・・・」 |
 |
フレディオ 「・・・・・願望!?そうかその手が!!!!」 |
 |
エディアン 「ゼッッッッタイにやめてください。」 |
フレディオの胸倉をつかみ強く睨みつける!
 |
白南海 「そういえば聞きたかったんすけど、あんたらロストって一体どういう存在――」 |
――ザザッ
チャットが閉じられる――







ウシ区 R-4
チェックポイント《古寺》
チェックポイント。チェックポイント《古寺》
仄かな光に包まれた六角形の柱が立っている。
・・・柱から滲み出るように、何かが生み出される。

守護者《ZEBRA》
黒闇に包まれた巨大なシマウマのようなもの。
 |
守護者《ZEBRA》 「――我が脳は我が姫の意思。我が力は我が主の力。」 |
それは言葉を発すると共に襲いかかる!





ENo.1372
クウィリーノ・椿坂
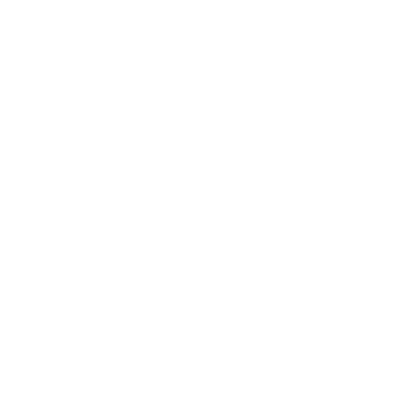
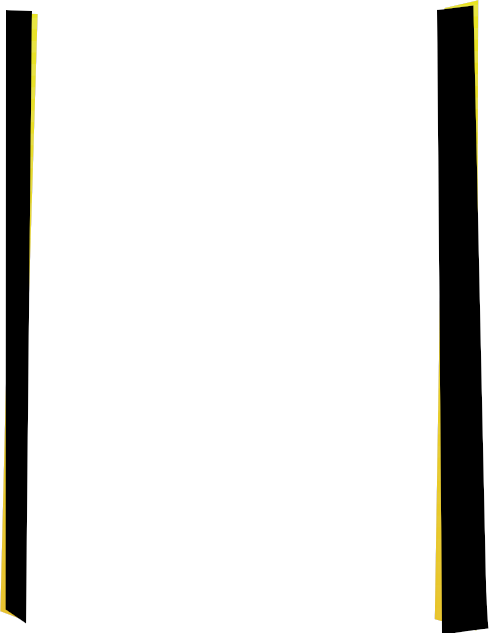
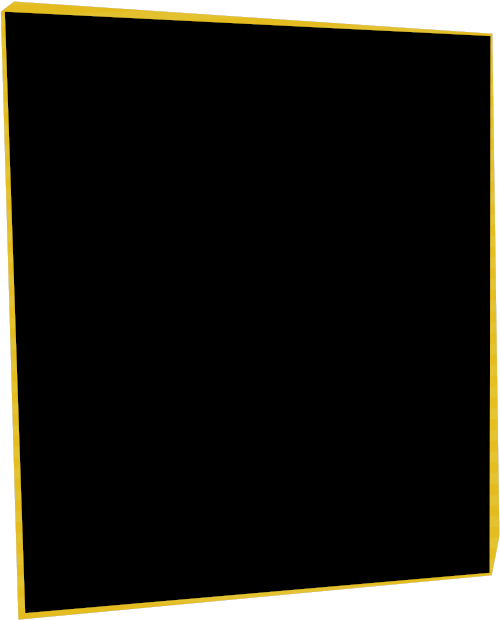
清掃会社の偉いお兄さん。
//
表向きはカメリア清掃株式会社の社長。
ただし人には「ちょっと偉いお兄さん」を自称する。
カメリアは人気アイドルを起用した地上波CMを打つほどクリーンな清掃会社。
インテリ眼鏡に擬態して喋ると台無しになるタイプのチャラ男。
発言がいちいち軽い。
倫理観ガバガバな所為でふとした拍子に言動に出る。
//
男/28歳→29歳/184cm
シルバーアッシュの髪、赤い目
耳、唇、舌、臍にピアス穴
右眉尻は一部カットされている。
お掃除するために身体は鍛えられている。
カメリア清掃株式会社
http://lisge.com/ib/talk.php?s=685
クウィリーノのIBARINE
http://lisge.com/ib/talk.php?p=3770
//
のんびりめに参加です、よろしくお願いします。
PCは倫理観ガバ、語尾に特殊文字(♡や✩)使いそうなので、気になる方はご注意ください。
//
表向きはカメリア清掃株式会社の社長。
ただし人には「ちょっと偉いお兄さん」を自称する。
カメリアは人気アイドルを起用した地上波CMを打つほどクリーンな清掃会社。
インテリ眼鏡に擬態して喋ると台無しになるタイプのチャラ男。
発言がいちいち軽い。
倫理観ガバガバな所為でふとした拍子に言動に出る。
//
男/28歳→29歳/184cm
シルバーアッシュの髪、赤い目
耳、唇、舌、臍にピアス穴
右眉尻は一部カットされている。
お掃除するために身体は鍛えられている。
カメリア清掃株式会社
http://lisge.com/ib/talk.php?s=685
クウィリーノのIBARINE
http://lisge.com/ib/talk.php?p=3770
//
のんびりめに参加です、よろしくお願いします。
PCは倫理観ガバ、語尾に特殊文字(♡や✩)使いそうなので、気になる方はご注意ください。
30 / 30
643 PS
チナミ区
D-2
D-2







































No.1 こぐま (種族:こぐま)
 |
|
|
||||||||||||||||
| 被研究 | スキル名 | LV | EP | SP | 説明 |
| フロウライフ | 5 | 0 | 80 | 自:MHP・DF増 | |
| カウンター | 5 | 0 | 130 | 自:反撃LV増 | |
| 練2 | デスペラート | 5 | 0 | 130 | 敵:報讐LV増+6連撃+報讐消滅 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 背水 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:現在HP割合が低いほど被攻撃ダメージ減 |
最大EP[20]
No.2 秘書 (種族:土偶) |
|
クウィリーノの秘書。 阿左見(あさみ)諜報に長けている 雲右(くもえ)戦闘に長けている |
||||||||||||||||
| 被研究 | スキル名 | LV | EP | SP | 説明 |
| マーチ | 5 | 0 | 100 | 味全:AT増(4T) | |
| モラール | 5 | 0 | 210 | 味全:DX増 | |
| スキューア | 5 | 0 | 100 | 敵貫:地痛撃&次受ダメ増 | |
| 練3 | パワフルヒール | 5 | 0 | 100 | 味傷:精確地痛撃&HP増 |
| 瑠璃樹 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP・精神変調防御・領域値[地][闇]増+守護+連続減 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 聖音 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:発動する「味全」「敵味全」「他全」を強化 | |
| 地の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:自然LVが高いほど地特性・耐性増 | |
| ★バトルダンス | 10 | 0 | 240 | 味全:AT・DX増(3T) |
最大EP[20]
No.3 歩行軍手 (種族:歩行軍手) |
|
|
||||||||||||||||
| 被研究 | スキル名 | LV | EP | SP | 説明 |
| 練3 | パワフルヒール | 5 | 0 | 100 | 味傷:精確地痛撃&HP増 |
| マナ | 5 | 0 | 10 | 自:消費SP減 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 肉体変調耐性 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:肉体変調耐性増 | |
| 精神変調耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:精神変調耐性増 | |
| 背水 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:現在HP割合が低いほど被攻撃ダメージ減 | |
| 強打 | 5 | 4 | 0 | 【自分行動前】自:次与ダメ増 | |
| ★トランス | 10 | 0 | 100 | 自:混乱+自:AT・HL増+魅了を祝福化 |
最大EP[20]



| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 駄物 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50) | |||
| 2 | 駄物 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50) | |||
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | ボウイナイフ | 武器 | 40 | 攻撃10 | - | - | 【射程2】 |
| 5 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]防御10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) | |||
| 6 | 黒手袋 | 装飾 | 40 | 防御10 | - | - | |
| 7 | 駄物 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50) | |||
| 8 | 白石 | 素材 | 15 | [武器]祝福10(LV10)[防具]反祝10(LV10)[装飾]舞祝10(LV10) | |||
| 9 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
| 10 | 何か固い物体 | 素材 | 15 | [武器]攻撃10(LV20)[防具]防御10(LV20)[装飾]共鳴10(LV20) | |||
| 11 | 黒玉のピアス | 装飾 | 200 | 体力20 | - | - | |
| 12 | ハーフリムの眼鏡 | 魔晶 | 27 | 体力10 | - | 充填9 | |
| 13 | ド根性雑草 | 素材 | 15 | [武器]防狂10(LV20)[防具]反護10(LV25)[装飾]復活10(LV25) | |||
| 14 | 大軽石 | 素材 | 15 | [武器]幸運10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]舞護10(LV20) | |||
| 15 | 皮 | 素材 | 15 | [武器]闇纏15(LV30)[防具]反護15(LV30)[装飾]舞祝15(LV25) | |||
| 16 | 駄物 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50) | |||
| 17 | お肉 | 食材 | 10 | [効果1]攻撃10(LV15)[効果2]防御10(LV25)[効果3]増幅10(LV35) | |||
| 18 | 何か柔らかい物体 | 素材 | 10 | [武器]治癒10(LV20)[防具]命脈10(LV25)[装飾]防御10(LV20) | |||
| 19 | 腐肉 | 素材 | 15 | [武器]腐朽15(LV30)[防具]放腐20(LV35)[装飾]耐疫15(LV30) | |||
| 20 | ハーフリムの眼鏡 | 魔晶 | 106 | 幸運25 | - | 充填15 | |
| 21 | 鉄くず | 素材 | 10 | [武器]強撃10(LV20)[防具]増勢10(LV20)[装飾]反地10(LV20) | |||
| 22 | マチェット | 呪器 | 167 | 攻撃10 | - | 自滅12 | 【射程2】 |
| 23 | 黒スーツ | 防具 | 164 | 活力15 | - | - | |
| 24 | 紅小石 | 素材 | 15 | [武器]火撃15(LV30)[防具]耐火20(LV30)[装飾]舞痺20(LV35) | |||
| 25 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 26 | 毒牙 | 素材 | 20 | [武器]猛毒15(LV30)[防具]反毒15(LV30)[装飾]耐疫15(LV25) | |||
| 27 | お野菜 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV15)[効果2]幸運10(LV25)[効果3]命脈10(LV35) | |||
| 28 | さっぱり冷しゃぶ | 料理 | 85 | 攻撃10 | 防御10 | 増幅10 | |
| 29 | 駄物 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50) | |||
| 30 | 何かの骨 | 素材 | 20 | [武器]闇撃10(LV25)[防具]活力15(LV30)[装飾]強靭10(LV20) | |||
| 31 | ネジ | 素材 | 15 | [武器]貫撃10(LV25)[防具]地纏10(LV25)[装飾]舞乱10(LV25) | |||
| 32 | お肉 | 食材 | 10 | [効果1]攻撃10(LV15)[効果2]防御10(LV25)[効果3]増幅10(LV35) | |||
| 33 | すごい木材 | 素材 | 30 | [武器]攻撃20(LV40)[防具]敏捷20(LV40)[装飾]回復20(LV40) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 具現 | 20 | 創造/召喚 |
| 使役 | 35 | エイド/援護 |
| 解析 | 20 | 精確/対策/装置 |
| 合成 | 75 | 合成に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 6 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 6 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 6 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| クリエイト:タライ | 6 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |
| サステイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:守護 | |
| プリディクション | 5 | 0 | 120 | 味列:AG増(3T) | |
| アシスト | 5 | 0 | 50 | 自:束縛+自従全:AT・DX増 | |
| クリエイト:メガネ | 6 | 0 | 100 | 味:DX・AG増(5T) | |
| パワーブースター | 5 | 0 | 40 | 自従:AT・DF・DX・AG・HL増(3T) | |
| ブロック | 5 | 0 | 80 | 自:守護+DF増(2T)+味傷:護衛 | |
| マインドリカバー | 5 | 0 | 0 | 自:連続減+SP30%以下ならSP増+名前に「自」を含む付加効果のLV減 | |
| サモン:サーヴァント | 6 | 5 | 300 | 自:サーヴァント召喚 | |
| ラッシュ | 5 | 0 | 100 | 味全:連続増 | |
| リンクブレイク | 5 | 0 | 150 | 敵全:精確攻撃&従者ならDX・AG減(3T) | |
| アイギス | 5 | 0 | 50 | 自従全:守護 | |
| サモン:スプーキーアイ | 5 | 3 | 300 | 自:スプーキーアイ召喚(複数可) | |
| アーマメント | 5 | 0 | 150 | 自従全:連撃LV・鎮痛LV・強靭LV増+連続減 | |
| リビルド | 5 | 0 | 300 | 自:連続増+総行動数を0に変更+名前に「クリエイト」を含む全スキルの残り発動回数増 | |
| スタンピート | 6 | 0 | 50 | 自従:AT・DX・AG増(3T) | |
| ウィークサーチ | 5 | 0 | 130 | 自:朦朧+敵:DF・AG減(3T) | |
| クリエイト:マシンガン | 5 | 0 | 260 | 自:射程2増(1T)+敵10:攻撃 | |
| サークルバリア | 5 | 0 | 200 | 自:DF・AG増(3T)+自従傷:DF・AG増(3T) |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 召喚強化 | 6 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:具現LVが高いほど自身の召喚するNPCが強化 | |
| 魅惑 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:使役LVが高いほど戦闘勝利時に敵をエイドにできる確率増 | |
| 祈誓 | 5 | 3 | 0 | 【通常攻撃後】自:祝福消費でDF・LK増(2T) | |
| 修復 | 5 | 3 | 0 | 【被HP回復後】自:守護 | |
| 共存共栄 | 5 | 4 | 0 | 【通常攻撃後】自:DF増(2T)+自従全:DF増(2T) | |
| 機知奇策 | 5 | 4 | 0 | 【スキル使用後】自従全:SP増 | |
| 駄物発生 | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『合成』で、合成成功時に自分にアイテム「駄物」が手に入る。(実験除く、1更新1つまで) |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
中継ぎエース (リリーフ) |
0 | 70 | 味傷3:HP増+祝福 | |
|
ハジマリの透明彗星 (レイ) |
0 | 30 | 敵貫:盲目 | |
|
破廉恥はいけません (ライトニング) |
0 | 50 | 敵:精確光撃 | |
|
鎖の従者 (サモン:サーヴァント) |
5 | 300 | 自:サーヴァント召喚 | |
|
渡りの魔力 (クイック) |
0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| 練3 |
[DSN309]ウミネコ (クリエイト:グレイル) |
0 | 70 | 味傷:精確光撃&HP増&祝福 |
|
邪祓 (パージ) |
0 | 120 | 敵列:粗雑SP光撃 | |
|
フレイムインパクト (フレイムインパクト) |
0 | 230 | 敵:5連鎖火痛撃 | |
| 練2 |
とんでもない爆発 (ファイアグレネード) |
2 | 260 | 敵6:火領撃&炎上 |
|
コンスタンティン (ダストデビル) |
0 | 180 | 敵:反風LV増+8連風撃 | |
|
カルコサ聖帰団の名刺 (アウデンティア) |
0 | 300 | 味全:AT・LK増+炎上 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]リザレクション | [ 3 ]サモン:サーヴァント | [ 3 ]ナース |
| [ 3 ]サステイン | [ 3 ]超過適応 | [ 3 ]スタンピート |
| [ 3 ]クリエイト:グレイル | [ 3 ]ワンオンキル | [ 3 ]ラッシュ |
| [ 3 ]パワフルヒール | [ 3 ]グリモワール |

PL / め