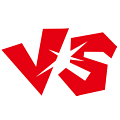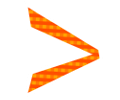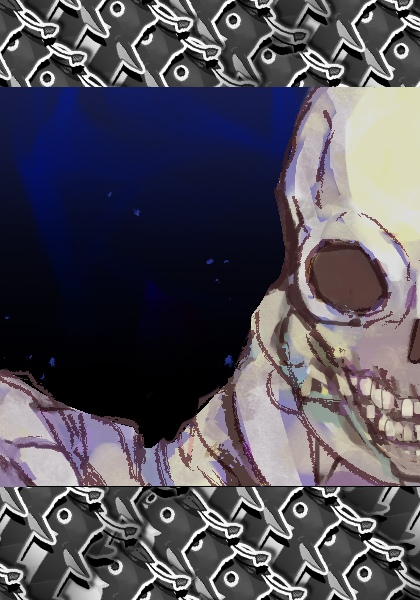<< 9:00~10:00




【10年前、某日・某所】
「あ、よかった。みんないるわね」
からり、部室の扉が開いて彼女が覗き込んできた
大体のいつもの面子がそろっていることを確認して、中に入ってくる
「あれ、夢咲さん。まだ夏休み終わってないよ?」
「みんなだって、もういるじゃない」
くすくすと笑いながら、彼女は何やら大きな袋を机の上に置いた
まだ夏休みが明けていないのは事実だが、この新聞部の面子は大体部室にそろっていた
夏休み明けてすぐに学校新聞を出す予定だから、その作業があるせいだ
もっとも、作業ついでに皆で集まって喋るのが目的と言うのも、多少はあるだろうが
彼女も、その点わかっていてやってきたに違いない
「零羅ちゃん、その大きな袋何?」
「これ?夏休み終わる一足前に、みんなにお土産よ」
部長の問いに、彼女はにっこり笑ってそう答えた
半分、暑さでだらけていた皆ががバリ、起き上がる
「お土産?どこの?」
「ヴァーチャシティと、あとはヨーロッパのいくつかの国よ」
「仕事で行ったんだったよな。わざわざ。買ってきてくれたのか」
彼女、夢咲 零羅は現役高校生にして現役の作家だ
それも、いくつかの作品は映画化やらドラマ化やら……最近はアニメ化された物もある。そんな人気作家である
国外でも作品は人気らしく、夏休みのような長期の休みの期間は国内外あちこち飛び回って、サイン会なり関連の仕事をしていると聞いていた
正直、長期の休み期間の方が普段より忙しいのではないか?とも感じる
そんな多忙な中、自分達に土産物を買ってきてくれるくらいには彼女はこの新聞部面子を親しく思ってくれているのだろう。純粋に、彼女が親切なだけかもしれないが
「ヴァーチャシティ辺りの物は、まだこっちにはあまり入ってこないんですもの。せっかくだからね。ほら。ヴァーチャシティ名産のスイートナッツ」
「よりによってハワイシティのマカダミアンナッツのようなチョイス!?」
でんっ、と机の上に出された袋の中に、アーモンドに似た見た目のスイートナッツがぎっしり、入っている
聞いたことがある。見た目完全にアーモンドのくせに、味付けせずとも大変と甘いと噂の食べ物だ。自然でこんな甘さ出るのか、と疑問は浮かぶが、あのヴァーチャシティ特産であるのだ。遺伝子改良とかそうしたもので生まれたものなのだろう
「あら、私、食べたことあるけど結構おいしいわよ?一気にたくさん食べると胃もたれするような気がするけど」
「夢咲は甘いもん好きだからそうだろうけど。日本人の平均味覚からするとあっっまいことに変わりないよな。いや、土産物だからもらうけど」
「何だったら、そのまま食べないで他のお菓子に加工して食べても美味しいわよ」
向こうで食べたタルト、美味しかったものと彼女は笑っている
なるほど、加工すれば甘さは多少ましに……いや、加工次第ではもっと甘くなるのでは……?
「加工……そういえば、家庭科部も今日は学校来てるやつらいたな。よし、頼みに行くか」
「え、部長。家庭科部と言う女子の園に突撃して頼みに行くの?勇気MAX?」
「いや、家庭科部の男女比は大体半々だ。問題ない。ついでに、家庭科部の取材ってことにすれば聞いてもらえるだろ。零羅ちゃん、スイートナッツもらっていくよ?」
「えぇ、どうぞ」
よし!と部長がスイートナッツの袋を持って部室を出ていく
取材なら、という事か。ついでに家庭科部で何かつまみ食いでもしてくるつもりなのか、他の面子もぞろぞろと出ていった
「あら、文雄君はいかないの?」
「今のうちに片づけときたい原稿あるから。それに、夢咲さん一人残すの悪い……というか、夢咲さんはみなについていかなくてよかったのかい」
ノートパソコンのキーボードをたたきながら問いに答えて、ついでに問い返す
えぇ、と適当な椅子に腰かけて彼女は頷いた
「今日は、ゆっくりしたいし」
「夏休み中、ほぼ仕事だったんだろう?お疲れさま。宿題とかは大丈夫?」
「ふふ、仕事の合間にちゃんとやったわ。きっちり見張ってくる人がいるとさぼれないもの」
おそらく、護衛の人がその辺きっちり見張っていたのだろう
彼女は生まれ自体そこそこいい家であるようだし、何より人気作家だ
ヴァーチャシティのような治安が死滅しているような国に行く時は、いや、そうじゃなくとも仕事の時はほぼ、護衛の人間がついている
仕事どころか、新聞部の面子と一緒に映画を見に行った時も、こっそりと護衛らしき人間がついているのを目撃した
……ある意味、常に見張られているようなものだろう。堅苦しいだろうに、彼女にとっては「当たり前」の事であるのか、その環境に慣れきっているようだった
こうやって学校にいる時はさすがに護衛の影はない。数少なく、護衛の目を気にすることのない時間が学校にいる間なのではないだろうか
「あ。そうだわ。ちょうどいいから……はい、これ」
何やら、彼女はほかにもおみやげ物が入った袋をガサゴソとし始めた
そうして取り出したのは、小さな紙袋。それを、こちらに手渡してきた
「俺に?」
「えぇ。文雄君個人へのお土産。文雄君には、色々お世話になってるもの」
「お世話に、って……大したこともしてないと思うけど」
「あら。あなたのおかげで、また一つ新しいネタが浮かんだんですもの。十二分にお世話になっているわ」
そんなものだろうか
新しいネタ、と言うのはこちらの取材を受けている間に「あ、閃いた」とか言っていたから、その事か。一体何を閃いたのか、教えてはくれなったが。また何か書くのだろう
……それはさておき、この紙袋だ
本当に受け取っていいのか問えば、もちろんと微笑まれる
それならば、と正直に受け取ることにした。友人の行為は素直に受け取るべきだろう
他の部員がいる前だったら、変にはやし立てられたに違いない。こうして他の連中がいない時に渡してくれたのはありがたい
開けてみれば、中に入っていたのはエメラルドを抱いた青い蠍のチャームがついた、ストラップ
「これは……」
「お守り、みたいなものね。ほら、文雄君、女性関係でろくな縁がない、って言ってたから」
「よく覚えてるね」
「覚えているわよ。かなりぐったりしながら愚痴っていたじゃない」
そうだっただろうか?
そうだったのかもしれない
「青い蠍は「色欲」の象徴。されど、それも見方を変えれば、素敵な恋を、愛を求めるという事。そしてエメラルドは愛の力が強い宝石よ。それ以外にも疲れた心を癒し、思考能力を高める効果があるとも言われているの。文雄君に、素敵な縁がありますように、と。取材やらなにやらで疲れ気味の心が休まりますように、って思って」
「そうか……ありがとう、夢咲さん」
きっと、そのおみやげ物がどういうものであったとしても
自分にとって、それは「特別」となりえたのだろう
自分と彼女の間には、間違っても色恋沙汰と呼べるような感情はなかった
それはただの男女間の友情でしかなく、だとしても特別な友情であったと……少なくとも、自分はそう感じていた
夢咲の家の人間として、作家として、「普通の女子高生」ではいられなかった彼女が、自分達新聞部にいる時だけは「普通の女子高生」でいられたならば、その場を自分達が提供することができていたならば……それが、幸せであり、妙な誇りのようなものを感じていたのは事実だった
彼女は「特別」な人間だったかもしれない
けれど、同時に「普通」の人間でもあったことは事実だ
彼女が「特別」足りえたのは、周囲の環境なり、周囲から持ち上げられたからであり……彼女自身が、若くして作家と言う道を歩むことを決めたからでもある
それでも、そうだとしても
彼女は「特別」な人間である以上に、ただ一人の「夢咲 零羅」という女性でもあった
だから
……だから
彼女が死んだ理由が、彼女が「特別」だったからなのか
彼女が「夢咲 零羅」だったからなのか
それとも、それすらも関係ない、ただただ偶発的なものだったのか
せめて
せめて、それだけでも知りたい
そして、もし、彼女が殺されたのだと、したら
そうなのだとしたら
せめて、俺にできる形で、彼女の仇討ちを成し遂げることは、許されるだろうか?



ENo.21 レイ とのやりとり

ENo.157 ケイ とのやりとり

以下の相手に送信しました













響鳴LV を 5 UP!(LV15⇒20、-5CP)
料理LV を 5 UP!(LV65⇒70、-5CP)
来訪者たち(15) により ItemNo.13 大蒜 から防具『ラージシールド』を作製してもらいました!
⇒ ラージシールド/防具:強さ90/[効果1]体力15 [効果2]- [効果3]-
ノジコ(456) とカードを交換しました!
ノジコのおうえん! (ムーンサルトプレス)

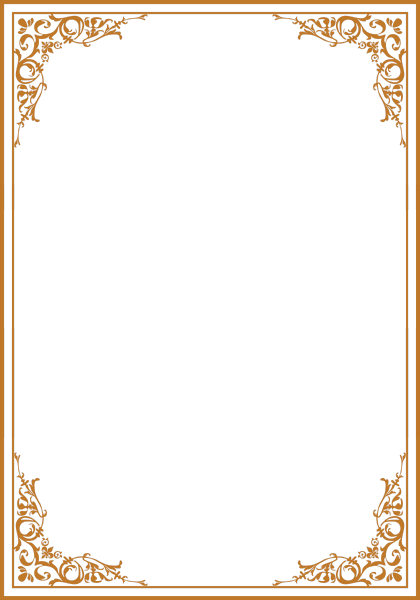
光輝燦然 を研究しました!(深度0⇒1)
光輝燦然 を研究しました!(深度1⇒2)
光輝燦然 を研究しました!(深度2⇒3)
エファヴェセント を習得!
マナ を習得!
アディクティブチューン を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



来訪者たち(15) は 枝豆 を入手!
フェル(284) は 白詰草 を入手!
玲(290) は 枝豆 を入手!
秋桐誠司(302) は 白詰草 を入手!
フェル(284) は 剛毛 を入手!
秋桐誠司(302) は 腐肉 を入手!
来訪者たち(15) は 腐肉 を入手!
玲(290) は 剛毛 を入手!



チナミ区 M-15(草原)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 N-15(森林)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 O-15(森林)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 O-16(森林)に移動!(体調22⇒21)
チナミ区 P-16(森林)に移動!(体調21⇒20)
MISSION!!
チナミ区 O-16:梅楽園 が発生!
- 来訪者たち(15) が経由した チナミ区 O-16:梅楽園
- フェル(284) が経由した チナミ区 O-16:梅楽園
- 玲(290) が経由した チナミ区 O-16:梅楽園
- 秋桐誠司(302) が経由した チナミ区 O-16:梅楽園





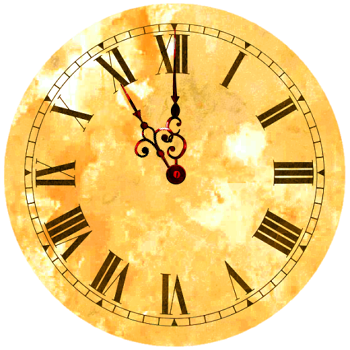
[842 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[382 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[420 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[127 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
[233 / 500] ―― 《大通り》より堅固な戦型
[43 / 500] ―― 《商店街》より安定な戦型
[27 / 500] ―― 《鰻屋》より俊敏な戦型
―― Cross+Roseに映し出される。


落ち着きなくウロウロと歩き回っている白南海。
ゆらりと顔を上げ、微笑を浮かべる。
チャットが閉じられる――












相変わらず、木々が蠢いている・・・







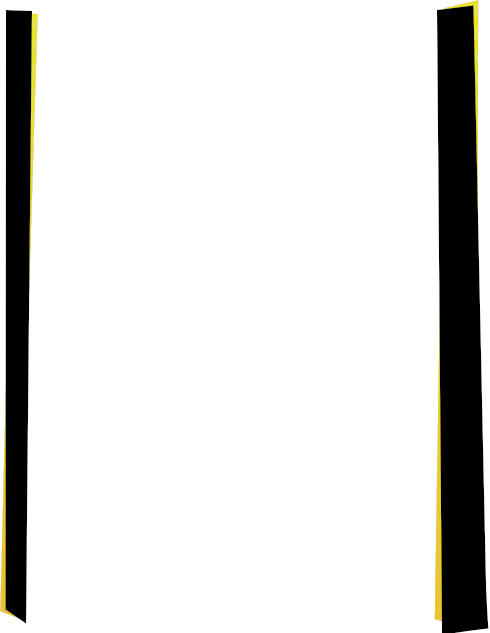
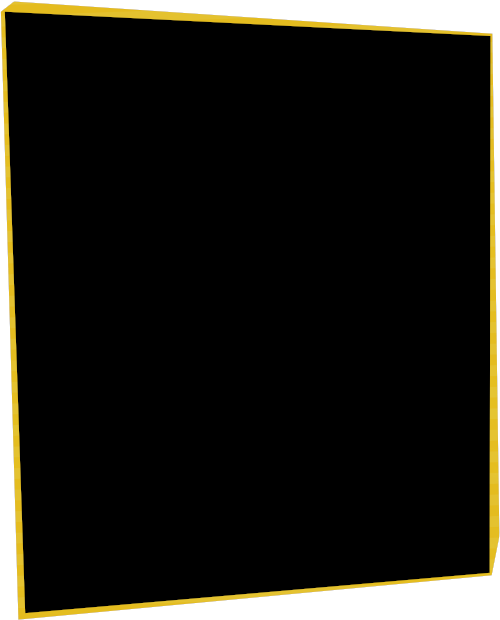





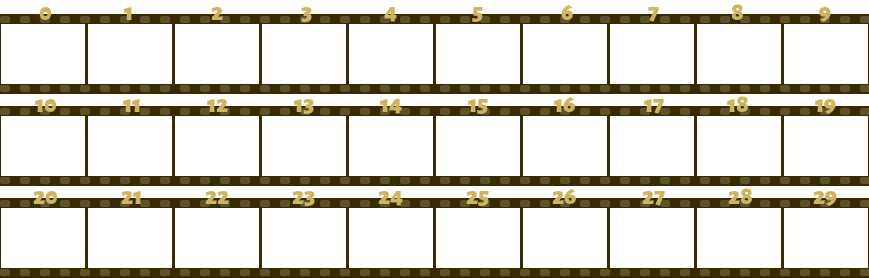







































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [スキル]OK.



【10年前、某日・某所】
「あ、よかった。みんないるわね」
からり、部室の扉が開いて彼女が覗き込んできた
大体のいつもの面子がそろっていることを確認して、中に入ってくる
「あれ、夢咲さん。まだ夏休み終わってないよ?」
「みんなだって、もういるじゃない」
くすくすと笑いながら、彼女は何やら大きな袋を机の上に置いた
まだ夏休みが明けていないのは事実だが、この新聞部の面子は大体部室にそろっていた
夏休み明けてすぐに学校新聞を出す予定だから、その作業があるせいだ
もっとも、作業ついでに皆で集まって喋るのが目的と言うのも、多少はあるだろうが
彼女も、その点わかっていてやってきたに違いない
「零羅ちゃん、その大きな袋何?」
「これ?夏休み終わる一足前に、みんなにお土産よ」
部長の問いに、彼女はにっこり笑ってそう答えた
半分、暑さでだらけていた皆ががバリ、起き上がる
「お土産?どこの?」
「ヴァーチャシティと、あとはヨーロッパのいくつかの国よ」
「仕事で行ったんだったよな。わざわざ。買ってきてくれたのか」
彼女、夢咲 零羅は現役高校生にして現役の作家だ
それも、いくつかの作品は映画化やらドラマ化やら……最近はアニメ化された物もある。そんな人気作家である
国外でも作品は人気らしく、夏休みのような長期の休みの期間は国内外あちこち飛び回って、サイン会なり関連の仕事をしていると聞いていた
正直、長期の休み期間の方が普段より忙しいのではないか?とも感じる
そんな多忙な中、自分達に土産物を買ってきてくれるくらいには彼女はこの新聞部面子を親しく思ってくれているのだろう。純粋に、彼女が親切なだけかもしれないが
「ヴァーチャシティ辺りの物は、まだこっちにはあまり入ってこないんですもの。せっかくだからね。ほら。ヴァーチャシティ名産のスイートナッツ」
「よりによってハワイシティのマカダミアンナッツのようなチョイス!?」
でんっ、と机の上に出された袋の中に、アーモンドに似た見た目のスイートナッツがぎっしり、入っている
聞いたことがある。見た目完全にアーモンドのくせに、味付けせずとも大変と甘いと噂の食べ物だ。自然でこんな甘さ出るのか、と疑問は浮かぶが、あのヴァーチャシティ特産であるのだ。遺伝子改良とかそうしたもので生まれたものなのだろう
「あら、私、食べたことあるけど結構おいしいわよ?一気にたくさん食べると胃もたれするような気がするけど」
「夢咲は甘いもん好きだからそうだろうけど。日本人の平均味覚からするとあっっまいことに変わりないよな。いや、土産物だからもらうけど」
「何だったら、そのまま食べないで他のお菓子に加工して食べても美味しいわよ」
向こうで食べたタルト、美味しかったものと彼女は笑っている
なるほど、加工すれば甘さは多少ましに……いや、加工次第ではもっと甘くなるのでは……?
「加工……そういえば、家庭科部も今日は学校来てるやつらいたな。よし、頼みに行くか」
「え、部長。家庭科部と言う女子の園に突撃して頼みに行くの?勇気MAX?」
「いや、家庭科部の男女比は大体半々だ。問題ない。ついでに、家庭科部の取材ってことにすれば聞いてもらえるだろ。零羅ちゃん、スイートナッツもらっていくよ?」
「えぇ、どうぞ」
よし!と部長がスイートナッツの袋を持って部室を出ていく
取材なら、という事か。ついでに家庭科部で何かつまみ食いでもしてくるつもりなのか、他の面子もぞろぞろと出ていった
「あら、文雄君はいかないの?」
「今のうちに片づけときたい原稿あるから。それに、夢咲さん一人残すの悪い……というか、夢咲さんはみなについていかなくてよかったのかい」
ノートパソコンのキーボードをたたきながら問いに答えて、ついでに問い返す
えぇ、と適当な椅子に腰かけて彼女は頷いた
「今日は、ゆっくりしたいし」
「夏休み中、ほぼ仕事だったんだろう?お疲れさま。宿題とかは大丈夫?」
「ふふ、仕事の合間にちゃんとやったわ。きっちり見張ってくる人がいるとさぼれないもの」
おそらく、護衛の人がその辺きっちり見張っていたのだろう
彼女は生まれ自体そこそこいい家であるようだし、何より人気作家だ
ヴァーチャシティのような治安が死滅しているような国に行く時は、いや、そうじゃなくとも仕事の時はほぼ、護衛の人間がついている
仕事どころか、新聞部の面子と一緒に映画を見に行った時も、こっそりと護衛らしき人間がついているのを目撃した
……ある意味、常に見張られているようなものだろう。堅苦しいだろうに、彼女にとっては「当たり前」の事であるのか、その環境に慣れきっているようだった
こうやって学校にいる時はさすがに護衛の影はない。数少なく、護衛の目を気にすることのない時間が学校にいる間なのではないだろうか
「あ。そうだわ。ちょうどいいから……はい、これ」
何やら、彼女はほかにもおみやげ物が入った袋をガサゴソとし始めた
そうして取り出したのは、小さな紙袋。それを、こちらに手渡してきた
「俺に?」
「えぇ。文雄君個人へのお土産。文雄君には、色々お世話になってるもの」
「お世話に、って……大したこともしてないと思うけど」
「あら。あなたのおかげで、また一つ新しいネタが浮かんだんですもの。十二分にお世話になっているわ」
そんなものだろうか
新しいネタ、と言うのはこちらの取材を受けている間に「あ、閃いた」とか言っていたから、その事か。一体何を閃いたのか、教えてはくれなったが。また何か書くのだろう
……それはさておき、この紙袋だ
本当に受け取っていいのか問えば、もちろんと微笑まれる
それならば、と正直に受け取ることにした。友人の行為は素直に受け取るべきだろう
他の部員がいる前だったら、変にはやし立てられたに違いない。こうして他の連中がいない時に渡してくれたのはありがたい
開けてみれば、中に入っていたのはエメラルドを抱いた青い蠍のチャームがついた、ストラップ
「これは……」
「お守り、みたいなものね。ほら、文雄君、女性関係でろくな縁がない、って言ってたから」
「よく覚えてるね」
「覚えているわよ。かなりぐったりしながら愚痴っていたじゃない」
そうだっただろうか?
そうだったのかもしれない
「青い蠍は「色欲」の象徴。されど、それも見方を変えれば、素敵な恋を、愛を求めるという事。そしてエメラルドは愛の力が強い宝石よ。それ以外にも疲れた心を癒し、思考能力を高める効果があるとも言われているの。文雄君に、素敵な縁がありますように、と。取材やらなにやらで疲れ気味の心が休まりますように、って思って」
「そうか……ありがとう、夢咲さん」
きっと、そのおみやげ物がどういうものであったとしても
自分にとって、それは「特別」となりえたのだろう
自分と彼女の間には、間違っても色恋沙汰と呼べるような感情はなかった
それはただの男女間の友情でしかなく、だとしても特別な友情であったと……少なくとも、自分はそう感じていた
夢咲の家の人間として、作家として、「普通の女子高生」ではいられなかった彼女が、自分達新聞部にいる時だけは「普通の女子高生」でいられたならば、その場を自分達が提供することができていたならば……それが、幸せであり、妙な誇りのようなものを感じていたのは事実だった
彼女は「特別」な人間だったかもしれない
けれど、同時に「普通」の人間でもあったことは事実だ
彼女が「特別」足りえたのは、周囲の環境なり、周囲から持ち上げられたからであり……彼女自身が、若くして作家と言う道を歩むことを決めたからでもある
それでも、そうだとしても
彼女は「特別」な人間である以上に、ただ一人の「夢咲 零羅」という女性でもあった
だから
……だから
彼女が死んだ理由が、彼女が「特別」だったからなのか
彼女が「夢咲 零羅」だったからなのか
それとも、それすらも関係ない、ただただ偶発的なものだったのか
せめて
せめて、それだけでも知りたい
そして、もし、彼女が殺されたのだと、したら
そうなのだとしたら
せめて、俺にできる形で、彼女の仇討ちを成し遂げることは、許されるだろうか?



ENo.21 レイ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
ENo.157 ケイ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
以下の相手に送信しました



 |
『……ホブゴブリン、と……ホボゴブリン、の……違い、とは……?』 |
 |
玲 「さぁ……??;」 |





対戦相手未発見のため不戦勝!
影響力が 8 増加!
影響力が 8 増加!



響鳴LV を 5 UP!(LV15⇒20、-5CP)
料理LV を 5 UP!(LV65⇒70、-5CP)
来訪者たち(15) により ItemNo.13 大蒜 から防具『ラージシールド』を作製してもらいました!
⇒ ラージシールド/防具:強さ90/[効果1]体力15 [効果2]- [効果3]-
 |
“魔術師” 「はいよ。 結構重くなったが大丈夫か?」 |
ノジコ(456) とカードを交換しました!
ノジコのおうえん! (ムーンサルトプレス)
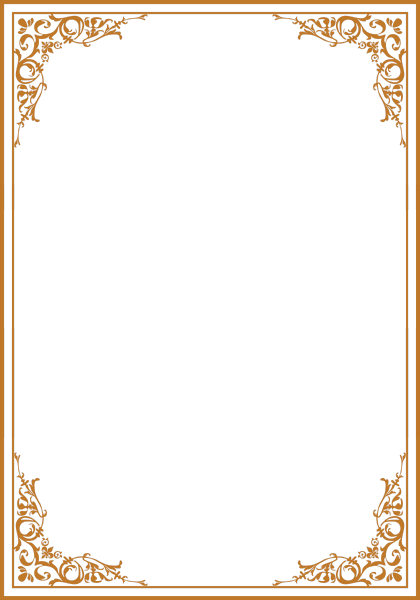
光輝燦然 を研究しました!(深度0⇒1)
光輝燦然 を研究しました!(深度1⇒2)
光輝燦然 を研究しました!(深度2⇒3)
エファヴェセント を習得!
マナ を習得!
アディクティブチューン を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



来訪者たち(15) は 枝豆 を入手!
フェル(284) は 白詰草 を入手!
玲(290) は 枝豆 を入手!
秋桐誠司(302) は 白詰草 を入手!
フェル(284) は 剛毛 を入手!
秋桐誠司(302) は 腐肉 を入手!
来訪者たち(15) は 腐肉 を入手!
玲(290) は 剛毛 を入手!



チナミ区 M-15(草原)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 N-15(森林)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 O-15(森林)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 O-16(森林)に移動!(体調22⇒21)
チナミ区 P-16(森林)に移動!(体調21⇒20)
MISSION!!
チナミ区 O-16:梅楽園 が発生!
- 来訪者たち(15) が経由した チナミ区 O-16:梅楽園
- フェル(284) が経由した チナミ区 O-16:梅楽園
- 玲(290) が経由した チナミ区 O-16:梅楽園
- 秋桐誠司(302) が経由した チナミ区 O-16:梅楽園





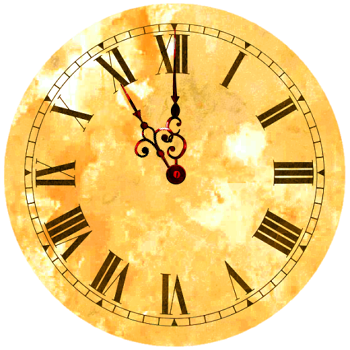
[842 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[382 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[420 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[127 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
[233 / 500] ―― 《大通り》より堅固な戦型
[43 / 500] ―― 《商店街》より安定な戦型
[27 / 500] ―― 《鰻屋》より俊敏な戦型
―― Cross+Roseに映し出される。

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
 |
白南海 「・・・・・おや、どうしました?まだ恐怖心が拭えねぇんすか?」 |
 |
エディアン 「・・・何を澄ました顔で。窓に勧誘したの、貴方ですよね。」 |
 |
白南海 「・・・・・・・・・」 |
落ち着きなくウロウロと歩き回っている白南海。
 |
白南海 「・・・・・・・・・あああぁぁワカァァ!! 俺これ嫌っすよぉぉ!!最初は世界を救うカッケー役割とか思ってたっすけどッ!!」 |
 |
エディアン 「わかわかわかわか・・・・・何を今更なっさけない。 そんなにワカが恋しいんです?そんなに頼もしいんです?」 |
 |
白南海 「・・・・・・・・・」 |
ゆらりと顔を上げ、微笑を浮かべる。
 |
白南海 「それはもう!若はとんでもねぇ器の持ち主でねぇッ!!」 |
 |
エディアン 「突然元気になった・・・・・」 |
 |
白南海 「俺が頼んだラーメンに若は、若のチャーシューメンのチャーシューを1枚分けてくれたんすよッ!!」 |
 |
エディアン 「・・・・・。・・・・他には?」 |
 |
白南海 「俺が501円のを1000円で買おうとしたとき、そっと1円足してくれたんすよ!!そっとッ!!」 |
 |
エディアン 「・・・・・あとは?」 |
 |
白南海 「俺が車道側歩いてたら、そっと車道側と代わってくれたんすよ!!そっとッ!!」 |
 |
エディアン 「・・・うーん。他の、あります?」 |
 |
白南海 「俺がアイスをシングルかダブルかで悩ん――」 |
 |
エディアン 「――あー、もういいです。いいでーす。」 |
 |
白南海 「・・・お分かりいただけましたか?若の素晴らしさ。」 |
 |
エディアン 「えぇぇーとってもーーー。」 |
 |
白南海 「いやー若の話をすると気分が良くなりますァ!」 |
 |
白南海 「・・・・・・・・・」 |
 |
白南海 「・・・・・・・・・あああぁぁワカァァ!!!!!!」 |
 |
エディアン 「・・・あーうるさい。帰りますよ?帰りますからねー。」 |
チャットが閉じられる――







決闘不成立!
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。



チナミ区 O-16 周辺
梅楽園
ハザマのなか、咲き乱れる梅の木たち。梅楽園

動く梅木
地を砕き歩く梅の木。
美しく咲いては散ってゆく花々。
美しく咲いては散ってゆく花々。
 |
動く梅木 「(ギギギ・・・・・ギギ・・・ッ)」 |
相変わらず、木々が蠢いている・・・





ENo.284
「世間知らず」フェル

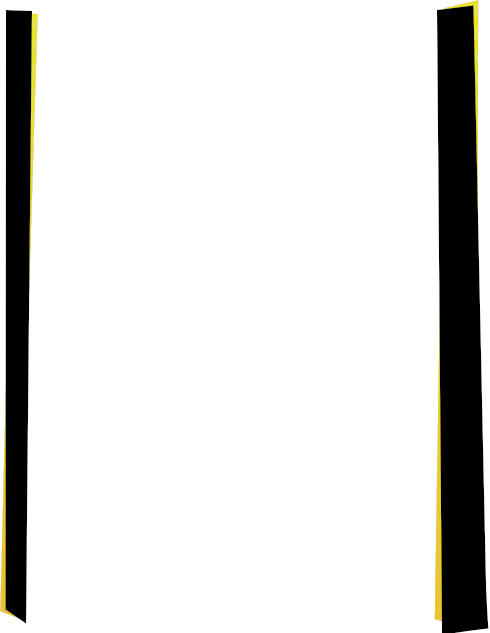
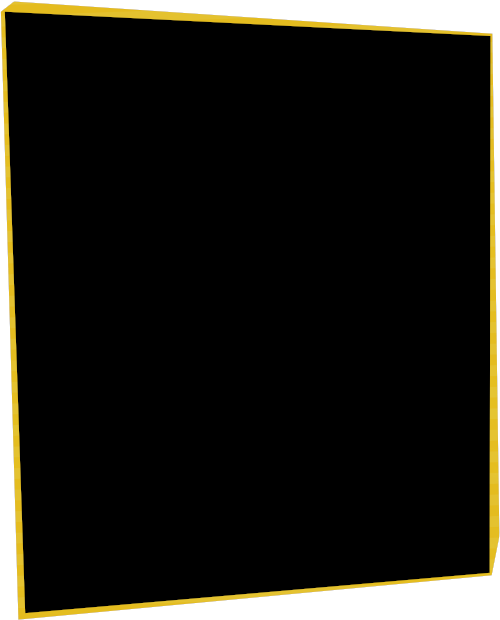
■「世間知らず」フェル
金髪金眼の小柄な16,7歳程度の未成年
このたび、無事、イバラ創藍高校に通うこととなった
同時に公認家出ではなく学校に通うためにイバラシティにいる、と言う事にもなったようだ
生まれて初めての学校に内心だいぶはしゃいでいる
ただ、相変わらず諸事情につきフルネームを名乗りたがらない
実家から「騎士」が二人派遣されている状態である事を考えると、まだまだ普通からは程遠いのだろう
・もらい物
トランシーバー(桐生 玲(ENo290)様から。不審者通報用)
変装セット(寒色系の色合いのカツラと伊達メガネ)(桐生 玲(ENo290)様から)
・通信機能つき懐中時計(杜若(旧ENo361サブ)様から)
【異能】押し付けられた祝福《ギフト》
祈りによって、様々な奇跡を起こす異能
治癒や浄化などが主であり、浄化に関しては普段から無自覚に発動し続けている様子である
死者を復活させうる可能性があるらしい…?
【拠点】チナミ区「古いお屋敷(心霊スポット)」内「お屋敷の一室」http://lisge.com/ib/talk.php?p=229
【出没プレイス】チナミ区内あちこち
イバラ創藍高校等
■九十九屋
20代前半と思われる男性
イバラシティの外からやってきた様子
常に黒い革手袋を身につけている
基本的には丁寧な言葉づかいを心がけているようだが、喋る内容まで丁寧とは限らない。失礼な事でも平気で口に出す事も多々ある様子。親友相手には一切合切の遠慮のない口調になっている
【裏稼業の知識がある人は、彼の名前に関して適当にダイスロールしてくださって問題ありません。成功した場合、こちらからそっと情報提供させていただきます】
【異能】『引き寄せ引き裂け《グラヴィタ・リパルション》』
針金を操って見せた
他にも、何かしらできるようだが…?
【拠点】ツクナミ区「雲林園荘」内「雲林園荘:202号室」
ツクナミ区「雑居ビル スターゲイズ」内「針金家具とインテリアの店アルマ」
【出没プレイス】ツクナミ区内や「インドカレー BASHAR」等
■ヴィトリオ
20代前半の男性
司祭服を身にまとい、大きな棺桶を背に担いだ不審者
九十九屋の親友との事
フェルの実家に仕える「騎士」。「灰色の騎士」
フェルの護衛として今回送り込まれてきた
基本的には明るい女好きだが、今回はお仕事中なので頑張ってナンパ自重中
【異能】神様の宝箱《Scrigno del tesoro di Dio》
他者を入れ物の中に「閉じ込める」異能
当人曰く弱点だらけで使いづらいとの事
【異能】騎士よ武器を取れ《ナイト・オブ・グローリー》
詳細不明
儀礼用の装飾が施された銀の剣を出してみせた
【出没プレイス】ランダム。フェルと共に行動している場合が多い?
■白神 虎樹
20代半ばほどの青年
黒いジャケットを身に着け、首元と両手首に金属製の輪を装着している
フェルの実家から派遣されてきた「騎士」の一人
ヴィットリオとは「騎士」としての所属が違うようだ
護衛以外にも、何か仕事が……?
【異能】?????
詳細不明
■バグ
160cm程の小柄で目付きの悪い男性
フェルの誘拐事件にて黒幕に最も近い位置にいたが、命の危険を感じたり等で手を引いた
体が丈夫でなく、以前は時折発作を起こし吐血している様子が見られていた。今はだいぶ治療がなされた為、だいぶマシになっている……体が弱い事には変わりないが
現在、ホロウさん(ENo,302様サブ)と交際中
彼から贈られた髪飾りをひどく大切にしていて、常に身につけている
【異能】潜り込む電脳蟲《バグ》
電脳系異能
電子機器を意のままに操る・ネットでのハッキングや情報収集等、今の御時世ではかなり便利な異能
■クライ
18歳程度の少年のような青年のような
フェルの誘拐事件に加担していたが、今は手を引いている
結構な臆病者
身体能力が高く、自然治癒力も高いがそれは異能ではない様子
【異能】誰にも見えない《ソリュテード・クライ》
透明になる異能
触れたものも透明化する事ができる
最近、やっと制御できるようになってきた
■メリッサ・ウィルソン
19歳くらいのちょっぴりぽっちゃりガール
怠惰で甘いものや美味しいものが大好き
自覚なしに悪い人に利用されたりもしていたけど、今は平和です
【異能】確率操作《プロバビリティー ザ トイ》
ありとあらゆる物事の確率を1%から99%の間で操作する程度の異能
使用にはカロリーを消耗してしまうらしい
なお、0%と100%はどうしようもない
■ケネス・ブラックマン・アーキナイト
16,7歳程度の少年
イバラシティ外の学校に通っていたのだが、今現在故あってイバラシティに在住している
異能『燃え盛る庭《ムスペルヘイム》』
炎を生み出し、操る異能。その最大火力は凄まじく、一歩間違えば自身すら焼き殺し兼ねない
正式には冷気も操れるようであるが、当人の使い方は炎に寄っている
また、常に体温は一定の温度に保たれており、人間離れした基礎代謝の持ち主でもある(ただし代償としてか相当な大食らい)
■その他色々
お屋敷の怪異とかぶたさんとかなんか色々いるみたいですね
■荊街情報所へのリンクはこちら
https://ibarainfo.wiki.fc2.com/wiki/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%AB
■著作権一覧
「らぬきの立ち絵保管庫」様(http://ranuking.ko-me.com/):フェルプロフとアイコン、ヴィットリオアイコン、白コートの男、ケネス、零羅、鰐塚
かおぱた様(http://shitamachi.xyz/p24/):九十九屋
きゃらふと様:???
わんころ様:虚無、おばけ
ツラの悪い男(Picrew):バグ
まいきゃらメーカー(Picrew):クライ
男の子メーカー(Picrew):虎樹
自作:りぼん、バチバチ、ぶたさん
ぽょメーカー(Picrew):メリッサ
ふわ様:羊執事ぶたさん
ただの メーカー(Picrew):鰐塚
鬼姫様:おりぼんぶたさんシリーズ
※以下、退場済エネミーキャラ
傷物男子(Picrew):ニーヒッツ
おんなのこをつくろう。(Picrew):アマンテ
金髪金眼の小柄な16,7歳程度の未成年
このたび、無事、イバラ創藍高校に通うこととなった
同時に公認家出ではなく学校に通うためにイバラシティにいる、と言う事にもなったようだ
生まれて初めての学校に内心だいぶはしゃいでいる
ただ、相変わらず諸事情につきフルネームを名乗りたがらない
実家から「騎士」が二人派遣されている状態である事を考えると、まだまだ普通からは程遠いのだろう
・もらい物
トランシーバー(桐生 玲(ENo290)様から。不審者通報用)
変装セット(寒色系の色合いのカツラと伊達メガネ)(桐生 玲(ENo290)様から)
・通信機能つき懐中時計(杜若(旧ENo361サブ)様から)
【異能】押し付けられた祝福《ギフト》
祈りによって、様々な奇跡を起こす異能
治癒や浄化などが主であり、浄化に関しては普段から無自覚に発動し続けている様子である
死者を復活させうる可能性があるらしい…?
【拠点】チナミ区「古いお屋敷(心霊スポット)」内「お屋敷の一室」http://lisge.com/ib/talk.php?p=229
【出没プレイス】チナミ区内あちこち
イバラ創藍高校等
■九十九屋
20代前半と思われる男性
イバラシティの外からやってきた様子
常に黒い革手袋を身につけている
基本的には丁寧な言葉づかいを心がけているようだが、喋る内容まで丁寧とは限らない。失礼な事でも平気で口に出す事も多々ある様子。親友相手には一切合切の遠慮のない口調になっている
【裏稼業の知識がある人は、彼の名前に関して適当にダイスロールしてくださって問題ありません。成功した場合、こちらからそっと情報提供させていただきます】
【異能】『引き寄せ引き裂け《グラヴィタ・リパルション》』
針金を操って見せた
他にも、何かしらできるようだが…?
【拠点】ツクナミ区「雲林園荘」内「雲林園荘:202号室」
ツクナミ区「雑居ビル スターゲイズ」内「針金家具とインテリアの店アルマ」
【出没プレイス】ツクナミ区内や「インドカレー BASHAR」等
■ヴィトリオ
20代前半の男性
司祭服を身にまとい、大きな棺桶を背に担いだ不審者
九十九屋の親友との事
フェルの実家に仕える「騎士」。「灰色の騎士」
フェルの護衛として今回送り込まれてきた
基本的には明るい女好きだが、今回はお仕事中なので頑張ってナンパ自重中
【異能】神様の宝箱《Scrigno del tesoro di Dio》
他者を入れ物の中に「閉じ込める」異能
当人曰く弱点だらけで使いづらいとの事
【異能】騎士よ武器を取れ《ナイト・オブ・グローリー》
詳細不明
儀礼用の装飾が施された銀の剣を出してみせた
【出没プレイス】ランダム。フェルと共に行動している場合が多い?
■白神 虎樹
20代半ばほどの青年
黒いジャケットを身に着け、首元と両手首に金属製の輪を装着している
フェルの実家から派遣されてきた「騎士」の一人
ヴィットリオとは「騎士」としての所属が違うようだ
護衛以外にも、何か仕事が……?
【異能】?????
詳細不明
■バグ
160cm程の小柄で目付きの悪い男性
フェルの誘拐事件にて黒幕に最も近い位置にいたが、命の危険を感じたり等で手を引いた
体が丈夫でなく、以前は時折発作を起こし吐血している様子が見られていた。今はだいぶ治療がなされた為、だいぶマシになっている……体が弱い事には変わりないが
現在、ホロウさん(ENo,302様サブ)と交際中
彼から贈られた髪飾りをひどく大切にしていて、常に身につけている
【異能】潜り込む電脳蟲《バグ》
電脳系異能
電子機器を意のままに操る・ネットでのハッキングや情報収集等、今の御時世ではかなり便利な異能
■クライ
18歳程度の少年のような青年のような
フェルの誘拐事件に加担していたが、今は手を引いている
結構な臆病者
身体能力が高く、自然治癒力も高いがそれは異能ではない様子
【異能】誰にも見えない《ソリュテード・クライ》
透明になる異能
触れたものも透明化する事ができる
最近、やっと制御できるようになってきた
■メリッサ・ウィルソン
19歳くらいのちょっぴりぽっちゃりガール
怠惰で甘いものや美味しいものが大好き
自覚なしに悪い人に利用されたりもしていたけど、今は平和です
【異能】確率操作《プロバビリティー ザ トイ》
ありとあらゆる物事の確率を1%から99%の間で操作する程度の異能
使用にはカロリーを消耗してしまうらしい
なお、0%と100%はどうしようもない
■ケネス・ブラックマン・アーキナイト
16,7歳程度の少年
イバラシティ外の学校に通っていたのだが、今現在故あってイバラシティに在住している
異能『燃え盛る庭《ムスペルヘイム》』
炎を生み出し、操る異能。その最大火力は凄まじく、一歩間違えば自身すら焼き殺し兼ねない
正式には冷気も操れるようであるが、当人の使い方は炎に寄っている
また、常に体温は一定の温度に保たれており、人間離れした基礎代謝の持ち主でもある(ただし代償としてか相当な大食らい)
■その他色々
お屋敷の怪異とかぶたさんとかなんか色々いるみたいですね
■荊街情報所へのリンクはこちら
https://ibarainfo.wiki.fc2.com/wiki/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%AB
■著作権一覧
「らぬきの立ち絵保管庫」様(http://ranuking.ko-me.com/):フェルプロフとアイコン、ヴィットリオアイコン、白コートの男、ケネス、零羅、鰐塚
かおぱた様(http://shitamachi.xyz/p24/):九十九屋
きゃらふと様:???
わんころ様:虚無、おばけ
ツラの悪い男(Picrew):バグ
まいきゃらメーカー(Picrew):クライ
男の子メーカー(Picrew):虎樹
自作:りぼん、バチバチ、ぶたさん
ぽょメーカー(Picrew):メリッサ
ふわ様:羊執事ぶたさん
ただの メーカー(Picrew):鰐塚
鬼姫様:おりぼんぶたさんシリーズ
※以下、退場済エネミーキャラ
傷物男子(Picrew):ニーヒッツ
おんなのこをつくろう。(Picrew):アマンテ
20 / 30
492 PS
チナミ区
P-16
P-16







































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 大光明遍照の護札 | 装飾 | 50 | 体力10 | - | - | |
| 5 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]防御10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) | |||
| 6 | 柳 | 素材 | 20 | [武器]風纏10(LV20)[防具]舞撃10(LV20)[装飾]風柳15(LV30) | |||
| 7 | ポトフ | 料理 | 65 | 器用14 | 敏捷14 | 耐疫14 | |
| 8 | 丈夫な学ラン | 防具 | 30 | 体力10 | - | - | |
| 9 | 白石 | 素材 | 15 | [武器]祝福10(LV10)[防具]反祝10(LV10)[装飾]舞祝10(LV10) | |||
| 10 | 木瓜 | 素材 | 15 | [武器]恐撃10(LV25)[防具]反地10(LV25)[装飾]器用10(LV10) | |||
| 11 | 雑木 | 素材 | 15 | [武器]回復10(LV15)[防具]活力10(LV15)[装飾]体力10(LV15) | |||
| 12 | 花びら | 素材 | 10 | [武器]混乱10(LV25)[防具]舞魅10(LV10)[装飾]祝福10(LV20) | |||
| 13 | ラージシールド | 防具 | 90 | 体力15 | - | - | |
| 14 | 不思議な牙 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV5)[防具]活力10(LV5)[装飾]体力10(LV5) | |||
| 15 | 良いお野菜 | 食材 | 20 | [効果1]器用20(LV20)[効果2]幸運20(LV30)[効果3]命脈20(LV40) | |||
| 16 | 赤い薔薇 | 素材 | 10 | [武器]火撃10(LV25)[防具]反魅10(LV25)[装飾]火纏10(LV25) | |||
| 17 | 栄養ドリンク | 食材 | 20 | [効果1]活力10(LV10)[効果2]防御15(LV20)[効果3]鎮痛20(LV30) | |||
| 18 | 白詰草 | 素材 | 25 | [武器]幸運20(LV35)[防具]命脈20(LV40)[装飾]器用20(LV35) | |||
| 19 | 剛毛 | 素材 | 10 | [武器]放縛15(LV25)[防具]反縛15(LV25)[装飾]強靭15(LV25) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 命術 | 25 | 生命/復元/水 |
| 響鳴 | 20 | 歌唱/音楽/振動 |
| 百薬 | 25 | 化学/病毒/医術 |
| 料理 | 70 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 7 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ウォーターフォール | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |
| クリエイト:タライ | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |
| エチュード | 6 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) | |
| ヒールポーション | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+猛毒減 | |
| リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |
| アクアシェル | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+火耐性増 | |
| コールドウェイブ | 5 | 0 | 80 | 敵4:水撃&凍結+自:炎上 | |
| アクアリカバー | 7 | 0 | 80 | 味肉:HP増+肉体変調を守護化 | |
| ヘイルカード | 5 | 0 | 100 | 敵5:粗雑水領撃 | |
| クリエイト:ヴェノム | 5 | 0 | 90 | 敵:猛毒・麻痺・腐食 | |
| トランス | 5 | 0 | 100 | 自:混乱+自:AT・HL増+魅了を祝福化 | |
| クイックレメディ | 5 | 0 | 100 | 味傷:HP増+自:混乱+連続増 | |
| アクアヒール | 7 | 0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 | |
| ビブラート | 5 | 0 | 120 | 敵全2:粗雑SP攻撃 | |
| ファーマシー | 7 | 0 | 110 | 味傷:HP増+肉体精神変調減 | |
| ガーディアン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+味傷:護衛 | |
| フリーズノート | 5 | 0 | 110 | 敵従全:水領痛撃 | |
| スノードロップ | 5 | 0 | 150 | 敵全:凍結+凍結状態ならDX減(1T) | |
| サモン:スライム | 5 | 2 | 300 | 自:スライム召喚 | |
| エネルジコ | 5 | 0 | 150 | 自:MHP・MSP増 | |
| ウィルスゾーン | 5 | 0 | 140 | 敵全:衰弱 | |
| ヒーリングソング | 5 | 0 | 120 | 味全:HP増+魅了 | |
| ツインブラスト | 5 | 0 | 220 | 敵全:攻撃&麻痺+敵全:攻撃&盲目 | |
| アクアレゾナンス | 5 | 0 | 160 | 自:水特性・火耐性・水耐性増 | |
| ヒールミスト | 7 | 0 | 200 | 味全:HP増+敵全:射程3以上ならDX減(2T) | |
| パーガティブ | 5 | 0 | 200 | 敵全:攻撃&食事による付加効果のLV減 | |
| ディスインフェクト | 6 | 0 | 100 | 味全:HP増+肉体変調を守護化 | |
| アイシクルランス | 5 | 0 | 150 | 敵:水痛撃&凍結 | |
| エファヴェセント | 5 | 0 | 280 | 敵全:攻撃、命中ごとに自:AT・DX増(1T) | |
| インフェクシャスキュア | 5 | 0 | 140 | 味列:HP増 | |
| マナ | 5 | 0 | 10 | 自:消費SP減 | |
| クライオセラピー | 5 | 0 | 150 | 味傷5:HP増+凍結 | |
| アディクティブチューン | 5 | 0 | 200 | 敵列:攻撃&祝福を猛毒化 | |
| コンフィデンス | 5 | 0 | 300 | 自:MSP・HL増 | |
| コンテイジョン | 5 | 0 | 200 | 敵:猛毒・麻痺・衰弱・盲目・腐食 | |
| アナスタシス | 5 | 0 | 200 | 味傷:名前に「復活」を含む付加効果があればDF・AG増(2T)、なければ復活LV増 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 召喚強化 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:具現LVが高いほど自身の召喚するNPCが強化 | |
| 五月雨 | 5 | 4 | 0 | 【スキル使用後】敵:3連水撃 | |
| 水特性回復 | 6 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:水属性スキルのHP増効果に水特性が影響 | |
| 水の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:命術LVが高いほど水特性・耐性増 | |
| 薬師 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+名前に「防」を含む付加効果のLV増 | |
| 治癒領域 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】味傷3:HP増 | |
| 美酒佳肴 | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『料理』で、作る料理の付加効果のLVが増加するが、3D6が5以下なら料理の効果1が「自滅」になる。 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
VERANDERING (ブレイク) |
0 | 50 | 敵:攻撃 | |
|
風撃のカード (ショックウェイブ) |
0 | 160 | 自:連続減+敵全:風撃&朦朧 | |
|
自尊心に溢れた男 (アクアヒール) |
0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 | |
|
ネガフィールド (インヴァージョン) |
0 | 150 | 敵全:攻撃&祝福を猛毒化 | |
|
ほうじ茶ミルクティ (ヒーリングソング) |
0 | 120 | 味全:HP増+魅了 | |
|
過去 (ヒートイミッター) |
0 | 100 | 敵列:火撃&麻痺+自:凍結 | |
|
早打ち (ディクリースアイズ) |
0 | 100 | 自:連続増+自身のスキル・付加効果内のダイス目が低めになる | |
|
頭突 (フィアスファング) |
0 | 150 | 敵:攻撃&MHP減 | |
|
妖怪のつくりかた (クリエイト:モンスター) |
0 | 150 | 敵:粗雑攻撃 | |
|
ノジコのおうえん! (ムーンサルトプレス) |
0 | 120 | 敵:光撃&MSP減 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]ソウルビート | [ 2 ]ライトニング | [ 3 ]イレイザー |
| [ 3 ]光輝燦然 | [ 2 ]ストラテージュ | [ 3 ]サモン:サーヴァント |
| [ 3 ]クリエイト:シールド | [ 3 ]エファヴェセント | [ 3 ]デアデビル |
| [ 1 ]ラッシュ | [ 3 ]サンダーフォーム | [ 3 ]プチメテオカード |

PL / スパマル滅べ温泉