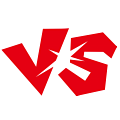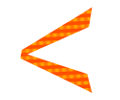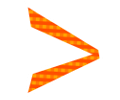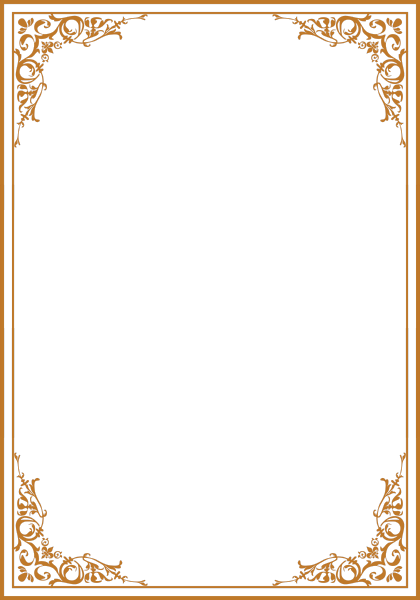<< 6:00~7:00




人を殺そうと思うと、意外と大変だ。
それでもやっぱり、人が死ぬのはあっけない。
***
「わたし、美しい死に方を探しているの」
ぼくの初恋は、そんなことを平然と言い放つ少し変わった女性だった。
大学生になったぼくは、ぼくを引き取った青斑教授の研究室をよく訪れていた。
最初は体よく用事を言いつけられて渋々だったが、そこで飼育されている有毒生物達を眺めるのは割と好きだった。どこか親近感のようなものを感じていたのかもしれない。
青斑教授に勧められて、部屋で毒蛇も飼っていた。カナエと名付けて可愛がっていたその蛇は、今はぼくの財布になっている。
その頃には幼少から続いていた"検査"はなくなっていたけれど、年に一回程度、体内の毒素を調べる検査は続いていた。ぼくは少しずつでも体外に排出されたり、消えてなくなったりしてくれないものかと僅かに期待していたけれど、そんな気配はなく、青斑教授は何故だか喜んでいた。
ぼくの体には毒がある。
当時はまだ、人を殺すに至るものではなかった。
それでも自分の唾液や汗、涙に毒があるという事実は、人との関わりを避けるのに十分な理由だった。
友人は相変わらず少なかったし、まして恋人など作る資格はないと思っていた。
それでもやっぱり、ぼくは誰かに必要とされたかった。
きっと心のどこかで、ぼくの体質ごと受け入れてくれる誰かを待っていた。
だから姫椿冬子(ひめつばき ふゆこ)がぼくの前に現れた時、彼女が運命の人だと思ってしまった。
今思えばそれは彼女の言動と異能がそう思わせていただけで、深く思い込んでしまったのはひとえにぼくの精神性のせいだろう。

彼女はぼくと同じ大学に通う学生で、大きな目と艶やかな黒髪が美しい、それでいてどこか幼い雰囲気を持った女性だった。
自分と目を合わせた人間に"何かしてあげたい"と思わせるという異能を持つ彼女の周りには、いつも惹き寄せられるように誰かが寄り添っていた。
異能によって駆り立てられた"何かしてあげたい"という思いは、多くの人によっては何のことはない、"ジュースを一本奢ってあげよう"とか"次の講義の教室まで送っていってあげよう"とか、その程度のことだ。
そんなささやかな善意のような何かに囲まれて育った彼女は、恐れることも嫌うことも知らないように見えた。
「きみ、斑目くんよね。さっきの講義でも一緒だった」
「えっ。あ、そ、そうだっけ……ごめん、よく、おぼえてなくて」
「どうして謝るの? それより、わたし冬子よ。姫椿冬子。よろしくね」
当時のぼくは人と関わるのを極力避けていたし、見た目通りの暗い人間だったし、その頃には無理をして明るく振舞うこともしなくなっていた。そんなぼくに、たいした用事もないのに何度も話しかけてきたのは彼女くらいだった。
彼女にしてみれば、目を合わせて話した人間はみんな何かしらいいことをしてくれるのだから、相手が多少気持ち悪くとも話しかけることにはメリットがある。
それでも、たまたまいくつか同じ授業を取っていただけのぼくを覚えていてくれた。言葉を交わしてくれた。
同世代の人間と話すのが久しぶりすぎて、うまく受け答えができなかったぼくに微笑みかけてくれた。
それだけで、彼女に夢中になるには十分だった。
「ユリの花を部屋いっぱいに敷き詰めて眠ると美しく死ねるって本当かしら?」
「ユリの毒は人にはあまり……花で死にたいなら、スズランとか……」
「スズラン! かわいいお花ね、どんな風に死ねるの?」
「えっと……主な中毒症状は、嘔吐、頭痛、眩暈とか……」
「うーん、苦しそうだからやめるわ」
ぼくが有毒生物を扱う青斑研究室に入り浸っているのを見かけたのか、彼女は毒についてよく聞いてきた。
青斑教授は食事中でも延々と毒物の話をし続ける人間だったので、一応居候という形になっていたぼくも人より少し詳しくなってしまっていて、彼女の質問にはだいたい答えられた。
「……姫椿さんは、死にたいの?」
ある時、ぼくは彼女にそう聞いた。
容姿もよくて、人からちやほやされて、彼女が死にたがる理由なんて何も思いつかなかった。
彼女は大きな目でぼくを見つめ返して、細い首を傾げた。
「今は別に。でも、人はいずれ死ぬものでしょ?
それなら、歳を取ってから死ぬより、今が一番楽しくて美しいと思った瞬間がいい」
彼女はその瞳の中にぼくを捉えたまま、ゆっくりと瞬きをした。
宝石のような輝きが見えなくなる一瞬すらもどかしくて、目が離せなくなっていた。
「だから人生最高の瞬間に、綺麗なわたしのままで死にたいの」
できれば即効性があって、ほとんど苦しまずに死ねる毒がいい。
そう、彼女は言った。
「……それなら。ぼくが用意してあげる。
少し、時間がかかるかもしれないけど……君だけのために」
気付いたら零れていたその言葉は、異能によって芽生えた"何かしてあげたい"だったのかもしれないけれど。
それでも、その後ぼくがしてしまったことは間違いなくぼくの意思で、ぼくの罪だ。
ぼくの血に含まれる毒に即死性はない。それはきっと、彼女にとって理想的な毒ではない。
血やあらゆる体液が持つ毒は、人をすぐに殺すには至らない。
でも、毒を溜め続ければ、いずれは。
この血の一滴で人を殺せるようになるだろう。
そのために、飼っていた毒蛇に腕を噛ませた。
彼女を殺すために。注射の痕の上から、何度も。何度も。
この先何年かかってもいい、初めてぼくが人の役に立てると思った。
そう思えば、あれほど嫌いだった痛みすら愛おしかった。
ずっと名前をつけていなかったこの異能に、"一滴の愛"(ラスト・ギフト)と名付けたのもこの時だった。
もう少し。もう少しだけ、待っていて。
そうしたら、きっと君を綺麗に死なせてあげられる。
***
けれど彼女は、待っていてはくれなかった。
翌年、彼女は講義棟の階段から転落してあっけなく死んだ。
彼女に熱を上げていた学生の一人が、思い余ってか彼女を突き落としたのだ。
もしかしたらぼくのように、彼女の願いを叶えてやりたいと思ってしまったクチだったのかもしれない。
野次馬の隙間から見えた彼女は長い黒髪が床に扇のように広がって、細い首がおかしな角度に折れていた。
きっと理想的な死に方ではなかっただろう、と麻痺したような頭で考えながら家に帰った。
"――ほんとう? 楽しみに待ってるわ。"
ぼくが彼女に毒を贈ると誓った日、去り際に向けられた笑顔は蕩けるようで、蜜のように甘くて。
気付けば、青斑教授の飼っている毒蠍の水槽に手を差し入れていた。
注射よりもなお鋭い、文字通り突き刺される痛み。
毒液が体の中に入ってくる感覚。
思えば昔からそうだった。
痛みを我慢すれば、褒めてもらえる。
報われることがなくなっても、一度紐づけられた条件づけは簡単には消えない。
まるで涎の止められない犬のようだと思いながらも。
この無意味な代替行為を、ぼくは長いことやめることができなかった。

***
今ならきっと、望むとおりに彼女を死なせることができる。
ぼくの血や骨や肉は、大学院を出る頃にはその域まで達していた。
その後、ぼくが毒を溜め込むことを黙認していた青斑教授が亡くなって、ぼくの管理は彼の縁者に移った。
後継者は教授とは方針が違ったようで、以降故意に毒を摂取することは禁止されて、色々な体液の成分検査も月に一度に増えた。
それからこの歳になるまでぼくは一人で生活しているけれど、青斑家はずっとぼくを管理している。今住んでいる部屋も彼らが手配したものだし、担当医も青斑の人間だ。
この先もずっと、恐らくは死んだ後も。
ぼくは一種の毒物として管理され続けるだろう。
別段それが幸せだとも、不幸せだとも思わない。そうであるべきだと思う。
でもどうしたって寂しくて、人恋しくなる時があって。
多分、ぼくが教授なんかやっているのは、学生達と関わりたいからだ。
近すぎない距離で、人と関わることができるからだ。
近すぎない距離。そのはずだったのに。
「……やっぱり、だめだなぁ。ぼく」



ENo.93 Eva とのやりとり

ENo.273 闇 とのやりとり

ENo.520 チャコール とのやりとり

ENo.719 ケムルス とのやりとり

以下の相手に送信しました













ぺちか(34) から 5 PS 受け取りました。
ぺちか(34) に 10 PS 送付しました。
百薬LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
武術LV を 5 UP!(LV20⇒25、-5CP)
命術LV を 5 UP!(LV20⇒25、-5CP)
防具LV を 7 UP!(LV50⇒57、-7CP)
タウラシアス(173) により ItemNo.15 不思議な雫 から射程1の武器『暴れ馬の黒蹄』を作製してもらいました!
⇒ 暴れ馬の黒蹄/武器:強さ67/[効果1]水纏10 [効果2]- [効果3]-【射程1】
タウラシアス(173) の持つ ItemNo.16 牙 から防具『ケライノ』を作製しました!
ぺちか(34) により ItemNo.16 禁断じゃない果実 から料理『さくらのわたあめ』をつくってもらいました!
⇒ 美酒佳肴![ 2 1 6 = 9 ]成功!料理の付加効果のLVが増加!
⇒ さくらのわたあめ/料理:強さ28/[効果1]攻撃6 [効果2]防御6 [効果3]器用6
ノクターン を研究しました!(深度0⇒1)
ノクターン を研究しました!(深度1⇒2)
ノクターン を研究しました!(深度2⇒3)
☆フィアスファング を習得!
☆コンフィデンス を習得!
☆ヴァンピール を習得!
☆初習得ボーナス:各FPが6増加した!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





タウラシアス(173) に移動を委ねました。
カミセイ区 Q-1(山岳)に移動!(体調15⇒14)
カミセイ区 R-1(山岳)に移動!(体調14⇒13)
カミセイ区 R-2(山岳)に移動!(体調13⇒12)
カミセイ区 R-3(山岳)に移動!(体調12⇒11)
カミセイ区 S-3(山岳)に移動!(体調11⇒10)





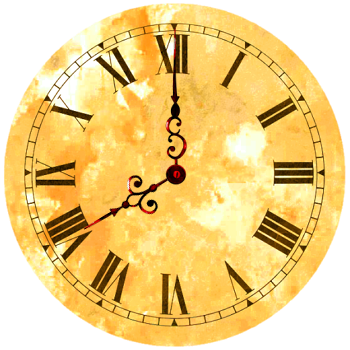
[787 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[347 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[301 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[75 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
―― Cross+Roseに映し出される。
ザザッ――
画面の情報が揺らぎ消えたかと思うと突然チャットが開かれ、
時計台の前にいるドライバーさんが映し出された。

チャットが閉じられる――










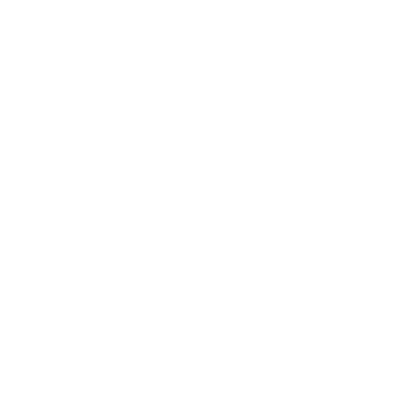
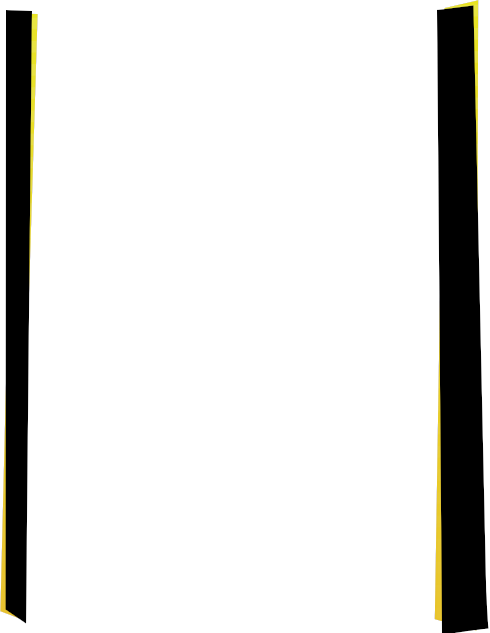
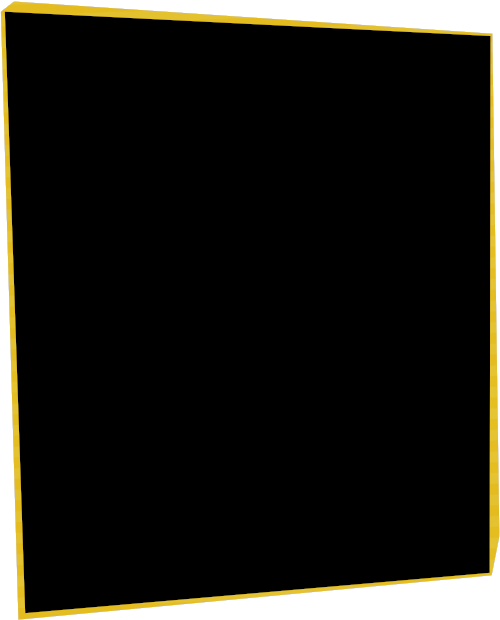





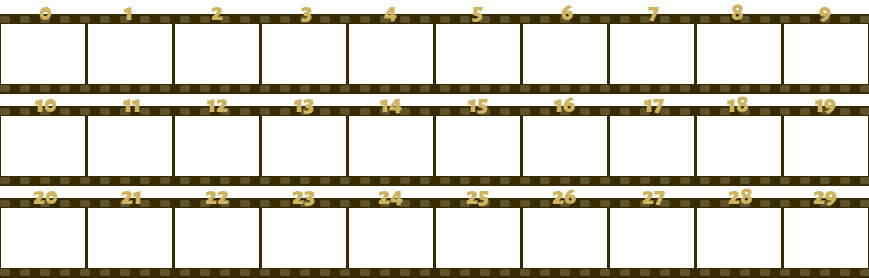







































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



人を殺そうと思うと、意外と大変だ。
それでもやっぱり、人が死ぬのはあっけない。
***
「わたし、美しい死に方を探しているの」
ぼくの初恋は、そんなことを平然と言い放つ少し変わった女性だった。
大学生になったぼくは、ぼくを引き取った青斑教授の研究室をよく訪れていた。
最初は体よく用事を言いつけられて渋々だったが、そこで飼育されている有毒生物達を眺めるのは割と好きだった。どこか親近感のようなものを感じていたのかもしれない。
青斑教授に勧められて、部屋で毒蛇も飼っていた。カナエと名付けて可愛がっていたその蛇は、今はぼくの財布になっている。
その頃には幼少から続いていた"検査"はなくなっていたけれど、年に一回程度、体内の毒素を調べる検査は続いていた。ぼくは少しずつでも体外に排出されたり、消えてなくなったりしてくれないものかと僅かに期待していたけれど、そんな気配はなく、青斑教授は何故だか喜んでいた。
ぼくの体には毒がある。
当時はまだ、人を殺すに至るものではなかった。
それでも自分の唾液や汗、涙に毒があるという事実は、人との関わりを避けるのに十分な理由だった。
友人は相変わらず少なかったし、まして恋人など作る資格はないと思っていた。
それでもやっぱり、ぼくは誰かに必要とされたかった。
きっと心のどこかで、ぼくの体質ごと受け入れてくれる誰かを待っていた。
だから姫椿冬子(ひめつばき ふゆこ)がぼくの前に現れた時、彼女が運命の人だと思ってしまった。
今思えばそれは彼女の言動と異能がそう思わせていただけで、深く思い込んでしまったのはひとえにぼくの精神性のせいだろう。
姫椿 冬子
創峰大学に通う大学生。
異能:"赤い花をわたしに頂戴"
(トリート・ライク・ア・プリンセス)
異能:"赤い花をわたしに頂戴"
(トリート・ライク・ア・プリンセス)
彼女はぼくと同じ大学に通う学生で、大きな目と艶やかな黒髪が美しい、それでいてどこか幼い雰囲気を持った女性だった。
自分と目を合わせた人間に"何かしてあげたい"と思わせるという異能を持つ彼女の周りには、いつも惹き寄せられるように誰かが寄り添っていた。
異能によって駆り立てられた"何かしてあげたい"という思いは、多くの人によっては何のことはない、"ジュースを一本奢ってあげよう"とか"次の講義の教室まで送っていってあげよう"とか、その程度のことだ。
そんなささやかな善意のような何かに囲まれて育った彼女は、恐れることも嫌うことも知らないように見えた。
「きみ、斑目くんよね。さっきの講義でも一緒だった」
「えっ。あ、そ、そうだっけ……ごめん、よく、おぼえてなくて」
「どうして謝るの? それより、わたし冬子よ。姫椿冬子。よろしくね」
当時のぼくは人と関わるのを極力避けていたし、見た目通りの暗い人間だったし、その頃には無理をして明るく振舞うこともしなくなっていた。そんなぼくに、たいした用事もないのに何度も話しかけてきたのは彼女くらいだった。
彼女にしてみれば、目を合わせて話した人間はみんな何かしらいいことをしてくれるのだから、相手が多少気持ち悪くとも話しかけることにはメリットがある。
それでも、たまたまいくつか同じ授業を取っていただけのぼくを覚えていてくれた。言葉を交わしてくれた。
同世代の人間と話すのが久しぶりすぎて、うまく受け答えができなかったぼくに微笑みかけてくれた。
それだけで、彼女に夢中になるには十分だった。
「ユリの花を部屋いっぱいに敷き詰めて眠ると美しく死ねるって本当かしら?」
「ユリの毒は人にはあまり……花で死にたいなら、スズランとか……」
「スズラン! かわいいお花ね、どんな風に死ねるの?」
「えっと……主な中毒症状は、嘔吐、頭痛、眩暈とか……」
「うーん、苦しそうだからやめるわ」
ぼくが有毒生物を扱う青斑研究室に入り浸っているのを見かけたのか、彼女は毒についてよく聞いてきた。
青斑教授は食事中でも延々と毒物の話をし続ける人間だったので、一応居候という形になっていたぼくも人より少し詳しくなってしまっていて、彼女の質問にはだいたい答えられた。
「……姫椿さんは、死にたいの?」
ある時、ぼくは彼女にそう聞いた。
容姿もよくて、人からちやほやされて、彼女が死にたがる理由なんて何も思いつかなかった。
彼女は大きな目でぼくを見つめ返して、細い首を傾げた。
「今は別に。でも、人はいずれ死ぬものでしょ?
それなら、歳を取ってから死ぬより、今が一番楽しくて美しいと思った瞬間がいい」
彼女はその瞳の中にぼくを捉えたまま、ゆっくりと瞬きをした。
宝石のような輝きが見えなくなる一瞬すらもどかしくて、目が離せなくなっていた。
「だから人生最高の瞬間に、綺麗なわたしのままで死にたいの」
できれば即効性があって、ほとんど苦しまずに死ねる毒がいい。
そう、彼女は言った。
「……それなら。ぼくが用意してあげる。
少し、時間がかかるかもしれないけど……君だけのために」
気付いたら零れていたその言葉は、異能によって芽生えた"何かしてあげたい"だったのかもしれないけれど。
それでも、その後ぼくがしてしまったことは間違いなくぼくの意思で、ぼくの罪だ。
ぼくの血に含まれる毒に即死性はない。それはきっと、彼女にとって理想的な毒ではない。
血やあらゆる体液が持つ毒は、人をすぐに殺すには至らない。
でも、毒を溜め続ければ、いずれは。
この血の一滴で人を殺せるようになるだろう。
そのために、飼っていた毒蛇に腕を噛ませた。
彼女を殺すために。注射の痕の上から、何度も。何度も。
この先何年かかってもいい、初めてぼくが人の役に立てると思った。
そう思えば、あれほど嫌いだった痛みすら愛おしかった。
ずっと名前をつけていなかったこの異能に、"一滴の愛"(ラスト・ギフト)と名付けたのもこの時だった。
もう少し。もう少しだけ、待っていて。
そうしたら、きっと君を綺麗に死なせてあげられる。
***
けれど彼女は、待っていてはくれなかった。
翌年、彼女は講義棟の階段から転落してあっけなく死んだ。
彼女に熱を上げていた学生の一人が、思い余ってか彼女を突き落としたのだ。
もしかしたらぼくのように、彼女の願いを叶えてやりたいと思ってしまったクチだったのかもしれない。
野次馬の隙間から見えた彼女は長い黒髪が床に扇のように広がって、細い首がおかしな角度に折れていた。
きっと理想的な死に方ではなかっただろう、と麻痺したような頭で考えながら家に帰った。
"――ほんとう? 楽しみに待ってるわ。"
ぼくが彼女に毒を贈ると誓った日、去り際に向けられた笑顔は蕩けるようで、蜜のように甘くて。
気付けば、青斑教授の飼っている毒蠍の水槽に手を差し入れていた。
注射よりもなお鋭い、文字通り突き刺される痛み。
毒液が体の中に入ってくる感覚。
思えば昔からそうだった。
痛みを我慢すれば、褒めてもらえる。
報われることがなくなっても、一度紐づけられた条件づけは簡単には消えない。
まるで涎の止められない犬のようだと思いながらも。
この無意味な代替行為を、ぼくは長いことやめることができなかった。

斑目 水緒
創峰大学に通う大学生。
いつも手や腕に包帯をしている。
異能:"一滴の愛"(ラスト・ギフト)
いつも手や腕に包帯をしている。
異能:"一滴の愛"(ラスト・ギフト)
***
今ならきっと、望むとおりに彼女を死なせることができる。
ぼくの血や骨や肉は、大学院を出る頃にはその域まで達していた。
その後、ぼくが毒を溜め込むことを黙認していた青斑教授が亡くなって、ぼくの管理は彼の縁者に移った。
後継者は教授とは方針が違ったようで、以降故意に毒を摂取することは禁止されて、色々な体液の成分検査も月に一度に増えた。
それからこの歳になるまでぼくは一人で生活しているけれど、青斑家はずっとぼくを管理している。今住んでいる部屋も彼らが手配したものだし、担当医も青斑の人間だ。
この先もずっと、恐らくは死んだ後も。
ぼくは一種の毒物として管理され続けるだろう。
別段それが幸せだとも、不幸せだとも思わない。そうであるべきだと思う。
でもどうしたって寂しくて、人恋しくなる時があって。
多分、ぼくが教授なんかやっているのは、学生達と関わりたいからだ。
近すぎない距離で、人と関わることができるからだ。
近すぎない距離。そのはずだったのに。
「……やっぱり、だめだなぁ。ぼく」



ENo.93 Eva とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.273 闇 とのやりとり
| ▲ |
| ||||||
| |||||
| |||||
ENo.520 チャコール とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
ENo.719 ケムルス とのやりとり
| ▲ |
| ||||||
以下の相手に送信しました



 |
タウラシアス 「今回は人間は食えねぇってよ。 もっがみーん、残念だったなー?」 |





対戦相手未発見のため不戦勝!
影響力が 9 増加!
影響力が 9 増加!



ぺちか(34) から 5 PS 受け取りました。
 |
ぺちか 「₍*°✇°*₎」 |
ぺちか(34) に 10 PS 送付しました。
百薬LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)
武術LV を 5 UP!(LV20⇒25、-5CP)
命術LV を 5 UP!(LV20⇒25、-5CP)
防具LV を 7 UP!(LV50⇒57、-7CP)
タウラシアス(173) により ItemNo.15 不思議な雫 から射程1の武器『暴れ馬の黒蹄』を作製してもらいました!
⇒ 暴れ馬の黒蹄/武器:強さ67/[効果1]水纏10 [効果2]- [効果3]-【射程1】
 |
タウラシアス 「しっかり骨まで砕いてから食えよ」 |
タウラシアス(173) の持つ ItemNo.16 牙 から防具『ケライノ』を作製しました!
ぺちか(34) により ItemNo.16 禁断じゃない果実 から料理『さくらのわたあめ』をつくってもらいました!
⇒ 美酒佳肴![ 2 1 6 = 9 ]成功!料理の付加効果のLVが増加!
⇒ さくらのわたあめ/料理:強さ28/[効果1]攻撃6 [効果2]防御6 [効果3]器用6
 |
ぺちか 「₍*°✇°*₎」 |
ノクターン を研究しました!(深度0⇒1)
ノクターン を研究しました!(深度1⇒2)
ノクターン を研究しました!(深度2⇒3)
☆フィアスファング を習得!
☆コンフィデンス を習得!
☆ヴァンピール を習得!
☆初習得ボーナス:各FPが6増加した!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





タウラシアス(173) に移動を委ねました。
カミセイ区 Q-1(山岳)に移動!(体調15⇒14)
カミセイ区 R-1(山岳)に移動!(体調14⇒13)
カミセイ区 R-2(山岳)に移動!(体調13⇒12)
カミセイ区 R-3(山岳)に移動!(体調12⇒11)
カミセイ区 S-3(山岳)に移動!(体調11⇒10)





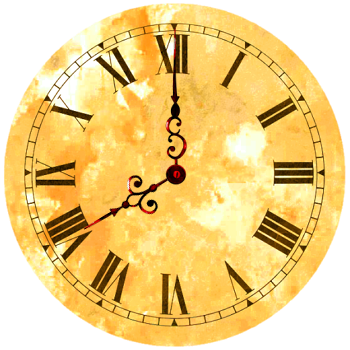
[787 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[347 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[301 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[75 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
―― Cross+Roseに映し出される。
ザザッ――
画面の情報が揺らぎ消えたかと思うと突然チャットが開かれ、
時計台の前にいるドライバーさんが映し出された。

ドライバーさん
次元タクシーの運転手。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。初老くらいに見える。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。初老くらいに見える。
 |
ドライバーさん 「・・・こんにちは皆さん。ハザマでの暮らしは充実していますか?」 |
 |
ドライバーさん 「私も今回の試合には大変愉しませていただいております。 こうして様子を見に来るくらいに・・・ですね。ありがとうございます。」 |
 |
ドライバーさん 「さて、皆さんに今後についてお伝えすることがございまして。 あとで驚かれてもと思い、参りました。」 |
 |
ドライバーさん 「まず、影響力の低い方々に向けて。 影響力が低い状態が続きますと、皆さんの形状に徐々に変化が現れます。」 |
 |
ドライバーさん 「ナレハテ――最初に皆さんが戦った相手ですね。 多くは最終的にはあのように、または別の形に変化する者もいるでしょう。」 |
 |
ドライバーさん 「そして試合に関しまして。 ある条件を満たすことで、決闘を避ける手段が一斉に失われます。避けている皆さんは、ご注意を。」 |
 |
ドライバーさん 「手短に、用件だけで申し訳ありませんが。皆さんに幸あらんことを――」 |
チャットが閉じられる――









ENo.502
藻噛 叢馬
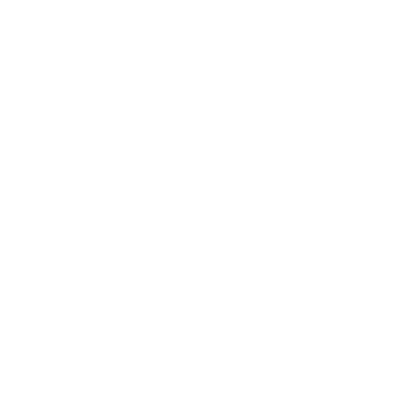
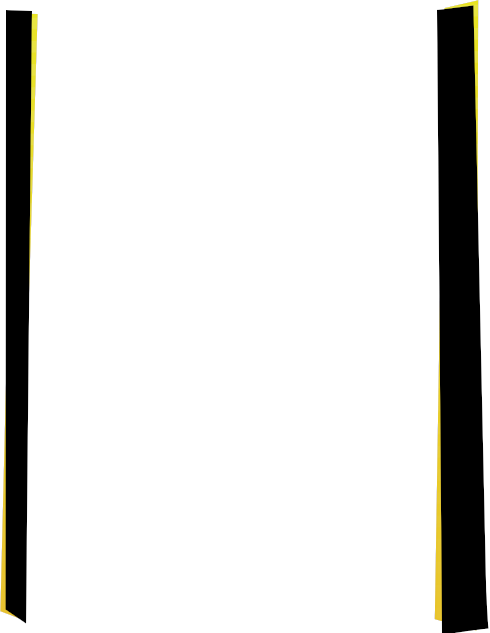
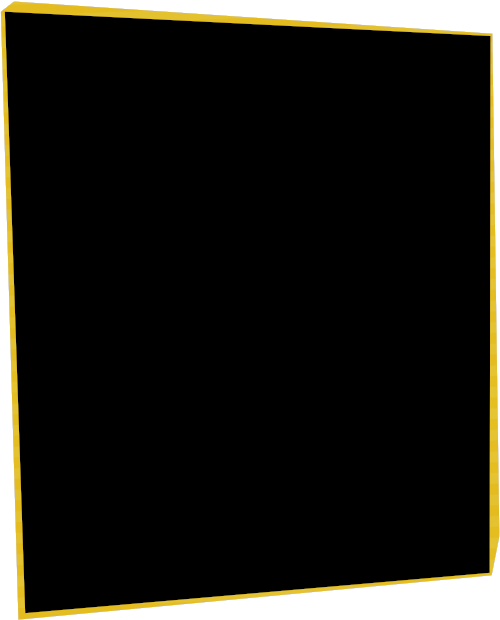
藻噛 叢馬(もがみ そうま)
一人称:俺
二人称:お前、君
25歳/身長190cm/体重85kg
創峰大学の院生。D1。
生物学専攻で、興味の対象は専ら海洋生物。斑目研究室に所属。
海の幻想譚や怪談に登場する生物に憧憬を抱いており、奇形や突然変異の海洋生物を蒐集している。研究に没頭して寝食を忘れがち。
大柄で表情に乏しいため周囲に威圧感を与えていることも儘あるようだが、本人はあまり気にしていない。
嫌いなものは馬肉とホルモン。
好きなものは上記以外の肉全般と酒(特にビールと麦焼酎)。
趣味は海水浴・潜水・遠泳。着衣水泳も難なくこなすが、真水・淡水では泳げない。
異能:"微睡む藻屑の幻想海"(ドリーミング・サルガッソー)
海水を粘度のある液体に変化させ、自在に操る。粘度はとろみがつく程度から人が上を歩ける程度まで調節可能。
ただし自分で水を発生させることはできず、かつ対象は海水でなければならないため、常に試験管に入れた海水を持ち歩いている。
『アンディの骨董屋』をよく訪れ、海で拾った漂着物を買い取ってもらったり荷運びを手伝ったりしている。
故あって懐事情はかなり寒い。
■ハザマでの姿
体高2m(耳の先までで約3m)/体重1t
海藻のように揺蕩う鬣を持ち、言葉巧みに人を海に引きずり込む蒼馬《アハ・イシュケ》。
長い腕の膂力で暴れ回る、赤く剥けたような肌の半人半馬《ナックラヴィー》。
人の噂が噂を呼び、死の海域と畏れられた美しい海《サルガッソー海》。
忘れ去られ、"否定"された海の怪異が寄り集まったばけもの。
それがこの怪物の正体である。
全身図︰http://file.gespenst.en-grey.com/mogami_hazama.png
■サブキャラ
斑目 水緒(まだらめ みずお)
一人称:ぼく
二人称:君、あなた
47歳/身長168cm/体重56kg
創峰大学第二学部海洋生物学専攻斑目研究室のゆるふわ教授。
異能:"一滴の愛"(ラスト・ギフト)
生物由来の毒が一切効かない異能。
「別に解毒ができるわけじゃないし、人の役には立たない」。
聞かれればそうとだけ答えるが、実際は取り込んだ毒素を体内に溜め込み続ける異能である。
溜め込むという特性故か体外に出る体液には微量な毒素しか含まれていないが、血液や骨、臓器そのものは猛毒を帯びている。
---
大曲 晴人(おおまが はるひと)
28歳/身長180cm/体重65kg
黒峰総研製薬部門営業部に所属する営業マン。
異能:"未観測運命理論・不在の黒猫"(シュレーディンガー・ブラックキャット)
詳細不明。
***
テストプレイの記憶を引き継いでいます。
テストプレイ時に交流のあった方にはそのように接しますが、不都合ありましたら連絡頂ければ訂正します。
現在プロフ絵2種。
ほぼほぼ置きレスですが交流歓迎です。お気軽にどうぞ!
■ログまとめプレイス『微睡む藻屑の幻想海』
http://lisge.com/ib/talk.php?p=757
■外部ログ置き場(テストプレイ時含)
http://niwatori.kuchinawa.com/dreaming_salgasso/index.html
■自重しないついった
@yaneura_coqua
一人称:俺
二人称:お前、君
25歳/身長190cm/体重85kg
創峰大学の院生。D1。
生物学専攻で、興味の対象は専ら海洋生物。斑目研究室に所属。
海の幻想譚や怪談に登場する生物に憧憬を抱いており、奇形や突然変異の海洋生物を蒐集している。研究に没頭して寝食を忘れがち。
大柄で表情に乏しいため周囲に威圧感を与えていることも儘あるようだが、本人はあまり気にしていない。
嫌いなものは馬肉とホルモン。
好きなものは上記以外の肉全般と酒(特にビールと麦焼酎)。
趣味は海水浴・潜水・遠泳。着衣水泳も難なくこなすが、真水・淡水では泳げない。
異能:"微睡む藻屑の幻想海"(ドリーミング・サルガッソー)
海水を粘度のある液体に変化させ、自在に操る。粘度はとろみがつく程度から人が上を歩ける程度まで調節可能。
ただし自分で水を発生させることはできず、かつ対象は海水でなければならないため、常に試験管に入れた海水を持ち歩いている。
『アンディの骨董屋』をよく訪れ、海で拾った漂着物を買い取ってもらったり荷運びを手伝ったりしている。
故あって懐事情はかなり寒い。
■ハザマでの姿
体高2m(耳の先までで約3m)/体重1t
海藻のように揺蕩う鬣を持ち、言葉巧みに人を海に引きずり込む蒼馬《アハ・イシュケ》。
長い腕の膂力で暴れ回る、赤く剥けたような肌の半人半馬《ナックラヴィー》。
人の噂が噂を呼び、死の海域と畏れられた美しい海《サルガッソー海》。
忘れ去られ、"否定"された海の怪異が寄り集まったばけもの。
それがこの怪物の正体である。
全身図︰http://file.gespenst.en-grey.com/mogami_hazama.png
■サブキャラ
斑目 水緒(まだらめ みずお)
一人称:ぼく
二人称:君、あなた
47歳/身長168cm/体重56kg
創峰大学第二学部海洋生物学専攻斑目研究室のゆるふわ教授。
異能:"一滴の愛"(ラスト・ギフト)
生物由来の毒が一切効かない異能。
「別に解毒ができるわけじゃないし、人の役には立たない」。
聞かれればそうとだけ答えるが、実際は取り込んだ毒素を体内に溜め込み続ける異能である。
溜め込むという特性故か体外に出る体液には微量な毒素しか含まれていないが、血液や骨、臓器そのものは猛毒を帯びている。
---
大曲 晴人(おおまが はるひと)
28歳/身長180cm/体重65kg
黒峰総研製薬部門営業部に所属する営業マン。
異能:"未観測運命理論・不在の黒猫"(シュレーディンガー・ブラックキャット)
詳細不明。
***
テストプレイの記憶を引き継いでいます。
テストプレイ時に交流のあった方にはそのように接しますが、不都合ありましたら連絡頂ければ訂正します。
現在プロフ絵2種。
ほぼほぼ置きレスですが交流歓迎です。お気軽にどうぞ!
■ログまとめプレイス『微睡む藻屑の幻想海』
http://lisge.com/ib/talk.php?p=757
■外部ログ置き場(テストプレイ時含)
http://niwatori.kuchinawa.com/dreaming_salgasso/index.html
■自重しないついった
@yaneura_coqua
10 / 30
668 PS
カミセイ区
S-3
S-3




















| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 駄物 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50) | |||
| 2 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 海棲馬の蹄 | 武器 | 30 | 攻撃10 | - | - | 【射程1】 |
| 5 | 幻想藻の鬣 | 防具 | 30 | 防御10 | - | - | |
| 6 | わたあめ | 料理 | 45 | 治癒13 | 充填13 | 増幅13 | |
| 7 | 駄石 | 素材 | 10 | [武器]体力10(LV20)[防具]防御10(LV20)[装飾]幸運10(LV20) | |||
| 8 | 桜 | 素材 | 25 | [武器]祝福20(LV30)[防具]反魅15(LV25)[装飾]舞護15(LV30) | |||
| 9 | 巻き込んだ石ころ | 魔晶 | 20 | 幸運10 | - | 充填6 | |
| 10 | 薄紫の花びら | 装飾 | 82 | 復活10 | 増勢10 | - | |
| 11 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
| 12 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
| 13 | 皮 | 素材 | 15 | [武器]闇纏15(LV30)[防具]反護15(LV30)[装飾]舞祝15(LV25) | |||
| 14 | 幻想藻の尾 | 防具 | 90 | 耐疫10 | - | - | |
| 15 | 暴れ馬の黒蹄 | 武器 | 67 | 水纏10 | - | - | 【射程1】 |
| 16 | さくらのわたあめ | 料理 | 28 | 攻撃6 | 防御6 | 器用6 | |
| 17 | 薔薇 | 素材 | 20 | [武器]獄炎15(LV30)[防具]舞魅20(LV30)[装飾]地纏20(LV40) | |||
| 18 | パンの耳 | 食材 | 10 | [効果1]体力10(LV10)[効果2]幸運10(LV20)[効果3]活力10(LV30) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 25 | 身体/武器/物理 |
| 命術 | 25 | 生命/復元/水 |
| 呪術 | 5 | 呪詛/邪気/闇 |
| 防具 | 57 | 防具作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 | |
| ウォーターフォール | 6 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |
| カース | 6 | 0 | 50 | 敵:闇撃&束縛 | |
| 決3 | クリエイト:タライ | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 |
| 決3 | ヒールポーション | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+猛毒減 |
| リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |
| フロウライフ | 5 | 0 | 80 | 自:MHP・DF増 | |
| ブラックバンド | 5 | 0 | 80 | 敵貫:闇撃&盲目 | |
| クリエイト:シールド | 5 | 2 | 200 | 自:DF増+守護 | |
| コンテイン | 5 | 0 | 50 | 敵列:精確攻撃&次与ダメ減 | |
| 決2 | ボロウライフ | 6 | 0 | 70 | 敵:闇撃&味傷:HP増 |
| アクアシェル | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+火耐性増 | |
| アクアリカバー | 5 | 0 | 80 | 味肉:HP増+肉体変調を守護化 | |
| ヘイルカード | 5 | 0 | 100 | 敵5:粗雑水領撃 | |
| クリエイト:スパイク | 5 | 0 | 60 | 敵貫:闇痛撃&衰弱 | |
| ポイズン | 5 | 0 | 80 | 敵:猛毒 | |
| デッドライン | 6 | 0 | 100 | 敵列:闇痛撃 | |
| 決1 | チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 |
| 決1 | アクアヒール | 6 | 0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 |
| アクアブランド | 6 | 1 | 50 | 敵:水痛撃&味傷:HP増 | |
| 決3 | イレイザー | 5 | 0 | 100 | 敵傷:攻撃 |
| チャクラグラント | 5 | 2 | 100 | 味傷3:精確水撃&HP増 | |
| ハードブレイク | 5 | 1 | 120 | 敵:攻撃 | |
| アイシクルランス | 6 | 0 | 150 | 敵:水痛撃&凍結 | |
| フィアスファング | 5 | 0 | 150 | 敵:攻撃&MHP減 | |
| コンフィデンス | 5 | 0 | 300 | 自:MSP・HL増 | |
| ヴァンピール | 5 | 0 | 150 | 敵:攻撃&魅了&自:HP増 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 異形の膂力 (猛攻) | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 怪物の体躯 (堅守) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 否定への憤怒 (攻勢) | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 肉体変調耐性 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:肉体変調耐性増 | |
| 召喚強化 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:具現LVが高いほど自身の召喚するNPCが強化 | |
| 幻想海・サルガッソー (五月雨) | 6 | 4 | 0 | 【スキル使用後】敵:3連水撃 | |
| 水の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:命術LVが高いほど水特性・耐性増 | |
| 精神力 | 5 | 4 | 0 | 【被攻撃命中後】自:SP増+SP10%以下なら復活LV増 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
夢喰花 (ドレイン) |
0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| 決2 |
≪s@4dw≫ (ダークネス) |
0 | 100 | 敵列:闇撃&盲目 |
| 決2 |
塩弾 (ストーンブラスト) |
0 | 50 | 敵:地撃&朦朧 |
|
大咆哮 (ブレイブハート) |
0 | 100 | 味:AT・DX増(3T)+精神変調を祝福化 | |
|
冥境止水 (ノーマライズ) |
0 | 80 | 味環:HP増+環境変調を守護化 | |
|
もっと深い海 (サモン:ビーフ) |
0 | 100 | 敵:連続減+アイテム「ビーフ」をドロップするようになる(遭遇戦・採集のみ) |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]ノクターン | [ 3 ]ノーマライズ | [ 3 ]リザレクション |
| [ 3 ]ヒーリングソング | [ 3 ]ファーマシー | [ 3 ]ブレッシングレイン |
| [ 3 ]マナポーション | [ 3 ]ナース |

PL / こか