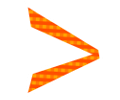<< 6:00~7:00




赤い空、ひび割れたアスファルトの上に張られた無数のテント、露店商が道行く客を呼び込んでいる。
周囲を壁に囲まれた空間…ハザマには違いないが、ハザマでもまだ健全な空気がある場所、それがこのキャンプ地である。
ここには襲い掛かってくる生物もいないし、アンジニティ側の人間もいないため、しっかりと休息が取れる安全地帯だ。
ハザマに来るのはイバラシティの時間で10日に1回、1時間程度。
そうしてハザマに来ている間、本来のイバラシティではほとんど時間経過がない。
逆にハザマでは以前呼び出された時の続きからとなる…ゲームでセーブデータを読み込んでから再開するというのはこんな感じなのかもしれない。
また、イバラシティではハザマでのことを思い出すことはないが、ハザマではイバラシティでの出来事も含めたすべての記憶がある。
最初は混乱して、周囲を警戒せねばならず、生き抜くことに精一杯だったから落ち着いて情報を精査していなかった…というのは怠慢だ。
もっと早くそれに気付いていれば、ここで連れの少女があんなに憔悴することもなかったろうに。
チラリと隣のテントに視線を送るが、少女が起きた気配はない。
森での敗走が響いているのだろう…無理もない話だ。
視線を戻すと、赤いトカゲにも似たフォルムの生き物が周囲の生き物と戯れていた。
「マーレ、あんまり遠くに行くなよ」
「キュイ!」
ミランが一声かければエイドであるベビードラゴンから元気な返事が返ってくる。
テントの入り口で周囲の様子を眺めている間に飛び出していった彼女(多分)は随分と好奇心旺盛らしい。
他所のエイドに挨拶して回っては楽しそうに声を上げ、時折思い出したようにこちらの姿を探しては戻ってくる。
他のエイドの主らしい人と目礼を交わし、戻ってきたマーレの喉をくすぐるように撫でてやればぐるぐると目を細めて喉を鳴らした。
「よし、マーレ。ちょっとこっちに来な。手を見せて…そう。怪我はないな?」
抱き上げれば、人間の乳児くらいの重さだろうか…結構しっかりとした重量を感じる。
先の練習試合で泣いてリタイアしたので一応のチェックはしたが、念のためもう一度確認することにした。
不安にさせないように一つ一つの動作に声をかけ、何を見るのかを伝えればマーレは素直に従ってくれるので、随分頭がいい。
あるいは、親にもそうやって健康チェックをされていたのかもしれない。
「…鱗の剥がれや欠けはないな。よし…マーレ、牙も見よう。口開けてみな?あーんてして?」
「キュアー?」
首を傾げながら口を開けて見せるさまはなかなか可愛らしいが、ずらりと並ぶ牙は小さいながらなかなかの迫力だ。
口の中は血色もよく、牙がぐらついてる様子もない。
爬虫類の口の中をまじまじ見たことはないが、口内炎や歯槽膿漏のような症状も見られないから多分健康だと思う。
「よし、いい子だマーレ!お利口さんだな!」
「キュイ!キュイ!」
「ぎゃ゙~あ゙?」
「お、館長起きたのかい?」
マーレを撫で回して褒めていると、よちよちとした歩みでアデリーペンギンが近付いてくる。
森なんかの足場が悪い場所では当ペンギン的には不本意ながらミランに抱えられて移動していたためか、比較的元気そうだ。
一応館長にも異常がないか改めてチェックし、足の爪や足裏に割れや傷がないのを確認する。
「館長も口開けられるかな…館長、マーレみたいにできるか?マーレ、さっきのお手本見せたげて」
「キュア~~~ア!」
「ぎゅ゙あ゙あ゙あ゙あ゙あ゙!」
「うわ口怖っ!!」
隣のベビードラゴンに倣って口を開けてくれたはいいが、ペンギンの口の中は見た目だけならドラゴンより凶悪だった。
上顎と舌には喉の奥に向かってギザギザした返し状の突起がびっしり並んでいるのである。
本来ペンギンとは海中で生きた魚などを捉える生態を持つので、捉えた魚が容易に逃げられないように、また飲み込みやすいようにと進化していった結果なのだろう。
絶対食う!という生存への強い意志を感じる。
ドラゴン以上に健康状態が分からないが、血色はいいと思うので多分大丈夫だろう…多分。
館長の口を閉じさせて嘴の下を撫でていると、ふと影が差した。
「ミランさん」
声をかけて来たのは、隣のテントで休んでいた少女だ。
ミランはテントの入り口に腰を下ろし、外に足を投げ出すような形で座っているので、いつもとは逆に少女を見上げる体勢である。
「サツキちゃん、ちょっとは休めた?」
「はい、お陰様で」
そう言って笑う顔はここに戻ってきた時より大分マシになっており、ミランもほっと安堵の息を吐く。
「そっか、よかった」
とはいえ、蓄積された疲労がそう簡単に抜けるわけでもない。
なんの訓練の受けていない一般人であり、学生であった彼女ならば、なおさら。
「丁度よかった、今健康チェックしててね…サツキちゃん、ちょっと手を出して」
「? はい」
差し出した手に、素直に細くたおやかな手が乗せられる。
寝起きだろうに少しひやりとしたその手の爪は白い。
「ちょっと脈計るよ」
「え、あ…はい」
親指で細い手首を探り、筋と骨の間の脈を探し出す。
トッ…トッ…と規則正しく打つ脈拍は正常の範囲内だが、やはり少しばかり体温が低い気がする。
「ん。脈は大丈夫だね。何か体調に異常はない?火傷が残ってるとか、痺れがあるとかは?」
「大丈夫です。ミランさんのお蔭で、すっかり」
「そう?ならいいんだけど」
細い手を解放しながら、少女を見上げる。
ハザマでは異能の力は強くなるらしい。
日常生活では使ったこともないような強力な異能スキルを戦闘に使うというのは、体力的にも精神的にもしんどいものだ。
ミランのように軍属経験があって、それこそ戦闘に特化した異能を見た経験があればまた別だが、少女の場合は自分や対戦相手のスキルでしか経験がないはずで。
心配事に加えて、そういった情報の錯綜が彼女を追い詰めているのは明らかだ。
ひやりとした指先が示すものに、ミランは内心で溜息を吐く。
守り、生きることを最優先事項としたため、自分が最前線で防御と回復を担ったことに後悔はない。
ただ、できることなら攻撃も自分が受け持てたならよかった。
先の敗走に彼女が責任を感じる必要がなく、前を向いていられるくらい、自分に力があればよかった。
それが傲慢な願いだということも自覚してはいるけれど…
「サツキちゃん、情報を整理してて気付いたことがあるから、聞いてくれる?」
「はい!」
今から自分が話すことが、少しでも彼女の心を軽くできればいい。
その憂いを晴らす切欠になればいい。
そうしてもう少しだけ、彼女が休める時間を取れたら…
そんな風に願わずにはいられなかった。
時間の流れに容赦はなく、けれど今はまだ立ち止まる。
次へ進むために。



ENo.296 枢木 とのやりとり




ItemNo.12 BANKAの美味果実デザート を食べました!
体調が 0 回復!(30⇒30)
今回の全戦闘において 攻撃10 防御10 強靭15 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!











六角形の柱から天に向け、赤色の光柱が立つ。
どうやら次元タクシーで行けるようになったようだ。



ぺんぎん(1397) から 駄物 を受け取りました。
ぺんぎん(1397) から 何か柔らかい物体 を受け取りました。
ぺんぎん(1397) から ビーフ を受け取りました。
お魚(50 PS)を購入しました。
お魚(50 PS)を購入しました。
駄石(50 PS)を購入しました。
使役LV を 10 DOWN。(LV10⇒0、+10CP、-10FP)
具現LV を 15 UP!(LV0⇒15、-15CP)
料理LV を 5 UP!(LV50⇒55、-5CP)
ぺんぎん(1397) により ItemNo.2 不思議な防具 に ItemNo.11 花びら を合成してもらい、駄物 に変化させました!
⇒ 駄物/素材:強さ10/[武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50)/特殊アイテム
アキラ(812) の持つ ItemNo.12 美味しい草 から料理『山菜BANKAラーメン』をつくりました!
ItemNo.9 美味しい果実 から料理『BANKAの美味果実デザート』をつくりました!
⇒ BANKAの美味果実デザート/料理:強さ97/[効果1]攻撃10 [効果2]防御10 [効果3]強靭15
ぺんぎん(1397) の持つ ItemNo.18 パンの耳 から料理『BANKAの賄い揚げパン』をつくりました!
ぺんぎん(1397) により ItemNo.1 シャツチェスター に ItemNo.14 韮 を付加してもらいました!
⇒ シャツチェスター/防具:強さ60/[効果1]活力10 [効果2]体力10 [効果3]-/特殊アイテム
オニキス(301) とカードを交換しました!
Onyx (デスグラスプ)

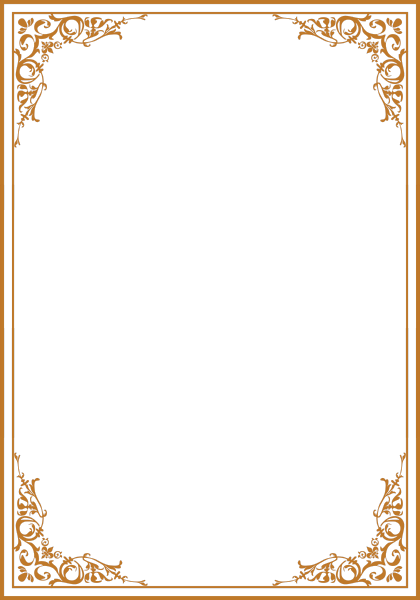
アクアヒール を研究しました!(深度0⇒1)
アクアヒール を研究しました!(深度1⇒2)
アクアヒール を研究しました!(深度2⇒3)
クリエイト:タライ を習得!
アクアシェル を習得!
クリエイト:ヴェノム を習得!
クリエイト:メガネ を習得!
召喚強化 を習得!
五月雨 を習得!
サモン:スライム を習得!
修復 を習得!
サモン:サーヴァント を習得!
サモン:ウンディーネ を習得!
クリエイト:バンデージ を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



ぺんぎん(1397) は 毛 を入手!
ぺんぎん(1397) は 何かの骨 を入手!
サツキ(1396) は ビーフ を入手!
サツキ(1396) は 毛 を入手!
サツキ(1396) は 毒牙 を入手!
サツキ(1396) は 毒牙 を入手!
ミラン(1395) は 毒牙 を入手!



特に移動せずその場に留まることにしました。
体調が全回復しました!
『チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》』へ採集に向かうことにしました!
- ミラン(1395) の選択は チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
MISSION!!
チナミ区 O-16:梅楽園 を選択!
- ミラン(1395) の選択は チナミ区 O-16:梅楽園





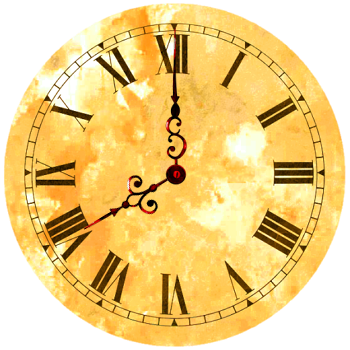
[787 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[347 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[301 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[75 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
―― Cross+Roseに映し出される。
ザザッ――
画面の情報が揺らぎ消えたかと思うと突然チャットが開かれ、
時計台の前にいるドライバーさんが映し出された。

チャットが閉じられる――












梅林にはほんのりと良い香りが漂う。
その景色は美しく見えるが、同時に異様にも映る。
園内を進んでいくと、周囲の梅の木がざわめく・・・

木が不自然に捻れ、音を立てる。
ボコッと地面から根が飛び出し、木が"歩き"はじめる・・・






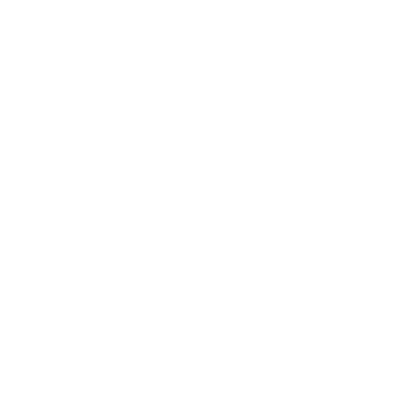
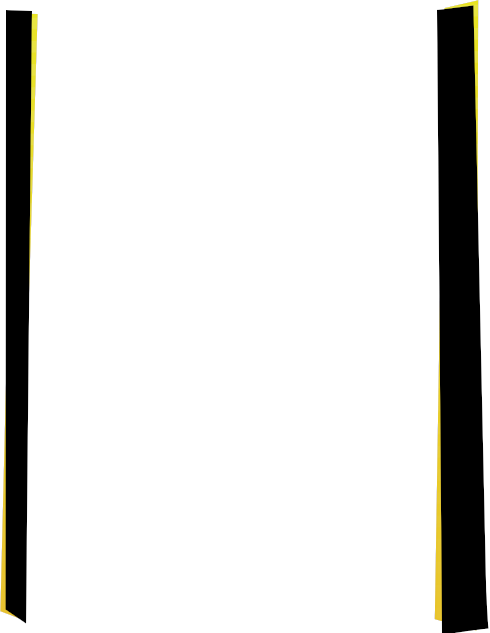
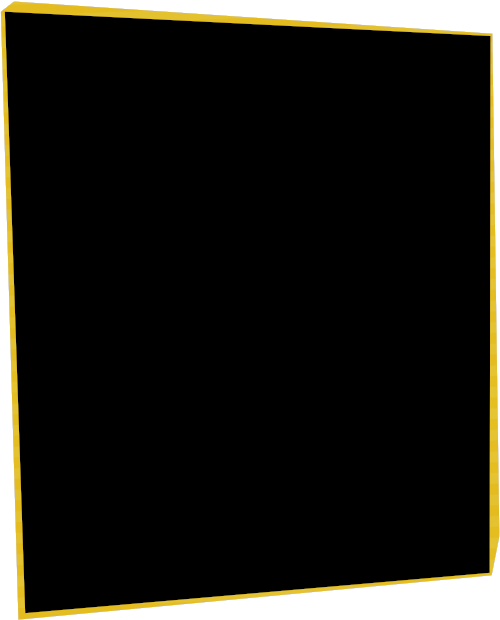





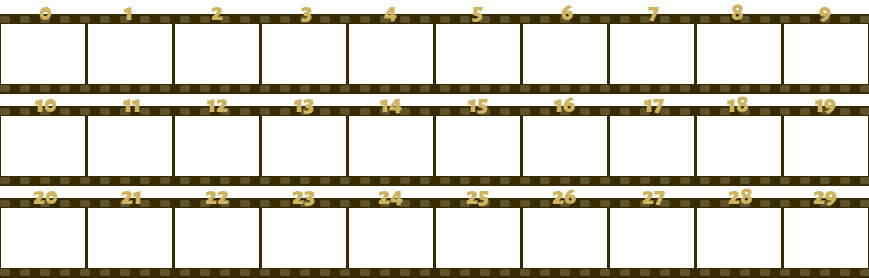


































No.1 マーレ (種族:ベビードラゴン)






異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [戦闘:エイド1]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



赤い空、ひび割れたアスファルトの上に張られた無数のテント、露店商が道行く客を呼び込んでいる。
周囲を壁に囲まれた空間…ハザマには違いないが、ハザマでもまだ健全な空気がある場所、それがこのキャンプ地である。
ここには襲い掛かってくる生物もいないし、アンジニティ側の人間もいないため、しっかりと休息が取れる安全地帯だ。
ハザマに来るのはイバラシティの時間で10日に1回、1時間程度。
そうしてハザマに来ている間、本来のイバラシティではほとんど時間経過がない。
逆にハザマでは以前呼び出された時の続きからとなる…ゲームでセーブデータを読み込んでから再開するというのはこんな感じなのかもしれない。
また、イバラシティではハザマでのことを思い出すことはないが、ハザマではイバラシティでの出来事も含めたすべての記憶がある。
最初は混乱して、周囲を警戒せねばならず、生き抜くことに精一杯だったから落ち着いて情報を精査していなかった…というのは怠慢だ。
もっと早くそれに気付いていれば、ここで連れの少女があんなに憔悴することもなかったろうに。
チラリと隣のテントに視線を送るが、少女が起きた気配はない。
森での敗走が響いているのだろう…無理もない話だ。
視線を戻すと、赤いトカゲにも似たフォルムの生き物が周囲の生き物と戯れていた。
「マーレ、あんまり遠くに行くなよ」
「キュイ!」
ミランが一声かければエイドであるベビードラゴンから元気な返事が返ってくる。
テントの入り口で周囲の様子を眺めている間に飛び出していった彼女(多分)は随分と好奇心旺盛らしい。
他所のエイドに挨拶して回っては楽しそうに声を上げ、時折思い出したようにこちらの姿を探しては戻ってくる。
他のエイドの主らしい人と目礼を交わし、戻ってきたマーレの喉をくすぐるように撫でてやればぐるぐると目を細めて喉を鳴らした。
「よし、マーレ。ちょっとこっちに来な。手を見せて…そう。怪我はないな?」
抱き上げれば、人間の乳児くらいの重さだろうか…結構しっかりとした重量を感じる。
先の練習試合で泣いてリタイアしたので一応のチェックはしたが、念のためもう一度確認することにした。
不安にさせないように一つ一つの動作に声をかけ、何を見るのかを伝えればマーレは素直に従ってくれるので、随分頭がいい。
あるいは、親にもそうやって健康チェックをされていたのかもしれない。
「…鱗の剥がれや欠けはないな。よし…マーレ、牙も見よう。口開けてみな?あーんてして?」
「キュアー?」
首を傾げながら口を開けて見せるさまはなかなか可愛らしいが、ずらりと並ぶ牙は小さいながらなかなかの迫力だ。
口の中は血色もよく、牙がぐらついてる様子もない。
爬虫類の口の中をまじまじ見たことはないが、口内炎や歯槽膿漏のような症状も見られないから多分健康だと思う。
「よし、いい子だマーレ!お利口さんだな!」
「キュイ!キュイ!」
「ぎゃ゙~あ゙?」
「お、館長起きたのかい?」
マーレを撫で回して褒めていると、よちよちとした歩みでアデリーペンギンが近付いてくる。
森なんかの足場が悪い場所では当ペンギン的には不本意ながらミランに抱えられて移動していたためか、比較的元気そうだ。
一応館長にも異常がないか改めてチェックし、足の爪や足裏に割れや傷がないのを確認する。
「館長も口開けられるかな…館長、マーレみたいにできるか?マーレ、さっきのお手本見せたげて」
「キュア~~~ア!」
「ぎゅ゙あ゙あ゙あ゙あ゙あ゙!」
「うわ口怖っ!!」
隣のベビードラゴンに倣って口を開けてくれたはいいが、ペンギンの口の中は見た目だけならドラゴンより凶悪だった。
上顎と舌には喉の奥に向かってギザギザした返し状の突起がびっしり並んでいるのである。
本来ペンギンとは海中で生きた魚などを捉える生態を持つので、捉えた魚が容易に逃げられないように、また飲み込みやすいようにと進化していった結果なのだろう。
絶対食う!という生存への強い意志を感じる。
ドラゴン以上に健康状態が分からないが、血色はいいと思うので多分大丈夫だろう…多分。
館長の口を閉じさせて嘴の下を撫でていると、ふと影が差した。
「ミランさん」
声をかけて来たのは、隣のテントで休んでいた少女だ。
ミランはテントの入り口に腰を下ろし、外に足を投げ出すような形で座っているので、いつもとは逆に少女を見上げる体勢である。
「サツキちゃん、ちょっとは休めた?」
「はい、お陰様で」
そう言って笑う顔はここに戻ってきた時より大分マシになっており、ミランもほっと安堵の息を吐く。
「そっか、よかった」
とはいえ、蓄積された疲労がそう簡単に抜けるわけでもない。
なんの訓練の受けていない一般人であり、学生であった彼女ならば、なおさら。
「丁度よかった、今健康チェックしててね…サツキちゃん、ちょっと手を出して」
「? はい」
差し出した手に、素直に細くたおやかな手が乗せられる。
寝起きだろうに少しひやりとしたその手の爪は白い。
「ちょっと脈計るよ」
「え、あ…はい」
親指で細い手首を探り、筋と骨の間の脈を探し出す。
トッ…トッ…と規則正しく打つ脈拍は正常の範囲内だが、やはり少しばかり体温が低い気がする。
「ん。脈は大丈夫だね。何か体調に異常はない?火傷が残ってるとか、痺れがあるとかは?」
「大丈夫です。ミランさんのお蔭で、すっかり」
「そう?ならいいんだけど」
細い手を解放しながら、少女を見上げる。
ハザマでは異能の力は強くなるらしい。
日常生活では使ったこともないような強力な異能スキルを戦闘に使うというのは、体力的にも精神的にもしんどいものだ。
ミランのように軍属経験があって、それこそ戦闘に特化した異能を見た経験があればまた別だが、少女の場合は自分や対戦相手のスキルでしか経験がないはずで。
心配事に加えて、そういった情報の錯綜が彼女を追い詰めているのは明らかだ。
ひやりとした指先が示すものに、ミランは内心で溜息を吐く。
守り、生きることを最優先事項としたため、自分が最前線で防御と回復を担ったことに後悔はない。
ただ、できることなら攻撃も自分が受け持てたならよかった。
先の敗走に彼女が責任を感じる必要がなく、前を向いていられるくらい、自分に力があればよかった。
それが傲慢な願いだということも自覚してはいるけれど…
「サツキちゃん、情報を整理してて気付いたことがあるから、聞いてくれる?」
「はい!」
今から自分が話すことが、少しでも彼女の心を軽くできればいい。
その憂いを晴らす切欠になればいい。
そうしてもう少しだけ、彼女が休める時間を取れたら…
そんな風に願わずにはいられなかった。
時間の流れに容赦はなく、けれど今はまだ立ち止まる。
次へ進むために。



ENo.296 枢木 とのやりとり
| ▲ |
| ||



 |
ミラン 「サツキちゃん、館長、ここでは買い物もできるみたいだから、食料確保しておこうか」 |
 |
ぺんぎん 「ぎゃ¨ー」 ミランから貰ったボロ布を銜えて遊んでいる。妖怪床擦りおばけ。 |
ItemNo.12 BANKAの美味果実デザート を食べました!
 |
ミラン 「うん、なかなか悪くないな」 |
今回の全戦闘において 攻撃10 防御10 強靭15 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!







カミセイ区 H-4:チェックポイント《森の学舎》
店主とJKと館長
|
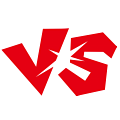 |
立ちはだかるもの
|



カミセイ区 H-4:チェックポイント《森の学舎》
守護者の姿が消え去った――六角形の柱から天に向け、赤色の光柱が立つ。
どうやら次元タクシーで行けるようになったようだ。



ぺんぎん(1397) から 駄物 を受け取りました。
 |
白猫便見参。手始めに駄物を差し出す。 |
ぺんぎん(1397) から 何か柔らかい物体 を受け取りました。
 |
何か柔らかい物体を差し出す。 |
ぺんぎん(1397) から ビーフ を受け取りました。
 |
クハシャ (とどめのビーフを出し終え、視線を合わす) 「次は我にも馳走を」 |
お魚(50 PS)を購入しました。
お魚(50 PS)を購入しました。
駄石(50 PS)を購入しました。
使役LV を 10 DOWN。(LV10⇒0、+10CP、-10FP)
具現LV を 15 UP!(LV0⇒15、-15CP)
料理LV を 5 UP!(LV50⇒55、-5CP)
ぺんぎん(1397) により ItemNo.2 不思議な防具 に ItemNo.11 花びら を合成してもらい、駄物 に変化させました!
⇒ 駄物/素材:強さ10/[武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50)/特殊アイテム
 |
ぺんぎん 「ぎゃ¨ー」 |
アキラ(812) の持つ ItemNo.12 美味しい草 から料理『山菜BANKAラーメン』をつくりました!
ItemNo.9 美味しい果実 から料理『BANKAの美味果実デザート』をつくりました!
⇒ BANKAの美味果実デザート/料理:強さ97/[効果1]攻撃10 [効果2]防御10 [効果3]強靭15
 |
店長 「夏場はアイスくらいメニューに入れててもいいかなぁ…」 |
ぺんぎん(1397) の持つ ItemNo.18 パンの耳 から料理『BANKAの賄い揚げパン』をつくりました!
ぺんぎん(1397) により ItemNo.1 シャツチェスター に ItemNo.14 韮 を付加してもらいました!
⇒ シャツチェスター/防具:強さ60/[効果1]活力10 [効果2]体力10 [効果3]-/特殊アイテム
 |
シャツチェスターに韮を近づけた。韮は啓示を示した。 レ…バ…ニ…ラ 韮、シャツチェスターに浮かんだ文字共々、光となって消えた。Jesus...✟ |
オニキス(301) とカードを交換しました!
Onyx (デスグラスプ)

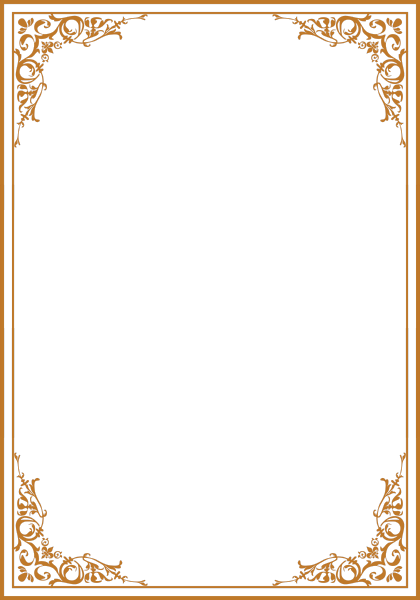
アクアヒール を研究しました!(深度0⇒1)
アクアヒール を研究しました!(深度1⇒2)
アクアヒール を研究しました!(深度2⇒3)
クリエイト:タライ を習得!
アクアシェル を習得!
クリエイト:ヴェノム を習得!
クリエイト:メガネ を習得!
召喚強化 を習得!
五月雨 を習得!
サモン:スライム を習得!
修復 を習得!
サモン:サーヴァント を習得!
サモン:ウンディーネ を習得!
クリエイト:バンデージ を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



ぺんぎん(1397) は 毛 を入手!
ぺんぎん(1397) は 何かの骨 を入手!
サツキ(1396) は ビーフ を入手!
サツキ(1396) は 毛 を入手!
サツキ(1396) は 毒牙 を入手!
サツキ(1396) は 毒牙 を入手!
ミラン(1395) は 毒牙 を入手!



特に移動せずその場に留まることにしました。
体調が全回復しました!
『チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》』へ採集に向かうことにしました!
- ミラン(1395) の選択は チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
MISSION!!
チナミ区 O-16:梅楽園 を選択!
- ミラン(1395) の選択は チナミ区 O-16:梅楽園





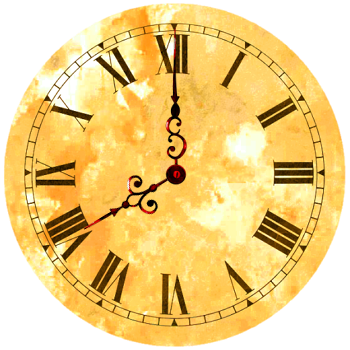
[787 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[347 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[301 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[75 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
―― Cross+Roseに映し出される。
ザザッ――
画面の情報が揺らぎ消えたかと思うと突然チャットが開かれ、
時計台の前にいるドライバーさんが映し出された。

ドライバーさん
次元タクシーの運転手。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。初老くらいに見える。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。初老くらいに見える。
 |
ドライバーさん 「・・・こんにちは皆さん。ハザマでの暮らしは充実していますか?」 |
 |
ドライバーさん 「私も今回の試合には大変愉しませていただいております。 こうして様子を見に来るくらいに・・・ですね。ありがとうございます。」 |
 |
ドライバーさん 「さて、皆さんに今後についてお伝えすることがございまして。 あとで驚かれてもと思い、参りました。」 |
 |
ドライバーさん 「まず、影響力の低い方々に向けて。 影響力が低い状態が続きますと、皆さんの形状に徐々に変化が現れます。」 |
 |
ドライバーさん 「ナレハテ――最初に皆さんが戦った相手ですね。 多くは最終的にはあのように、または別の形に変化する者もいるでしょう。」 |
 |
ドライバーさん 「そして試合に関しまして。 ある条件を満たすことで、決闘を避ける手段が一斉に失われます。避けている皆さんは、ご注意を。」 |
 |
ドライバーさん 「手短に、用件だけで申し訳ありませんが。皆さんに幸あらんことを――」 |
チャットが閉じられる――











チナミ区 O-16 周辺
梅楽園
ハザマのなか、咲き乱れる梅の木たち。梅楽園
梅林にはほんのりと良い香りが漂う。
その景色は美しく見えるが、同時に異様にも映る。
園内を進んでいくと、周囲の梅の木がざわめく・・・

動く梅木
地を砕き歩く梅の木。
美しく咲いては散ってゆく花々。
美しく咲いては散ってゆく花々。
 |
動く梅木 「(ギギギ・・・・・ギギ・・・ッ)」 |
木が不自然に捻れ、音を立てる。
ボコッと地面から根が飛び出し、木が"歩き"はじめる・・・





ENo.1395
ミラン・オルランディーニ
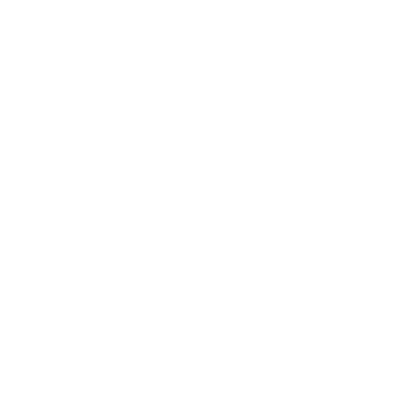
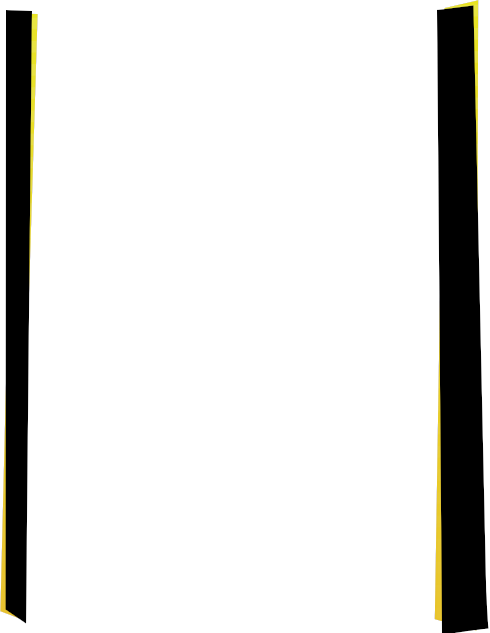
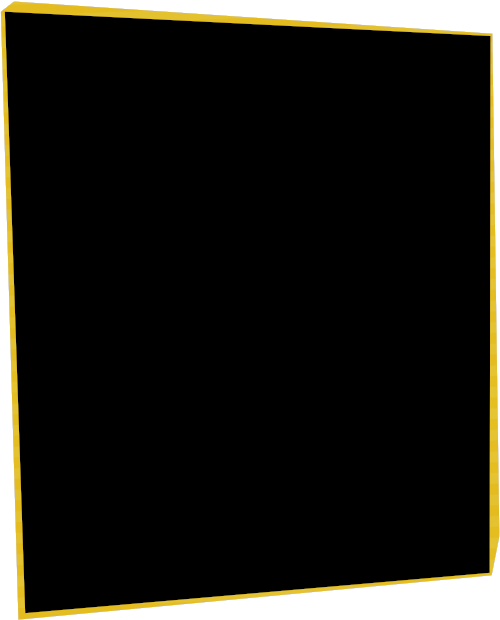
ミラン・オルランディーニ
190cm/128㎏/30歳
『麺屋 BANKA』を営むラーメン屋の店長。
ちょっと厳つい外見だが世話焼きで気のいいおっさんである。
口元の傷痕は子供の頃に実家の羊から尻に頭突きを食らって転倒した際にできたもの。
そのことを問われれば、少しばかりの哀愁をにじませて、
「俺は奴に背を向け、奴はその隙を突いた…それだけさ…」
とか意味深なことを言うが、特にこれといったドラマはない。
あくまで羊に尻をカチ上げられただけである。
なお、出身はイバラシティのある島ではなく別の島。
ティーンの頃に観光で訪れたイバラシティのラーメンに惚れ込み、その後移住して修行すること10年、自分の店を持つに至った。
サッカー観戦が好きで、店にはちょっぴり大きめのモニタが設置されており、大抵サッカーが映っている。
深夜にワールドワイドな試合があった翌日とかめっちゃ眠そうにラーメン作ってる時があるが、クオリティは下がったりしないのでご安心いただきたい。
アルバイトのサツキちゃん(Eno.1396)を看板娘に、散歩がてら訪れる館長とその保護者(Eno.1397)を常連客に持ち、そこそこの賑わいを見せる店内で今日も店長の天空下ろしは湯を切っている。
ちなみに店名のBANKAとは蕃茄…トマトのことである。
異能:手の中の火種【Tipi di fuoco nelle mani】
ちょっとした熱を操る力。
ごく燃えやすいものへの着火の他、ふきこぼれる鍋の火を弱める程度の能力。
日常生活やサバイバル方面では多少役立つものの、戦闘では全く役に立たない。
190cm/128㎏/30歳
『麺屋 BANKA』を営むラーメン屋の店長。
ちょっと厳つい外見だが世話焼きで気のいいおっさんである。
口元の傷痕は子供の頃に実家の羊から尻に頭突きを食らって転倒した際にできたもの。
そのことを問われれば、少しばかりの哀愁をにじませて、
「俺は奴に背を向け、奴はその隙を突いた…それだけさ…」
とか意味深なことを言うが、特にこれといったドラマはない。
あくまで羊に尻をカチ上げられただけである。
なお、出身はイバラシティのある島ではなく別の島。
ティーンの頃に観光で訪れたイバラシティのラーメンに惚れ込み、その後移住して修行すること10年、自分の店を持つに至った。
サッカー観戦が好きで、店にはちょっぴり大きめのモニタが設置されており、大抵サッカーが映っている。
深夜にワールドワイドな試合があった翌日とかめっちゃ眠そうにラーメン作ってる時があるが、クオリティは下がったりしないのでご安心いただきたい。
アルバイトのサツキちゃん(Eno.1396)を看板娘に、散歩がてら訪れる館長とその保護者(Eno.1397)を常連客に持ち、そこそこの賑わいを見せる店内で今日も店長の天空下ろしは湯を切っている。
ちなみに店名のBANKAとは蕃茄…トマトのことである。
異能:手の中の火種【Tipi di fuoco nelle mani】
ちょっとした熱を操る力。
ごく燃えやすいものへの着火の他、ふきこぼれる鍋の火を弱める程度の能力。
日常生活やサバイバル方面では多少役立つものの、戦闘では全く役に立たない。
30 / 30
439 PS
チナミ区
D-2
D-2




































No.1 マーレ (種族:ベビードラゴン)
 |
|
(ついて)来ちゃった☆ レッドドラゴンの幼体。 まだコロンコロンしている。 親の居ぬ間に巣から離れて迷子になっていたが、ひょんなことからミランを同族と勘違いしてくっついて来てしまった。 好奇心旺盛な女の子。 |
||||||||||||||||
| 被研究 | スキル名 | LV | EP | SP | 説明 |
| マジックミサイル | 5 | 0 | 70 | 敵:精確火領撃 | |
| ファイアレイド | 5 | 0 | 110 | 敵列:炎上 | |
| ティンダー | 5 | 0 | 50 | 敵:火撃&炎上 | |
| 血気 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:現在HP割合が低いほど攻撃ダメージ増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 火の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:魔術LVが高いほど火特性・耐性増 | |
| 環境変調特性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:環境変調特性増 | |
| 炎上耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:炎上耐性増 |
最大EP[20]



| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | シャツチェスター | 防具 | 60 | 活力10 | 体力10 | - | |
| 2 | 駄物 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50) | |||
| 3 | 山査子 | 素材 | 15 | [武器]防疫15(LV30)[防具]耐疫10(LV20)[装飾]快癒10(LV25) | |||
| 4 | 牙のお守り | 装飾 | 40 | 体力10 | 回復10 | - | |
| 5 | サバイバルナイフ | 武器 | 40 | 回復10 | - | - | 【射程1】 |
| 6 | 何か柔らかい物体 | 素材 | 10 | [武器]治癒10(LV20)[防具]命脈10(LV25)[装飾]防御10(LV20) | |||
| 7 | 白石 | 素材 | 15 | [武器]祝福10(LV10)[防具]反祝10(LV10)[装飾]舞祝10(LV10) | |||
| 8 | チェスターコート | 防具 | 40 | 体力10 | - | - | |
| 9 | BANKAの美味果実デザート | 料理 | 97 | 攻撃10 | 防御10 | 強靭15 | |
| 10 | フォールディングナイフ | 武器 | 90 | 回復10 | - | - | 【射程1】 |
| 11 | 毒牙 | 素材 | 20 | [武器]猛毒15(LV30)[防具]反毒15(LV30)[装飾]耐疫15(LV25) | |||
| 12 | 駄物 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50) | |||
| 13 | 毛皮 | 素材 | 15 | [武器]道連10(LV20)[防具]鎮痛10(LV30)[装飾]耐災10(LV25) | |||
| 14 | |||||||
| 15 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
| 16 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
| 17 | 防刃インナー | 防具 | 82 | 反護15 | - | - | |
| 18 | 何か柔らかい物体 | 素材 | 10 | [武器]治癒10(LV20)[防具]命脈10(LV25)[装飾]防御10(LV20) | |||
| 19 | ビーフ | 食材 | 5 | [効果1]活力5(LV30)[効果2]体力5(LV30)[効果3]防御5(LV30) | |||
| 20 | お魚 | 食材 | 10 | [効果1]活力10(LV15)[効果2]敏捷10(LV25)[効果3]強靭10(LV35) | |||
| 21 | お魚 | 食材 | 10 | [効果1]活力10(LV15)[効果2]敏捷10(LV25)[効果3]強靭10(LV35) | |||
| 22 | 駄石 | 素材 | 10 | [武器]体力10(LV20)[防具]防御10(LV20)[装飾]幸運10(LV20) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 命術 | 15 | 生命/復元/水 |
| 具現 | 15 | 創造/召喚 |
| 百薬 | 15 | 化学/病毒/医術 |
| 解析 | 10 | 精確/対策/装置 |
| 料理 | 55 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 6 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ウォーターフォール | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |
| クリエイト:タライ | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |
| サステイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:守護 | |
| 練3 | ヒールポーション | 6 | 0 | 50 | 味傷:HP増+猛毒減 |
| プリディクション | 5 | 0 | 120 | 味列:AG増(3T) | |
| 練3 | アクアシェル | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+火耐性増 |
| ライフリンク | 5 | 0 | 50 | 自従傷:HP増+HP譲渡 | |
| アクアリカバー | 6 | 0 | 80 | 味肉:HP増+肉体変調を守護化 | |
| アイスソーン | 5 | 0 | 70 | 敵貫:水痛撃 | |
| クリエイト:ヴェノム | 5 | 0 | 90 | 敵:猛毒・麻痺・腐食 | |
| クリエイト:メガネ | 5 | 0 | 100 | 味:DX・AG増(5T) | |
| スコーピオン | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃&衰弱+痛撃&朦朧 | |
| パワーブースター | 5 | 0 | 40 | 自従:AT・DF・DX・AG・HL増(3T) | |
| マナポーション | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP・SP増 | |
| アクアヒール | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 | |
| 練3 | ファーマシー | 5 | 0 | 110 | 味傷:HP増+肉体精神変調減 |
| ブロック | 6 | 0 | 80 | 自:守護+DF増(2T)+味傷:護衛 | |
| バックフロウ | 5 | 0 | 100 | 味傷:精確水領撃&HP増&隊列後退 | |
| サモン:スライム | 5 | 2 | 300 | 自:スライム召喚 | |
| パワーブリンガー | 5 | 0 | 100 | 自従全:AT・DF・DX・AG・HL・LK増+猛毒 | |
| マインドリカバー | 5 | 0 | 0 | 自:連続減+SP30%以下ならSP増+名前に「自」を含む付加効果のLV減 | |
| サモン:サーヴァント | 5 | 5 | 300 | 自:サーヴァント召喚 | |
| サモン:ウンディーネ | 5 | 5 | 400 | 自:ウンディーネ召喚 | |
| ヒールミスト | 5 | 0 | 200 | 味全:HP増+敵全:射程3以上ならDX減(2T) | |
| クリエイト:バンデージ | 5 | 0 | 150 | 味傷:HP・鎮痛LV増 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 召喚強化 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:具現LVが高いほど自身の召喚するNPCが強化 | |
| 魅惑 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:使役LVが高いほど戦闘勝利時に敵をエイドにできる確率増 | |
| 練1 | 五月雨 | 5 | 4 | 0 | 【スキル使用後】敵:3連水撃 |
| 氷水避け | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:水耐性・凍結耐性増+凍結によるHP・SP減少量減 | |
| 水特性回復 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:水属性スキルのHP増効果に水特性が影響 | |
| 修復 | 5 | 3 | 0 | 【被HP回復後】自:守護 | |
| 対症下薬 | 5 | 3 | 0 | 【HP回復後】対:変調軽減+名前に「自」を含む付加効果のLV減 | |
| 水の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:命術LVが高いほど水特性・耐性増 | |
| 薬師 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+名前に「防」を含む付加効果のLV増 |
最大EP[20]





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]マナポーション | [ 3 ]五月雨 | [ 3 ]アクアヒール |
| [ 3 ]リフレッシュ | [ 3 ]パワフルヒール | [ 3 ]カームフレア |

PL / 毛玉