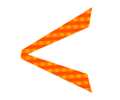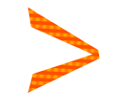<< 1:00~2:00




まだ暖かい灰が、辺りにうっすら散らばっている。
その中央に膝をついた少年は、己の上着を脱ぎ捨てた。

一心不乱に掻き集め、地面に敷いたそれへと乗せていく。
何も言葉を発することなく、ただそうして積み上げられた灰の山を作っていく。
風に散ってしまうことを恐れているように。
ある程度集められた灰が、俄に熱を帯びて輝き始める。
手で集めきらなかった細かな燃え残りもまた発光し、彼が集めた灰の山へふわりふわりと漂って集まってきた。
状況を鑑みなければ、幻想的な光景だ。
ほどなく灰の山の頂上から、勢いよく何かが飛び出した。
燃えるように輝く人間の腕だ。肘くらいまでのそれが、掌を天に向けてもがくように蠢いている。
(――あいつの手だ)
現実とはかけ離れたこの状況であっても、なぜかそう確信した。
探り当てるその先を教えるように、あるいは引っ張り出すように、強く握る。
燃えているように見える腕は触れてみるとほの暖かく、肌を焦がすような熱さではなかった。
虚空を探っていた手が縁を見つけたようにしっかりと握り返す。軽く力を込めると、僅かな手応えと共に腕は引き寄せられ――
腕から引きずりあげられるように、よく見知った残りの肉体が、身につけていた衣服ごと灰によって形作られていった。
灰が固まって目の前に現れたまだ仄かに青く輝く少年は、引き上げられた片腕に頼ってだらりと力なく座った姿勢のまま動かない。
両目が閉じられて眠っているようにも見えるが、握り返す手の力だけは未だにしっかりと力強い。
「……すみれ、目を開けてくれ」
下手に扱えばまた崩れ去ってしまうのではないかと逡巡した挙句、その姿の名を呼び、そっと頬へふれる。
目の前の人物の異能に、このような働きがあった覚えはない。
あるいは、知らなかっただけに過ぎないのか……
そこまで考えて、何より彼の無事を確認すべきであることを思い、仄かな光越しの顔を見つめる。
頬はまるで焼き物のような感触だった。しかし躊躇いがちな指がそれに触れた瞬間、硬く乾いた肌が突然ふっくらと弾力を取り戻していく。
声が聞こえたのかは定かでないが、うっすらと少年の瞼が上がった。
平時の薄くブルーの入ったグレーではなく、纏う炎とほぼ同じ鮮やかなライトシアンの瞳と目が合う。
弱々しい声とともにその身を包んでいた神秘の一切は炎とともに掻き消え、ただそこには寝起きのようにぼんやりした少年がすっかり元通りの様子で座り込んでいた。
疑いようもなく、いつもの幼馴染――菫 啓文その人である。

「ああ、俺だ」
すっかり元通りになった頬へもう一度ふれる。繋いだ手の感触と同じく、柔らかい。
「一体なにが、……いや、それよりも、怪我は?どこか痛かったりは……」
「そ、そうか……ならいいんだが……」
つぶさに観察するも、言葉通りどこにも外傷は見当たらない。ひとまず、安堵の息をつく。
そんなこちらの様子を見て、まだぼんやりとした表情ではありつつも困り笑いを向けた。
「また、って……お前、もしかしてこういう風になったことあったか……?」
あるとするなら、あの時、彼が生死の境を彷徨っていた時だろうか。
けれども、今のように手を握ったりは出来なかった。
親族でもない俺は、ついぞ病室に入れなかったのだから……俺が助けたというのは、すこし、噛み合わない。
そのことを問おうとしたが、彼は突然はっとしたように目を見開く。
そうして一転頭をぶんぶんと振って、立ち上がった。自分もつられて立つ。
手は繋がれたままだ。幼い頃から感じてきた温もりがそこにある。
「無理もない。幾ら異能があるって言っても、こんなに大掛かりなことをすれば混乱して当たり前だ」
立ち上がった跡に目をやった。
もう灰はどこにもなく、ただ乱雑に自分の上着が投げ捨てられているだけに見えた。
気付けば、心配そうにこちらを覗き込む顔。
半分ほど、目の前の幼馴染の言うことが理解できない。
――死んでいた?灰になって……そこから蘇ったとでも言うのだろうか。
「俺はなんともない。死んでもとか、そんなに軽々しく言うなよ。
……いや、力不足だったのは、それでも確かか」
少し変な力のある男子高校生として、なんの変哲も無い日常を過ごしてきたつもりだった。当然人の害し方など知らない。
いや、知ればいつか叶えてしまうかもしれない。そういった性質の異能であるが故に、余計避けていた。
……けれど、このままでは目の前の存在がいたずらに傷つき続けてしまうことになる。
今度こそ、本当に失ってしまうかもしれないのに。
「ごめん。守れなくて……」
放っていた上着を叩いて、差し出してくれる。
「そりゃあ、…………ずっとあのままかと、思って」
いつもそうだ。平然とした、柔和な微笑みから吐き出されるのは過剰な奉仕と自己犠牲。
それでは本末転倒だ、と何度も言っている筈なのだが。
「お前が役に立つかどうか以前に、死んだらなにも意味がない」
やんわりとした、しかし明確な否定。
それほど取り付くしまのない答えを返されることはそうそうなかった。
肩にかけてやった上着を握っている。
「っ……でも、」
言い返そうとした。
けれども、逆の立場ならおそらく同じことを言うであろうし、ここまで彼が真っ向から意志を主張することはまずない。
それなら、やることはひとつだ。
「……俺も、もっと探そうと思う。すみれを守れる方法。二人で帰れる方法」
何としてもお互いのために命を使うことをやめないのなら、その事態が起こらないようにすればいい。
最善を叶えること。「互いのため」のぶつけ合いなら、それが一番シンプルな解決法だ。
思わず繋いだ手に力が入る。
それを握り返され、すぐ隣にぴったりと寄り添われる。
迷いのない返事は、明快な了承のしるしだ。
「ああ。約束だぞ」
考え方はともかく、こいつが自分の要求なら絶対に守ろうとするのを知っていながらこうするのは、狡い手だ。けれども、命には代えられない。
その選択を肯定するように微笑み、頷く。
「それがいいな。適宜食材もこの調子で調達しながら、慎重に進もう」
そうして赤い空の下を、ふたりで歩き出す。



ENo.512 《冒涜する天秤》 とのやりとり




ItemNo.7 青いパウンドケーキ を食べました!
体調が 1 回復!(21⇒22)
今回の全戦闘において 器用14 敏捷14 耐疫14 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!









自然LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
料理LV を 5 UP!(LV25⇒30、-5CP)
ItemNo.6 美味しい草 から料理『きまぐれガーデンサラダ』をつくりました!
⇒ 美酒佳肴![ 2 2 1 = 5 ]大失敗!なんか妙だ!!!!料理の効果1が「自滅」に変化!
⇒ きまぐれガーデンサラダ/料理:強さ40/[効果1]自滅11 [効果2]充填11 [効果3]増幅11
スミレ(1127) の持つ ItemNo.6 美味しい草 から料理『きまぐれガーデンサラダ』をつくりました!
⇒ 美酒佳肴![ 2 2 4 = 8 ]成功!料理の付加効果のLVが増加!
ダイスさん(1170) の持つ ItemNo.8 美味しい草 から料理『きまぐれガーデンサラダ』をつくりました!
⇒ 美酒佳肴![ 2 4 1 = 7 ]成功!料理の付加効果のLVが増加!
PSY.B.峰子(564) とカードを交換しました!
ヘイルカード (ヘイルカード)

マナポーション を研究しました!(深度1⇒2)
アクアシェル を研究しました!(深度0⇒1)
カームフレア を研究しました!(深度1⇒2)
ストーンブラスト を習得!
リフレッシュ を習得!
ヒールハーブ を習得!
ノーマライズ を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



スミレ(1127) は 白石 を入手!
茅(1134) は 白石 を入手!
ダイスさん(1170) は 白石 を入手!
スミレ(1127) は 毛 を入手!
ダイスさん(1170) は ネジ を入手!
ダイスさん(1170) は 不思議な雫 を入手!



ダイスさん(1170) がパーティから離脱しました!
スミレ(1127) に移動を委ねました。
チナミ区 F-13(山岳)に移動!(体調22⇒21)
チナミ区 G-13(山岳)に移動!(体調21⇒20)
チナミ区 H-13(草原)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 I-13(道路)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 I-14(道路)に移動!(体調18⇒17)
採集はできませんでした。
- スミレ(1127) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。

ため息をつく。
Cross+Roseにロスト7名の容姿と簡単なプロフィールが映し出される。







大きな打撃音と泣き声と共に、チャットが閉じられる――
























































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



【ハザマ時間 1:00】
SIDE:T
SIDE:T
まだ暖かい灰が、辺りにうっすら散らばっている。
その中央に膝をついた少年は、己の上着を脱ぎ捨てた。

烏木 茅
少年。
先程ハザマでの戦闘を終えたばかり。
先程ハザマでの戦闘を終えたばかり。
一心不乱に掻き集め、地面に敷いたそれへと乗せていく。
何も言葉を発することなく、ただそうして積み上げられた灰の山を作っていく。
風に散ってしまうことを恐れているように。
ある程度集められた灰が、俄に熱を帯びて輝き始める。
手で集めきらなかった細かな燃え残りもまた発光し、彼が集めた灰の山へふわりふわりと漂って集まってきた。
状況を鑑みなければ、幻想的な光景だ。
ほどなく灰の山の頂上から、勢いよく何かが飛び出した。
燃えるように輝く人間の腕だ。肘くらいまでのそれが、掌を天に向けてもがくように蠢いている。
(――あいつの手だ)
現実とはかけ離れたこの状況であっても、なぜかそう確信した。
探り当てるその先を教えるように、あるいは引っ張り出すように、強く握る。
燃えているように見える腕は触れてみるとほの暖かく、肌を焦がすような熱さではなかった。
虚空を探っていた手が縁を見つけたようにしっかりと握り返す。軽く力を込めると、僅かな手応えと共に腕は引き寄せられ――
腕から引きずりあげられるように、よく見知った残りの肉体が、身につけていた衣服ごと灰によって形作られていった。
灰が固まって目の前に現れたまだ仄かに青く輝く少年は、引き上げられた片腕に頼ってだらりと力なく座った姿勢のまま動かない。
両目が閉じられて眠っているようにも見えるが、握り返す手の力だけは未だにしっかりと力強い。
「……すみれ、目を開けてくれ」
下手に扱えばまた崩れ去ってしまうのではないかと逡巡した挙句、その姿の名を呼び、そっと頬へふれる。
目の前の人物の異能に、このような働きがあった覚えはない。
あるいは、知らなかっただけに過ぎないのか……
そこまで考えて、何より彼の無事を確認すべきであることを思い、仄かな光越しの顔を見つめる。
頬はまるで焼き物のような感触だった。しかし躊躇いがちな指がそれに触れた瞬間、硬く乾いた肌が突然ふっくらと弾力を取り戻していく。
声が聞こえたのかは定かでないが、うっすらと少年の瞼が上がった。
平時の薄くブルーの入ったグレーではなく、纏う炎とほぼ同じ鮮やかなライトシアンの瞳と目が合う。
「……ちがや、」
弱々しい声とともにその身を包んでいた神秘の一切は炎とともに掻き消え、ただそこには寝起きのようにぼんやりした少年がすっかり元通りの様子で座り込んでいた。
疑いようもなく、いつもの幼馴染――菫 啓文その人である。

菫 啓文
もうひとりの少年。
戦闘中、突如として灰になった。
戦闘中、突如として灰になった。
「ああ、俺だ」
すっかり元通りになった頬へもう一度ふれる。繋いだ手の感触と同じく、柔らかい。
「一体なにが、……いや、それよりも、怪我は?どこか痛かったりは……」
「だいじょうぶ……君のおかげでもとどおり」
「そ、そうか……ならいいんだが……」
つぶさに観察するも、言葉通りどこにも外傷は見当たらない。ひとまず、安堵の息をつく。
そんなこちらの様子を見て、まだぼんやりとした表情ではありつつも困り笑いを向けた。
「ありがとう。また君に、引っ張りあげて貰っちゃった」
「また、って……お前、もしかしてこういう風になったことあったか……?」
あるとするなら、あの時、彼が生死の境を彷徨っていた時だろうか。
けれども、今のように手を握ったりは出来なかった。
親族でもない俺は、ついぞ病室に入れなかったのだから……俺が助けたというのは、すこし、噛み合わない。
「んえ」
そのことを問おうとしたが、彼は突然はっとしたように目を見開く。
「ないよ。ごめん、寝ぼけてた……寝ぼけてたって言っていいのかな?これ」
そうして一転頭をぶんぶんと振って、立ち上がった。自分もつられて立つ。
手は繋がれたままだ。幼い頃から感じてきた温もりがそこにある。
「無理もない。幾ら異能があるって言っても、こんなに大掛かりなことをすれば混乱して当たり前だ」
立ち上がった跡に目をやった。
もう灰はどこにもなく、ただ乱雑に自分の上着が投げ捨てられているだけに見えた。
「俺、この世界なら茅さえいれば死んでも元に戻れるみたい。
茅のほうこそ大丈夫?あの人たちに酷いことされてないよね……?」
茅のほうこそ大丈夫?あの人たちに酷いことされてないよね……?」
気付けば、心配そうにこちらを覗き込む顔。
半分ほど、目の前の幼馴染の言うことが理解できない。
――死んでいた?灰になって……そこから蘇ったとでも言うのだろうか。
「俺はなんともない。死んでもとか、そんなに軽々しく言うなよ。
……いや、力不足だったのは、それでも確かか」
少し変な力のある男子高校生として、なんの変哲も無い日常を過ごしてきたつもりだった。当然人の害し方など知らない。
いや、知ればいつか叶えてしまうかもしれない。そういった性質の異能であるが故に、余計避けていた。
……けれど、このままでは目の前の存在がいたずらに傷つき続けてしまうことになる。
今度こそ、本当に失ってしまうかもしれないのに。
「ごめん。守れなくて……」
「ごめんなさいは俺のほうだよ、茅。先に死んじゃって役に立てなかった。戦えそうな異能を持ってるのは俺なのに」
「俺の灰、頑張って集めてくれたんだよね。ありがとう」
「俺の灰、頑張って集めてくれたんだよね。ありがとう」
放っていた上着を叩いて、差し出してくれる。
「そりゃあ、…………ずっとあのままかと、思って」
いつもそうだ。平然とした、柔和な微笑みから吐き出されるのは過剰な奉仕と自己犠牲。
それでは本末転倒だ、と何度も言っている筈なのだが。
「お前が役に立つかどうか以前に、死んだらなにも意味がない」
「俺はそう思わない」
やんわりとした、しかし明確な否定。
それほど取り付くしまのない答えを返されることはそうそうなかった。
肩にかけてやった上着を握っている。
「ありがと。……茅の気持ちはいつも嬉しいんだ。茅が悲しむところも見たくない。
だから、ちゃんと死なない方法は考えるよ。ごめんね」
だから、ちゃんと死なない方法は考えるよ。ごめんね」
「っ……でも、」
言い返そうとした。
けれども、逆の立場ならおそらく同じことを言うであろうし、ここまで彼が真っ向から意志を主張することはまずない。
それなら、やることはひとつだ。
「……俺も、もっと探そうと思う。すみれを守れる方法。二人で帰れる方法」
何としてもお互いのために命を使うことをやめないのなら、その事態が起こらないようにすればいい。
最善を叶えること。「互いのため」のぶつけ合いなら、それが一番シンプルな解決法だ。
思わず繋いだ手に力が入る。
「うん」
それを握り返され、すぐ隣にぴったりと寄り添われる。
「そうだね。ふたりで帰ろう」
迷いのない返事は、明快な了承のしるしだ。
「ああ。約束だぞ」
考え方はともかく、こいつが自分の要求なら絶対に守ろうとするのを知っていながらこうするのは、狡い手だ。けれども、命には代えられない。
その選択を肯定するように微笑み、頷く。
「じゃ……行こっか、茅。今度は勝てるように、武器の材料とか集めようよ」
「それがいいな。適宜食材もこの調子で調達しながら、慎重に進もう」
そうして赤い空の下を、ふたりで歩き出す。



ENo.512 《冒涜する天秤》 とのやりとり
| ▲ |
| ||



 |
スミレ 「心配かけてごめんね。 俺のことは、心配しないで。」 |
 |
茅 「ちゃんと飯食ったか?今のうちだぞ」 |
ItemNo.7 青いパウンドケーキ を食べました!
 |
茅 「意外といける。ここだと見た目が変な料理ばかりできるな……」 |
今回の全戦闘において 器用14 敏捷14 耐疫14 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!





アンジニティ異形の会
|
 |
男子学生と時々サイコロ
|



自然LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
料理LV を 5 UP!(LV25⇒30、-5CP)
ItemNo.6 美味しい草 から料理『きまぐれガーデンサラダ』をつくりました!
⇒ 美酒佳肴![ 2 2 1 = 5 ]大失敗!なんか妙だ!!!!料理の効果1が「自滅」に変化!
⇒ きまぐれガーデンサラダ/料理:強さ40/[効果1]自滅11 [効果2]充填11 [効果3]増幅11
スミレ(1127) の持つ ItemNo.6 美味しい草 から料理『きまぐれガーデンサラダ』をつくりました!
⇒ 美酒佳肴![ 2 2 4 = 8 ]成功!料理の付加効果のLVが増加!
ダイスさん(1170) の持つ ItemNo.8 美味しい草 から料理『きまぐれガーデンサラダ』をつくりました!
⇒ 美酒佳肴![ 2 4 1 = 7 ]成功!料理の付加効果のLVが増加!
PSY.B.峰子(564) とカードを交換しました!
ヘイルカード (ヘイルカード)

マナポーション を研究しました!(深度1⇒2)
アクアシェル を研究しました!(深度0⇒1)
カームフレア を研究しました!(深度1⇒2)
ストーンブラスト を習得!
リフレッシュ を習得!
ヒールハーブ を習得!
ノーマライズ を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



スミレ(1127) は 白石 を入手!
茅(1134) は 白石 を入手!
ダイスさん(1170) は 白石 を入手!
スミレ(1127) は 毛 を入手!
ダイスさん(1170) は ネジ を入手!
ダイスさん(1170) は 不思議な雫 を入手!



ダイスさん(1170) がパーティから離脱しました!
スミレ(1127) に移動を委ねました。
チナミ区 F-13(山岳)に移動!(体調22⇒21)
チナミ区 G-13(山岳)に移動!(体調21⇒20)
チナミ区 H-13(草原)に移動!(体調20⇒19)
チナミ区 I-13(道路)に移動!(体調19⇒18)
チナミ区 I-14(道路)に移動!(体調18⇒17)
採集はできませんでした。
- スミレ(1127) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
ノウレット 「またまたこんにちは―――ッ!!」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
 |
白南海 「・・・っつぅ・・・・・また貴方ですか・・・ ・・・耳が痛くなるんでフリップにでも書いてくれませんかねぇ。」 |
 |
ノウレット 「はぁい!イヤですッ!!」 |
 |
白南海 「Yesなのか、Noなのか・・・」 |
ため息をつく。
 |
白南海 「それで、自己紹介の次は何用です?」 |
 |
ノウレット 「はぁい!今回はロストに関する情報を持ってきましたよーッ!!」 |
 |
白南海 「おぉそれは感心ですね、イルカよりは性能良さそうです。褒めてあげましょう。」 |
 |
ノウレット 「やったぁぁ―――ッ!!!!」 |
 |
白南海 「だから大声やめろおぉぉぉクソ妖精ッッ!!!」 |
 |
ノウレット 「早速ですが・・・・・ジャーンッ!!こちらがロスト情報ですよー!!!!」 |
Cross+Roseにロスト7名の容姿と簡単なプロフィールが映し出される。

アンドリュウ
紫の瞳、金髪ドレッドヘア。
体格の良い気さくなお兄さん。
料理好き、エプロン姿が何か似合っている。
体格の良い気さくなお兄さん。
料理好き、エプロン姿が何か似合っている。

ロジエッタ
水色の瞳、菫色の長髪。
大人しそうな小さな女の子。
黒いドレスを身につけ、男の子の人形を大事そうに抱えている。
大人しそうな小さな女の子。
黒いドレスを身につけ、男の子の人形を大事そうに抱えている。

アルメシア
金の瞳、白い短髪。褐色肌。
戦闘狂で活動的な少女。
鎧を身につけハルバードを持っている。
戦闘狂で活動的な少女。
鎧を身につけハルバードを持っている。

ソージロウ
黒い瞳、黒いもじゃもじゃ頭。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。

フレディオ
碧眼、ロマンスグレーの短髪。
彫りが深く、男前な老翁。
黒のライダースジャケットを身に着けている。
彫りが深く、男前な老翁。
黒のライダースジャケットを身に着けている。

ミヨチン
茶色の瞳、桜色のロング巻き髪。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。

マッドスマイル
乱れた長い黒緑色の髪。
両手に紅いナイフを持ち、
猟奇的な笑顔の仮面をつけている。
両手に紅いナイフを持ち、
猟奇的な笑顔の仮面をつけている。
 |
白南海 「ほぅほぅ、みな人間・・・のような容姿ですね。ハザマの様子的に意外なようでもあり。 彼らの願望を叶えると影響力が上がり、ハザマでの力も高めてくれる・・・と。」 |
 |
白南海 「どんな願望なのやら、無茶振りされないといいんですが。 ロストに若がいたならどんな願望もソッコーで叶えに行きますがね!」 |
 |
ノウレット 「ワカは居ませんよ?」 |
 |
白南海 「・・・わかってますよ。」 |
 |
白南海 「ところで情報はこれだけっすか?クソ妖精。」 |
 |
ノウレット 「あだ名で呼ぶとか・・・・・まだ早いと思います。出会ったばかりですし私たち。」 |
 |
白南海 「ねぇーんですね。居場所くらい持ってくるもんかと。」 |
 |
白南海 「ちなみに、ロストってのは何者なんで? これもハザマのシステムって解釈でいいのかね。」 |
 |
ノウレット 「ごめんなさい!私はCross+Roseの妖精なのでハザマのことはよくわかりません!! Cross+Roseに送られた情報を伝えることしか・・・・・」 |
 |
白南海 「・・・まぁそーか。仕方ないが、どうも断片的っすねぇ。」 |
 |
白南海 「そんじゃ、チェックポイントを目指しがてらロスト探しもしていきましょうかね。」 |
 |
ノウレット 「レッツゴォォ―――ッ!!!!」 |
大きな打撃音と泣き声と共に、チャットが閉じられる――







ENo.1134
烏木 茅



うぼく ちがや と読む。
年齢:16歳
所属校:イバラ創藍高校
年組:1-2
身長:183cm
誕生日:11/8
好き:お菓子全般、音楽、可愛いもの(小動物系)、クソ映画、静かな場所
苦手:辛い食べ物、人混み
高校1年生男子。
茶髪のアシンメトリー、茶色の目。泣きぼくろ。
両耳にはシンプルなシルバーのピアスを付けている。異能抑制用とファッション用のものを使い分ける。
だが特段ヤンキーというわけでもなく、制服はきちんと着ているし温厚で寡黙な人物である。
人見知り気味で決して朗らかな性格とは言い難いが、根はお人好しで情に厚い。
たまにわかりにくくボケる。
インドア派。
幼馴染であるひとつ下の少年(Eno.1127)を非常に気にかけている。
家はウラド区にある「黒木屋」という老舗和菓子店。
http://lisge.com/ib/talk.php?s=594
跡継ぎは彼しかいないのだが、本人は洋菓子作りが趣味。
イバラインはこちら
http://lisge.com/ib/talk.php?p=3374
【異能】
自分の手で作ったものにささやかな願いを込め、それを実現させる力。
ただし、作るとき心の底から願ったことでなければならない。
またイバラシティでは、命に関わるほど強い効果は出せない。
実現の形としては、食べた人に何らかの効果を与えるものや、作成物自体が何かになるものなどさまざま。
作成に関わった度合いと願いの強さによって、実現度も増す。
本人はこの力を食べ物に対してしか発揮できないと思い込んでいるが、他の物質に対しては実感できないほど効果が薄くなってしまうだけ。
ハザマでは、彼が「己の手で作り」「願いを込める」なら、どんなものでも少なからずその願いを叶えようとする。
(例)
「美味しくできるといいんだが」→本来の出来に関わらずおいしい!
「これを食べた人が元気になってほしい」→治療効果
「ちくしょう、あいつ腹でも下せばいいのに」→下剤
「この卵はひよこになるはずだったんだよな……」→ひよこ形になりトテトテ歩き出す
※
本稼働からの参加。レス遅め。
同じ学校の方など、既知歓迎です。
交流頑張りたい。
実質初定期のため、なにか不手際があったら教えていただけると嬉しいです。
【システム面】
生産は料理ガン振り予定。
戦闘ではおそらくヒーラーです。
【くれじっと】
立ち絵/アイコン0:もえかす氏
【連絡先】
Twitter:@toya0119k
mastodon:toya0119@pawoo.net
年齢:16歳
所属校:イバラ創藍高校
年組:1-2
身長:183cm
誕生日:11/8
好き:お菓子全般、音楽、可愛いもの(小動物系)、クソ映画、静かな場所
苦手:辛い食べ物、人混み
高校1年生男子。
茶髪のアシンメトリー、茶色の目。泣きぼくろ。
両耳にはシンプルなシルバーのピアスを付けている。異能抑制用とファッション用のものを使い分ける。
だが特段ヤンキーというわけでもなく、制服はきちんと着ているし温厚で寡黙な人物である。
人見知り気味で決して朗らかな性格とは言い難いが、根はお人好しで情に厚い。
たまにわかりにくくボケる。
インドア派。
幼馴染であるひとつ下の少年(Eno.1127)を非常に気にかけている。
家はウラド区にある「黒木屋」という老舗和菓子店。
http://lisge.com/ib/talk.php?s=594
跡継ぎは彼しかいないのだが、本人は洋菓子作りが趣味。
イバラインはこちら
http://lisge.com/ib/talk.php?p=3374
【異能】
自分の手で作ったものにささやかな願いを込め、それを実現させる力。
ただし、作るとき心の底から願ったことでなければならない。
またイバラシティでは、命に関わるほど強い効果は出せない。
実現の形としては、食べた人に何らかの効果を与えるものや、作成物自体が何かになるものなどさまざま。
作成に関わった度合いと願いの強さによって、実現度も増す。
本人はこの力を食べ物に対してしか発揮できないと思い込んでいるが、他の物質に対しては実感できないほど効果が薄くなってしまうだけ。
ハザマでは、彼が「己の手で作り」「願いを込める」なら、どんなものでも少なからずその願いを叶えようとする。
(例)
「美味しくできるといいんだが」→本来の出来に関わらずおいしい!
「これを食べた人が元気になってほしい」→治療効果
「ちくしょう、あいつ腹でも下せばいいのに」→下剤
「この卵はひよこになるはずだったんだよな……」→ひよこ形になりトテトテ歩き出す
※
本稼働からの参加。レス遅め。
同じ学校の方など、既知歓迎です。
交流頑張りたい。
実質初定期のため、なにか不手際があったら教えていただけると嬉しいです。
【システム面】
生産は料理ガン振り予定。
戦闘ではおそらくヒーラーです。
【くれじっと】
立ち絵/アイコン0:もえかす氏
【連絡先】
Twitter:@toya0119k
mastodon:toya0119@pawoo.net
17 / 30
53 PS
チナミ区
I-14
I-14







































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 白いシャツ | 防具 | 30 | 活力10 | - | - | |
| 5 | 戦闘用電動泡立て器 | 武器 | 30 | 回復10 | - | - | 【射程3】 |
| 6 | きまぐれガーデンサラダ | 料理 | 40 | 自滅11 | 充填11 | 増幅11 | |
| 7 | 白石 | 素材 | 15 | [武器]祝福10(LV10)[防具]反祝10(LV10)[装飾]舞祝10(LV10) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 命術 | 5 | 生命/復元/水 |
| 自然 | 5 | 植物/鉱物/地 |
| 百薬 | 15 | 化学/病毒/医術 |
| 領域 | 5 | 範囲/法則/結界 |
| 料理 | 30 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 6 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ウォーターフォール | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |
| ストーンブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵:地撃&朦朧 | |
| 決1 | ヒールポーション | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+猛毒減 |
| リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |
| リフレッシュ | 5 | 0 | 50 | 味肉精3:祝福+肉体精神変調をAT化 | |
| アクアリカバー | 5 | 0 | 80 | 味肉:HP増+肉体変調を守護化 | |
| ヘイルカード | 5 | 0 | 100 | 敵5:粗雑水領撃 | |
| ヒールハーブ | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+自:領域値[地]3以上ならヒールハーブの残り発動回数増 | |
| ノーマライズ | 5 | 0 | 80 | 味環:HP増+環境変調を守護化 | |
| クイックレメディ | 5 | 0 | 100 | 味傷:HP増+自:混乱+連続増 | |
| ファーマシー | 6 | 0 | 110 | 味傷:HP増+肉体精神変調減 | |
| インフェクシャスキュア | 5 | 0 | 140 | 味列:HP増 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| おまじない (薬師) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+名前に「防」を含む付加効果のLV増 | |
| 美酒佳肴 | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『料理』で、作る料理の付加効果のLVが増加するが、3D6が5以下なら料理の効果1が「自滅」になる。 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
ある朝の日の (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
|
鎮静の癒し (アクアリカバー) |
0 | 80 | 味肉:HP増+肉体変調を守護化 | |
|
ヘイルカード (ヘイルカード) |
0 | 100 | 敵5:粗雑水領撃 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]ヒールポーション | [ 2 ]カームフレア | [ 1 ]アクアシェル |
| [ 1 ]ウィンドポーション | [ 1 ]ホーリーポーション | [ 2 ]マナポーション |
| [ 1 ]アクアヒール |

PL / とうや