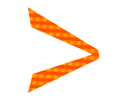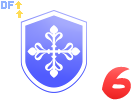<< 0:00~1:00




※ 暴力的表現が含まれます。

私が身に纏う衣服は、一体いつのものなのか──赤く汚れていた。
その汚れがいつのものであったのかなんて、もう覚えていない。
返り血ではない。私はこれまで、だれかを殺めたことなんてなかったもの。
全部、全部。全部、私の血だ。


『あいしてる。』
彼奴はそう言って、私を暗くて冷たい部屋へと繋ぎ止めた。
護りたいのだと。守りたいのだと。傷つけたくないのだと。熱に浮かされた目をして、男は呟いていた。
一体だれが、いつ、こんなことを頼んだというのだ。
出してと、止めてと喚いたところで聞き届けられることはなかった。
どうしてなんてこっちが聞きたい。逃げようとすれば、まるで私が悪いみたいに責められた。
その度に抑えつけられた。その度に締め上げられた。
──ある時、とうとう殴られた。
男は己の行動が信じられないというように瞠目して、困惑して、錯乱して、「もうダメだ」なんて言って。
ごき。って、何かが折れる音がして、私の意識は途絶えた。

『あいしてる。』
男はそう言って、私を強く抱き締めた。
──胸元に刃物が深々と突き刺されて、痛みに頭が真っ白になって、それ以上の記憶はない。
あいしてる、あいしてると。壊れたスピーカーみたいに、何度も耳元で男は囁いていた。

『あいしてる。』
だから誰の元にも行かないでくれと。
だからずっと傍にいてくれと。
──あいしてる。
あいしてる。あいしてる。愛してる。
だから、もう何も言わないでくれと。
だから、もう何も見ないでくれと。
だから、もう何も知らないでいてくれ。汚れないでくれ。
ごめん。
そう最後に呟いた男は、物言わぬ死体に縋り続けていた。
──こんなことばかりだ。
いい加減にして。もうやめて。たすけて。ゆるして。
どれだけ懇願しても、哀願しても、世界は私を諦めてくれやしない。
可哀想。可哀想。可哀想。可哀想。
憐れんで、悼んで、世界は私を愛そうとした。
── なにが愛だ。
ただ、愛という尊き感情を免罪符にして、横暴を許されようとしているだけではないか。
なにが愛だ。
愛という感情さえ有していれば、どのような暴力だろうと正当化できるなどと思い上がっているだけではないか。
なにが愛だ。愛しているだ。
ああそうだ、最初だってそうだった。そうだったのだ。

私はいつものように、いつもの道を通って学校から家へ帰る途中だった。
違うことといえば、その時の私はひどく浮足立っていたことだろう。
真っ赤だったランドセルはもう随分と色も剥げてしまっていて、そろそろ新しいリュックがほしいな──なんて思っていた。
だからおばあちゃんにおねだりしたのだ。
そうしたら、今度の国語のテストで90点以上取れたら新しい鞄を買ってくれるって!
私、がんばったの。わからないところはお母さんやお父さんに聞いたりした。
がんばった。がんばったの。ギリギリだったけど、90点をどうにか取ることができた。
……本当は86点だったけど、先生に物申して、三角を増やして、どうにか90点にしたの。
なのに。

なのに! どうして!!

……知らない人に、車に押し込まれた。
知らない匂いだった。知らない声だった。会ったこともない人だった。
こわかった。
殺されるんだと思った。きっと。殺されちゃうんだと思った。怖かった。
目隠しをされていたから、連れて来られた場所がどこなのかもわからなかった。
彼は優しかった。
ただ、外に出ようとさえしなければ。口答えさえしなければ。
彼に応えていれば。施される物に、言葉に、感情に。
でも
「嫌……!!」
一体どれだけの時間が過ぎていたのかはわからない。
私の不安は、恐怖は、やがて爆発した。
服に手をかけられて、私は彼を拒絶した。
わざとじゃなかったけど、私の爪は彼の皮膚を真一文字に引き裂いていた。
男は激昂した。僕を拒絶するのかと叫んだ。
なんて悪い子だと罵った。なんて可愛くない子だと嘆いた。
怖かった怖かった怖かった怖かった怖かった怖かった怖かった!!
その後、少女は殺された。
死体は砕かれ、液体に浸され、ドラム缶に詰められた。
原型は残らなかった。
男は言った。
愛しい彼女の姿を、他のだれにも見せたくなかったのだと。
最期の彼女は、確かに、自分だけのものであったのだと。


「運が悪かったねえ」
傍にいた男は、まるでひとごとのように言う。
私は思わず面を上げて、男を見た。
今の。今までの何を。一体、どう聞いていれば。
そんな言葉が出てくるのだと思った。

……男は、微笑んでいた。
雨も降っていないというのに、私に傘を差しだしながら(一体どこから持ってきたのだろう。持ち込んだのか? 傘を?)、イバラシティで過ごしたときと何も変わらない顔で。
「……ねえ」
尋ねる。
「どうしてあなたは、──わたしが"あの子"だと気付いたの?」

私は、人間が嫌いだ。おとなが嫌いだ。
愛が嫌いだ。社会が嫌いだ。世界が嫌いだ。
私は、彼らと過ごした日々を愛しいとは思わない。
あの世界を守りたいとは思わない。
思えない。思えるわけがない。
どんなにあたたかくても、穏やかでも、幸せでも、私は忘れない。
見たところ、彼はイバラシティと変わらぬ姿をしている。
順当に考えれば、彼はアンジニティの人間ではないということだ。
私が、嫌いな人間だ。
別に私は侵略に意欲的なわけではない。
ただ、嫌いなだけなのだ。嫌いなのだ。大嫌い。
あんな世界、私を見捨てた世界なんて、壊れてしまって構わない。
例え彼が、あの世界では私の兄であっても、今の私はどうとも思わない。
私は彼と敵対する。覚悟なんて決めるまでもない。
記憶を取り戻した瞬間、私の胸にはただのひとつも未練なんてなくなった。
……だから、その前に聞きたかった。
イバラシティとは、私の姿は違う。
あの世界のように、へらへら笑って能天気に過ごしているのとはわけが違う。
だというのに、彼奴は私の姿を見て逃げるどころか言ったのだ。「サアヤ?」と。
あの人格は、私ではない。私じゃない娘のものだ。
きっと、この肉体が、有していた、最期の人格だっただけで。
私とは違って、幸せなエンディングを迎えた憎たらしい娘の……!
少し困ったように眉を下げてはいるものの、男は微笑っていた。
あの世界とは違う私を前にしても、怯えることも惑うこともなく。
男は微笑んでいる。
まるでそれは、私を助けなかった世界のようだと思った。
まるでそれは、私を見殺しにしたおとなのようだと思った。
まるでそれは。
まるでそれは。
まるでそれは。
男は口を開く。受け取られることのなかった傘を肩に寄せると、こてりと小首を傾げた。
──あんな世界、どうだっていい。どうとも思わない。
だのに、彼の言葉に私は確かに動揺した。
──気付いていた。と、いうのは。
それは、つまり。
あの世界での時間さえも、
この男にとっては "本物"ではなかったということではないのか?
私は、"そういう風にされている"とはいえ、彼が、本当に兄だと思っていた。
のに。この男は。
それを、否定するのか。
……そんなのは、ずるい と。 私は。
言葉を失った私に対し、男は相変わらずの面で微笑んでいた。



ENo.17 サクマ とのやりとり

ENo.1081 『カーラ』 とのやりとり

ENo.1111 仁枝 とのやりとり

ENo.1316 『漂白』 とのやりとり

以下の相手に送信しました










百薬LV を 15 DOWN。(LV20⇒5、+15CP、-15FP)
命術LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
自然LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
料理LV を 5 UP!(LV20⇒25、-5CP)
サクマ(17) により ItemNo.4 不思議な牙 から装飾『赤飴と白飴の菊飾り』を作製してもらいました!
⇒ 赤飴と白飴の菊飾り/装飾:強さ35/[効果1]体力10 [効果2]- [効果3]-/特殊アイテム
女王とナレハテ(641) により ItemNo.5 不思議な石 から射程1の武器『薔薇の花束(99本)』を作製してもらいました!
⇒ 薔薇の花束(99本)/武器:強さ35/[効果1]回復10 [効果2]- [効果3]-【射程1】/特殊アイテム
ItemNo.7 不思議な食材 から料理『ラベンダーキャンディ』をつくりました!
⇒ 美酒佳肴![ 2 5 4 = 11 ]成功!料理の付加効果のLVが増加!
⇒ ラベンダーキャンディ/料理:強さ35/[効果1]器用13 [効果2]敏捷13 [効果3]耐疫13
サクマ(17) の持つ ItemNo.7 不思議な食材 から料理『ラベンダーキャンディ』をつくりました!
⇒ 美酒佳肴![ 3 3 3 = 9 ]成功!料理の付加効果のLVが増加!
飼い鳥(104) とカードを交換しました!
カラスが足元で雪遊びするカード (アイスソーン)


ストライク を研究しました!(深度0⇒1)
チャージ を研究しました!(深度0⇒1)
オートヒール を研究しました!(深度0⇒1)
ウォーターフォール を習得!
ストーンブラスト を習得!
リフレッシュ を習得!
アクアリカバー を習得!
ヒールハーブ を習得!
アクアヒール を習得!
ブルーム を習得!
オートヒール を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





チナミ区 D-10(道路)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 D-11(草原)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 D-12(草原)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 D-13(草原)に移動!(体調22⇒21)
チナミ区 E-13(草原)に移動!(体調21⇒20)






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。
そう言ってフロントダブルバイセップス。
・・・姿を現すことなく、女性のような声が伝わる。
ため息のような音が漏れる。
声はそこで終わる。
チャットが閉じられる――




















































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



※ 暴力的表現が含まれます。

私が身に纏う衣服は、一体いつのものなのか──赤く汚れていた。
その汚れがいつのものであったのかなんて、もう覚えていない。
返り血ではない。私はこれまで、だれかを殺めたことなんてなかったもの。
全部、全部。全部、私の血だ。


『あいしてる。』
彼奴はそう言って、私を暗くて冷たい部屋へと繋ぎ止めた。
護りたいのだと。守りたいのだと。傷つけたくないのだと。熱に浮かされた目をして、男は呟いていた。
一体だれが、いつ、こんなことを頼んだというのだ。
出してと、止めてと喚いたところで聞き届けられることはなかった。
どうしてなんてこっちが聞きたい。逃げようとすれば、まるで私が悪いみたいに責められた。
その度に抑えつけられた。その度に締め上げられた。
──ある時、とうとう殴られた。
男は己の行動が信じられないというように瞠目して、困惑して、錯乱して、「もうダメだ」なんて言って。
ごき。って、何かが折れる音がして、私の意識は途絶えた。

『あいしてる。』
男はそう言って、私を強く抱き締めた。
──胸元に刃物が深々と突き刺されて、痛みに頭が真っ白になって、それ以上の記憶はない。
あいしてる、あいしてると。壊れたスピーカーみたいに、何度も耳元で男は囁いていた。

『あいしてる。』
だから誰の元にも行かないでくれと。
だからずっと傍にいてくれと。
──あいしてる。
あいしてる。あいしてる。愛してる。
だから、もう何も言わないでくれと。
だから、もう何も見ないでくれと。
だから、もう何も知らないでいてくれ。汚れないでくれ。
ごめん。
そう最後に呟いた男は、物言わぬ死体に縋り続けていた。
──こんなことばかりだ。
いい加減にして。もうやめて。たすけて。ゆるして。
どれだけ懇願しても、哀願しても、世界は私を諦めてくれやしない。
可哀想。可哀想。可哀想。可哀想。
憐れんで、悼んで、世界は私を愛そうとした。
── なにが愛だ。
ただ、愛という尊き感情を免罪符にして、横暴を許されようとしているだけではないか。
なにが愛だ。
愛という感情さえ有していれば、どのような暴力だろうと正当化できるなどと思い上がっているだけではないか。
なにが愛だ。愛しているだ。
ああそうだ、最初だってそうだった。そうだったのだ。

私はいつものように、いつもの道を通って学校から家へ帰る途中だった。
違うことといえば、その時の私はひどく浮足立っていたことだろう。
真っ赤だったランドセルはもう随分と色も剥げてしまっていて、そろそろ新しいリュックがほしいな──なんて思っていた。
だからおばあちゃんにおねだりしたのだ。
そうしたら、今度の国語のテストで90点以上取れたら新しい鞄を買ってくれるって!
私、がんばったの。わからないところはお母さんやお父さんに聞いたりした。
がんばった。がんばったの。ギリギリだったけど、90点をどうにか取ることができた。
……本当は86点だったけど、先生に物申して、三角を増やして、どうにか90点にしたの。
なのに。

なのに! どうして!!

……知らない人に、車に押し込まれた。
知らない匂いだった。知らない声だった。会ったこともない人だった。
こわかった。
殺されるんだと思った。きっと。殺されちゃうんだと思った。怖かった。
目隠しをされていたから、連れて来られた場所がどこなのかもわからなかった。
「……いや」
彼は優しかった。
ただ、外に出ようとさえしなければ。口答えさえしなければ。
彼に応えていれば。施される物に、言葉に、感情に。
「いや……」
でも
「嫌……!!」
一体どれだけの時間が過ぎていたのかはわからない。
私の不安は、恐怖は、やがて爆発した。
服に手をかけられて、私は彼を拒絶した。
わざとじゃなかったけど、私の爪は彼の皮膚を真一文字に引き裂いていた。
男は激昂した。僕を拒絶するのかと叫んだ。
なんて悪い子だと罵った。なんて可愛くない子だと嘆いた。
皮膚を切り裂かれながら、愛を吐いた。
粘膜を焼かれながら、愛を誓った。
呼吸を締め付けられながら、愛を乞うた。
網膜が干からびようとも、彼だけを見つめ続けた。
血の味を覚えながらも、望む通りに唄い続けた。
……怖かった。
粘膜を焼かれながら、愛を誓った。
呼吸を締め付けられながら、愛を乞うた。
網膜が干からびようとも、彼だけを見つめ続けた。
血の味を覚えながらも、望む通りに唄い続けた。
……怖かった。
怖かった怖かった怖かった怖かった怖かった怖かった怖かった!!
その後、少女は殺された。
死体は砕かれ、液体に浸され、ドラム缶に詰められた。
原型は残らなかった。
男は言った。
愛しい彼女の姿を、他のだれにも見せたくなかったのだと。
最期の彼女は、確かに、自分だけのものであったのだと。


「運が悪かったねえ」
傍にいた男は、まるでひとごとのように言う。
私は思わず面を上げて、男を見た。
今の。今までの何を。一体、どう聞いていれば。
そんな言葉が出てくるのだと思った。

……男は、微笑んでいた。
雨も降っていないというのに、私に傘を差しだしながら(一体どこから持ってきたのだろう。持ち込んだのか? 傘を?)、イバラシティで過ごしたときと何も変わらない顔で。
「……ねえ」
尋ねる。
「どうしてあなたは、──わたしが"あの子"だと気付いたの?」

私は、人間が嫌いだ。おとなが嫌いだ。
愛が嫌いだ。社会が嫌いだ。世界が嫌いだ。
私は、彼らと過ごした日々を愛しいとは思わない。
あの世界を守りたいとは思わない。
思えない。思えるわけがない。
どんなにあたたかくても、穏やかでも、幸せでも、私は忘れない。
見たところ、彼はイバラシティと変わらぬ姿をしている。
順当に考えれば、彼はアンジニティの人間ではないということだ。
私が、嫌いな人間だ。
別に私は侵略に意欲的なわけではない。
ただ、嫌いなだけなのだ。嫌いなのだ。大嫌い。
あんな世界、私を見捨てた世界なんて、壊れてしまって構わない。
例え彼が、あの世界では私の兄であっても、今の私はどうとも思わない。
私は彼と敵対する。覚悟なんて決めるまでもない。
記憶を取り戻した瞬間、私の胸にはただのひとつも未練なんてなくなった。
……だから、その前に聞きたかった。
イバラシティとは、私の姿は違う。
あの世界のように、へらへら笑って能天気に過ごしているのとはわけが違う。
だというのに、彼奴は私の姿を見て逃げるどころか言ったのだ。「サアヤ?」と。
あの人格は、私ではない。私じゃない娘のものだ。
きっと、この肉体が、有していた、最期の人格だっただけで。
私とは違って、幸せなエンディングを迎えた憎たらしい娘の……!
 |
ミハル 「なんとなくかなあ」 |
 |
転生者 「……」 |
 |
転生者 「……は?」 |
 |
ミハル 「うん。これでも一応真面目だからね。 そんな真夏に放置したカレーを見るような目しないでね」 |
少し困ったように眉を下げてはいるものの、男は微笑っていた。
あの世界とは違う私を前にしても、怯えることも惑うこともなく。
 |
転生者 「なんで……」 |
 |
ミハル 「……」 |
男は微笑んでいる。
 |
転生者 「なんで……ッ!」 |
まるでそれは、私を助けなかった世界のようだと思った。
まるでそれは、私を見殺しにしたおとなのようだと思った。
まるでそれは。
まるでそれは。
まるでそれは。
 |
ミハル 「──そもそもね」 |
男は口を開く。受け取られることのなかった傘を肩に寄せると、こてりと小首を傾げた。
 |
ミハル 「あっちの世界の時から、 お前がオレの妹でないことは察していたんだよ」 |
 |
転生者 「……!」 |
──あんな世界、どうだっていい。どうとも思わない。
だのに、彼の言葉に私は確かに動揺した。
──気付いていた。と、いうのは。
それは、つまり。
あの世界での時間さえも、
この男にとっては "本物"ではなかったということではないのか?
私は、"そういう風にされている"とはいえ、彼が、本当に兄だと思っていた。
のに。この男は。
それを、否定するのか。
……そんなのは、ずるい と。 私は。
 |
言葉を失った私に対し、男は相変わらずの面で微笑んでいた。



ENo.17 サクマ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.1081 『カーラ』 とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.1111 仁枝 とのやりとり
| ▲ |
| ||
ENo.1316 『漂白』 とのやりとり
| ▲ |
| ||||
以下の相手に送信しました



 |
転生者 「私がやるから、邪魔しないでよね」 |
 |
ミハル 「うん。何もしないよ」 |
 |
転生者 「……いや、ちょっとは手伝おうとか思わないわけ?」 |
 |
ミハル 「あー……(面倒くさっ)」 |





百薬LV を 15 DOWN。(LV20⇒5、+15CP、-15FP)
命術LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
自然LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
料理LV を 5 UP!(LV20⇒25、-5CP)
サクマ(17) により ItemNo.4 不思議な牙 から装飾『赤飴と白飴の菊飾り』を作製してもらいました!
⇒ 赤飴と白飴の菊飾り/装飾:強さ35/[効果1]体力10 [効果2]- [効果3]-/特殊アイテム
| サクマ 「……ん、アリガトね♪ じゃあこれで、ギブアンドテイクってことで。 ふふふ、きっと似合うわよ。」 |
女王とナレハテ(641) により ItemNo.5 不思議な石 から射程1の武器『薔薇の花束(99本)』を作製してもらいました!
⇒ 薔薇の花束(99本)/武器:強さ35/[効果1]回復10 [効果2]- [効果3]-【射程1】/特殊アイテム
 |
すやぴ 「きゅー……きゅっ!」 |
ItemNo.7 不思議な食材 から料理『ラベンダーキャンディ』をつくりました!
⇒ 美酒佳肴![ 2 5 4 = 11 ]成功!料理の付加効果のLVが増加!
⇒ ラベンダーキャンディ/料理:強さ35/[効果1]器用13 [効果2]敏捷13 [効果3]耐疫13
 |
ミハル 「……」 |
サクマ(17) の持つ ItemNo.7 不思議な食材 から料理『ラベンダーキャンディ』をつくりました!
⇒ 美酒佳肴![ 3 3 3 = 9 ]成功!料理の付加効果のLVが増加!
飼い鳥(104) とカードを交換しました!
カラスが足元で雪遊びするカード (アイスソーン)


ストライク を研究しました!(深度0⇒1)
チャージ を研究しました!(深度0⇒1)
オートヒール を研究しました!(深度0⇒1)
ウォーターフォール を習得!
ストーンブラスト を習得!
リフレッシュ を習得!
アクアリカバー を習得!
ヒールハーブ を習得!
アクアヒール を習得!
ブルーム を習得!
オートヒール を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





チナミ区 D-10(道路)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 D-11(草原)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 D-12(草原)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 D-13(草原)に移動!(体調22⇒21)
チナミ区 E-13(草原)に移動!(体調21⇒20)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
「おっくれまして―――ッ!!」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
 |
ノウレット 「はぁい!はじめましてーッ!!私はここCross+Roseの管・・・妖精! ノウレットでーっす!!皆さんよろしくおねがいしまぁーっす!!」 |
チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。
 |
エディアン 「初めまして初めまして! 私はエディアンといいます、便利な機能をありがとうございます!」 |
 |
ノウレット 「わぁい!どーいたしましてーっ!!」 |
 |
エディアン 「ノウレットさんもドライバーさんと同じ、ハザマを司る方なんですね。」 |
 |
ノウレット 「司る!なんかそれかっこいいですね!!そうです!司ってますよぉ!!」 |
 |
ノウレット 「Cross+Roseのことで分からないことは何でも聞いてくださいねーっ!!」 |
 |
エディアン 「仄暗いハザマの中でマスコットみたいな方に会えて、何だか和みます! ワールドスワップの能力者はマスコットまで創るんですねー。」 |
 |
ノウレット 「マスコット!妖精ですけどマスコットもいいですねぇーっ!! エディアンさんは言葉の天才ですか!?すごい!すごい!!」 |
そう言ってフロントダブルバイセップス。
 |
ノウレット 「えーっとそれでですねーッ!!」 |
 |
ノウレット 「・・・・・あれっ 創造主さまからメッセージが!」 |
 |
エディアン 「むむむ、要チェックですね。」 |
・・・姿を現すことなく、女性のような声が伝わる。
 |
声 「――お疲れ様です御二方。役目を担ってくれて、感謝しています。」 |
 |
エディアン 「方法はどうあれ、こちらも機会を与えてくれて感謝していますよ?」 |
 |
声 「そしてハザマに招かれた方々、申し訳ありません。」 |
 |
声 「・・・・・・・・・」 |
 |
声 「このワールドスワップという能力は、招かれた方々全員が――ザザッ・・・」 |
 |
声 「――失われ、そう――ザザッ・・・――周期的に発動する、能力というより・・・」 |
 |
声 「制御不能な・・・呪いのよう。今までに発動した数度、自分への利は・・・ない。」 |
 |
声 「・・・・・・・・・」 |
ため息のような音が漏れる。
 |
声 「どうか、自らが自らであ―― ザザッ・・・」 |
 |
エディアン 「・・・・・雑音が酷いですねぇ。」 |
 |
声 「――ザザッ・・・・・・・・己の世界のために、争え。」 |
声はそこで終わる。
 |
エディアン 「ノウレットさん、何か通信おかしくないです?」 |
 |
ノウレット 「そうですかーっ!!?そうでもないですよーっ!!!?」 |
 |
エディアン 「むぅ。・・・大した情報は得られませんでしたね。」 |
 |
エディアン 「・・・さ、それじゃこの1時間も頑張っていきましょう!!」 |
チャットが閉じられる――





ENo.36
泥被る造花



「ねえ、兄貴。やばい。今の女の子、顔の大きさ、これっっっっっくらいしかなかった!(1円玉サイズ)」
「うん。エイリアンでも見た?」
♢花守瞠(はなもり - みはる)
男性 20代 172cm ▷https://t.co/6xage8vMgO
祖父母の経営する小さな花屋の手伝いをしている青年。
新輝楼学園卒。気性穏やかであり、人当たりも良い。
良く言えばいい人だが、平たく言えば凡人だ。
彼のプライベートは謎に包まれており、実は既婚者とか大学生とか、芸能人だとかそもそも女だとか噂は絶えない。
対象の遺伝子の一部(体液や髪など)を経口摂取することで、姿を真似る能力をもつ。が、使いたがらない。潔癖症!!
============
♢花守沙綾(はなもり - さあや)
女性 15歳 156cm ▷https://t.co/UAQVKfK7RZ
公立爆波津中学校三年生。腐女子。
兄とともに花屋の手伝いをしている明るく活発なオタク。
顔の良い男がすき。かわいい女の子もすき。
嫌いなものは徹夜組と転売屋と名前変更機能。
能力『おもしろい女』
強制魅了や洗脳といった精神干渉を無効化する。
尚、上記の情報は殆どが嘘であり真である。
幾度の死を越え
幾度も愛憎にもまれ
幾度の厄災を経て、
その身は既にひとから外れてしまっていた。
その身は既にひとではいられなくなっていた。
否。 きっと最初から、ひとではなかったのだ。
===================================
♢転生者
鮮やかな桃色の髪と、新緑を映す眼をもつ
血にまみれた和服を纏っている
===================================
齢九つの時、見知らぬ男に殺害された。しかし彼女の人生はそこで途絶えず、異世界に転生し第二の人生を歩むことになる。歩むことになる。歩むことになる。歩むことになる。歩むことになる。歩むことになる。歩むことになる。歩むことになる。歩むことになる。歩むことに歩む歩歩夢歩歩歩歩
──嗚呼、もう、うんざりだ!
『異世界の救世主《インスタント・ヒーロー》』
死ぬと魂の形成を保持したまま別の世界へと輪廻転生する。
その際、絶対的な要素として『愛される』という属性を付与される。異世界で生き残るためには、まず、その世界から『愛される』ことは絶対条件となるからだ。厳密的には、『愛される』のではなく転生者を「求める」世界とリンクされやすくなっている。
また、転生した世界に応じた能力をひとつ有するが、次の転生時に引き継ぐことはできない。
『女王蜂《クイーン・オブ・ハニー》』
女王は何者からの干渉も受けつけない。愛されているからだ。しかし、彼女に『愛』を抱いている上での干渉は可能だろう。そう、愛さえあれば殺すこともできる。
愛さえあれば、なんでもできるし許されるのだ。
===================================
♢ミハル
ハザマであってもその姿は変われない
===================================
妹が"妹"でないことには気付いている。
-----------
SUB
♢小鳥遊まひる(たかなし -)
女性 14歳 142cm
ブランブル女学院中等部二年一組。図書委員。
箱入り娘の常識知らず。話すことや歩くことが苦手。
強力な異能を持つ子どもを人為的につくる試みの中で生まれた【失敗作(デザインベビー)】。出生後も投薬や実験など幾度と行われてきたが、理想とする能力は発現していない。
尚、箱入り娘といっても"蝶よ花よと愛でられ育った"わけではない。無菌室にて監視・管理下で育てられたことを指す。彼女に頼れる存在はなく、神に祈ることを常としてきた。が、神を信奉してはいない。それはただの拠り所でしかない。
現在は、篠川昴(Eno.660)の家に下宿中。
▷https://t.co/TQeLyVZ8Bb(個別ページ)
✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶
♛memo
・イバラ初心者です
・キャラは加齢式(年齢があがります)
・既知や確定ロールは良識の範囲でご自由に
・基本的に交流相手のRP雰囲気に合わせます。基本的に。
・レス多病を抱えてますが、気にせず一蹴してください
「うん。エイリアンでも見た?」
♢花守瞠(はなもり - みはる)
男性 20代 172cm ▷https://t.co/6xage8vMgO
祖父母の経営する小さな花屋の手伝いをしている青年。
新輝楼学園卒。気性穏やかであり、人当たりも良い。
良く言えばいい人だが、平たく言えば凡人だ。
彼のプライベートは謎に包まれており、実は既婚者とか大学生とか、芸能人だとかそもそも女だとか噂は絶えない。
対象の遺伝子の一部(体液や髪など)を経口摂取することで、姿を真似る能力をもつ。が、使いたがらない。潔癖症!!
============
♢花守沙綾(はなもり - さあや)
女性 15歳 156cm ▷https://t.co/UAQVKfK7RZ
公立爆波津中学校三年生。腐女子。
兄とともに花屋の手伝いをしている明るく活発なオタク。
顔の良い男がすき。かわいい女の子もすき。
嫌いなものは徹夜組と転売屋と名前変更機能。
能力『おもしろい女』
強制魅了や洗脳といった精神干渉を無効化する。
尚、上記の情報は殆どが嘘であり真である。
幾度の死を越え
幾度も愛憎にもまれ
幾度の厄災を経て、
その身は既にひとから外れてしまっていた。
その身は既にひとではいられなくなっていた。
否。 きっと最初から、ひとではなかったのだ。
===================================
♢転生者
鮮やかな桃色の髪と、新緑を映す眼をもつ
血にまみれた和服を纏っている
===================================
齢九つの時、見知らぬ男に殺害された。しかし彼女の人生はそこで途絶えず、異世界に転生し第二の人生を歩むことになる。歩むことになる。歩むことになる。歩むことになる。歩むことになる。歩むことになる。歩むことになる。歩むことになる。歩むことになる。歩むことに歩む歩歩夢歩歩歩歩
──嗚呼、もう、うんざりだ!
『異世界の救世主《インスタント・ヒーロー》』
死ぬと魂の形成を保持したまま別の世界へと輪廻転生する。
その際、絶対的な要素として『愛される』という属性を付与される。異世界で生き残るためには、まず、その世界から『愛される』ことは絶対条件となるからだ。厳密的には、『愛される』のではなく転生者を「求める」世界とリンクされやすくなっている。
また、転生した世界に応じた能力をひとつ有するが、次の転生時に引き継ぐことはできない。
『女王蜂《クイーン・オブ・ハニー》』
女王は何者からの干渉も受けつけない。愛されているからだ。しかし、彼女に『愛』を抱いている上での干渉は可能だろう。そう、愛さえあれば殺すこともできる。
愛さえあれば、なんでもできるし許されるのだ。
===================================
♢ミハル
ハザマであってもその姿は変われない
===================================
妹が"妹"でないことには気付いている。
-----------
SUB
♢小鳥遊まひる(たかなし -)
女性 14歳 142cm
ブランブル女学院中等部二年一組。図書委員。
箱入り娘の常識知らず。話すことや歩くことが苦手。
強力な異能を持つ子どもを人為的につくる試みの中で生まれた【失敗作(デザインベビー)】。出生後も投薬や実験など幾度と行われてきたが、理想とする能力は発現していない。
尚、箱入り娘といっても"蝶よ花よと愛でられ育った"わけではない。無菌室にて監視・管理下で育てられたことを指す。彼女に頼れる存在はなく、神に祈ることを常としてきた。が、神を信奉してはいない。それはただの拠り所でしかない。
現在は、篠川昴(Eno.660)の家に下宿中。
▷https://t.co/TQeLyVZ8Bb(個別ページ)
✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶
♛memo
・イバラ初心者です
・キャラは加齢式(年齢があがります)
・既知や確定ロールは良識の範囲でご自由に
・基本的に交流相手のRP雰囲気に合わせます。基本的に。
・レス多病を抱えてますが、気にせず一蹴してください
20 / 30
60 PS
チナミ区
E-13
E-13




































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 赤飴と白飴の菊飾り | 装飾 | 35 | 体力10 | - | - | |
| 5 | 薔薇の花束(99本) | 武器 | 35 | 回復10 | - | - | 【射程1】 |
| 6 | 黄色の薬 | 料理 | 30 | 器用10 | 敏捷10 | 耐疫10 | |
| 7 | ラベンダーキャンディ | 料理 | 35 | 器用13 | 敏捷13 | 耐疫13 | |
| 8 | 松 | 素材 | 15 | [武器]器用10(LV15)[防具]応報10(LV25)[装飾]耐地10(LV20) | |||
| 9 | 美味しい果実 | 食材 | 15 | [効果1]攻撃10(LV10)[効果2]防御10(LV15)[効果3]強靭15(LV25) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 命術 | 10 | 生命/復元/水 |
| 自然 | 10 | 植物/鉱物/地 |
| 百薬 | 5 | 化学/病毒/医術 |
| 料理 | 25 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ウォーターフォール | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |
| ストーンブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵:地撃&朦朧 | |
| ヒールポーション | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+猛毒減 | |
| リフレッシュ | 5 | 0 | 50 | 味肉精3:祝福+肉体精神変調をAT化 | |
| アクアリカバー | 5 | 0 | 80 | 味肉:HP増+肉体変調を守護化 | |
| 決1 | ヒールハーブ | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+自:領域値[地]3以上ならヒールハーブの残り発動回数増 |
| アクアヒール | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 | |
| ブルーム | 5 | 0 | 120 | 敵全:地撃&魅了・束縛 | |
| ファーマシー | 5 | 0 | 110 | 味傷:HP増+肉体精神変調減 | |
| オートヒール | 5 | 0 | 60 | 味傷:治癒LV増 | |
| インフェクシャスキュア | 5 | 0 | 140 | 味列:HP増 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 薬師 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+名前に「防」を含む付加効果のLV増 | |
| 美酒佳肴 | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『料理』で、作る料理の付加効果のLVが増加するが、3D6が5以下なら料理の効果1が「自滅」になる。 |
最大EP[20]





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]ストライク | [ 1 ]チャージ | [ 1 ]オートヒール |

PL / 花葉