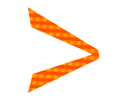<< 0:00~1:00




林檎が浮いています。
糸に吊されているわけでもなく、透明の台座に置かれているわけでもありません。
これが、わたし――端留更田の異能です。
『とどめのひとくち(リップ・クリップ)』
唇に触れたものを止める。
林檎は浮いたまま固定され、空気はキスに息を呑み立ち竦む――。
響きだけはロマンチックな異能なのですけれどぉ、わたしはこの異能を制御できません。

ああ、うっかり唇で触れてしまったものを固定してしまったことなんて、もう数えきれません……。
コーヒーは温かいまま固まり、白い息は磨りガラスのように固くなり、わたしの日常を阻みます。
例えそれが数秒程度のことだったとしても、すごく苦になってしまうのです。
そう、わたしにとって異能を制御できないというのは、実に実に死活問題なんですぅ。
「んぶぇっ」
そして今日も、横切った黒猫に驚いた拍子に異能は暴発。
自分の吐いた白い息にぶつかりながら、わたしはため息をつくのです。

「動かす」異能を持つ姉がいなければ、もっともっと苦労していたと思います。
固定の効果が消えて、霧散する吐息を見送って、わたしは学校への道を急ぎます。
わたしは、わたしがあまり好きではありません。
もうちょっと、ちゃんとできたらなって思うこともありますぅ。
爆波津中には、中学生でももっとしっかり異能をコントロールできる人がたくさんいます。
わたしだってもう三年生。来年には卒業を控えているというのに、
まだまだ全然、異能についてはうまくなりません。
もしも、もしもわたしの異能が暴発して、本当にずっと誰かが『固定』されてしまったら、
と考えると気が気ではなく、クラスの人にも内緒のままです。
つまり、わたしのことを知っている人は、そんなに多くないのです。
「は? 侵略? は??? ど、どうしろっていうんですかぁ……」
そんなわたしのところにシロナミという男の人からの連絡があったのは、ついこの間のこと。
アンジニティという世界がイバラシティに……わーるどすわっぷ?をして成り代わるために、
攻めてくるという話でした。
にわかには信じられない話でしたが、空の色がほんの少し変になったような気もします。
爆波津中でも、少しは噂になっているようで、あちこちからひそひそとした声が聞こえてきます。
それもなんだか苦になってしまって、わたしはより一層縮こまって過ごすこととなりました。
(わ、わたしなんかに何が……)
言葉通りの意味で小さなわたしに、何かが期待されている。
わたしにできることは、その日の温かさにキスをして、ほんの少し留めておくことだけなのに。
――というのが、イバラシティでのわたしの話。
「……少し卑屈すぎますかねぇ」

わたしの名前は端留更田。口付けで全てを縫い止める、アンジニティの住人です。
否定された理由も非常に簡潔です。
行き交う人々も、満員の電車も、空に漂う雲さえも。
わたしがキスを落とせば、時を止める。
停止という名の滅亡を、わたしは抱えているのです。
この身体がただの少女のものであったとしても、異能の危険性は変わりません。
それは、追放に値することだとわたしも思います。
ですが、追放理由の納得と、その境遇に甘んじることとは別の話です。
「……お姉ちゃん」

わたしは、「存在しない」お姉ちゃんに思いを馳せました。
お姉ちゃんとは、わたしがよりイバラシティにおいて巧妙に潜伏できるよう組み込まれた、一種の舞台装置です。
ですから、彼女はイバラシティでもアンジニティでもない、まぼろしなのです。
そう、わたしが安心を求めて作り上げた夢のひとかけら。
それこそが、姉の正体です。
だから、本当のわたしはひとりぼっちです。
(他には誰もいなさそう、ですね……?)
幸いにして、わたしは単独で動ける立場のようでした。
確かにアンジニティの人々は不気味ですし、イバラシティの人たちも今は血眼で恐ろしいです。
みんな敵を探しています。「襲ってもいい人」を探しています。
わたしは争いが好きなわけではないので、一人歩きが丁度良いというわけです。
火の粉を払えるかは分かりませんが、人型のわたしを無理に敵視するイバラシティの人も少ないでしょう。
アンジニティの人とは、ケンカする理由がありませんし、ね?
「とにかく、そのあたりを歩いて気が合う人なり何なり、探してみるのもいいですねぇ」
有象無象が歩き回るハザマを、わたしは一歩踏み出します。
――さあ、侵略を始めましょう。
あの日、おごってもらったコーンスープの缶のぬくもりを、わたしは永遠に抱きしめたいだけなのですから。









駄石(50 PS)を購入しようとしましたが、PSが足りませんでした。
エナジー棒(30 PS)を購入しようとしましたが、PSが足りませんでした。
武術LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
制約LV を 15 UP!(LV0⇒15、-15CP)
装飾LV を 25 UP!(LV0⇒25、-25CP)
ツタ(1377) により ItemNo.4 不思議な牙 から射程2の武器『リップクリーム』を作製してもらいました!
⇒ リップクリーム/武器:強さ35/[効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程2】/特殊アイテム
ItemNo.5 不思議な石 から装飾『髪留め』を作製しました!
⇒ 髪留め/装飾:強さ35/[効果1]幸運10 [効果2]- [効果3]-/特殊アイテム
白蛇(743) とカードを交換しました!
菊に盃 (ディベスト)


チャージ を研究しました!(深度0⇒1)
チャージ を研究しました!(深度1⇒2)
アクアヒール を研究しました!(深度0⇒1)
ストライク を習得!
アサルト を習得!
デアデビル を習得!
チャージ を習得!
ペナルティ を習得!
スピアトラップ を習得!
ピットトラップ を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





次元タクシーに乗り チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》 に転送されました!
チナミ区 F-5(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 G-5(道路)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 H-5(山岳)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 I-5(山岳)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 J-5(道路)に移動!(体調26⇒25)
採集はできませんでした。
- サラタ(1522) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。
そう言ってフロントダブルバイセップス。
・・・姿を現すことなく、女性のような声が伝わる。
ため息のような音が漏れる。
声はそこで終わる。
チャットが閉じられる――






















































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



林檎が浮いています。
糸に吊されているわけでもなく、透明の台座に置かれているわけでもありません。
これが、わたし――端留更田の異能です。
『とどめのひとくち(リップ・クリップ)』
唇に触れたものを止める。
林檎は浮いたまま固定され、空気はキスに息を呑み立ち竦む――。
響きだけはロマンチックな異能なのですけれどぉ、わたしはこの異能を制御できません。

端留更田
はしどめさらた。
どこにでもいる女子中学生。
『固定』の異能をもっている。
どこにでもいる女子中学生。
『固定』の異能をもっている。
ああ、うっかり唇で触れてしまったものを固定してしまったことなんて、もう数えきれません……。
コーヒーは温かいまま固まり、白い息は磨りガラスのように固くなり、わたしの日常を阻みます。
例えそれが数秒程度のことだったとしても、すごく苦になってしまうのです。
そう、わたしにとって異能を制御できないというのは、実に実に死活問題なんですぅ。
「んぶぇっ」
そして今日も、横切った黒猫に驚いた拍子に異能は暴発。
自分の吐いた白い息にぶつかりながら、わたしはため息をつくのです。

端留便
はしどめたより。
更田の姉であり、大学生。
『流動』の異能をもっている。
更田の姉であり、大学生。
『流動』の異能をもっている。
「サラタ、また何か固めちゃったの?」
「う、うん……」
「ったく、私が『動かす』から場所を教えな」
「う、ううん! 今回は、すぐ、動いたから……だ、大丈夫ですぅ!」
「そうかい? 困ったら、ちゃんと言うんだよ」
「動かす」異能を持つ姉がいなければ、もっともっと苦労していたと思います。
固定の効果が消えて、霧散する吐息を見送って、わたしは学校への道を急ぎます。
わたしは、わたしがあまり好きではありません。
もうちょっと、ちゃんとできたらなって思うこともありますぅ。
爆波津中には、中学生でももっとしっかり異能をコントロールできる人がたくさんいます。
わたしだってもう三年生。来年には卒業を控えているというのに、
まだまだ全然、異能についてはうまくなりません。
もしも、もしもわたしの異能が暴発して、本当にずっと誰かが『固定』されてしまったら、
と考えると気が気ではなく、クラスの人にも内緒のままです。
つまり、わたしのことを知っている人は、そんなに多くないのです。
「は? 侵略? は??? ど、どうしろっていうんですかぁ……」
そんなわたしのところにシロナミという男の人からの連絡があったのは、ついこの間のこと。
アンジニティという世界がイバラシティに……わーるどすわっぷ?をして成り代わるために、
攻めてくるという話でした。
にわかには信じられない話でしたが、空の色がほんの少し変になったような気もします。
爆波津中でも、少しは噂になっているようで、あちこちからひそひそとした声が聞こえてきます。
それもなんだか苦になってしまって、わたしはより一層縮こまって過ごすこととなりました。
(わ、わたしなんかに何が……)
言葉通りの意味で小さなわたしに、何かが期待されている。
わたしにできることは、その日の温かさにキスをして、ほんの少し留めておくことだけなのに。
――というのが、イバラシティでのわたしの話。
「……少し卑屈すぎますかねぇ」

ハシドメ サラタ
ハザマでの端留更田の姿をしたなにか。
あるいは、
シティでなにかだった端留更田の本来の姿。
あるいは、
シティでなにかだった端留更田の本来の姿。
わたしの名前は端留更田。口付けで全てを縫い止める、アンジニティの住人です。
否定された理由も非常に簡潔です。
『わたしは、全てを固定する可能性を孕んでいる』。
行き交う人々も、満員の電車も、空に漂う雲さえも。
わたしがキスを落とせば、時を止める。
停止という名の滅亡を、わたしは抱えているのです。
この身体がただの少女のものであったとしても、異能の危険性は変わりません。
それは、追放に値することだとわたしも思います。
ですが、追放理由の納得と、その境遇に甘んじることとは別の話です。
「……お姉ちゃん」

ハシドメ タヨリ
わたしは、「存在しない」お姉ちゃんに思いを馳せました。
お姉ちゃんとは、わたしがよりイバラシティにおいて巧妙に潜伏できるよう組み込まれた、一種の舞台装置です。
ですから、彼女はイバラシティでもアンジニティでもない、まぼろしなのです。
そう、わたしが安心を求めて作り上げた夢のひとかけら。
それこそが、姉の正体です。
だから、本当のわたしはひとりぼっちです。
(他には誰もいなさそう、ですね……?)
幸いにして、わたしは単独で動ける立場のようでした。
確かにアンジニティの人々は不気味ですし、イバラシティの人たちも今は血眼で恐ろしいです。
みんな敵を探しています。「襲ってもいい人」を探しています。
わたしは争いが好きなわけではないので、一人歩きが丁度良いというわけです。
火の粉を払えるかは分かりませんが、人型のわたしを無理に敵視するイバラシティの人も少ないでしょう。
アンジニティの人とは、ケンカする理由がありませんし、ね?
「とにかく、そのあたりを歩いて気が合う人なり何なり、探してみるのもいいですねぇ」
有象無象が歩き回るハザマを、わたしは一歩踏み出します。
――さあ、侵略を始めましょう。
あの日、おごってもらったコーンスープの缶のぬくもりを、わたしは永遠に抱きしめたいだけなのですから。



 |
サラタ 「とは言うものの、どこに行きましょうかねぇ」 |





駄石(50 PS)を購入しようとしましたが、PSが足りませんでした。
エナジー棒(30 PS)を購入しようとしましたが、PSが足りませんでした。
武術LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
制約LV を 15 UP!(LV0⇒15、-15CP)
装飾LV を 25 UP!(LV0⇒25、-25CP)
ツタ(1377) により ItemNo.4 不思議な牙 から射程2の武器『リップクリーム』を作製してもらいました!
⇒ リップクリーム/武器:強さ35/[効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程2】/特殊アイテム
 |
ツタ 「ご利用いただき、ありがとうございます。私はいつもここにおりますので、またの機会があれば、そのときはまたよろしくおねがいします。」 |
ItemNo.5 不思議な石 から装飾『髪留め』を作製しました!
⇒ 髪留め/装飾:強さ35/[効果1]幸運10 [効果2]- [効果3]-/特殊アイテム
 |
サラタ 「まずはひとつ、こんな感じでぇ」 |
白蛇(743) とカードを交換しました!
菊に盃 (ディベスト)


チャージ を研究しました!(深度0⇒1)
チャージ を研究しました!(深度1⇒2)
アクアヒール を研究しました!(深度0⇒1)
ストライク を習得!
アサルト を習得!
デアデビル を習得!
チャージ を習得!
ペナルティ を習得!
スピアトラップ を習得!
ピットトラップ を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





次元タクシーに乗り チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》 に転送されました!
 |
ドライバーさん 「・・・はい到着ぅ。気をつけて行きな。」 |
チナミ区 F-5(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 G-5(道路)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 H-5(山岳)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 I-5(山岳)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 J-5(道路)に移動!(体調26⇒25)
採集はできませんでした。
- サラタ(1522) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
「おっくれまして―――ッ!!」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
 |
ノウレット 「はぁい!はじめましてーッ!!私はここCross+Roseの管・・・妖精! ノウレットでーっす!!皆さんよろしくおねがいしまぁーっす!!」 |
チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。
 |
エディアン 「初めまして初めまして! 私はエディアンといいます、便利な機能をありがとうございます!」 |
 |
ノウレット 「わぁい!どーいたしましてーっ!!」 |
 |
エディアン 「ノウレットさんもドライバーさんと同じ、ハザマを司る方なんですね。」 |
 |
ノウレット 「司る!なんかそれかっこいいですね!!そうです!司ってますよぉ!!」 |
 |
ノウレット 「Cross+Roseのことで分からないことは何でも聞いてくださいねーっ!!」 |
 |
エディアン 「仄暗いハザマの中でマスコットみたいな方に会えて、何だか和みます! ワールドスワップの能力者はマスコットまで創るんですねー。」 |
 |
ノウレット 「マスコット!妖精ですけどマスコットもいいですねぇーっ!! エディアンさんは言葉の天才ですか!?すごい!すごい!!」 |
そう言ってフロントダブルバイセップス。
 |
ノウレット 「えーっとそれでですねーッ!!」 |
 |
ノウレット 「・・・・・あれっ 創造主さまからメッセージが!」 |
 |
エディアン 「むむむ、要チェックですね。」 |
・・・姿を現すことなく、女性のような声が伝わる。
 |
声 「――お疲れ様です御二方。役目を担ってくれて、感謝しています。」 |
 |
エディアン 「方法はどうあれ、こちらも機会を与えてくれて感謝していますよ?」 |
 |
声 「そしてハザマに招かれた方々、申し訳ありません。」 |
 |
声 「・・・・・・・・・」 |
 |
声 「このワールドスワップという能力は、招かれた方々全員が――ザザッ・・・」 |
 |
声 「――失われ、そう――ザザッ・・・――周期的に発動する、能力というより・・・」 |
 |
声 「制御不能な・・・呪いのよう。今までに発動した数度、自分への利は・・・ない。」 |
 |
声 「・・・・・・・・・」 |
ため息のような音が漏れる。
 |
声 「どうか、自らが自らであ―― ザザッ・・・」 |
 |
エディアン 「・・・・・雑音が酷いですねぇ。」 |
 |
声 「――ザザッ・・・・・・・・己の世界のために、争え。」 |
声はそこで終わる。
 |
エディアン 「ノウレットさん、何か通信おかしくないです?」 |
 |
ノウレット 「そうですかーっ!!?そうでもないですよーっ!!!?」 |
 |
エディアン 「むぅ。・・・大した情報は得られませんでしたね。」 |
 |
エディアン 「・・・さ、それじゃこの1時間も頑張っていきましょう!!」 |
チャットが閉じられる――





ENo.1522
端留更田



◆はしどめ さらた◆@hd_salad
身長:142cm
所属:公立爆波津中学校 三年
「こ、こんにちはぁ……。端留更田といいますぅ」
常に困り顔を浮かべる、臆病で小さな女子中学生。
焦げ茶のショートボブは横髪だけが伸ばされており、
前髪のひと房は緑色のメッシュになっている。
異能:『とどめのひとくち(リップ・クリップ)』
【口づけ】した【もの】を短時間【固定】するちから。
扱いにくい条件とそれに見合わぬ効力の弱さをしており、
更田自身の引っ込み思案な性格と相まって
無闇に能力の仔細をひけらかすことはまずない。
あまり制御が出来ておらず、驚いた時や眠たい時などに
無意識的に発動することがある。
◇ハシドメサラタはアンジニティの住民である◇
絵:Picrew「なんとかメーカー(仮)」様、同「なゆた。のメーカー」様
→https://picrew.me/image_maker/175799
→https://picrew.me/image_maker/157366
☆ログの公開など含め、色々フリーです。ご自由に。
身長:142cm
所属:公立爆波津中学校 三年
「こ、こんにちはぁ……。端留更田といいますぅ」
常に困り顔を浮かべる、臆病で小さな女子中学生。
焦げ茶のショートボブは横髪だけが伸ばされており、
前髪のひと房は緑色のメッシュになっている。
異能:『とどめのひとくち(リップ・クリップ)』
【口づけ】した【もの】を短時間【固定】するちから。
扱いにくい条件とそれに見合わぬ効力の弱さをしており、
更田自身の引っ込み思案な性格と相まって
無闇に能力の仔細をひけらかすことはまずない。
あまり制御が出来ておらず、驚いた時や眠たい時などに
無意識的に発動することがある。
◇ハシドメサラタはアンジニティの住民である◇
絵:Picrew「なんとかメーカー(仮)」様、同「なゆた。のメーカー」様
→https://picrew.me/image_maker/175799
→https://picrew.me/image_maker/157366
☆ログの公開など含め、色々フリーです。ご自由に。
25 / 30
5 PS
チナミ区
J-5
J-5







































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | リップクリーム | 武器 | 35 | 攻撃10 | - | - | 【射程2】 |
| 5 | 髪留め | 装飾 | 35 | 幸運10 | - | - | |
| 6 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 10 | 身体/武器/物理 |
| 制約 | 15 | 拘束/罠/リスク |
| 装飾 | 25 | 装飾作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 | |
| アサルト | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃+自:連続減 | |
| デアデビル | 5 | 0 | 60 | 自:HP減+敵傷4:痛撃 | |
| チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 | |
| ペナルティ | 5 | 0 | 120 | 敵3:麻痺・混乱 | |
| スピアトラップ | 5 | 0 | 100 | 敵:罠《突刺》LV増 | |
| ピットトラップ | 5 | 0 | 120 | 敵全:罠《奈落》LV増 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 |
最大EP[20]





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 2 ]チャージ | [ 1 ]アクアヒール |

PL / ヒラミン