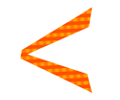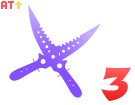<< 0:00~1:00




年末年始のため記事執筆なんてお休みデース
お餅とこたつって世界に広まるべきだと思う……記事にする? …………パソコン取りにこたつから出るなんてあり得ない……
私がこたつから出るのはお餅を焼くときとトイレに行くときだけ、それが正月のルール
次はバター醤油焼きにするか、きな粉にするか……



特に何もしませんでした。






武術LV を 5 UP!(LV20⇒25、-5CP)
武器LV を 5 UP!(LV20⇒25、-5CP)
りえる(570) とカードを交換しました!
小さな祈り (ヒール)

リザレクション を研究しました!(深度0⇒1)
ダウンフォール を研究しました!(深度0⇒1)
イービルサークル を研究しました!(深度0⇒1)
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





チナミ区 D-10(道路)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 D-11(草原)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 D-12(草原)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 D-13(草原)に移動!(体調22⇒21)
チナミ区 E-13(草原)に移動!(体調21⇒20)
採集はできませんでした。
- メアリー(1302) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。
元気よく両手両足を伸ばし空間を飛びまわる!
・・・姿を現すことなく、女性のような声が伝わる。
ため息のような音が漏れる。
声はそこで終わる。
チャットが閉じられる――


















































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [スキル]OK.



年末年始のため記事執筆なんてお休みデース
お餅とこたつって世界に広まるべきだと思う……記事にする? …………パソコン取りにこたつから出るなんてあり得ない……
私がこたつから出るのはお餅を焼くときとトイレに行くときだけ、それが正月のルール
次はバター醤油焼きにするか、きな粉にするか……



特に何もしませんでした。





武術LV を 5 UP!(LV20⇒25、-5CP)
武器LV を 5 UP!(LV20⇒25、-5CP)
りえる(570) とカードを交換しました!
小さな祈り (ヒール)

リザレクション を研究しました!(深度0⇒1)
ダウンフォール を研究しました!(深度0⇒1)
イービルサークル を研究しました!(深度0⇒1)
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





チナミ区 D-10(道路)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 D-11(草原)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 D-12(草原)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 D-13(草原)に移動!(体調22⇒21)
チナミ区 E-13(草原)に移動!(体調21⇒20)
採集はできませんでした。
- メアリー(1302) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
「おっくれまして―――ッ!!」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
 |
ノウレット 「はぁい!はじめましてーッ!!私はここCross+Roseの管・・・妖精! ノウレットでーっす!!皆さんよろしくおねがいしまぁーっす!!」 |
チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。
 |
白南海 「・・・・・。管理用アバター・・・ですかね。」 |
 |
ノウレット 「元気ないですねーッ!!死んでるんですかーッ!!!!」 |
 |
白南海 「貴方よりは生物的かと思いますよ。 ドライバーさんと同じく、ハザマの機能ってやつですか。」 |
 |
ノウレット 「機能なんて言わないでください!妖精です!!妖精なんですッ!!」 |
 |
ノウレット 「Cross+Roseのことで分からないことは何でも聞いてくださいねーっ!!」 |
 |
白南海 「あぁ、どっちかというとアレですか。"お前を消す方法"・・・みたいな。」 |
 |
ノウレット 「よくご存知でーっ!!そうです!多分それでーっす!!!!」 |
元気よく両手両足を伸ばし空間を飛びまわる!
 |
ノウレット 「えーっとそれでですねーッ!!」 |
 |
ノウレット 「・・・・・あれっ 創造主さまからメッセージが!」 |
 |
白南海 「おや、なんでしょうね。」 |
・・・姿を現すことなく、女性のような声が伝わる。
 |
声 「――お疲れ様です御二方。役目を担ってくれて、感謝しています。」 |
 |
白南海 「担うも何も、強制ですけどね。報酬でも頂きたいくらいで。」 |
 |
声 「そしてハザマに招かれた方々、申し訳ありません。」 |
 |
声 「・・・・・・・・・」 |
 |
声 「このワールドスワップという能力は、招かれた方々全員が――ザザッ・・・」 |
 |
声 「――失われ、そう――ザザッ・・・――周期的に発動する、能力というより・・・」 |
 |
声 「制御不能な・・・呪いのよう。今までに発動した数度、自分への利は・・・ない。」 |
 |
声 「・・・・・・・・・」 |
ため息のような音が漏れる。
 |
声 「どうか、自らが自らであ―― ザザッ・・・」 |
 |
白南海 「・・・・・?」 |
 |
声 「――ザザッ・・・・・・・・己の世界のために、争え。」 |
声はそこで終わる。
 |
白南海 「何だか変なふうに終わりましたねぇ。」 |
 |
ノウレット 「そうですかーっ!!?そうでもないですよーっ!!!?」 |
 |
白南海 「どーも、嫌な予感が・・・ ・・・いや、十分嫌な状況ではありますがね。」 |
 |
白南海 「・・・・・ま、とりあえずやれることやるだけっすね。」 |
チャットが閉じられる――



ENo.1302
壁に耳あり正直メアリー



「ワタシこの国のコトワザに感銘を受けたネ!」
メアリーと名乗る雑誌記者は快活な声で語る。
「壁に耳あり正直メアリー、それまさにワタシのことネ!」
どうやら聞きかじったことわざを間違って覚えているようだ。
「噂話集めるの得意! ワタシ嘘つかない! この国で記者やるワタシの運命!」
そう言って彼女はろくに取材もせずに帰って行った。なぜ新聞記者じゃなくて雑誌記者なのだろうという疑問も、何となく理解出来た。
金髪に碧眼、胸も大きい陽気な外国人記者に取材を申し込まれた店主は、最初こそ鼻の下を伸ばしていたが、その勢いと適当さに少し引き気味になりながら、なんとか取材を乗り切った。
後日発売された雑誌には当たり障りのない紹介と、間違ってはいないが適当な文言が並んでいたのであった。
――――――――――――――――
「だっるぅ~」
メアリーはため息と共にドアをしめると、ソファベッドにカバンを放り投げ、ジャケットを脱ぎ捨て、胸元からパッドを雑に抜き取った。
洗面台に向かい、カラーコンタクトを外すと、馴染み深いグレーの瞳が鏡越しに髪の毛を捉える。
「あ~、根元ちょっと茶色が見えてんじゃん、また染めないと。傷むんだよなぁ、髪も財布も。めんどくさいな~」
彼女の名はマリー・オブライエン。違った、メアリー・オード。正直メアリーの名で親しまれているアイルランド系アメrじゃないオーストラリア系移民である。
正直者で嘘のつけない彼女は偶然耳にしたコトワザに感銘を受けてこの国にやってきたという事になっている。
小さな出版社でローカル雑誌の記者として薄給で働いている。
雑誌の給料だけでは家賃が払えないため、タウン誌にヘルプの記者として記事を書かせて貰う事もある。
蓄えは前の仕事でたんまりと溜め込んだので困ってはいないが、派手に使うと足が付くので節制を心がけているというしっかり者だ。
「頭の残念なアホ外人のふりしてりゃ、ノリで押し切れんだから、良い国だよねホント」
笑顔が朗らかで人の良さが滲み出ていると評判の彼女は、不思議と私生活を明かさない。明かせるはずがない。
「そういや、そろそろ証明写真撮りに行かなきゃダメだっけ? めんどくさいな~。いっそ身分証明書に証明写真なくても良いんじゃないの?」
そんなわけでプロフ絵はないのである。
「写真あってもそれが本当にメアリーかなんて証明できないんだし」
おっとそこまでだ。
メアリーと名乗る雑誌記者は快活な声で語る。
「壁に耳あり正直メアリー、それまさにワタシのことネ!」
どうやら聞きかじったことわざを間違って覚えているようだ。
「噂話集めるの得意! ワタシ嘘つかない! この国で記者やるワタシの運命!」
そう言って彼女はろくに取材もせずに帰って行った。なぜ新聞記者じゃなくて雑誌記者なのだろうという疑問も、何となく理解出来た。
金髪に碧眼、胸も大きい陽気な外国人記者に取材を申し込まれた店主は、最初こそ鼻の下を伸ばしていたが、その勢いと適当さに少し引き気味になりながら、なんとか取材を乗り切った。
後日発売された雑誌には当たり障りのない紹介と、間違ってはいないが適当な文言が並んでいたのであった。
――――――――――――――――
「だっるぅ~」
メアリーはため息と共にドアをしめると、ソファベッドにカバンを放り投げ、ジャケットを脱ぎ捨て、胸元からパッドを雑に抜き取った。
洗面台に向かい、カラーコンタクトを外すと、馴染み深いグレーの瞳が鏡越しに髪の毛を捉える。
「あ~、根元ちょっと茶色が見えてんじゃん、また染めないと。傷むんだよなぁ、髪も財布も。めんどくさいな~」
彼女の名はマリー・オブライエン。違った、メアリー・オード。正直メアリーの名で親しまれているアイルランド系アメrじゃないオーストラリア系移民である。
正直者で嘘のつけない彼女は偶然耳にしたコトワザに感銘を受けてこの国にやってきたという事になっている。
小さな出版社でローカル雑誌の記者として薄給で働いている。
雑誌の給料だけでは家賃が払えないため、タウン誌にヘルプの記者として記事を書かせて貰う事もある。
蓄えは前の仕事でたんまりと溜め込んだので困ってはいないが、派手に使うと足が付くので節制を心がけているというしっかり者だ。
「頭の残念なアホ外人のふりしてりゃ、ノリで押し切れんだから、良い国だよねホント」
笑顔が朗らかで人の良さが滲み出ていると評判の彼女は、不思議と私生活を明かさない。明かせるはずがない。
「そういや、そろそろ証明写真撮りに行かなきゃダメだっけ? めんどくさいな~。いっそ身分証明書に証明写真なくても良いんじゃないの?」
そんなわけでプロフ絵はないのである。
「写真あってもそれが本当にメアリーかなんて証明できないんだし」
おっとそこまでだ。
20 / 30
38 PS
チナミ区
E-13
E-13





































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | タクティカルえんぴつ | 武器 | 30 | 攻撃10 | - | - | 【射程1】 |
| 5 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]防御10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) | |||
| 6 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 8 | 花びら | 素材 | 10 | [武器]混乱10(LV25)[防具]舞魅10(LV10)[装飾]祝福10(LV20) | |||
| 9 | 不思議な雫 | 素材 | 10 | [武器]水纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV10)[装飾]耐水10(LV20) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 25 | 身体/武器/物理 |
| 武器 | 25 | 武器作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 | |
| チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 | |
| イレイザー | 5 | 0 | 100 | 敵傷:攻撃 | |
| ハードブレイク | 5 | 1 | 120 | 敵:攻撃 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 |
最大EP[20]





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]リザレクション | [ 1 ]ダウンフォール | [ 1 ]イービルサークル |

PL / Crymson