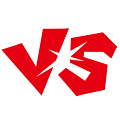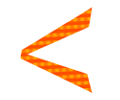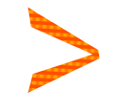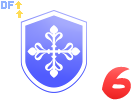<< 0:00~0:00




眠りから覚醒した神父は、そこが自室のベッドでないことにまず驚いた。
横たわった背中から伝わってくるのは地面の冷たさだ。
目だけを動かして周囲を見回してみれば、荒廃した世界がどこまでも広がっているように見える。
何故かズキズキと痛む頭を押さえながら起き上がれば、空気の匂いや空の色、何もかもが見知った街とは違っている。
そこが元居た世界と違う空間であることは嫌というほど理解出来た。
何故自分はこんな場所に。
動揺を抑えながら一つ一つ遡ろうとするも記憶が混濁しており上手く思い出せない。ごくりと唾を飲み込めば、酷く喉が渇いていることに気付く。
確か昨日は日曜のミサを行って、信徒の人々と会話を……
昨日話した人の名が、どうしても思い出せなかった。
寒気のようなものが背筋を這い上がる。
それを振り払うように周囲の確認を再開した。
どうやら教会の裏庭に居るらしい。
しかしそこに植えたばかりのはずの苗は影も形も無く、赤茶けた乾燥土があるのみだ。
白い輝きを放っているはずの教会の壁には亀裂が走り、煤のような黒い汚れに塗れている。
尖塔に掲げられていた十字架は、根元からもげてその名残すら残していない。
自分が守ってきた物が、須らく蹂躙されていた。
まさか。あれは幻覚ではなかったというのか。
脳裏に過ぎるのは、数日前に届いた謎の声だ。
侵略者、アンジニティ。
世界が入れ替わる。
そんな絵空事のような話が、俄かに現実味を帯びてきた。
侵略は団体殲滅戦、という案内人のような男の言葉が頭の中で繰り返される。
殲滅戦、ということは戦えと言うのだろうか。
ただの聖職者である自分に戦闘の心得は無い。
人ならざる存在に襲い掛かられては、勝つどころか生き残れるかどうかすら定かではなかった。
しかし。
神父の胸中に飛来した感情は恐怖だけではなかった。
侵略が達成されてしまえば何が起こるのか、全て理解出来てはいないだろう。
だが今のこの世界がほとんど消えて無くなるような激変が訪れるのは本能的に悟っていた。
それは冒涜だ。この世界を作った神への反逆。
神父が信じて歩んできた道を頭から否定するような行いである。
看過する事は出来なかった。
……この世界に生きる人々を、守りたかった。



ENo.233 阿闍砂 陽炎 とのやりとり

ENo.383 レオン とのやりとり




特に何もしませんでした。






幻術LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
百薬LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
防具LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)
ItemNo.6 不思議な食材 から料理『料理』をつくりました!
⇒ 料理/料理:強さ10/[効果1]- [効果2]- [効果3]-/特殊アイテム
ライトニング を習得!
ヒールポーション を習得!
ホーリーポーション を習得!
ディム を習得!
ファーマシー を習得!
ホーリーウォーター を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





チナミ区 D-3(隔壁)には移動できません。
チナミ区 E-2(水地)には移動できません。
チナミ区 D-3(隔壁)には移動できません。
体調が全回復しました!
『チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》』へ採集に向かうことにしました!






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャットで時間が伝えられる。
グチャッとなったどこかのナレハテの映像をまじまじと見つめる白南海。
その背後から、突然タクシーが現れる!!
白南海のすぐ横を走り抜け、止まる。
タクシーの窓が開く。

帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。
窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。
白南海からのチャットが閉じられる――














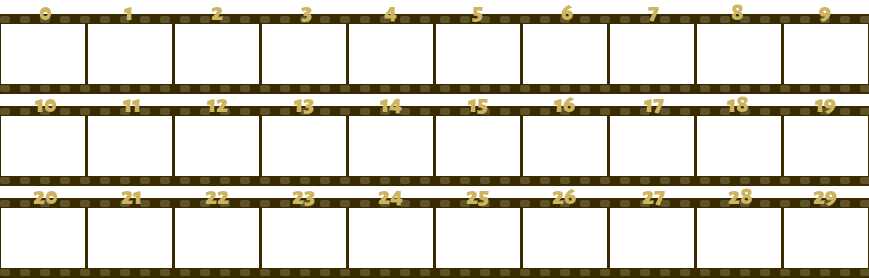





































異能・生産
アクティブ
パッシブ





[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



眠りから覚醒した神父は、そこが自室のベッドでないことにまず驚いた。
横たわった背中から伝わってくるのは地面の冷たさだ。
目だけを動かして周囲を見回してみれば、荒廃した世界がどこまでも広がっているように見える。
 |
古橋 「ここは……?」 |
何故かズキズキと痛む頭を押さえながら起き上がれば、空気の匂いや空の色、何もかもが見知った街とは違っている。
そこが元居た世界と違う空間であることは嫌というほど理解出来た。
何故自分はこんな場所に。
動揺を抑えながら一つ一つ遡ろうとするも記憶が混濁しており上手く思い出せない。ごくりと唾を飲み込めば、酷く喉が渇いていることに気付く。
確か昨日は日曜のミサを行って、信徒の人々と会話を……
 |
古橋 「……あれは誰だ?」 |
昨日話した人の名が、どうしても思い出せなかった。
寒気のようなものが背筋を這い上がる。
それを振り払うように周囲の確認を再開した。
どうやら教会の裏庭に居るらしい。
しかしそこに植えたばかりのはずの苗は影も形も無く、赤茶けた乾燥土があるのみだ。
白い輝きを放っているはずの教会の壁には亀裂が走り、煤のような黒い汚れに塗れている。
尖塔に掲げられていた十字架は、根元からもげてその名残すら残していない。
自分が守ってきた物が、須らく蹂躙されていた。
まさか。あれは幻覚ではなかったというのか。
脳裏に過ぎるのは、数日前に届いた謎の声だ。
侵略者、アンジニティ。
世界が入れ替わる。
そんな絵空事のような話が、俄かに現実味を帯びてきた。
侵略は団体殲滅戦、という案内人のような男の言葉が頭の中で繰り返される。
殲滅戦、ということは戦えと言うのだろうか。
ただの聖職者である自分に戦闘の心得は無い。
人ならざる存在に襲い掛かられては、勝つどころか生き残れるかどうかすら定かではなかった。
しかし。
神父の胸中に飛来した感情は恐怖だけではなかった。
侵略が達成されてしまえば何が起こるのか、全て理解出来てはいないだろう。
だが今のこの世界がほとんど消えて無くなるような激変が訪れるのは本能的に悟っていた。
それは冒涜だ。この世界を作った神への反逆。
神父が信じて歩んできた道を頭から否定するような行いである。
看過する事は出来なかった。
……この世界に生きる人々を、守りたかった。



ENo.233 阿闍砂 陽炎 とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.383 レオン とのやりとり
| ▲ |
| ||



特に何もしませんでした。





幻術LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
百薬LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
防具LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)
ItemNo.6 不思議な食材 から料理『料理』をつくりました!
⇒ 料理/料理:強さ10/[効果1]- [効果2]- [効果3]-/特殊アイテム
ライトニング を習得!
ヒールポーション を習得!
ホーリーポーション を習得!
ディム を習得!
ファーマシー を習得!
ホーリーウォーター を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





チナミ区 D-3(隔壁)には移動できません。
チナミ区 E-2(水地)には移動できません。
チナミ区 D-3(隔壁)には移動できません。
体調が全回復しました!
『チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》』へ採集に向かうことにしました!






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
白南海 「長針一周・・・っと。丁度1時間っすね。」 |

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
チャットで時間が伝えられる。
 |
白南海 「ケンカは無事済みましたかね。 こてんぱんにすりゃいいってわけですかい。」 |
グチャッとなったどこかのナレハテの映像をまじまじと見つめる白南海。
その背後から、突然タクシーが現れる!!
白南海のすぐ横を走り抜け、止まる。
 |
白南海 「・・・・・こ、殺す気ですかね。」 |
タクシーの窓が開く。

ドライバーさん
次元タクシーの運転手。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。初老くらいに見える。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。初老くらいに見える。
 |
ドライバーさん 「すまんすまん、出口の座標を少し間違えた。 挨拶に来たぜ。『次元タクシー』の運転役だ。」 |
帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。
 |
白南海 「イバラシティ側を潰そうってんじゃねぇでしょーね。・・・ぶっ殺しますよ?」 |
 |
ドライバーさん 「安心しな、どっちにも加勢するさ。俺らはそういう役割の・・・ハザマの機能ってとこだ。」 |
 |
ドライバーさん 「チェックポイントとかの行き来の際にゃ、へいタクシーの一声を。 俺もタクシーも同じのが沢山"在る"んでな、待たしゃしない。・・・そんじゃ。」 |
窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。
 |
白南海 「ひとを轢きかけといてあの態度・・・後で営業妨害でもしてやろうか。」 |
 |
白南海 「さて、それでは私は・・・のんびり傍観させてもらいますかね。この役も悪くない。」 |
白南海からのチャットが閉じられる――





ENo.972
古橋 献



古橋 献(ふるはし ささぐ)
カトリックツクナミ教会の神父
年齢 34歳
身長 182cm
職業 神父
誕生日 2月12日
黒髪・黒目・セミロング程度を一つ括り
【異能】
不浄なものを浄化する能力
ただし強い力は無く、普段は周囲の空気を綺麗にする程度
【性格】
不愛想な男で、笑顔を見せることも滅多と無い。
しかし職務に対しては非常に真摯に取り組み、教会を訪れる信徒からの信頼は厚い。
イラストはストイックな男メーカーさんにて制作させていただきました。
カトリックツクナミ教会の神父
年齢 34歳
身長 182cm
職業 神父
誕生日 2月12日
黒髪・黒目・セミロング程度を一つ括り
【異能】
不浄なものを浄化する能力
ただし強い力は無く、普段は周囲の空気を綺麗にする程度
【性格】
不愛想な男で、笑顔を見せることも滅多と無い。
しかし職務に対しては非常に真摯に取り組み、教会を訪れる信徒からの信頼は厚い。
イラストはストイックな男メーカーさんにて制作させていただきました。
30 / 30
5 PS
チナミ区
D-2
D-2





































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 不思議な牙 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV5)[防具]活力10(LV5)[装飾]体力10(LV5) | |||
| 5 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]防御10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) | |||
| 6 | 料理 | 料理 | 10 | - | - | - | |
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 幻術 | 10 | 夢幻/精神/光 |
| 百薬 | 10 | 化学/病毒/医術 |
| 防具 | 20 | 防具作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ライトニング | 5 | 0 | 50 | 敵:精確光撃 | |
| ヒールポーション | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+猛毒減 | |
| ホーリーポーション | 5 | 0 | 80 | 味傷:HP増+変調をLK化 | |
| ディム | 5 | 0 | 50 | 敵:SP光撃 | |
| ファーマシー | 5 | 0 | 110 | 味傷:HP増+肉体精神変調減 | |
| ホーリーウォーター | 5 | 0 | 80 | 敵腐:祝福+腐食状態なら精確光撃 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 |
最大EP[20]



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |

PL / なつき