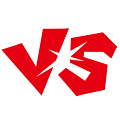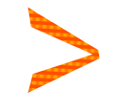<< 0:00~0:00




正方形の島一つをまるごと都市としたイバラシティ。
その十六区画の中でもっとも賑やかとされるツクナミ区の町並みが、黄金色の光に包まれてある。
波をまぶしく輝かせる海。その少し手前から悠々と影を落とすイバモールツクナミの本館ビル。今ごろ中では、従業員たちがせわしなく開店の準備をしていることだろう。
枝分かれして伸びる水路が、一つの区にすぎないこの地域をさらに分割している。かつては運河としても用いられたのであろうそれらは、トラックの類が一通り行き渡ってしまった今となっては単なる区切り以上のものではなくなりつつある。静々と流れる川の内側で白煙を立てるのは、しのぎを削りあうラーメン屋。あるいは、個人経営の小さな店舗も少なくない。それと、川沿いの桜をベランダから見られるのを売りにした住宅も。
たいていの人は、さほど驚きもしないだろう場所だった。その見てくれだけを伝えられたのであれば。
☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆
黒いニット帽を被り、マルーンのジャケットをまとった少年は、そんな町並みを見下ろしながら食事の支度をしていた。
五百ミリリットルのミネラルウォーターのボトルを片手鍋に注いでふたをする。それから無骨な折りたたみ携帯コンロを組み立て、真ん中にアルミホイルを敷いてから固形燃料を置き、マッチで火を灯す。寒さはきつくても風がないのは幸いだった。十数分ほどしてふんわり湯気を立てはじめたお湯の半分をマグカップへ注いだらインスタントコーヒーにし、残る半分にはコーンポタージュの粉を注ぐ。
あとは魚肉ソーセージが一本と、野菜ジュース。ここまでの全ては区内でしか知られてないようなミニスーパーのセールで調達してきたものだ。最後に一斤百円にも満たない食パンの一切れを小さくちぎって、コーンポタージュに放り込む。焼かずに食べるための工夫だった。
この町に家すら持たない彼が、なんとか身体をもたせるためのぎりぎりの食事だった。
彼は、ここツクナミ丘陵の展望台をねぐらにしていたのだ。設置されたトイレはいざとなれば雨風を防ぐためにも使えるし、夜になればそうそう人も来ない、都合のいい場所だった。
少年は早々に朝食を済ませるとバックパックを背負い、ツクナミ丘陵の山道を降りていった。
☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆
古びたビルの狭間、まだすっかり陰になっている中へ、若い男が駆け込んできた。
摂氏数度の空の下、上着の一つも着ていない彼は、保温性に優れるインナーウェアのおかげで鈍ることなく走り続けている。対して首から上は、鼻からあごまでも覆うマスクに、サングラス、ハンチング帽。手袋をした右手には、カーキ色の折り畳み財布を握りしめている。
男は時折後ろを振り返りながら走り続けているが、前への注意も怠ってはいないらしい。傍若無人に迫り出したゴミバケツや室外機をかわし、とうとう通路を塞いでしまってすらいるボロソファを踏んづけて大ジャンプ。両足でがっしりと着地をし、男は思わず自惚れた。
が、それが運の尽きだったのかもしれなかった。
ふと、何か柔らかなものが男の脚にひっかかれば、空中で半時計回りをやらせた挙げ句、背中を強かに打ちつけさせたのだった。
「っあいってェ……!」
衝撃で外れかけたマスクから呻きつつ、男は逆さになった大地に、自らを転ばせたものの姿をみた。
ぐにゃぐにゃのたるんだ塊が広がっている。
空気が抜けたビニールの玩具のようでもあったが、それにしては色がどうも不思議だった……薄ピンクの肌色なのだ。おまけに桃色の布のようなものが絡みついてもいる。もしかして、何かいかがわしい物だったのだろうか、とさえ考えてしまう。
そこへ―――バウッ、バウッ!
「ンッ!?」
男は上体を起こして前方を見やった。
T字の分岐路へと続く道の手前で、薄汚れた焦げ茶の犬が立ちはだかっていた……バウ! ワウッ!! まだ何もしてこない男を相手に、わめいている。
「なんだ、野良か……」
それならどうということはないのだ。男は立ち上がろうとした。
が、できなかった。
左脚はくの字に曲がって地面を押しているのに、右はだらりと弛緩したままだ。
バウ! ワウ! ガゥッ!!
犬は、あいも変わらず吠え続けている……
「アァ!?」
突然のことだった。上半身を支えていた左腕が力を失い、男は再び地面に打たれた。
そのまま、左腕は右脚と同じく、ぐったりと動かない。
男は脂汗をたらしながら右手で左腕に触れてみる……それは、あまりにも柔らかすぎていた。
男は、もう一度だけ、後ろを振り向く。
あの肌色の塊……その表面に、毛穴を、認めてしまった。
バウ、バウ、バウ、バウ……
野良犬が吠え続ける。その顔はどこか悦んでいるようにすら見える。
男の左脚が、右腕が―――端から崩れ落ちるように―――舗装のもとへ吸い込まれていく。
「―――アッ、いたッ!」
甲高い声がスッ飛んできた。
その主は前方のT字路の左側からきて、黒いニット帽を被り、インディゴブルーのジャケットをまとった少年だった。
「そこのォ! 財布!」
まだ声変わりしたての少年の叫びが路地裏に響く。
尻尾を振るいながら吠えまくっていた野良犬は、振り向くと、喉を鳴らした。
―――ウゥーッ!
「返して……ッ……!?」
少年は思わず足を止める。
つんのめりながらも踏みとどまれたのは、その脚にまだ芯が通っていたからだ。
―――ウゥーッ、ブルル……!
が、犬のうなりを前に、少年は進むことができない。踏み込んだ脚が音叉のように震え、それ以上の動きを妨げている。
「たっ……た、た、す、け……てェ!」
男の悲鳴が少年には聞こえて、犬の向こう側にも目を向けさせる。
仰向けになった男。四肢はだらりと投げ出され、ゴム人形のようにぐんにゃりとしている。
脳に規定された形と明らかに異なるそれは、少年に軽く動悸を起こさせた。
さらにその先には、たるんだ肉塊。
「う、ウッ……!」
少年の震えはいまや上半身にまで伝わっていた……しかし不随意でなく、右手を腰のあたりでわきわきと動かしてもいた。
左腕は横へと広げ、背筋を伸ばし―――己をどうにか大きく見せようと試みつつ。
が、野良犬はとうとう頭をあげ、喉をふるわせかかる。
その、まさに、一瞬のうちに。
―――パッ!!
乾いた音が、路地裏に、ひとつ……
犬はビクンと緊張し、振戦をおこしたかと思うと、まもなく横倒しとなった。
血溜まりができたりはしなかった。
驚くひまもなく、少年は駆け寄ってくるものを認めた。
肉塊と倒れた男を避けてやってくる彼は、自分のようにニット帽を被り、暗い赤のあるジャケットをしている。
その両手は小さく煙をたてる拳銃を支えていたが、すぐにホルスターの中に戻してしまった。そのまま、舌を出したまま倒れている犬の近くまで来たら、空けた右腕で抱え上げようとする。
「あ、あの……!」
青いジャケットの少年はやっとの思いで声をかけた。
が、赤いジャケットの少年は振り向きもせず、犬を担いでここを去ろうとしているらしかった。
「そ、そのワンコ、きみのか!?」
返事はない。赤ジャケットの左手は、なにかを探して懐に伸びる。
「そいつのせいなの!? あそこの人、骨抜きにされてンだぞ……!」
必死さを増して訴えかけても赤の少年は動作をやめない。彼の左手はすでに、ジャケットの中から丸いカプセルを取り出していた。白い表面に赤い線が一本走っているのが見えた。
「……応えてよ!! 聞いてンだろッ!!」
腹の底からの叫びが、赤の少年の背中を叩いた。
……そして、力なく垂れる、野良犬の頭をも。
―――グワゥッ!
起き抜けの、ひと吠え!
それは、まっすぐに、赤の少年の踏み込んだ右足首を震わせて……その機能を停止させた。
勢いのままにぐにゃりと変形していくように、青の少年には見える。
それが、確信となった。
犬は傾いでいく少年の腕の中から抜け出ると、再び大地に立った。
そのまま、尻尾を巻いて逃げ去るでもなく……貪欲によだれを垂らして、青の少年に睨みかかっている。
「お、オマエ……ッ!」
何かをしなくてはならない。
青の少年に、あらゆるものの流れが遅くなって思える。
この骨抜き犬に対して、一瞬のうちに、何かを!
「―――フゥゥッ!」
掌を、突き出す!
足元の舗装、左右のコンクリートが、一斉に分厚いほこりを発したかと思うと、とたんに全てが青の少年の手の中へと凝集する。
それは、宇宙のブラックホールがガスを吸い上げる様にも似ていた。
「ツァァッ!!」
ジィンッ!!
金属を激しくこすりあわせたような音とともに、青白い光芒が顕れ、少年の手と地面とを繋いだ。
犬の喉と胴とが、その線分の上に在った……
―――パァン!!
四脚の身体が、鮮血を撒き散らして、炸裂した。
「なんだァ!?」
流血に汚されたビルの住民たちは、ただならぬものを感じて窓を開け下に目をやる。
「ウッ!」
「人が倒れてる!!」
「血まみれだ!!」
「何よこれ、殺し!?」
降り注ぐ悲鳴と怒号。
その中で、倒れたままだった赤の少年は、一度はおさめた銃を握り直すと、転ぶ際に放り出したあのカプセルを撃った。
ブシューッ!!
銃弾で穴の空いたカプセルは猛烈な勢いで白いガスを噴射し、あたりを満たした。
比重は、空気よりも軽いらしい。すぐにベランダで騒ぎ立てる市民も巻き込まれていった。
やがてガスが晴れた時、赤の少年の姿はなかった。
☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆
まだ日が登りきらないせいで、路地裏は暗い。
青いジャケットを着た少年は苦しそうに頭を抱えつつ、立ち上がる。
目の前には、小さな血溜まり。その先に、手足がミミズみたいにぐにゃぐにゃになったままピクリとも動かない男と、なにかの塊。
少年は思わず、口元を押さえる。
「な……何さ、これ……ッ!」
心臓が激しく脈打つ。胸に触れてもいないのにはっきりと感じられるほどだ。
そこへさらに、
「人が倒れてる!!」
「あそこ! 血まみれじゃんか!!」
「ひぇッ!? 殺しか!?」
上の住民たちから悲鳴が飛んできた。
そのけたたましい声が、少年の脳をゆさぶった。
―――さっきも、この人達は、同じようなことを言っていたぞ……。
そうとわかったとたんに、少年はその場から駆け出していた。
☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆
赤いジャケットの少年は、川と直角に伸びる鉄道橋の下、コンクリートの塊にもたれかかっていた。
すでに日は高く登り、傾きつつあるところだが、人の気配はあまりない。
ここコヌマ区はツクナミ区の北側に位置し、イバラシティの中でも特に自然を多く残した地域として知られていた。
やや南西に位置する『小沼』をはじめとし、ラフティングが楽しめる川もあり、休日にはキャンプ場が賑わう。が、今はほとんどの人が会社や学校にいる時間だ。こんな場所を訪れる者は少ない。
手元には、松葉杖代わりにゴミ捨て場から拝借した物干し竿が二本。それから昼食としたパンの袋と牛乳のパック。
赤ジャケットの少年は疲れから眠りにつき、しばらくは起きる様子もない……はずだった。
「ねえ、きみ……」
そうならなかったのは、あの青いジャケットの少年が、気がつくと目の前に立っていたからだ。
―――なぜ、ここに?
赤ジャケットの少年は、青いほうの少年に鋭く冷たい視線を向ける。
言葉はない。
「……きみは……きみは、何者だ!?」
青いジャケットの少年は、震えながら、問うた。
瓜二つの顔が、向き合う。




特に何もしませんでした。






魔術LV を 15 UP!(LV0⇒15、-15CP)
響鳴LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
武器LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
付加LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
ItemNo.4 不思議な牙 から射程1の武器『SRmkVI』を作製しました!
⇒ SRmkVI/武器:強さ20/[効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程1】/特殊アイテム
不幸喰らい(546) の持つ ItemNo.5 不思議な石 から射程1の武器『罪悪滔天』を作製しました!
リリア(4) とカードを交換しました!
ダメージアブソーバー (ヒール)


ティンダー を研究しました!(深度0⇒1)
ファイアダンス を研究しました!(深度0⇒1)
ファイアレイド を研究しました!(深度0⇒1)
ティンダー を習得!
エチュード を習得!
ファイアダンス を習得!
ファイアボルト を習得!
☆火の祝福 を習得!
☆初習得ボーナス:各FPが2増加した!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





次元タクシーに乗り チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》 に転送されました!
チナミ区 E-6(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 E-7(道路)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 E-8(道路)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 E-9(草原)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 F-9(沼地)に移動!(体調26⇒25)
不幸喰らい(546) からパーティに勧誘されました!
採集はできませんでした。
- 一穂(3) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- シエ(11) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- アクドイナー(51) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- 不幸喰らい(546) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャットで時間が伝えられる。
グチャッとなったどこかのナレハテの映像をまじまじと見つめる白南海。
その背後から、突然タクシーが現れる!!
白南海のすぐ横を走り抜け、止まる。
タクシーの窓が開く。

帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。
窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。
白南海からのチャットが閉じられる――

















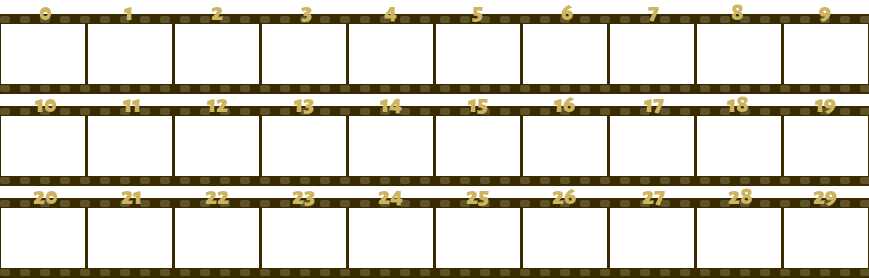





































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



正方形の島一つをまるごと都市としたイバラシティ。
その十六区画の中でもっとも賑やかとされるツクナミ区の町並みが、黄金色の光に包まれてある。
波をまぶしく輝かせる海。その少し手前から悠々と影を落とすイバモールツクナミの本館ビル。今ごろ中では、従業員たちがせわしなく開店の準備をしていることだろう。
枝分かれして伸びる水路が、一つの区にすぎないこの地域をさらに分割している。かつては運河としても用いられたのであろうそれらは、トラックの類が一通り行き渡ってしまった今となっては単なる区切り以上のものではなくなりつつある。静々と流れる川の内側で白煙を立てるのは、しのぎを削りあうラーメン屋。あるいは、個人経営の小さな店舗も少なくない。それと、川沿いの桜をベランダから見られるのを売りにした住宅も。
たいていの人は、さほど驚きもしないだろう場所だった。その見てくれだけを伝えられたのであれば。
☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆
黒いニット帽を被り、マルーンのジャケットをまとった少年は、そんな町並みを見下ろしながら食事の支度をしていた。
五百ミリリットルのミネラルウォーターのボトルを片手鍋に注いでふたをする。それから無骨な折りたたみ携帯コンロを組み立て、真ん中にアルミホイルを敷いてから固形燃料を置き、マッチで火を灯す。寒さはきつくても風がないのは幸いだった。十数分ほどしてふんわり湯気を立てはじめたお湯の半分をマグカップへ注いだらインスタントコーヒーにし、残る半分にはコーンポタージュの粉を注ぐ。
あとは魚肉ソーセージが一本と、野菜ジュース。ここまでの全ては区内でしか知られてないようなミニスーパーのセールで調達してきたものだ。最後に一斤百円にも満たない食パンの一切れを小さくちぎって、コーンポタージュに放り込む。焼かずに食べるための工夫だった。
この町に家すら持たない彼が、なんとか身体をもたせるためのぎりぎりの食事だった。
彼は、ここツクナミ丘陵の展望台をねぐらにしていたのだ。設置されたトイレはいざとなれば雨風を防ぐためにも使えるし、夜になればそうそう人も来ない、都合のいい場所だった。
少年は早々に朝食を済ませるとバックパックを背負い、ツクナミ丘陵の山道を降りていった。
☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆
古びたビルの狭間、まだすっかり陰になっている中へ、若い男が駆け込んできた。
摂氏数度の空の下、上着の一つも着ていない彼は、保温性に優れるインナーウェアのおかげで鈍ることなく走り続けている。対して首から上は、鼻からあごまでも覆うマスクに、サングラス、ハンチング帽。手袋をした右手には、カーキ色の折り畳み財布を握りしめている。
男は時折後ろを振り返りながら走り続けているが、前への注意も怠ってはいないらしい。傍若無人に迫り出したゴミバケツや室外機をかわし、とうとう通路を塞いでしまってすらいるボロソファを踏んづけて大ジャンプ。両足でがっしりと着地をし、男は思わず自惚れた。
が、それが運の尽きだったのかもしれなかった。
ふと、何か柔らかなものが男の脚にひっかかれば、空中で半時計回りをやらせた挙げ句、背中を強かに打ちつけさせたのだった。
「っあいってェ……!」
衝撃で外れかけたマスクから呻きつつ、男は逆さになった大地に、自らを転ばせたものの姿をみた。
ぐにゃぐにゃのたるんだ塊が広がっている。
空気が抜けたビニールの玩具のようでもあったが、それにしては色がどうも不思議だった……薄ピンクの肌色なのだ。おまけに桃色の布のようなものが絡みついてもいる。もしかして、何かいかがわしい物だったのだろうか、とさえ考えてしまう。
そこへ―――バウッ、バウッ!
「ンッ!?」
男は上体を起こして前方を見やった。
T字の分岐路へと続く道の手前で、薄汚れた焦げ茶の犬が立ちはだかっていた……バウ! ワウッ!! まだ何もしてこない男を相手に、わめいている。
「なんだ、野良か……」
それならどうということはないのだ。男は立ち上がろうとした。
が、できなかった。
左脚はくの字に曲がって地面を押しているのに、右はだらりと弛緩したままだ。
バウ! ワウ! ガゥッ!!
犬は、あいも変わらず吠え続けている……
「アァ!?」
突然のことだった。上半身を支えていた左腕が力を失い、男は再び地面に打たれた。
そのまま、左腕は右脚と同じく、ぐったりと動かない。
男は脂汗をたらしながら右手で左腕に触れてみる……それは、あまりにも柔らかすぎていた。
男は、もう一度だけ、後ろを振り向く。
あの肌色の塊……その表面に、毛穴を、認めてしまった。
バウ、バウ、バウ、バウ……
野良犬が吠え続ける。その顔はどこか悦んでいるようにすら見える。
男の左脚が、右腕が―――端から崩れ落ちるように―――舗装のもとへ吸い込まれていく。
「―――アッ、いたッ!」
甲高い声がスッ飛んできた。
その主は前方のT字路の左側からきて、黒いニット帽を被り、インディゴブルーのジャケットをまとった少年だった。
「そこのォ! 財布!」
まだ声変わりしたての少年の叫びが路地裏に響く。
尻尾を振るいながら吠えまくっていた野良犬は、振り向くと、喉を鳴らした。
―――ウゥーッ!
「返して……ッ……!?」
少年は思わず足を止める。
つんのめりながらも踏みとどまれたのは、その脚にまだ芯が通っていたからだ。
―――ウゥーッ、ブルル……!
が、犬のうなりを前に、少年は進むことができない。踏み込んだ脚が音叉のように震え、それ以上の動きを妨げている。
「たっ……た、た、す、け……てェ!」
男の悲鳴が少年には聞こえて、犬の向こう側にも目を向けさせる。
仰向けになった男。四肢はだらりと投げ出され、ゴム人形のようにぐんにゃりとしている。
脳に規定された形と明らかに異なるそれは、少年に軽く動悸を起こさせた。
さらにその先には、たるんだ肉塊。
「う、ウッ……!」
少年の震えはいまや上半身にまで伝わっていた……しかし不随意でなく、右手を腰のあたりでわきわきと動かしてもいた。
左腕は横へと広げ、背筋を伸ばし―――己をどうにか大きく見せようと試みつつ。
が、野良犬はとうとう頭をあげ、喉をふるわせかかる。
その、まさに、一瞬のうちに。
―――パッ!!
乾いた音が、路地裏に、ひとつ……
犬はビクンと緊張し、振戦をおこしたかと思うと、まもなく横倒しとなった。
血溜まりができたりはしなかった。
驚くひまもなく、少年は駆け寄ってくるものを認めた。
肉塊と倒れた男を避けてやってくる彼は、自分のようにニット帽を被り、暗い赤のあるジャケットをしている。
その両手は小さく煙をたてる拳銃を支えていたが、すぐにホルスターの中に戻してしまった。そのまま、舌を出したまま倒れている犬の近くまで来たら、空けた右腕で抱え上げようとする。
「あ、あの……!」
青いジャケットの少年はやっとの思いで声をかけた。
が、赤いジャケットの少年は振り向きもせず、犬を担いでここを去ろうとしているらしかった。
「そ、そのワンコ、きみのか!?」
返事はない。赤ジャケットの左手は、なにかを探して懐に伸びる。
「そいつのせいなの!? あそこの人、骨抜きにされてンだぞ……!」
必死さを増して訴えかけても赤の少年は動作をやめない。彼の左手はすでに、ジャケットの中から丸いカプセルを取り出していた。白い表面に赤い線が一本走っているのが見えた。
「……応えてよ!! 聞いてンだろッ!!」
腹の底からの叫びが、赤の少年の背中を叩いた。
……そして、力なく垂れる、野良犬の頭をも。
―――グワゥッ!
起き抜けの、ひと吠え!
それは、まっすぐに、赤の少年の踏み込んだ右足首を震わせて……その機能を停止させた。
勢いのままにぐにゃりと変形していくように、青の少年には見える。
それが、確信となった。
犬は傾いでいく少年の腕の中から抜け出ると、再び大地に立った。
そのまま、尻尾を巻いて逃げ去るでもなく……貪欲によだれを垂らして、青の少年に睨みかかっている。
「お、オマエ……ッ!」
何かをしなくてはならない。
青の少年に、あらゆるものの流れが遅くなって思える。
この骨抜き犬に対して、一瞬のうちに、何かを!
「―――フゥゥッ!」
掌を、突き出す!
足元の舗装、左右のコンクリートが、一斉に分厚いほこりを発したかと思うと、とたんに全てが青の少年の手の中へと凝集する。
それは、宇宙のブラックホールがガスを吸い上げる様にも似ていた。
「ツァァッ!!」
ジィンッ!!
金属を激しくこすりあわせたような音とともに、青白い光芒が顕れ、少年の手と地面とを繋いだ。
犬の喉と胴とが、その線分の上に在った……
―――パァン!!
四脚の身体が、鮮血を撒き散らして、炸裂した。
「なんだァ!?」
流血に汚されたビルの住民たちは、ただならぬものを感じて窓を開け下に目をやる。
「ウッ!」
「人が倒れてる!!」
「血まみれだ!!」
「何よこれ、殺し!?」
降り注ぐ悲鳴と怒号。
その中で、倒れたままだった赤の少年は、一度はおさめた銃を握り直すと、転ぶ際に放り出したあのカプセルを撃った。
ブシューッ!!
銃弾で穴の空いたカプセルは猛烈な勢いで白いガスを噴射し、あたりを満たした。
比重は、空気よりも軽いらしい。すぐにベランダで騒ぎ立てる市民も巻き込まれていった。
やがてガスが晴れた時、赤の少年の姿はなかった。
☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆
まだ日が登りきらないせいで、路地裏は暗い。
青いジャケットを着た少年は苦しそうに頭を抱えつつ、立ち上がる。
目の前には、小さな血溜まり。その先に、手足がミミズみたいにぐにゃぐにゃになったままピクリとも動かない男と、なにかの塊。
少年は思わず、口元を押さえる。
「な……何さ、これ……ッ!」
心臓が激しく脈打つ。胸に触れてもいないのにはっきりと感じられるほどだ。
そこへさらに、
「人が倒れてる!!」
「あそこ! 血まみれじゃんか!!」
「ひぇッ!? 殺しか!?」
上の住民たちから悲鳴が飛んできた。
そのけたたましい声が、少年の脳をゆさぶった。
―――さっきも、この人達は、同じようなことを言っていたぞ……。
そうとわかったとたんに、少年はその場から駆け出していた。
☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆ ○ ☆
赤いジャケットの少年は、川と直角に伸びる鉄道橋の下、コンクリートの塊にもたれかかっていた。
すでに日は高く登り、傾きつつあるところだが、人の気配はあまりない。
ここコヌマ区はツクナミ区の北側に位置し、イバラシティの中でも特に自然を多く残した地域として知られていた。
やや南西に位置する『小沼』をはじめとし、ラフティングが楽しめる川もあり、休日にはキャンプ場が賑わう。が、今はほとんどの人が会社や学校にいる時間だ。こんな場所を訪れる者は少ない。
手元には、松葉杖代わりにゴミ捨て場から拝借した物干し竿が二本。それから昼食としたパンの袋と牛乳のパック。
赤ジャケットの少年は疲れから眠りにつき、しばらくは起きる様子もない……はずだった。
「ねえ、きみ……」
そうならなかったのは、あの青いジャケットの少年が、気がつくと目の前に立っていたからだ。
―――なぜ、ここに?
赤ジャケットの少年は、青いほうの少年に鋭く冷たい視線を向ける。
言葉はない。
「……きみは……きみは、何者だ!?」
青いジャケットの少年は、震えながら、問うた。
瓜二つの顔が、向き合う。




特に何もしませんでした。





魔術LV を 15 UP!(LV0⇒15、-15CP)
響鳴LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
武器LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
付加LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
ItemNo.4 不思議な牙 から射程1の武器『SRmkVI』を作製しました!
⇒ SRmkVI/武器:強さ20/[効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程1】/特殊アイテム
不幸喰らい(546) の持つ ItemNo.5 不思議な石 から射程1の武器『罪悪滔天』を作製しました!
リリア(4) とカードを交換しました!
ダメージアブソーバー (ヒール)


ティンダー を研究しました!(深度0⇒1)
ファイアダンス を研究しました!(深度0⇒1)
ファイアレイド を研究しました!(深度0⇒1)
ティンダー を習得!
エチュード を習得!
ファイアダンス を習得!
ファイアボルト を習得!
☆火の祝福 を習得!
☆初習得ボーナス:各FPが2増加した!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





次元タクシーに乗り チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》 に転送されました!
 |
ドライバーさん 「ちと雑だったかね。次元酔いは大丈夫か?」 |
チナミ区 E-6(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 E-7(道路)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 E-8(道路)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 E-9(草原)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 F-9(沼地)に移動!(体調26⇒25)
不幸喰らい(546) からパーティに勧誘されました!
採集はできませんでした。
- 一穂(3) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- シエ(11) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- アクドイナー(51) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- 不幸喰らい(546) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
白南海 「長針一周・・・っと。丁度1時間っすね。」 |

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
チャットで時間が伝えられる。
 |
白南海 「ケンカは無事済みましたかね。 こてんぱんにすりゃいいってわけですかい。」 |
グチャッとなったどこかのナレハテの映像をまじまじと見つめる白南海。
その背後から、突然タクシーが現れる!!
白南海のすぐ横を走り抜け、止まる。
 |
白南海 「・・・・・こ、殺す気ですかね。」 |
タクシーの窓が開く。

ドライバーさん
次元タクシーの運転手。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。初老くらいに見える。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。初老くらいに見える。
 |
ドライバーさん 「すまんすまん、出口の座標を少し間違えた。 挨拶に来たぜ。『次元タクシー』の運転役だ。」 |
帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。
 |
白南海 「イバラシティ側を潰そうってんじゃねぇでしょーね。・・・ぶっ殺しますよ?」 |
 |
ドライバーさん 「安心しな、どっちにも加勢するさ。俺らはそういう役割の・・・ハザマの機能ってとこだ。」 |
 |
ドライバーさん 「チェックポイントとかの行き来の際にゃ、へいタクシーの一声を。 俺もタクシーも同じのが沢山"在る"んでな、待たしゃしない。・・・そんじゃ。」 |
窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。
 |
白南海 「ひとを轢きかけといてあの態度・・・後で営業妨害でもしてやろうか。」 |
 |
白南海 「さて、それでは私は・・・のんびり傍観させてもらいますかね。この役も悪くない。」 |
白南海からのチャットが閉じられる――







決闘不成立!
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。

ENo.3
宮田一穂とK.M.



《宮田一穂(みやたかずほ)》
『すべてはいつの日か記号に還元されるでしょう』
・種族: 地球人(モンゴロイド)
・年齢:14歳/身長: 164cm/体重: 42kg/誕生日:10月3日
・特技:記憶すること/趣味:持たない/好物:特にない
イバラシティの片隅で路上生活を続ける少年。
言葉に抑揚が薄く、感情もほとんど示さない。ロボットのような印象を与えがちだが、優しさを見せないこともない。
赤いジャケットとニット帽を常に着用している。
その異能は『記憶』の異能。
自らの記憶を物体に焼き付けることができ、それを触れたものに記憶を『伝染』させ、自らのことのように感じさせる。代償として、焼き付けた記憶は本人の中から失われてしまう。
異能とは別にほぼ完璧な記憶力を持ち、先述の異能の代償やなにか異常なものの影響にさらされた場合をのぞいて物事を忘れるということがない。
武器として拳銃を一丁所持している。相当に使い慣れている模様。
どこか異なる場所から来たようで、帰り方を探している。
※遭遇したものに対しメモを取る場合がございます。もし、問題がございましたら、ご一報頂ければ削除いたします。
⇒http://lisge.com/ib/talk.php?p=1821
《K.M.(クリストファ・マルムクヴィスト)》
--- 詳細不明 ---
PL: 切り株(@BehindForestBoy)
『すべてはいつの日か記号に還元されるでしょう』
・種族: 地球人(モンゴロイド)
・年齢:14歳/身長: 164cm/体重: 42kg/誕生日:10月3日
・特技:記憶すること/趣味:持たない/好物:特にない
イバラシティの片隅で路上生活を続ける少年。
言葉に抑揚が薄く、感情もほとんど示さない。ロボットのような印象を与えがちだが、優しさを見せないこともない。
赤いジャケットとニット帽を常に着用している。
その異能は『記憶』の異能。
自らの記憶を物体に焼き付けることができ、それを触れたものに記憶を『伝染』させ、自らのことのように感じさせる。代償として、焼き付けた記憶は本人の中から失われてしまう。
異能とは別にほぼ完璧な記憶力を持ち、先述の異能の代償やなにか異常なものの影響にさらされた場合をのぞいて物事を忘れるということがない。
武器として拳銃を一丁所持している。相当に使い慣れている模様。
どこか異なる場所から来たようで、帰り方を探している。
※遭遇したものに対しメモを取る場合がございます。もし、問題がございましたら、ご一報頂ければ削除いたします。
⇒http://lisge.com/ib/talk.php?p=1821
《K.M.(クリストファ・マルムクヴィスト)》
--- 詳細不明 ---
PL: 切り株(@BehindForestBoy)
25 / 30
5 PS
チナミ区
F-9
F-9





































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | SRmkVI | 武器 | 20 | 攻撃10 | - | - | 【射程1】 |
| 5 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]防御10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) | |||
| 6 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 魔術 | 15 | 破壊/詠唱/火 |
| 響鳴 | 5 | 歌唱/音楽/振動 |
| 武器 | 10 | 武器作製に影響 |
| 付加 | 10 | 装備品への素材の付加に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ティンダー | 5 | 0 | 50 | 敵:火撃&炎上 | |
| エチュード | 5 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) | |
| ファイアダンス | 5 | 0 | 80 | 敵:2連火領撃&炎上+領域値[火]3以上なら、火領撃&炎上 | |
| ファイアボルト | 5 | 0 | 100 | 敵貫:火痛撃 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 火の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:魔術LVが高いほど火特性・耐性増 |
最大EP[20]





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]ティンダー | [ 1 ]ファイアダンス | [ 1 ]ファイアレイド |

PL / 切り株