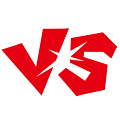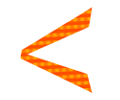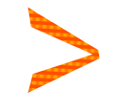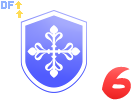<< 0:00~0:00




「――そこまでだ。」
男たちに囲まれた女性。
何も不思議な事ではない。
何時の世もある普通の光景――
もっとも日常とかけはなれたそれは、
男たちの欲望に歪んではいるが。
そんな中、1人の女性が男たちの背後から突然現れた。
その女はとにかく目を引く女性だった。
月光に煌めく銀の髪、
夜闇に輝くようなルビーの目。
男たちに負けぬほどその身の丈は高く、
そのシルエットですら分かるほど魅力的な肉体。
襲われている女性よりも、
情欲にそそられるその美貌、肉体。
獣欲に身を焦がす男たちの視線は、
たった一言で現れた銀髪の女へと集中し、
獲物が増えたと下卑た声で男たちは笑いあう。
「フッ……」
だが、銀髪の女は動じない。
笑いあう男たちを一笑に切って捨てる。
なんとくだらない奴らなのか。
そのうっすらと浮かべた妖艶な笑みは嘲けり、
男たちを見下すものだった。
もとより、短絡的に女を襲おうとしていた男たちだ。
たった一人の女ごときに侮られ、
怒りを堪えれるわけもなく、
己たちの力で抑えきれないなどという想像などもまた出来るはずもなかった。
見る見るうちに顔を真っ赤にして男たちは銀髪の女へと掴みかからんと駆け出した。
しかし、
そんな様子が見えているか、
否、それ以前に今の事態を理解していないのか……
女は微動だにしない。
ただ、嘲り、見下し続けているだけだ。
男たちと銀髪の女を遮るものがない以上、
男たちの手は見る見るうちに銀髪の女を捉え、
掴みとろうとした矢先――
女の姿は掻き消えた。
「なっ――!?」
「ど、どうなってやがる!」
「おい、女はどこに消えた!」
「知らねえよ!」
突然の思わぬ事態に混乱する男たち。
特殊な能力を持つものがいる。
そんな認識があれども、
何の予兆もなく、
あまりにも突然の出来事に対応できるものはなく、
慌てふためき辺りを見回し、
銀髪の女を探す事しかできない。
銀髪の女ははたしてどこへいったのか?
それを男たちが知るのはほんの僅かに後の事。
何故、ほんの僅かなのかというと――
「レディ、お手を。
麗しい貴女の身に、そして心に――
忌まわしき者たちの手で傷がついてしまう事なんて、
許される事ではない……
心配しないで、
貴女の騎士が今、やってまいりましたよ。」
何故なら銀髪の女は襲われ、
銀髪の女が現れた為に放置された女に対し、
恭しく、丁寧に、
愛しい者を見る目で、
愛しい者を見る口調で、
柔らかく微笑み、
男たちの姿などまるで存在しないかのように口説き、
手を差し伸べていたのだから。
逃げもしなければ立ち向かいもしない。
完全に無視したような銀髪の女を見つけれない等という道理はなかった。
「えっ?
あ、あの……その……
えっと……?」
そして、手を差し伸べられた女はというと、
突然の銀髪の女の登場、消失、出現――
そして、この行動である。
当然の如く混乱し、
何が起きているのか、
どうしてこうなっているのか、
――わずかばかりとはいえ助かった事なども分からず、
ただうろたえ、ためらい、
その視線は銀髪の女、虚空、男たちと定まる事なく揺れ動き、
手を取る事も出来ずに呆然とするばかり。
「手前――!」
「俺たちを無視するとはいい度胸だ!」
混乱から一早く立ち直ったのは誰あろう男たち。
もっとも……混乱よりも怒りが勝っただけだが。
再度、女目掛けて突撃する男たちに、
銀髪の女はめんどくさそうに――
本当にめんどくさそうに一瞥すると、
やれやれと肩をすくめ――
「ああ、無粋――
無粋にもほどがある。
せっかくにも……
襲われて怯える麗しいレディーをエスコートし、
救い――
ゆるりと楽しくい一時を享受し、
あわよくば甘美なる一時をも過ごそうと思っていたのに、
エスコートの最中でケチがつくとは――
まったく。
見逃された事にすら気づかぬのであれば、
こちらとて暴力に訴えるしかないか、
全く、スマートじゃないな。
だが、いいだろう。
その無粋なる罪はその実に刻んでもらうとしよう。
――そぉら!」
真っ先に掴みかかった男の腕をつかむと、
そのまま男を持ち上げ、
まるでこん棒か何かの如く一振りする。
――4人いた男達の二人が、
振られた男にぶち当たり、
骨の砕ける嫌な音を響かせながら吹き飛び、
同時に強い膂力によってただ一振りされ、
男たちのうち二人にぶつけられ、
全身が砕けるかのような感覚に涙し、
顔がぐちゃぐちゃになっている男に対し、
興味なさげにそのあたりに放り捨てた。
「えっ……?」
残された男一人は、
そのあまりの惨状が一瞬で作られた事に気づかず硬直し、
動きを止めた。
だが、銀髪の女の動きは止まらない。
瞬く間に距離を詰め、
残された男の瞳を覗き込む。
紅い、紅い瞳。
それは一瞬妖しく輝くと、
だらりと残された男の体が弛緩し、
呆けた表情となる。
「……お前の仲間のゴミ共を救急車でも呼んで連れ去れ。
そして、我達には関わるな。
同じ目にあいたくないならな。
おっと。
ひょっとしたら、この程度でも済まないかも知れないが……
ま、お前達次第だ。
いいな。」
銀髪の女の言葉に頷く男に、
興味を失ったように銀髪の女は襲われていた女の元へと舞い戻る。
「さ、無粋な者たちは去りました。
行きましょう、レディー。
あなたにこんな場は似合わない。
君は穏やかな日常で笑っているべきだ。
……」
そして何事もなかったかのように手を差し伸べるが、
襲われていた女は、
更に混乱した状態に陥っていた。
とりあえず助かったことは分かったのか、
手を伸ばそうとするも、
その手が途中で止まる。
当たり前といえば当たり前だろう。
さっきまで自分を襲っていた男達を、
存在しないかの如く無視し、
まるで塵芥の如く蹴散らしたのだ。
それも、
蹴散らし方も尋常じゃない。
まるで人をそこらの棒きれのように振り回したのだ。
恐怖に勝る恐怖。
柔らかな銀髪の女に安堵を覚え、
助けられた事を理解してなお、
その差し伸べられた手に対して本能に恐怖する。
混乱していなければ、
助けられた感謝をもってすぐにその手をつかんでいただろう。
どうしよう、どうするべきか。
襲われた女の取った行動は、
助けられたものにあるまじき行為。
だが、
人知を超えたバケモノに恐怖するがゆえに本能が巻き起こす行為……
――に、なるはずだった。
「――成程。
失礼。
こんな所に長々といるのはお互いにとってもよろしくないし、
気分も優れぬでしょう。
手を取るのもまってもいいのだが、
その御体に少し触れさせてもらうとしましょう。」
行動を起こす前にふわりと銀髪の女に抱き上げられる。
それは所謂お姫様抱っこというやつだ。
「えっ?えっ――!」
突然の行為、
突然の姿勢。
女同士とはいえ、
整った端正な顔立ちの美女に優しく微笑まれ、
まるで本当のお姫様になったかのような気分になり、
思わず襲われていた女の顔は朱に染まる。
それは、
先ほどまでの恐怖すらも払拭し、
ただ、ただ身を任せるしかできないほどに、
頭の中を沸騰させ――
「しっかり捕まっていてくださいね。
少々――
荒っぽくなるやもしれませんので。」
「は、はい……!」
優しく告げられる銀髪の女の言葉に素直に従い、
いわれたようにお姫様抱っこの体勢のままぎゅっとしがみつく事しかできなかった。
その様子に銀髪の女は満足し、
ビルを飛び越えるかのように高く――高く跳躍する。
「きゃっ……!」
思わずその衝撃にお姫様抱っこされた女は驚くが、
大丈夫と笑いかけるだけで銀髪の女は見る見るうちにビルを飛び越え、
ビルの上を駆け――
離れた所にある小さな公園へと着地し、
ベンチへと抱えた女を降ろした。
そして――
「……もう大丈夫ですよ。
駅の傍の公園です。
駅に関しても出ればすぐわかりますし、
人気も直ぐに多くなります。
どうにでもなるでしょう。
もちろん、
送って行って欲しいといわれればエスコートして送り返しますし、
お礼がしたいとあれば、
そうですね。
お茶にでも付き合っていただければ光栄です。」
助けられた女は、
大丈夫、安心してほしいと告げる銀髪の女に対し、
既に警戒はなく、
顔を真っ赤にしながらありがとうございますというように頭を下げるも――
帰るのか、
送って行って欲しいのか、
お茶に付き合うのか、
その問いには答えれなかった。
帰る……
というのは一番無難な選択肢だが、
助けてくれた女と二度とあえないような気もする。
お礼もきちんといえていないし、
縁が断たれるのは少し嫌な気がしたからだ。
ならば、送ってもらえばいい……
かというとどうだろうか。
助けてもらったとはいえ、
怖い部分が完全に消えたわけではなく、
それ以上にそれだけではもったいない欲がでたからだ。
ならば……
お茶をするというのも手ではあるが、
流石にあの状況から抜け出し、
今そんな気分にはなれなかったのと、
そこまでしてもいいのか、
迷いがあったからだ。
……そして、そんな混乱した頭に、
男たちに襲われた記憶がフラッシュバックする。
伸びる手、
情欲に満ちた瞳、
抗えぬ自分……
思わずぽろぽろと涙が零れ落ちた。
「おっと、レディに涙は似合わないな。
我のハンカチで――
……
…………?」
そんな突然泣き出した女に、
銀髪の女は優しく手を差し伸べるようにハンカチを取り出そうとする仕草をしたのち、
何か、探すように自分の体を探り始めた。
「……?」
なきながらも突然の事態に困惑する女。
不可解そうに銀髪の女を見やる。
じっと見ていると、
たとえようもなく困った顔で銀髪の女は告げた。
「……ハンカチ、家に忘れた……ようだ……
財布も……ない……」
世界が一瞬で凍りつき、
冷たい空気が流れる。
当たり前である。
この展開、
この流れでどうしてこんな事態を巻き起こせようか。
ここで、ハンカチを取り出せたなら決まっていただろう。
そうでなくても優しくするだけでよかった。
だが、これはない。
これは酷い……
が、
それが幸を奏したのか、
その一言で助けられた女の緊張の糸は切れた。
今までカッコよく助けてくれて、
それでいてバケモノのように強い彼女。
しかし、
蓋をあけてみるとどうだろう。
その風貌、その行為に見合わず、
ひょうきんというか抜けているというか……
人間らしさに触れたのだから。
「……ぷっ、クスクス!」
思わず口から笑いがこぼれる。
思わず大きな声で笑いそうになるのを必死でこらえる。
「うっ、わ、笑わないで欲しい……
いや、本当にこんなつもりじゃなかったんだ。
こう、さっとハンカチを出してお茶に誘うつもりだったんだ、
本当だぞ!」
そんな様子に非情に情けない顔をする銀髪の女はそういった。
必至で弁解する彼女の姿がまたおかしくて、
こらえきれずに大笑いする助けられた女。
今度は笑いでこぼれる涙を思わずぬぐい――
「そういう事なら奢らせてください。
助けてくれたお礼がしたいので。
近くのお店でいいですよね?
後は送ってくれると嬉しいです。」
もう少し彼女の事を知りたいななんてそう提案すると、
銀髪の女は嬉しそうに笑って、
胸をどんと叩き。
「!
ああ、ありがたい!
もちろんいいとも。
すまないな。不甲斐ない所をみせた。」
嬉しそうにそう答えた。
――銀髪の女の名は社 映美莉。
彼女がイバラシティの件に巻き込まれるのはもう少し後のお話。





特に何もしませんでした。






駄木(50 PS)を購入しようとしましたが、PSが足りませんでした。
駄石(50 PS)を購入しようとしましたが、PSが足りませんでした。
お肉(50 PS)を購入しようとしましたが、PSが足りませんでした。
魔術LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
使役LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
解析LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
付加LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
料理LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
五十嵐(1237) とカードを交換しました!
麺棒で、えいえい! (クイック)


リンクブレイク を研究しました!(深度0⇒1)
リンクブレイク を研究しました!(深度1⇒2)
リンクブレイク を研究しました!(深度2⇒3)
ティンダー を習得!
サステイン を習得!
プリディクション を習得!
アドレナリン を習得!
マジックミサイル を習得!
パワーブースター を習得!
魅惑 を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





次元タクシーに乗り チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》 に転送されました!
現在のパーティから離脱しました!
チナミ区 E-6(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 E-7(道路)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 E-8(道路)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 E-9(草原)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 D-9(草原)に移動!(体調26⇒25)
あかり(223) からパーティに勧誘されました!
採集はできませんでした。
- あかり(223) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- えみりん(1239) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャットで時間が伝えられる。
グチャッとなったどこかのナレハテの映像をまじまじと見つめる白南海。
その背後から、突然タクシーが現れる!!
白南海のすぐ横を走り抜け、止まる。
タクシーの窓が開く。

帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。
窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。
白南海からのチャットが閉じられる――
















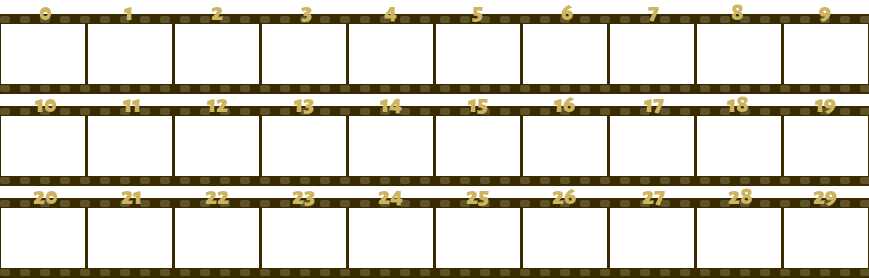





































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



「――そこまでだ。」
男たちに囲まれた女性。
何も不思議な事ではない。
何時の世もある普通の光景――
もっとも日常とかけはなれたそれは、
男たちの欲望に歪んではいるが。
そんな中、1人の女性が男たちの背後から突然現れた。
その女はとにかく目を引く女性だった。
月光に煌めく銀の髪、
夜闇に輝くようなルビーの目。
男たちに負けぬほどその身の丈は高く、
そのシルエットですら分かるほど魅力的な肉体。
襲われている女性よりも、
情欲にそそられるその美貌、肉体。
獣欲に身を焦がす男たちの視線は、
たった一言で現れた銀髪の女へと集中し、
獲物が増えたと下卑た声で男たちは笑いあう。
「フッ……」
だが、銀髪の女は動じない。
笑いあう男たちを一笑に切って捨てる。
なんとくだらない奴らなのか。
そのうっすらと浮かべた妖艶な笑みは嘲けり、
男たちを見下すものだった。
もとより、短絡的に女を襲おうとしていた男たちだ。
たった一人の女ごときに侮られ、
怒りを堪えれるわけもなく、
己たちの力で抑えきれないなどという想像などもまた出来るはずもなかった。
見る見るうちに顔を真っ赤にして男たちは銀髪の女へと掴みかからんと駆け出した。
しかし、
そんな様子が見えているか、
否、それ以前に今の事態を理解していないのか……
女は微動だにしない。
ただ、嘲り、見下し続けているだけだ。
男たちと銀髪の女を遮るものがない以上、
男たちの手は見る見るうちに銀髪の女を捉え、
掴みとろうとした矢先――
女の姿は掻き消えた。
「なっ――!?」
「ど、どうなってやがる!」
「おい、女はどこに消えた!」
「知らねえよ!」
突然の思わぬ事態に混乱する男たち。
特殊な能力を持つものがいる。
そんな認識があれども、
何の予兆もなく、
あまりにも突然の出来事に対応できるものはなく、
慌てふためき辺りを見回し、
銀髪の女を探す事しかできない。
銀髪の女ははたしてどこへいったのか?
それを男たちが知るのはほんの僅かに後の事。
何故、ほんの僅かなのかというと――
「レディ、お手を。
麗しい貴女の身に、そして心に――
忌まわしき者たちの手で傷がついてしまう事なんて、
許される事ではない……
心配しないで、
貴女の騎士が今、やってまいりましたよ。」
何故なら銀髪の女は襲われ、
銀髪の女が現れた為に放置された女に対し、
恭しく、丁寧に、
愛しい者を見る目で、
愛しい者を見る口調で、
柔らかく微笑み、
男たちの姿などまるで存在しないかのように口説き、
手を差し伸べていたのだから。
逃げもしなければ立ち向かいもしない。
完全に無視したような銀髪の女を見つけれない等という道理はなかった。
「えっ?
あ、あの……その……
えっと……?」
そして、手を差し伸べられた女はというと、
突然の銀髪の女の登場、消失、出現――
そして、この行動である。
当然の如く混乱し、
何が起きているのか、
どうしてこうなっているのか、
――わずかばかりとはいえ助かった事なども分からず、
ただうろたえ、ためらい、
その視線は銀髪の女、虚空、男たちと定まる事なく揺れ動き、
手を取る事も出来ずに呆然とするばかり。
「手前――!」
「俺たちを無視するとはいい度胸だ!」
混乱から一早く立ち直ったのは誰あろう男たち。
もっとも……混乱よりも怒りが勝っただけだが。
再度、女目掛けて突撃する男たちに、
銀髪の女はめんどくさそうに――
本当にめんどくさそうに一瞥すると、
やれやれと肩をすくめ――
「ああ、無粋――
無粋にもほどがある。
せっかくにも……
襲われて怯える麗しいレディーをエスコートし、
救い――
ゆるりと楽しくい一時を享受し、
あわよくば甘美なる一時をも過ごそうと思っていたのに、
エスコートの最中でケチがつくとは――
まったく。
見逃された事にすら気づかぬのであれば、
こちらとて暴力に訴えるしかないか、
全く、スマートじゃないな。
だが、いいだろう。
その無粋なる罪はその実に刻んでもらうとしよう。
――そぉら!」
真っ先に掴みかかった男の腕をつかむと、
そのまま男を持ち上げ、
まるでこん棒か何かの如く一振りする。
――4人いた男達の二人が、
振られた男にぶち当たり、
骨の砕ける嫌な音を響かせながら吹き飛び、
同時に強い膂力によってただ一振りされ、
男たちのうち二人にぶつけられ、
全身が砕けるかのような感覚に涙し、
顔がぐちゃぐちゃになっている男に対し、
興味なさげにそのあたりに放り捨てた。
「えっ……?」
残された男一人は、
そのあまりの惨状が一瞬で作られた事に気づかず硬直し、
動きを止めた。
だが、銀髪の女の動きは止まらない。
瞬く間に距離を詰め、
残された男の瞳を覗き込む。
紅い、紅い瞳。
それは一瞬妖しく輝くと、
だらりと残された男の体が弛緩し、
呆けた表情となる。
「……お前の仲間のゴミ共を救急車でも呼んで連れ去れ。
そして、我達には関わるな。
同じ目にあいたくないならな。
おっと。
ひょっとしたら、この程度でも済まないかも知れないが……
ま、お前達次第だ。
いいな。」
銀髪の女の言葉に頷く男に、
興味を失ったように銀髪の女は襲われていた女の元へと舞い戻る。
「さ、無粋な者たちは去りました。
行きましょう、レディー。
あなたにこんな場は似合わない。
君は穏やかな日常で笑っているべきだ。
……」
そして何事もなかったかのように手を差し伸べるが、
襲われていた女は、
更に混乱した状態に陥っていた。
とりあえず助かったことは分かったのか、
手を伸ばそうとするも、
その手が途中で止まる。
当たり前といえば当たり前だろう。
さっきまで自分を襲っていた男達を、
存在しないかの如く無視し、
まるで塵芥の如く蹴散らしたのだ。
それも、
蹴散らし方も尋常じゃない。
まるで人をそこらの棒きれのように振り回したのだ。
恐怖に勝る恐怖。
柔らかな銀髪の女に安堵を覚え、
助けられた事を理解してなお、
その差し伸べられた手に対して本能に恐怖する。
混乱していなければ、
助けられた感謝をもってすぐにその手をつかんでいただろう。
どうしよう、どうするべきか。
襲われた女の取った行動は、
助けられたものにあるまじき行為。
だが、
人知を超えたバケモノに恐怖するがゆえに本能が巻き起こす行為……
――に、なるはずだった。
「――成程。
失礼。
こんな所に長々といるのはお互いにとってもよろしくないし、
気分も優れぬでしょう。
手を取るのもまってもいいのだが、
その御体に少し触れさせてもらうとしましょう。」
行動を起こす前にふわりと銀髪の女に抱き上げられる。
それは所謂お姫様抱っこというやつだ。
「えっ?えっ――!」
突然の行為、
突然の姿勢。
女同士とはいえ、
整った端正な顔立ちの美女に優しく微笑まれ、
まるで本当のお姫様になったかのような気分になり、
思わず襲われていた女の顔は朱に染まる。
それは、
先ほどまでの恐怖すらも払拭し、
ただ、ただ身を任せるしかできないほどに、
頭の中を沸騰させ――
「しっかり捕まっていてくださいね。
少々――
荒っぽくなるやもしれませんので。」
「は、はい……!」
優しく告げられる銀髪の女の言葉に素直に従い、
いわれたようにお姫様抱っこの体勢のままぎゅっとしがみつく事しかできなかった。
その様子に銀髪の女は満足し、
ビルを飛び越えるかのように高く――高く跳躍する。
「きゃっ……!」
思わずその衝撃にお姫様抱っこされた女は驚くが、
大丈夫と笑いかけるだけで銀髪の女は見る見るうちにビルを飛び越え、
ビルの上を駆け――
離れた所にある小さな公園へと着地し、
ベンチへと抱えた女を降ろした。
そして――
「……もう大丈夫ですよ。
駅の傍の公園です。
駅に関しても出ればすぐわかりますし、
人気も直ぐに多くなります。
どうにでもなるでしょう。
もちろん、
送って行って欲しいといわれればエスコートして送り返しますし、
お礼がしたいとあれば、
そうですね。
お茶にでも付き合っていただければ光栄です。」
助けられた女は、
大丈夫、安心してほしいと告げる銀髪の女に対し、
既に警戒はなく、
顔を真っ赤にしながらありがとうございますというように頭を下げるも――
帰るのか、
送って行って欲しいのか、
お茶に付き合うのか、
その問いには答えれなかった。
帰る……
というのは一番無難な選択肢だが、
助けてくれた女と二度とあえないような気もする。
お礼もきちんといえていないし、
縁が断たれるのは少し嫌な気がしたからだ。
ならば、送ってもらえばいい……
かというとどうだろうか。
助けてもらったとはいえ、
怖い部分が完全に消えたわけではなく、
それ以上にそれだけではもったいない欲がでたからだ。
ならば……
お茶をするというのも手ではあるが、
流石にあの状況から抜け出し、
今そんな気分にはなれなかったのと、
そこまでしてもいいのか、
迷いがあったからだ。
……そして、そんな混乱した頭に、
男たちに襲われた記憶がフラッシュバックする。
伸びる手、
情欲に満ちた瞳、
抗えぬ自分……
思わずぽろぽろと涙が零れ落ちた。
「おっと、レディに涙は似合わないな。
我のハンカチで――
……
…………?」
そんな突然泣き出した女に、
銀髪の女は優しく手を差し伸べるようにハンカチを取り出そうとする仕草をしたのち、
何か、探すように自分の体を探り始めた。
「……?」
なきながらも突然の事態に困惑する女。
不可解そうに銀髪の女を見やる。
じっと見ていると、
たとえようもなく困った顔で銀髪の女は告げた。
「……ハンカチ、家に忘れた……ようだ……
財布も……ない……」
世界が一瞬で凍りつき、
冷たい空気が流れる。
当たり前である。
この展開、
この流れでどうしてこんな事態を巻き起こせようか。
ここで、ハンカチを取り出せたなら決まっていただろう。
そうでなくても優しくするだけでよかった。
だが、これはない。
これは酷い……
が、
それが幸を奏したのか、
その一言で助けられた女の緊張の糸は切れた。
今までカッコよく助けてくれて、
それでいてバケモノのように強い彼女。
しかし、
蓋をあけてみるとどうだろう。
その風貌、その行為に見合わず、
ひょうきんというか抜けているというか……
人間らしさに触れたのだから。
「……ぷっ、クスクス!」
思わず口から笑いがこぼれる。
思わず大きな声で笑いそうになるのを必死でこらえる。
「うっ、わ、笑わないで欲しい……
いや、本当にこんなつもりじゃなかったんだ。
こう、さっとハンカチを出してお茶に誘うつもりだったんだ、
本当だぞ!」
そんな様子に非情に情けない顔をする銀髪の女はそういった。
必至で弁解する彼女の姿がまたおかしくて、
こらえきれずに大笑いする助けられた女。
今度は笑いでこぼれる涙を思わずぬぐい――
「そういう事なら奢らせてください。
助けてくれたお礼がしたいので。
近くのお店でいいですよね?
後は送ってくれると嬉しいです。」
もう少し彼女の事を知りたいななんてそう提案すると、
銀髪の女は嬉しそうに笑って、
胸をどんと叩き。
「!
ああ、ありがたい!
もちろんいいとも。
すまないな。不甲斐ない所をみせた。」
嬉しそうにそう答えた。
――銀髪の女の名は社 映美莉。
彼女がイバラシティの件に巻き込まれるのはもう少し後のお話。
 |
えみりん 「はい。日記です。現在絶賛チキンレース中!」 |
 |
えみりん 「更新日当日、2・3時間前に突然思い立って書き始めました!」 |
 |
えみりん 「……正気かな?」 |
 |
えみりん 「という訳でチキンレース敗北したら笑ってください!」 |
 |
えみりん 「勝ちました!間に合ったー!」 |
 |
えみりん 「ちなみに今後の日記の内容は続きを書き上げた後――」 |
 |
えみりん 「その時の気分となるか真っ白になります。」 |





特に何もしませんでした。





駄木(50 PS)を購入しようとしましたが、PSが足りませんでした。
駄石(50 PS)を購入しようとしましたが、PSが足りませんでした。
お肉(50 PS)を購入しようとしましたが、PSが足りませんでした。
魔術LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
使役LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
解析LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
付加LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
料理LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
五十嵐(1237) とカードを交換しました!
麺棒で、えいえい! (クイック)


リンクブレイク を研究しました!(深度0⇒1)
リンクブレイク を研究しました!(深度1⇒2)
リンクブレイク を研究しました!(深度2⇒3)
ティンダー を習得!
サステイン を習得!
プリディクション を習得!
アドレナリン を習得!
マジックミサイル を習得!
パワーブースター を習得!
魅惑 を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!





次元タクシーに乗り チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》 に転送されました!
 |
ドライバーさん 「ほら降りた降りた。次の客が待ってんだわ。」 |
現在のパーティから離脱しました!
チナミ区 E-6(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 E-7(道路)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 E-8(道路)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 E-9(草原)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 D-9(草原)に移動!(体調26⇒25)
あかり(223) からパーティに勧誘されました!
採集はできませんでした。
- あかり(223) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- えみりん(1239) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
白南海 「長針一周・・・っと。丁度1時間っすね。」 |

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
チャットで時間が伝えられる。
 |
白南海 「ケンカは無事済みましたかね。 こてんぱんにすりゃいいってわけですかい。」 |
グチャッとなったどこかのナレハテの映像をまじまじと見つめる白南海。
その背後から、突然タクシーが現れる!!
白南海のすぐ横を走り抜け、止まる。
 |
白南海 「・・・・・こ、殺す気ですかね。」 |
タクシーの窓が開く。

ドライバーさん
次元タクシーの運転手。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。初老くらいに見える。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。初老くらいに見える。
 |
ドライバーさん 「すまんすまん、出口の座標を少し間違えた。 挨拶に来たぜ。『次元タクシー』の運転役だ。」 |
帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。
 |
白南海 「イバラシティ側を潰そうってんじゃねぇでしょーね。・・・ぶっ殺しますよ?」 |
 |
ドライバーさん 「安心しな、どっちにも加勢するさ。俺らはそういう役割の・・・ハザマの機能ってとこだ。」 |
 |
ドライバーさん 「チェックポイントとかの行き来の際にゃ、へいタクシーの一声を。 俺もタクシーも同じのが沢山"在る"んでな、待たしゃしない。・・・そんじゃ。」 |
窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。
 |
白南海 「ひとを轢きかけといてあの態度・・・後で営業妨害でもしてやろうか。」 |
 |
白南海 「さて、それでは私は・・・のんびり傍観させてもらいますかね。この役も悪くない。」 |
白南海からのチャットが閉じられる――







ENo.1239
社 映美莉



るび:やしろ えみり
本名はエミリア=S=シュライネン
のんべんだらりとやってる女好きの残念美女大学生。
欠点は物をよく忘れる事。
能力は吸血鬼。
身長:180cm
体重:秘密だ
スリーサイズ:
出るところは出て引っ込む所は引っ込んでいる。
測った内容を忘れたとかでは断じてないと思っていただこう。
思っていただこう。
本名はエミリア=S=シュライネン
のんべんだらりとやってる女好きの残念美女大学生。
欠点は物をよく忘れる事。
能力は吸血鬼。
身長:180cm
体重:秘密だ
スリーサイズ:
出るところは出て引っ込む所は引っ込んでいる。
測った内容を忘れたとかでは断じてないと思っていただこう。
思っていただこう。
25 / 30
5 PS
チナミ区
D-9
D-9





































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 不思議な牙 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV5)[防具]活力10(LV5)[装飾]体力10(LV5) | |||
| 5 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]防御10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) | |||
| 6 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 魔術 | 5 | 破壊/詠唱/火 |
| 使役 | 10 | エイド/援護 |
| 解析 | 5 | 精確/対策/装置 |
| 付加 | 10 | 装備品への素材の付加に影響 |
| 料理 | 10 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ティンダー | 5 | 0 | 50 | 敵:火撃&炎上 | |
| サステイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:守護 | |
| プリディクション | 5 | 0 | 120 | 味列:AG増(3T) | |
| アドレナリン | 5 | 0 | 50 | 自従傷:AT増(4T)+麻痺・衰弱をDX化 | |
| マジックミサイル | 5 | 0 | 70 | 敵:精確火領撃 | |
| パワーブースター | 5 | 0 | 40 | 自従:AT・DF・DX・AG・HL増(3T) |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 魅惑 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:使役LVが高いほど戦闘勝利時に敵をエイドにできる確率増 |
最大EP[20]





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]リンクブレイク |

PL / 小鳥遊玲華