<< 5:00




ハザマにいる記憶と、イバラシティにいる記憶は、おかしな話だが区別できていた。
ハザマからイバラシティに戻って、それからまたハザマに来て――という記憶があるわけでなく、
ハザマにいる時の記憶はそれで続いているのに、それとは別にイバラシティで生活している数日分の記憶もある。
考えてみれば、混乱せずに整理できているのが不思議だなあ、と思った切っ掛けは、
イバラシティの記憶が途中で止まったからだ。
色々なことがあったせいで、多少混乱しているが、どうやら俺は死んでしまったらしい。
ハザマの赤い空の下。
何となく、もうイバラシティの青い空を見上げることはないのだと思った。
それでもいいと思った。
この世界に、彼女が――いや、『滝 鶺鴒』がいてくれるなら。
「……ああ。今度こそ、ずっと……鶺鴒さんと、一緒に」
イバラシティでの最後の記憶は、同じカフェでバイトしている鶺鴒さんと話をして、俺は彼女の力になりたいって伝えて。
その後、鶺鴒さんが急に咳をして――赤い花を吐くのは知っていたけど、その時は、何故か白い花だった。
いつもの咳と様子が違ったから、すぐにヨアヒム店長に連絡をして、そして……
確か、鶺鴒さんの具合が本当に酷くて、救急車で運ばれて行ったことは覚えている。
救急車?
「なんで……なんで、鶺鴒さんが、こんな目に遭わなきゃなんねえんだ……?」
俺は、鶺鴒さんが死んでしまうと店長に聞いて
鶺鴒さんが死ぬんじゃないかと心配で、以前に聞いた話を思い出して、思わず、
あの話って、いつ、誰から聞いたんだ?

鳥籠の中に、誰か、
何か、いる。
いつの間にか、俺のポケットの中に手帳が入っていた。
俺はくたびれた手帳を持っていた。
ページは黒っぽい汚れで読み辛かったが、目当てのページは鮮明だった。
なんで俺、そのページが読めるんだ?
そこには、知らない男の字で、こう書いてあった。
ーー猿の手、という昔話がある。
どんな願いも、三つまでなら叶えてくれる、不思議な手のミイラ。
手……正しく『お願い』すれば何でも叶う異形の腕、『やちまたさま』の噂と似ていないか?ーーと。
何の偶然か、それをヨアヒム店長が所有していることを、俺は知っている。
「やちまたさまに、お願いすれば……鶺鴒さんも、助かるのか……?」
これがタチの悪い悪戯だとしても、それでも俺は、見知らぬ手帳に縋るしかなかった。
あの本にも同じようなことが書かれていたんだから、
俺の異能はコーヒーを入れる時にちょびっとだけ役に立つ程度のもので、
怪我を治すだとか、病気を良くするだとか、ともかく鶺鴒さんを助けるような力じゃない。
だから、もしもやちまたさまが鶺鴒さんを助けてくれるなら、俺の頭くらいいくらでも下げてやる。
――やちまたさまの鳥籠、さっきまでカウンターにあった筈なのに
鳥籠は、ヨアヒム店長の部屋にあった筈だ。
何故かビルには誰もいなくて、
店長は、付き添いで病院に行ってるから、今なら俺が部屋に向かっても誰も気付かない。
よほど急いで出て行ったのか、玄関の鍵は開いていた。
留守中に勝手に部屋に入るのは多少罪悪感もあるが、人命が掛かってるんだから見逃してくれ。
「お邪魔しまーす……っと」
そろりと室内に入って、後ろ手に玄関を閉める。
ベッドサイドのポールに、鳥籠が吊ってあるのが見えて、ほっとする。
店長が鳥籠を持ったまま病院に行ってたら、本当に何もできなくなるところだった。
靴も脱がずに近寄って、鳥籠を掴んだ。中のティーカップが倒れるが、大事の前の小事だ。
「おい、やちまたさまはいないのか!?」
「え、えと、ちーちゃんは」
「いいから、さっさとしてくれ! 急がないと間に合わないんだ!」
急かしても、鳥籠の中に、薄気味悪い腕は出てこない。
なんでだよ、どうでもいい時にはフラフラしてたじゃねーか!
「手帳に書いてあっただろ、やちまたさまなら、鶺鴒さんを助けられるって!」
困った顔をしていた小人が、俺の後ろを見てほっとした顔になる。
俺の後ろにいる、誰かを見ている。
気付けば、鳥籠を掴んでいた手は、動かなくなって、まるで何かに掴まれたみたいに、
手を放していた。
小人が、首を傾げる。
「あきとおにいさんも、ちーちゃんに、おねがいする?」
「当たり前だろ! 鶺鴒さんを……鶺鴒さんのいた世界を返せって、そのためなら俺の頭くらい、」

ゴキン、というか、ボキン、というか、妙に響く重い音がした。
小人は首を傾げたまま、四つに分かれたパーツの内、一番大きな塊が床に倒れるのを眼で追った。
それから顔を上げて、残る三つのパーツを――正しくは、それを握り潰した三本の腕を――見て、
今度は反対側にこてんと首を倒す。
状況がわかっていないような顔で少しの間考えていたが、やがて小人ははっとして、腕に向かって声をかけた。
「あ! あのね、ちーちゃん。あきとおにいさんが、ちーちゃんにおねがいごと、あるんだって!
わたし、でんごんしようとおもったのに、とちゅうできこえなくなっちゃって…
ちーちゃんは、ちゃんときこえた…?」
口を持たない腕は、小人の問いに、何の反応も返さなかった。

「また葬式? この間もそうじゃなかったか?」
「あれは叔父さんの所のでしょ、今度はほら、従弟の――」
「そうか、随分若いのに……事故だなんて気の毒に」
「それがね、亡くなった時の状況がおかしくて、異能での殺人じゃないかって聞いたわよ。
――あら? ねえ、ちょっと、お義母さんの妹さんにも不幸が……」
「おいおい、何でそんなに――」
通りかかったリビングで、ハガキを見たお父さんとお母さんが、怪訝な顔をしている。
そう言えば、学校でも最近、変な事故で一家全員が死んだって噂があったっけ。
異能での連続無差別殺人事件とか、勘弁してよ。しかも親戚が巻き込まれてるとか、生々しくて嫌な感じ。
このタイミングで親戚が何人か死んでるって学校で言ったら、あたしまで変な噂の関係者にされそうだ。
憂鬱なため息をついて、あたしはそのままバスルームに向かった。
「あー、でも、葬式に行くなら学校休むのよね……」
自分からは言わなくても、担任教師が「身内の葬式のために今日はお休みしています」なんて言ったら、
次の日には勝手に関係者扱いになっているかもしれない。勘弁して欲しい。
嫌な気分になりながら脱衣所で上着を脱ぎ、何となく鏡を、見――
「――は?」
なに、これ。
鏡の中、立ちすくんでいるあたしの肩からお腹にかけて、変な模様が出ていた。
内出血とは明らかに違う紫色で、歪な四角形を組み合わせたような……
そう言えば、この前に亡くなった親戚の家族が、そんなことを言っていなかっただろうか。
首に変な痣が出て、何だろうと思っていたら、事故で首が――と。
まさか、その痣って、これ? 放って置いたら、あたしも、死ぬ……?
なかなかお風呂に入る様子がないのを心配したお母さんが様子を見に来るまで、あたしは鏡の前で立ち竦んでいた。



ENo.226 エド とのやりとり

ENo.1532 ハヤテ とのやりとり

以下の相手に送信しました













コウ(187) は ド根性雑草 を入手!
タキ(223) は ド根性雑草 を入手!
秋人(285) は 雑木 を入手!
うつみん(1058) は 雑木 を入手!
タキ(223) は ボロ布 を入手!
タキ(223) は 花びら を入手!
コウ(187) は 花びら を入手!
コウ(187) は 羽 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
うつみん(1058) のもとに 歩行軍手 がスキップしながら近づいてきます。



具現LV を 3 UP!(LV2⇒5、-3CP)
装飾LV を 3 UP!(LV32⇒35、-3CP)
クリエイト:ガトリング を習得!



チナミ区 D-2(ベースキャンプ)に戻りました!
体調が全回復しました!
『チナミ区 H-15:釣り堀』へ採集に向かうことにしました!
- タキ(223) の選択は チナミ区 H-15:釣り堀
- うつみん(1058) の選択は チナミ区 H-15:釣り堀
MISSION!!
チナミ区 P-3:瓦礫の山 を選択!
- タキ(223) の選択は チナミ区 P-3:瓦礫の山





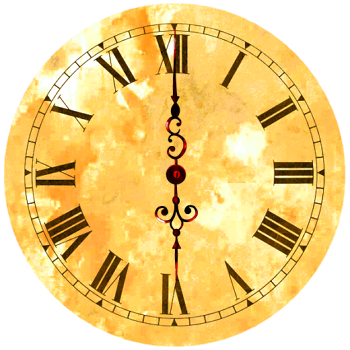
―― ハザマ時間が紡がれる。


ふたりが時計台を見上げると、時計の針が反時計回りに動き始める。
針の動きは加速し、0時を指したところで停止する。
時計台から、女性のような声――
声は淡々と、話を続ける。
声はそこで終わる。
榊がこちらを向き、軽く右手を挙げる。
エディアンもこちらを向き、大きく左手を振る。
















































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [スキル]OK.



ハザマにいる記憶と、イバラシティにいる記憶は、おかしな話だが区別できていた。
ハザマからイバラシティに戻って、それからまたハザマに来て――という記憶があるわけでなく、
ハザマにいる時の記憶はそれで続いているのに、それとは別にイバラシティで生活している数日分の記憶もある。
考えてみれば、混乱せずに整理できているのが不思議だなあ、と思った切っ掛けは、
イバラシティの記憶が途中で止まったからだ。
色々なことがあったせいで、多少混乱しているが、どうやら俺は死んでしまったらしい。
ハザマの赤い空の下。
何となく、もうイバラシティの青い空を見上げることはないのだと思った。
それでもいいと思った。
この世界に、彼女が――いや、『滝 鶺鴒』がいてくれるなら。
「……ああ。今度こそ、ずっと……鶺鴒さんと、一緒に」
イバラシティでの最後の記憶は、同じカフェでバイトしている鶺鴒さんと話をして、俺は彼女の力になりたいって伝えて。
その後、鶺鴒さんが急に咳をして――赤い花を吐くのは知っていたけど、その時は、何故か白い花だった。
いつもの咳と様子が違ったから、すぐにヨアヒム店長に連絡をして、そして……
確か、鶺鴒さんの具合が本当に酷くて、救急車で運ばれて行ったことは覚えている。
「なんで……なんで、鶺鴒さんが、こんな目に遭わなきゃなんねえんだ……?」
俺は、
鶺鴒さんが死ぬんじゃないかと心配で、以前に聞いた話を思い出して、思わず、
「神サマって奴が本当にいるんなら、何とかして見せろよ!」
「あきとおにいさんも、ちーちゃんに、おねがいする?」

鳥籠の中に、
何か、いる。
いつの間にか、
俺はくたびれた手帳を持っていた。
ページは黒っぽい汚れで読み辛かったが、目当てのページは鮮明だった。
そこには、知らない男の字で、こう書いてあった。
ーー猿の手、という昔話がある。
どんな願いも、三つまでなら叶えてくれる、不思議な手のミイラ。
手……正しく『お願い』すれば何でも叶う異形の腕、『やちまたさま』の噂と似ていないか?ーーと。
何の偶然か、それをヨアヒム店長が所有していることを、俺は知っている。
「やちまたさまに、お願いすれば……鶺鴒さんも、助かるのか……?」
これがタチの悪い悪戯だとしても、それでも俺は、見知らぬ手帳に縋るしかなかった。
俺の異能はコーヒーを入れる時にちょびっとだけ役に立つ程度のもので、
怪我を治すだとか、病気を良くするだとか、ともかく鶺鴒さんを助けるような力じゃない。
だから、もしもやちまたさまが鶺鴒さんを助けてくれるなら、俺の頭くらいいくらでも下げてやる。
――やちまたさまの
鳥籠は、ヨアヒム店長の部屋にあった筈だ。
店長は、付き添いで病院に行ってるから、今なら俺が部屋に向かっても誰も気付かない。
よほど急いで出て行ったのか、玄関の鍵は開いていた。
留守中に勝手に部屋に入るのは多少罪悪感もあるが、人命が掛かってるんだから見逃してくれ。
「お邪魔しまーす……っと」
そろりと室内に入って、後ろ手に玄関を閉める。
ベッドサイドのポールに、鳥籠が吊ってあるのが見えて、ほっとする。
店長が鳥籠を持ったまま病院に行ってたら、本当に何もできなくなるところだった。
靴も脱がずに近寄って、鳥籠を掴んだ。中のティーカップが倒れるが、大事の前の小事だ。
「おい、やちまたさまはいないのか!?」
「え、えと、ちーちゃんは」
「いいから、さっさとしてくれ! 急がないと間に合わないんだ!」
急かしても、鳥籠の中に、薄気味悪い腕は出てこない。
なんでだよ、どうでもいい時にはフラフラしてたじゃねーか!
「手帳に書いてあっただろ、やちまたさまなら、鶺鴒さんを助けられるって!」
困った顔をしていた小人が、俺の後ろを見てほっとした顔になる。
気付けば、鳥籠を掴んでいた
手を放していた。
小人が、首を傾げる。
「あきとおにいさんも、ちーちゃんに、おねがいする?」
「当たり前だろ! 鶺鴒さんを……鶺鴒さんのいた世界を返せって、そのためなら俺の頭くらい、」

ゴキン、というか、ボキン、というか、妙に響く重い音がした。
小人は首を傾げたまま、四つに分かれたパーツの内、一番大きな塊が床に倒れるのを眼で追った。
それから顔を上げて、残る三つのパーツを――正しくは、それを握り潰した三本の腕を――見て、
今度は反対側にこてんと首を倒す。
状況がわかっていないような顔で少しの間考えていたが、やがて小人ははっとして、腕に向かって声をかけた。
「あ! あのね、ちーちゃん。あきとおにいさんが、ちーちゃんにおねがいごと、あるんだって!
わたし、でんごんしようとおもったのに、とちゅうできこえなくなっちゃって…
ちーちゃんは、ちゃんときこえた…?」
口を持たない腕は、小人の問いに、何の反応も返さなかった。

「また葬式? この間もそうじゃなかったか?」
「あれは叔父さんの所のでしょ、今度はほら、従弟の――」
「そうか、随分若いのに……事故だなんて気の毒に」
「それがね、亡くなった時の状況がおかしくて、異能での殺人じゃないかって聞いたわよ。
――あら? ねえ、ちょっと、お義母さんの妹さんにも不幸が……」
「おいおい、何でそんなに――」
通りかかったリビングで、ハガキを見たお父さんとお母さんが、怪訝な顔をしている。
そう言えば、学校でも最近、変な事故で一家全員が死んだって噂があったっけ。
異能での連続無差別殺人事件とか、勘弁してよ。しかも親戚が巻き込まれてるとか、生々しくて嫌な感じ。
このタイミングで親戚が何人か死んでるって学校で言ったら、あたしまで変な噂の関係者にされそうだ。
憂鬱なため息をついて、あたしはそのままバスルームに向かった。
「あー、でも、葬式に行くなら学校休むのよね……」
自分からは言わなくても、担任教師が「身内の葬式のために今日はお休みしています」なんて言ったら、
次の日には勝手に関係者扱いになっているかもしれない。勘弁して欲しい。
嫌な気分になりながら脱衣所で上着を脱ぎ、何となく鏡を、見――
「――は?」
なに、これ。
鏡の中、立ちすくんでいるあたしの肩からお腹にかけて、変な模様が出ていた。
内出血とは明らかに違う紫色で、歪な四角形を組み合わせたような……
そう言えば、この前に亡くなった親戚の家族が、そんなことを言っていなかっただろうか。
首に変な痣が出て、何だろうと思っていたら、事故で首が――と。
まさか、その痣って、これ? 放って置いたら、あたしも、死ぬ……?
なかなかお風呂に入る様子がないのを心配したお母さんが様子を見に来るまで、あたしは鏡の前で立ち竦んでいた。
 |
祟り神は、祟るからこそ手厚く祀られているものなのだ。 |



ENo.226 エド とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.1532 ハヤテ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
以下の相手に送信しました



 |
滝 「……白水ビルのみんなにはごめんなさい。死んでも、イバラシティをアンジニティから守るのには、変わりないから。」 |
 |
秋人 「悪い、イバラシティではもう逢えなくなっちまう。 ……だけど、なんつーか……侵略戦争、負けねえように、応援はしてるからな!」 |
 |
うつみん 「――それじゃあ、またいつか。どこかでね。また、記憶は消えてしまうかもしれないけれど」 |





TeamNo.187
|
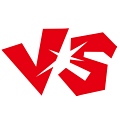 |
行き当たりばったり4人組
|



コウ(187) は ド根性雑草 を入手!
タキ(223) は ド根性雑草 を入手!
秋人(285) は 雑木 を入手!
うつみん(1058) は 雑木 を入手!
タキ(223) は ボロ布 を入手!
タキ(223) は 花びら を入手!
コウ(187) は 花びら を入手!
コウ(187) は 羽 を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
うつみん(1058) のもとに 歩行軍手 がスキップしながら近づいてきます。



具現LV を 3 UP!(LV2⇒5、-3CP)
装飾LV を 3 UP!(LV32⇒35、-3CP)
クリエイト:ガトリング を習得!



チナミ区 D-2(ベースキャンプ)に戻りました!
体調が全回復しました!
『チナミ区 H-15:釣り堀』へ採集に向かうことにしました!
- タキ(223) の選択は チナミ区 H-15:釣り堀
- うつみん(1058) の選択は チナミ区 H-15:釣り堀
MISSION!!
チナミ区 P-3:瓦礫の山 を選択!
- タキ(223) の選択は チナミ区 P-3:瓦礫の山





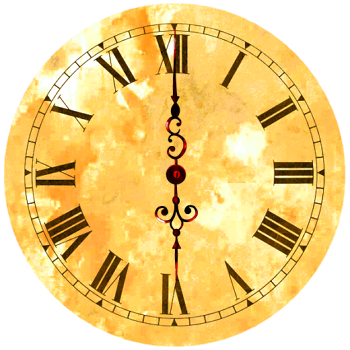
―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
榊 「……時計台に呼ばれてしまいましたが、はてさて。」 |
 |
エディアン 「なーんか、嫌な予感がします。」 |

榊
黒髪に蒼い瞳、黒スーツ。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
ふたりが時計台を見上げると、時計の針が反時計回りに動き始める。
 |
エディアン 「ほら……ほらぁ……。」 |
 |
榊 「どういうことでしょうねぇ。」 |
針の動きは加速し、0時を指したところで停止する。
時計台から、女性のような声――
 |
声 「――お疲れ様です御二方。役目を担ってくれて、感謝してます。」 |
 |
エディアン 「……ワールドスワップの能力者さんですよね。 機会を与えてくれて、感謝していますよ?」 |
 |
榊 「お姿は拝めないんですかねぇ。私は興味津々桃色片想いなのですが。」 |
声は淡々と、話を続ける。
 |
声 「どうやらこのワールドスワップ、時計の進みが狂っているようです。 特殊な因子を含めてしまった為と能力が訴えます。その因子が――」 |
 |
声 「――榊さん、貴方のようですね。何か、心当たりは?」 |
 |
榊 「大いにございます!特殊な世界の住人ゆえ、私は今や特異な存在なのでしょう。 妻に『貴方は変人』とよく言われていましたが、そういうことでしたか!納得ですッ」 |
 |
榊 「では、役目を果たすのは難しいということでよろしいですか?」 |
 |
声 「……………………」 |
 |
榊 「……? ……どうしました?」 |
 |
声 「……仕切り直し、世界線を変更する、と能力が言ってきます。 貴方が案内役にならない世界線。イバラシティも、アンジニティも、新たなものになる……と。」 |
 |
エディアン 「……そ、そんなことまでできてしまう能力? ワールドスワップという名の範疇を超えてません?」 |
 |
榊 「世界線を別のものと交換する……と考えるなら、ギリギリ……ですかね。 というか、スワップから外れた現象は既に起こっていますが。」 |
 |
声 「これは能力ではなく、……呪い。呪いという言葉が合う。 今まで勝手に発動した数度、自分への利はない。制御下にない、把握できない、呪い。」 |
 |
声 「……………………」 |
 |
声 「ハザマへの次の転送時間に、ハザマに転送される代わりに、世界線が変更される。 そして、案内役も、転送対象も、変わる。」 |
 |
声 「変わるものは、多いだろう。しかし変わらぬものも、あるだろう。」 |
 |
エディアン 「別の世界線、ですものね。 ……どうせなら私がアンジニティにいない世界線がいいんですけど。」 |
 |
榊 「……なるほど、奇妙な枝の正体は世界線操作者でしたかッ! 少なくとも私が案内役となれない世界線になるのですね、残念です。」 |
 |
声 「……………………」 |
 |
声 「連絡は終わり。さようなら。」 |
声はそこで終わる。
 |
榊 「さて…… とても短い間ではありましたが、 エディアンさん、皆様、お付き合いありがとうございました!」 |
 |
エディアン 「お別れですか。悪人顔っぽくて敵視しやすい相手だったんですけどねー。」 |
 |
榊 「こんな素敵な笑顔を悪人顔呼ばわりとは、失礼な娘さんです。 なるほどアンジニティにいらっしゃるわけですねぇ。」 |
 |
エディアン 「……うるっさいですね。事情は人それぞれあるんですよ、色々!」 |
 |
榊 「……それでは、」 |
 |
エディアン 「……それでは、」 |
榊がこちらを向き、軽く右手を挙げる。
エディアンもこちらを向き、大きく左手を振る。
 |
榊 「お疲れ様でした。」 |
 |
エディアン 「お疲れ様でしたー!」 |

ENo.285
越馬 秋人



[置きレス多め。まったりお付き合い頂ければ幸いです。]
■■■越馬秋人■◆メインキャラ◆
イバラシティで暮らす男子高校生。生まれも育ちもイバラ市民。
15歳。男。
異能はカップ程度の量の液体の温度維持。
ようはほっといても冷めないコーヒーを入れられるくらいのショボいもの。当然のように戦闘には使えない。
「コーヒー冷めない能力でどう戦えっていうんだよ!?」
過去に両親を火事で亡くしているために火が苦手。恐怖症ではないが、近寄らないで済むなら近寄りたくない、くらいの苦手さ。
火事の後は親戚に引き取られているが、居心地の悪さから半ば家出するようにバイト先であるカフェ「ミルクホール」で寝泊まりしている。
親戚とは疎遠。月に一回電話で無事を知らせたり、多少の仕送りを受け取る程度のやり取りはある。
同じくカフェで給仕のバイトをしている「鶺鴒さん」のことが気になっており、花吐き病であると知ってからは何か病を治す方法はないかと考えている。病については実はよく知らない。
成績は中の下で、よく言えば思い切りがいい、悪く言えば短慮なところがある性格。
怪しげな魔法の品であるフィンの鳥籠も「何か願いを叶える力があるけど危ないシロモノらしい」程度に思っている。
■■■ヨアヒム・コースフェルト■◆サブキャラ◆
カフェ「ミルクホール」のマスター。
年齢不詳。性別はジェシーさん。
イバラシティに移住してきただけなので異能の類は持っておらず、来る前の来歴は不明。
副業で情報屋をやっているが、副業なのでいまいち本腰を入れていない。イバラシティではただの明るいカフェの店長さん。
イニシャルの「JC」を聴き間違えたフィンから「ジェシーおねえさん」と呼ばれている。
■■■フィン■◆サブキャラ◆
カフェ「ミルクホール」に置かれている鳥籠の中で暮らしている童女。
年齢は不明だが手のひらサイズで子供っぽい。おんなのこ。
ヨアヒムに連れられてイバラシティにやって来て、カフェのマスコット的な扱いを受けている。
性格はのんびりぽやぽやで、頭の回転がとてもゆっくり。ハザマにいてもちっとも危機感を感じていない言動を見せる。
魔法っぽいものが使えるが、危なっかしいので店の中では使用禁止。しかしティーカップを浮かせて運んだり花瓶の花を長持ちさせたりと、ちょいちょい使っている現場を目撃されている。
戦闘時は異能が全く訳に立たない秋人を援助するのも彼女の魔法っぽいものである。
■■■やちまたさまのて■◆サブキャラ◆
カフェ「ミルクホール」にてフィンの入っている鳥籠の上に時々顕現する異形の腕。左右の区別がない六本指。
年齢不明。性別不明。種族も不明。
ヨアヒムからは、穂が手の形にも見える「ヤツマタ」という植物の名前が訛ったものだと思われているが、フィンからは「ちーちゃん」という威厳もへったくれもない呼び方をされている。
過去の観測結果を経緯ごと歪ませる性質があり、見た目や能力がその時々で変わるが、基本的にはフィンを手に乗せて散歩するくらいしかしない。
ハザマにおいて秋人からは「マジでやちまたさまってヤツ何もしねーな!」などと思われているが、祟り神と言うのは人間から「お願いですから何もしないでください」と頼まれる側である。
彼らのこれからの命運についての注意事項
↓
↓
↓
越馬 秋人は、試遊会中に死亡または再起不能の障害を負うことが確定済み。
やちまたさまのては最後まで正体不明のまま。
ヨアヒムは自称ドイツ人だけどドイツ国家が存在しない世界ではしれっと別の国籍を名乗るような人だよ!
■■■越馬秋人■◆メインキャラ◆
イバラシティで暮らす男子高校生。生まれも育ちもイバラ市民。
15歳。男。
異能はカップ程度の量の液体の温度維持。
ようはほっといても冷めないコーヒーを入れられるくらいのショボいもの。当然のように戦闘には使えない。
「コーヒー冷めない能力でどう戦えっていうんだよ!?」
過去に両親を火事で亡くしているために火が苦手。恐怖症ではないが、近寄らないで済むなら近寄りたくない、くらいの苦手さ。
火事の後は親戚に引き取られているが、居心地の悪さから半ば家出するようにバイト先であるカフェ「ミルクホール」で寝泊まりしている。
親戚とは疎遠。月に一回電話で無事を知らせたり、多少の仕送りを受け取る程度のやり取りはある。
同じくカフェで給仕のバイトをしている「鶺鴒さん」のことが気になっており、花吐き病であると知ってからは何か病を治す方法はないかと考えている。病については実はよく知らない。
成績は中の下で、よく言えば思い切りがいい、悪く言えば短慮なところがある性格。
怪しげな魔法の品であるフィンの鳥籠も「何か願いを叶える力があるけど危ないシロモノらしい」程度に思っている。
■■■ヨアヒム・コースフェルト■◆サブキャラ◆
カフェ「ミルクホール」のマスター。
年齢不詳。性別はジェシーさん。
イバラシティに移住してきただけなので異能の類は持っておらず、来る前の来歴は不明。
副業で情報屋をやっているが、副業なのでいまいち本腰を入れていない。イバラシティではただの明るいカフェの店長さん。
イニシャルの「JC」を聴き間違えたフィンから「ジェシーおねえさん」と呼ばれている。
■■■フィン■◆サブキャラ◆
カフェ「ミルクホール」に置かれている鳥籠の中で暮らしている童女。
年齢は不明だが手のひらサイズで子供っぽい。おんなのこ。
ヨアヒムに連れられてイバラシティにやって来て、カフェのマスコット的な扱いを受けている。
性格はのんびりぽやぽやで、頭の回転がとてもゆっくり。ハザマにいてもちっとも危機感を感じていない言動を見せる。
魔法っぽいものが使えるが、危なっかしいので店の中では使用禁止。しかしティーカップを浮かせて運んだり花瓶の花を長持ちさせたりと、ちょいちょい使っている現場を目撃されている。
戦闘時は異能が全く訳に立たない秋人を援助するのも彼女の魔法っぽいものである。
■■■やちまたさまのて■◆サブキャラ◆
カフェ「ミルクホール」にてフィンの入っている鳥籠の上に時々顕現する異形の腕。左右の区別がない六本指。
年齢不明。性別不明。種族も不明。
ヨアヒムからは、穂が手の形にも見える「ヤツマタ」という植物の名前が訛ったものだと思われているが、フィンからは「ちーちゃん」という威厳もへったくれもない呼び方をされている。
過去の観測結果を経緯ごと歪ませる性質があり、見た目や能力がその時々で変わるが、基本的にはフィンを手に乗せて散歩するくらいしかしない。
ハザマにおいて秋人からは「マジでやちまたさまってヤツ何もしねーな!」などと思われているが、祟り神と言うのは人間から「お願いですから何もしないでください」と頼まれる側である。
彼らのこれからの命運についての注意事項
↓
↓
↓
越馬 秋人は、試遊会中に死亡または再起不能の障害を負うことが確定済み。
やちまたさまのては最後まで正体不明のまま。
ヨアヒムは自称ドイツ人だけどドイツ国家が存在しない世界ではしれっと別の国籍を名乗るような人だよ!
30 / 30
338 PS
チナミ区
D-2
D-2





































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材・消耗の場合は詳細等) |
| 1 | 紅い結糸 | 装飾 | 33 | 回復10 | - | - | |
| 2 | 一年生の制服 | 防具 | 63 | 鎮痛10 | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 男子校の制服 | 防具 | 25 | 防御10 | - | - | |
| 5 | 鳥無鳥籠 | 武器 | 30 | 回復10 | 水纏10 | - | 【射程5】 |
| 6 | 雑木 | 素材 | 15 | [武器]攻撃10(LV15)[防具]防御10(LV15)[装飾]体力10(LV15) | |||
| 7 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]加速10(LV25)[装飾]敏捷10(LV10) | |||
| 8 | 雑木 | 素材 | 15 | [武器]攻撃10(LV15)[防具]防御10(LV15)[装飾]体力10(LV15) | |||
| 9 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]加速10(LV25)[装飾]敏捷10(LV10) | |||
| 10 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]敏捷10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) | |||
| 11 | 何か柔らかい物体 | 素材 | 10 | [武器]祝福10(LV20)[防具]鎮痛10(LV20)[装飾]防御10(LV20) | |||
| 12 | ぬめぬめ | 素材 | 10 | [武器]水纏10(LV20)[防具]舞撃10(LV25)[装飾]加速10(LV25) | |||
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 命術 | 10 | 生命/復元/水 |
| 具現 | 5 | 創造/召喚 |
| 響鳴 | 10 | 歌唱/音楽/振動 |
| 解析 | 10 | 精確/対策/装置 |
| 装飾 | 35 | 装飾作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 6 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 6 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| アクアヒール | 6 | 0 | 40 | 味傷:HP増+炎上・麻痺防御 | |
| クリエイト:タライ | 5 | 0 | 40 | 敵:攻撃&朦朧・混乱 | |
| ビブラート | 6 | 0 | 60 | 敵:SP攻撃 | |
| プリディクション | 5 | 0 | 60 | 味列:AG増(3T) | |
| ウォーターフォール | 5 | 0 | 70 | 敵:水撃&連続減 | |
| ヒーリングソング | 6 | 0 | 70 | 味精2:HP増&精神変調減 | |
| ノーマライズ | 5 | 0 | 100 | 味肉精:HP増+肉体・精神変調減 | |
| クリエイト:マイク | 6 | 0 | 40 | 自:混乱・魅了特性増 | |
| クリエイト:ガトリング | 5 | 0 | 110 | 味:貫撃LV増 | |
| リゾルート | 5 | 0 | 60 | 敵:精確攻撃 | |
| バトルソング | 6 | 0 | 180 | 味列:AT・LK増(3T) | |
| クイックアナライズ | 5 | 0 | 200 | 敵全:AG減 | |
| リップル | 5 | 0 | 150 | 敵全:水痛撃(対象の領域値[水]が高いほど威力増) | |
| アクアスピット | 5 | 2 | 200 | 敵貫2:水痛撃 | |
| サモン:セイレーン | 5 | 0 | 300 | 自:セイレーン召喚 | |
| ワイドアナライズ | 5 | 2 | 200 | 敵全:DX・AG減 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 回復 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| 活力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 体力 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 治癒 | 6 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| 幸運 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 | |
| 水特性回復 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:水属性スキルのHP増効果に水特性が影響 | |
| 召喚強化 | 5 | 2 | 0 | 【常時】異能『具現』のLVに応じて、自身の召喚するNPCが強化 |



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
BANKAラーメン (ヒール) |
0 | 20 | 味傷:HP増 | |
|
ディスペアニードル (エナジードレイン) |
0 | 160 | 敵:闇撃&DF奪取 | |
|
protection (プロテクション) |
0 | 60 | 味傷:守護 | |
|
ネクタール (キュアディジーズ) |
0 | 70 | 味肉2:HP増&肉体変調減 | |
|
『節制』 (アクアエレメント) |
0 | 140 | 自:水特性・水耐性増 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]ストーンブラスト | [ 1 ]ヒールポーション | [ 1 ]アキュラシィ |
| [ 1 ]レックレスチャージ | [ 1 ]アニマート | [ 1 ]ヒールハーブ |
| [ 1 ]イレイザー | [ 1 ]水特性回復 | [ 1 ]光特性回復 |
| [ 1 ]エナジードレイン | [ 1 ]バトルソング | [ 1 ]クイックアナライズ |

PL / ぼーろ
























