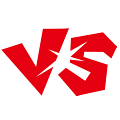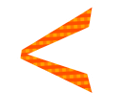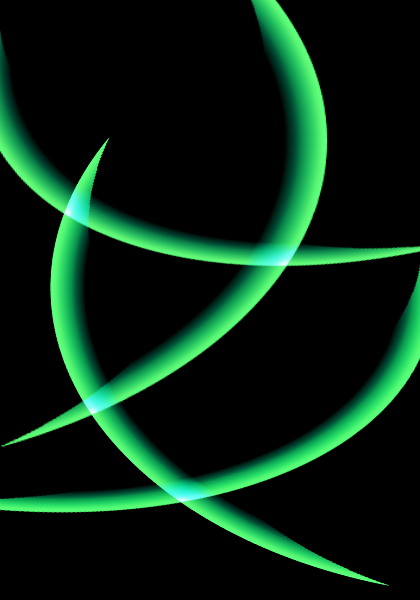<< 4:00>> 6:00




桜が散った。花びらが土に溶けてゆく。
藤のつぼみはまだ小さくて硬い。
春が来て、過ぎ去って行く。初夏を過ぎれば暑くなっていく。
今までもずっとそうで、きっと来年もそうだ。
金魚屋は、庭の桜にも藤にも、極力手をかけずに好き放題に育たせている。
さほど多くはない木である。放っておいても日照やら掃除やらは問題なさそうだからだ。
勝手に咲いては勝手に散りゆく、勝手に育ってたまに枝を落とす、そんな植物たち。
もしも金魚屋がいなくなってもそれは変わらないだろう。
世話をするものがいなくなって駄目になってしまう、ということは恐らくないだろう。
ただ雑草の背丈が伸びて、虫が増えて、鼠が増えるだけだろう。
木のデッキは腐り落ちて。
テーブルセットは塗装が落ちて錆びていく。
傍らの瓶では金魚が白い腹を晒した後、色を濁らせて腐っていく。
蠅とボウフラが湧いて、いずれ小さな骨が沈んでいく。水は澱んで苔と黴が繁殖していく。
夢見る。
庭がそんな有様になったころには、店内も荒れているだろう。
鍵は壊れ、或いは開けっ放しで、窓硝子は割れていようが割れていまいが透明感が損なわれ。
ざらつく床。埃の匂い。
この地区は些か治安が良くないようなので、きっとゴミも散乱する。
浮浪者が貪ったであろう菓子の包装紙。売るには手間で腹いせにぶちまけられた茶葉や珈琲。
漁るためにかはたまた地震でも起こったか、棚から落ちて割れた香水瓶と、すっかり乾いて揮発した液体の跡。
あちらこちらに散らばって踏まれて砕けた、透明な欠片たち。
夢見る。
金魚屋は、自分以外を見るのが好きだ。
自分の関与しなくなった景色が好きだ。
薄煙のフィルター越し、分厚いレンズ越しでは物足りないくらいに、金魚屋は金魚屋が邪魔だ。
希死念慮だとかそういうものではない、金魚屋は痛いのも苦しいのも好きではない。
けれどいつだって金魚屋は、どこかに消えてなくなりたいのだ。決してネガティブな意味ではなく、金魚屋はそれを愛している。それらを愛するためには、金魚屋はそこから去る必要があるのだ。
例えば家族。
例えば友人。
例えば故郷。
例えば名前。
例えば年齢、性別、存在、人格、「■■■■■」という人間。
愛している。愛しているからこそ手放す。
金魚屋の人生は、いわばそれそのものが金魚屋の作品だ。
金魚堂は、金魚屋の最高で最後の愛するものになる予定だ。
猫はそこで目を開いた。
猫は、退屈そうに一つ大欠伸をして、歩みを再開させた。
猫にとっては、どうだっていいことだ。
今まで、なんて一つもなかったのだから。



ENo.201 チカギ とのやりとり




ItemNo.5 魚の丸焼き を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(17⇒18)
今回の全戦闘において 防御10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!










合成LV を 4 DOWN。(LV16⇒12、+4CP、-4FP)
制約LV を 6 UP!(LV0⇒6、-6CP)
料理LV を 10 UP!(LV10⇒20、-10CP)
ItemNo.7 パンの耳 から料理『魚の丸焼き』をつくりました!
⇒ 魚の丸焼き/料理:強さ30/[効果1]防御10 [効果2]治癒10 [効果3]-
幽霊タクシー(944) とカードを交換しました!
outrage (アウトレイジ)

イレイザー を研究しました!(深度0⇒1)
イレイザー を研究しました!(深度1⇒2)
リストリクト を研究しました!(深度2⇒3)
リストリクト を習得!
ファイアダンス を習得!
デスパレイト を習得!
ウィザー を習得!



チナミ区 R-4(沼地)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 R-3(沼地)に移動!(体調17⇒16)
チナミ区 Q-3(沼地)に移動!(体調16⇒15)
チナミ区 P-3(チェックポイント)に移動!(体調15⇒14)
採集はできませんでした。
- 大化け猫(1656) の選択は チナミ区 E-5:出発地(ベースキャンプ外のため無効)
MISSION!!
チナミ区 P-3:瓦礫の山 が発生!
- 大化け猫(1656) が経由した チナミ区 P-3:瓦礫の山






―― ハザマ時間が紡がれる。

時計台の前でタバコをふかす、ドライバーさん。
時計台をぼーっと見上げる。
自分の腕時計を確認する。
・・・とても嫌そうな表情になる。








瓦礫の山の上に立つ、棒のような何かが呼んでいる。

チーン!という音と共に頭から湯呑茶碗が現れ、それを手渡す。
地面からマイケルと同じようなものがボコッと現れる。












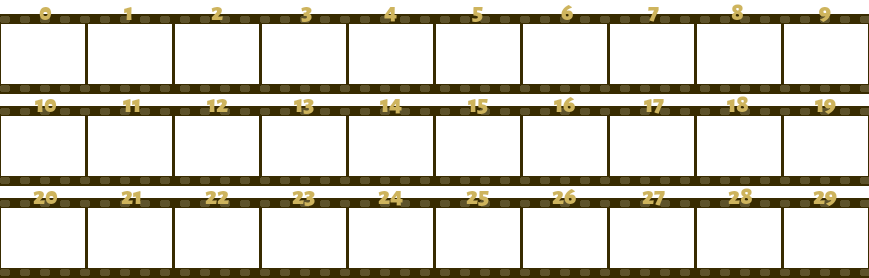





































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



桜が散った。花びらが土に溶けてゆく。
藤のつぼみはまだ小さくて硬い。
春が来て、過ぎ去って行く。初夏を過ぎれば暑くなっていく。
今までもずっとそうで、きっと来年もそうだ。
金魚屋は、庭の桜にも藤にも、極力手をかけずに好き放題に育たせている。
さほど多くはない木である。放っておいても日照やら掃除やらは問題なさそうだからだ。
勝手に咲いては勝手に散りゆく、勝手に育ってたまに枝を落とす、そんな植物たち。
もしも金魚屋がいなくなってもそれは変わらないだろう。
世話をするものがいなくなって駄目になってしまう、ということは恐らくないだろう。
ただ雑草の背丈が伸びて、虫が増えて、鼠が増えるだけだろう。
木のデッキは腐り落ちて。
テーブルセットは塗装が落ちて錆びていく。
傍らの瓶では金魚が白い腹を晒した後、色を濁らせて腐っていく。
蠅とボウフラが湧いて、いずれ小さな骨が沈んでいく。水は澱んで苔と黴が繁殖していく。
夢見る。
庭がそんな有様になったころには、店内も荒れているだろう。
鍵は壊れ、或いは開けっ放しで、窓硝子は割れていようが割れていまいが透明感が損なわれ。
ざらつく床。埃の匂い。
この地区は些か治安が良くないようなので、きっとゴミも散乱する。
浮浪者が貪ったであろう菓子の包装紙。売るには手間で腹いせにぶちまけられた茶葉や珈琲。
漁るためにかはたまた地震でも起こったか、棚から落ちて割れた香水瓶と、すっかり乾いて揮発した液体の跡。
あちらこちらに散らばって踏まれて砕けた、透明な欠片たち。
夢見る。
金魚屋は、自分以外を見るのが好きだ。
自分の関与しなくなった景色が好きだ。
薄煙のフィルター越し、分厚いレンズ越しでは物足りないくらいに、金魚屋は金魚屋が邪魔だ。
希死念慮だとかそういうものではない、金魚屋は痛いのも苦しいのも好きではない。
けれどいつだって金魚屋は、どこかに消えてなくなりたいのだ。決してネガティブな意味ではなく、金魚屋はそれを愛している。それらを愛するためには、金魚屋はそこから去る必要があるのだ。
例えば家族。
例えば友人。
例えば故郷。
例えば名前。
例えば年齢、性別、存在、人格、「■■■■■」という人間。
愛している。愛しているからこそ手放す。
金魚屋の人生は、いわばそれそのものが金魚屋の作品だ。
金魚堂は、金魚屋の最高で最後の愛するものになる予定だ。
 |
金魚屋 「……だから、あんま、侵略とか勘弁してほしいでやすねぇ…。」 |
猫はそこで目を開いた。
猫は、退屈そうに一つ大欠伸をして、歩みを再開させた。
猫にとっては、どうだっていいことだ。
今まで、なんて一つもなかったのだから。



ENo.201 チカギ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||



ItemNo.5 魚の丸焼き を美味しくいただきました!
体調が 1 回復!(17⇒18)
今回の全戦闘において 防御10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!









合成LV を 4 DOWN。(LV16⇒12、+4CP、-4FP)
制約LV を 6 UP!(LV0⇒6、-6CP)
料理LV を 10 UP!(LV10⇒20、-10CP)
ItemNo.7 パンの耳 から料理『魚の丸焼き』をつくりました!
⇒ 魚の丸焼き/料理:強さ30/[効果1]防御10 [効果2]治癒10 [効果3]-
 |
パンの耳に寄ってきた魚がこんがり焼けている。 |
幽霊タクシー(944) とカードを交換しました!
outrage (アウトレイジ)

イレイザー を研究しました!(深度0⇒1)
イレイザー を研究しました!(深度1⇒2)
リストリクト を研究しました!(深度2⇒3)
リストリクト を習得!
ファイアダンス を習得!
デスパレイト を習得!
ウィザー を習得!



チナミ区 R-4(沼地)に移動!(体調18⇒17)
チナミ区 R-3(沼地)に移動!(体調17⇒16)
チナミ区 Q-3(沼地)に移動!(体調16⇒15)
チナミ区 P-3(チェックポイント)に移動!(体調15⇒14)
採集はできませんでした。
- 大化け猫(1656) の選択は チナミ区 E-5:出発地(ベースキャンプ外のため無効)
MISSION!!
チナミ区 P-3:瓦礫の山 が発生!
- 大化け猫(1656) が経由した チナミ区 P-3:瓦礫の山






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
ドライバーさん 「・・・・・ふー。」 |

ドライバーさん
次元タクシーの運転手。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。
時計台の前でタバコをふかす、ドライバーさん。
 |
ドライバーさん 「・・・・・。」 |
時計台をぼーっと見上げる。
 |
ドライバーさん 「・・・・・。」 |
自分の腕時計を確認する。
 |
ドライバーさん 「・・・・・。」 |
・・・とても嫌そうな表情になる。
 |
ドライバーさん 「・・・・・狂ってんじゃねーか。」 |
 |
ドライバーさん 「早出手当は出・・・ ・・・ねぇよなぁ。あー・・・・・ ・・・・・面倒だが、社長に報告かね。あー、めんでぇー・・・」 |







チナミ区 P-3
瓦礫の山
瓦礫の山
 |
マイケル 「あ、来ましたかー。チェックポイントはこちらですよー。」 |
瓦礫の山の上に立つ、棒のような何かが呼んでいる。

マイケル
陽気な棒形人工生命体。
マイケル以外にもいろんな種類があるんだZE☆
マイケル以外にもいろんな種類があるんだZE☆
 |
マイケル 「遠方までご苦労さまです、私はマイケルです。 お疲れでしょう。とりあえずお茶でも。」 |
チーン!という音と共に頭から湯呑茶碗が現れ、それを手渡す。
 |
マイケル 「……少しは休めましたか?」 |
 |
マイケル 「それではさっさとおっ始めましょう。」 |
地面からマイケルと同じようなものがボコッと現れる。
 |
マイケル 「私達に勝利できればこのチェックポイントを利用できるようになります。 何人で来ようと手加減はしませんからねぇー!!」 |



ENo.1656
金魚屋



「心は砕けて気は配れちまうもんでさぁ、そやって使って配って擦り減っちまった心ってやつは、ちゃぁんと補充せにゃぁならんと思いますよぅ。」
「そのためのお手伝い、安らぎ求めて、どうぞどうぞ、お気軽に。」
「よぉこそ、いらっしゃいまし、煙と香りの『金魚堂』へ。」
名前:金魚屋
身長:165cmあるかないか程度
煙と香りの店、【金魚堂】の店主。
名乗りは金魚屋、年齢も性別も不詳。聞かれるとはぐらかす不審者っぷり。
喋りもわざとらしいまでに怪しさ満載だが、他意はない。ただの趣味。
人は良く、面倒見も良いが、ぱっと見変わり者。
(※無理矢理な性別看破はご遠慮頂けると幸いです)
++++++++++
異能:心離【ストレイマインド】
想いや心情、それに伴う記憶の一部を固形化する能力。対象が拒否する場合は発動できない。また、固形化したところで完全に想いがなくなるわけではない。
固形は想いによってさまざまな香りや色を持ち、砕くことができ、液体に溶け、熱によって立ち上る。粘膜による摂取が可能。
摂取によりその想いを感じることができる。ただ、感じるのみ。
別の物質とこの固形を混ぜ合わせると物質の性質が変化することがあるが、それによって人体に影響を及ぼすことはできない。
金魚堂で売られている商品には金魚屋の想いがふんわりうっすら混ぜられていることがある。
また、固形化された想いはパッと見ただけでは想いであると知ることはできない。
ただし、金魚屋はそれを知ることができる。どんな想いが固まったのかも、見れば察することができる。あくまで察するだけ。
++++++++++
sub
名前:熊谷紫明(クマガヤ シメイ)
年齢:17歳
身長:174㎝
金魚屋の家に居候している不良男子高校生。彼もまた、金魚屋の素性は知らない。
素行はよくないが、すごく悪気があるというわけではない。自由人。
異能:【呱々】
芽吹かせる能力。種さえあれば植物でも生命でも感情でも芽吹かせることができる。
ただし種がなければ何も起こらない。また、芽吹いたものが育つか育たないかはこの能力の範疇にはない。
++++++++++
【???】
金魚屋のハザマでの姿。所謂真の姿。大の大人ほどもある大化け猫。
気紛れで、楽しいことが大好き。
それだけ。
「そのためのお手伝い、安らぎ求めて、どうぞどうぞ、お気軽に。」
「よぉこそ、いらっしゃいまし、煙と香りの『金魚堂』へ。」
名前:金魚屋
身長:165cmあるかないか程度
煙と香りの店、【金魚堂】の店主。
名乗りは金魚屋、年齢も性別も不詳。聞かれるとはぐらかす不審者っぷり。
喋りもわざとらしいまでに怪しさ満載だが、他意はない。ただの趣味。
人は良く、面倒見も良いが、ぱっと見変わり者。
(※無理矢理な性別看破はご遠慮頂けると幸いです)
++++++++++
異能:心離【ストレイマインド】
想いや心情、それに伴う記憶の一部を固形化する能力。対象が拒否する場合は発動できない。また、固形化したところで完全に想いがなくなるわけではない。
固形は想いによってさまざまな香りや色を持ち、砕くことができ、液体に溶け、熱によって立ち上る。粘膜による摂取が可能。
摂取によりその想いを感じることができる。ただ、感じるのみ。
別の物質とこの固形を混ぜ合わせると物質の性質が変化することがあるが、それによって人体に影響を及ぼすことはできない。
金魚堂で売られている商品には金魚屋の想いがふんわりうっすら混ぜられていることがある。
また、固形化された想いはパッと見ただけでは想いであると知ることはできない。
ただし、金魚屋はそれを知ることができる。どんな想いが固まったのかも、見れば察することができる。あくまで察するだけ。
++++++++++
sub
名前:熊谷紫明(クマガヤ シメイ)
年齢:17歳
身長:174㎝
金魚屋の家に居候している不良男子高校生。彼もまた、金魚屋の素性は知らない。
素行はよくないが、すごく悪気があるというわけではない。自由人。
異能:【呱々】
芽吹かせる能力。種さえあれば植物でも生命でも感情でも芽吹かせることができる。
ただし種がなければ何も起こらない。また、芽吹いたものが育つか育たないかはこの能力の範疇にはない。
++++++++++
【???】
金魚屋のハザマでの姿。所謂真の姿。大の大人ほどもある大化け猫。
気紛れで、楽しいことが大好き。
それだけ。
14 / 30
146 PS
チナミ区
P-3
P-3





































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材・消耗の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 採れたて新鮮ねこじゃらし | 武器 | 36 | 祝福10 | - | - | 【射程1】 |
| 5 | 何かの骨 | 素材 | 20 | [武器]舞衰10(LV15)[防具]活力15(LV30)[装飾]鎮痛10(LV15) | |||
| 6 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]敏捷10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) | |||
| 7 | 魚の丸焼き | 料理 | 30 | 防御10 | 治癒10 | - | |
| 8 | 花びら | 素材 | 10 | [武器]地纏10(LV25)[防具]回復10(LV10)[装飾]祝福10(LV20) | |||
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 魔術 | 6 | 破壊/詠唱/火 |
| 呪術 | 10 | 呪詛/邪気/闇 |
| 制約 | 6 | 拘束/罠/リスク |
| 変化 | 10 | 強化/弱化/変身 |
| 合成 | 12 | 合成に影響 |
| 料理 | 20 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 7 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| ティンダー | 6 | 0 | 40 | 敵:火撃&炎上 | |
| ダークネス | 6 | 0 | 60 | 敵:闇撃&盲目 | |
| リストリクト | 5 | 0 | 60 | 敵:DX・AG減(2T) | |
| ストレングス | 5 | 0 | 100 | 自:AT増 | |
| ブラックウェッジ | 6 | 0 | 60 | 敵:闇痛撃 | |
| ファイアダンス | 5 | 0 | 80 | 敵:2連火撃&炎上、領域値[火]3以上なら、更に火撃&炎上 | |
| ファイアウィング | 6 | 0 | 60 | 自:炎上LV・AG増 | |
| デスパレイト | 5 | 0 | 60 | 敵:闇痛撃+自:瀕死なら連続増 | |
| アウトレイジ | 6 | 0 | 90 | 自:AT・闇特性増 | |
| ウィザー | 5 | 0 | 60 | 敵:痛撃&次与ダメ減 | |
| エナジードレイン | 6 | 0 | 160 | 敵:闇撃&DF奪取 | |
| ストライキング | 5 | 0 | 150 | 自:MHP・AT・DF増+連続減 | |
| コラプション | 5 | 0 | 160 | 敵:SP攻撃&AT・DF減(3T) |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| 敏捷 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| 活力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 体力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 治癒 | 6 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 鎮痛 | 7 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| 幸運 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 |



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
ナレハテのカード (サモン:ナレハテ) |
0 | 200 | 自:ナレハテ召喚 | |
|
オケヤの商機 (エアスラスト) |
0 | 60 | 敵:4連風撃 | |
|
outrage (アウトレイジ) |
0 | 90 | 自:AT・闇特性増 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]リストリクト | [ 3 ]ハルシネイト | [ 2 ]イレイザー |
| [ 1 ]テリトリー |

PL / 646