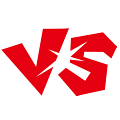<< 4:00>> 6:00




「軍手拾ったった」
「軍手……?」
ある日の夕暮れ、警察署からコンビニへ弁当を買いに行く最中だった。まっすぐコンビニへ向かおうとするMグチととは違い、Sグチは同じくコンビニへ向かおうとしているのにあっちへふらふらこっちへふらふら。猫に話しかけたり、買うわけでもない店先の焼き芋に目をやっていたり。Mグチも、小言を言いながらもいちいちそれを待つので、警察署から歩いて5分もしないコンビニのはずが10分以上ってもまだたどり着いていない有様。
「かわいそうに、かたっぽだけだ」
「トラックから落ちちゃったんだろ。よくあることだよ」
軍手を拾ったSグチは、両手で軍手を操り、まるで手足のある人形のように動かして遊んでいる。夕日に照らされるその様子が、なんだか本当に動いて襲ってくるのではないかと思わせてくるのは、なんだろう。バカらしい、ただの軍手だ。
「そういや、俺、昨日の夜、軍手の夢見たんだよね」
「軍手の夢?」
「廃墟になったイバラシティで、俺とMグチが歩く軍手と戦う夢」
歩きながら話し出す。どうやら、Sグチは見る夢もずいぶん突飛なものらしい。
「なんだそれ。軍手が攻撃してくるの?」
「ちょうどこのくらいの軍手だったと思うんだけどさ。『ぐぐぅ』ってかわいく鳴いて、異能で攻撃してくんの」
それは、恐ろしいな。他人の夢の話はつまらないと言うけれど、こんな突飛でくだらない話だとなかなかおもしろい。
「それで、僕たちは軍手と戦ってるわけ? イバラシティが廃墟になんてなってたら街中大混乱で、軍手なんかに構ってる暇なさそうだけど」
「いや、そこには俺とお前しかいなくてさぁ。軍手もなかなか強くて。なんとか勝ってたけど」
なんというか、とても夢らしい夢だ。僕だったら、廃墟になったイバラシティに兄と二人きりなんて、恐ろしくて軍手と戦うどころじゃないだろう。兄さんの夢の中の僕は強い。
「そんで……、あっ、そうそう。なんか、俺たちは花見をするために梅楽園に行こうとしてんの」
梅楽園、とはチナミ区にある公園の梅楽園だろう。街が廃墟と化してるのに、夢の中の僕らはずいぶんとのんきだ。
「ふーん。で、僕らは梅楽園に行けたの?」
「いや、そのあとは覚えてない。なんか、そんな夢見たから梅楽園行きたくなっちゃってさ〜。今度の非番の日に行ってこようかなぁ」
「チナミ区だろ? 遠いなぁ。急な呼び出しが無ければいいけど」
「今年、桜だって満足に見れなかったからな〜。いつも、いつの間にか散ってんのよな。だから、せめて、梅くらいはゆっくり見たいんだよ〜」
たしかに、春に花見なんてもう10年以上行っていない。それは、休みが少ないのもあるけれど、休みがあっても疲れてて花見に行く気分じゃないからというのもある。
「兄さんは元気だな。もう、この歳になったら普通、非番の日はゆっくり家で休んでたいものなのに」
「なに言ってんのMグっちゃん、俺ら花の30代よ。まだまだ、人生を楽しまなきゃ。人生には心をカサカサさせないことも大事よ。なぁ、歩行軍手くん」
ソウダヨッ、とSグチが軍手を動かしながら裏声でアテレコする。歩行軍手とは、またそのまんまなネーミングだ。
「はいはい、それより前にまずは弁当ね」
曲がり角を曲がると、いつものコンビニが見えた。Sグチは軍手を腰のポケットに突っ込むと、コンビニへ駆けていく。それを、Mグチは慌てて追っていった。
「その軍手、どうするの」
署に戻り、デスクで竜田揚げ弁当を食べながら、隣の席に座るSグチに聞いた。
「どうって、俺達はお巡りさんだぜ」
「落とし物センターに届けるの?」
「俺たちで軍手の落とし主を見つけるのだ!」
小気味の良い音がした。Mグチか、Sグチの頭を叩く音。周囲の刑事たちがこちらに目をやってくるが、すぐに各々の会話や作業に戻っていった。
「あんな夢みたからって、まだ寝ぼけてんの?」
「Mグっちゃん、手厳しーな……。いやぁ、なんか、夢の中で見た軍手と似てるから名残惜しくてさ」
花見も満足に行けない僕らが、どこにいるかもわからない、手がかりもない軍手のかたっぽを落とし主に届けるなんてできるはずがない。そんなことは兄もわかっている。つまり、兄はまだ軍手を手放したくはないらしい。
「でも、刑事がネコババするわけにもいかないだろ。おとなしく、落とし物センターに足を運ぶことだね」
Sグチは、眉を絵に描いたようなハの字にしてしょぼくれている。そんなにその薄汚れた軍手が欲しいのだろうか。兄の考えることはよくわからない。
「兄さん、そんなに夢で見た軍手が忘れられないの? たかが夢じゃないか」
「夢で見た歩く軍手がさぁ、これまたゆるキャラっぽくてかわいいのよ……」
Sグチは、そう言って弁当の竜田揚げを口に運んだ。
小気味の良い音。二度目。
「僕の弁当!!」
「なんでよ〜、食わねーならいいじゃん」
「最後に食べようとしてたの!」
その、くだらない騒ぎが同僚に叱られて止まるまで、もうすこしだけ時間がかかる。
空が赤く染まる、逢魔が時のことだった。
赤い空を見上げて、Mグチはため息をついた。言い合いの熱も冷めている。先程まで言い合いの最中だったと、自分の脳みそが伝えていた。
「Mグチが先に食わねーから悪いんだろーが!」
隣りにいるSグチが言った。
ハザマ時間がやってきた。ここに来ると、今までなんでこんな大変な事態を忘れていたんだろうと不思議になる。自らの居場所を賭けた戦いの舞台。そこに、僕らは立っている。のだが……
「いつも思ってたけど、そういう良いのものは最後にみたいなみみっちい考え止めたほうがいいと思うぜ! そんなんだから、おいしいとこ持ってかれて更に眉間に皺が寄るんだ!」
Sグチは、ハザマ時間などお構いなしに先程のくだらない言い合いを続けている。冷めていたはずなのに、そう突っかかられると自分も次第に熱がこもってくる。
「他人の弁当を勝手に食う人にとやかく言われる筋合いはないね。軍手に続いて竜田揚げまで盗んで」
言ってやった。イライラして、眉間に皺が寄る。
「はぁ!? 軍手は盗んでねーだろ!」
「僕が言わなきゃ、盗んでたんだろ。刑事より泥棒のほうが才能あるんじゃないの」
「お前っ、言わせておけば!!」
Sグチが飛びかかってきた。丁度いい。ここなら、いくら暴れても周りに被害は無い。普段の鬱憤を晴らさせてもらおうと、僕は兄のケンカを真っ向から買うことにした。
「くっ………だらねぇ……」
床に組み伏せられたMグチが、息を切らせながら言った。Mグチを押さえつけているSグチは、同じく息を切らせながら、しかし満足そうにニヤリと笑っていた。
「俺の勝ち」
真っ向からの殴り合いの喧嘩だった。しばらくは互角といった具合だったが、先に息切れを起こしたMグチをSグチが隙を突いて押さえつけた。腕をねじりあげられ、Mグチは動くことができない。次第に、熱が冷めていく。同時に、後悔の波。
「……なにしてんだろ、僕ら。世界を巡って争っている最中なんじゃないの?」
「へへ、やべぇな。30分くらいケンカしてたか? いやぁ、それにしても久しぶりだな。こんなに派手に喧嘩したの」
Sグチが楽しげに笑った。
弁当のおかずを食べられたからと言って、こんなに喧嘩するなんて小学生でもしないだろう。人が通らなくて本当に良かった。
「ま、結果はこの通り俺の勝ちだ。一番美味しいのはつぶあんで、きのこの大勝利ってわけよ」
「なんの話?」
兄が何のために戦っていたのか、もはやわからない。多分、途中で言い合いなんてどうでもよくなって、ただただケンカをしたいだけだったんじゃないだろうか。もしや、兄の娯楽に付き合うためだけに焚き付けられていたのか、僕は?
「ねぇ、僕ら、次ここに来たら梅楽園に行こうって言ってたじゃないか。今から行って間に合うかな」
「微妙いなぁ。また次に持ち越しになっちゃうかな。でも、走って行けばギリでなんとか着くかも」
「じゃ、早く行こうよ」
「おう」
Sグチが、元気よく返事をした。
「……兄さん」
「なに?」
「離して……」
Mグチは、未だにSグチに組み伏せられたままだ。Sグチは、Mグチを開放しようとしない。
「なんか、久々に喧嘩したから、もっと勝利の余韻を味わいたくて……」
これまた、くだらない理由だ。
「せっかく勝ったのに、ただで開放するのも癪じゃん。そうだ、Mグっちゃん。お前が俺の言うこと一つ聞いてくれたら、開放してやろう」
くだらない提案。兄の享楽的脳みそはおもちゃかなにかでできているのだろうか。Sグチの顔になんとか目をやると、相変わらずのニヤケ顔をしている。
「一回、俺のこと『お兄ちゃん』って呼んでみてくんない? 呼ばれて、どんな感じか気になるんだよね」
Mグチは、苦虫を噛み潰したような顔をした。すごく嫌だ。兄さんとお兄ちゃんでは雲泥の差がある。第一、今はそんなことをしている場合じゃないはずだ。が、きっと兄には関係無いのだろう。
「はやく〜、梅楽園に間に合わねーぞぉ?」
兄の一時の愉悦のために自分のプライドを擦り減らさねばいけないのが、これまた腹が立つ。それに、自分が腕を離せば解決することなのに、まるで僕が悪いと言うような言い方も合わさり、もはや腹をたてるのが馬鹿らしく思えるほどだ。
「お……」
早く、梅楽園に行きたい。こんなおどろおどろしい廃墟ではなく、梅の花が咲き乱れる公園で一休みしたい。そんな思いで羞恥を誤魔化し、口を開いた。
「……あっ、あれっ! 軍手! 歩行軍手じゃーん! ちょちょちょ、待って〜!」
Sグチが突然Mグチを押さえつけるのをやめ、走り出す。先には、以前見かけた歩行する軍手。
「逃げんな! あっ、やめろそのビターンってするの痛いから!!」
「ぐぐぅ!」
威嚇と攻撃を繰り返す軍手を捕まえようと、Sグチは必死で攻撃を堪えている。
取り残されたMグチは、そのくだらなさにもはや起き上がる気力もなく、呆れた視線をSグチに送るしか無かった。
「……今度から、兄さんの気を逸らせたい時は軍手でも投げるか」
ぽつり、と呟いた言葉は、Sグチと軍手が起こす喧騒に掻き消されていった。
「で、兄さんが僕にお兄ちゃんとか呼ばせようとして、そこに軍手が現れて……」
「なんで、お兄ちゃんなんて呼ばせようとしてんの? お前の夢の中の俺」
翌朝、署の仮眠室で目覚めたMグチは、見た夢の話をSグチに聞かせていた。
「あー、わかったぞ。実のところ、お前は俺のことを『お兄ちゃん』って呼びたいという深層心理の表れだ! いいぜ〜、Mグっちゃん。お前の望み、聞き入れてやろう。そら、お兄ちゃんって呼んでみ」
「バカ言ってないで、顔洗いに行くよ、兄さん」
「なぁなぁ、呼んでみってぇ。ほら、お兄ちゃんですよ〜」
「僕、朝から人の頭を叩きたくないんだけど」
仮眠室を出て、洗面台へ二人並んで歩いていく。窓から見える空にはすっかり日が昇り、清々しい朝の空そのものだ。
「そうそう、なんか気になって調べたんだけど、軍手の夢って努力が実るって意味らしいぜ。かーっ、俺の長年の努力が報われる日が近いかぁ」
「兄さん、なんか努力してることあるの?」
「スマホのゲーム」
「あっそ」
兄らしい返答を聞き流し、首を回すとコキコキと鳴った。まだ、疲れが取れていない。きっと、夢のように兄と長くケンカをしてたらこんな疲れが貯まるだろう。
「兄さんが夢の話なんてするから、変な夢見ちゃったなぁ。なんか、まだ疲れてる」
「俺ァ、清々しい気分だけどね。なんか、勝利の翌日って感じ」
兄は、いつもこんな調子だ。今は、それが羨ましい。腰に手を当てて、背伸びをした。今日も一日を始めるために、僕らは廊下を歩いていく。



特に何もしませんでした。










具現LV を 3 UP!(LV14⇒17、-3CP)
武器LV を 3 UP!(LV29⇒32、-3CP)
ローエレメント を研究しました!(深度0⇒1)
ローエレメント を研究しました!(深度1⇒2)
ローエレメント を研究しました!(深度2⇒3)



チナミ区 O-15(草原)に移動!(体調12⇒11)
チナミ区 O-16(森林)に移動!(体調11⇒10)
採集はできませんでした。
- Mグチ(1162) の選択は チナミ区 E-5:出発地(ベースキャンプ外のため無効)
MISSION - 未発生:
- Mグチ(1162) の選択は チナミ区 P-3:瓦礫の山(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。

時計台の前でタバコをふかす、ドライバーさん。
時計台をぼーっと見上げる。
自分の腕時計を確認する。
・・・とても嫌そうな表情になる。














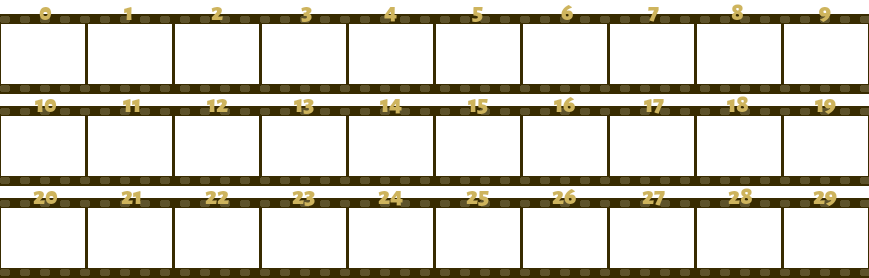





































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [スキル]OK.



「軍手拾ったった」
「軍手……?」
ある日の夕暮れ、警察署からコンビニへ弁当を買いに行く最中だった。まっすぐコンビニへ向かおうとするMグチととは違い、Sグチは同じくコンビニへ向かおうとしているのにあっちへふらふらこっちへふらふら。猫に話しかけたり、買うわけでもない店先の焼き芋に目をやっていたり。Mグチも、小言を言いながらもいちいちそれを待つので、警察署から歩いて5分もしないコンビニのはずが10分以上ってもまだたどり着いていない有様。
「かわいそうに、かたっぽだけだ」
「トラックから落ちちゃったんだろ。よくあることだよ」
軍手を拾ったSグチは、両手で軍手を操り、まるで手足のある人形のように動かして遊んでいる。夕日に照らされるその様子が、なんだか本当に動いて襲ってくるのではないかと思わせてくるのは、なんだろう。バカらしい、ただの軍手だ。
「そういや、俺、昨日の夜、軍手の夢見たんだよね」
「軍手の夢?」
「廃墟になったイバラシティで、俺とMグチが歩く軍手と戦う夢」
歩きながら話し出す。どうやら、Sグチは見る夢もずいぶん突飛なものらしい。
「なんだそれ。軍手が攻撃してくるの?」
「ちょうどこのくらいの軍手だったと思うんだけどさ。『ぐぐぅ』ってかわいく鳴いて、異能で攻撃してくんの」
それは、恐ろしいな。他人の夢の話はつまらないと言うけれど、こんな突飛でくだらない話だとなかなかおもしろい。
「それで、僕たちは軍手と戦ってるわけ? イバラシティが廃墟になんてなってたら街中大混乱で、軍手なんかに構ってる暇なさそうだけど」
「いや、そこには俺とお前しかいなくてさぁ。軍手もなかなか強くて。なんとか勝ってたけど」
なんというか、とても夢らしい夢だ。僕だったら、廃墟になったイバラシティに兄と二人きりなんて、恐ろしくて軍手と戦うどころじゃないだろう。兄さんの夢の中の僕は強い。
「そんで……、あっ、そうそう。なんか、俺たちは花見をするために梅楽園に行こうとしてんの」
梅楽園、とはチナミ区にある公園の梅楽園だろう。街が廃墟と化してるのに、夢の中の僕らはずいぶんとのんきだ。
「ふーん。で、僕らは梅楽園に行けたの?」
「いや、そのあとは覚えてない。なんか、そんな夢見たから梅楽園行きたくなっちゃってさ〜。今度の非番の日に行ってこようかなぁ」
「チナミ区だろ? 遠いなぁ。急な呼び出しが無ければいいけど」
「今年、桜だって満足に見れなかったからな〜。いつも、いつの間にか散ってんのよな。だから、せめて、梅くらいはゆっくり見たいんだよ〜」
たしかに、春に花見なんてもう10年以上行っていない。それは、休みが少ないのもあるけれど、休みがあっても疲れてて花見に行く気分じゃないからというのもある。
「兄さんは元気だな。もう、この歳になったら普通、非番の日はゆっくり家で休んでたいものなのに」
「なに言ってんのMグっちゃん、俺ら花の30代よ。まだまだ、人生を楽しまなきゃ。人生には心をカサカサさせないことも大事よ。なぁ、歩行軍手くん」
ソウダヨッ、とSグチが軍手を動かしながら裏声でアテレコする。歩行軍手とは、またそのまんまなネーミングだ。
「はいはい、それより前にまずは弁当ね」
曲がり角を曲がると、いつものコンビニが見えた。Sグチは軍手を腰のポケットに突っ込むと、コンビニへ駆けていく。それを、Mグチは慌てて追っていった。
「その軍手、どうするの」
署に戻り、デスクで竜田揚げ弁当を食べながら、隣の席に座るSグチに聞いた。
「どうって、俺達はお巡りさんだぜ」
「落とし物センターに届けるの?」
「俺たちで軍手の落とし主を見つけるのだ!」
小気味の良い音がした。Mグチか、Sグチの頭を叩く音。周囲の刑事たちがこちらに目をやってくるが、すぐに各々の会話や作業に戻っていった。
「あんな夢みたからって、まだ寝ぼけてんの?」
「Mグっちゃん、手厳しーな……。いやぁ、なんか、夢の中で見た軍手と似てるから名残惜しくてさ」
花見も満足に行けない僕らが、どこにいるかもわからない、手がかりもない軍手のかたっぽを落とし主に届けるなんてできるはずがない。そんなことは兄もわかっている。つまり、兄はまだ軍手を手放したくはないらしい。
「でも、刑事がネコババするわけにもいかないだろ。おとなしく、落とし物センターに足を運ぶことだね」
Sグチは、眉を絵に描いたようなハの字にしてしょぼくれている。そんなにその薄汚れた軍手が欲しいのだろうか。兄の考えることはよくわからない。
「兄さん、そんなに夢で見た軍手が忘れられないの? たかが夢じゃないか」
「夢で見た歩く軍手がさぁ、これまたゆるキャラっぽくてかわいいのよ……」
Sグチは、そう言って弁当の竜田揚げを口に運んだ。
小気味の良い音。二度目。
「僕の弁当!!」
「なんでよ〜、食わねーならいいじゃん」
「最後に食べようとしてたの!」
その、くだらない騒ぎが同僚に叱られて止まるまで、もうすこしだけ時間がかかる。
空が赤く染まる、逢魔が時のことだった。
赤い空を見上げて、Mグチはため息をついた。言い合いの熱も冷めている。先程まで言い合いの最中だったと、自分の脳みそが伝えていた。
「Mグチが先に食わねーから悪いんだろーが!」
隣りにいるSグチが言った。
ハザマ時間がやってきた。ここに来ると、今までなんでこんな大変な事態を忘れていたんだろうと不思議になる。自らの居場所を賭けた戦いの舞台。そこに、僕らは立っている。のだが……
「いつも思ってたけど、そういう良いのものは最後にみたいなみみっちい考え止めたほうがいいと思うぜ! そんなんだから、おいしいとこ持ってかれて更に眉間に皺が寄るんだ!」
Sグチは、ハザマ時間などお構いなしに先程のくだらない言い合いを続けている。冷めていたはずなのに、そう突っかかられると自分も次第に熱がこもってくる。
「他人の弁当を勝手に食う人にとやかく言われる筋合いはないね。軍手に続いて竜田揚げまで盗んで」
言ってやった。イライラして、眉間に皺が寄る。
「はぁ!? 軍手は盗んでねーだろ!」
「僕が言わなきゃ、盗んでたんだろ。刑事より泥棒のほうが才能あるんじゃないの」
「お前っ、言わせておけば!!」
Sグチが飛びかかってきた。丁度いい。ここなら、いくら暴れても周りに被害は無い。普段の鬱憤を晴らさせてもらおうと、僕は兄のケンカを真っ向から買うことにした。
「くっ………だらねぇ……」
床に組み伏せられたMグチが、息を切らせながら言った。Mグチを押さえつけているSグチは、同じく息を切らせながら、しかし満足そうにニヤリと笑っていた。
「俺の勝ち」
真っ向からの殴り合いの喧嘩だった。しばらくは互角といった具合だったが、先に息切れを起こしたMグチをSグチが隙を突いて押さえつけた。腕をねじりあげられ、Mグチは動くことができない。次第に、熱が冷めていく。同時に、後悔の波。
「……なにしてんだろ、僕ら。世界を巡って争っている最中なんじゃないの?」
「へへ、やべぇな。30分くらいケンカしてたか? いやぁ、それにしても久しぶりだな。こんなに派手に喧嘩したの」
Sグチが楽しげに笑った。
弁当のおかずを食べられたからと言って、こんなに喧嘩するなんて小学生でもしないだろう。人が通らなくて本当に良かった。
「ま、結果はこの通り俺の勝ちだ。一番美味しいのはつぶあんで、きのこの大勝利ってわけよ」
「なんの話?」
兄が何のために戦っていたのか、もはやわからない。多分、途中で言い合いなんてどうでもよくなって、ただただケンカをしたいだけだったんじゃないだろうか。もしや、兄の娯楽に付き合うためだけに焚き付けられていたのか、僕は?
「ねぇ、僕ら、次ここに来たら梅楽園に行こうって言ってたじゃないか。今から行って間に合うかな」
「微妙いなぁ。また次に持ち越しになっちゃうかな。でも、走って行けばギリでなんとか着くかも」
「じゃ、早く行こうよ」
「おう」
Sグチが、元気よく返事をした。
「……兄さん」
「なに?」
「離して……」
Mグチは、未だにSグチに組み伏せられたままだ。Sグチは、Mグチを開放しようとしない。
「なんか、久々に喧嘩したから、もっと勝利の余韻を味わいたくて……」
これまた、くだらない理由だ。
「せっかく勝ったのに、ただで開放するのも癪じゃん。そうだ、Mグっちゃん。お前が俺の言うこと一つ聞いてくれたら、開放してやろう」
くだらない提案。兄の享楽的脳みそはおもちゃかなにかでできているのだろうか。Sグチの顔になんとか目をやると、相変わらずのニヤケ顔をしている。
「一回、俺のこと『お兄ちゃん』って呼んでみてくんない? 呼ばれて、どんな感じか気になるんだよね」
Mグチは、苦虫を噛み潰したような顔をした。すごく嫌だ。兄さんとお兄ちゃんでは雲泥の差がある。第一、今はそんなことをしている場合じゃないはずだ。が、きっと兄には関係無いのだろう。
「はやく〜、梅楽園に間に合わねーぞぉ?」
兄の一時の愉悦のために自分のプライドを擦り減らさねばいけないのが、これまた腹が立つ。それに、自分が腕を離せば解決することなのに、まるで僕が悪いと言うような言い方も合わさり、もはや腹をたてるのが馬鹿らしく思えるほどだ。
「お……」
早く、梅楽園に行きたい。こんなおどろおどろしい廃墟ではなく、梅の花が咲き乱れる公園で一休みしたい。そんな思いで羞恥を誤魔化し、口を開いた。
「……あっ、あれっ! 軍手! 歩行軍手じゃーん! ちょちょちょ、待って〜!」
Sグチが突然Mグチを押さえつけるのをやめ、走り出す。先には、以前見かけた歩行する軍手。
「逃げんな! あっ、やめろそのビターンってするの痛いから!!」
「ぐぐぅ!」
威嚇と攻撃を繰り返す軍手を捕まえようと、Sグチは必死で攻撃を堪えている。
取り残されたMグチは、そのくだらなさにもはや起き上がる気力もなく、呆れた視線をSグチに送るしか無かった。
「……今度から、兄さんの気を逸らせたい時は軍手でも投げるか」
ぽつり、と呟いた言葉は、Sグチと軍手が起こす喧騒に掻き消されていった。
「で、兄さんが僕にお兄ちゃんとか呼ばせようとして、そこに軍手が現れて……」
「なんで、お兄ちゃんなんて呼ばせようとしてんの? お前の夢の中の俺」
翌朝、署の仮眠室で目覚めたMグチは、見た夢の話をSグチに聞かせていた。
「あー、わかったぞ。実のところ、お前は俺のことを『お兄ちゃん』って呼びたいという深層心理の表れだ! いいぜ〜、Mグっちゃん。お前の望み、聞き入れてやろう。そら、お兄ちゃんって呼んでみ」
「バカ言ってないで、顔洗いに行くよ、兄さん」
「なぁなぁ、呼んでみってぇ。ほら、お兄ちゃんですよ〜」
「僕、朝から人の頭を叩きたくないんだけど」
仮眠室を出て、洗面台へ二人並んで歩いていく。窓から見える空にはすっかり日が昇り、清々しい朝の空そのものだ。
「そうそう、なんか気になって調べたんだけど、軍手の夢って努力が実るって意味らしいぜ。かーっ、俺の長年の努力が報われる日が近いかぁ」
「兄さん、なんか努力してることあるの?」
「スマホのゲーム」
「あっそ」
兄らしい返答を聞き流し、首を回すとコキコキと鳴った。まだ、疲れが取れていない。きっと、夢のように兄と長くケンカをしてたらこんな疲れが貯まるだろう。
「兄さんが夢の話なんてするから、変な夢見ちゃったなぁ。なんか、まだ疲れてる」
「俺ァ、清々しい気分だけどね。なんか、勝利の翌日って感じ」
兄は、いつもこんな調子だ。今は、それが羨ましい。腰に手を当てて、背伸びをした。今日も一日を始めるために、僕らは廊下を歩いていく。



特に何もしませんでした。









具現LV を 3 UP!(LV14⇒17、-3CP)
武器LV を 3 UP!(LV29⇒32、-3CP)
ローエレメント を研究しました!(深度0⇒1)
ローエレメント を研究しました!(深度1⇒2)
ローエレメント を研究しました!(深度2⇒3)



チナミ区 O-15(草原)に移動!(体調12⇒11)
チナミ区 O-16(森林)に移動!(体調11⇒10)
採集はできませんでした。
- Mグチ(1162) の選択は チナミ区 E-5:出発地(ベースキャンプ外のため無効)
MISSION - 未発生:
- Mグチ(1162) の選択は チナミ区 P-3:瓦礫の山(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
ドライバーさん 「・・・・・ふー。」 |

ドライバーさん
次元タクシーの運転手。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。
時計台の前でタバコをふかす、ドライバーさん。
 |
ドライバーさん 「・・・・・。」 |
時計台をぼーっと見上げる。
 |
ドライバーさん 「・・・・・。」 |
自分の腕時計を確認する。
 |
ドライバーさん 「・・・・・。」 |
・・・とても嫌そうな表情になる。
 |
ドライバーさん 「・・・・・狂ってんじゃねーか。」 |
 |
ドライバーさん 「早出手当は出・・・ ・・・ねぇよなぁ。あー・・・・・ ・・・・・面倒だが、社長に報告かね。あー、めんでぇー・・・」 |





ENo.1162
SグチとMグチ



※Talkでは、お返事がめちゃくちゃ遅れたりします。気長にお付き合いいただければと思います。
なんだったら、PCたちはその後適当に話して切り上げて帰ったことにしといてください。自分もあまりに遅れてたらそんな感じでなんかします。(ガバガバロール勢)
Mグチ
真面目で神経質な男。32歳。身長は約180㎝。普段はSグチとともに刑事として働いている。
突飛な物事、非現実的なことに対応するのが苦手。蒸気アイマスクと焼き魚、ノンフィクション作品が好きで、リスケとパソコンのフリーズが嫌い。
本名、名鳥 正口(などり まさぐち)。Sグチの弟。
異能の名は「Master」。
Mグチを守ろうとする意思を持つ者の能力を強化する。
発動すると、その力は教鞭の形をもって手元に現れる。
Sグチ
飄々として物臭な男。35歳。身長は約180㎝。普段はMグチとともに刑事として働いている。
気ままで、大体の物事には驚かない性格。わくわくすることと駄菓子と酒が好きで、暇やマンネリ、ピーマンが嫌い。
本名、名鳥 真口(などり さなぐち)。Mグチの兄。
異能の名は「Servant」。
Sグチが誰かを守ろうとする意思を持った時、自身の身体能力を強化する。
発動すると、その力はイバラ鞭の形をもって手元に現れる。
いろいろ
●二人は刑事としてペアを組んでいるわけでは無いようだ
●同僚らには「SM兄弟」と言われたりする。Sグチはともかく、Mグチはあからさまに嫌な顔をする。
ーーーーー
ねこアイコンは「CHARAT/キャラット https://charat.me/」で作成させていただきました
なんだったら、PCたちはその後適当に話して切り上げて帰ったことにしといてください。自分もあまりに遅れてたらそんな感じでなんかします。(ガバガバロール勢)
Mグチ
真面目で神経質な男。32歳。身長は約180㎝。普段はSグチとともに刑事として働いている。
突飛な物事、非現実的なことに対応するのが苦手。蒸気アイマスクと焼き魚、ノンフィクション作品が好きで、リスケとパソコンのフリーズが嫌い。
本名、名鳥 正口(などり まさぐち)。Sグチの弟。
異能の名は「Master」。
Mグチを守ろうとする意思を持つ者の能力を強化する。
発動すると、その力は教鞭の形をもって手元に現れる。
Sグチ
飄々として物臭な男。35歳。身長は約180㎝。普段はMグチとともに刑事として働いている。
気ままで、大体の物事には驚かない性格。わくわくすることと駄菓子と酒が好きで、暇やマンネリ、ピーマンが嫌い。
本名、名鳥 真口(などり さなぐち)。Mグチの兄。
異能の名は「Servant」。
Sグチが誰かを守ろうとする意思を持った時、自身の身体能力を強化する。
発動すると、その力はイバラ鞭の形をもって手元に現れる。
いろいろ
●二人は刑事としてペアを組んでいるわけでは無いようだ
●同僚らには「SM兄弟」と言われたりする。Sグチはともかく、Mグチはあからさまに嫌な顔をする。
ーーーーー
ねこアイコンは「CHARAT/キャラット https://charat.me/」で作成させていただきました
10 / 30
257 PS
チナミ区
O-16
O-16




































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材・消耗の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 不思議な牙 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV5)[防具]防御10(LV5)[装飾]器用10(LV5) | |||
| 5 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]敏捷10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) | |||
| 6 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV5)[効果2]活力10(LV10)[効果3]鎮痛10(LV15) | |||
| 7 | 白樺 | 素材 | 15 | [武器]活力10(LV10)[防具]活力15(LV20)[装飾]活力10(LV10) | |||
| 8 | 駄木 | 素材 | 10 | [武器]体力10(LV20)[防具]防御10(LV20)[装飾]攻撃10(LV20) | |||
| 9 | 吸い殻 | 素材 | 10 | [武器]炎上10(LV25)[防具]道連10(LV20)[装飾]火纏10(LV25) | |||
| 10 | 青く光るイバラムチ(Sグチ用) | 武器 | 39 | 束縛10 | - | - | 【射程1】 |
| 11 | ネジ | 素材 | 15 | [武器]混乱10(LV25)[防具]追撃10(LV25)[装飾]貫通10(LV25) | |||
| 12 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]衰弱10(LV20)[防具]体力10(LV5)[装飾]防御10(LV15) | |||
| 13 | 白石 | 素材 | 15 | [武器]敏捷10(LV10)[防具]祝福10(LV10)[装飾]活力10(LV10) | |||
| 14 | ネジ | 素材 | 15 | [武器]混乱10(LV25)[防具]追撃10(LV25)[装飾]貫通10(LV25) | |||
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 15 | 身体/武器/物理 |
| 具現 | 17 | 創造/召喚 |
| 武器 | 32 | 武器作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 6 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 6 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| エキサイト | 6 | 0 | 40 | 敵:攻撃+自:AT増(1T) | |
| クリエイト:タライ | 6 | 0 | 40 | 敵:攻撃&朦朧・混乱 | |
| クリエイト:ウェポン | 6 | 0 | 60 | 味:追撃LV・次与ダメ増 | |
| イレイザー | 5 | 0 | 150 | 敵傷:攻撃 | |
| サモン:ウルフ | 5 | 0 | 300 | 自:ウルフ召喚 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| 活力 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 体力 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 治癒 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| 幸運 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 | |
| 召喚強化 | 5 | 2 | 0 | 【常時】異能『具現』のLVに応じて、自身の召喚するNPCが強化 |





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]シャイン | [ 3 ]クリエイト:タライ | [ 3 ]エナジードレイン |
| [ 3 ]ローエレメント |

PL / あすかパン