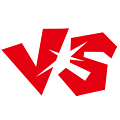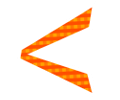<< 3:00>> 5:00




「茶屋を探しに行こうぜ、Mグチ」
暗い空のもと、荒廃したビルの屋上で兄が言った。
SグチとMグチは、薄ら寒い風に吹かれながら、ベンチに腰掛けていた。
これで4回目のハザマ時間だろうか。一時間という制限があるにしても、まるで世界の終わりのような世界を歩かなくてはいけないというのは精神的に辛かった。兄とともに連れてこられる分、自分はまだマシなのだろう。
ビルの屋上からは、見渡す限りの廃墟と化したイバラシティが一望できた。一時間もこんな場所でひとり過ごすなんて考えたくもない。
「ほら、さっき榊のヤツが食ってた……。ほら、"無"味のだんごあったじゃん」
Sグチが座っていたベンチから立ち上がり、だんごを食べる仕草をした。
数分前に榊という男がクロスローズ空間で食べていただんごのことだ。こんな退廃した世界には似つかわしくない、華やかな代物。そういえば、茶屋の周りには梅の花も咲いていた。
「あの景色が見えたってことはさ。つまり、このボロボロになったイバラシティのどこかにあの茶屋があるってことだろ? 我が家の様子を見に行くのもいいけどさぁ。心をカサカサさせないことも大事だと思うんだよね、俺は」
珍しく、Sグチの意見に賛同できた。アンジニティなんていう意味のわからない者たちと、イバラシティに住む権利を巡って戦うなんて馬鹿げてる。世界のはぐれ者集団だかなんだか知らないが、Mグチはただの平凡な刑事であって、街の平和を守りはすれど異世界からの侵略などどうしようもない。それに、いくら侵略者とはいえ街ですれ違ったことがあるかもしれない者を打ち倒すなど、Mグチは嫌だった。
「そんなにしょげんなよ。もう4回目だろ、ここに来んの」
「兄さんはさ」
うん、とSグチが相槌を返す。フェンスの外には退廃した町並みがひろがっている。どこかで、安寧の権利を得るために戦っている者たちがいるのだろうか。
「イバラシティのこと、どう思う。戦って、敵を打ち倒してまで住みたい街?」
僕らは、もうすっかり大人になった。どこに言ったっていい。どこに住んだっていい。全てに責任は伴うけれど、ずっと自由だ。
「僕、他人を傷つけてまで住みたいほどイバラシティに執着はしてないんだ。たしかにいい街だけどさ」
「イヤン、Mぐっちゃんは意外と大胆ね。こんな荒廃した世界でも、僕はやってけるぞってか」
「そんなんじゃないけど」
茶屋の風景を思い出す。花が咲き、店があって人がいる。こんな世界にも、たしかに人の営みはあった。
「なんか、よくわかんないんだよね。人の場所を奪ってまで居たくない場所っていうのが」
「そんなん、俺にだってわからん。もしかしたら、アンジニティの世界ってのは肥溜めみたいに臭い世界なのかもしれん」
「兄さん、僕真面目に話してるんだけど」
Sグチは、鼻をつまみながらうめき声をあげている。人目がないというのもあって、普段よりアクションが大きい。
「俺はイバラシティ好きだぜ。一番じゃないけどな。アンジニティのやつらも、イバラシティに住みたいんなら素直に転居届けでも出しゃいいのにな」
人が増えて市役所の奴らは泣き喚くだろうけど、とSグチが言う。
「あんま難しく考えんなよ。昔からの悪い癖だぞ。俺たちに襲いかかってくる奴らは倒す。それだけでいいじゃねーか。居場所を巡る争いなんて、俺達には関係無いもんね」
「……ハザマっていうのは、イバラシティの管轄なのかな?」
「おめー、そんなこと考えてたの? ナイナイ。似てるだけの別存在です。アニメとか見ないから、そんなこともわからんのだよ。イバラシティに帰ったら、撮り貯めたアニメいっしょに消化するぞ」
アニメはアニメだろ、とMグチは眉間にシワをよせた。この調子では、あと10年したら眉間のシワが取れなくなってしまうかもしれない。
「考えても仕方ないことを考えてても仕方ないの! 今の俺たちに必要なとこは、茶屋を探して一服すること。そして、いつのまにか散ってて逃した花見をすること! わぁーった?」
Sグチは気合の入った声で、Mグチにそう宣言した。兄さんらしいな、と呆れつつも、普段どおりのその態度に安心感を覚える。
「仕方ないな。じゃ、その茶屋を探しに行こうか。だんご、おいしそうだったもんね」
兄が普段どおりなのだ。だったら、弟である自分も普段どおりにしよう。
Mグチはベンチから立ち上がり、普段どおり、天真爛漫な兄に文句を言いながらついていく。
「で、どこなんだろうな。あの梅の茶屋は」
「榊さんに場所聞いとけばよかったね」
二人は、人家の無い古い住宅街をさまよっていた。
茶屋を目指そうと決めたのはいいものの、その場所がわからない。梅の花など、イバラシティではいくらでもある。
「多分、そんな遠くないと思うんだよね」
「なんでなんで?」
「このチナミ区って梅が多いじゃないか。だから、たぶんこのあたりじゃないかなって」
へー、とSグチが感心したような声を出した。そして
「あっ」
と、一言。
「どうしたの兄さん。忘れ物?」
「違うぞMグチ。俺はわかってしまったのだ」
Sグチが、ドヤ顔でこちらを見てくる。まるで、映画に出てくる謎を解決する決定的証拠を見つけた名探偵のごとく。
「おっと、そんな呆れたような顔をするな。俺は以前にチナミ区に来たことがあるのだよ。そのときに、梅の花が満開の場所を見たのだよ、ワトソンくん」
誰がワトソンだ。しかし、どうやら兄さんはあの茶屋の場所がわかったようだ。もったいぶらずに早く言ってほしい。探偵の真似もそんなに似てないし。
「ふふん、飽きっぽいお前がそっぽを向く前にズバリ言い当ててやろう。あの場所は、梅楽園だ!」
梅楽園。その名を聞いて思い出した。そういえば、同僚に話を聞いたことがある。チナミ区には常に梅の花が咲き乱れる場所があるのだという。それが異能の力かはわからないが、年中梅の花が見られる場所とあってよく見物客で賑わっているのだとか。しかし……。
「たしかに、可能性は高いね。兄さんはここから梅楽園への行き方はわかるの?」
得意げだったSグチの顔が、スンと普段どおりのやる気のない顔に戻った。
「そんなん知らん」
「だと思った! そうだ、たしかクロスローズで場所の確認ができるはず……」
「クロ……何……?」
「あんた、人の説明ほんとに聞かないな!」
Cross+Rose。このハザマ世界で様々の情報の閲覧、やり取りができる便利な機能だ。これも、誰かの異能なのだろうか?
地図を見ると、幸い梅楽園は遠くはなかった。歩いて一時間、というところだろうか。
「これは、また次回にお預けだね。残り時間じゃ梅楽園までは着けないよ」
「バスが出てりゃいいのにな。それか、タクシー使わしてくれるとか」
「さすがに、タクシーの運転手に未知の場所まで送ってもらうわけにはいかないよ。刑事が民間人を危険な目に遭わせちゃいけないからね」
「ありゃ、民間人なのかぁ?」
怪訝な顔をして、Sグチが首を傾げた。
地図を閉じる。次は、梅楽園へ行ってみよう。もしかしたら、なにもないかもしれないが細かい目標を立てるのはいいことだ。
「……おっと、もしかして、そろそろ一時間経つ? 時間が経つのは早いねぇ。非日常的なのが、俺の少年心をくすぐってくんのかな」
「おっさんの少年心なんてしまったまま出さないでほしいんだけどな。まったく……」
そう言って、腕時計を見る。時間は57分を示していた。
「戻ったら、またなんにも覚えてないんだろうなぁ。こんなゲームみたいな空間が記憶から抜け落ちるなんて、ちょっともったいないな」
「僕は一刻も早く忘れたいけどね……」
ふたりでボヤく。時計の針は少しずつ、イバラシティへと戻る時刻に近づいていく。
「ま、どこでも自由なのが大人ってやつよ。おもしろき〜こともなき世をなんとやらってね」
Mグチが、Sグチの顔を見た。
「おいおい、俺がイケメンだからってそんなに見つめられちゃ困っちゃうぜ」
Sグチも、同じことを思っていたのだ。大人は自由だと。そうだ、どこに行こうが、なにを成そうが僕らは自由なのだ。日常では大人げない一蹴するだろう思想が、この非現実的な世界では救いだった。
「おもしろく、だろ」
Sグチの笑顔につられて、Mグチもニヤリと笑った。



特に何もしませんでした。










具現LV を 3 UP!(LV11⇒14、-3CP)
武器LV を 3 UP!(LV26⇒29、-3CP)
ItemNo.10 毛 から射程1の武器『青く光るイバラムチ(Sグチ用)』を作製しました!
⇒ 青く光るイバラムチ(Sグチ用)/武器:強さ39/[効果1]束縛10 [効果2]- [効果3]-【射程1】



チナミ区 K-14(道路)に移動!(体調17⇒16)
チナミ区 K-15(道路)に移動!(体調16⇒15)
チナミ区 L-15(草原)に移動!(体調15⇒14)
チナミ区 M-15(草原)に移動!(体調14⇒13)
チナミ区 N-15(草原)に移動!(体調13⇒12)






―― ハザマ時間が紡がれる。

時計台の正面に立ち、怪訝な顔をしている。
一定のリズムで指を鳴らし、口笛を吹く――




















































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



「茶屋を探しに行こうぜ、Mグチ」
暗い空のもと、荒廃したビルの屋上で兄が言った。
SグチとMグチは、薄ら寒い風に吹かれながら、ベンチに腰掛けていた。
これで4回目のハザマ時間だろうか。一時間という制限があるにしても、まるで世界の終わりのような世界を歩かなくてはいけないというのは精神的に辛かった。兄とともに連れてこられる分、自分はまだマシなのだろう。
ビルの屋上からは、見渡す限りの廃墟と化したイバラシティが一望できた。一時間もこんな場所でひとり過ごすなんて考えたくもない。
「ほら、さっき榊のヤツが食ってた……。ほら、"無"味のだんごあったじゃん」
Sグチが座っていたベンチから立ち上がり、だんごを食べる仕草をした。
数分前に榊という男がクロスローズ空間で食べていただんごのことだ。こんな退廃した世界には似つかわしくない、華やかな代物。そういえば、茶屋の周りには梅の花も咲いていた。
「あの景色が見えたってことはさ。つまり、このボロボロになったイバラシティのどこかにあの茶屋があるってことだろ? 我が家の様子を見に行くのもいいけどさぁ。心をカサカサさせないことも大事だと思うんだよね、俺は」
珍しく、Sグチの意見に賛同できた。アンジニティなんていう意味のわからない者たちと、イバラシティに住む権利を巡って戦うなんて馬鹿げてる。世界のはぐれ者集団だかなんだか知らないが、Mグチはただの平凡な刑事であって、街の平和を守りはすれど異世界からの侵略などどうしようもない。それに、いくら侵略者とはいえ街ですれ違ったことがあるかもしれない者を打ち倒すなど、Mグチは嫌だった。
「そんなにしょげんなよ。もう4回目だろ、ここに来んの」
「兄さんはさ」
うん、とSグチが相槌を返す。フェンスの外には退廃した町並みがひろがっている。どこかで、安寧の権利を得るために戦っている者たちがいるのだろうか。
「イバラシティのこと、どう思う。戦って、敵を打ち倒してまで住みたい街?」
僕らは、もうすっかり大人になった。どこに言ったっていい。どこに住んだっていい。全てに責任は伴うけれど、ずっと自由だ。
「僕、他人を傷つけてまで住みたいほどイバラシティに執着はしてないんだ。たしかにいい街だけどさ」
「イヤン、Mぐっちゃんは意外と大胆ね。こんな荒廃した世界でも、僕はやってけるぞってか」
「そんなんじゃないけど」
茶屋の風景を思い出す。花が咲き、店があって人がいる。こんな世界にも、たしかに人の営みはあった。
「なんか、よくわかんないんだよね。人の場所を奪ってまで居たくない場所っていうのが」
「そんなん、俺にだってわからん。もしかしたら、アンジニティの世界ってのは肥溜めみたいに臭い世界なのかもしれん」
「兄さん、僕真面目に話してるんだけど」
Sグチは、鼻をつまみながらうめき声をあげている。人目がないというのもあって、普段よりアクションが大きい。
「俺はイバラシティ好きだぜ。一番じゃないけどな。アンジニティのやつらも、イバラシティに住みたいんなら素直に転居届けでも出しゃいいのにな」
人が増えて市役所の奴らは泣き喚くだろうけど、とSグチが言う。
「あんま難しく考えんなよ。昔からの悪い癖だぞ。俺たちに襲いかかってくる奴らは倒す。それだけでいいじゃねーか。居場所を巡る争いなんて、俺達には関係無いもんね」
「……ハザマっていうのは、イバラシティの管轄なのかな?」
「おめー、そんなこと考えてたの? ナイナイ。似てるだけの別存在です。アニメとか見ないから、そんなこともわからんのだよ。イバラシティに帰ったら、撮り貯めたアニメいっしょに消化するぞ」
アニメはアニメだろ、とMグチは眉間にシワをよせた。この調子では、あと10年したら眉間のシワが取れなくなってしまうかもしれない。
「考えても仕方ないことを考えてても仕方ないの! 今の俺たちに必要なとこは、茶屋を探して一服すること。そして、いつのまにか散ってて逃した花見をすること! わぁーった?」
Sグチは気合の入った声で、Mグチにそう宣言した。兄さんらしいな、と呆れつつも、普段どおりのその態度に安心感を覚える。
「仕方ないな。じゃ、その茶屋を探しに行こうか。だんご、おいしそうだったもんね」
兄が普段どおりなのだ。だったら、弟である自分も普段どおりにしよう。
Mグチはベンチから立ち上がり、普段どおり、天真爛漫な兄に文句を言いながらついていく。
「で、どこなんだろうな。あの梅の茶屋は」
「榊さんに場所聞いとけばよかったね」
二人は、人家の無い古い住宅街をさまよっていた。
茶屋を目指そうと決めたのはいいものの、その場所がわからない。梅の花など、イバラシティではいくらでもある。
「多分、そんな遠くないと思うんだよね」
「なんでなんで?」
「このチナミ区って梅が多いじゃないか。だから、たぶんこのあたりじゃないかなって」
へー、とSグチが感心したような声を出した。そして
「あっ」
と、一言。
「どうしたの兄さん。忘れ物?」
「違うぞMグチ。俺はわかってしまったのだ」
Sグチが、ドヤ顔でこちらを見てくる。まるで、映画に出てくる謎を解決する決定的証拠を見つけた名探偵のごとく。
「おっと、そんな呆れたような顔をするな。俺は以前にチナミ区に来たことがあるのだよ。そのときに、梅の花が満開の場所を見たのだよ、ワトソンくん」
誰がワトソンだ。しかし、どうやら兄さんはあの茶屋の場所がわかったようだ。もったいぶらずに早く言ってほしい。探偵の真似もそんなに似てないし。
「ふふん、飽きっぽいお前がそっぽを向く前にズバリ言い当ててやろう。あの場所は、梅楽園だ!」
梅楽園。その名を聞いて思い出した。そういえば、同僚に話を聞いたことがある。チナミ区には常に梅の花が咲き乱れる場所があるのだという。それが異能の力かはわからないが、年中梅の花が見られる場所とあってよく見物客で賑わっているのだとか。しかし……。
「たしかに、可能性は高いね。兄さんはここから梅楽園への行き方はわかるの?」
得意げだったSグチの顔が、スンと普段どおりのやる気のない顔に戻った。
「そんなん知らん」
「だと思った! そうだ、たしかクロスローズで場所の確認ができるはず……」
「クロ……何……?」
「あんた、人の説明ほんとに聞かないな!」
Cross+Rose。このハザマ世界で様々の情報の閲覧、やり取りができる便利な機能だ。これも、誰かの異能なのだろうか?
地図を見ると、幸い梅楽園は遠くはなかった。歩いて一時間、というところだろうか。
「これは、また次回にお預けだね。残り時間じゃ梅楽園までは着けないよ」
「バスが出てりゃいいのにな。それか、タクシー使わしてくれるとか」
「さすがに、タクシーの運転手に未知の場所まで送ってもらうわけにはいかないよ。刑事が民間人を危険な目に遭わせちゃいけないからね」
「ありゃ、民間人なのかぁ?」
怪訝な顔をして、Sグチが首を傾げた。
地図を閉じる。次は、梅楽園へ行ってみよう。もしかしたら、なにもないかもしれないが細かい目標を立てるのはいいことだ。
「……おっと、もしかして、そろそろ一時間経つ? 時間が経つのは早いねぇ。非日常的なのが、俺の少年心をくすぐってくんのかな」
「おっさんの少年心なんてしまったまま出さないでほしいんだけどな。まったく……」
そう言って、腕時計を見る。時間は57分を示していた。
「戻ったら、またなんにも覚えてないんだろうなぁ。こんなゲームみたいな空間が記憶から抜け落ちるなんて、ちょっともったいないな」
「僕は一刻も早く忘れたいけどね……」
ふたりでボヤく。時計の針は少しずつ、イバラシティへと戻る時刻に近づいていく。
「ま、どこでも自由なのが大人ってやつよ。おもしろき〜こともなき世をなんとやらってね」
Mグチが、Sグチの顔を見た。
「おいおい、俺がイケメンだからってそんなに見つめられちゃ困っちゃうぜ」
Sグチも、同じことを思っていたのだ。大人は自由だと。そうだ、どこに行こうが、なにを成そうが僕らは自由なのだ。日常では大人げない一蹴するだろう思想が、この非現実的な世界では救いだった。
「おもしろく、だろ」
Sグチの笑顔につられて、Mグチもニヤリと笑った。



特に何もしませんでした。









具現LV を 3 UP!(LV11⇒14、-3CP)
武器LV を 3 UP!(LV26⇒29、-3CP)
ItemNo.10 毛 から射程1の武器『青く光るイバラムチ(Sグチ用)』を作製しました!
⇒ 青く光るイバラムチ(Sグチ用)/武器:強さ39/[効果1]束縛10 [効果2]- [効果3]-【射程1】



チナミ区 K-14(道路)に移動!(体調17⇒16)
チナミ区 K-15(道路)に移動!(体調16⇒15)
チナミ区 L-15(草原)に移動!(体調15⇒14)
チナミ区 M-15(草原)に移動!(体調14⇒13)
チナミ区 N-15(草原)に移動!(体調13⇒12)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
榊 「・・・・・?」 |

榊
黒髪に蒼い瞳、黒スーツ。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
時計台の正面に立ち、怪訝な顔をしている。
 |
榊 「・・・この世界でオカシイも何も無いと言えば、無いのですが。 どうしましょうかねぇ。・・・どうしましょうねぇ。」 |
一定のリズムで指を鳴らし、口笛を吹く――





ENo.1162
SグチとMグチ



※Talkでは、お返事がめちゃくちゃ遅れたりします。気長にお付き合いいただければと思います。
Mグチ
真面目で神経質な男。32歳。身長は約180㎝。普段はSグチとともに刑事として働いている。
突飛な物事、非現実的なことに対応するのが苦手。現実主義者であり、誤魔化しや建前を嫌う正直者。いつも口をMの字にしてムスッとしている。その真面目さと表情故に、冷たい人間と思われがち。蒸気アイマスクと焼き魚、ノンフィクション作品が好きで、リスケとパソコンのフリーズが嫌い。
本名、名鳥 正口(などり まさぐち)。Sグチの弟。
異能の名は「Master」。
Mグチを守ろうとする意思を持つ者の能力を強化する。
発動すると、その力は教鞭の形をもって手元に現れる。
Sグチ
飄々として物臭な男。35歳。身長は約180㎝。普段はMグチとともに刑事として働いている。
気ままで、大体の物事には驚かない性格。理想主義者で、楽しそうなことがあればすぐに飛び込んでいく。いつも口をSの字にしてへらへらと笑っている。わくわくすることと駄菓子と酒が好きで、暇やマンネリ、ピーマンが嫌い。
本名、名鳥 真口(などり さなぐち)。Mグチの兄。
異能の名は「Servant」。
Sグチが誰かを守ろうとする意思を持った時、自身の身体能力を強化する。
発動すると、その力はイバラ鞭の形をもって手元に現れる。
いろいろ
●二人は刑事としてペアを組んでいるわけでは無いようだ
●同僚らには「SM兄弟」と言われたりする。Sグチはともかく、Mグチはあからさまに嫌な顔をする。
ーーーーー
ねこアイコンは「CHARAT/キャラット https://charat.me/」で作成させていただきました
Mグチ
真面目で神経質な男。32歳。身長は約180㎝。普段はSグチとともに刑事として働いている。
突飛な物事、非現実的なことに対応するのが苦手。現実主義者であり、誤魔化しや建前を嫌う正直者。いつも口をMの字にしてムスッとしている。その真面目さと表情故に、冷たい人間と思われがち。蒸気アイマスクと焼き魚、ノンフィクション作品が好きで、リスケとパソコンのフリーズが嫌い。
本名、名鳥 正口(などり まさぐち)。Sグチの弟。
異能の名は「Master」。
Mグチを守ろうとする意思を持つ者の能力を強化する。
発動すると、その力は教鞭の形をもって手元に現れる。
Sグチ
飄々として物臭な男。35歳。身長は約180㎝。普段はMグチとともに刑事として働いている。
気ままで、大体の物事には驚かない性格。理想主義者で、楽しそうなことがあればすぐに飛び込んでいく。いつも口をSの字にしてへらへらと笑っている。わくわくすることと駄菓子と酒が好きで、暇やマンネリ、ピーマンが嫌い。
本名、名鳥 真口(などり さなぐち)。Mグチの兄。
異能の名は「Servant」。
Sグチが誰かを守ろうとする意思を持った時、自身の身体能力を強化する。
発動すると、その力はイバラ鞭の形をもって手元に現れる。
いろいろ
●二人は刑事としてペアを組んでいるわけでは無いようだ
●同僚らには「SM兄弟」と言われたりする。Sグチはともかく、Mグチはあからさまに嫌な顔をする。
ーーーーー
ねこアイコンは「CHARAT/キャラット https://charat.me/」で作成させていただきました
12 / 30
191 PS
チナミ区
N-15
N-15




































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材・消耗の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 不思議な牙 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV5)[防具]防御10(LV5)[装飾]器用10(LV5) | |||
| 5 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]敏捷10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) | |||
| 6 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV5)[効果2]活力10(LV10)[効果3]鎮痛10(LV15) | |||
| 7 | 白樺 | 素材 | 15 | [武器]活力10(LV10)[防具]活力15(LV20)[装飾]活力10(LV10) | |||
| 8 | 駄木 | 素材 | 10 | [武器]体力10(LV20)[防具]防御10(LV20)[装飾]攻撃10(LV20) | |||
| 9 | 吸い殻 | 素材 | 10 | [武器]炎上10(LV25)[防具]道連10(LV20)[装飾]火纏10(LV25) | |||
| 10 | 青く光るイバラムチ(Sグチ用) | 武器 | 39 | 束縛10 | - | - | 【射程1】 |
| 11 | ネジ | 素材 | 15 | [武器]混乱10(LV25)[防具]追撃10(LV25)[装飾]貫通10(LV25) | |||
| 12 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]衰弱10(LV20)[防具]体力10(LV5)[装飾]防御10(LV15) | |||
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 15 | 身体/武器/物理 |
| 具現 | 14 | 創造/召喚 |
| 武器 | 29 | 武器作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 6 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 6 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| エキサイト | 6 | 0 | 40 | 敵:攻撃+自:AT増(1T) | |
| クリエイト:タライ | 6 | 0 | 40 | 敵:攻撃&朦朧・混乱 | |
| クリエイト:ウェポン | 6 | 0 | 60 | 味:追撃LV・次与ダメ増 | |
| イレイザー | 5 | 0 | 150 | 敵傷:攻撃 | |
| サモン:ウルフ | 5 | 0 | 300 | 自:ウルフ召喚 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| 活力 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 体力 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 治癒 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| 幸運 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 | |
| 召喚強化 | 5 | 2 | 0 | 【常時】異能『具現』のLVに応じて、自身の召喚するNPCが強化 |





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]シャイン | [ 3 ]クリエイト:タライ | [ 3 ]エナジードレイン |

PL / あすかパン