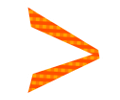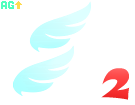<< 2:00>> 4:00




第二節 二人の大人
沙羅にはウタが在った。
幼い頃から得意であったそのウタを阻むものは何も無く、自由を謳歌する鳥の歌そのものであった。
それを否定されたことは無かったし、両親や祖父母から咎められたことは無かった。
だから沙羅は、好きなことを、好きなように出来たのだ。
沙羅はもうすぐ十代半ばを過ぎていく。
大人になると声というものは変わるらしい。けれど沙羅はそれを恐怖しなかった。
大人になれば世界は広がって、もっとたくさんの地を踏みしめて、もっとたくさんの知を学び、もし声が変わっても皆が受け入れてくれることを沙羅は知っていた。
いつか大人になったら、きっともっと素晴らしいことになるのだろう。
だから沙羅は日々の積み重ねが楽しかったし、そして大人になるなら楽しみですらあった。
変声期を感じさせる声の掠れもだから沙羅は好きだった。
もし変わってしまっても、きっと自分も世界で好きでいられると、沙羅は揺るぎなく知っていたからだ。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
「シャ・ラ」には翼が在った。
しかしその翼がはためくには檻は小さくまた、幸運の鳥をみすみす逃そうと思う者は居ない。
さて、どうするか。簡単だ。羽を切れば良い。
「シャ・ラ」は、翼が生えてきていることに恐怖していた。
それは大人になることであり、大人になれば翼を切られ、より愛玩のモノになる。
そのことは檻の外の会話から理解していた。
それに大人になって、いつか次の「シャ・ラ」を生み出せば、自分は親鳥となり死んでしまうだろう。
「シャ・ラ」は、大人の証である腕の翼を嫌悪していた。
けれど、それを自ら千切る程のちからも、自分には無かったのだ。



特に何もしませんでした。










料理LV を 6 UP!(LV10⇒16、-6CP)



次元タクシーに乗り『チナミ区 E-5:出発地』に転送されました!
チナミ区 E-6(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 F-6(道路)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 G-6(道路)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 G-7(草原)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 G-8(沼地)に移動!(体調26⇒25)






―― ハザマ時間が紡がれる。

花の香りと共に、Cross+Rose内が梅の花に囲まれた売店のある景色に変わる。
何か甘い香りが漂っている売店のほうを見ると――


静かに何かを作っているふたり。
榊の質問に、反応する。
そう言って焼いた団子を隣りに渡す。
団子にもっさりとアンコを乗せ、榊に手渡す。
両手でピースサインを出すカグハ。
ピースサインを下ろそうとするカオリ。
Cross+Rose内の景色が元に戻り、ふたりの姿も消える。
チャットが閉じられる――














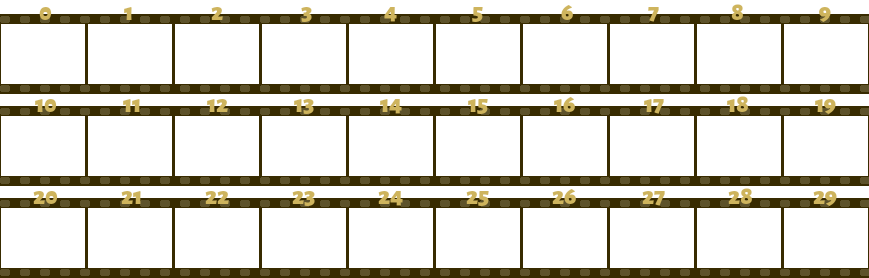





































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [スキル]OK.



第二節 二人の大人
沙羅にはウタが在った。
幼い頃から得意であったそのウタを阻むものは何も無く、自由を謳歌する鳥の歌そのものであった。
それを否定されたことは無かったし、両親や祖父母から咎められたことは無かった。
だから沙羅は、好きなことを、好きなように出来たのだ。
沙羅はもうすぐ十代半ばを過ぎていく。
大人になると声というものは変わるらしい。けれど沙羅はそれを恐怖しなかった。
大人になれば世界は広がって、もっとたくさんの地を踏みしめて、もっとたくさんの知を学び、もし声が変わっても皆が受け入れてくれることを沙羅は知っていた。
いつか大人になったら、きっともっと素晴らしいことになるのだろう。
だから沙羅は日々の積み重ねが楽しかったし、そして大人になるなら楽しみですらあった。
変声期を感じさせる声の掠れもだから沙羅は好きだった。
もし変わってしまっても、きっと自分も世界で好きでいられると、沙羅は揺るぎなく知っていたからだ。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
「シャ・ラ」には翼が在った。
しかしその翼がはためくには檻は小さくまた、幸運の鳥をみすみす逃そうと思う者は居ない。
さて、どうするか。簡単だ。羽を切れば良い。
「シャ・ラ」は、翼が生えてきていることに恐怖していた。
それは大人になることであり、大人になれば翼を切られ、より愛玩のモノになる。
そのことは檻の外の会話から理解していた。
それに大人になって、いつか次の「シャ・ラ」を生み出せば、自分は親鳥となり死んでしまうだろう。
「シャ・ラ」は、大人の証である腕の翼を嫌悪していた。
けれど、それを自ら千切る程のちからも、自分には無かったのだ。



特に何もしませんでした。









料理LV を 6 UP!(LV10⇒16、-6CP)



次元タクシーに乗り『チナミ区 E-5:出発地』に転送されました!
チナミ区 E-6(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 F-6(道路)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 G-6(道路)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 G-7(草原)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 G-8(沼地)に移動!(体調26⇒25)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
榊 「・・・おや?何だか良い香りが。」 |

榊
黒髪に蒼い瞳、黒スーツ。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
花の香りと共に、Cross+Rose内が梅の花に囲まれた売店のある景色に変わる。
 |
榊 「香りまで再現、高機能な代物ですねぇ。」 |
 |
榊 「しかし香るのは、花の匂いだけではないような・・・」 |
何か甘い香りが漂っている売店のほうを見ると――

カオリ
黒髪のサイドテールに赤い瞳、橙色の着物の少女。
カグハと瓜二つの顔をしている。
カグハと瓜二つの顔をしている。

カグハ
黒髪のサイドテールに赤い瞳、桃色の着物の少女。
カオリと瓜二つの顔をしている。
カオリと瓜二つの顔をしている。
静かに何かを作っているふたり。
 |
榊 「ごきげんよう。それは・・・・・団子、ですか?」 |
榊の質問に、反応する。
 |
カグハ 「団子いっちょーう。180円。カオリちゃん、具。」 |
そう言って焼いた団子を隣りに渡す。
 |
カオリ 「はいはいカグハちゃん。はいアンコ奮発しちゃうよー!!」 |
団子にもっさりとアンコを乗せ、榊に手渡す。
 |
榊 「おお・・・これはこれは美味しそうな!ありがとうございます。」 |
 |
カオリ 「・・・・・って、チャットでやってもねー。無意味だねぇ!無意味っ!!」 |
 |
カグハ 「ホンモノ食べたきゃおいでませ梅楽園。」 |
両手でピースサインを出すカグハ。
 |
カオリ 「いやまだお店準備中だから!来てもやってないよー!! 材料創りはカグハちゃんなんだから自分で知ってるでしょ!!」 |
ピースサインを下ろそうとするカオリ。
Cross+Rose内の景色が元に戻り、ふたりの姿も消える。
 |
榊 「いただいた団子は・・・・・これは無味ッ!!味の再現は難しいのですかね。」 |
 |
榊 「まだ準備中のようですが、こんな世界の中でも美味しいものをいただけるとは。 いつか立ち寄ってみるとしましょう。」 |
チャットが閉じられる――





ENo.1590
SHa-La



祖父母の家に居候しているこども。
空を見上げてうたい、大きなカバンを持って跳ね回る快活な子。
両親は旅行中であり、その帰りを楽しみに待っている。
空を見上げてうたい、大きなカバンを持って跳ね回る快活な子。
両親は旅行中であり、その帰りを楽しみに待っている。
25 / 30
80 PS
チナミ区
G-8
G-8





































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材・消耗の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 伽羅 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 5 | Kalanchoe | 装飾 | 20 | 幸運10 | - | - | |
| 6 | 湧き水 | 料理 | 20 | 治癒10 | 活力10 | - | |
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV5)[効果2]活力10(LV10)[効果3]鎮痛10(LV15) | |||
| 8 | 焼きそばパン | 料理 | 10 | 攻撃10 | - | - | |
| 9 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]加速10(LV25)[装飾]敏捷10(LV10) | |||
| 10 | ねばねば | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV10)[防具]敏捷10(LV10)[装飾]束縛10(LV25) | |||
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 具現 | 10 | 創造/召喚 |
| 響鳴 | 10 | 歌唱/音楽/振動 |
| 装飾 | 10 | 装飾作製に影響 |
| 料理 | 16 | 料理に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 6 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| クリエイト:タライ | 5 | 0 | 40 | 敵:攻撃&朦朧・混乱 | |
| ビブラート | 5 | 0 | 60 | 敵:SP攻撃 | |
| クリエイト:マイク | 5 | 0 | 40 | 自:混乱・魅了特性増 | |
| バトルソング | 5 | 0 | 180 | 味列:AT・LK増(3T) | |
| サモン:セイレーン | 5 | 0 | 300 | 自:セイレーン召喚 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| 活力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 体力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 治癒 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| 幸運 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 | |
| 召喚強化 | 5 | 2 | 0 | 【常時】異能『具現』のLVに応じて、自身の召喚するNPCが強化 |





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]ダークネス |

PL / D