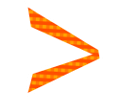<< 1:00>> 3:00




随分梅の花が咲いてきたな。
柔らかな午後の日差しを浴びながら、丁度巣箱の点検を終えたところであった。日は傾きつつあり、この時期独特の冷えた空気を感じることができる、そんな時間帯であった。養子として世話になっている家、その庭に設置された蜜蜂の巣箱からは何匹かの蜂が顔を覗かせている。今年も無事に冬を越すことができた。このままうまくいけば、世話になっている人達に上等な蜜を届けることができるだろう。
無論、彼自身も区分としては蜂にあたるものであるから、当然自分で蜜を作ることはできるのだが。どうやら種族の関係か、或いは単純に彼にその才能が無いせいか、彼が作る蜜は一般的な蜜蜂のそれとは味も粘度も比べるべくもなかった。日々の細やかな雑用をこなしてはいるものの、それだけでずっと納屋の一部を間借りさせてもらえるとは思っていない。ただの穀潰しにはなるまいと手探りで始めた養蜂、その努力が実を結んでからは、実に良質な蜜を毎年家主に渡すことができている。
「…………」
外骨格に覆われた腕をそっと前に差し出すと、先ほど顔を出していた蜂が一匹、その爪先に止まった。忙しなく前肢を動かす様子を黙って見つめている。
明日は随分暖かくなると聞いた。換気を良くしてやらなければいけないだろう。奨励給仕を始めるなら、日が暮れるまでには準備をしておかなければ。粗目は厨に残っていただろうか――。
そんなことを考えたときだった。
――――!?
ざわりと甲殻の繋ぎ目が痺れるような感覚に襲われた。人であれば、肌が粟立つなどと形容するのだろうが、生憎彼には種族として柔らかい素肌の持ち合わせが無い。それでも彼に備わったあらゆる感覚器官が、何か良くないものがその身に迫っていると警鐘を鳴らしていた。巣箱を――と一瞬考えながら視線を動かしたその視界の端、明らかに先ほどまでとは違う、禍々しい赤に染まった空を認めた瞬間、まだ記憶に新しいあの耳障りな男の声を思い出していた。
* * *
自分の身体が内側から裏返るような、おぞましい感覚。思わず目を閉じた一瞬で、世界は変わり果てていた。
裏返ったのは本当に自分なのか――。そんなことを考えたのが、初めてではないということを彼は思い出していた。自分はつい先ほどまでここに居たのだ。先日の、あの狐目の人間の耳障りな声、それを聞いて世界が裏返り、同じように突然連れて来られたらしい者たちの中に彼も居た。
そして――
そして、自分が何者だったのかということも、明確に思い出していた。
打ち棄てられた、世界の掃き溜め。自ら背負った咎が、呪いの詞を吐きながらゆっくりと自分の中を這い上がってくる。恨みと怨みが絡みつき、やがて身体の感覚すら奪って世界の傍観者へと成り果てるのだ。渇き切った心には、どれだけ水を注いでも、どれだけ濃厚な蜜を垂らそうと、たちまち渇いて干乾びていく。
だが、もし。
もしも奴らの言う『侵略』とやらが成功し、あの仮初の存在が自分の正となるのなら。
傍観者として朽ちるのではなく、もう一度平穏な生をやり直すことが許されるのなら……。
その可能性に行き当たったとき、彼は心の奥底から粘ついた感情が湧いて出るのを感じていた。













らうらさん(88) は ぬめぬめ を入手!
テュルム(287) は 何かの殻 を入手!
飼い鳥(888) は 何かの殻 を入手!
ファルドール(895) は 何かの殻 を入手!
テュルム(287) は 何か柔らかい物体 を入手!
飼い鳥(888) は 何か柔らかい物体 を入手!
テュルム(287) は ボロ布 を入手!
飼い鳥(888) は 甲殻 を入手!



制約LV を 2 DOWN。(LV10⇒8、+2CP、-2FP)
変化LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
防具LV を 3 UP!(LV20⇒23、-3CP)
ファルドール(895) により ItemNo.1 不思議な武器 に ItemNo.2 不思議な防具 を合成してもらい、どうでもよさげな物体 に変化させました!
⇒ どうでもよさげな物体/素材:強さ10/[武器]器用10(LV2)[防具]治癒10(LV2)[装飾]回復10(LV2)/特殊アイテム
飼い鳥(888) の持つ ItemNo.6 どうでもよさげな物体 から防具『走馬灯』を作製しました!
ItemNo.8 駄石 から防具『コロホニー』を作製しました!
⇒ コロホニー/防具:強さ33/[効果1]敏捷10 [効果2]- [効果3]-
としお(552) とカードを交換しました!
《錯覚》Knock!Knock! (クイック)
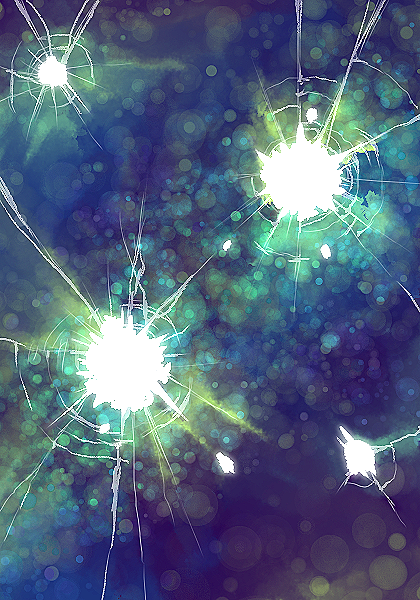

ヒールポーション を研究しました!(深度0⇒1)
ヒールポーション を研究しました!(深度1⇒2)
ストレングス を研究しました!(深度0⇒1)
ストレングス を習得!
ウィンドスピア を習得!
ウィザー を習得!



チナミ区 G-9(沼地)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 H-9(沼地)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 I-9(沼地)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 J-9(沼地)に移動!(体調22⇒21)
チナミ区 K-9(沼地)に移動!(体調21⇒20)






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。

元気よく両手両足を伸ばし空間を飛びまわる!
そう言ってフロントダブルバイセップス。
賞品について何だか盛り上がっているふたり。
チャットが閉じられる――


















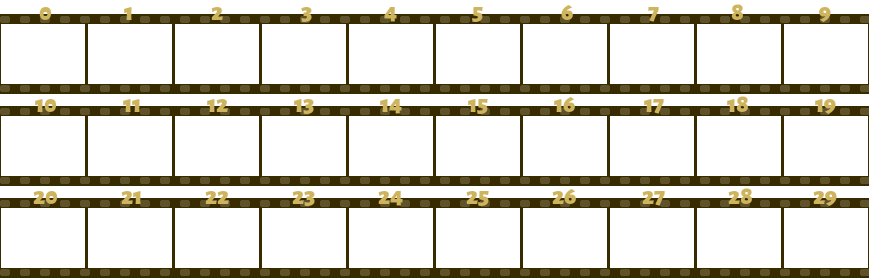





































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



随分梅の花が咲いてきたな。
柔らかな午後の日差しを浴びながら、丁度巣箱の点検を終えたところであった。日は傾きつつあり、この時期独特の冷えた空気を感じることができる、そんな時間帯であった。養子として世話になっている家、その庭に設置された蜜蜂の巣箱からは何匹かの蜂が顔を覗かせている。今年も無事に冬を越すことができた。このままうまくいけば、世話になっている人達に上等な蜜を届けることができるだろう。
無論、彼自身も区分としては蜂にあたるものであるから、当然自分で蜜を作ることはできるのだが。どうやら種族の関係か、或いは単純に彼にその才能が無いせいか、彼が作る蜜は一般的な蜜蜂のそれとは味も粘度も比べるべくもなかった。日々の細やかな雑用をこなしてはいるものの、それだけでずっと納屋の一部を間借りさせてもらえるとは思っていない。ただの穀潰しにはなるまいと手探りで始めた養蜂、その努力が実を結んでからは、実に良質な蜜を毎年家主に渡すことができている。
「…………」
外骨格に覆われた腕をそっと前に差し出すと、先ほど顔を出していた蜂が一匹、その爪先に止まった。忙しなく前肢を動かす様子を黙って見つめている。
明日は随分暖かくなると聞いた。換気を良くしてやらなければいけないだろう。奨励給仕を始めるなら、日が暮れるまでには準備をしておかなければ。粗目は厨に残っていただろうか――。
そんなことを考えたときだった。
――――!?
ざわりと甲殻の繋ぎ目が痺れるような感覚に襲われた。人であれば、肌が粟立つなどと形容するのだろうが、生憎彼には種族として柔らかい素肌の持ち合わせが無い。それでも彼に備わったあらゆる感覚器官が、何か良くないものがその身に迫っていると警鐘を鳴らしていた。巣箱を――と一瞬考えながら視線を動かしたその視界の端、明らかに先ほどまでとは違う、禍々しい赤に染まった空を認めた瞬間、まだ記憶に新しいあの耳障りな男の声を思い出していた。
* * *
自分の身体が内側から裏返るような、おぞましい感覚。思わず目を閉じた一瞬で、世界は変わり果てていた。
裏返ったのは本当に自分なのか――。そんなことを考えたのが、初めてではないということを彼は思い出していた。自分はつい先ほどまでここに居たのだ。先日の、あの狐目の人間の耳障りな声、それを聞いて世界が裏返り、同じように突然連れて来られたらしい者たちの中に彼も居た。
そして――
そして、自分が何者だったのかということも、明確に思い出していた。
打ち棄てられた、世界の掃き溜め。自ら背負った咎が、呪いの詞を吐きながらゆっくりと自分の中を這い上がってくる。恨みと怨みが絡みつき、やがて身体の感覚すら奪って世界の傍観者へと成り果てるのだ。渇き切った心には、どれだけ水を注いでも、どれだけ濃厚な蜜を垂らそうと、たちまち渇いて干乾びていく。
だが、もし。
もしも奴らの言う『侵略』とやらが成功し、あの仮初の存在が自分の正となるのなら。
傍観者として朽ちるのではなく、もう一度平穏な生をやり直すことが許されるのなら……。
その可能性に行き当たったとき、彼は心の奥底から粘ついた感情が湧いて出るのを感じていた。



 |
飼い鳥 「お菓子持った? 持って無いなら半分こ。」 |
 |
ファルドール 「無事に集合出来てよかった。……危うく迷子になるかと思ったが」 |



カピバラお兄さんと愉快な仲間たち
|
 |
ハザマに生きるもの
|



TeamNo.363
|
 |
カピバラお兄さんと愉快な仲間たち
|



らうらさん(88) は ぬめぬめ を入手!
テュルム(287) は 何かの殻 を入手!
飼い鳥(888) は 何かの殻 を入手!
ファルドール(895) は 何かの殻 を入手!
テュルム(287) は 何か柔らかい物体 を入手!
飼い鳥(888) は 何か柔らかい物体 を入手!
テュルム(287) は ボロ布 を入手!
飼い鳥(888) は 甲殻 を入手!



制約LV を 2 DOWN。(LV10⇒8、+2CP、-2FP)
変化LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
防具LV を 3 UP!(LV20⇒23、-3CP)
ファルドール(895) により ItemNo.1 不思議な武器 に ItemNo.2 不思議な防具 を合成してもらい、どうでもよさげな物体 に変化させました!
⇒ どうでもよさげな物体/素材:強さ10/[武器]器用10(LV2)[防具]治癒10(LV2)[装飾]回復10(LV2)/特殊アイテム
 |
*バッチリだ、と言わんばかりの顔で出来たものを渡してくれる* |
飼い鳥(888) の持つ ItemNo.6 どうでもよさげな物体 から防具『走馬灯』を作製しました!
ItemNo.8 駄石 から防具『コロホニー』を作製しました!
⇒ コロホニー/防具:強さ33/[効果1]敏捷10 [効果2]- [効果3]-
| テュルム 「…………」 |
としお(552) とカードを交換しました!
《錯覚》Knock!Knock! (クイック)
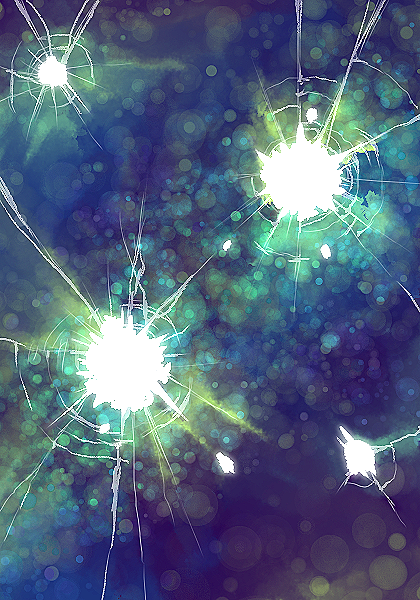

ヒールポーション を研究しました!(深度0⇒1)
ヒールポーション を研究しました!(深度1⇒2)
ストレングス を研究しました!(深度0⇒1)
ストレングス を習得!
ウィンドスピア を習得!
ウィザー を習得!



チナミ区 G-9(沼地)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 H-9(沼地)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 I-9(沼地)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 J-9(沼地)に移動!(体調22⇒21)
チナミ区 K-9(沼地)に移動!(体調21⇒20)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
ノウレット 「おっくれまして―――ッ!!」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。
 |
エディアン 「わぁぁ!!なんですなんですぅ!!!?」 |

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
 |
ノウレット 「はぁい!初めまして初めましてノウレットって言いまぁす!! ここCrossRoseの管・・・妖精ですよぉっ!!皆さんよろしくおねがいしまぁーっす!!」 |
 |
エディアン 「初めまして初めまして! 私はエディアンといいます、便利な機能をありがとうございます!」 |
 |
ノウレット 「わぁい!どーいたしましてーっ!!」 |
元気よく両手両足を伸ばし空間を飛びまわる!
 |
エディアン 「ノウレットさんもドライバーさんと同じ、ハザマを司る方なんですね。」 |
 |
ノウレット 「司る!なんかそれかっこいいですね!!そうです!司ってますよぉ!!」 |
そう言ってフロントダブルバイセップス。
 |
エディアン 「仄暗いハザマの中でマスコットみたいな方に会えて、何だか和みます! ワールドスワップの能力者はマスコットまで創るんですねー。」 |
 |
ノウレット 「マスコット!妖精ですけどマスコットもいいですねぇーっ!! エディアンさんは言葉の天才ですか!?すごい!すごい!!」 |
 |
ノウレット 「――ぁ、そうだ。そういえば告知があって出演したんですよぉ!!」 |
 |
エディアン 「告知?なんでしょう??」 |
 |
ノウレット 「はぁい!ここCrossRoseを舞台に、大大大大闘技大会をするのですっ!! 両陣営入り乱れてのハチャメチャトーナメントバトルですよぉ!!」 |
 |
エディアン 「ハチャメチャトーナメントバトル!楽しそうですねぇ!!」 |
 |
ノウレット 「はぁい!たまには娯楽もないと疲れちゃいますのでッ!!」 |
 |
エディアン 「そうですよねぇ。息抜きって大事だと思います。」 |
 |
ノウレット 「はぁい!豪華賞品も考えてるんですよぉ!!」 |
 |
エディアン 「賞品はあると燃えますね!豪華賞品・・・・・ホールケーキとか。」 |
 |
ノウレット 「ホールケーキ!!1人1個用意しちゃいますっ!!?」 |
 |
エディアン 「夢のようですね!食べきれるか怪しいですけど。」 |
賞品について何だか盛り上がっているふたり。
 |
ノウレット 「・・・・・あ!でも開催はすぐじゃなくてまだ先なんです!! 賞品の準備とかもありますしぃー!!」 |
 |
エディアン 「わかりました、楽しみにしていますね。」 |
 |
ノウレット 「はぁい!それでは!おったのしみにぃ――ッ!!!!」 |
チャットが閉じられる――



カピバラお兄さんと愉快な仲間たち
|
 |
ハザマに生きるもの
|




TRIQSHOT
|
 |
カピバラお兄さんと愉快な仲間たち
|


ENo.287
テュルム



蜂。
----------------
生まれ落ちたコロニーを喪った。その原因の一端を担ったことにより、積み上げられた恨みと怨みが彼をこの掃き溜めに打ち棄てた。
それから長い間――すでに記憶の中の世界が色褪せてしまうほど――特に当てもなく世界を彷徨い、無為に時を過ごす日々を送っている。
自分自身に決着を付けるための度胸は、どこかに置き忘れてしまったらしい。
その身に宿した異能は『隷属』。
自らが認めた誰かに命じられたときにのみ、本領を発揮することができる。
----------------
でかい蜂。150cmくらい。
蜂なので普通に甘党だし、やっぱり火と煙は嫌い。
寡黙なのは単純にコミュ障のせいでもあり、生に飽いて自ら行動を起こすことを諦めてしまったせいでもある。
絶対に人前では兜を外さないため、そもそも感情の起伏すら窺うのは難しい。
一方で、生来の気質なのか何か頼まれたりするとあっさりそれに従ったりする。自発的な行動を期待してはいけない。
イバラではとある家に養子として世話になっている。コミュ障なので基本は引き籠もりつつ養蜂をしているらしい。
ヒロ〇カ的世界観で許されるということなので姿もこのままだ! やったね!
----------------
生まれ落ちたコロニーを喪った。その原因の一端を担ったことにより、積み上げられた恨みと怨みが彼をこの掃き溜めに打ち棄てた。
それから長い間――すでに記憶の中の世界が色褪せてしまうほど――特に当てもなく世界を彷徨い、無為に時を過ごす日々を送っている。
自分自身に決着を付けるための度胸は、どこかに置き忘れてしまったらしい。
その身に宿した異能は『隷属』。
自らが認めた誰かに命じられたときにのみ、本領を発揮することができる。
----------------
でかい蜂。150cmくらい。
蜂なので普通に甘党だし、やっぱり火と煙は嫌い。
寡黙なのは単純にコミュ障のせいでもあり、生に飽いて自ら行動を起こすことを諦めてしまったせいでもある。
絶対に人前では兜を外さないため、そもそも感情の起伏すら窺うのは難しい。
一方で、生来の気質なのか何か頼まれたりするとあっさりそれに従ったりする。自発的な行動を期待してはいけない。
イバラではとある家に養子として世話になっている。コミュ障なので基本は引き籠もりつつ養蜂をしているらしい。
ヒロ〇カ的世界観で許されるということなので姿もこのままだ! やったね!
20 / 30
46 PS
チナミ区
K-9
K-9
































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果等 |
| 1 | どうでもよさげな物体 | 素材 | 10 | [武器]器用10(LV2)[防具]治癒10(LV2)[装飾]回復10(LV2) |
| 2 | ||||
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |
| 4 | ブースター | 武器 | 30 | [効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程3】 |
| 5 | タリスマン | 装飾 | 30 | [効果1]幸運10 [効果2]- [効果3]- |
| 6 | 不思議ケーキ | 料理 | 30 | [効果1]治癒10 [効果2]活力10 [効果3]鎮痛10 |
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV5)[効果2]活力10(LV10)[効果3]鎮痛10(LV15) |
| 8 | コロホニー | 防具 | 33 | [効果1]敏捷10 [効果2]- [効果3]- |
| 9 | 何かの殻 | 素材 | 15 | [武器]加速10(LV15)[防具]幸運10(LV5)[装飾]水纏15(LV25) |
| 10 | 何か柔らかい物体 | 素材 | 10 | [武器]祝福10(LV20)[防具]鎮痛10(LV20)[装飾]防御10(LV20) |
| 11 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]衰弱10(LV20)[防具]体力10(LV5)[装飾]防御10(LV15) |
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 時空 | 10 | 空間/時間/風 |
| 制約 | 8 | 拘束/罠/リスク |
| 変化 | 5 | 強化/弱化/変身 |
| 防具 | 23 | 防具作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| ヘイスト | 5 | 0 | 40 | 自:AG増 | |
| リストリクト | 5 | 0 | 60 | 敵:DX・AG減(2T) | |
| ストレングス | 5 | 0 | 100 | 自:AT増 | |
| レックレスチャージ | 5 | 0 | 80 | 自:HP減+敵全:風痛撃 | |
| ウィンドスピア | 5 | 0 | 100 | 敵貫:風痛撃 | |
| ウィザー | 5 | 0 | 60 | 敵:痛撃&次与ダメ減 | |
| エアスラスト | 5 | 0 | 60 | 敵:4連風撃 | |
| キャプチャー | 5 | 0 | 70 | 自:束縛LV増 | |
| ストームフィールド | 5 | 0 | 140 | 自:風特性・風耐性・連続増+HP減 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| 活力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 体力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 治癒 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| 幸運 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 |





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 2 ]ヘイスト | [ 1 ]ストレングス | [ 2 ]ヒールポーション |
| [ 1 ]アリア |

PL / door