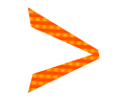<< 0:00>> 2:00




【ネオンという少年】
\チャリーン/
\センキュー/
\シャリリリン/
頭の中で哀れみの鐘が響く。
頭上に浮かぶ数字が回転し増えていく。これで合計金額が140万5342円となった。
おそらく3,000円程度の投げ銭があったと思う。
ネオンは少しため息をついて周囲を確認すると20代女性が好奇の目でこちらを見ている姿を発見した。
明らかにその人が投げ銭をしたと、経験と、「目」でわかった。
みすぼらしい自分がその日暮らしのお金を漁っている醜い様子に憐れみを感じてしまい投げ銭したのだとネオンは予想する。
異能の条件さえ満たせば投げ銭は自動的に回収されてしまう。これは本能でわかっている。というより以前いた世界での生活環境が変質した異能であるため直感で理解できただけである。
①投げ銭したいという気持ち
②具体的な金額
の条件を満たせば相手の現金や電子マネー・貯蓄から回収して自分のものとなる。
今回は約3,000円であった。
ネオンは今手に10円を握っている。
自動販売機の小銭口にて手を入れて見つけたお金で、日々の収入であった。
それに比べると3,000円は大金である。数日食に困らないだろう。
嬉しいはずの金額だが、端正な顔が悔しさで歪む。
(僕は…そんなお金…望んでいないのに…)
この異能で獲得するお金は、自分の意思で拒否することができない。通知音を消すこともできない。
相手が無自覚で、かつ自らが望んでいなくても、投げ銭を受けた恩義には感謝しないといけない。ネオンはそういう性格。
「ぅぐ…あ、ありがとうございます…」
「…え? 私に…? お礼を言われることはないも」
「…それでも、ありがとうございます…」
「いえ、どういたしまして? ?」
少年は逃げるようにその場を去る。
後ろから待ってと呼び止める声があったがすぐに消えた。
_______________
「は~…危ない人じゃなくて良かった…」
河川敷で半額おにぎりを2つ食べながらため息を吐いた。
「投げ銭する人ってなんか怖い人が多いんですよねぇ…。この前も腕を掴まれて路地裏に連れて行かれそうになったし…」
そう言って、短い経験の中で得ている知識で考えられるそのあとのことを想像して身震いする。
恐怖の感情を紛らわせるためおにぎりを一気に口に入れて飲み込んだ。
「今日のお仕事はまだたくさんありますけど…どうしようかな…」
設置された公共の時計を見ると午後3時を指していた。
「今の時間なら図書館で勉強しましょう。下校した小学生がいるので何も言われないでしょう…」
そう決めて早速図書館へ向かう。
ちなみに図書館などに入る際は、大人の背後にくっついて親子の振りをするのが処世術の一つである。
________________
机の上には数冊の本が並んでいる。
算数や社会といった学業の本から、背を伸ばす本・社会人生活本など。
小さな頭ではまだ理解できないことも必死に詰めていく。
(この時間が一番幸せかもしれません…もっとお金があればたくさん勉強できるのでしょうね)
ふと、別のテーブルに座る小学生達が嫌そうに声色で宿題をしている姿が見えた。
(学校、行ってみたいなぁ…。そんなに嫌なら代わってもいいんですよ…。)
なんて嫌な事を思ってしまったんだと振り払うため頭を降った。
(今日は、もう頭がいっぱいなので帰りますか…)
本当は別の理由であるが、そう納得して帰る準備をする。
身分証の類がないため図書カードは作れていない。本をすべて元に戻して外へ出た。
\チャリーン/
\センキュー/
\シャリリリン/
外を出て十数m、鐘がなった。
金額を確認すると21,000円。悪寒が走る。
慌てて後ろを見ると図書館から出てくる中年男性と目があった。
「あっ…、あり…うわぁ、ご、ごめんなさい…!」
すぐに駆け出して、交番がある人通りの多い場所へ向かう。
「ちょっと君ィ!まちなさい!くっ」
「ごめんなさい!ごめんなさい!」
後ろを振り返る余裕もなく全力で逃げる。
すぐに男性の声は聞こえなくなっていたが気付いていなかった。
小さな雑貨屋の前で息を整えている。
「はぁ…はぁ…。あの人…はあっ…多分、危ない人だっ…ハァ…」
全く知らない人だったが、そう思える根拠がある。
投げ銭の最高額が21,000円。そう思うのはそれ以上の金額を見た事がないからだ。
そして、その金額を投げる人に何度も危ない目にあっている。
「んっ…はぁ…あの人も『目』が…他の人と違う気が…する…はあぁぁぁ…」
少し泣きそうになるが上を向いて堪える。
その時、雑貨屋さんのガラスの向こうにあるものが見えた。
ネオンは電子マネー対応店だと確認すると息を平常にして入店する。
「お兄さん、これください。お金は電子マネーでお願いします」
「…これどうするんだい」
「親に頼まれてお使いしてるんだ。僕は子供に絶対売ってくれないって言ったんだけど、工事?とかで手が離せなくてどうしてもって。カードも預かっているんだ」
「…そうかい。10,800円と8,000円と2,160円で計20,960円だよ。そこにタッチして」
「ありがとう!」
緊張でゴクリとツバを飲むと、手で覆いかぶせたカードで電子決算する。
ピッと完了音がすると目にみえて安堵する。
その様子を怪訝そうな態度の店員だが、深くは追求しなかった。
ネオンは頭を下げてお店を出る。
すぐ路地裏へ走り、袋を開けた。
「ベルト」
「携帯用ミニ警棒」
そして「防御カバーのついた小型ナイフ」
小さな警棒をズボンの中に引っ掛ける。
そして、上の服を脱いで上半身にベルトを巻き付け、小型ナイフを差し込む。
武器を携帯した安心感でその場で座り込んでしまう。
「うまくいってよかった…。」
頭の上の数字を確認すると20,960円引かれている。
この能力を使うのは二回目。
一回目はこの世界に来て、何もわからないまま空腹で死にそうでコンビニで万引きをして、偶然発動し事なきを得た時。
二回目が今。
一回目でこの能力は体の一部を当てると溜まった投げ銭から電子決算ができるものだと理解できた。
その後、怪しまれないように普及している電子決算対応カードを偽造し所持していた。
手でカードを隠すように持っていたのも偽造がバレないため。
それがうまくいって良かったと何度も呟いて、胸のナイフを抱きしめた。
_________________
夜。ダンボールハウスストリート。
浮浪者が集まってダンボールハウスを無造作に建てまくり、治安が悪くなったことで一般人が近寄らなくなった通り道。
その中の建つ小さなダンボールハウスで、ネオンは横になっていた。
「今日は冷え込みますが…不思議と寒くないですね」
初めて仕込んだ凶器の熱がまだ引いてないなかった。
「…今日のような事があれば、どう対処するか考えながら寝ましょう…」
ダンボールの布団を厚めにかぶり、ナイフを抱いて目を閉じる。
今日はいつもより安心して寝られる気がした。
「明日も…頑張ろう……」
白い少年の一日が終わった。



特に何もしませんでした。








武術LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
解析LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
武器LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
付加LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
エキサイト を習得!
プリディクション を習得!
アキュラシィ を習得!
イレイザー を習得!
クイックアナライズ を習得!
ウィークポイント を習得!



チナミ区 E-2(水地)には移動できません。
チナミ区 E-2(水地)には移動できません。
チナミ区 E-2(水地)には移動できません。
チナミ区 E-2(水地)には移動できません。
チナミ区 E-2(水地)には移動できません。
体調が全回復しました!
『チナミ区 E-5:出発地』へ採集に向かうことにしました!






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャットで時間が伝えられる。
榊の前に1台のタクシーが止まり、窓が開く。

帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。
窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。
榊からのチャットが閉じられる――




















































異能・生産
アクティブ
パッシブ





[基本]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



【ネオンという少年】
\チャリーン/
\センキュー/
\シャリリリン/
頭の中で哀れみの鐘が響く。
頭上に浮かぶ数字が回転し増えていく。これで合計金額が140万5342円となった。
おそらく3,000円程度の投げ銭があったと思う。
ネオンは少しため息をついて周囲を確認すると20代女性が好奇の目でこちらを見ている姿を発見した。
明らかにその人が投げ銭をしたと、経験と、「目」でわかった。
みすぼらしい自分がその日暮らしのお金を漁っている醜い様子に憐れみを感じてしまい投げ銭したのだとネオンは予想する。
異能の条件さえ満たせば投げ銭は自動的に回収されてしまう。これは本能でわかっている。というより以前いた世界での生活環境が変質した異能であるため直感で理解できただけである。
①投げ銭したいという気持ち
②具体的な金額
の条件を満たせば相手の現金や電子マネー・貯蓄から回収して自分のものとなる。
今回は約3,000円であった。
ネオンは今手に10円を握っている。
自動販売機の小銭口にて手を入れて見つけたお金で、日々の収入であった。
それに比べると3,000円は大金である。数日食に困らないだろう。
嬉しいはずの金額だが、端正な顔が悔しさで歪む。
(僕は…そんなお金…望んでいないのに…)
この異能で獲得するお金は、自分の意思で拒否することができない。通知音を消すこともできない。
相手が無自覚で、かつ自らが望んでいなくても、投げ銭を受けた恩義には感謝しないといけない。ネオンはそういう性格。
「ぅぐ…あ、ありがとうございます…」
「…え? 私に…? お礼を言われることはないも」
「…それでも、ありがとうございます…」
「いえ、どういたしまして? ?」
少年は逃げるようにその場を去る。
後ろから待ってと呼び止める声があったがすぐに消えた。
_______________
「は~…危ない人じゃなくて良かった…」
河川敷で半額おにぎりを2つ食べながらため息を吐いた。
「投げ銭する人ってなんか怖い人が多いんですよねぇ…。この前も腕を掴まれて路地裏に連れて行かれそうになったし…」
そう言って、短い経験の中で得ている知識で考えられるそのあとのことを想像して身震いする。
恐怖の感情を紛らわせるためおにぎりを一気に口に入れて飲み込んだ。
「今日のお仕事はまだたくさんありますけど…どうしようかな…」
設置された公共の時計を見ると午後3時を指していた。
「今の時間なら図書館で勉強しましょう。下校した小学生がいるので何も言われないでしょう…」
そう決めて早速図書館へ向かう。
ちなみに図書館などに入る際は、大人の背後にくっついて親子の振りをするのが処世術の一つである。
________________
机の上には数冊の本が並んでいる。
算数や社会といった学業の本から、背を伸ばす本・社会人生活本など。
小さな頭ではまだ理解できないことも必死に詰めていく。
(この時間が一番幸せかもしれません…もっとお金があればたくさん勉強できるのでしょうね)
ふと、別のテーブルに座る小学生達が嫌そうに声色で宿題をしている姿が見えた。
(学校、行ってみたいなぁ…。そんなに嫌なら代わってもいいんですよ…。)
なんて嫌な事を思ってしまったんだと振り払うため頭を降った。
(今日は、もう頭がいっぱいなので帰りますか…)
本当は別の理由であるが、そう納得して帰る準備をする。
身分証の類がないため図書カードは作れていない。本をすべて元に戻して外へ出た。
\チャリーン/
\センキュー/
\シャリリリン/
外を出て十数m、鐘がなった。
金額を確認すると21,000円。悪寒が走る。
慌てて後ろを見ると図書館から出てくる中年男性と目があった。
「あっ…、あり…うわぁ、ご、ごめんなさい…!」
すぐに駆け出して、交番がある人通りの多い場所へ向かう。
「ちょっと君ィ!まちなさい!くっ」
「ごめんなさい!ごめんなさい!」
後ろを振り返る余裕もなく全力で逃げる。
すぐに男性の声は聞こえなくなっていたが気付いていなかった。
小さな雑貨屋の前で息を整えている。
「はぁ…はぁ…。あの人…はあっ…多分、危ない人だっ…ハァ…」
全く知らない人だったが、そう思える根拠がある。
投げ銭の最高額が21,000円。そう思うのはそれ以上の金額を見た事がないからだ。
そして、その金額を投げる人に何度も危ない目にあっている。
「んっ…はぁ…あの人も『目』が…他の人と違う気が…する…はあぁぁぁ…」
少し泣きそうになるが上を向いて堪える。
その時、雑貨屋さんのガラスの向こうにあるものが見えた。
ネオンは電子マネー対応店だと確認すると息を平常にして入店する。
「お兄さん、これください。お金は電子マネーでお願いします」
「…これどうするんだい」
「親に頼まれてお使いしてるんだ。僕は子供に絶対売ってくれないって言ったんだけど、工事?とかで手が離せなくてどうしてもって。カードも預かっているんだ」
「…そうかい。10,800円と8,000円と2,160円で計20,960円だよ。そこにタッチして」
「ありがとう!」
緊張でゴクリとツバを飲むと、手で覆いかぶせたカードで電子決算する。
ピッと完了音がすると目にみえて安堵する。
その様子を怪訝そうな態度の店員だが、深くは追求しなかった。
ネオンは頭を下げてお店を出る。
すぐ路地裏へ走り、袋を開けた。
「ベルト」
「携帯用ミニ警棒」
そして「防御カバーのついた小型ナイフ」
小さな警棒をズボンの中に引っ掛ける。
そして、上の服を脱いで上半身にベルトを巻き付け、小型ナイフを差し込む。
武器を携帯した安心感でその場で座り込んでしまう。
「うまくいってよかった…。」
頭の上の数字を確認すると20,960円引かれている。
この能力を使うのは二回目。
一回目はこの世界に来て、何もわからないまま空腹で死にそうでコンビニで万引きをして、偶然発動し事なきを得た時。
二回目が今。
一回目でこの能力は体の一部を当てると溜まった投げ銭から電子決算ができるものだと理解できた。
その後、怪しまれないように普及している電子決算対応カードを偽造し所持していた。
手でカードを隠すように持っていたのも偽造がバレないため。
それがうまくいって良かったと何度も呟いて、胸のナイフを抱きしめた。
_________________
夜。ダンボールハウスストリート。
浮浪者が集まってダンボールハウスを無造作に建てまくり、治安が悪くなったことで一般人が近寄らなくなった通り道。
その中の建つ小さなダンボールハウスで、ネオンは横になっていた。
「今日は冷え込みますが…不思議と寒くないですね」
初めて仕込んだ凶器の熱がまだ引いてないなかった。
「…今日のような事があれば、どう対処するか考えながら寝ましょう…」
ダンボールの布団を厚めにかぶり、ナイフを抱いて目を閉じる。
今日はいつもより安心して寝られる気がした。
「明日も…頑張ろう……」
白い少年の一日が終わった。



特に何もしませんでした。







武術LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
解析LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
武器LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
付加LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
エキサイト を習得!
プリディクション を習得!
アキュラシィ を習得!
イレイザー を習得!
クイックアナライズ を習得!
ウィークポイント を習得!



チナミ区 E-2(水地)には移動できません。
チナミ区 E-2(水地)には移動できません。
チナミ区 E-2(水地)には移動できません。
チナミ区 E-2(水地)には移動できません。
チナミ区 E-2(水地)には移動できません。
体調が全回復しました!
『チナミ区 E-5:出発地』へ採集に向かうことにしました!






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
榊 「・・・60分!区切り目ですねぇッ!!」 |

榊
黒髪に蒼い瞳、黒スーツ。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
チャットで時間が伝えられる。
 |
榊 「先程の戦闘、観察させていただきました。 ざっくりと戦闘不能を目指せば良いようで。」 |
 |
榊 「・・・おっと、お呼びしていた方が来たようです。 我々が今後お世話になる方をご紹介しましょう!」 |
榊の前に1台のタクシーが止まり、窓が開く。

ドライバーさん
次元タクシーの運転手。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。
 |
ドライバーさん 「どーも、『次元タクシー』の運転役だ。よろしく。」 |
帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。
 |
榊 「こちら、中立に位置する方のようでして。 陣営に関係なくお手伝いいただけるとのこと。」 |
 |
ドライバーさん 「中立っつーかなぁ・・・。俺もタクシーも同じのが沢山"在る"んでな。 面倒なんで人と思わずハザマの機能の一部とでも思ってくれ。」 |
 |
ドライバーさん 「ま・・・チェックポイントとかの行き来の際にゃ、へいタクシーの一声を。じゃあな。」 |
窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。
 |
榊 「何だか似た雰囲気の方が身近にいたような・・・ あの方もタクシー運転手が似合いそうです。」 |
 |
榊 「ともあれ開幕ですねぇぇッ!!!! じゃんじゃん打倒していくとしましょうッ!!!!」 |
榊からのチャットが閉じられる――





ENo.484
由羅 ネオン



由羅 ネオン
性別:男
年齢:2歳
身長:120cm
とある世界の無関係の男性二人がバ美肉してネットで出逢い恋し、しまいにはバーチャル結婚を得てAIショタを出産(設定)するも、そのAIが自我を持ってすくすく育ち、バーチャル世界に嫌気がさして現代に受肉した苦難系AIショタ。
人生に少し疲れている。
ホームレス生活をしている。
両親が憎い。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
青い腕は異能の【自動投銭集金回路】。数字は所持金額。
ネオンに具体的な金額を投銭したいと思えば自動で回収されてしまう。限度額は一回3万円。謎の手数料が30%とられて数字に加算される。このお金は電子マネーでしか使用できない。
性別:男
年齢:2歳
身長:120cm
とある世界の無関係の男性二人がバ美肉してネットで出逢い恋し、しまいにはバーチャル結婚を得てAIショタを出産(設定)するも、そのAIが自我を持ってすくすく育ち、バーチャル世界に嫌気がさして現代に受肉した苦難系AIショタ。
人生に少し疲れている。
ホームレス生活をしている。
両親が憎い。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
青い腕は異能の【自動投銭集金回路】。数字は所持金額。
ネオンに具体的な金額を投銭したいと思えば自動で回収されてしまう。限度額は一回3万円。謎の手数料が30%とられて数字に加算される。このお金は電子マネーでしか使用できない。
30 / 30
50 PS
チナミ区
D-2
D-2





































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果等 |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]-【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |
| 4 | 不思議な牙 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV5)[防具]防御10(LV5)[装飾]器用10(LV5) |
| 5 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]敏捷10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) |
| 6 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV5)[効果2]活力10(LV10)[効果3]鎮痛10(LV15) |
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV5)[効果2]活力10(LV10)[効果3]鎮痛10(LV15) |
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 10 | 身体/武器/物理 |
| 解析 | 10 | 精確/対策/装置 |
| 武器 | 10 | 武器作製と、武器への素材の付加に影響。 |
| 付加 | 10 | 装備品への素材の付加に影響。 |
アクティブ
| スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 |
| ピンポイント | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 |
| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 |
| ヒール | 5 | 0 | 20 | 味傷:HP増 |
| エキサイト | 5 | 0 | 40 | 敵:攻撃+自:AT増(1T) |
| プリディクション | 5 | 0 | 60 | 味列:AG増(3T) |
| アキュラシィ | 5 | 0 | 80 | 自:連続減+敵:精確攻撃 |
| イレイザー | 5 | 0 | 150 | 敵傷:攻撃 |
| クイックアナライズ | 5 | 0 | 200 | 敵全:AG減 |
| ウィークポイント | 5 | 0 | 140 | 敵:3連痛撃 |
パッシブ
| スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 |
| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 |
| 活力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 |
| 体力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 |
| 治癒 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 |
| 幸運 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:運増 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |

PL / PeL