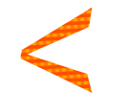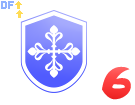<< 0:00>> 2:00




突出して秀でた才能も、特別夢中になる趣味もなかった。幼くから慣れ親しんだ花の手入れも、職にしようと思うほどではなく。面白味を感じるオカルト話も、一心に打ち込む程度ではなく。行先を決める決定打を持たない、つまらない人生だった。
そう、だった。一冊の聖典に出会う、その時まで。
通いやすい立地を理由に入学した大学で、なんとなくで籍を置いたオカルト研究サークル。オカルト研究といっても本格的なものではなく、その手の本を読み解き雑談混じりの論議を広げたり、ちょっとした肝試しで怪しげなスポットを訪れる程度のものだったが。その一環で行った小旅行こそが、人生の転機だった。今思えば、その行動すらも神の導きだったのかもしれない。
連休を利用し、少し足を伸ばしてのパワースポット巡り。夜には寂れた廃墟に足を運んだりして、少人数ながらもそれなりに学生らしい楽しみ方をしていたと思う。最終日、廃墟と化した教会へと足を運ぶまでは。
僕たちが生まれるよりも前に放棄されたらしい教会は、夜な夜な怪しげな集団が儀式を行っている、なんて噂を持つ場所であった。しかし噂は所詮噂、真実などせいぜい半分がいいところ。獣の足跡だけが残る埃だらけの床と獣道と化した通り道が、人の出入りがないことを如実に語っていた。怪しげな集団が出入りしているなんて法螺話だったのだと、安堵と落胆を全員が感じていただろう。その中で僕だけが、僕だけが、半分だけの真実を知ってしまった。知ることができたのだ。狭く灯りのない懺悔室の中、訪問者を待つ個室に残る儀式の痕跡。色褪せたカーペットの下に隠された、一冊の本。
インクは掠れ、紙は変色し、表紙は薄汚れてタイトルすらも読み取ることができない。仲間を呼ぶ前に少しだけと、数ページ紙をめくって理解した。遊び半分にラテン語の勉強をしていた自分を褒め称えたいと思ったのは、後にも先にもここだけであろう。己がすべてを捧げるべき、圧倒的で絶対の存在。神と呼ぶに相応しい、偉大な存在。古びた本がそれを記す聖典であると、その場で知ることができたのだから。子供程度の言語力ですべての文章を理解することは叶わなかったが、一語一語に意識を奪われるような気分だった。周りの音が耳に入らない、周りの景色が目に入らない、無我夢中になるという初めての体験。己の生の意味はこの本に記された存在のためにあるのだと、教典を探し得た僕にはその権利があるのだと、天啓を授かった気分だった。
しかし同時に僕は理解する。偉大なる権利を得た僕は数多の敵を作ってしまったのだと。数多の信徒がその権利を奪いに来るであろう、愚かな一般人が神を貶し邪魔をするだろう。準備もないうちにそれを退けるためにはどうしたらいいのか。答えは一つ。己が得た権利を人に悟られぬよう、秘密裏に事を進める、だ。その回答へ行きつくまでの時間は長かったようで、ごく短いものだった。思い返せば、今までにないほど集中し頭を働かせていたのだろう。
平然を装いながら帰宅し、その日は一晩本を読むことに費やした。翌日は、親族を言いくるめることに費やした。その次の日はサークルの脱退に、その次は退学の手続きに。常と変わらぬ日常を送りながら、神のために費やす時間を確保した。己を高め、贄を探し、相応しい空間を整える。その為に時間も労力も財も全てを惜しむことなく使ってきた。神の祝福を受けるに相応しい存在になるべく、努力をしてきた。神の忠実な僕たる己に起こる事象はすべて、神のお告げ。
ゆえに、戸惑うことは何もない。
己がアンジニティサイドと説明されている以上、神は世界の侵略を望んでいるのだろう。であれば、それに従うほかない。きっとこの混沌たる世界に、神が存在しているのだろう。広く安穏とした地を求め、侵略を肯定しているのだろう。きっと侵略は、大規模な儀式なのだ。
この戦場で死すかもしれない恐怖はない、神の祝福を受けている僕が死すはずがないのだから。
目の前にいる敵も恐ろしいものではない、それはきっと神へ捧げる贄なのだから。
ゆえに、何も恐れるべきものではない。
確かな高揚感に血の巡りが早くなっていくのを感じる。神の力になれる初めての機会、神との邂逅が近づく予感。身に余る光栄と期待感に胸が高鳴り、口元が歪んだ。



特に何もしませんでした。








自然LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
領域LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
武器LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)
千白(1413) により ItemNo.4 不思議な牙 から防具『信者のローブ』を作製してもらいました!
⇒ 信者のローブ/防具:強さ30/[効果1]防御10 [効果2]- [効果3]-/特殊アイテム
暦(1414) により ItemNo.5 不思議な石 から装飾『蜂蜜色のお守り』を作製してもらいました!
⇒ 蜂蜜色のお守り/装飾:強さ30/[効果1]幸運10 [効果2]- [効果3]-/特殊アイテム
巳子(1412) の持つ ItemNo.4 不思議な牙 から射程3の武器『鉄製のプーンギー』を作製しました!
千白(1413) の持つ ItemNo.4 不思議な牙 から射程4の武器『おっきなキッチン鋏』を作製しました!
暦(1414) の持つ ItemNo.5 不思議な石 から射程3の武器『エホンの書』を作製しました!
ストーンブラスト を習得!
プロテクション を習得!
アイヴィー を習得!
クラック を習得!
テリトリー を習得!
アースフェイバー を習得!



次元タクシーに乗り『チナミ区 E-5:出発地』に転送されました!
チナミ区 E-6(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 E-7(道路)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 F-7(草原)に移動!(体調28⇒27)
巳子(1412) からパーティに勧誘されました!






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャットで時間が伝えられる。
エディアンの前に1台のタクシーが止まり、窓が開く。

帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。
窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。
エディアンからのチャットが閉じられる――




















































異能・生産
アクティブ
パッシブ





[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



突出して秀でた才能も、特別夢中になる趣味もなかった。幼くから慣れ親しんだ花の手入れも、職にしようと思うほどではなく。面白味を感じるオカルト話も、一心に打ち込む程度ではなく。行先を決める決定打を持たない、つまらない人生だった。
そう、だった。一冊の聖典に出会う、その時まで。
通いやすい立地を理由に入学した大学で、なんとなくで籍を置いたオカルト研究サークル。オカルト研究といっても本格的なものではなく、その手の本を読み解き雑談混じりの論議を広げたり、ちょっとした肝試しで怪しげなスポットを訪れる程度のものだったが。その一環で行った小旅行こそが、人生の転機だった。今思えば、その行動すらも神の導きだったのかもしれない。
連休を利用し、少し足を伸ばしてのパワースポット巡り。夜には寂れた廃墟に足を運んだりして、少人数ながらもそれなりに学生らしい楽しみ方をしていたと思う。最終日、廃墟と化した教会へと足を運ぶまでは。
僕たちが生まれるよりも前に放棄されたらしい教会は、夜な夜な怪しげな集団が儀式を行っている、なんて噂を持つ場所であった。しかし噂は所詮噂、真実などせいぜい半分がいいところ。獣の足跡だけが残る埃だらけの床と獣道と化した通り道が、人の出入りがないことを如実に語っていた。怪しげな集団が出入りしているなんて法螺話だったのだと、安堵と落胆を全員が感じていただろう。その中で僕だけが、僕だけが、半分だけの真実を知ってしまった。知ることができたのだ。狭く灯りのない懺悔室の中、訪問者を待つ個室に残る儀式の痕跡。色褪せたカーペットの下に隠された、一冊の本。
インクは掠れ、紙は変色し、表紙は薄汚れてタイトルすらも読み取ることができない。仲間を呼ぶ前に少しだけと、数ページ紙をめくって理解した。遊び半分にラテン語の勉強をしていた自分を褒め称えたいと思ったのは、後にも先にもここだけであろう。己がすべてを捧げるべき、圧倒的で絶対の存在。神と呼ぶに相応しい、偉大な存在。古びた本がそれを記す聖典であると、その場で知ることができたのだから。子供程度の言語力ですべての文章を理解することは叶わなかったが、一語一語に意識を奪われるような気分だった。周りの音が耳に入らない、周りの景色が目に入らない、無我夢中になるという初めての体験。己の生の意味はこの本に記された存在のためにあるのだと、教典を探し得た僕にはその権利があるのだと、天啓を授かった気分だった。
しかし同時に僕は理解する。偉大なる権利を得た僕は数多の敵を作ってしまったのだと。数多の信徒がその権利を奪いに来るであろう、愚かな一般人が神を貶し邪魔をするだろう。準備もないうちにそれを退けるためにはどうしたらいいのか。答えは一つ。己が得た権利を人に悟られぬよう、秘密裏に事を進める、だ。その回答へ行きつくまでの時間は長かったようで、ごく短いものだった。思い返せば、今までにないほど集中し頭を働かせていたのだろう。
平然を装いながら帰宅し、その日は一晩本を読むことに費やした。翌日は、親族を言いくるめることに費やした。その次の日はサークルの脱退に、その次は退学の手続きに。常と変わらぬ日常を送りながら、神のために費やす時間を確保した。己を高め、贄を探し、相応しい空間を整える。その為に時間も労力も財も全てを惜しむことなく使ってきた。神の祝福を受けるに相応しい存在になるべく、努力をしてきた。神の忠実な僕たる己に起こる事象はすべて、神のお告げ。
ゆえに、戸惑うことは何もない。
己がアンジニティサイドと説明されている以上、神は世界の侵略を望んでいるのだろう。であれば、それに従うほかない。きっとこの混沌たる世界に、神が存在しているのだろう。広く安穏とした地を求め、侵略を肯定しているのだろう。きっと侵略は、大規模な儀式なのだ。
この戦場で死すかもしれない恐怖はない、神の祝福を受けている僕が死すはずがないのだから。
目の前にいる敵も恐ろしいものではない、それはきっと神へ捧げる贄なのだから。
ゆえに、何も恐れるべきものではない。
確かな高揚感に血の巡りが早くなっていくのを感じる。神の力になれる初めての機会、神との邂逅が近づく予感。身に余る光栄と期待感に胸が高鳴り、口元が歪んだ。
 |
静海 「 ――神よ、この機会。必ずやものにして見せましょう」 |



特に何もしませんでした。







自然LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
領域LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
武器LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)
千白(1413) により ItemNo.4 不思議な牙 から防具『信者のローブ』を作製してもらいました!
⇒ 信者のローブ/防具:強さ30/[効果1]防御10 [効果2]- [効果3]-/特殊アイテム
 |
千白 「てめえこの俺様が作ってやってんだ感謝しろよ!!!!!!!!!!!」 |
暦(1414) により ItemNo.5 不思議な石 から装飾『蜂蜜色のお守り』を作製してもらいました!
⇒ 蜂蜜色のお守り/装飾:強さ30/[効果1]幸運10 [効果2]- [効果3]-/特殊アイテム
巳子(1412) の持つ ItemNo.4 不思議な牙 から射程3の武器『鉄製のプーンギー』を作製しました!
千白(1413) の持つ ItemNo.4 不思議な牙 から射程4の武器『おっきなキッチン鋏』を作製しました!
暦(1414) の持つ ItemNo.5 不思議な石 から射程3の武器『エホンの書』を作製しました!
ストーンブラスト を習得!
プロテクション を習得!
アイヴィー を習得!
クラック を習得!
テリトリー を習得!
アースフェイバー を習得!



次元タクシーに乗り『チナミ区 E-5:出発地』に転送されました!
チナミ区 E-6(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 E-7(道路)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 F-7(草原)に移動!(体調28⇒27)
巳子(1412) からパーティに勧誘されました!






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
エディアン 「1時間が経過しましたね。」 |

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
チャットで時間が伝えられる。
 |
エディアン 「ナレハテとの戦闘、お疲れ様でした! 相手を戦闘不能にすればいいようですねぇ。」 |
 |
エディアン 「さてさて。皆さんにご紹介したい方がいるんです。 ――はぁい、こちらです!こちらでーっす!!」 |
エディアンの前に1台のタクシーが止まり、窓が開く。

ドライバーさん
次元タクシーの運転手。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。
 |
ドライバーさん 「どーも、『次元タクシー』の運転役だ。よろしく。」 |
帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。
 |
エディアン 「陣営に関わらず連れて行ってくれるようですのでどんどん利用しましょー!! ドライバーさんは中立ってことですよね?」 |
 |
ドライバーさん 「中立っつーかなぁ・・・。俺もタクシーも同じのが沢山"在る"んでな。 面倒なんで人と思わずハザマの機能の一部とでも思ってくれ。」 |
 |
ドライバーさん 「ま・・・チェックポイントとかの行き来の際にゃ、へいタクシーの一声を。じゃあな。」 |
窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。
 |
エディアン 「たくさん・・・ 同じ顔がいっぱいいるんですかねぇ・・・。 ここはまだ、分からないことだらけです。」 |
 |
エディアン 「それでは再びの1時間、頑張りましょう! 新情報を得たらご連絡しますね。ファイトー!!オーッ!!」 |
エディアンからのチャットが閉じられる――



morimoriオラウータン
|
 |
ハザマに生きるもの
|


ENo.1415
久藤 静海



名前:久藤 静海(くとう しずみ)
性別:♂ㅤ年齢:24歳
身長:172cmㅤ体重:60kg
■以下概要
裕福な家庭の長男にして無職、外との接触を図りたがららない半引きこもり。元は進路に悩むごく一般的な大学生だったが、三年前に『ある本』を手にしたことにより強い願望を抱くようになる。秘めたる願望を成すために大学を中退し、それを叶えるため日々を過ごしている。
性別:♂ㅤ年齢:24歳
身長:172cmㅤ体重:60kg
■以下概要
裕福な家庭の長男にして無職、外との接触を図りたがららない半引きこもり。元は進路に悩むごく一般的な大学生だったが、三年前に『ある本』を手にしたことにより強い願望を抱くようになる。秘めたる願望を成すために大学を中退し、それを叶えるため日々を過ごしている。
27 / 30
50 PS
チナミ区
F-7
F-7





































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果等 |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]-【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |
| 4 | 信者のローブ | 防具 | 30 | [効果1]防御10 [効果2]- [効果3]- |
| 5 | 蜂蜜色のお守り | 装飾 | 30 | [効果1]幸運10 [効果2]- [効果3]- |
| 6 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV5)[効果2]活力10(LV10)[効果3]鎮痛10(LV15) |
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV5)[効果2]活力10(LV10)[効果3]鎮痛10(LV15) |
| 8 | 何か柔らかい物体 | 素材 | 10 | [武器]祝福10(LV20)[防具]鎮痛10(LV20)[装飾]防御10(LV20) |
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 自然 | 10 | 植物/鉱物/地 |
| 領域 | 10 | 範囲/法則/結界 |
| 武器 | 20 | 武器作製と、武器への素材の付加に影響。 |
アクティブ
| スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 |
| ピンポイント | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 |
| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 |
| ヒール | 5 | 0 | 20 | 味傷:HP増 |
| ストーンブラスト | 5 | 0 | 40 | 敵:地撃 |
| プロテクション | 5 | 0 | 60 | 味傷:守護 |
| アイヴィー | 5 | 0 | 60 | 敵列:束縛 |
| クラック | 5 | 0 | 160 | 敵全:地撃&次与ダメ減 |
| テリトリー | 5 | 0 | 160 | 味列:DX増 |
| アースフェイバー | 5 | 0 | 140 | 自:地特性・復活LV増 |
パッシブ
| スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 |
| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 |
| 活力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 |
| 体力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 |
| 治癒 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 |
| 幸運 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:運増 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |

PL / ゆうぎ