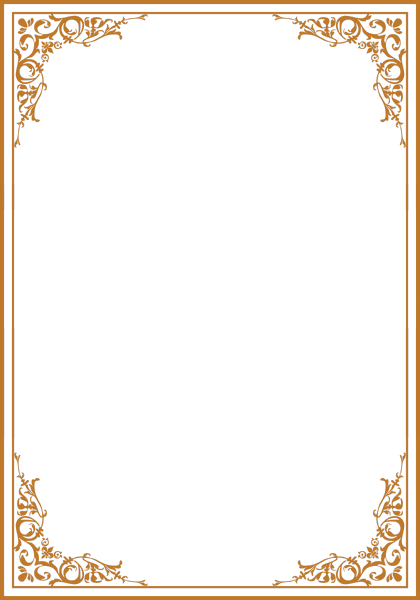<< 16:00~17:00




後方から追いすがるツタがK.Mの脚を絡め取り、にわかに空中に持ち上げた。
「やめろよぉッ!!」
すると、一瞬の内にK.Mの手のなかに刃が生まれ、ギィンッ!! 青白い光が奔って、縛るものが切り落とされる……
こんなことがもう何度繰り返されたか、K.Mにもわからない。目の前の出口に本当に近づいているのかどうかすらも。
「逃げる・こと・ない。ここが・終わり。ゴール」
それは、自分を診てくれたあの木の医師の声かも、王様の声かもしれなかったが、K.Mにはどうでもよかった。
とにかく少しでもここから離れなくてはならない。それだけで思考を満たした。
「くそっ、くそ……!!」
ギンッ! ギィン!
脅かすものを拒む異能力は一穂を守ってはくれるが、いつまでももちはしない。
K.Mは後ろを向き、仰向けになった。
おぞましく聳える巨樹が、床のおよそ七割を根で満たし―――その割合も見る見るうちに増大している―――その上には細いツタが千本ものたくりまわって、自分を狙っている。
幹にでも攻撃の主体が潜んでいるのだろうとK.Mは期待していた……実際、そこには眼球を思わせる、巨大な琥珀の球が埋め込まれていたのだから。
「アレが……敵かァーッ!?」
その敵が何者なのかは一切考えず、K.Mはただ絶叫した。
ギィーン!!
応えるように、閃光が琥珀の眼を打つ……が、直後その軌道はくの字に折れ曲がり、天井へと突き刺さるのがK.Mには見えた。
―――どういう硬さをしているんだ?
思案した瞬間、数本のツタがK.Mをめがけて飛翔した……
が、そこへ、パゥ、パゥッ!! K.Mの眼前でツタが弾けとぶ。
かと思えば、臙脂色のジャケットをまとった胴体が降ってくる―――K.Mはそれに見覚えがあった。
「犬の時の……!!」

☆ ★ ☆ ★ ☆
「……そうか。俺はずいぶんお前をピンチにしちまったんだな」
医師はもう手は止めている。一穂にはもうやれるだけの処置は施していた。
後は、彼自身が持ちこたえられるかどうかという段階であった―――もっともそれは確実そうに見えた。一穂の回復力は、なぜだか異常だったのだ。
「つーかコーヒーなんぞもらっちまって……文句言ってくれりゃタダにしたのにさ」
「い、いえいえ……だってあなたのせいかどうかもわかんないじゃないですか」
慌て気味に両手を振るK.Mを、医師はどこか覚悟していたような眼で見ていた。
「それで、お前は助かったんだよな?」
K.Mは首を縦に振った。
その拍子に、医師の足元が少し見えた。何もしていないのに靴が脱げていた。
☆ ★ ☆ ★ ☆
おとぎの国の空は今や炎に包まれ、あたりに火の雨が降り注いでいた。
どれだけ巨大で恐ろしくても所詮は樹だった。俊夫が連れてきた異能者の中で火炎の制御を得意とする者たちが、逃げる最中に耐えかねて火を放った。その結果がこれだった。
「ちくしょう! ちくしょう!!」
俊夫はそこらの動物をひっつかんでは己が異能で放水ポンプに変え、上に水を噴射しながら全力疾走していた。前方に一穂、後方に美香、ほか二名の異能者たちが続く。
「燃やすの早すぎんでしょ……!」
美香は毒づいたが、内心その張本人達は既に炭になっているのだろうと覚悟していた―――おとぎの国への突入メンバーは十数名はいたはずだったのだが、今ではここに居る者が全てだ。
それでも、後はもう逃げ続ければいつかは助かるはずだった。
「そうだよなぁ一穂ォ、逃げりゃいいんだよなァオイ!?」
生命を使い捨てながら走る俊夫が、悲鳴のように問うてくる。
一穂は、このおとぎの国につけられたDE-1401という名前を知っていた。
それが本質的には植物であり、どこかで発芽すると異次元に根を伸ばし、十分に成長すると生きづらさや空虚さを抱えた人々を己の養分にするのだと知っていた。
そこまでわかっているのはつまり、一度は大規模に根を張ってみせた個体がいたということで、それは無数の火炎放射器で恙無く焼き殺されたのだということを知っていた。
けれどそれは、誰かがまとめた報告書に書かれていたことにすぎない。
おとぎの国を支える巨樹は、突如として燃え盛る身体を地上へと伸ばしたのだった。
最後の力を振り絞るように―――あるいは、何か新たな活路を見出したかのように。
☆ ★ ☆ ★ ☆
「……イバラシティの死傷者は、今の所322名。
ついに『侵略』が本格的に始まったんだって、誰も彼も騒いでます」
「そうか」
巨樹はあれから炎に包まれた腕で、異能者たちを襲って、襲って、しかしどうにもならず、ついに力尽きた。彼も、美香も俊夫も、おとぎの国の唯一の生存者となったらしいK.Mも、それをただ見ているしかなかった。
一穂の知らない異常性が発揮されていた―――イバラシティの環境がそうさせたのか? だが、それを考える余地も、余裕もなかった。
いまにデマが飛び交い始めるだろう。そうなれば暴動が起こり、隣人同士で殺し合うようになるかもしれない。歴史の教科書に、あるいはだいぶ昔の漫画にでも描かれていたようなことが現実になりつつあった。
「……ぼく、あのシロナミって人と連絡を取る方法を探します。
あの人に頼んで、これは少なくともアンジニティのせいじゃないんだってことを伝えれば―――」
「やめとけ」
医師が制すると、K.Mは少し黙らなくてはならなくなった。
「パニクってる時に得体の知れないヤツがテレパシー飛ばしてきたとして、信じるか?」
医師はベッドに横たわる一穂に目をやる。彼の胸は静かに上下しており、そこだけを見れば普通に眠っているようにもとれた。
「どうすれば……」
「どうしようもないさ。まあ、いっそイバラシティが住めないくらいメチャクチャになっちまえば、アンジニティの連中も戦う理由をなくして―――」
「そんな!」
K.Mは医師に食ってかかった。
「そんなのってないです……イバラシティがこのままダメになるなんて、それこそダメですよ!」
「だったら、なんだ。このハザマからどうにかできるのか?」
医師の諦観は正しかった。ハザマからイバラシティに干渉する術など、今わかっている限りでは無いに等しい。
「それでも……それでも! こんなのって!!」
駄々をこねる子どものような気が、何かを押したのかもしれなかった。
医師はく、と傾くと、ドサリと椅子から床へ落ちた。
「だ、大丈夫……!?」
声をかけたK.Mの瞳が、縮まった。
白衣越しにもわかった―――医師には、膝から下がない。その膝もどんどん消失しているらしく、布がくたりと床に垂れ下がっていっている。
「……俺は、ここでも戦うことから逃げ続けてた。ナレハテになって、当然なんだよ」
医師の哀しげな微笑み、その表面を汗が伝っている―――いや、汗ではない。肉がアイスのように溶けて滴り落ちている。
「な、なんとか、なんとかしなきゃ……! そうだ、異能を使って!」
「無理だ。ナレハテ化を止める薬なんてあるわけねえだろ」
「やってみなくちゃ分かんないじゃないですか!!」
K.Mは半ば気が触れたように、この部屋の本を引っ張り出す。
どれもこれも、イバラシティにも存在していたこの病院の蔵書である……ナレハテのことが書かれているものなど、あるわけがなかった。
そのことに気づいてか、単に体力が尽きてか、K.Mは息を切らしてへたり込む。
「……お前さ、なんだってそんな一生懸命になれるんだ」
そう言う医師は仰向けに倒れていた。まだ、腕は残っているらしい。
「誰だって幸せになれるんだって、綺麗事が本当になることもあるんだって、信じなくっちゃ……
世界がそういう風にできてないわけ、ないんです……! きっと……、いや、絶対に!!」
どうしてそうも愚直になれるのか、問いただす時間はもはやない。
ただ医師は、心のなかで確信した。彼は、目の前の少年は、イバラシティの人ではない。
こんなに夢見がちで、けれど具体的にどうするかは全くわかってないような奴が、イバラシティに―――結局は生まれついての異能が生き方を決める世界に住んでいるとは思えない。
それでも、もしももっと早いうちにこの少年に出会っていたら、自分の人生はどうなっていただろう……
「お前……これからどうしたい? お前の夢はなんだ? そのためにどうするんだ?」
だから、思わず、聞いていた。両腕で上半身を起こして。
見下ろせば脚の大部分が既に失われ、股関節が溶け消えつつあるのがわかる。
「……。」
目の前の少年の言葉を、医師は唇を噛むようにして待った。
「……やっぱり、探します。どうすれば、イバラシティの人たちも、アンジニティの人たちも、助かるかを……
ワールドスワップを止めるのがいいのか、やらせるのがいいのかだって、決めなくちゃ。こうなったからには、戦いが終わった後でどうするかさえも考えなくちゃいけないんです。これから……急いで……」
そこまでが、今の少年の決意の限界らしい。
けれど言葉だけではない、目の輝きや顔つきといったものが、心に波紋をつくる。
「そう、か」
腕が体を支えきれなくなるより一瞬早く、医師は椅子にもたれかかった。
体中の骨が硬さを失い、粘土のような状態を経て、泥っぽくなりつつあった。今に顎が外れて喋れなくなり、眼窩からは目玉が転げ落ちていくのだろう。
ナレハテのあの顔を忘れることはなかった。ハザマに来た最初の一時間、振り向きざまに見せつけられたあれを……
「……泣いてるんですか?」
ふと、K.Mが言った。
医師の頬を、なにかが伝う―――彼自身、それは眼球の組織が溶けたものだと思っていた。
なぜ、今更泣かなくてはならないのだろう。
何がしたいのかもわからないまま生きてきた。
むしろ、何もしたくはないのだと思っていた。
あのおとぎの国に誘われたのも、そのせいだ。
死んでしまうくらいのこと、どうでもいいはずだった。
いっそ死ねたらいいとすら、思っていたんじゃないのか……
「……ぁ、ぁあ、」
閉じられなくなった口から、奇妙な声が漏れる。
「あぇ、ぇ、ぇあ、あ」
漏れる、漏れる、止まらない。
何を言おうとしているのかさえわからなくなってくる。
それでも、もう原型を留めてすらいないのだろう声帯を、震わせ続けなければいけない。
どうして……
「お医者さん……。」
K.Mが顔を近づけてくる。
「ぁぇ、ぇ、ぇあ、ア、ぇア゛……」
―――助けてほしい。
この体をもとに戻して。
ほんの一日だけ時間をくれればいい。
そしたらすぐにも病院を飛び出して、死ぬ気で戦ってみせるから。何かと。
「ァア゛、ぁエエ゛、ェッ、ェア……」
なぜ、そんなことを願っているんだろう。
できるはずがないと思っていたことを、この期に及んでやりたがるんだろう。
「ァアア゛ア゛ア゛ア゛……」
「お医者さん! ダメだ、しっかりしてッ!!」
誰の声なのだろう。
心が、思い出が、溶けていく。
赤黒い泥になっていく。
もう後戻りはできない。
なのに、そうとわかる度に、思わされる。
まだいたい。
『健介』でいたい……。
『健介』で……
―――パゥ、パゥッ!!
☆ ★ ☆ ★ ☆
ナレハテの赤い肉片を上半身に浴びたまま、K.Mは停止していた。
ベッドの上では一穂が体を起こし、その右手の中で拳銃が細い煙を吐いている。
「ここを出ますよ」
一穂はそう言うとK.Mに肩を貸し、引きずるようにして病室を後にした。
一穂の命をつないだマシンだけがその場に残され、少しずつ汗をかきはじめていた。



特に何もしませんでした。




変化LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
付加LV を 5 UP!(LV1⇒6、-5CP)
ガードフォーム を習得!
クリーンヒット を習得!
フェイタルトラップ を習得!
ローバスト を習得!
カームソング を習得!
プロテクション を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



特に移動せずその場に留まることにしました。
体調が全回復しました!





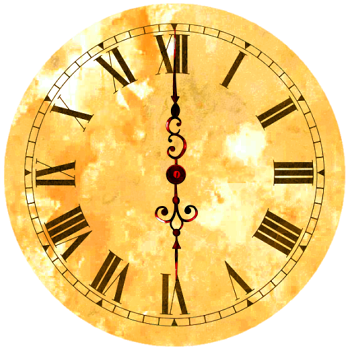
[870 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[443 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[500 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[190 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
[380 / 500] ―― 《大通り》より堅固な戦型
[296 / 500] ―― 《商店街》より安定な戦型
[204 / 500] ―― 《鰻屋》より俊敏な戦型
[143 / 500] ―― 《古寺》戦型不利の緩和
[61 / 500] ―― 《堤防》顕著な変化
[123 / 400] ―― 《駅舎》追尾撃破
[5 / 5] ―― 《美術館》異能増幅
[108 / 1000] ―― 《沼沢》いいものみっけ
[100 / 100] ―― 《道の駅》新商品入荷
[129 / 400] ―― 《果物屋》敢闘
[12 / 400] ―― 《黒い水》影響力奪取
[37 / 400] ―― 《源泉》鋭い眼光
―― Cross+Roseに映し出される。


チャット画面に映るふたりの姿。
清々しい笑顔を見せるふたり。
ふたりの愚痴が延々と続き、チャットが閉じられる――






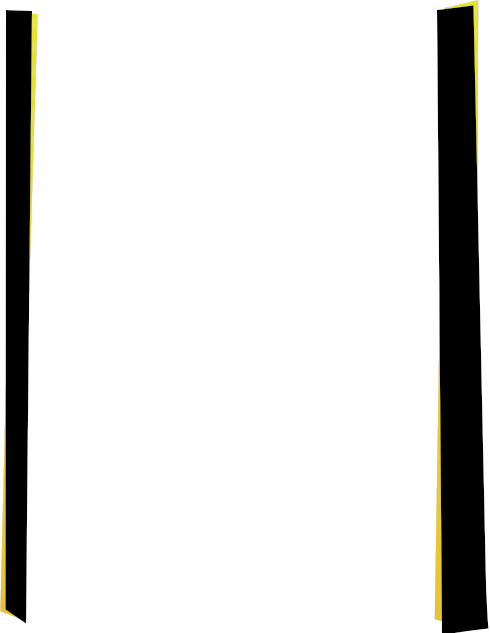
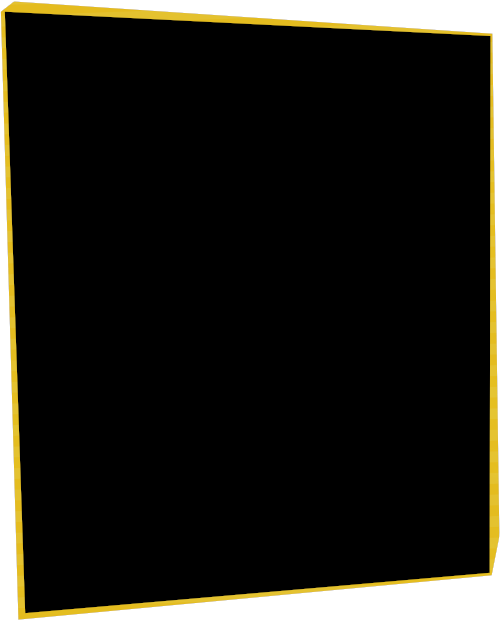





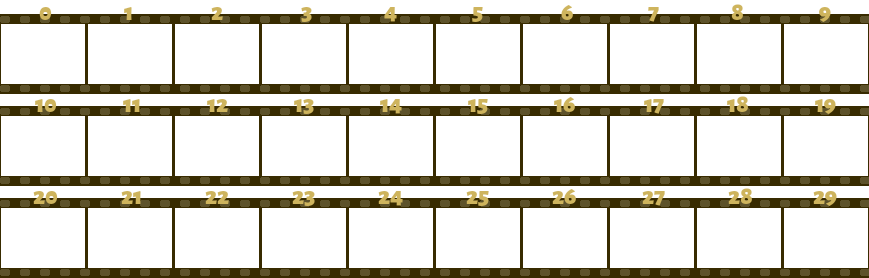







































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [スキル]OK.



後方から追いすがるツタがK.Mの脚を絡め取り、にわかに空中に持ち上げた。
「やめろよぉッ!!」
すると、一瞬の内にK.Mの手のなかに刃が生まれ、ギィンッ!! 青白い光が奔って、縛るものが切り落とされる……
こんなことがもう何度繰り返されたか、K.Mにもわからない。目の前の出口に本当に近づいているのかどうかすらも。
「逃げる・こと・ない。ここが・終わり。ゴール」
それは、自分を診てくれたあの木の医師の声かも、王様の声かもしれなかったが、K.Mにはどうでもよかった。
とにかく少しでもここから離れなくてはならない。それだけで思考を満たした。
「くそっ、くそ……!!」
ギンッ! ギィン!
脅かすものを拒む異能力は一穂を守ってはくれるが、いつまでももちはしない。
K.Mは後ろを向き、仰向けになった。
おぞましく聳える巨樹が、床のおよそ七割を根で満たし―――その割合も見る見るうちに増大している―――その上には細いツタが千本ものたくりまわって、自分を狙っている。
幹にでも攻撃の主体が潜んでいるのだろうとK.Mは期待していた……実際、そこには眼球を思わせる、巨大な琥珀の球が埋め込まれていたのだから。
「アレが……敵かァーッ!?」
その敵が何者なのかは一切考えず、K.Mはただ絶叫した。
ギィーン!!
応えるように、閃光が琥珀の眼を打つ……が、直後その軌道はくの字に折れ曲がり、天井へと突き刺さるのがK.Mには見えた。
―――どういう硬さをしているんだ?
思案した瞬間、数本のツタがK.Mをめがけて飛翔した……
が、そこへ、パゥ、パゥッ!! K.Mの眼前でツタが弾けとぶ。
かと思えば、臙脂色のジャケットをまとった胴体が降ってくる―――K.Mはそれに見覚えがあった。
「犬の時の……!!」
☆ ★ ☆ ★ ☆
「……そうか。俺はずいぶんお前をピンチにしちまったんだな」
医師はもう手は止めている。一穂にはもうやれるだけの処置は施していた。
後は、彼自身が持ちこたえられるかどうかという段階であった―――もっともそれは確実そうに見えた。一穂の回復力は、なぜだか異常だったのだ。
「つーかコーヒーなんぞもらっちまって……文句言ってくれりゃタダにしたのにさ」
「い、いえいえ……だってあなたのせいかどうかもわかんないじゃないですか」
慌て気味に両手を振るK.Mを、医師はどこか覚悟していたような眼で見ていた。
「それで、お前は助かったんだよな?」
K.Mは首を縦に振った。
その拍子に、医師の足元が少し見えた。何もしていないのに靴が脱げていた。
☆ ★ ☆ ★ ☆
おとぎの国の空は今や炎に包まれ、あたりに火の雨が降り注いでいた。
どれだけ巨大で恐ろしくても所詮は樹だった。俊夫が連れてきた異能者の中で火炎の制御を得意とする者たちが、逃げる最中に耐えかねて火を放った。その結果がこれだった。
「ちくしょう! ちくしょう!!」
俊夫はそこらの動物をひっつかんでは己が異能で放水ポンプに変え、上に水を噴射しながら全力疾走していた。前方に一穂、後方に美香、ほか二名の異能者たちが続く。
「燃やすの早すぎんでしょ……!」
美香は毒づいたが、内心その張本人達は既に炭になっているのだろうと覚悟していた―――おとぎの国への突入メンバーは十数名はいたはずだったのだが、今ではここに居る者が全てだ。
それでも、後はもう逃げ続ければいつかは助かるはずだった。
「そうだよなぁ一穂ォ、逃げりゃいいんだよなァオイ!?」
生命を使い捨てながら走る俊夫が、悲鳴のように問うてくる。
一穂は、このおとぎの国につけられたDE-1401という名前を知っていた。
それが本質的には植物であり、どこかで発芽すると異次元に根を伸ばし、十分に成長すると生きづらさや空虚さを抱えた人々を己の養分にするのだと知っていた。
そこまでわかっているのはつまり、一度は大規模に根を張ってみせた個体がいたということで、それは無数の火炎放射器で恙無く焼き殺されたのだということを知っていた。
けれどそれは、誰かがまとめた報告書に書かれていたことにすぎない。
おとぎの国を支える巨樹は、突如として燃え盛る身体を地上へと伸ばしたのだった。
最後の力を振り絞るように―――あるいは、何か新たな活路を見出したかのように。
☆ ★ ☆ ★ ☆
「……イバラシティの死傷者は、今の所322名。
ついに『侵略』が本格的に始まったんだって、誰も彼も騒いでます」
「そうか」
巨樹はあれから炎に包まれた腕で、異能者たちを襲って、襲って、しかしどうにもならず、ついに力尽きた。彼も、美香も俊夫も、おとぎの国の唯一の生存者となったらしいK.Mも、それをただ見ているしかなかった。
一穂の知らない異常性が発揮されていた―――イバラシティの環境がそうさせたのか? だが、それを考える余地も、余裕もなかった。
いまにデマが飛び交い始めるだろう。そうなれば暴動が起こり、隣人同士で殺し合うようになるかもしれない。歴史の教科書に、あるいはだいぶ昔の漫画にでも描かれていたようなことが現実になりつつあった。
「……ぼく、あのシロナミって人と連絡を取る方法を探します。
あの人に頼んで、これは少なくともアンジニティのせいじゃないんだってことを伝えれば―――」
「やめとけ」
医師が制すると、K.Mは少し黙らなくてはならなくなった。
「パニクってる時に得体の知れないヤツがテレパシー飛ばしてきたとして、信じるか?」
医師はベッドに横たわる一穂に目をやる。彼の胸は静かに上下しており、そこだけを見れば普通に眠っているようにもとれた。
「どうすれば……」
「どうしようもないさ。まあ、いっそイバラシティが住めないくらいメチャクチャになっちまえば、アンジニティの連中も戦う理由をなくして―――」
「そんな!」
K.Mは医師に食ってかかった。
「そんなのってないです……イバラシティがこのままダメになるなんて、それこそダメですよ!」
「だったら、なんだ。このハザマからどうにかできるのか?」
医師の諦観は正しかった。ハザマからイバラシティに干渉する術など、今わかっている限りでは無いに等しい。
「それでも……それでも! こんなのって!!」
駄々をこねる子どものような気が、何かを押したのかもしれなかった。
医師はく、と傾くと、ドサリと椅子から床へ落ちた。
「だ、大丈夫……!?」
声をかけたK.Mの瞳が、縮まった。
白衣越しにもわかった―――医師には、膝から下がない。その膝もどんどん消失しているらしく、布がくたりと床に垂れ下がっていっている。
「……俺は、ここでも戦うことから逃げ続けてた。ナレハテになって、当然なんだよ」
医師の哀しげな微笑み、その表面を汗が伝っている―――いや、汗ではない。肉がアイスのように溶けて滴り落ちている。
「な、なんとか、なんとかしなきゃ……! そうだ、異能を使って!」
「無理だ。ナレハテ化を止める薬なんてあるわけねえだろ」
「やってみなくちゃ分かんないじゃないですか!!」
K.Mは半ば気が触れたように、この部屋の本を引っ張り出す。
どれもこれも、イバラシティにも存在していたこの病院の蔵書である……ナレハテのことが書かれているものなど、あるわけがなかった。
そのことに気づいてか、単に体力が尽きてか、K.Mは息を切らしてへたり込む。
「……お前さ、なんだってそんな一生懸命になれるんだ」
そう言う医師は仰向けに倒れていた。まだ、腕は残っているらしい。
「誰だって幸せになれるんだって、綺麗事が本当になることもあるんだって、信じなくっちゃ……
世界がそういう風にできてないわけ、ないんです……! きっと……、いや、絶対に!!」
どうしてそうも愚直になれるのか、問いただす時間はもはやない。
ただ医師は、心のなかで確信した。彼は、目の前の少年は、イバラシティの人ではない。
こんなに夢見がちで、けれど具体的にどうするかは全くわかってないような奴が、イバラシティに―――結局は生まれついての異能が生き方を決める世界に住んでいるとは思えない。
それでも、もしももっと早いうちにこの少年に出会っていたら、自分の人生はどうなっていただろう……
「お前……これからどうしたい? お前の夢はなんだ? そのためにどうするんだ?」
だから、思わず、聞いていた。両腕で上半身を起こして。
見下ろせば脚の大部分が既に失われ、股関節が溶け消えつつあるのがわかる。
「……。」
目の前の少年の言葉を、医師は唇を噛むようにして待った。
「……やっぱり、探します。どうすれば、イバラシティの人たちも、アンジニティの人たちも、助かるかを……
ワールドスワップを止めるのがいいのか、やらせるのがいいのかだって、決めなくちゃ。こうなったからには、戦いが終わった後でどうするかさえも考えなくちゃいけないんです。これから……急いで……」
そこまでが、今の少年の決意の限界らしい。
けれど言葉だけではない、目の輝きや顔つきといったものが、心に波紋をつくる。
「そう、か」
腕が体を支えきれなくなるより一瞬早く、医師は椅子にもたれかかった。
体中の骨が硬さを失い、粘土のような状態を経て、泥っぽくなりつつあった。今に顎が外れて喋れなくなり、眼窩からは目玉が転げ落ちていくのだろう。
ナレハテのあの顔を忘れることはなかった。ハザマに来た最初の一時間、振り向きざまに見せつけられたあれを……
「……泣いてるんですか?」
ふと、K.Mが言った。
医師の頬を、なにかが伝う―――彼自身、それは眼球の組織が溶けたものだと思っていた。
なぜ、今更泣かなくてはならないのだろう。
何がしたいのかもわからないまま生きてきた。
むしろ、何もしたくはないのだと思っていた。
あのおとぎの国に誘われたのも、そのせいだ。
死んでしまうくらいのこと、どうでもいいはずだった。
いっそ死ねたらいいとすら、思っていたんじゃないのか……
「……ぁ、ぁあ、」
閉じられなくなった口から、奇妙な声が漏れる。
「あぇ、ぇ、ぇあ、あ」
漏れる、漏れる、止まらない。
何を言おうとしているのかさえわからなくなってくる。
それでも、もう原型を留めてすらいないのだろう声帯を、震わせ続けなければいけない。
どうして……
「お医者さん……。」
K.Mが顔を近づけてくる。
「ぁぇ、ぇ、ぇあ、ア、ぇア゛……」
―――助けてほしい。
この体をもとに戻して。
ほんの一日だけ時間をくれればいい。
そしたらすぐにも病院を飛び出して、死ぬ気で戦ってみせるから。何かと。
「ァア゛、ぁエエ゛、ェッ、ェア……」
なぜ、そんなことを願っているんだろう。
できるはずがないと思っていたことを、この期に及んでやりたがるんだろう。
「ァアア゛ア゛ア゛ア゛……」
「お医者さん! ダメだ、しっかりしてッ!!」
誰の声なのだろう。
心が、思い出が、溶けていく。
赤黒い泥になっていく。
もう後戻りはできない。
なのに、そうとわかる度に、思わされる。
まだいたい。
『健介』でいたい……。
『健介』で……
―――パゥ、パゥッ!!
☆ ★ ☆ ★ ☆
ナレハテの赤い肉片を上半身に浴びたまま、K.Mは停止していた。
ベッドの上では一穂が体を起こし、その右手の中で拳銃が細い煙を吐いている。
「ここを出ますよ」
一穂はそう言うとK.Mに肩を貸し、引きずるようにして病室を後にした。
一穂の命をつないだマシンだけがその場に残され、少しずつ汗をかきはじめていた。



特に何もしませんでした。



変化LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
付加LV を 5 UP!(LV1⇒6、-5CP)
ガードフォーム を習得!
クリーンヒット を習得!
フェイタルトラップ を習得!
ローバスト を習得!
カームソング を習得!
プロテクション を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



特に移動せずその場に留まることにしました。
体調が全回復しました!





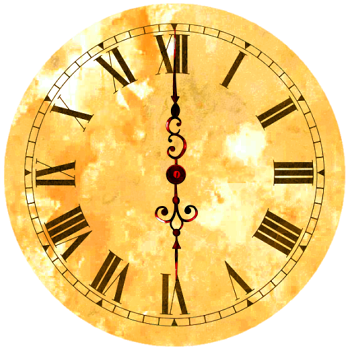
[870 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[443 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[500 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[190 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
[380 / 500] ―― 《大通り》より堅固な戦型
[296 / 500] ―― 《商店街》より安定な戦型
[204 / 500] ―― 《鰻屋》より俊敏な戦型
[143 / 500] ―― 《古寺》戦型不利の緩和
[61 / 500] ―― 《堤防》顕著な変化
[123 / 400] ―― 《駅舎》追尾撃破
[5 / 5] ―― 《美術館》異能増幅
[108 / 1000] ―― 《沼沢》いいものみっけ
[100 / 100] ―― 《道の駅》新商品入荷
[129 / 400] ―― 《果物屋》敢闘
[12 / 400] ―― 《黒い水》影響力奪取
[37 / 400] ―― 《源泉》鋭い眼光
―― Cross+Roseに映し出される。
 |
白南海 「・・・・・」 |
 |
エディアン 「・・・・・」 |

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
チャット画面に映るふたりの姿。
 |
エディアン 「・・・白南海さんからの招待なんて、珍しいじゃないですか。」 |
 |
白南海 「・・・・・いや、言いたいことあるんじゃねぇかな、とね・・・」 |
 |
エディアン 「・・・・・あぁ、そうですね。・・・とりあえず、叫んでおきますか。」 |
 |
白南海 「・・・・・そうすっかぁ。」 |
 |
白南海 「案内役に案内させろぉぉ―――ッ!!!!」 |
 |
エディアン 「案内役って何なんですかぁぁ―――ッ!!!!」 |
 |
白南海 「・・・・・」 |
 |
エディアン 「・・・・・」 |
 |
白南海 「役割与えてんだからちゃんと使えってーの!!!! 何でも自分でやっちまう上司とかいいと思ってんのか!!!!」 |
 |
エディアン 「そもそも人の使い方が下手すぎなんですよワールドスワップのひと。 少しも上の位置に立ったことないんですかねまったく、格好ばかり。」 |
 |
白南海 「・・・・・」 |
 |
エディアン 「・・・・・」 |
 |
白南海 「・・・いやぁすっきりした。」 |
 |
エディアン 「・・・どうもどうも、敵ながらあっぱれ。」 |
清々しい笑顔を見せるふたり。
 |
白南海 「・・・っつーわけだからよぉ、ワールドスワップの旦那は俺らを介してくれていいんだぜ?」 |
 |
エディアン 「ぶっちゃけ暇なんですよねこの頃。案内することなんてやっぱり殆どないじゃないですか。」 |
 |
エディアン 「あと可愛いノウレットちゃんを使ってあんなこと伝えるの、やめてくれません?」 |
 |
白南海 「・・・・・もういっそ、サボっちまっていいんじゃねぇすか?」 |
 |
エディアン 「あーそれもいいですねぇ。美味しい物でも食べに行っちゃおうかなぁ。」 |
 |
白南海 「うめぇもんか・・・・・水タバコどっかにねぇかなー。あーかったりぃー。」 |
 |
エディアン 「かったりぃですねぇほんと、もう好きにやっちゃいましょー!!」 |
 |
白南海 「よっしゃ、そんじゃブラブラと探しに――」 |
ふたりの愚痴が延々と続き、チャットが閉じられる――



決闘不成立!
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。
対戦相手が見つけられなかった!
不戦勝扱いになります。

ENo.3
宮田一穂とK.M.

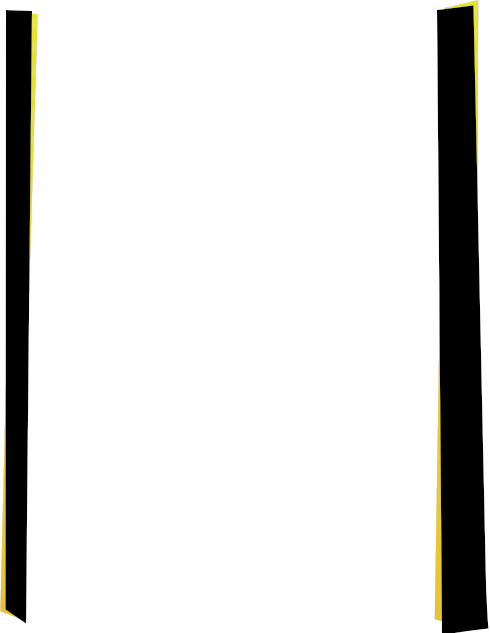
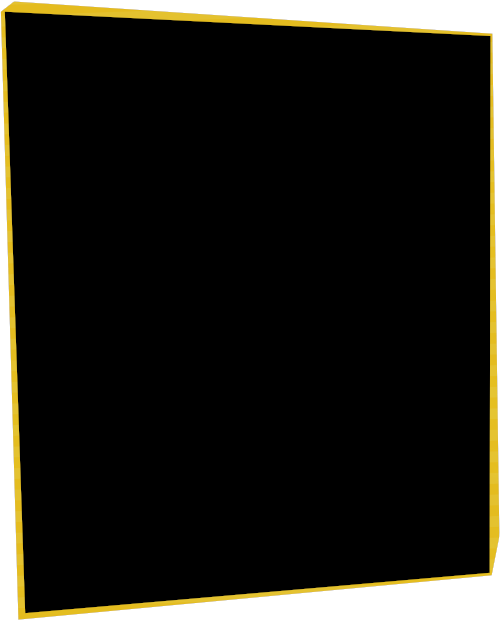
《宮田一穂(みやたかずほ)》
『すべてはいつの日か記号に還元されるでしょう』
・種族: 地球人(モンゴロイド)
・年齢:14歳/身長: 164cm/体重: 42kg/誕生日:10月3日
・特技:記憶すること/趣味:持たない/好物:特にない
イバラシティの片隅で路上生活を続ける少年。
言葉に抑揚が薄く、感情もほとんど示さない。ロボットのような印象を与えがちだが、優しさを見せないこともない。
赤いジャケットとニット帽を常に着用している。
その異能は『記憶』の異能。
自らの記憶を物体に焼き付けることができ、それを触れたものに記憶を『伝染』させ、自らのことのように感じさせる。代償として、焼き付けた記憶は本人の中から失われてしまう。また、記憶を焼きつけた物体は一度『伝染』させると効力を失い、再利用はできない。
異能とは別にほぼ完璧な記憶力を持ち、先述の異能の代償やなにか異常なものの影響にさらされた場合をのぞいて物事を忘れるということがない。
武器として拳銃を一丁所持している。相当に使い慣れている模様。
どこか異なる場所から来たようで、帰り方を探している。
※遭遇したものに対しメモを取る場合がございます。もし、問題がございましたら、ご一報頂ければ削除いたします。
⇒http://lisge.com/ib/talk.php?p=1821
《K.M.(クリストファ・マルムクヴィスト)》
ジャケットが青いのを除けば一穂とうりふたつの姿を持つ少年。
一穂と異なり、かなり殺傷力の強い異能を持っているようだ。また感情も普通に見せる。
PL: 切り株(@BehindForestBoy)
『すべてはいつの日か記号に還元されるでしょう』
・種族: 地球人(モンゴロイド)
・年齢:14歳/身長: 164cm/体重: 42kg/誕生日:10月3日
・特技:記憶すること/趣味:持たない/好物:特にない
イバラシティの片隅で路上生活を続ける少年。
言葉に抑揚が薄く、感情もほとんど示さない。ロボットのような印象を与えがちだが、優しさを見せないこともない。
赤いジャケットとニット帽を常に着用している。
その異能は『記憶』の異能。
自らの記憶を物体に焼き付けることができ、それを触れたものに記憶を『伝染』させ、自らのことのように感じさせる。代償として、焼き付けた記憶は本人の中から失われてしまう。また、記憶を焼きつけた物体は一度『伝染』させると効力を失い、再利用はできない。
異能とは別にほぼ完璧な記憶力を持ち、先述の異能の代償やなにか異常なものの影響にさらされた場合をのぞいて物事を忘れるということがない。
武器として拳銃を一丁所持している。相当に使い慣れている模様。
どこか異なる場所から来たようで、帰り方を探している。
※遭遇したものに対しメモを取る場合がございます。もし、問題がございましたら、ご一報頂ければ削除いたします。
⇒http://lisge.com/ib/talk.php?p=1821
《K.M.(クリストファ・マルムクヴィスト)》
ジャケットが青いのを除けば一穂とうりふたつの姿を持つ少年。
一穂と異なり、かなり殺傷力の強い異能を持っているようだ。また感情も普通に見せる。
PL: 切り株(@BehindForestBoy)
30 / 30
160 PS
チナミ
D-2
D-2







































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | SRmkVI | 武器 | 20 | 攻撃10 | - | - | 【射程1】 |
| 5 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]防御10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) | |||
| 6 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 8 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
| 9 | SRmkVI-P | 武器 | 35 | 束縛10 | - | - | 【射程3】 |
| 10 | 甲殻 | 素材 | 15 | [武器]地纏10(LV20)[防具]防御10(LV15)[装飾]反射10(LV25) | |||
| 11 | 防刃ベスト | 防具 | 67 | 活力15 | - | - | |
| 12 | 吸い殻 | 素材 | 10 | [武器]炎上10(LV25)[防具]火纏10(LV25)[装飾]耐火10(LV20) | |||
| 13 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 20 | 身体/武器/物理 |
| 制約 | 25 | 拘束/罠/リスク |
| 具現 | 30 | 創造/召喚 |
| 変化 | 5 | 強化/弱化/変身 |
| 響鳴 | 5 | 歌唱/音楽/振動 |
| 領域 | 20 | 範囲/法則/結界 |
| 武器 | 99 | 武器作製に影響 |
| 付加 | 6 | 装備品への素材の付加に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 6 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 6 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 6 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 | |
| ティンダー | 5 | 0 | 50 | 敵:火撃&炎上 | |
| アサルト | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃+自:連続減 | |
| クリエイト:タライ | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |
| ガードフォーム | 5 | 0 | 100 | 自:DF増 | |
| エチュード | 5 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) | |
| リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |
| デアデビル | 5 | 0 | 60 | 自:HP減+敵傷4:痛撃 | |
| クリエイト:シールド | 5 | 2 | 200 | 自:DF増+守護 | |
| クリーンヒット | 5 | 0 | 60 | 敵:痛撃&次与ダメ減 | |
| マーチ | 5 | 0 | 100 | 味全:AT増(4T) | |
| コンテイン | 5 | 0 | 50 | 敵列:精確攻撃&次与ダメ減 | |
| アリア | 5 | 2 | 0 | 自:SP・次与ダメ増 | |
| ファイアダンス | 5 | 0 | 80 | 敵:2連火領撃&炎上+領域値[火]3以上なら、火領撃&炎上 | |
| クリエイト:チェーン | 5 | 0 | 100 | 敵3:攻撃&束縛+自:AG減(1T) | |
| フェイタルトラップ | 5 | 0 | 100 | 敵貫:罠《追討》LV増 | |
| アラベスク | 5 | 0 | 50 | 味全:HP・AG増+魅了 | |
| カプリシャスナイト | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃&祝福 | |
| ローバスト | 5 | 0 | 100 | 自従:MSP・AT増 | |
| クリエイト:パワードスピーカー | 5 | 0 | 130 | 自:魅了LV増 | |
| クリエイト:ウィング | 5 | 0 | 130 | 自:追撃LV増 | |
| カームソング | 5 | 0 | 100 | 敵全:攻撃&DX減(2T) | |
| プロテクション | 5 | 0 | 80 | 自:守護 | |
| ミラー&ミラー | 5 | 0 | 100 | 味傷:HP増+反射状態なら反射 | |
| チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 | |
| ファイアボルト | 5 | 0 | 100 | 敵貫:火痛撃 | |
| ペナルティ | 5 | 0 | 120 | 敵3:麻痺・混乱 | |
| ガーディアン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+味傷:護衛 | |
| スピアトラップ | 5 | 0 | 100 | 敵:罠《突刺》LV増 | |
| サモン:ウォリアー | 5 | 5 | 300 | 自:ウォリアー召喚 | |
| カウンター | 5 | 0 | 130 | 自:反撃LV増 | |
| ボムトラップ | 5 | 0 | 110 | 敵:罠《爆弾》LV増 | |
| サモン:レッサーデーモン | 5 | 5 | 400 | 自:レッサーデーモン召喚 | |
| ブラッドアイズ | 5 | 0 | 150 | 自:HP減+AG・LK増+3D6が11以上ならAG・LK増(3T) | |
| サモン:ハンター | 5 | 4 | 300 | 自:ハンター召喚 | |
| イレイザー | 5 | 0 | 100 | 敵傷:攻撃 | |
| ピットトラップ | 5 | 0 | 120 | 敵全:罠《奈落》LV増 | |
| サモン:サーヴァント | 5 | 5 | 300 | 自:サーヴァント召喚 | |
| ツインブラスト | 5 | 0 | 220 | 敵全:攻撃&麻痺+敵全:攻撃&盲目 | |
| エスコート | 5 | 0 | 100 | 自:次受ダメ減+味列:護衛 | |
| クリエイト:ワイヤートラップ | 5 | 0 | 280 | 敵全:罠《鋼線》LV増 | |
| インクリースアイズ | 5 | 0 | 100 | 自:連続増+自身のスキル・付加効果内のダイス目が高めになる | |
| ハードブレイク | 5 | 1 | 120 | 敵:攻撃 | |
| イグニス | 5 | 0 | 120 | 敵傷3:火領撃 | |
| リビルド | 5 | 0 | 300 | 自:連続増+総行動数を0に変更+名前に「クリエイト」を含む全スキルの残り発動回数増 | |
| インヴァージョン | 5 | 0 | 150 | 敵全:攻撃&祝福を猛毒化 | |
| デスペラート | 5 | 0 | 130 | 敵:報讐LV増+6連撃+報讐消滅 | |
| クリエイト:ウェポン | 5 | 0 | 280 | 味全:追撃LV増 | |
| クリエイト:フォートレス | 5 | 0 | 300 | 味全:DF増(3T) | |
| フィアスファング | 5 | 0 | 150 | 敵:攻撃&MHP減 | |
| マイントラップ | 5 | 0 | 250 | 敵:罠《地雷》LV増 | |
| クリエイト:モンスター | 5 | 0 | 150 | 敵:粗雑攻撃 | |
| インファイト | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&隊列1なら更に4連撃 | |
| サモン:ヴァンパイア | 5 | 5 | 500 | 自:ヴァンパイア召喚 | |
| サモン:ソルジャー | 5 | 5 | 600 | 自:ソルジャー召喚(複数可) |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 召喚強化 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:具現LVが高いほど自身の召喚するNPCが強化 | |
| 火の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:魔術LVが高いほど火特性・耐性増 | |
| 阿修羅 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HP減+AT・DX・LK増 | |
| 集気 | 5 | 4 | 0 | 【通常攻撃後】自:次与ダメ増 | |
| 再利用 | 5 | 5 | 0 | 【スキル使用後】自:直前に使用したスキル名に「クリエイト」が含まれるなら、SP増 | |
| 高速配置 | 5 | 4 | 0 | 【スキル使用後】自:直前に使用したスキル名に「トラップ」が含まれるなら、連続増 | |
| 覇気 | 5 | 4 | 0 | 【被HP回復後】敵全:精確攻撃 | |
| 超技術 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:名前に「トラップ」「クリエイト」を含む全スキルを強化 | |
| 腐敗堕落 | 5 | 3 | 0 | 【攻撃回避後】対:腐食+自堕落LV増 | |
| 大砲作製 | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『装備作製』で武器「大砲」を選択できる。大砲は射程が必ず4になる。 | |
| 魔弾作製 | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『装備作製』で武器「魔弾」を選択できる。魔弾は「攻撃命中後」のパッシブスキル・付加効果の発動率が増加する。大砲と共に装備することで更に増加する。 |
最大EP[25]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
ダメージアブソーバー (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
|
雷鳥は頂きを目指す (インヴァージョン) |
0 | 150 | 敵全:攻撃&祝福を猛毒化 | |
|
猟犬の一撃 (イグニス) |
0 | 120 | 敵傷3:火領撃 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 2 ]ミラージュ | [ 1 ]ティンダー | [ 1 ]ファイアダンス |
| [ 1 ]ファイアレイド | [ 1 ]イレイザー | [ 3 ]ハードブレイク |
| [ 3 ]インパクト |

PL / 切り株