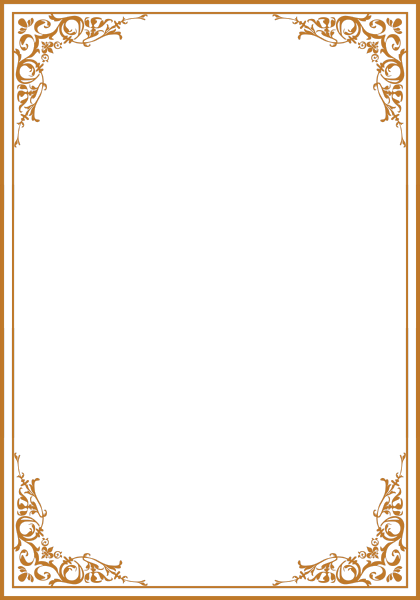<< 13:00~14:00




リュウジン湖を南に望む通りにはすでにパトカーが駆けつけ、警察官たちが失踪事件の現場検証を行っていた。そこへ一穂、美香、俊夫が遅れて現れる。
「俊夫!」
彼の母親らしき女性が狼狽しつつ駆け寄ってきた。ショートヘアに緑色のタートルネックを着た細めの体つきで、長ズボンがピッと合っている。
「母ちゃん! 姉ちゃんが!?」
「行方がわかんないんだよォ、戻ってこないんだ……!」
「道路に穴は掘ったのか!?」
と、そこへがっしりとした体格の、ひげを蓄えた警部補の男が向いてきて、
「さっき透視の異能を持つ者にやらせたがコンクリの塊と管しかなかったとです。君は息子さんかね?」
「えっ、は、はい」
「また何があるやらわからんから離れとることです。奇怪な事件だがお姉さんはきっと見つけ出します」
警部補はそう言ってまた現場に目をやった。
「ね、姉ちゃん、なんで……」
俊夫はがっくりと力が抜けへたりこんでしまった。
流石にかける言葉がなく、美香は押し黙る。一穂も黙っていたが、彼の場合は違うところを見つめていたからだった。
「一穂?」
「あれを」
一穂の目線の先に、道路を突き破り天を仰ぐ花があった。ちょうど、警官たちもそれを摘もうとしている。
「……ポピーの花だ。なんで―――」
こんな所にあるんだろうと言い切る前に、美香の耳に一穂の唇が接近した。
「この事件はデビアンスによるものです」
「はぁ!?」
神経系が急激に緊張し喉を震わせそうになった美香を、一穂は人差し指で制して話し続ける。
「……DE-1401、かつて大規模なインシデントを発生させたものです。
対処が必要ですが、相手がこれでは……」

☆ ★ ☆ ★ ☆
おもちゃ箱をひっくり返したような世界でも時間は流れているらしい。
空が水彩絵の具でオレンジ色に、次第に暗い青に塗りつぶされていく。ブーメランみたいにひん曲がった三日月と、五つのトゲをもった星が、糸で吊られているみたいにふんわり降りてくる。
「おや、さっきまで明るかったのに」
『王様』の少年は不思議そうに空を眺めて言った。
「もう夜なんだね。ねむたいや」
と、二本足のブタが大あくび。
「それじゃあ今日はこの辺にして、みんなでおやすみしようか」
「そうしよう、そうしよう」
冠をした少年を先頭に、おとぎの国の人々は歩き出す。色とりどりの体は星と月の光に照らされ、一人残らず蒼く染まっていた。
向かう先は、あの天を衝く巨城。
途中、丘の上からニット帽を被った少年が駆けてきて、行列に加わった。
飾り以上の意味がない門をくぐり、城の一階、巨大なドームへ。その天井は太い枝や細い枝が複雑に絡み合ってできており、昼間は木漏れ日が差して床に魔法の紋様をあらわす。
その端っこから螺旋階段を降り、地下へ。そこは鉢のような形状で、一階と合わせればちょうど球になる。中は一面ふかふかの土で覆われ、淡い色をした花がいくつも生えていた。どれもこれも巨大で、大人の一人や二人軽く支えられそうなほどだ。
「今夜はここで寝よーっと!」
とんがり帽子に蝶々の羽根の妖精がピンクのチューリップの中に飛び込んだ。他のベッドも次々埋まっていく。中に人が入れば、花弁は閉じた。
あのニット帽の少年も良さげな寝床を探していると、
「ねえねえ、きみK.Mだよねっ、いっしょに寝ようよぉ」
兵隊の格好をした男の子がジャケットをぐいぐい引っ張ってきた。
「え……あ、そうだ、うん、いいよ」
K.Mはあれから退院を言い渡されていたので、別にここで寝ても問題はなかった。
「わあい、やったあ!」
K.Mは兵隊が三回目のバンザイをしたところを抱え上げ、一緒にポピーの花の中に潜り込む。
「おやすみK.M」
「うん、おやすみ」
さらさらの布団のような花弁が閉じて、目の前が薄暗くなっていく。雄しべは赤子を慈しむ母の腕のように身体の全てを抱きしめる。
ふんわりと甘い匂い。脳が急激に、だが自然に減速させられていき、何か考えることを許さない。明日、何して遊ぼうかさえも。
それなのに、K.Mの意識にしつこくこびりつく言葉が一つあった。
「……ユー、ミ……?」
☆ ★ ☆ ★ ☆
ひび割れ凸凹になった道路が無愛想に伸びている―――そんなものでさえ、まだこの世界ではマシな道だった。数分ほど前からK.Mは道すらない中を歩き続けるはめになっていたのだ。
イバラシティを元にしたハザマは、そういう荒れ果てた世界だった。
それでもK.Mは前に進まねばならなかった。その華奢な体に、今にも命尽きてしまいそうな一穂を背負っていたから。そしてイバラの地図と照らし合わせればこの先に大きな病院があるはずだった。
一穂が死ねば、自分の希望も死ぬ―――それ以前に、瀕死の人間が目の前に居て、あっさり諦められるような精神性は持たないのがK.Mである。これが例えば砂漠や荒れ狂う大河だったとしても彼は歩き続けただろう。
が、ふと見えざる何かが彼をうち、その悲壮な歩みを止めた。
「ッ……!?」
自己の連続性に、強制的に割り込んでくる何か―――例えばルーズリーフバインダーに自意識があったとしたら、新しい紙を差し込まれる時にこんな思いをするのだろうか。
これは初めての体験というわけでもない。イバラシティの自分が十日ほどを過ごす度、直後の一瞬のうちにハザマでの一時間が進むわけだが、その際同時にイバラ側の記憶がドッと脳に書き込まれるのだ。これについては慣れろと『侵略』の始まりにきつく言われていたから、K.Mも気にしないよう努力していた。
けれど今回ばかりは無理だった。無理なものが、割り込んできていた。
☆ ★ ☆ ★ ☆
アンジニティのK.Mと、イバラシティに『挿入』されたK.Mとで違わなかったのは、なにも容姿だけではない。
イバラのK.Mもどうにも虐められ体質だったのである。足をつっかけられて転ばされたり、先生に当てられて間違えでもしたら盛大に笑われたり……怒り方をよく知らないK.Mは格好のサンドバッグにされていた。自分の異能がうっかり暴発でもした日には死傷者が出かねないので、怒るに怒れないのもあったのだ―――異能者が集うイバラシティにおいてそういう『事故』は時折発生し、ニュースにのぼる。都度市民はなくそうイジメ・ハラスメントと声を上げるが、それは例えるならドブ池にいくつも小石を放り込んでみるようなものだった。何せ人が死んだところで遺族や縁のあった者以外は早々に忘れてゆくものだし、虐める側はまさか相手に殺されるだろうだなんて思うわけがない……少なくとも、愉しんでいる間は。
その日のK.Mは夏休みの真っ最中で、開放された小学校のプールに通っていた。が、ひとしきり泳いで校門を出たところで、いつもの連中に水着鞄をひったくられてしまう。
おかげで摂氏四十度に迫る猛暑の中、玉のような汗をポトポト落としながら街をさまようことになった。プールで使った水着は、その日のうちに洗濯機できれいにしなくてはならないのだ。
「あぁ、あいつら、どこに行ったンだ……」
嫌々ながらに、ビルの間から、陽光に焼かれる川沿いの通りへと出る。
眩しく染まる視界……その中でふと、ボトム・アップ的注意が反応をした。道をゆくやんちゃ坊主ども。先頭の一人が手首に何かのひもを引っ掛け、くるくる回してる―――あれは、僕の水着鞄!!
「アッ、いた! 待てぇ!!」
よせばいいのにK.Mは叫んでしまった。おかげで虐めっ子どもは彼の方を向き、邪な考えをする時間すら持てた。
「あーらクリスちゃーん! 見つかっちゃったわねーェ! カバンは返すわよぉーン!?」
甲高い声で、虐めっ子の首魁、とんがった顔の長身の少年が叫ぶ。彼はそのまま振り回してた水着鞄の紐から手を引っこ抜いた。
鞄はくるくる舞って川の真ん中に落っこちる。バッシャーン。とりあえずは浮いたが、今にも沈んでしまいそうだ。
「ワァーッ」
K.Mは半泣きになりながら川にざぶざぶ飛び込んでいった。足が、膝が、腰が、水面下に消えていく。
「ギャッハハハハハハ……」
虐めっ子連中は笑いながら歩き去る。K.Mが溺死しようなどとは考えもしない。
K.Mも泳げないわけではなかった。つい数十分ほど前まで、プールで平泳ぎに背泳ぎだってしていた。だが着衣水泳とあっては話は別である。
水の重みに負けそうになる身体を、必死さに任せて突き動かす。フォームは崩れ、半ば犬かきのようになり、それでも流されていくプール鞄に抱きついた。
だが、それがK.Mの精一杯だった。
流れが意外と……早すぎる。そういえば昨日は雨だったし、そのせいかな……
と、ふと身体が虚空へ投げ出され―――ドパァーン!! 河川に設けられた段差から、K.Mは水面に叩きつけられてしまった。
そのショックが心を折ってしまったかのようだった。もう、これ以上どこにも泳げない。このまま溺れて死ぬんじゃないか?
「助けてェ。だれ、かッ……ゴボッ、助けてェ!!」
水に呑まれそうになりながらもK.Mは叫んだ。
けれど、助けにくる者はいない。K.Mがわめくことすらできなくなるのも時間の問題だった。
そこへ……また、ドッパァン。
何かが降ってきて―――K.Mの幼い身体を、能動的に支えた。
「本当にうちの子がご迷惑をおかけして……ありがとうございました……」
K.Mの母は息子の前に出て、その女性の前でペコペコと頭を下げ続けた。
女性は栗色の髪と、つややかに血の通った肌をしていた。道に迷ったら尋ねてみたくなるような、柔和そうな顔つきだ。
それなのに、彼女はK.M母子から一定の距離を保つようにしていた。
「そんな、気にしないで下さい。私、急いでますから……」
「クリストファは虐められてたんです、あなたのような方がもう二度とこんな目に遭わなくて済みますようもう断固もう抗議します、本当に本当に、モウ……」
女性の赤いトップスの前でK.M母はモウモウと頭を上下している。
牛は赤いものを見ると興奮するっていうけど本当なのかもなあ、というのがこの時のK.Mの思考である。そんなことより、この女の人―――磯崎ユーミに、自分なりのお礼がしたかった。
「私の異能は危ないの。だから……今は、一緒にはいられない」
管理すらまともにされてないらしい寂れた公園にヒグラシが鳴く。そんな中、ユーミはK.Mから目をそらしがちに告げた。
「危ないって……?」
「……生命を吸ってしまう力なの。自分でも、いつ出るか……出てしまったら止められないの。
親も危険な力を持ってて……うち、代々呪われてるのかもね」
K.Mは目を見開く。だとしたら、あの時助けてくれたのは……
「……クリス君が溺れていた時は、なぜだか、いても立ってもいられなかったの。
力が出ませんように、出ませんように……って祈りながら泳いだわ。それでたまたま出なかっただけなの」
「ならまた抑えられるかもしれないじゃないですか! 二度でも三度でも……!」
「無理よ。自分じゃ、無理……」
ユーミはくるりとK.Mに背を向ける。
「そんな!」
「でもね」
ユーミはすぐには歩き出さず、言葉を続ける。
「……今度、病院へ行って、異能を危なくなくする治療を受けることになったの。お父さんやお母さんも一緒にね。
それは一年とか二年じゃ済まないかもしれない……だけど治療が終わったら、きっと、きっとまた会えるわ。
それまで、待っててくれる?」
「……は、はいっ! 僕、待ちます! 絶対待ってます!」
K.Mはぱあっと笑顔になり、ユーミも最後に微笑み返して、お互い帰路についた。
けれど、お互い元気な姿で会うことができたのは、この時が最後だったのである。



特に何もしませんでした。




武器LV を 15 UP!(LV75⇒90、-15CP)
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



特に移動せずその場に留まることにしました。
体調が全回復しました!





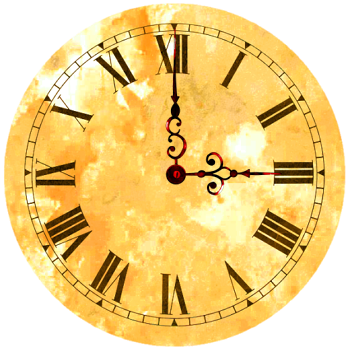
[852 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[422 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[483 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[161 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
[354 / 500] ―― 《大通り》より堅固な戦型
[251 / 500] ―― 《商店街》より安定な戦型
[182 / 500] ―― 《鰻屋》より俊敏な戦型
[118 / 500] ―― 《古寺》戦型不利の緩和
[44 / 500] ―― 《堤防》顕著な変化
[111 / 400] ―― 《駅舎》追尾撃破
[5 / 5] ―― 《美術館》異能増幅
―― Cross+Roseに映し出される。

Cross+Rose越しにどこかの様子を見ているエディアン。


元気よくチャットに入り込むノウレットと、少し機嫌の悪そうな白南海。
見ていた何かをサッと消す。
ノウレットにゲンコツする白南海。
検索方法をエディアンに教わり、若を検索してみる。
ノウレットにゲンコツ。
ノウレットの頭を優しく撫でるエディアン。
こっそりと、Cross+Rose越しに再びどこかの様子を見るエディアン。
チャットが閉じられる――


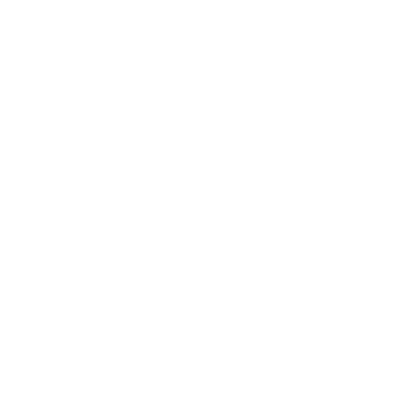
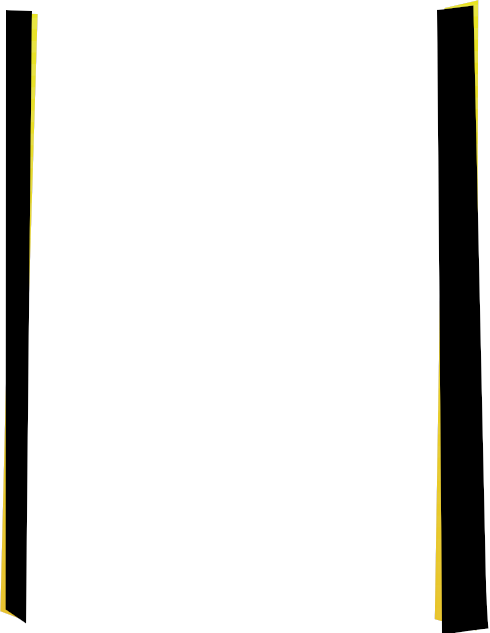
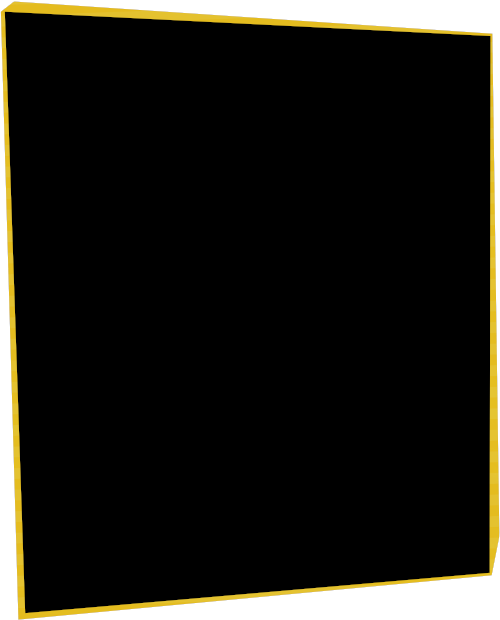





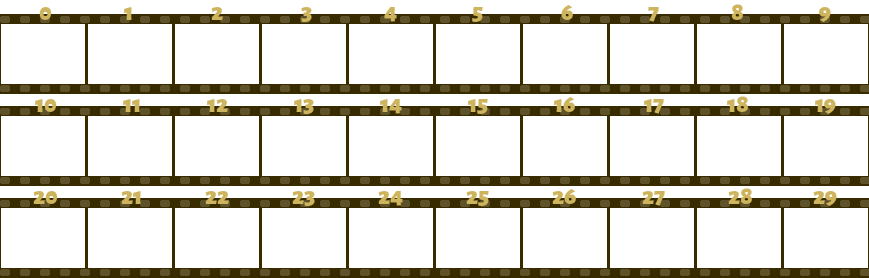







































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [スキル]OK.



リュウジン湖を南に望む通りにはすでにパトカーが駆けつけ、警察官たちが失踪事件の現場検証を行っていた。そこへ一穂、美香、俊夫が遅れて現れる。
「俊夫!」
彼の母親らしき女性が狼狽しつつ駆け寄ってきた。ショートヘアに緑色のタートルネックを着た細めの体つきで、長ズボンがピッと合っている。
「母ちゃん! 姉ちゃんが!?」
「行方がわかんないんだよォ、戻ってこないんだ……!」
「道路に穴は掘ったのか!?」
と、そこへがっしりとした体格の、ひげを蓄えた警部補の男が向いてきて、
「さっき透視の異能を持つ者にやらせたがコンクリの塊と管しかなかったとです。君は息子さんかね?」
「えっ、は、はい」
「また何があるやらわからんから離れとることです。奇怪な事件だがお姉さんはきっと見つけ出します」
警部補はそう言ってまた現場に目をやった。
「ね、姉ちゃん、なんで……」
俊夫はがっくりと力が抜けへたりこんでしまった。
流石にかける言葉がなく、美香は押し黙る。一穂も黙っていたが、彼の場合は違うところを見つめていたからだった。
「一穂?」
「あれを」
一穂の目線の先に、道路を突き破り天を仰ぐ花があった。ちょうど、警官たちもそれを摘もうとしている。
「……ポピーの花だ。なんで―――」
こんな所にあるんだろうと言い切る前に、美香の耳に一穂の唇が接近した。
「この事件はデビアンスによるものです」
「はぁ!?」
神経系が急激に緊張し喉を震わせそうになった美香を、一穂は人差し指で制して話し続ける。
「……DE-1401、かつて大規模なインシデントを発生させたものです。
対処が必要ですが、相手がこれでは……」

☆ ★ ☆ ★ ☆
おもちゃ箱をひっくり返したような世界でも時間は流れているらしい。
空が水彩絵の具でオレンジ色に、次第に暗い青に塗りつぶされていく。ブーメランみたいにひん曲がった三日月と、五つのトゲをもった星が、糸で吊られているみたいにふんわり降りてくる。
「おや、さっきまで明るかったのに」
『王様』の少年は不思議そうに空を眺めて言った。
「もう夜なんだね。ねむたいや」
と、二本足のブタが大あくび。
「それじゃあ今日はこの辺にして、みんなでおやすみしようか」
「そうしよう、そうしよう」
冠をした少年を先頭に、おとぎの国の人々は歩き出す。色とりどりの体は星と月の光に照らされ、一人残らず蒼く染まっていた。
向かう先は、あの天を衝く巨城。
途中、丘の上からニット帽を被った少年が駆けてきて、行列に加わった。
飾り以上の意味がない門をくぐり、城の一階、巨大なドームへ。その天井は太い枝や細い枝が複雑に絡み合ってできており、昼間は木漏れ日が差して床に魔法の紋様をあらわす。
その端っこから螺旋階段を降り、地下へ。そこは鉢のような形状で、一階と合わせればちょうど球になる。中は一面ふかふかの土で覆われ、淡い色をした花がいくつも生えていた。どれもこれも巨大で、大人の一人や二人軽く支えられそうなほどだ。
「今夜はここで寝よーっと!」
とんがり帽子に蝶々の羽根の妖精がピンクのチューリップの中に飛び込んだ。他のベッドも次々埋まっていく。中に人が入れば、花弁は閉じた。
あのニット帽の少年も良さげな寝床を探していると、
「ねえねえ、きみK.Mだよねっ、いっしょに寝ようよぉ」
兵隊の格好をした男の子がジャケットをぐいぐい引っ張ってきた。
「え……あ、そうだ、うん、いいよ」
K.Mはあれから退院を言い渡されていたので、別にここで寝ても問題はなかった。
「わあい、やったあ!」
K.Mは兵隊が三回目のバンザイをしたところを抱え上げ、一緒にポピーの花の中に潜り込む。
「おやすみK.M」
「うん、おやすみ」
さらさらの布団のような花弁が閉じて、目の前が薄暗くなっていく。雄しべは赤子を慈しむ母の腕のように身体の全てを抱きしめる。
ふんわりと甘い匂い。脳が急激に、だが自然に減速させられていき、何か考えることを許さない。明日、何して遊ぼうかさえも。
それなのに、K.Mの意識にしつこくこびりつく言葉が一つあった。
「……ユー、ミ……?」
☆ ★ ☆ ★ ☆
ひび割れ凸凹になった道路が無愛想に伸びている―――そんなものでさえ、まだこの世界ではマシな道だった。数分ほど前からK.Mは道すらない中を歩き続けるはめになっていたのだ。
イバラシティを元にしたハザマは、そういう荒れ果てた世界だった。
それでもK.Mは前に進まねばならなかった。その華奢な体に、今にも命尽きてしまいそうな一穂を背負っていたから。そしてイバラの地図と照らし合わせればこの先に大きな病院があるはずだった。
一穂が死ねば、自分の希望も死ぬ―――それ以前に、瀕死の人間が目の前に居て、あっさり諦められるような精神性は持たないのがK.Mである。これが例えば砂漠や荒れ狂う大河だったとしても彼は歩き続けただろう。
が、ふと見えざる何かが彼をうち、その悲壮な歩みを止めた。
「ッ……!?」
自己の連続性に、強制的に割り込んでくる何か―――例えばルーズリーフバインダーに自意識があったとしたら、新しい紙を差し込まれる時にこんな思いをするのだろうか。
これは初めての体験というわけでもない。イバラシティの自分が十日ほどを過ごす度、直後の一瞬のうちにハザマでの一時間が進むわけだが、その際同時にイバラ側の記憶がドッと脳に書き込まれるのだ。これについては慣れろと『侵略』の始まりにきつく言われていたから、K.Mも気にしないよう努力していた。
けれど今回ばかりは無理だった。無理なものが、割り込んできていた。
☆ ★ ☆ ★ ☆
アンジニティのK.Mと、イバラシティに『挿入』されたK.Mとで違わなかったのは、なにも容姿だけではない。
イバラのK.Mもどうにも虐められ体質だったのである。足をつっかけられて転ばされたり、先生に当てられて間違えでもしたら盛大に笑われたり……怒り方をよく知らないK.Mは格好のサンドバッグにされていた。自分の異能がうっかり暴発でもした日には死傷者が出かねないので、怒るに怒れないのもあったのだ―――異能者が集うイバラシティにおいてそういう『事故』は時折発生し、ニュースにのぼる。都度市民はなくそうイジメ・ハラスメントと声を上げるが、それは例えるならドブ池にいくつも小石を放り込んでみるようなものだった。何せ人が死んだところで遺族や縁のあった者以外は早々に忘れてゆくものだし、虐める側はまさか相手に殺されるだろうだなんて思うわけがない……少なくとも、愉しんでいる間は。
その日のK.Mは夏休みの真っ最中で、開放された小学校のプールに通っていた。が、ひとしきり泳いで校門を出たところで、いつもの連中に水着鞄をひったくられてしまう。
おかげで摂氏四十度に迫る猛暑の中、玉のような汗をポトポト落としながら街をさまようことになった。プールで使った水着は、その日のうちに洗濯機できれいにしなくてはならないのだ。
「あぁ、あいつら、どこに行ったンだ……」
嫌々ながらに、ビルの間から、陽光に焼かれる川沿いの通りへと出る。
眩しく染まる視界……その中でふと、ボトム・アップ的注意が反応をした。道をゆくやんちゃ坊主ども。先頭の一人が手首に何かのひもを引っ掛け、くるくる回してる―――あれは、僕の水着鞄!!
「アッ、いた! 待てぇ!!」
よせばいいのにK.Mは叫んでしまった。おかげで虐めっ子どもは彼の方を向き、邪な考えをする時間すら持てた。
「あーらクリスちゃーん! 見つかっちゃったわねーェ! カバンは返すわよぉーン!?」
甲高い声で、虐めっ子の首魁、とんがった顔の長身の少年が叫ぶ。彼はそのまま振り回してた水着鞄の紐から手を引っこ抜いた。
鞄はくるくる舞って川の真ん中に落っこちる。バッシャーン。とりあえずは浮いたが、今にも沈んでしまいそうだ。
「ワァーッ」
K.Mは半泣きになりながら川にざぶざぶ飛び込んでいった。足が、膝が、腰が、水面下に消えていく。
「ギャッハハハハハハ……」
虐めっ子連中は笑いながら歩き去る。K.Mが溺死しようなどとは考えもしない。
K.Mも泳げないわけではなかった。つい数十分ほど前まで、プールで平泳ぎに背泳ぎだってしていた。だが着衣水泳とあっては話は別である。
水の重みに負けそうになる身体を、必死さに任せて突き動かす。フォームは崩れ、半ば犬かきのようになり、それでも流されていくプール鞄に抱きついた。
だが、それがK.Mの精一杯だった。
流れが意外と……早すぎる。そういえば昨日は雨だったし、そのせいかな……
と、ふと身体が虚空へ投げ出され―――ドパァーン!! 河川に設けられた段差から、K.Mは水面に叩きつけられてしまった。
そのショックが心を折ってしまったかのようだった。もう、これ以上どこにも泳げない。このまま溺れて死ぬんじゃないか?
「助けてェ。だれ、かッ……ゴボッ、助けてェ!!」
水に呑まれそうになりながらもK.Mは叫んだ。
けれど、助けにくる者はいない。K.Mがわめくことすらできなくなるのも時間の問題だった。
そこへ……また、ドッパァン。
何かが降ってきて―――K.Mの幼い身体を、能動的に支えた。
「本当にうちの子がご迷惑をおかけして……ありがとうございました……」
K.Mの母は息子の前に出て、その女性の前でペコペコと頭を下げ続けた。
女性は栗色の髪と、つややかに血の通った肌をしていた。道に迷ったら尋ねてみたくなるような、柔和そうな顔つきだ。
それなのに、彼女はK.M母子から一定の距離を保つようにしていた。
「そんな、気にしないで下さい。私、急いでますから……」
「クリストファは虐められてたんです、あなたのような方がもう二度とこんな目に遭わなくて済みますようもう断固もう抗議します、本当に本当に、モウ……」
女性の赤いトップスの前でK.M母はモウモウと頭を上下している。
牛は赤いものを見ると興奮するっていうけど本当なのかもなあ、というのがこの時のK.Mの思考である。そんなことより、この女の人―――磯崎ユーミに、自分なりのお礼がしたかった。
「私の異能は危ないの。だから……今は、一緒にはいられない」
管理すらまともにされてないらしい寂れた公園にヒグラシが鳴く。そんな中、ユーミはK.Mから目をそらしがちに告げた。
「危ないって……?」
「……生命を吸ってしまう力なの。自分でも、いつ出るか……出てしまったら止められないの。
親も危険な力を持ってて……うち、代々呪われてるのかもね」
K.Mは目を見開く。だとしたら、あの時助けてくれたのは……
「……クリス君が溺れていた時は、なぜだか、いても立ってもいられなかったの。
力が出ませんように、出ませんように……って祈りながら泳いだわ。それでたまたま出なかっただけなの」
「ならまた抑えられるかもしれないじゃないですか! 二度でも三度でも……!」
「無理よ。自分じゃ、無理……」
ユーミはくるりとK.Mに背を向ける。
「そんな!」
「でもね」
ユーミはすぐには歩き出さず、言葉を続ける。
「……今度、病院へ行って、異能を危なくなくする治療を受けることになったの。お父さんやお母さんも一緒にね。
それは一年とか二年じゃ済まないかもしれない……だけど治療が終わったら、きっと、きっとまた会えるわ。
それまで、待っててくれる?」
「……は、はいっ! 僕、待ちます! 絶対待ってます!」
K.Mはぱあっと笑顔になり、ユーミも最後に微笑み返して、お互い帰路についた。
けれど、お互い元気な姿で会うことができたのは、この時が最後だったのである。



特に何もしませんでした。



武器LV を 15 UP!(LV75⇒90、-15CP)
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



特に移動せずその場に留まることにしました。
体調が全回復しました!





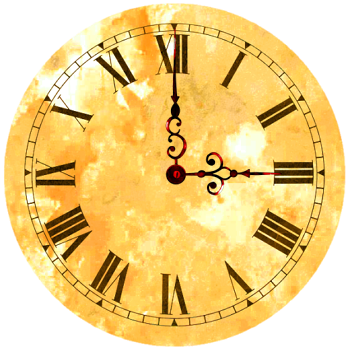
[852 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[422 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[483 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[161 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
[354 / 500] ―― 《大通り》より堅固な戦型
[251 / 500] ―― 《商店街》より安定な戦型
[182 / 500] ―― 《鰻屋》より俊敏な戦型
[118 / 500] ―― 《古寺》戦型不利の緩和
[44 / 500] ―― 《堤防》顕著な変化
[111 / 400] ―― 《駅舎》追尾撃破
[5 / 5] ―― 《美術館》異能増幅
―― Cross+Roseに映し出される。

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
 |
エディアン 「・・・・・・・・・うわぁ。」 |
Cross+Rose越しにどこかの様子を見ているエディアン。

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
 |
ノウレット 「こんちゃーっすエディアンさん!お元気っすかー??」 |
 |
白南海 「・・・・・・チッ」 |
元気よくチャットに入り込むノウレットと、少し機嫌の悪そうな白南海。
 |
エディアン 「あ、えっと、どうしました?・・・突然。」 |
 |
白南海 「ん、取り込み中だったか。」 |
 |
エディアン 「いえいえいえいえいえー!!なーんでもないでーす!!!!」 |
見ていた何かをサッと消す。
 |
エディアン 「・・・・・それで、何の用です?」 |
 |
白南海 「ん・・・・・ぁー・・・・・クソ妖精がな・・・」 |
 |
ノウレット 「コイツがワカワカドコドコうるせぇんでワカなんていませんって教えたんすわ!」 |
 |
エディアン 「・・・・・・・・・」 |
 |
エディアン 「・・・何かノウレットちゃん、様子おかしくないです?」 |
 |
白南海 「ちょいちょい話してたら・・・・・・何かこうなった。」 |
 |
エディアン 「え・・・・・口調を覚えたりしちゃうんですかこの子。てゆか、ちょいちょい話してたんですか。」 |
 |
ノウレット 「問い合わせ含め58回ってところっすね!!!!」 |
ノウレットにゲンコツする白南海。
 |
ノウレット 「ひいぅ!!」 |
 |
白南海 「いやそこはいいとしてだ・・・・・若がいねぇーっつーんだよこのクソ妖精がよぉ。」 |
 |
エディアン 「そんなこと、名前で検索すればわかるんじゃ?」 |
 |
白南海 「検索・・・・・そういうのあんのかやっぱ。教えてくれ。」 |
検索方法をエディアンに教わり、若を検索してみる。
 |
白南海 「――やっぱいねぇのかよ!」 |
 |
ノウレット 「ほらー!!言ったとおりじゃねーっすかー!!!!」 |
 |
白南海 「だぁーまぁー・・・れ。」 |
ノウレットにゲンコツ。
 |
ノウレット 「ひいぅぅ!!・・・・・また、なぐられた・・・・・うぅ・・・」 |
 |
エディアン 「システムだからっていじめないでくださいよぉ、かわいそうでしょ!!」 |
ノウレットの頭を優しく撫でるエディアン。
 |
エディアン 「ノウレットちゃんに聞いたんなら、結果はそりゃ一緒でしょうねぇ。 そもそも我々からの連絡を受けた者しかハザマには呼ばれないわけですし。」 |
 |
白南海 「・・・・・ぇ、そうなん・・・?」 |
 |
エディアン 「忘れたんです?貴方よくそれで案内役なんて・・・・・」 |
 |
エディアン 「あー、あと名前で引っ掛からないんなら、若さんアンジニティって可能性も?」 |
 |
エディアン 「そしたらこちらのお仲間ですねぇ!ザンネーン!!」 |
 |
白南海 「・・・・・ふざけたこと言ってんじゃねーぞ。」 |
 |
白南海 「まぁいねぇのは寂しいっすけどイバラシティで楽しくやってるってことっすねー!! それはそれで若が幸せってなもんで私も幸せってなもんで!」 |
こっそりと、Cross+Rose越しに再びどこかの様子を見るエディアン。
 |
エディアン 「さてあいつめ・・・・・どうしたものか。」 |
チャットが閉じられる――

ENo.3
宮田一穂とK.M.
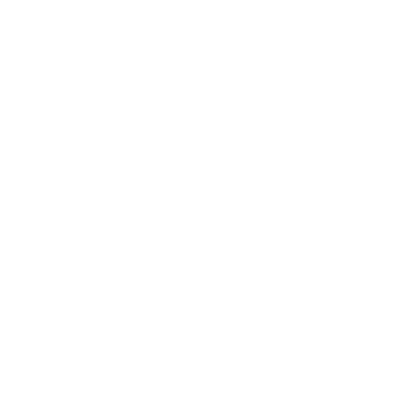
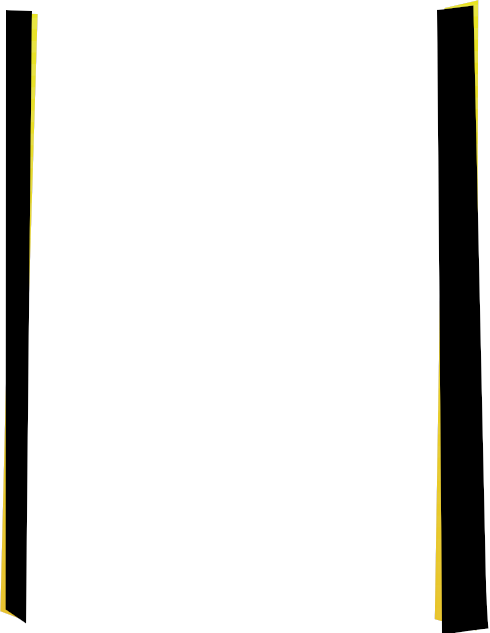
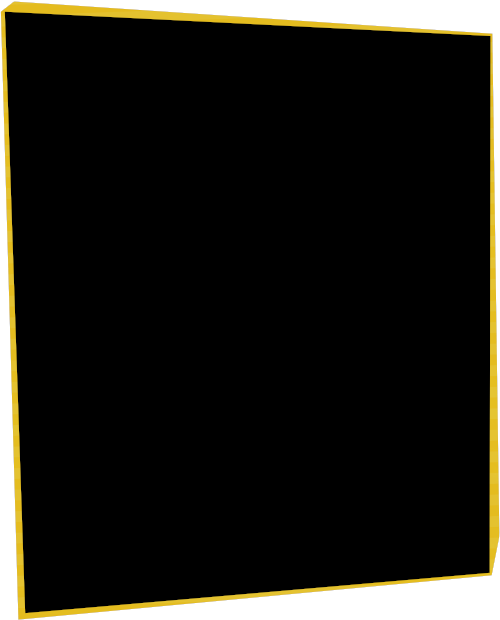
《宮田一穂(みやたかずほ)》
『すべてはいつの日か記号に還元されるでしょう』
・種族: 地球人(モンゴロイド)
・年齢:14歳/身長: 164cm/体重: 42kg/誕生日:10月3日
・特技:記憶すること/趣味:持たない/好物:特にない
イバラシティの片隅で路上生活を続ける少年。
言葉に抑揚が薄く、感情もほとんど示さない。ロボットのような印象を与えがちだが、優しさを見せないこともない。
赤いジャケットとニット帽を常に着用している。
その異能は『記憶』の異能。
自らの記憶を物体に焼き付けることができ、それを触れたものに記憶を『伝染』させ、自らのことのように感じさせる。代償として、焼き付けた記憶は本人の中から失われてしまう。また、記憶を焼きつけた物体は一度『伝染』させると効力を失い、再利用はできない。
異能とは別にほぼ完璧な記憶力を持ち、先述の異能の代償やなにか異常なものの影響にさらされた場合をのぞいて物事を忘れるということがない。
武器として拳銃を一丁所持している。相当に使い慣れている模様。
どこか異なる場所から来たようで、帰り方を探している。
※遭遇したものに対しメモを取る場合がございます。もし、問題がございましたら、ご一報頂ければ削除いたします。
⇒http://lisge.com/ib/talk.php?p=1821
《K.M.(クリストファ・マルムクヴィスト)》
ジャケットが青いのを除けば一穂とうりふたつの姿を持つ少年。
一穂と異なり、かなり殺傷力の強い異能を持っているようだ。また感情も普通に見せる。
PL: 切り株(@BehindForestBoy)
『すべてはいつの日か記号に還元されるでしょう』
・種族: 地球人(モンゴロイド)
・年齢:14歳/身長: 164cm/体重: 42kg/誕生日:10月3日
・特技:記憶すること/趣味:持たない/好物:特にない
イバラシティの片隅で路上生活を続ける少年。
言葉に抑揚が薄く、感情もほとんど示さない。ロボットのような印象を与えがちだが、優しさを見せないこともない。
赤いジャケットとニット帽を常に着用している。
その異能は『記憶』の異能。
自らの記憶を物体に焼き付けることができ、それを触れたものに記憶を『伝染』させ、自らのことのように感じさせる。代償として、焼き付けた記憶は本人の中から失われてしまう。また、記憶を焼きつけた物体は一度『伝染』させると効力を失い、再利用はできない。
異能とは別にほぼ完璧な記憶力を持ち、先述の異能の代償やなにか異常なものの影響にさらされた場合をのぞいて物事を忘れるということがない。
武器として拳銃を一丁所持している。相当に使い慣れている模様。
どこか異なる場所から来たようで、帰り方を探している。
※遭遇したものに対しメモを取る場合がございます。もし、問題がございましたら、ご一報頂ければ削除いたします。
⇒http://lisge.com/ib/talk.php?p=1821
《K.M.(クリストファ・マルムクヴィスト)》
ジャケットが青いのを除けば一穂とうりふたつの姿を持つ少年。
一穂と異なり、かなり殺傷力の強い異能を持っているようだ。また感情も普通に見せる。
PL: 切り株(@BehindForestBoy)
30 / 30
160 PS
チナミ
D-2
D-2







































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | SRmkVI | 武器 | 20 | 攻撃10 | - | - | 【射程1】 |
| 5 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]防御10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) | |||
| 6 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 8 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
| 9 | SRmkVI-P | 武器 | 35 | 束縛10 | - | - | 【射程3】 |
| 10 | 甲殻 | 素材 | 15 | [武器]地纏10(LV20)[防具]防御10(LV15)[装飾]反射10(LV25) | |||
| 11 | 防刃ベスト | 防具 | 67 | 活力15 | - | - | |
| 12 | 吸い殻 | 素材 | 10 | [武器]炎上10(LV25)[防具]火纏10(LV25)[装飾]耐火10(LV20) | |||
| 13 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 25 | 身体/武器/物理 |
| 制約 | 25 | 拘束/罠/リスク |
| 響鳴 | 5 | 歌唱/音楽/振動 |
| 武器 | 90 | 武器作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 6 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 6 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 6 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 | |
| ティンダー | 5 | 0 | 50 | 敵:火撃&炎上 | |
| アサルト | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃+自:連続減 | |
| エチュード | 5 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) | |
| デアデビル | 5 | 0 | 60 | 自:HP減+敵傷4:痛撃 | |
| マーチ | 5 | 0 | 100 | 味全:AT増(4T) | |
| アリア | 5 | 2 | 0 | 自:SP・次与ダメ増 | |
| ファイアダンス | 5 | 0 | 80 | 敵:2連火領撃&炎上+領域値[火]3以上なら、火領撃&炎上 | |
| アラベスク | 5 | 0 | 50 | 味全:HP・AG増+魅了 | |
| チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 | |
| ファイアボルト | 5 | 0 | 100 | 敵貫:火痛撃 | |
| ペナルティ | 5 | 0 | 120 | 敵3:麻痺・混乱 | |
| スピアトラップ | 5 | 0 | 100 | 敵:罠《突刺》LV増 | |
| ボムトラップ | 5 | 0 | 110 | 敵:罠《爆弾》LV増 | |
| イレイザー | 5 | 0 | 100 | 敵傷:攻撃 | |
| ピットトラップ | 5 | 0 | 120 | 敵全:罠《奈落》LV増 | |
| ハードブレイク | 5 | 1 | 120 | 敵:攻撃 | |
| イグニス | 5 | 0 | 120 | 敵傷3:火領撃 | |
| デスペラート | 5 | 0 | 130 | 敵:報讐LV増+6連撃+報讐消滅 | |
| フィアスファング | 5 | 0 | 150 | 敵:攻撃&MHP減 | |
| マイントラップ | 5 | 0 | 250 | 敵:罠《地雷》LV増 | |
| インファイト | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&隊列1なら更に4連撃 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 火の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:魔術LVが高いほど火特性・耐性増 | |
| 阿修羅 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HP減+AT・DX・LK増 | |
| 高速配置 | 5 | 4 | 0 | 【スキル使用後】自:直前に使用したスキル名に「トラップ」が含まれるなら、連続増 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
ダメージアブソーバー (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
|
雷鳥は頂きを目指す (インヴァージョン) |
0 | 150 | 敵全:攻撃&祝福を猛毒化 | |
|
猟犬の一撃 (イグニス) |
0 | 120 | 敵傷3:火領撃 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]イレイザー | [ 1 ]ファイアレイド | [ 2 ]ミラージュ |
| [ 1 ]ティンダー | [ 3 ]インパクト | [ 1 ]ファイアダンス |
| [ 3 ]ハードブレイク |

PL / 切り株