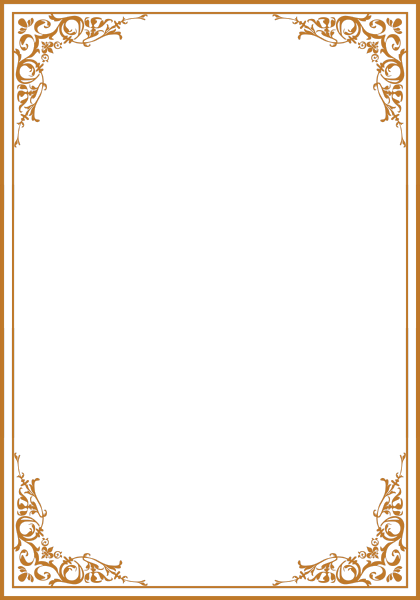<< 10:00~11:00




イバラシティ北西、マガサ区の南半分。
大通りでいくつかに区切られたこの一帯は、朝から夕方まで同じくらいに騒がしい。午前八時ごろになれば通りの内側に密集した家々から学生やら社会人やらが飛び出して、マガサ駅へと駆けこみ、美しい海を拝みながら満員電車に揉まれていく。
もちろん駅に行くまでもない者も多い。健介少年もその一人だった。眠たいまぶたをこすり、中肉中背の体を重たく感じながら―――夜ふかしをしたわけでもないのに―――リュウジン区にある高校へ走っていく。
赤信号数秒前の横断歩道を突破し、長い坂道を駆け下り駆け下り……盛大にすっ転んで膝をすりむく。学校についてから水と石鹸できれいにしなくては。大っぴらに治癒の異能を使ってくれるやつなんてうちのクラスにはいやしない……よしんばいても頼る気になれない。
なんとか遅刻は免れて座席につく。ここの机は七行六列で、健介の席は教壇手前から三番目、窓際から四列目に位置する。一時間目の授業が始まった。
異能の基礎理論に関するお話だった。
「まずはね、近代になって確立されたね、異能の十五区分ですね」
教師はのんきな声と共に、黒板にカツカツとチョークで書いていく。武術、魔術、命術、時空、自然、幻術、呪術、制約、具現、使役、変化、共鳴、百薬、領域、解析―――健介はまどろっこしかった。今年で七十二になる健介の祖父が言うにはこれが全部書けただけで一目置かれたものだそうだが、今日日幼稚園児にだってこのくらい諳んじてみせるやつはいる。
「みなさんも近くどれかの分類を受けるかと思います……私はみなさんくらいの年頃にはもう受けてましたがね。というのも私が大学を出て少ししたくらいの頃から、異能開発学という考え方が主流になってきたのですね。我々が持つ異能はずっと先天的に―――要は生まれた時点で全く決まってしまっていて一生ありのまま受け入れて生きてかなきゃならんものだって思われていたのです。ですが、生まれた後からでも訓練や学習次第で変えていけるんではないかとわかったのですね」
この提唱に希望をみた人は少なくないだろうと想像はできる―――マイナス二十六.七五等星の閃光が頭上の分厚い雲に風穴を開けつつ自分を撃ち抜いていくような、強烈な希望を。
けど、これも健介からすればロクでもない話であった。
後の授業はもう聞きもしない。健介はこの場には必要ない本を取り出し、教科書に重ねて開く。その表紙には『大花塾 特別強化ドリル』とあった。
☆ ★ ☆ ★ ☆
『イバラシティNo.1 完全保証 進学から就職まで 未来花咲く大花塾』
そう書かれたのぼりが倒れ、建物の中に入ろうとする健介の行く手を阻んでいた。軽く踏んづけそうになり、小さくジャンプして跳び越す。
講師の一人の顔が健介の頭に浮かぶ。この塾の講師であるという事実、それと真面目さと一途さとを拠り所にして生きている人だ。尊敬しているわけでもないけれど、それでものぼりを踏んづけた足で会いに行くのは少々怖かった―――今日は彼の授業を受ける日だ。
自動ドアをくぐって入り、階段の前にある駅の改札みたいなゲートに塾生証を通して教室の並ぶフロアへ進む。この塾はイバラシティでも一、二を争うほどの巨大さで、すれ違う連中も同い年だったり年下だったり年上だったりする。ここは中学から大学受験はおろかその先までもサポートしているのだ……でなきゃ今どきあんな自信過剰なのぼりは立てておけまいと健介は思う。
健介は廊下の端の階段を駆け降りて、地下に進んだ。
☆ ★ ☆ ★ ☆
「世界の限界は己の限界! 己の限界は思い込みの限界! 思い込みは変えられる!」
講師・松原が太い首からトロンボーンのように気を吐き、地下の教室を震わせた。
「世界の限界は己の限界、己の限界は……」
松原の授業は、毎回このスローガンを全身全霊をもって復唱させられるところから始まる。が、別にこれのせいで地下の教室を使わないといけないわけでもない。
「では今日もVMTに入ります。手元のゴーグルをかけなさい」
その頭の前面をすっぽり覆ってしまう仮面のような『ゴーグル』は全員の目の前に、アクリルのケースに入れられてあった。この部屋には机はなく、代わりにやわらかい仕切りがされたパーソナルスペースが並んでいる。
ランダムなタイムラグを経て動き出す塾生たち。健介もケースの小さな戸をあけてゴーグルを取り出し、身につける。
いったん真っ暗になった視界は光に透かした黒へと変わり、ついで『Now Calibrating...』の一文がぼんやりと浮かび上がってすぐ消える。それから、映画じみて現れるタイトル。VMT、の下に小さくVision modify training。
場面が変わる。殺風景な部屋の中、鏡が一枚立っている。中に映るのは健介自身だ。手足を動かせば予測通りの反応もする。
が、ふとその鏡の健介にぴょこんと耳が生えた。犬の耳だ。マズルもだ。手先も毛むくじゃらになる。背中が曲がって立っていられなくなるのを健介は感じる。
急速に浮上してきたパニックに耐えかね『ワン』と叫びかけたところで第二の変化がくる。今度は手足が消え、背骨がひょろ長く伸びて蛇になってしまった。それから魚に。コウモリに。やっと人間に戻れたと思ったら今度はろくろ首になり、足長手長になり、とどめは実体すらない幽霊にされた。
―――本当に獣なり妖怪なりになれてしまえばいいのに。一旦ゴーグルを取ることを許された健介の眼は、どこを向いているのだかよくわからない有様だった。
一番最初の授業で松原はこう語った。
異能とは自己に結びついたもの。第一段階としてVMTを用い、セルフイメージを追い詰めるのを通じて無意識が形づくる心のガードを解除する訓練を行う。それが済めば今度は異能そのものに手を触れ、粘土細工を作るようにこねまわすことができるようになる。どちらも長く険しい道のりになることを覚悟しておくように。それ相応の価値はある。先生は保証する……
休憩時間の間も、松原の鬼気迫るトークは続く。間もなくまた、ゴーグルをかけねばならぬ時がやってくる……
☆ ★ ☆ ★ ☆
大花塾は、昼間健介の教師も語っていた『異能開発学』を取り入れたカリキュラムを売りにしていた。
人々がそれぞれ異なる異能を持つイバラシティにおいて、大学受験は就職活動のような一面をはらむ。すなわち、筆記試験で高得点を取るのも重要だが、それと同じくらい自らの個性―――異能を『もの』にしていることが大切だった。いかに成績が良くとも、例えば心理学者を育てる学部にトラックをも持ち上げる怪力の異能者が乗り込もうとすれば筋違いというものだった。自分を知り、自分が求められる場所を探し、そこへ全力でアピールをかけていくことが、この街で明るい将来を掴むための条件なのだ。
けれどもその求められる場所と一致するとは限らないのが、個々人の希望だ―――そしてその希望は、必ずしも本人のものではなかったりもする。
健介のケースもまた、そのひとつだった。
彼の父親と母親は共に医学部に入学し、同じ病院に就職して職場結婚を果たす。二人そろって患者の治療に役立つ異能を持ち、周囲からは名コンビともてはやされた。
二人の華々しい今の根っこにあるものについては健介もよく知っている。気がつけば生えていたしかしながら強固極まりない志、苦境の中でも諦めることを許さなかった両親に応えての必死の努力、志望校A判定を勝ち取った直後に無理がたたってか胃潰瘍を患い入院しD判定にまで落ち込むも自分のためにここで負けてはならぬと奮起し直前模試B判定からの逆転合格、もちろん医学部に入った後も医師になってからも苦労の連続だったが二人互いを信じあって乗り越え云々……ああそこまで言うならいっそ自伝なり自己啓発本なり書いて一儲けすればいいのだ俺など不要になるくらいに、なにせこんなご立派なお二人の間に産まれてきた俺の異能は極めてくだらないんだから―――描かれた絵を具現化する。ただしそいつらは何の役にも立たない。一度紙に描いた餅を本物にして口に放り込んでみたが味わえたのはヤギになった気分だけだった。そういやVMTではヤギにされたこともあったっけ……
だが、そんな健介も両親からしてみれば大切な一人息子であり、自分たちの輝きを引き継ぐべき者だった。成績をトップにすべく、健介の異能を『成長』させるべく、大花塾には小学校から世話になっている。
メンタルの調子が比較的いいときにふと―――もしかあの両親に反論できるチャンスもあるんじゃないかと思い至って、異能開発学に懐疑的な学者の本を立ち読みしたことがある。彼曰く、異能開発学の考え方を適用するには『異能の潜在能力の総量』が足りなすぎるかもしれない、とのことだった。
それは裏を返せば、異能の潜在能力とやらが高い者になら、異能開発学は祝福をもたらしてくれるということなのだろうか。異能の潜在能力とは何か。マンガの主人公みたいにピンチになった途端ものすごい力を発生させられれば潜在能力が高いといえるのか。基準は定義されず、ゆえにこれからどうすればいいのかもわからない。
今後会うこともないだろう著者に問いかけながら本を読むうち、健介には思えてきた―――あの両親が自分たちを省みることなんてあるだろうか。立派でいられるのは信じているものがあるからで、万が一それをへし折ってやれたとして、今度は二度と立ち直らなくなってしまったりするんじゃないか。そうなったら多分、俺も共倒れになるんだろう。
彼らに黙ってほしいのはただしんどいからで、特に志があるわけじゃない。逃げ出した後に行くアテがないのでは逃げても意味がない。
いや、逃げるのにそもそもアテなんて関係ないだろう。何を棄ててもどれだけ堕ちてもここにいるのが嫌だから逃げるのだ。生きていくために。
逃げる気すら消えていく。
それは、つまり、どういうことだ。
要するに俺は、生きていたくないのか―――
☆ ★ ☆ ★ ☆
鬱々と自動ドアをくぐって外に出ると、空はもう真っ暗になっていた―――いや、光に透かした黒、か。そこかしこに灯る明かりが、闇であることを許さない。
健介は家路につこうと歩きだした。父親はいないだろう。母親はもしか帰ってきているかもしれないが。冷食はなにが残っていただろう。白飯とからあげにインスタントの味噌汁を足せばよいか……
―――ビィーッ!!
そこへ一台のバイクがクラクションを鳴らしながら突っ込んできた。健介は慌ててかわすが、勢いに振るわれた鞄から―――授業からの帰りがけ、うっかり口を開けっぱなしにしてしまっていた―――家の鍵が飛び出し、どこかに落ちた。ああ、確かに鍵だ。今鞄に入ってる中でチャリンと音を立てられるのは鍵だけだ。
健介は映像の記憶と己が音源定位能力から鍵の飛んだ軌道を予測すると、かがみ込んで探した。案の定、予想したところに鍵はなくて、そこから先はがむしゃらとなる。人々は目もくれないが、通行のじゃまになっているような気がしてならず、健介は焦った。
が、ふと、視界の隅で何かが光るのを見た。
健介の探していた鍵が、大花塾とその隣のビルの狭間のスペースに落ちていた……とわかるやいなや、狭間に引きずり込まれていく。
健介は追って隙間に飛び込んだ。なにか動物に拾われたのか。夜だしカラスじゃあるまい、ネズミかなにかか。
踏み込み、手をのばす―――
―――そこに地面はなかった。
健介の顔面は九十度傾き、打ち付けられるかと思いきや、そのまま大地を貫通した。
その先は、ただ闇だった。
重力は感じる。どこかへ落ちている。
……どこへ?
健介は、虫のような生き物が、探していた鍵を抱えて舞い飛んでいるのを見た。




特に何もしませんでした。




武器LV を 5 UP!(LV70⇒75、-5CP)
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



特に移動せずその場に留まることにしました。
体調が全回復しました!





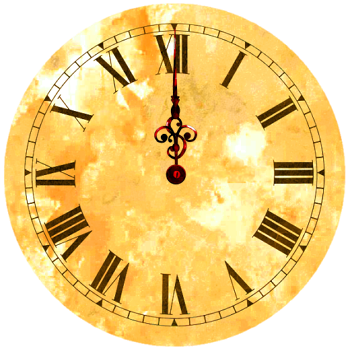
[843 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[396 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[440 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[138 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
[272 / 500] ―― 《大通り》より堅固な戦型
[125 / 500] ―― 《商店街》より安定な戦型
[125 / 500] ―― 《鰻屋》より俊敏な戦型
[24 / 500] ―― 《古寺》戦型不利の緩和
―― Cross+Roseに映し出される。




ロストのふたりがチャットに入り込んできた。
軽蔑の眼差しを向けるエディアン。
ミヨチンを制止する。
フレディオの胸倉をつかみ強く睨みつける!
――ザザッ
チャットが閉じられる――


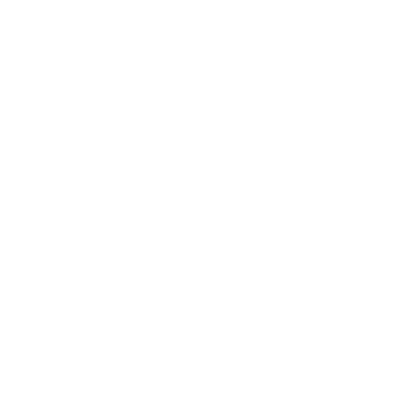
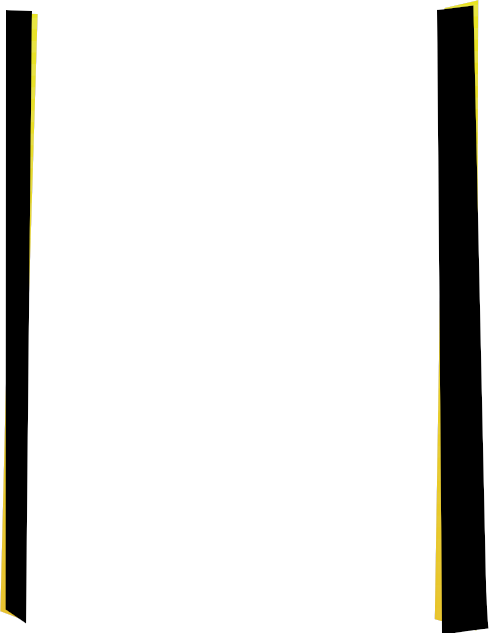
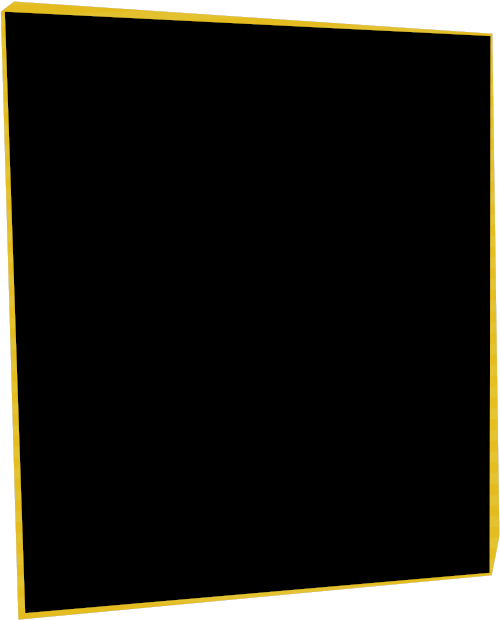





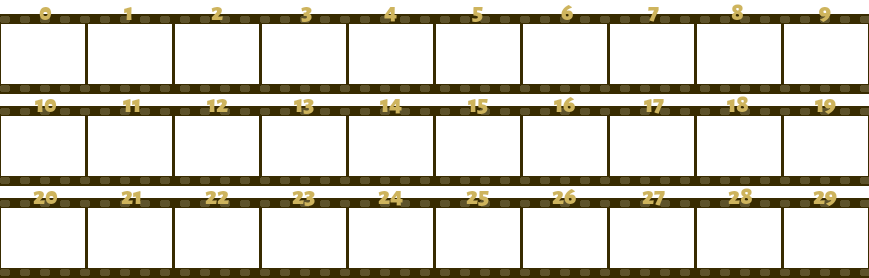







































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [スキル]OK.



イバラシティ北西、マガサ区の南半分。
大通りでいくつかに区切られたこの一帯は、朝から夕方まで同じくらいに騒がしい。午前八時ごろになれば通りの内側に密集した家々から学生やら社会人やらが飛び出して、マガサ駅へと駆けこみ、美しい海を拝みながら満員電車に揉まれていく。
もちろん駅に行くまでもない者も多い。健介少年もその一人だった。眠たいまぶたをこすり、中肉中背の体を重たく感じながら―――夜ふかしをしたわけでもないのに―――リュウジン区にある高校へ走っていく。
赤信号数秒前の横断歩道を突破し、長い坂道を駆け下り駆け下り……盛大にすっ転んで膝をすりむく。学校についてから水と石鹸できれいにしなくては。大っぴらに治癒の異能を使ってくれるやつなんてうちのクラスにはいやしない……よしんばいても頼る気になれない。
なんとか遅刻は免れて座席につく。ここの机は七行六列で、健介の席は教壇手前から三番目、窓際から四列目に位置する。一時間目の授業が始まった。
異能の基礎理論に関するお話だった。
「まずはね、近代になって確立されたね、異能の十五区分ですね」
教師はのんきな声と共に、黒板にカツカツとチョークで書いていく。武術、魔術、命術、時空、自然、幻術、呪術、制約、具現、使役、変化、共鳴、百薬、領域、解析―――健介はまどろっこしかった。今年で七十二になる健介の祖父が言うにはこれが全部書けただけで一目置かれたものだそうだが、今日日幼稚園児にだってこのくらい諳んじてみせるやつはいる。
「みなさんも近くどれかの分類を受けるかと思います……私はみなさんくらいの年頃にはもう受けてましたがね。というのも私が大学を出て少ししたくらいの頃から、異能開発学という考え方が主流になってきたのですね。我々が持つ異能はずっと先天的に―――要は生まれた時点で全く決まってしまっていて一生ありのまま受け入れて生きてかなきゃならんものだって思われていたのです。ですが、生まれた後からでも訓練や学習次第で変えていけるんではないかとわかったのですね」
この提唱に希望をみた人は少なくないだろうと想像はできる―――マイナス二十六.七五等星の閃光が頭上の分厚い雲に風穴を開けつつ自分を撃ち抜いていくような、強烈な希望を。
けど、これも健介からすればロクでもない話であった。
後の授業はもう聞きもしない。健介はこの場には必要ない本を取り出し、教科書に重ねて開く。その表紙には『大花塾 特別強化ドリル』とあった。
☆ ★ ☆ ★ ☆
『イバラシティNo.1 完全保証 進学から就職まで 未来花咲く大花塾』
そう書かれたのぼりが倒れ、建物の中に入ろうとする健介の行く手を阻んでいた。軽く踏んづけそうになり、小さくジャンプして跳び越す。
講師の一人の顔が健介の頭に浮かぶ。この塾の講師であるという事実、それと真面目さと一途さとを拠り所にして生きている人だ。尊敬しているわけでもないけれど、それでものぼりを踏んづけた足で会いに行くのは少々怖かった―――今日は彼の授業を受ける日だ。
自動ドアをくぐって入り、階段の前にある駅の改札みたいなゲートに塾生証を通して教室の並ぶフロアへ進む。この塾はイバラシティでも一、二を争うほどの巨大さで、すれ違う連中も同い年だったり年下だったり年上だったりする。ここは中学から大学受験はおろかその先までもサポートしているのだ……でなきゃ今どきあんな自信過剰なのぼりは立てておけまいと健介は思う。
健介は廊下の端の階段を駆け降りて、地下に進んだ。
☆ ★ ☆ ★ ☆
「世界の限界は己の限界! 己の限界は思い込みの限界! 思い込みは変えられる!」
講師・松原が太い首からトロンボーンのように気を吐き、地下の教室を震わせた。
「世界の限界は己の限界、己の限界は……」
松原の授業は、毎回このスローガンを全身全霊をもって復唱させられるところから始まる。が、別にこれのせいで地下の教室を使わないといけないわけでもない。
「では今日もVMTに入ります。手元のゴーグルをかけなさい」
その頭の前面をすっぽり覆ってしまう仮面のような『ゴーグル』は全員の目の前に、アクリルのケースに入れられてあった。この部屋には机はなく、代わりにやわらかい仕切りがされたパーソナルスペースが並んでいる。
ランダムなタイムラグを経て動き出す塾生たち。健介もケースの小さな戸をあけてゴーグルを取り出し、身につける。
いったん真っ暗になった視界は光に透かした黒へと変わり、ついで『Now Calibrating...』の一文がぼんやりと浮かび上がってすぐ消える。それから、映画じみて現れるタイトル。VMT、の下に小さくVision modify training。
場面が変わる。殺風景な部屋の中、鏡が一枚立っている。中に映るのは健介自身だ。手足を動かせば予測通りの反応もする。
が、ふとその鏡の健介にぴょこんと耳が生えた。犬の耳だ。マズルもだ。手先も毛むくじゃらになる。背中が曲がって立っていられなくなるのを健介は感じる。
急速に浮上してきたパニックに耐えかね『ワン』と叫びかけたところで第二の変化がくる。今度は手足が消え、背骨がひょろ長く伸びて蛇になってしまった。それから魚に。コウモリに。やっと人間に戻れたと思ったら今度はろくろ首になり、足長手長になり、とどめは実体すらない幽霊にされた。
―――本当に獣なり妖怪なりになれてしまえばいいのに。一旦ゴーグルを取ることを許された健介の眼は、どこを向いているのだかよくわからない有様だった。
一番最初の授業で松原はこう語った。
異能とは自己に結びついたもの。第一段階としてVMTを用い、セルフイメージを追い詰めるのを通じて無意識が形づくる心のガードを解除する訓練を行う。それが済めば今度は異能そのものに手を触れ、粘土細工を作るようにこねまわすことができるようになる。どちらも長く険しい道のりになることを覚悟しておくように。それ相応の価値はある。先生は保証する……
休憩時間の間も、松原の鬼気迫るトークは続く。間もなくまた、ゴーグルをかけねばならぬ時がやってくる……
☆ ★ ☆ ★ ☆
大花塾は、昼間健介の教師も語っていた『異能開発学』を取り入れたカリキュラムを売りにしていた。
人々がそれぞれ異なる異能を持つイバラシティにおいて、大学受験は就職活動のような一面をはらむ。すなわち、筆記試験で高得点を取るのも重要だが、それと同じくらい自らの個性―――異能を『もの』にしていることが大切だった。いかに成績が良くとも、例えば心理学者を育てる学部にトラックをも持ち上げる怪力の異能者が乗り込もうとすれば筋違いというものだった。自分を知り、自分が求められる場所を探し、そこへ全力でアピールをかけていくことが、この街で明るい将来を掴むための条件なのだ。
けれどもその求められる場所と一致するとは限らないのが、個々人の希望だ―――そしてその希望は、必ずしも本人のものではなかったりもする。
健介のケースもまた、そのひとつだった。
彼の父親と母親は共に医学部に入学し、同じ病院に就職して職場結婚を果たす。二人そろって患者の治療に役立つ異能を持ち、周囲からは名コンビともてはやされた。
二人の華々しい今の根っこにあるものについては健介もよく知っている。気がつけば生えていたしかしながら強固極まりない志、苦境の中でも諦めることを許さなかった両親に応えての必死の努力、志望校A判定を勝ち取った直後に無理がたたってか胃潰瘍を患い入院しD判定にまで落ち込むも自分のためにここで負けてはならぬと奮起し直前模試B判定からの逆転合格、もちろん医学部に入った後も医師になってからも苦労の連続だったが二人互いを信じあって乗り越え云々……ああそこまで言うならいっそ自伝なり自己啓発本なり書いて一儲けすればいいのだ俺など不要になるくらいに、なにせこんなご立派なお二人の間に産まれてきた俺の異能は極めてくだらないんだから―――描かれた絵を具現化する。ただしそいつらは何の役にも立たない。一度紙に描いた餅を本物にして口に放り込んでみたが味わえたのはヤギになった気分だけだった。そういやVMTではヤギにされたこともあったっけ……
だが、そんな健介も両親からしてみれば大切な一人息子であり、自分たちの輝きを引き継ぐべき者だった。成績をトップにすべく、健介の異能を『成長』させるべく、大花塾には小学校から世話になっている。
メンタルの調子が比較的いいときにふと―――もしかあの両親に反論できるチャンスもあるんじゃないかと思い至って、異能開発学に懐疑的な学者の本を立ち読みしたことがある。彼曰く、異能開発学の考え方を適用するには『異能の潜在能力の総量』が足りなすぎるかもしれない、とのことだった。
それは裏を返せば、異能の潜在能力とやらが高い者になら、異能開発学は祝福をもたらしてくれるということなのだろうか。異能の潜在能力とは何か。マンガの主人公みたいにピンチになった途端ものすごい力を発生させられれば潜在能力が高いといえるのか。基準は定義されず、ゆえにこれからどうすればいいのかもわからない。
今後会うこともないだろう著者に問いかけながら本を読むうち、健介には思えてきた―――あの両親が自分たちを省みることなんてあるだろうか。立派でいられるのは信じているものがあるからで、万が一それをへし折ってやれたとして、今度は二度と立ち直らなくなってしまったりするんじゃないか。そうなったら多分、俺も共倒れになるんだろう。
彼らに黙ってほしいのはただしんどいからで、特に志があるわけじゃない。逃げ出した後に行くアテがないのでは逃げても意味がない。
いや、逃げるのにそもそもアテなんて関係ないだろう。何を棄ててもどれだけ堕ちてもここにいるのが嫌だから逃げるのだ。生きていくために。
逃げる気すら消えていく。
それは、つまり、どういうことだ。
要するに俺は、生きていたくないのか―――
☆ ★ ☆ ★ ☆
鬱々と自動ドアをくぐって外に出ると、空はもう真っ暗になっていた―――いや、光に透かした黒、か。そこかしこに灯る明かりが、闇であることを許さない。
健介は家路につこうと歩きだした。父親はいないだろう。母親はもしか帰ってきているかもしれないが。冷食はなにが残っていただろう。白飯とからあげにインスタントの味噌汁を足せばよいか……
―――ビィーッ!!
そこへ一台のバイクがクラクションを鳴らしながら突っ込んできた。健介は慌ててかわすが、勢いに振るわれた鞄から―――授業からの帰りがけ、うっかり口を開けっぱなしにしてしまっていた―――家の鍵が飛び出し、どこかに落ちた。ああ、確かに鍵だ。今鞄に入ってる中でチャリンと音を立てられるのは鍵だけだ。
健介は映像の記憶と己が音源定位能力から鍵の飛んだ軌道を予測すると、かがみ込んで探した。案の定、予想したところに鍵はなくて、そこから先はがむしゃらとなる。人々は目もくれないが、通行のじゃまになっているような気がしてならず、健介は焦った。
が、ふと、視界の隅で何かが光るのを見た。
健介の探していた鍵が、大花塾とその隣のビルの狭間のスペースに落ちていた……とわかるやいなや、狭間に引きずり込まれていく。
健介は追って隙間に飛び込んだ。なにか動物に拾われたのか。夜だしカラスじゃあるまい、ネズミかなにかか。
踏み込み、手をのばす―――
―――そこに地面はなかった。
健介の顔面は九十度傾き、打ち付けられるかと思いきや、そのまま大地を貫通した。
その先は、ただ闇だった。
重力は感じる。どこかへ落ちている。
……どこへ?
健介は、虫のような生き物が、探していた鍵を抱えて舞い飛んでいるのを見た。




特に何もしませんでした。



武器LV を 5 UP!(LV70⇒75、-5CP)
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



特に移動せずその場に留まることにしました。
体調が全回復しました!





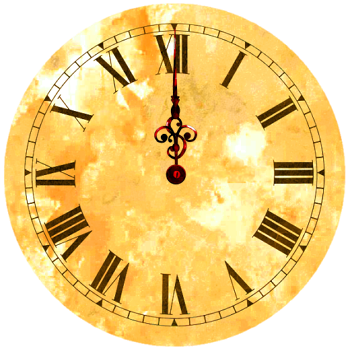
[843 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命
[396 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙
[440 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型
[138 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型
[272 / 500] ―― 《大通り》より堅固な戦型
[125 / 500] ―― 《商店街》より安定な戦型
[125 / 500] ―― 《鰻屋》より俊敏な戦型
[24 / 500] ―― 《古寺》戦型不利の緩和
―― Cross+Roseに映し出される。

フレディオ
碧眼、ロマンスグレーの短髪。
彫りが深く、男前な老翁。
黒のライダースジャケットを身に着けている。
彫りが深く、男前な老翁。
黒のライダースジャケットを身に着けている。

ミヨチン
茶色の瞳、桜色のロング巻き髪。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
 |
フレディオ 「いよぉ!なるほどこう入んのか、ようやく使えそうだぜ。」 |
 |
ミヨチン 「にゃー!遊びに来たっすよぉ!!」 |
 |
エディアン 「にゃー!いらっしゃいませー!!」 |
 |
白南海 「毎度毎度うっせぇなぁ・・・いやこれ俺絶対この役向いてねぇわ。」 |
ロストのふたりがチャットに入り込んできた。
 |
ミヨチン 「・・・・・?おっさん誰?」 |
 |
フレディオ 「フレディオにゃー。ピッチピチ小娘も大好きにゃん!」 |
 |
ミヨチン 「・・・・・」 |
 |
エディアン 「・・・・・」 |
 |
フレディオ 「・・・いやジョークだろジョーク、そんな反応すんなっつーの。」 |
 |
ミヨチン 「大好きなのは嬉しーけど、そのナリでにゃんは痛いっすよぉ! なんすかそれ口癖っすかぁ??まじウケるんですけど。」 |
 |
フレディオ 「え、あぁそっち?・・・ジョークだジョーク。」 |
 |
エディアン 「私はそっちじゃないほうですね。顔がいいだけに残念です。」 |
軽蔑の眼差しを向けるエディアン。
 |
白南海 「・・・別にいいだろーよ。若い女が好きな男なんてむしろ普通だ普通。」 |
 |
フレディオ 「おうおうそうだそうだ!話の分かる兄ちゃんがいて助かるわッ」 |
 |
フレディオ 「・・・っつーわけで、みんなで初めましてのハグしようや!!!!」 |
 |
ミヨチン 「ハグハグー!!」 |
 |
エディアン 「ダメダメやめなさいミヨちゃん、確実にろくでもないおっさんですよあれ。」 |
ミヨチンを制止する。
 |
フレディオ 「・・・ハグしたがってる者を止める権利がお前にはあるのか?」 |
 |
エディアン 「真面目な顔して何言ってんですかフレディオさ・・・・・フレディオ。おい。」 |
 |
白南海 「お堅いねぇ。ハグぐらいしてやりゃえぇでしょうに。」 |
 |
フレディオ 「そうだそうだ!枯れたおっさんのちょっとした願望・・・・・」 |
 |
フレディオ 「・・・・・願望!?そうかその手が!!!!」 |
 |
エディアン 「ゼッッッッタイにやめてください。」 |
フレディオの胸倉をつかみ強く睨みつける!
 |
白南海 「そういえば聞きたかったんすけど、あんたらロストって一体どういう存在――」 |
――ザザッ
チャットが閉じられる――

ENo.3
宮田一穂とK.M.
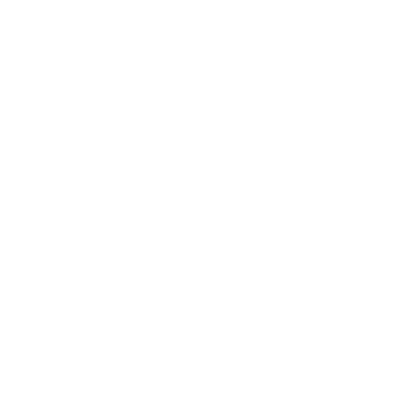
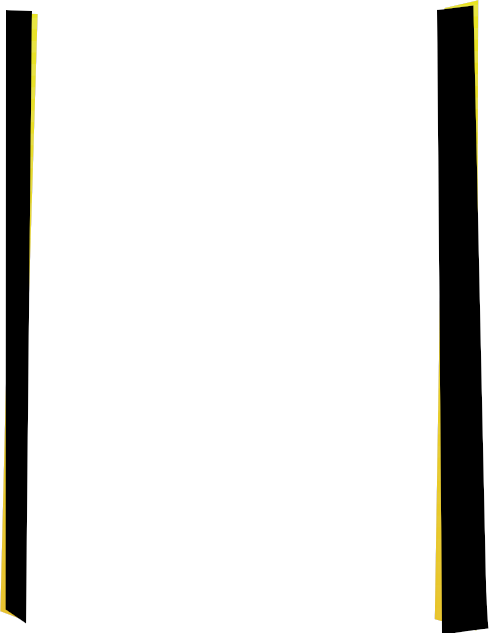
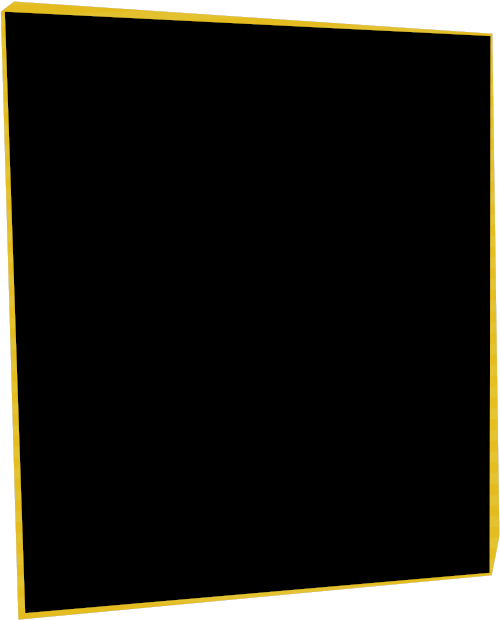
《宮田一穂(みやたかずほ)》
『すべてはいつの日か記号に還元されるでしょう』
・種族: 地球人(モンゴロイド)
・年齢:14歳/身長: 164cm/体重: 42kg/誕生日:10月3日
・特技:記憶すること/趣味:持たない/好物:特にない
イバラシティの片隅で路上生活を続ける少年。
言葉に抑揚が薄く、感情もほとんど示さない。ロボットのような印象を与えがちだが、優しさを見せないこともない。
赤いジャケットとニット帽を常に着用している。
その異能は『記憶』の異能。
自らの記憶を物体に焼き付けることができ、それを触れたものに記憶を『伝染』させ、自らのことのように感じさせる。代償として、焼き付けた記憶は本人の中から失われてしまう。また、記憶を焼きつけた物体は一度『伝染』させると効力を失い、再利用はできない。
異能とは別にほぼ完璧な記憶力を持ち、先述の異能の代償やなにか異常なものの影響にさらされた場合をのぞいて物事を忘れるということがない。
武器として拳銃を一丁所持している。相当に使い慣れている模様。
どこか異なる場所から来たようで、帰り方を探している。
※遭遇したものに対しメモを取る場合がございます。もし、問題がございましたら、ご一報頂ければ削除いたします。
⇒http://lisge.com/ib/talk.php?p=1821
《K.M.(クリストファ・マルムクヴィスト)》
ジャケットが青いのを除けば一穂とうりふたつの姿を持つ少年。
一穂と異なり、かなり殺傷力の強い異能を持っているようだ。また感情も普通に見せる。
PL: 切り株(@BehindForestBoy)
『すべてはいつの日か記号に還元されるでしょう』
・種族: 地球人(モンゴロイド)
・年齢:14歳/身長: 164cm/体重: 42kg/誕生日:10月3日
・特技:記憶すること/趣味:持たない/好物:特にない
イバラシティの片隅で路上生活を続ける少年。
言葉に抑揚が薄く、感情もほとんど示さない。ロボットのような印象を与えがちだが、優しさを見せないこともない。
赤いジャケットとニット帽を常に着用している。
その異能は『記憶』の異能。
自らの記憶を物体に焼き付けることができ、それを触れたものに記憶を『伝染』させ、自らのことのように感じさせる。代償として、焼き付けた記憶は本人の中から失われてしまう。また、記憶を焼きつけた物体は一度『伝染』させると効力を失い、再利用はできない。
異能とは別にほぼ完璧な記憶力を持ち、先述の異能の代償やなにか異常なものの影響にさらされた場合をのぞいて物事を忘れるということがない。
武器として拳銃を一丁所持している。相当に使い慣れている模様。
どこか異なる場所から来たようで、帰り方を探している。
※遭遇したものに対しメモを取る場合がございます。もし、問題がございましたら、ご一報頂ければ削除いたします。
⇒http://lisge.com/ib/talk.php?p=1821
《K.M.(クリストファ・マルムクヴィスト)》
ジャケットが青いのを除けば一穂とうりふたつの姿を持つ少年。
一穂と異なり、かなり殺傷力の強い異能を持っているようだ。また感情も普通に見せる。
PL: 切り株(@BehindForestBoy)
30 / 30
160 PS
チナミ区
D-2
D-2







































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | SRmkVI | 武器 | 20 | 攻撃10 | - | - | 【射程1】 |
| 5 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]防御10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) | |||
| 6 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 8 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
| 9 | SRmkVI-P | 武器 | 35 | 束縛10 | - | - | 【射程3】 |
| 10 | 甲殻 | 素材 | 15 | [武器]地纏10(LV20)[防具]防御10(LV15)[装飾]反射10(LV25) | |||
| 11 | 防刃ベスト | 防具 | 67 | 活力15 | - | - | |
| 12 | 吸い殻 | 素材 | 10 | [武器]炎上10(LV25)[防具]火纏10(LV25)[装飾]耐火10(LV20) | |||
| 13 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 25 | 身体/武器/物理 |
| 制約 | 25 | 拘束/罠/リスク |
| 響鳴 | 5 | 歌唱/音楽/振動 |
| 武器 | 75 | 武器作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 6 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 6 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 6 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 | |
| ティンダー | 5 | 0 | 50 | 敵:火撃&炎上 | |
| アサルト | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃+自:連続減 | |
| エチュード | 5 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) | |
| デアデビル | 5 | 0 | 60 | 自:HP減+敵傷4:痛撃 | |
| マーチ | 5 | 0 | 100 | 味全:AT増(4T) | |
| アリア | 5 | 2 | 0 | 自:SP・次与ダメ増 | |
| ファイアダンス | 5 | 0 | 80 | 敵:2連火領撃&炎上+領域値[火]3以上なら、火領撃&炎上 | |
| アラベスク | 5 | 0 | 50 | 味全:HP・AG増+魅了 | |
| チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 | |
| ファイアボルト | 5 | 0 | 100 | 敵貫:火痛撃 | |
| ペナルティ | 5 | 0 | 120 | 敵3:麻痺・混乱 | |
| スピアトラップ | 5 | 0 | 100 | 敵:罠《突刺》LV増 | |
| ボムトラップ | 5 | 0 | 110 | 敵:罠《爆弾》LV増 | |
| イレイザー | 5 | 0 | 100 | 敵傷:攻撃 | |
| ピットトラップ | 5 | 0 | 120 | 敵全:罠《奈落》LV増 | |
| ハードブレイク | 5 | 1 | 120 | 敵:攻撃 | |
| イグニス | 5 | 0 | 120 | 敵傷3:火領撃 | |
| デスペラート | 5 | 0 | 130 | 敵:報讐LV増+6連撃+報讐消滅 | |
| フィアスファング | 5 | 0 | 150 | 敵:攻撃&MHP減 | |
| マイントラップ | 5 | 0 | 250 | 敵:罠《地雷》LV増 | |
| インファイト | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&隊列1なら更に4連撃 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 火の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:魔術LVが高いほど火特性・耐性増 | |
| 阿修羅 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HP減+AT・DX・LK増 | |
| 高速配置 | 5 | 4 | 0 | 【スキル使用後】自:直前に使用したスキル名に「トラップ」が含まれるなら、連続増 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
ダメージアブソーバー (ヒール) |
0 | 50 | 味傷:HP増 | |
|
雷鳥は頂きを目指す (インヴァージョン) |
0 | 150 | 敵全:攻撃&祝福を猛毒化 | |
|
猟犬の一撃 (イグニス) |
0 | 120 | 敵傷3:火領撃 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]ティンダー | [ 2 ]ミラージュ | [ 1 ]ファイアダンス |
| [ 1 ]ファイアレイド | [ 3 ]インパクト | [ 1 ]イレイザー |
| [ 3 ]ハードブレイク |

PL / 切り株