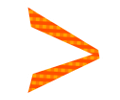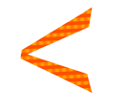<< 2:00~3:00




白と黒のチェック柄の部屋の中。
少年は一人何をするでもなく、ただ息を吸って吐いて。
目の前の壁の模様を見続けている。
その模様には何もない、変わらないままそこにある。
でも、彼にとってはそれでもよかった……否、どうでもよかった。
彼の意思が尊重されることも、彼の生が保証されることも。
支給される衣服に着替え、支給される食事をとり、支給された寝床に転がる。
そんな日々。
ある日、金属質な音が部屋に響く。
それはこの部屋にある唯一のドアが開いた音。
だが、少年は顔を向けることもせず、だからこそ。
「君は、どうしたの?」
部屋に少女が入ってきたことにも。
その少女が自分と同じくらいの年頃の少女であることにも。
声を掛けられるまで気が付くことはなかった。
「……」
話しかけられた少年はそれに対する答えを持っていなかった。
この世界(部屋)に自分一人だけで、それ以外が来るときは大抵敵で、生きるために撃退をするしかなかった。
自分一人だけだったからこそ、全てを諦めていた。
だがそこに他の人が入って来た、少年はどうすればいいのかがわかっていない。
他人を相手に自分の行動を決めることがこの数年でできなくなっていた。
「喋れないの?」
少女はなおも問いかける。
肩くらいまでに伸ばした黒髪が少年の顔をのぞき込もうとした時に揺れ、少年はそれをつい目で追いかける。
そして、少女の問いの意味を解読しようとして、結局答えを返せない。
声の出し方を思い出せなかったから。
「んー、じゃぁ、首を縦に振ったらはい、横に振ったらいいえで、いい?」
少女の言葉が追加される。
少年はどうにかその言葉を理解することができた。
だから首を縦に振る。
「言葉は聞こえてるんだね。なら、これからよろしく!」
少年は少女の言葉が理解できなかった。
「これからしばらく、この部屋で一緒に暮らす様にっていわれたんだ」
少年は言葉を理解できなかった。
「私の両親が病気で、その治療費を払う代わりに私がここにいるってわけ」
続けられた言葉でようやく理解する。
自分は売られたが、目の前の少女は自分を売ったのだと。
「私の名前は、三奈。これからよろしく、ね」
微笑んだ少女の瞳は奇麗なように見えて。
少年は少女の言葉に首を縦に振った。
そうして少年と少女が同じ部屋にいることになった。
それでも、少年が言葉を口にすることが無い以上、この部屋で生まれるのは少女から少年に対する一方的なものとなっていた。
■ 時は進む ■
「ねぇ、どうして壁を見つめてるの? 意味があるの?」
首を横に振る。
「……楽しい?」
首を横に振る。
「つまらない?」
首を横に振る。
「……どうして、君はここにいるの? 何でここにいるかわかってるの?」
首を縦に振ってから、言葉を発しようと口を開いた。
「あ……げほっ、ごほっ……」
が、少年の口から洩れた音はすぐさませき込んだそれに代わり、背を丸めて少年はせき込み続けた。
「だ、大丈夫!? ごめん、しゃべろうと、しないで、無理はしちゃだめだよ」
少女は少年の背中をさする。
しばらくすれば少年の様子は落ち着いたが、少女は申し訳なさそうな顔をして少年に謝る。
少年は言われたことの意味を考えたが、理解はできなかった。
■ 時は進む ■
「う……仕方ないけど私しか話してない」
少女の恨めし気な声が響く。
対象となった少年は顔を少女に向ける、そして口を開こうとするが。
「仕方がないって言ってるから! 君は無理しちゃダメ!」
慌てて少女が少年の口を押さえにかかる。
もごもごと口を動かしていた少年だが、口の動きを止めた。
「ちょっとずつ、一音ずつ声を出せるようになっていけばいいなあ」
少女の言葉に口を押えられたままの少年は首を傾げる。
何故、自分が声を出せることを少女は望んでいるのだろうか。
「む、今なんで? って思ったね? だってさ、今私がここにいて、君がここにいるんだよ」
少年は頷く。
ここに自分がいて、目の前の少女がいることは理解できている。
「この世界には人がいっぱいいて、人が生きてるうちに出会える人なんてわずかしかいないんだよ? そのわずかに入るってのすごいって思うんだ」
少年は首を傾げる。
言ってることは、理解はできた。
だが、すごい、という言葉はわからなかった。
「ほら! 何分の一ってやつ! それに入った人と話さないって何かほら、もったいないじゃん!」
少年は首を傾げる。
考えてもやはり、少女の言う言葉はわからなかった。
「人の出会いと別れはね、きっと貴重なんだよ。その機会を生かすには話すしかない! 私はそう思ってるんだ!」
元気な少女の声に、少年は首を傾げるばかりだった。
だが少女は、そんな少年にただ、微笑んでいた。
■ 時は進む ■
「思ったけど、この部屋寒くない?」
少年は首を横に振る。
「む、嘘だー! って、君の手暖かい!?」
少女が少年の手を握る。
それに頬を擦りつけるなどしているが少年はそれに動じない。
「あー……昨日寒くて眠れなかったからなんか眠い……」
少女はそう言って少年の手を掴んだまま寝てしまう。
少年は床に胡坐をかいている状態で、少女は少年の足の上に頭をのせている。
少年は、この部屋にある寝床に少女を運ばねばと、考えてしまった。
そして考えた自分に対してなぜかと疑問を持った。
しばし考えた後にわからなかったので結局少女を寝床に運んだ。
だが、少女は少年の手を離さなかった。
「……お父さん、お母さん」
少女の寝言が聞こえた。
少年は、少女を寝床に寝かせると自分もまた傍らにいた。
少年は自分が何故そうしたのかがわからなかった。
■ 日々は進む ■
■ 少女は少年へと語り続け ■
■ 少年はそれに答え続け ■
■ 少女は素直に応えてくれる少年を好ましく思い ■
■ 少年は自分を害さず、笑いかける少女を新鮮に思った ■
■ 少女が話しかける時間が増え ■
■ 少年が壁を見続ける時間が減っていった ■
■ 時は進む ■
「むう、まだ声は出ないかー」
少年は頷く、どこか申し訳なさそうに。
「気にしないで。君は素直だし、すぐにこっちの言葉に反応してくれるからね、私も嬉しかったりするし」
「無視絶対にしないもんね。最初からだったけど」
そうだっただろうか、と少年は首を傾げた。
「でも最初に比べて首を傾げる回数は減ったよね! うん、良かった!」
それは少女が少年に話しかけ続けて、言葉の意味などを教えてくれたからだった。
「私はそろそろここを出るけれども」
時間間隔が狂いそうだったが、それなりの時間を共に過ごした気がする。
その間獣と戦わされることもなかったのは、これが実験の一種だから、他の要素を入れたくなかったのだろうか、と少年は考えた。
「……君は、元気でね」
■ 時は進む ■
「私がここから出てさ。君もここから出れたら、海を見せたいなー! でっかくて青くて奇麗なんだよ」
少女が笑いながら口にする言葉に少年は首を傾げる。
海がどういうものか、知ってはいる。
だが、見たことはなかった。
「波がきて、波打ち際の線が揺れて。まるで空の色を映しているような青でね」
少女が語る内容を少年は想像ができず、ますます少年は首を傾げる。
「むう、まあいいや! ここから出たら連絡してよ、そしたら一緒に行こうよ。きっと楽しいと思うんだよ」
少年は少女の言葉で海の想像はできなかった。
ただ、この少女と共にこの部屋ではなく外に出れたのなら、それは楽しいことのように思えた。
それは少年が初めて抱いた望みだった。
「あー、でも君泳げるのかなぁ。泳げなかったら浮き輪借りないとだよね。ああ、海の家で焼きそばとか……」
言葉が途切れた理由を少年はその目で見ていた。
少女の腕から、少年が聞きなれている音が響いて、少女の右腕が狼の腕の様なものになっていた。
「…………あはは」
少女の笑い声に少年は顔を向ける。
「本当はね、気が付いていたんだ。私がここから出れないだろうって」
「だってさ、君の扱いを見たらわかるよ。絶対に外に漏らせないことがここで起こってるって」
「だから、覚悟してたんだ」
「怖かった、とっても。うん、とっても怖かった」
「でもね、君がいてくれたから。一人じゃないから」
「そんな怖さを、紛らわすことができたんだ」
訥々と語られる少女の言葉を少年は受け止め、口を開こうとする。
少女の体から肉が、骨が変質する音が響く。
「駄目だよ、無理しちゃ。ああ、でも、離れててほしいな」
「なんかね、私。駄目なんだ。目の前にある君を、殺さなきゃって、そう思っちゃってる。思いたくないけど、そう思っちゃってる」
乾いた笑いを少女は漏らした。
少年は何も、できなかった。
少年は思い返していた。
そう、いつだって『この世界(部屋)に自分一人だけで、それ以外が来るときは大抵敵で、生きるために撃退をするしかない』のだと。
「あーあ、君と一緒に外に出るの、楽しみだったんだけどな」
「君は知らないものが多くてさ、きっと私にいろいろ聞いてくれるんだろうなって」
「君もさ、だんだんと話せるようになって言って、私一人がこうして話すんじゃなくて、君も答えてくれるようになって」
「会話して、美味しいもの食べたりして」
「……でも無理だから」
「せめて君だけは、ちゃんと外に出て。そして、今まで私が話したこととか。覚えててくれたら嬉しいな」
少女は口を噤んだ。
堪える様な、泣きそうな、笑い顔を浮かべて。
「……あはは、苦しいや」
少年は、静かにその腕を、鋭い爪を持つ狼の腕に変えた。
「……君、苦しそうな顔を、しないでよ」
少年はそれを、自分が生きるためではなく、相手を殺すために向けた。
「自分の最期は、ずっと前から決めてた」
「だからね、君に殺されるわけにはいかないんだよ」
少女はそれを、自分が生きるためではなく、相手を生かすために向けた。
「―― 」
少女の異形の腕が、少女の体を穿った。
「―― 君に きず つける わけには いかない から」
少年は思わず少女に駆け寄る。
少女の体から流れる血を止める術もなく。
「あ は 。私 君に あげられたか な」
少女は、笑う。その体が血に塗れても。
少女は自分の死がわかっていたからこそ、此処までの日々で様々なものを少年に与えられればと。
少年が『人』で在れる要素を渡せればと。
そう思い、話しかけ続けていた。
「―― み …… な ……」
そして、それは一つの結果に帰結する。
言葉を発せなかった少年が、口にした少女の名前。
少女は、微笑み。
「私 の 名前 呼んで く」
そのまま、もう動くことは、なかった。
その同日、2/14に少年は救出されることになった。
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
■2/14 早朝■ イバラシティ 2年後
ある霊園に一人の少年が佇んでいた。
袖口から肩にかけてファスナーがある特徴的なそれを着た少年は、傍らの水桶に柄杓を入れると目の前の墓石を見つめる。
「……一緒に外を見ることが叶わなかったからと言って、名前を共に連れて行こうなどとは、二年前の俺は何を考えていたんだろうな」
過去に『3番』と呼ばれていた少年は、空を見上げた。
「いや、それが感傷。つまるところ思い入れか、弱さか」
誰も聞かない独り言、風にそれが消えたころに、今は『三波』と名乗っている少年はその場を去った。
「三奈の心の強さには、まだ届かんな……」
そんな言葉を、残して。



ENo.614 ミキ とのやりとり

ENo.1226 アケミ とのやりとり

以下の相手に送信しました














武術LV を 10 DOWN。(LV15⇒5、+10CP、-10FP)
魔術LV を 15 UP!(LV0⇒15、-15CP)
付加LV を 5 UP!(LV30⇒35、-5CP)
コハル(1440) の持つ ItemNo.4 水色の栞 に ItemNo.10 毛 を付加しました!
音々子(1191) とカードを交換しました!
アロマのうた (ハーバルメディスン)

エファヴェセント を研究しました!(深度0⇒1)
エファヴェセント を研究しました!(深度1⇒2)
エファヴェセント を研究しました!(深度2⇒3)
ティンダー を習得!
レッドショック を習得!
コントラスト を習得!
ファイアボルト を習得!
ヒートイミッター を習得!
火の祝福 を習得!
マナバースト を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



アリエス(1037) は 吸い殻 を入手!
ショウスケ(1439) は ネジ を入手!
コハル(1440) は ネジ を入手!
三波(1443) は ド根性雑草 を入手!
アリエス(1037) は ボロ布 を入手!
ショウスケ(1439) は 不思議な石 を入手!
三波(1443) は 不思議な石 を入手!
ショウスケ(1439) は 花びら を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
アリエス(1037) のもとに 歩行軍手 が興味津々な様子で近づいてきます。
アリエス(1037) のもとに 歩行石壁 が興味津々な様子で近づいてきます。
アリエス(1037) のもとに ダンデライオン が興味津々な様子で近づいてきます。



チナミ区 I-15(沼地)に移動!(体調15⇒14)
チナミ区 I-16(道路)に移動!(体調14⇒13)
チナミ区 H-16(チェックポイント)に移動!(体調13⇒12)
チナミ区 D-2(ベースキャンプ)に戻りました!
体調が全回復しました!
『チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》』へ採集に向かうことにしました!
- ショウスケ(1439) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》
- コハル(1440) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》
MISSION!!
チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》 が発生!
- アリエス(1037) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- ショウスケ(1439) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- コハル(1440) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- 三波(1443) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》






―― ハザマ時間が紡がれる。


チャット画面にふたりの姿が映る。
チャットに響く声。

画面に現れる3人目。
上目遣いでふたりに迫る。
ノイズで一部が聞き取れない。
突然現れるドライバーさん。
賑やかな雰囲気のまま、チャットが閉じられる――












仄かな光に包まれた六角形の柱が立っている。
・・・柱から滲み出るように、何かが生み出される。

それは言葉を発すると共に襲いかかる!
(初発生のイベント戦:異能FP+5!生産FP+5!)














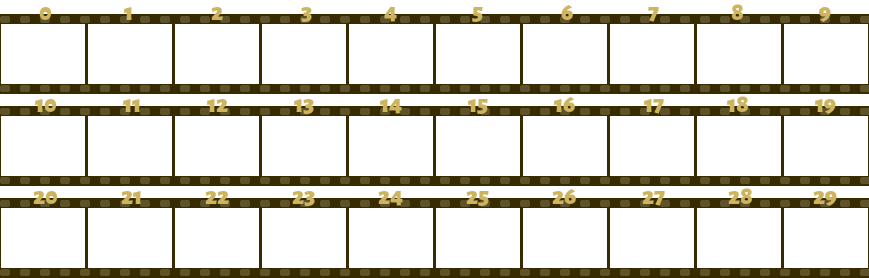







































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



白と黒のチェック柄の部屋の中。
少年は一人何をするでもなく、ただ息を吸って吐いて。
目の前の壁の模様を見続けている。
その模様には何もない、変わらないままそこにある。
でも、彼にとってはそれでもよかった……否、どうでもよかった。
彼の意思が尊重されることも、彼の生が保証されることも。
支給される衣服に着替え、支給される食事をとり、支給された寝床に転がる。
そんな日々。
ある日、金属質な音が部屋に響く。
それはこの部屋にある唯一のドアが開いた音。
だが、少年は顔を向けることもせず、だからこそ。
「君は、どうしたの?」
部屋に少女が入ってきたことにも。
その少女が自分と同じくらいの年頃の少女であることにも。
声を掛けられるまで気が付くことはなかった。
「……」
話しかけられた少年はそれに対する答えを持っていなかった。
この世界(部屋)に自分一人だけで、それ以外が来るときは大抵敵で、生きるために撃退をするしかなかった。
自分一人だけだったからこそ、全てを諦めていた。
だがそこに他の人が入って来た、少年はどうすればいいのかがわかっていない。
他人を相手に自分の行動を決めることがこの数年でできなくなっていた。
「喋れないの?」
少女はなおも問いかける。
肩くらいまでに伸ばした黒髪が少年の顔をのぞき込もうとした時に揺れ、少年はそれをつい目で追いかける。
そして、少女の問いの意味を解読しようとして、結局答えを返せない。
声の出し方を思い出せなかったから。
「んー、じゃぁ、首を縦に振ったらはい、横に振ったらいいえで、いい?」
少女の言葉が追加される。
少年はどうにかその言葉を理解することができた。
だから首を縦に振る。
「言葉は聞こえてるんだね。なら、これからよろしく!」
少年は少女の言葉が理解できなかった。
「これからしばらく、この部屋で一緒に暮らす様にっていわれたんだ」
少年は言葉を理解できなかった。
「私の両親が病気で、その治療費を払う代わりに私がここにいるってわけ」
続けられた言葉でようやく理解する。
自分は売られたが、目の前の少女は自分を売ったのだと。
「私の名前は、三奈。これからよろしく、ね」
微笑んだ少女の瞳は奇麗なように見えて。
少年は少女の言葉に首を縦に振った。
そうして少年と少女が同じ部屋にいることになった。
それでも、少年が言葉を口にすることが無い以上、この部屋で生まれるのは少女から少年に対する一方的なものとなっていた。
■ 時は進む ■
「ねぇ、どうして壁を見つめてるの? 意味があるの?」
首を横に振る。
「……楽しい?」
首を横に振る。
「つまらない?」
首を横に振る。
「……どうして、君はここにいるの? 何でここにいるかわかってるの?」
首を縦に振ってから、言葉を発しようと口を開いた。
「あ……げほっ、ごほっ……」
が、少年の口から洩れた音はすぐさませき込んだそれに代わり、背を丸めて少年はせき込み続けた。
「だ、大丈夫!? ごめん、しゃべろうと、しないで、無理はしちゃだめだよ」
少女は少年の背中をさする。
しばらくすれば少年の様子は落ち着いたが、少女は申し訳なさそうな顔をして少年に謝る。
少年は言われたことの意味を考えたが、理解はできなかった。
■ 時は進む ■
「う……仕方ないけど私しか話してない」
少女の恨めし気な声が響く。
対象となった少年は顔を少女に向ける、そして口を開こうとするが。
「仕方がないって言ってるから! 君は無理しちゃダメ!」
慌てて少女が少年の口を押さえにかかる。
もごもごと口を動かしていた少年だが、口の動きを止めた。
「ちょっとずつ、一音ずつ声を出せるようになっていけばいいなあ」
少女の言葉に口を押えられたままの少年は首を傾げる。
何故、自分が声を出せることを少女は望んでいるのだろうか。
「む、今なんで? って思ったね? だってさ、今私がここにいて、君がここにいるんだよ」
少年は頷く。
ここに自分がいて、目の前の少女がいることは理解できている。
「この世界には人がいっぱいいて、人が生きてるうちに出会える人なんてわずかしかいないんだよ? そのわずかに入るってのすごいって思うんだ」
少年は首を傾げる。
言ってることは、理解はできた。
だが、すごい、という言葉はわからなかった。
「ほら! 何分の一ってやつ! それに入った人と話さないって何かほら、もったいないじゃん!」
少年は首を傾げる。
考えてもやはり、少女の言う言葉はわからなかった。
「人の出会いと別れはね、きっと貴重なんだよ。その機会を生かすには話すしかない! 私はそう思ってるんだ!」
元気な少女の声に、少年は首を傾げるばかりだった。
だが少女は、そんな少年にただ、微笑んでいた。
■ 時は進む ■
「思ったけど、この部屋寒くない?」
少年は首を横に振る。
「む、嘘だー! って、君の手暖かい!?」
少女が少年の手を握る。
それに頬を擦りつけるなどしているが少年はそれに動じない。
「あー……昨日寒くて眠れなかったからなんか眠い……」
少女はそう言って少年の手を掴んだまま寝てしまう。
少年は床に胡坐をかいている状態で、少女は少年の足の上に頭をのせている。
少年は、この部屋にある寝床に少女を運ばねばと、考えてしまった。
そして考えた自分に対してなぜかと疑問を持った。
しばし考えた後にわからなかったので結局少女を寝床に運んだ。
だが、少女は少年の手を離さなかった。
「……お父さん、お母さん」
少女の寝言が聞こえた。
少年は、少女を寝床に寝かせると自分もまた傍らにいた。
少年は自分が何故そうしたのかがわからなかった。
■ 日々は進む ■
■ 少女は少年へと語り続け ■
■ 少年はそれに答え続け ■
■ 少女は素直に応えてくれる少年を好ましく思い ■
■ 少年は自分を害さず、笑いかける少女を新鮮に思った ■
■ 少女が話しかける時間が増え ■
■ 少年が壁を見続ける時間が減っていった ■
■ 時は進む ■
「むう、まだ声は出ないかー」
少年は頷く、どこか申し訳なさそうに。
「気にしないで。君は素直だし、すぐにこっちの言葉に反応してくれるからね、私も嬉しかったりするし」
「無視絶対にしないもんね。最初からだったけど」
そうだっただろうか、と少年は首を傾げた。
「でも最初に比べて首を傾げる回数は減ったよね! うん、良かった!」
それは少女が少年に話しかけ続けて、言葉の意味などを教えてくれたからだった。
「私はそろそろここを出るけれども」
時間間隔が狂いそうだったが、それなりの時間を共に過ごした気がする。
その間獣と戦わされることもなかったのは、これが実験の一種だから、他の要素を入れたくなかったのだろうか、と少年は考えた。
「……君は、元気でね」
■ 時は進む ■
「私がここから出てさ。君もここから出れたら、海を見せたいなー! でっかくて青くて奇麗なんだよ」
少女が笑いながら口にする言葉に少年は首を傾げる。
海がどういうものか、知ってはいる。
だが、見たことはなかった。
「波がきて、波打ち際の線が揺れて。まるで空の色を映しているような青でね」
少女が語る内容を少年は想像ができず、ますます少年は首を傾げる。
「むう、まあいいや! ここから出たら連絡してよ、そしたら一緒に行こうよ。きっと楽しいと思うんだよ」
少年は少女の言葉で海の想像はできなかった。
ただ、この少女と共にこの部屋ではなく外に出れたのなら、それは楽しいことのように思えた。
それは少年が初めて抱いた望みだった。
「あー、でも君泳げるのかなぁ。泳げなかったら浮き輪借りないとだよね。ああ、海の家で焼きそばとか……」
言葉が途切れた理由を少年はその目で見ていた。
少女の腕から、少年が聞きなれている音が響いて、少女の右腕が狼の腕の様なものになっていた。
「…………あはは」
少女の笑い声に少年は顔を向ける。
「本当はね、気が付いていたんだ。私がここから出れないだろうって」
「だってさ、君の扱いを見たらわかるよ。絶対に外に漏らせないことがここで起こってるって」
「だから、覚悟してたんだ」
「怖かった、とっても。うん、とっても怖かった」
「でもね、君がいてくれたから。一人じゃないから」
「そんな怖さを、紛らわすことができたんだ」
訥々と語られる少女の言葉を少年は受け止め、口を開こうとする。
少女の体から肉が、骨が変質する音が響く。
「駄目だよ、無理しちゃ。ああ、でも、離れててほしいな」
「なんかね、私。駄目なんだ。目の前にある君を、殺さなきゃって、そう思っちゃってる。思いたくないけど、そう思っちゃってる」
乾いた笑いを少女は漏らした。
少年は何も、できなかった。
少年は思い返していた。
そう、いつだって『この世界(部屋)に自分一人だけで、それ以外が来るときは大抵敵で、生きるために撃退をするしかない』のだと。
「あーあ、君と一緒に外に出るの、楽しみだったんだけどな」
「君は知らないものが多くてさ、きっと私にいろいろ聞いてくれるんだろうなって」
「君もさ、だんだんと話せるようになって言って、私一人がこうして話すんじゃなくて、君も答えてくれるようになって」
「会話して、美味しいもの食べたりして」
「……でも無理だから」
「せめて君だけは、ちゃんと外に出て。そして、今まで私が話したこととか。覚えててくれたら嬉しいな」
少女は口を噤んだ。
堪える様な、泣きそうな、笑い顔を浮かべて。
「……あはは、苦しいや」
少年は、静かにその腕を、鋭い爪を持つ狼の腕に変えた。
「……君、苦しそうな顔を、しないでよ」
少年はそれを、自分が生きるためではなく、相手を殺すために向けた。
「自分の最期は、ずっと前から決めてた」
「だからね、君に殺されるわけにはいかないんだよ」
少女はそれを、自分が生きるためではなく、相手を生かすために向けた。
「―― 」
少女の異形の腕が、少女の体を穿った。
「―― 君に きず つける わけには いかない から」
少年は思わず少女に駆け寄る。
少女の体から流れる血を止める術もなく。
「あ は 。私 君に あげられたか な」
少女は、笑う。その体が血に塗れても。
少女は自分の死がわかっていたからこそ、此処までの日々で様々なものを少年に与えられればと。
少年が『人』で在れる要素を渡せればと。
そう思い、話しかけ続けていた。
「―― み …… な ……」
そして、それは一つの結果に帰結する。
言葉を発せなかった少年が、口にした少女の名前。
少女は、微笑み。
「私 の 名前 呼んで く」
そのまま、もう動くことは、なかった。
その同日、2/14に少年は救出されることになった。
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
■2/14 早朝■ イバラシティ 2年後
ある霊園に一人の少年が佇んでいた。
袖口から肩にかけてファスナーがある特徴的なそれを着た少年は、傍らの水桶に柄杓を入れると目の前の墓石を見つめる。
「……一緒に外を見ることが叶わなかったからと言って、名前を共に連れて行こうなどとは、二年前の俺は何を考えていたんだろうな」
過去に『3番』と呼ばれていた少年は、空を見上げた。
「いや、それが感傷。つまるところ思い入れか、弱さか」
誰も聞かない独り言、風にそれが消えたころに、今は『三波』と名乗っている少年はその場を去った。
「三奈の心の強さには、まだ届かんな……」
そんな言葉を、残して。



ENo.614 ミキ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
ENo.1226 アケミ とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||
| |||
以下の相手に送信しました



 |
コハル 「早く終わってほしいよ……何でこんなことに……」 |



焼き肉やいても家焼くな!肉の王国!黄金のエバラシティ
|
 |
ハザマに生きるもの
|



焼き肉やいても家焼くな!肉の王国!黄金のエバラシティ
|
 |
2FA
|



武術LV を 10 DOWN。(LV15⇒5、+10CP、-10FP)
魔術LV を 15 UP!(LV0⇒15、-15CP)
付加LV を 5 UP!(LV30⇒35、-5CP)
コハル(1440) の持つ ItemNo.4 水色の栞 に ItemNo.10 毛 を付加しました!
音々子(1191) とカードを交換しました!
アロマのうた (ハーバルメディスン)

エファヴェセント を研究しました!(深度0⇒1)
エファヴェセント を研究しました!(深度1⇒2)
エファヴェセント を研究しました!(深度2⇒3)
ティンダー を習得!
レッドショック を習得!
コントラスト を習得!
ファイアボルト を習得!
ヒートイミッター を習得!
火の祝福 を習得!
マナバースト を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



アリエス(1037) は 吸い殻 を入手!
ショウスケ(1439) は ネジ を入手!
コハル(1440) は ネジ を入手!
三波(1443) は ド根性雑草 を入手!
アリエス(1037) は ボロ布 を入手!
ショウスケ(1439) は 不思議な石 を入手!
三波(1443) は 不思議な石 を入手!
ショウスケ(1439) は 花びら を入手!
▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)
アリエス(1037) のもとに 歩行軍手 が興味津々な様子で近づいてきます。
アリエス(1037) のもとに 歩行石壁 が興味津々な様子で近づいてきます。
アリエス(1037) のもとに ダンデライオン が興味津々な様子で近づいてきます。



チナミ区 I-15(沼地)に移動!(体調15⇒14)
チナミ区 I-16(道路)に移動!(体調14⇒13)
チナミ区 H-16(チェックポイント)に移動!(体調13⇒12)
チナミ区 D-2(ベースキャンプ)に戻りました!
体調が全回復しました!
『チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》』へ採集に向かうことにしました!
- ショウスケ(1439) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》
- コハル(1440) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》
MISSION!!
チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》 が発生!
- アリエス(1037) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- ショウスケ(1439) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- コハル(1440) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》
- 三波(1443) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
エディアン 「・・・・・あら?」 |
 |
白南海 「おっと、これはこれは。」 |

エディアン
プラチナブロンドヘアに紫の瞳。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。
緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。
長い髪は適当なところで雑に結んである。

白南海
黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。
青色レンズの色付き眼鏡をしている。
チャット画面にふたりの姿が映る。
 |
エディアン 「こんにちは白南海さん。元気そうで何より。」 |
 |
白南海 「そう尖らんでも、嬢さん。折角の美人が台無しだ。」 |
 |
エディアン 「・・・それもそうですね、私達同士がどうこうできる訳でもないですし。 それで、これは一体なんなんでしょう?」 |
 |
白南海 「招待されたとか、さっき出てましたけど。」 |
 |
「そ!お!でぇぇ―――っす☆」 |
チャットに響く声。

ミヨチン
茶色の瞳、桜色のロング巻き髪。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
画面に現れる3人目。
 |
白南海 「まぁた、うるせぇのが。・・・ってぇ、こいつァ・・・・・?」 |
 |
エディアン 「ロストじゃないですか、このこ。」 |
 |
白南海 「それとその格好・・・やっぱイバラシティの人間じゃ?あんた。」 |
 |
ミヨチン 「ロスト?イバラシティ?何のことっすかぁ??」 |
 |
ミヨチン 「それよりそれよりぃ!ミヨチンの願いを叶えてくれるって、聞いたんすけどぉー。」 |
上目遣いでふたりに迫る。
 |
白南海 「なるほど。こんな感じであっちから来るんすかねぇ、ロスト。」 |
 |
エディアン 「そっすねぇー。意外っすー。」 |
 |
ミヨチン 「聞いてるんすかぁ!?叶えてくれるんっすかぁー!!?」 |
 |
エディアン 「えぇ叶えます!叶えますともっ!!」 |
 |
白南海 「無茶なことじゃなけりゃー、ですがね。」 |
 |
ミヨチン 「やったーっ!!ミヨチンは、団子!団子が食べたいんすよぉ!! 美味しいやつ!!美味しい団子をたらふく食べたいッ!!」 |
 |
ミヨチン 「好みを言うなら―― ザザッ・・・ 堂のあんこたっぷりの―― ザザッ・・・ 団子がいいんすよねぇ! ガッコー帰りによく友達と食べてたんすよぉ!!」 |
ノイズで一部が聞き取れない。
 |
白南海 「団子だァ・・・??どんな願望かと思えばなんつぅ気の抜けた・・・」 |
 |
エディアン 「しかしこのハザマでお団子、お団子ですかぁ。」 |
 |
白南海 「イバラシティの団子屋なら、梅楽園のが絶品なんすけどねぇ。」 |
 |
エディアン 「あぁ!あそこのお団子はモッチモチで美味しかったです!! 夢のような日々の中でもあれはまた格別でしたねぇ!!」 |
 |
ミヨチン 「マジっすか!それ!それ食べれねぇんすかぁー!?」 |
 |
ドライバーさん 「食べれるぞ。」 |
突然現れるドライバーさん。
 |
白南海 「・・・び、ビビらせねぇでくれませんか?」 |
 |
ドライバーさん 「ビビったんか、そりゃすまん。」 |
 |
エディアン 「こんにちはドライバーさん。・・・お団子、食べれるんですか?」 |
 |
ドライバーさん 「おう。地図見りゃ分かるだろうが、ハザマのモデルはイバラシティだ。 そんでもって一部の名所は結構再現されてる、ハザマなりに・・・な。試しに見てくるといい。」 |
 |
エディアン 「ほんとですか!?ハザマも捨てたもんじゃないですねぇ!!」 |
 |
白南海 「いや、捨てたもんじゃって・・・なぁ・・・・・」 |
 |
ミヨチン 「んじゃんじゃその梅楽園の団子!よろしくお願いしゃーっす!!」 |
 |
白南海 「あの辺なら誰かしら丁度向かってる頃じゃねぇすかねぇ。」 |
 |
エディアン 「よろしく頼みますよぉ皆さん!私も後で行きたいなぁーっ!!」 |
 |
白南海 「・・・何か気が抜ける空気っすねぇ、やっぱ。」 |
賑やかな雰囲気のまま、チャットが閉じられる――



焼き肉やいても家焼くな!肉の王国!黄金のエバラシティ
|
 |
ハザマに生きるもの
|




ミハクサマ親衛隊
|
 |
焼き肉やいても家焼くな!肉の王国!黄金のエバラシティ
|




チナミ区 H-16
チェックポイント《瓦礫の山》
チェックポイント。チェックポイント《瓦礫の山》
仄かな光に包まれた六角形の柱が立っている。
・・・柱から滲み出るように、何かが生み出される。

守護者《DEER》
黒闇に包まれた巨大なシカのようなもの。
 |
守護者《DEER》 「――我が脳は我が姫の意思。我が力は我が主の力。」 |
それは言葉を発すると共に襲いかかる!
(初発生のイベント戦:異能FP+5!生産FP+5!)



焼き肉やいても家焼くな!肉の王国!黄金のエバラシティ
|
 |
立ちはだかるもの
|


ENo.1443
一波 三波



一波 三波(いつなみ みなみ)
年齢:17歳 高校二年生
身長:181cm
10歳になる少し前に両親に実験動物として売られる。
その後、16歳になる前後に研究施設が公的機関により排除されるまでの間、様々な実験をその身に受けた。
そのため、後遺症として髪の一部が白くなっていたり、目が赤が混ざった黒のような色となっている。
また10歳以前の記憶が、『自分を売って遊ぶ金ができたことを喜ぶ両親』のものしかない上、自分がどのように生活していたのかすらわからなくなってしまった。
16歳から17歳になるまでの間に自分に関する様々な構築を行い、今に至る。
上記の経歴から、話す言葉が理屈っぽいところがある。
また、言葉数は少ないようにも思えるが、冗談は言う。
……が、社会経験の少なさにより人と話すのは難儀をしているようだ。
自分の目つきが悪いことは自覚しているため、不特定多数のいる場所ではパーカーのフードを下ろして顔を隠している。
また、パーカーについては異能の関係で袖から肩にかけてファスナーのある特殊なものを着こんでいる。
自分の体を鍛えたり、様々な本を読み知識を蓄えたり、知らないことに挑戦したりと色々な手段で自分を鍛えようとしている。
それは、自分がある日売られてしまったような『理不尽』に抗うための力を求めてのものであり、その『理不尽』は決して自分にかかるものだけを指すわけでは無い。
-----------------------------
異能:ジャガーノート
自分の体を人とは違った異形へと変貌させる異能力。
元々は、自分の肉体の硬度などを変化させるものだった。
しかし、人体実験にさらされた際に『理不尽に抗うには人のままでは不十分だ』という意思により方向性が固定された。
体の一部を変化、もしくは一部を生やすことができ、大抵は自分の腕を増やしている。
彼の個人的観点で異形、と思ったものはこの能力の対象とすることができるがあくまで模造。
その部位が持つ100%の能力を発揮することはできず、力の発揮量は使用者の身体能力に依存する。
しかし見た目だけはほぼ完全再現可能。
ほぼ無意識の発動ができるため、咄嗟に腕を生やして行動することもある。
なお、イバラシティでは全身変化は無理で、精々が腕と足を二本ずつ生やすのが限界。
そして腕を生やした場合には体のバランスが崩れるため、足を増やすなどをしてバランスを取らないといけない欠点もある。
……だが、この能力はまだ成長途上である。
なお、三波はこの能力が腕を生やしても自在に操れる点から『自分の脳』も変化させてると推測。
能力が暴走した際は自我が失われる可能性を見込んでいる。
以下、三波は知らない情報。
これは、人と交流していく中で自覚をするかもしれないもの。
異能:名称未設定
三波の持つ本来の能力。歪んだために対象が一部限定された。
『物語』の中に出てくる、三波が異形と認識しているものを対象とする。
自分の体の部位を対象の体の部位に変化させることが可能な他、部位を追加することもできる。
この際、過不足なく自分の意識で動かせる。
物語』の定義は以下の二つ、どちらかを満たせていればいい。
・書籍としてまとめられており、誰かに読まれていること
・誰かの口から誰かに対して語られている
もちろん前提として使用者本人が、その『物語』を知らなければならない。
詳細:
魔法に片足を突っ込んでいる異能。
使用者の体力を使用者のみが使用できる疑似魔力に変換。
疑似魔力の形を整形し、現実に現すことで変化をさせる。
内臓についても仮想内臓を構築することで変化を実現させている。
そのため、変化後の筋力および関節の増加もあり体力の消耗が激しい。
場合によっては過労死する可能性が存在する異能。
年齢:17歳 高校二年生
身長:181cm
10歳になる少し前に両親に実験動物として売られる。
その後、16歳になる前後に研究施設が公的機関により排除されるまでの間、様々な実験をその身に受けた。
そのため、後遺症として髪の一部が白くなっていたり、目が赤が混ざった黒のような色となっている。
また10歳以前の記憶が、『自分を売って遊ぶ金ができたことを喜ぶ両親』のものしかない上、自分がどのように生活していたのかすらわからなくなってしまった。
16歳から17歳になるまでの間に自分に関する様々な構築を行い、今に至る。
上記の経歴から、話す言葉が理屈っぽいところがある。
また、言葉数は少ないようにも思えるが、冗談は言う。
……が、社会経験の少なさにより人と話すのは難儀をしているようだ。
自分の目つきが悪いことは自覚しているため、不特定多数のいる場所ではパーカーのフードを下ろして顔を隠している。
また、パーカーについては異能の関係で袖から肩にかけてファスナーのある特殊なものを着こんでいる。
自分の体を鍛えたり、様々な本を読み知識を蓄えたり、知らないことに挑戦したりと色々な手段で自分を鍛えようとしている。
それは、自分がある日売られてしまったような『理不尽』に抗うための力を求めてのものであり、その『理不尽』は決して自分にかかるものだけを指すわけでは無い。
-----------------------------
異能:ジャガーノート
自分の体を人とは違った異形へと変貌させる異能力。
元々は、自分の肉体の硬度などを変化させるものだった。
しかし、人体実験にさらされた際に『理不尽に抗うには人のままでは不十分だ』という意思により方向性が固定された。
体の一部を変化、もしくは一部を生やすことができ、大抵は自分の腕を増やしている。
彼の個人的観点で異形、と思ったものはこの能力の対象とすることができるがあくまで模造。
その部位が持つ100%の能力を発揮することはできず、力の発揮量は使用者の身体能力に依存する。
しかし見た目だけはほぼ完全再現可能。
ほぼ無意識の発動ができるため、咄嗟に腕を生やして行動することもある。
なお、イバラシティでは全身変化は無理で、精々が腕と足を二本ずつ生やすのが限界。
そして腕を生やした場合には体のバランスが崩れるため、足を増やすなどをしてバランスを取らないといけない欠点もある。
……だが、この能力はまだ成長途上である。
なお、三波はこの能力が腕を生やしても自在に操れる点から『自分の脳』も変化させてると推測。
能力が暴走した際は自我が失われる可能性を見込んでいる。
以下、三波は知らない情報。
これは、人と交流していく中で自覚をするかもしれないもの。
異能:名称未設定
三波の持つ本来の能力。歪んだために対象が一部限定された。
『物語』の中に出てくる、三波が異形と認識しているものを対象とする。
自分の体の部位を対象の体の部位に変化させることが可能な他、部位を追加することもできる。
この際、過不足なく自分の意識で動かせる。
物語』の定義は以下の二つ、どちらかを満たせていればいい。
・書籍としてまとめられており、誰かに読まれていること
・誰かの口から誰かに対して語られている
もちろん前提として使用者本人が、その『物語』を知らなければならない。
詳細:
魔法に片足を突っ込んでいる異能。
使用者の体力を使用者のみが使用できる疑似魔力に変換。
疑似魔力の形を整形し、現実に現すことで変化をさせる。
内臓についても仮想内臓を構築することで変化を実現させている。
そのため、変化後の筋力および関節の増加もあり体力の消耗が激しい。
場合によっては過労死する可能性が存在する異能。
30 / 30
147 PS
チナミ区
D-2
D-2




































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 手甲 | 武器 | 35 | 攻撃10 | - | - | 【射程1】 |
| 5 | 紺色のパーカー | 防具 | 35 | 防御10 | - | - | |
| 6 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 8 | バンテージ | 装飾 | 60 | 活力10 | - | - | |
| 9 | 羽 | 素材 | 10 | [武器]風撃10(LV25)[防具]風柳10(LV20)[装飾]風纏10(LV20) | |||
| 10 | 韮 | 素材 | 10 | [武器]朦朧10(LV20)[防具]体力10(LV10)[装飾]増勢10(LV25) | |||
| 11 | 不思議な雫 | 素材 | 10 | [武器]水纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV10)[装飾]耐水10(LV20) | |||
| 12 | ド根性雑草 | 素材 | 15 | [武器]防狂10(LV20)[防具]反護10(LV25)[装飾]復活10(LV25) | |||
| 13 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]防御10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 5 | 身体/武器/物理 |
| 魔術 | 15 | 破壊/詠唱/火 |
| 変化 | 15 | 強化/弱化/変身 |
| 付加 | 35 | 装備品への素材の付加に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| 練3 | ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 |
| 練3 | ティンダー | 5 | 0 | 50 | 敵:火撃&炎上 |
| カース | 5 | 0 | 50 | 敵:闇撃&束縛 | |
| ガードフォーム | 5 | 0 | 100 | 自:DF増 | |
| エチュード | 5 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) | |
| レッドショック | 5 | 0 | 80 | 敵:3連鎖火撃 | |
| ブラックバンド | 5 | 0 | 80 | 敵貫:闇撃&盲目 | |
| クリーンヒット | 5 | 0 | 60 | 敵:痛撃&次与ダメ減 | |
| コントラスト | 5 | 0 | 60 | 敵:火痛撃&炎上&自:守護・凍結 | |
| ラトゥンブロウ | 5 | 0 | 50 | 敵強:闇撃&腐食+敵味全:腐食 | |
| カームソング | 5 | 0 | 100 | 敵全:攻撃&DX減(2T) | |
| 練3 | チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 |
| ファイアボルト | 5 | 0 | 100 | 敵貫:火痛撃 | |
| ダークネス | 5 | 0 | 100 | 敵列:闇撃&盲目 | |
| ディベスト | 5 | 0 | 70 | 敵:強化奪取+痛撃 | |
| ビブラート | 5 | 0 | 120 | 敵全2:粗雑SP攻撃 | |
| ガーディアンフォーム | 5 | 0 | 200 | 自:DF・HL増+連続減 | |
| ヒートイミッター | 5 | 0 | 100 | 敵列:火撃&麻痺+自:凍結 | |
| ディライト | 5 | 0 | 100 | 敵全:SP攻撃&強化を魅了化 | |
| 練3 | イレイザー | 5 | 0 | 100 | 敵傷:攻撃 |
| アブソーブ | 5 | 0 | 100 | 敵全:次与ダメ減 | |
| マナバースト | 5 | 0 | 150 | 敵:火撃&SP50%以上なら火撃 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 敗柳残花 | 5 | 3 | 0 | 【攻撃命中後】対:祝福を腐食化 | |
| 上書き付加 | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『効果付加』で、効果2に既に付加があっても上書きするようになる。 | |
| 火の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:魔術LVが高いほど火特性・耐性増 | |
| 血気 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:現在HP割合が低いほど攻撃ダメージ増 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
響く鳴き声 (カースワード) |
0 | 130 | 敵全:闇撃&腐食 | |
|
★ミ (アサルト) |
0 | 50 | 敵:痛撃+自:連続減 | |
|
アロマのうた (ハーバルメディスン) |
0 | 100 | 味傷3:HP増+DF増(1T) |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]グランドクラッシャー | [ 3 ]ディライト | [ 3 ]サモン:レッサーデーモン |
| [ 3 ]エファヴェセント |

PL / 狩咲