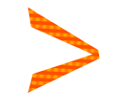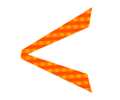<< 1:00~2:00





四捨五入すれば三十。
その言葉を耳にするたび、俺の胃はこの辺にあるんだと知らされる。一度吐いた吐瀉物を飲み込みなおしたような気分で弟の顔を見る。いくら眉根を寄せたところでどうやったってもうすぐ三十の男の顔には見えなかった。双子だからかあまり似ていない俺もそこは同じだった。
三十年生きてきたといっても、三十年近く生きてきただけだ。運悪く死ななかっただけ。頭も体も空っぽで、おんなじように思い出だって空っぽだ。
俺が積み重ねてきたものは恨みだ。奪われるだけの弱者が最後に持っているものなんて、恨みつらみくらいじゃないだろうか。内臓のいくつかは金に変えられた。その金で俺が食うこともなかったなんて笑い話にしようがない。家族が揃っていた頃は金に困る生活なんて考えたこともなかったはずだ。その頃の俺は生活がどういうものか考えられる歳じゃなかったのだけれど。母親もそんなこと考えていなかった。
物心ついて少ししてから親父が蒸発して、残った三人は真っ二つの道へ別れた。俺は母に連れられ、生まれた国とやらに帰った。双子の弟といえばそのまま置いていかれたのだけど、父親の親戚に引き取られたらしい。見知らぬ他人からはそっくりだと言われる双子だった俺と弟は愛され方が全く違った。弟はあんまり相手にされず、母から名前を貰えずに父からひねり出された。かと言って俺が愛されているわけでもなかった。母親は父親が好きで結婚したのであって、俺たち双子はそれに付随しただけのおまけだった。だから双子のどちらかと云えば親父に似ている俺だけを引き取ったんだろう。結局、似ているだけで俺は親父じゃなかったから、愛されることはなかった。
愛の話はどうでもいい。とりあえず、金の話だ。母親は仕事をするような人じゃなかった。国に帰って、食うに困ったら持っているものを売る。その金が尽きたらまたなにかを売る。そうやってすり減っていく生活だった。
そんな俺の道を夢という形で見せられた弟からは悪夢だって言われる。俺だって眠っているときは同じように、弟の人生は悪夢だって思ってるよ。
◇


生々しい夢が夢ではないと気づいたのはいつだったか。
飼っていた蟷螂が、もう片方の蟷螂を食い殺したのを見て、その意味を知ってからベッドに潜り込んだ日だ。
甘いモスクの香りと手触りの良いシーツから転がり落ちた先が病院のベッドだった時だろうか。夢の中ではまっさきに鏡を探そうとするのだけど、その努力はいつも無駄に終わる。視界のほとんどを覆う青い髪がかきあげられた。
数年は自分じゃない誰かの視界を介した夢を見ている。俺に似た青い髪で異様に細い体の持ち主らしい。現実で起こるどんな出来事も、夢の内容を思い出すきっかけにならなかった。また夢に潜ったときには思い出せる。視界の主は自分と大差ない背丈だろう。異様に肉のない骨の浮いた腕から体つきは違いそうだと感じる。違和感のある腕にはトンボみたいな形の点滴の針が刺さっていた。見上げた点滴の袋に貼ってあるシールに病院名が書いてある。見覚えがあるが思い出せない。
少し前には学校に通っていて、それから雑用みたいな仕事をしていたはずだ。それがなぜか今は病院の一室にいるらしい。なぜ入院しているのだろうか。栄養失調、それとも持病なのか。慢性的な飢餓だとしても、金が無いからの飢餓だからこそ、なぜ入院できた?少し前には仕事中にうっかりしたのかいじめられたのか、苦しそうに咳き込んでいた。もしかして本当に良くない状態なんだろうか?疑問が自分の方の頭を埋め尽くしている間に、視界は微塵も変わらなかった。無機質な病室にお似合いの無感情だ。そうやって言葉遊びをしたところで、暇なことに変わりはない。暇を持て余して眠ったところでどうして、更に暇な夢を見なければいけないのか。
少し前までは異国の地で働いているこの体の持ち主が一体どういった人物なのかを見ていた。金も頭も足りないやつだと知ってから持ち主の行動は真面目に見ず、ただ耳を澄まして異国の言葉を吸収していった。この体の持ち主は貧乏な家の子だからいじめられることが多く、罵る言葉から覚えることになった。それでも持ち主が理解できていないような言葉でもわかる程に、俺の頭は異国の言葉を吸収していた。
俺は父親に似て頭がいいときいていたから、そのくらいできて当然だと、そんなくらいに考えていた。そのことが俺にとって良かったのか悪かったのか。自分でも判断できないことだから、結局は考えても無駄だったのだろう。
現状に思考を戻す。久々に持ち主について気になった。よろけつつも窓際に立ち、異様に痛む腹部を擦る。前を合わせるだけの簡素な服にはベタつく黄色い汁がにじみ出て、傷跡が近いことを示していた。窓のふちなんて眺めていないで、もう少しヒントの有りそうな方向を見てほしい。体の持ち主の現状も、感情もわからず非常に不愉快なまま淀んだ空の方を見る。朝なのだろうか、夜なのだろうか。異国の地とは時差がどれだけあるか計算してみてもいいかもしれない。
「ずっと曇ってるですね」
この体の持ち主が独特な話し方をすることは、しばらく夢を見ているうちに知った。丁寧なようで、適当な話し方だ。はあ、とため息をつくようにひとりごちることが多い。この無機質な病室から、変わったものを抜き出そうとするなら外の風景しかない。その風景もぬるく淀んだ灰色の空だった。
しばらくそうして背を押す風もなくのろのろと進む煙のような雲を眺めていた。扉の方から近づいてきた足音には興味がないようで、それが部屋の中に来るまで振り返ることはなかった。ベッドと扉を遮るカーテンが開かれる。白衣の女が気だるげに立っていた。
「調子はどうだい?」
「見ればわかるんじゃないですか?」
ぞんざいな返事に女は気を悪くした様子はなかった。ベッドに腰掛けてこちらの様子を伺い、問題なさそうだと言わんばかりに笑顔で頷いた。
「あんたの母上も中々に悪い奴だと思わないかい?旦那が蒸発したのは可哀想だけれど、ただその事を嘆いて縋り付くだけだ。ぜーんぶ、家事も仕事もやってさ、あんたがだよ。それだってのに足りないからってあんたを売った」
女は持ち主のことをよく知っているらしい。ならぞんざいな返事でも問題なかったのだろう。しかし、売られたとはなんのことだろう。病室にいることと売られたことが結びつかずに早く次の言葉を聞きたくて仕方がない。反するように持ち主は少しだけ目を細めた。
「あんたは相当に運がない子なんだろうね」
女は寄り添うようにしなだれかかってくる。傷口に触ったのかぴくりと動き視線も釣られて下にやられた。女の眼鏡に反射した俺の顔には見覚えがあった。あと少しで記憶から消えそうになっていた、曇天に紛れた兄の顔。
ほのかに血生臭い息が吹きかけられて青い髪が揺れる。
生まれてから一緒に過ごしていた時間と、離れていた時間は奇しくも同じ。それにしたってまさか兄の視界を夢で見ているなんて思わなかった。父親に似て頭がいいだけじゃなく、人に興味がないところも似ていたなんて。それと、ネガティブ思考も似ていたなんて。おれはすでにどうして売られた兄がここにいるのか気づいていた。兄よりも顔を覚えていない母親はものに愛着のない人だ。そして俺たち双子のことをものだと思っていた。
近づいてきた女がぶつかるように唇を重ね合わせた。柔らかなそれが重なり、次の瞬間には舌と舌が触れ合っていた。気持ちが悪い。生臭いそれが絡みついてぬるりと動くたびに、やめてくれと叫びそうになる。もし俺の勘違いだったら、俺より先にこんな経験をするなんて羨ましいっていうところなんだろう。今はそれどころじゃない。兄の体で、その視界を見るのが本当に気持ち悪くて気が狂いそうだ。思考はぐにゃりとしているのに、体は抵抗もせずに視界はそれを見つめ耳は粘ついた音を聞く。互いの体温を分け合いきったところで女は体を離した。
「こっちの意味で買っちゃないんだけどさ、後払いでもあいつは気にしないだろ?」
返事を求められてはいなかった。ベッドに押し倒されてため息をつくだけだ。抜けてしまった点滴の針が腕に傷をつけて、留まる先がないようにぶらりと垂れ下がる。こんな光景は俺に耐えきれるものじゃない。病室に他の人が居ない意味、ネームプレートがない意味、女が兄を見る目の意味も全部が俺のせいだと言っているみたいで気持ちが悪い。母親に連れて行かれればこうなることは解っていた。俺は自分のことだけ考えて、叔母のところへ行ったんだ。あの時もう少し考えていれば。
「できる歳だろう?いい思いをさせてあげよう」
俺は飼っていた蟷螂のことを思い出した。雄と雌を同じ箱に入れて飼っていたんだ。雌が雄の頭を抱えていたのをみた。俺はその理由を知っている。兄は一瞬だけたじろいだようで、ベッドの上で微かに後ずさった。
「できないですよ」
申し訳なさそうな声に俺の頭は一瞬で沸騰した。兄は食われてしまうんだ。食われるために売られたんだ。垂れ下がったトンボみたいな針を掴んで、白衣を脱ごうとしている女の首に突き立てる。
「おれは、お前に食べられるために生まれてきたんじゃない」
押し倒された女の目には恐怖の色が見えた。この女は人肉を食うために兄を買ったんだ。そんな狂人が何を恐れているんだろう。突き立てた針を無理やりに下へと引きずって肉を切り開く。シーツに赤い染みができたところで女は甲高い叫び声をあげた。助けてくれ、殺される、と。そうだ、殺してやる。食われてなんかやるものか。叫びに応えるように駆けてくる足音より早く、簪代わりの鋼扇を髪から引き抜いて、まっしろな首を真横にパッカリと切り裂いた。雪原に赤い線がひかれたような光景だったが、気持ち悪さが増しただけだった。
悲鳴に気づいて走ってきたナースはこの光景に悲鳴をあげ、狭い病室へ人が雪崩れ込む。気がつけば持っていた鋼扇は髪の中に隠されて、ようやく俺は自分がしでかしてしまったことに気づいた。兄の体で人を殺してしまったことに。
部屋の隅に連れていかれ大人しくしているとすぐに事態は収まった。あの女は同僚に自分の趣味を明かしていたらしい。兄の服を開けば前に食われたときの跡があったし、女が更衣室に置いていたクーラーボックスには『食べ残し』が入っていた。血塗れの光景に吐かなかったナースが名前を聞き出して家を確認するまであっという間だった。連絡を受けた母が迎えにくると聞いて、兄が舌を噛み切ったのも一瞬だった。
女に食われることより、母親に失望されることのほうが「死にたくなる」出来事だったなんて。
痛みで気を失ったのか、俺が耐えきれなくなったのか甘いモスクの香りが血腥さを掻き消した。夢は終わった。シーツを頭からすっぽりと被り震え続ける。俺は知ってしまったんだ。夢が覚める直前に兄が何を考えていたのかを。
「貴重な収入源を失ってしまった」
ただそんなことを考えていたのが恐ろしくて、そう考えるようになってしまったのが恐ろしくてたまらなかった。
その日からおれはまともに話すことができなくなった。おれはこの震えをずっと抱きかかえていかなきゃならない。



欠けた器(384) から 美味しい果実 を手渡しされました。
ItemNo.7 おでん(鯛の揚げ団子入り) を食べました!
体調が 1 回復!(26⇒27)
今回の全戦闘において 器用10 敏捷10 耐疫10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!









欠けた器(384) から 71 PS 受け取りました。
響鳴LV を 5 UP!(LV10⇒15、-5CP)
ItemNo.6 白樺 から射程3の武器『刀』を作製しました!
⇒ 刀/武器:強さ52/[効果1]活力10 [効果2]- [効果3]-【射程3】
欠けた器(384) の持つ ItemNo.6 白樺 から射程3の武器『アルトリコーダー』を作製しました!
アオイ(1564) の持つ ItemNo.7 から射程1の武器『ひのきのぼう』を作製―― できるかーい!素材じゃないゾ☆
ユーリウス(117) により ItemNo.8 美味しい果実 から料理『おでん(パイナップル入り)』をつくってもらいました!
⇒ おでん(パイナップル入り)/料理:強さ60/[効果1]攻撃10 [効果2]防御10 [効果3]強靭15
布施(747) とカードを交換しました!
竜胆の描かれたカード (アンダークーリング)

リストア を研究しました!(深度2⇒3)
ファーマシー を研究しました!(深度2⇒3)
ファンタジア を研究しました!(深度1⇒2)
ヒーリングソング を習得!
☆ルージィグージィ を習得!
☆初習得ボーナス:各FPが2増加した!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



ユーリウス(117) は 松 を入手!
"ofLOSE"(380) は 杉 を入手!
欠けた器(384) は 杉 を入手!
欠けた器(384) は 毛 を入手!
"ofLOSE"(380) は 美味しい草 を入手!
"ofLOSE"(380) は 毛 を入手!



チナミ区 E-11(隔壁)には移動できません。
チナミ区 F-10(隔壁)には移動できません。
チナミ区 E-11(隔壁)には移動できません。
チナミ区 F-10(隔壁)には移動できません。
チナミ区 E-11(隔壁)には移動できません。
アオイ(1564) をパーティに勧誘しました!
欠けた器(384) をパーティに勧誘しようとしましたが既に背後にいました。
ユーリウス(117) をパーティに勧誘しようとしましたが既に背後にいました。
採集はできませんでした。
- "ofLOSE"(380) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- アオイ(1564) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。

Cross+Roseの音量を調整する。
Cross+Roseにロスト7名の容姿と簡単なプロフィールが映し出される。







チャットが閉じられる――
























































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.




オブルス
25歳。
舌っ足らずな青年。
遊園地『パラダイス』の管理人
舌っ足らずな青年。
遊園地『パラダイス』の管理人
四捨五入すれば三十。
その言葉を耳にするたび、俺の胃はこの辺にあるんだと知らされる。一度吐いた吐瀉物を飲み込みなおしたような気分で弟の顔を見る。いくら眉根を寄せたところでどうやったってもうすぐ三十の男の顔には見えなかった。双子だからかあまり似ていない俺もそこは同じだった。
三十年生きてきたといっても、三十年近く生きてきただけだ。運悪く死ななかっただけ。頭も体も空っぽで、おんなじように思い出だって空っぽだ。
俺が積み重ねてきたものは恨みだ。奪われるだけの弱者が最後に持っているものなんて、恨みつらみくらいじゃないだろうか。内臓のいくつかは金に変えられた。その金で俺が食うこともなかったなんて笑い話にしようがない。家族が揃っていた頃は金に困る生活なんて考えたこともなかったはずだ。その頃の俺は生活がどういうものか考えられる歳じゃなかったのだけれど。母親もそんなこと考えていなかった。
物心ついて少ししてから親父が蒸発して、残った三人は真っ二つの道へ別れた。俺は母に連れられ、生まれた国とやらに帰った。双子の弟といえばそのまま置いていかれたのだけど、父親の親戚に引き取られたらしい。見知らぬ他人からはそっくりだと言われる双子だった俺と弟は愛され方が全く違った。弟はあんまり相手にされず、母から名前を貰えずに父からひねり出された。かと言って俺が愛されているわけでもなかった。母親は父親が好きで結婚したのであって、俺たち双子はそれに付随しただけのおまけだった。だから双子のどちらかと云えば親父に似ている俺だけを引き取ったんだろう。結局、似ているだけで俺は親父じゃなかったから、愛されることはなかった。
愛の話はどうでもいい。とりあえず、金の話だ。母親は仕事をするような人じゃなかった。国に帰って、食うに困ったら持っているものを売る。その金が尽きたらまたなにかを売る。そうやってすり減っていく生活だった。
そんな俺の道を夢という形で見せられた弟からは悪夢だって言われる。俺だって眠っているときは同じように、弟の人生は悪夢だって思ってるよ。
◇

フレシ
12歳。
アーク兄弟の弟の方。母親似。
アーク兄弟の弟の方。母親似。

オブルス
12歳。
アーク兄弟の兄の方。父親似。
アーク兄弟の兄の方。父親似。
生々しい夢が夢ではないと気づいたのはいつだったか。
飼っていた蟷螂が、もう片方の蟷螂を食い殺したのを見て、その意味を知ってからベッドに潜り込んだ日だ。
甘いモスクの香りと手触りの良いシーツから転がり落ちた先が病院のベッドだった時だろうか。夢の中ではまっさきに鏡を探そうとするのだけど、その努力はいつも無駄に終わる。視界のほとんどを覆う青い髪がかきあげられた。
数年は自分じゃない誰かの視界を介した夢を見ている。俺に似た青い髪で異様に細い体の持ち主らしい。現実で起こるどんな出来事も、夢の内容を思い出すきっかけにならなかった。また夢に潜ったときには思い出せる。視界の主は自分と大差ない背丈だろう。異様に肉のない骨の浮いた腕から体つきは違いそうだと感じる。違和感のある腕にはトンボみたいな形の点滴の針が刺さっていた。見上げた点滴の袋に貼ってあるシールに病院名が書いてある。見覚えがあるが思い出せない。
少し前には学校に通っていて、それから雑用みたいな仕事をしていたはずだ。それがなぜか今は病院の一室にいるらしい。なぜ入院しているのだろうか。栄養失調、それとも持病なのか。慢性的な飢餓だとしても、金が無いからの飢餓だからこそ、なぜ入院できた?少し前には仕事中にうっかりしたのかいじめられたのか、苦しそうに咳き込んでいた。もしかして本当に良くない状態なんだろうか?疑問が自分の方の頭を埋め尽くしている間に、視界は微塵も変わらなかった。無機質な病室にお似合いの無感情だ。そうやって言葉遊びをしたところで、暇なことに変わりはない。暇を持て余して眠ったところでどうして、更に暇な夢を見なければいけないのか。
少し前までは異国の地で働いているこの体の持ち主が一体どういった人物なのかを見ていた。金も頭も足りないやつだと知ってから持ち主の行動は真面目に見ず、ただ耳を澄まして異国の言葉を吸収していった。この体の持ち主は貧乏な家の子だからいじめられることが多く、罵る言葉から覚えることになった。それでも持ち主が理解できていないような言葉でもわかる程に、俺の頭は異国の言葉を吸収していた。
俺は父親に似て頭がいいときいていたから、そのくらいできて当然だと、そんなくらいに考えていた。そのことが俺にとって良かったのか悪かったのか。自分でも判断できないことだから、結局は考えても無駄だったのだろう。
現状に思考を戻す。久々に持ち主について気になった。よろけつつも窓際に立ち、異様に痛む腹部を擦る。前を合わせるだけの簡素な服にはベタつく黄色い汁がにじみ出て、傷跡が近いことを示していた。窓のふちなんて眺めていないで、もう少しヒントの有りそうな方向を見てほしい。体の持ち主の現状も、感情もわからず非常に不愉快なまま淀んだ空の方を見る。朝なのだろうか、夜なのだろうか。異国の地とは時差がどれだけあるか計算してみてもいいかもしれない。
「ずっと曇ってるですね」
この体の持ち主が独特な話し方をすることは、しばらく夢を見ているうちに知った。丁寧なようで、適当な話し方だ。はあ、とため息をつくようにひとりごちることが多い。この無機質な病室から、変わったものを抜き出そうとするなら外の風景しかない。その風景もぬるく淀んだ灰色の空だった。
しばらくそうして背を押す風もなくのろのろと進む煙のような雲を眺めていた。扉の方から近づいてきた足音には興味がないようで、それが部屋の中に来るまで振り返ることはなかった。ベッドと扉を遮るカーテンが開かれる。白衣の女が気だるげに立っていた。
「調子はどうだい?」
「見ればわかるんじゃないですか?」
ぞんざいな返事に女は気を悪くした様子はなかった。ベッドに腰掛けてこちらの様子を伺い、問題なさそうだと言わんばかりに笑顔で頷いた。
「あんたの母上も中々に悪い奴だと思わないかい?旦那が蒸発したのは可哀想だけれど、ただその事を嘆いて縋り付くだけだ。ぜーんぶ、家事も仕事もやってさ、あんたがだよ。それだってのに足りないからってあんたを売った」
女は持ち主のことをよく知っているらしい。ならぞんざいな返事でも問題なかったのだろう。しかし、売られたとはなんのことだろう。病室にいることと売られたことが結びつかずに早く次の言葉を聞きたくて仕方がない。反するように持ち主は少しだけ目を細めた。
「あんたは相当に運がない子なんだろうね」
女は寄り添うようにしなだれかかってくる。傷口に触ったのかぴくりと動き視線も釣られて下にやられた。女の眼鏡に反射した俺の顔には見覚えがあった。あと少しで記憶から消えそうになっていた、曇天に紛れた兄の顔。
ほのかに血生臭い息が吹きかけられて青い髪が揺れる。
生まれてから一緒に過ごしていた時間と、離れていた時間は奇しくも同じ。それにしたってまさか兄の視界を夢で見ているなんて思わなかった。父親に似て頭がいいだけじゃなく、人に興味がないところも似ていたなんて。それと、ネガティブ思考も似ていたなんて。おれはすでにどうして売られた兄がここにいるのか気づいていた。兄よりも顔を覚えていない母親はものに愛着のない人だ。そして俺たち双子のことをものだと思っていた。
近づいてきた女がぶつかるように唇を重ね合わせた。柔らかなそれが重なり、次の瞬間には舌と舌が触れ合っていた。気持ちが悪い。生臭いそれが絡みついてぬるりと動くたびに、やめてくれと叫びそうになる。もし俺の勘違いだったら、俺より先にこんな経験をするなんて羨ましいっていうところなんだろう。今はそれどころじゃない。兄の体で、その視界を見るのが本当に気持ち悪くて気が狂いそうだ。思考はぐにゃりとしているのに、体は抵抗もせずに視界はそれを見つめ耳は粘ついた音を聞く。互いの体温を分け合いきったところで女は体を離した。
「こっちの意味で買っちゃないんだけどさ、後払いでもあいつは気にしないだろ?」
返事を求められてはいなかった。ベッドに押し倒されてため息をつくだけだ。抜けてしまった点滴の針が腕に傷をつけて、留まる先がないようにぶらりと垂れ下がる。こんな光景は俺に耐えきれるものじゃない。病室に他の人が居ない意味、ネームプレートがない意味、女が兄を見る目の意味も全部が俺のせいだと言っているみたいで気持ちが悪い。母親に連れて行かれればこうなることは解っていた。俺は自分のことだけ考えて、叔母のところへ行ったんだ。あの時もう少し考えていれば。
「できる歳だろう?いい思いをさせてあげよう」
俺は飼っていた蟷螂のことを思い出した。雄と雌を同じ箱に入れて飼っていたんだ。雌が雄の頭を抱えていたのをみた。俺はその理由を知っている。兄は一瞬だけたじろいだようで、ベッドの上で微かに後ずさった。
「できないですよ」
申し訳なさそうな声に俺の頭は一瞬で沸騰した。兄は食われてしまうんだ。食われるために売られたんだ。垂れ下がったトンボみたいな針を掴んで、白衣を脱ごうとしている女の首に突き立てる。
「おれは、お前に食べられるために生まれてきたんじゃない」
押し倒された女の目には恐怖の色が見えた。この女は人肉を食うために兄を買ったんだ。そんな狂人が何を恐れているんだろう。突き立てた針を無理やりに下へと引きずって肉を切り開く。シーツに赤い染みができたところで女は甲高い叫び声をあげた。助けてくれ、殺される、と。そうだ、殺してやる。食われてなんかやるものか。叫びに応えるように駆けてくる足音より早く、簪代わりの鋼扇を髪から引き抜いて、まっしろな首を真横にパッカリと切り裂いた。雪原に赤い線がひかれたような光景だったが、気持ち悪さが増しただけだった。
悲鳴に気づいて走ってきたナースはこの光景に悲鳴をあげ、狭い病室へ人が雪崩れ込む。気がつけば持っていた鋼扇は髪の中に隠されて、ようやく俺は自分がしでかしてしまったことに気づいた。兄の体で人を殺してしまったことに。
部屋の隅に連れていかれ大人しくしているとすぐに事態は収まった。あの女は同僚に自分の趣味を明かしていたらしい。兄の服を開けば前に食われたときの跡があったし、女が更衣室に置いていたクーラーボックスには『食べ残し』が入っていた。血塗れの光景に吐かなかったナースが名前を聞き出して家を確認するまであっという間だった。連絡を受けた母が迎えにくると聞いて、兄が舌を噛み切ったのも一瞬だった。
女に食われることより、母親に失望されることのほうが「死にたくなる」出来事だったなんて。
痛みで気を失ったのか、俺が耐えきれなくなったのか甘いモスクの香りが血腥さを掻き消した。夢は終わった。シーツを頭からすっぽりと被り震え続ける。俺は知ってしまったんだ。夢が覚める直前に兄が何を考えていたのかを。
「貴重な収入源を失ってしまった」
ただそんなことを考えていたのが恐ろしくて、そう考えるようになってしまったのが恐ろしくてたまらなかった。
その日からおれはまともに話すことができなくなった。おれはこの震えをずっと抱きかかえていかなきゃならない。



 |
ユーリウス 「どうだい?僕のおでんは。おいしいだろう? 僕の仲間になってくれたら、いつでも食べさせてあげられるのだけれどね。 どうかな、ひとつ。手を組まないか?」 |
欠けた器(384) から 美味しい果実 を手渡しされました。
ItemNo.7 おでん(鯛の揚げ団子入り) を食べました!
体調が 1 回復!(26⇒27)
今回の全戦闘において 器用10 敏捷10 耐疫10 が発揮されます。
今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!





つくねサマとラディカルサバイバーズ
|
 |
エアプ達のおでんパーティ
|



欠けた器(384) から 71 PS 受け取りました。
響鳴LV を 5 UP!(LV10⇒15、-5CP)
ItemNo.6 白樺 から射程3の武器『刀』を作製しました!
⇒ 刀/武器:強さ52/[効果1]活力10 [効果2]- [効果3]-【射程3】
欠けた器(384) の持つ ItemNo.6 白樺 から射程3の武器『アルトリコーダー』を作製しました!
アオイ(1564) の持つ ItemNo.7 から射程1の武器『ひのきのぼう』を作製―― できるかーい!素材じゃないゾ☆
ユーリウス(117) により ItemNo.8 美味しい果実 から料理『おでん(パイナップル入り)』をつくってもらいました!
⇒ おでん(パイナップル入り)/料理:強さ60/[効果1]攻撃10 [効果2]防御10 [効果3]強靭15
 |
ユーリウス 「今回はちょっと攻めてみたよ。味はどうかな?」 |
布施(747) とカードを交換しました!
竜胆の描かれたカード (アンダークーリング)

リストア を研究しました!(深度2⇒3)
ファーマシー を研究しました!(深度2⇒3)
ファンタジア を研究しました!(深度1⇒2)
ヒーリングソング を習得!
☆ルージィグージィ を習得!
☆初習得ボーナス:各FPが2増加した!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



ユーリウス(117) は 松 を入手!
"ofLOSE"(380) は 杉 を入手!
欠けた器(384) は 杉 を入手!
欠けた器(384) は 毛 を入手!
"ofLOSE"(380) は 美味しい草 を入手!
"ofLOSE"(380) は 毛 を入手!



チナミ区 E-11(隔壁)には移動できません。
チナミ区 F-10(隔壁)には移動できません。
チナミ区 E-11(隔壁)には移動できません。
チナミ区 F-10(隔壁)には移動できません。
チナミ区 E-11(隔壁)には移動できません。
アオイ(1564) をパーティに勧誘しました!
欠けた器(384) をパーティに勧誘しようとしましたが既に背後にいました。
ユーリウス(117) をパーティに勧誘しようとしましたが既に背後にいました。
採集はできませんでした。
- "ofLOSE"(380) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)
- アオイ(1564) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
ノウレット 「またまたこんにちは―――ッ!!」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
 |
エディアン 「わぁこんにちはノウレットさーん! えーと音量音量・・・コンフィグかな?」 |
Cross+Roseの音量を調整する。
 |
エディアン 「よし。・・・・・さて、どうしました?ノウレットちゃん。」 |
 |
ノウレット 「はぁい!今回はロストに関する情報を持ってきましたッ!」 |
 |
エディアン 「おや、てっきりあのざっくりした説明だけなのかと。」 |
 |
ノウレット 「お役に立てそうで嬉しいです!!」 |
 |
エディアン 「よろしくお願いしまーす。」 |
 |
ノウレット 「ではでは・・・・・ジャーンッ!こちらがロスト情報ですよー!!」 |
Cross+Roseにロスト7名の容姿と簡単なプロフィールが映し出される。

アンドリュウ
紫の瞳、金髪ドレッドヘア。
体格の良い気さくなお兄さん。
料理好き、エプロン姿が何か似合っている。
体格の良い気さくなお兄さん。
料理好き、エプロン姿が何か似合っている。

ロジエッタ
水色の瞳、菫色の長髪。
大人しそうな小さな女の子。
黒いドレスを身につけ、男の子の人形を大事そうに抱えている。
大人しそうな小さな女の子。
黒いドレスを身につけ、男の子の人形を大事そうに抱えている。

アルメシア
金の瞳、白い短髪。褐色肌。
戦闘狂で活動的な少女。
鎧を身につけハルバードを持っている。
戦闘狂で活動的な少女。
鎧を身につけハルバードを持っている。

ソージロウ
黒い瞳、黒いもじゃもじゃ頭。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。
常にダルそうな猫背で長身の青年。
デニムパンツにTシャツを着ている。

フレディオ
碧眼、ロマンスグレーの短髪。
彫りが深く、男前な老翁。
黒のライダースジャケットを身に着けている。
彫りが深く、男前な老翁。
黒のライダースジャケットを身に着けている。

ミヨチン
茶色の瞳、桜色のロング巻き髪。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。
ハイパーサイキックパワーJK。
着崩し制服コーデ。

マッドスマイル
乱れた長い黒緑色の髪。
両手に紅いナイフを持ち、
猟奇的な笑顔の仮面をつけている。
両手に紅いナイフを持ち、
猟奇的な笑顔の仮面をつけている。
 |
エディアン 「なるほど、いろんなかたがいますねぇ。 彼らの願望を叶えることで影響力を得て、ハザマで強くもなれるんですか。」 |
 |
エディアン 「どこにいるかとか、願望の内容とか、そういうのは分かります?」 |
 |
ノウレット 「ごめんなさい!私はCross+Roseの妖精なのでよくわかりません! Cross+Roseに送られた情報を伝えることしか・・・・・」 |
 |
エディアン 「むむむ・・・・・頑張って見つけないといけませんねぇ。 こう、ロストには頭にマークが付いてるとか・・・そういうのは?」 |
 |
ノウレット 「ごめんなさい!私はCross+Roseの妖精なのでハザマのことはよくわかりません! Cross+Roseに送られた情報を伝えることしか・・・・・」 |
 |
エディアン 「・・・・・システムメッセージなのかなこれ。 ・・・ノウレットちゃんの好きなものは?」 |
 |
ノウレット 「肉ですッ!!」 |
 |
エディアン 「・・・嫌いなものは?」 |
 |
ノウレット 「白南海さん、です・・・・・」 |
 |
エディアン 「・・・・・さては何かしましたね、彼。」 |
 |
エディアン 「では、ロスト情報もそこそこ気にしながら進めていきましょう!」 |
 |
ノウレット 「ファイトでーすッ!!」 |
チャットが閉じられる――







Strayeders
|
 |
エアプ達のおでんパーティ
|


ENo.380
アーク兄弟



双子の兄弟。
怪盗 フレシ=アーク=ロイヤル 弟
25歳/172.4cm/49kg/怪盗
吃音持ちの成年。人見知り。
極度の暑がりなため、いつでも同じような格好である。
薬科大卒だが、普通科のメツ校一年生として入学し直した。
異能:『 』
―――
闇探偵 オブルス=アーク=パラダイス 兄
25歳/168.1cm/43kg/闇探偵
死にたがりの成年。舌っ足らずでかなり頭が悪い。
胸の大きな女性がすきだが、女性が苦手。
高校中退だが、メツ校一年生として入学し直した。
異能:紫煙を操る……?
―――
管理スポット
SpotNo.187[オオキタ区 F-9] 廃遊園地《パラダイス》
http://lisge.com/ib/talk.php?s=187
```
ENo.380 アーク兄弟
予備世界の住人。
何者かによりアカシックレコードが改竄され、予備世界の住人が大量消費された中の生き残り。
消費された者たちは影だけになり。残された者たちは自分たちがただの予備、代替品であることを知る。
改竄した者へ。正常な世界で生きるもう一人の自分へ。
自分たちは何者かを問うために、イバラシティへやってきた。
```
怪盗 フレシ=アーク=ロイヤル 弟
25歳/172.4cm/49kg/怪盗
吃音持ちの成年。人見知り。
極度の暑がりなため、いつでも同じような格好である。
薬科大卒だが、普通科のメツ校一年生として入学し直した。
異能:『 』
―――
闇探偵 オブルス=アーク=パラダイス 兄
25歳/168.1cm/43kg/闇探偵
死にたがりの成年。舌っ足らずでかなり頭が悪い。
胸の大きな女性がすきだが、女性が苦手。
高校中退だが、メツ校一年生として入学し直した。
異能:紫煙を操る……?
―――
管理スポット
SpotNo.187[オオキタ区 F-9] 廃遊園地《パラダイス》
http://lisge.com/ib/talk.php?s=187
```
ENo.380 アーク兄弟
予備世界の住人。
何者かによりアカシックレコードが改竄され、予備世界の住人が大量消費された中の生き残り。
消費された者たちは影だけになり。残された者たちは自分たちがただの予備、代替品であることを知る。
改竄した者へ。正常な世界で生きるもう一人の自分へ。
自分たちは何者かを問うために、イバラシティへやってきた。
```
27 / 30
203 PS
チナミ区
E-10
E-10





































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 鉄扇 | 武器 | 30 | 攻撃10 | - | - | 【射程1】 |
| 5 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]防御10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) | |||
| 6 | 刀 | 武器 | 52 | 活力10 | - | - | 【射程3】 |
| 7 | 杉 | 素材 | 20 | [武器]疫15(LV30)[防具]放盲15(LV25)[装飾]舞盲10(LV20) | |||
| 8 | おでん(パイナップル入り) | 料理 | 60 | 攻撃10 | 防御10 | 強靭15 | |
| 9 | 美味しい草 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV10)[効果2]充填10(LV20)[効果3]増幅10(LV30) | |||
| 10 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 呪術 | 15 | 呪詛/邪気/闇 |
| 響鳴 | 15 | 歌唱/音楽/振動 |
| 武器 | 25 | 武器作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 6 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 6 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| カース | 5 | 0 | 50 | 敵:闇撃&束縛 | |
| エチュード | 5 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) | |
| カースワード | 5 | 0 | 130 | 敵全:闇撃&腐食 | |
| ダークネス | 5 | 0 | 100 | 敵列:闇撃&盲目 | |
| ビブラート | 5 | 0 | 120 | 敵全2:粗雑SP攻撃 | |
| ディプラヴィティ | 5 | 0 | 160 | 敵列:闇撃&自堕落LV増 | |
| ヒーリングソング | 5 | 0 | 120 | 味全:HP増+魅了 | |
| ルージィグージィ | 5 | 0 | 160 | 敵:精確SP闇撃&HL減(2T) |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 闇の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:呪術LVが高いほど闇特性・耐性増 |
最大EP[20]



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
無垢なる旅人 (スイープ) |
0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
|
The Moon (ダウンフォール) |
0 | 130 | 敵傷:闇撃 | |
|
竜胆の描かれたカード (アンダークーリング) |
0 | 70 | 敵傷:水撃+自:腐食+3D6が15以上なら凍結LV増 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]ファーマシー | [ 1 ]レジスト | [ 3 ]リストア |
| [ 2 ]ファンタジア |

PL / ぶるごにゅ