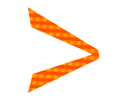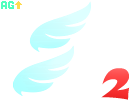<< 0:00~1:00




墨染ふみと稲井とわが出会ったのは、ふみがすでにアンジニティへ落とされた後だった。
ふみは何か強力な異能を持っているわけではないが、密かにアンジニティと外の世界を行き来していた。
アンジニティは正しく『強大な檻』だ。抜け出すことなど、ふみの能力程度では未来永劫かなわないだろう。
事実ふみは『抜け出していた』のではない。
ふみのわずかな一部が密かに染み出し、動きまわり、眺め回っていたにすぎない。
そのさなか、たまたま己の好みである状況に遭遇し、嬉しさのあまり、ほんの少しだけ手を出した。
だからそれは――ふみがとわに対してしたことは――どこまで行ってもふみの自己満足、言ってしまえば単なる独りよがりでしかないのだが、それがとわにとって得難い手助けであったこと、その後の『道』への間接的な手引きであったことも、また事実であった。
それらは、ふみにとってもとわにとっても、少しだけ楽しい記憶だ。――記憶だった。
それがいま。
そろってワールドスワップに巻き込まれたせいか、ふみの記憶もとわの記憶も見事改竄の憂き目にあった。
(ふたりの偽りの記憶に齟齬が生じていないことが何より恐ろしい、とふみは思う。)
イバラシティにおけるふみの記憶では、『異世界で新興宗教に軟禁されていたとわと知り合い、色々と調査に協力してくれたとわが逃亡する際、少し力を貸した在野の異能研究者』、それが己だ。
その後、謝礼代わりにとわの避難先であるイバラシティへ同行させてもらい(何しろいろんな異能がある世界と聞いたもので)、内心小躍りしながら地道な研究を続けている……、と思っていた。
イバラシティにおける、ふみの自己自認だ。
それがどうだろう。
ハザマに入り込み、アンジニティの記憶が戻れば、己はすでにずいぶん前から人ではなかった。
在野の異能研究者であることは、間違いではない。ふみは自分のことを常にそう思っている。
しかしその研究――というよりも好奇心のため、全てを捨て、引き替えて、人ならぬ罪と業の果てにアンジニティへと落ち、落ちた先でも変わらぬ自分がさらに裏道と禁忌を用いて、とわのいた異世界に偶然染み出していた存在だったことは、きれいさっぱり忘れていた。
初めてハザマでとわに対面したとき、何となくその旨を説明したところ、いささか驚かれたが――あの無表情のとわの目がまん丸になっていたし、そばにいた巨大なセキセイインコの青年の目も、いつもに増してまん丸になっていた――、ふみがとわたちに対して敵意がないことを示せば、まるでイバラシティにいるのと同じ態度で接してくれたことには、ふみの方が驚いた。
「いやあ、私、自分で言うのもなんだけど、随分な人でなしだと思うんだが」
「へえ、そう。でも、別に……。わたしには、あと、誠哉にも、酷いことをしてないから」
「とわがそういうなら、まあ、僕も……。実際、あのときは助かったしねえ」
「ねえ」
「これからも、僕たちやイバラシティに変なことをするつもりはないんでしょ?」
「ああ、ないよ」
「だったら、やっぱり、わたしは別に。……それより、ふみ、アンジニティにすんでいて、イバラの味方をしてしまって、良いの?」
「あ! そうだよ。良いの?」
「……君たち、私が言うのもおかしいけど、ハザマでは十分気をつけるんだよ……」
穏やかな会話だった。
ふみが置かれている――これからも置かれ続ける現状からすれば、嘘のように穏やかな会話だった。
イバラシティに戻れば忘れてしまうけれど、ハザマに戻るたびに思い出す会話だ。
これが、ふみがイバラシティ侵略に反対する理由では、決してない。ふみは最初から反対の立場をとっていた。
ふみはどこまで行っても身勝手で、異常で、今後も己の興味と好奇心のみを追求し、欲望を優先し、そのためなら恐ろしく底なしに何もかもを引き替えてしまうだろう。
ふみがイバラ侵略に反対するのは『普通の人に発現する異能が己の好みで、多元異世界等における多種多様な種族が強大な異能を保有し争い合っていることが当たり前の状態に興味がない』からだ。
だから、同じくイバラ侵略反対の立場をとったボルドールから声をかけられた時に頷いたし、侵略に嫌悪感を持っていたノーヴァルと併せて三人で組むことにも同意した。
ふみは、自分の欲望を優先し、イバラシティの侵略に反対している。



ENo.1386 ボルドール とのやりとり










呪術LV を 5 UP!(LV10⇒15、-5CP)
装飾LV を 5 UP!(LV20⇒25、-5CP)
ノジコ(456) とカードを交換しました!
ノジコのおうえん! (デストロイ)


カース を研究しました!(深度0⇒1)
ダークネス を研究しました!(深度0⇒1)
タクシックゾーン を研究しました!(深度0⇒1)
闇の祝福 を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



ボルドール(1386) は パンの耳 を入手!
ノーヴァル(1387) は パンの耳 を入手!
墨染ふみ(1388) は パンの耳 を入手!
墨染ふみ(1388) は ねばねば を入手!
ボルドール(1386) は 羽 を入手!
ノーヴァル(1387) は 毛 を入手!



ボルドール(1386) に移動を委ねました。
チナミ区 J-4(道路)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 K-4(道路)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 L-4(道路)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 M-4(道路)に移動!(体調22⇒21)
チナミ区 N-4(草原)に移動!(体調21⇒20)






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。
元気よく両手両足を伸ばし空間を飛びまわる!
・・・姿を現すことなく、女性のような声が伝わる。
ため息のような音が漏れる。
声はそこで終わる。
チャットが閉じられる――









「……それはさておき、君のその『異能』。……調べさせてもらえないかなあ?」
墨染ふみ(すみぞめふみ)
男。30代。
ひょろりとした中背痩躯。
いつ散髪に行ったのか定かでない適当に伸びた黒髪。
手には小さなノートとペンがあり、いつも何かをメモしている。
自称、在野の異能研究者。
研究者というか単に『異能への好奇心を抑えられない変態』。
他者の異能を知りたくて堪らず、知る機会や方法があれば違法なことでも無視するタイプだった。
真も、善も、徳も、全て引き換えて。
結果、アンジニティに堕ちた。
アンジニティで初めて『普通の人に発現する異能』が己の好みであって、多元異世界等における『多種多様な種族が強大な異能を保有し争い合っていることが当たり前の状態』にはあまり興味がないことを自覚する。
それもありイバラシティを侵略することには反対の立場だが、染み付いた『己の欲望優先』気質は抜けていない。
《異能》
『墨に染める』
ハザマでの姿は、外見はほぼそのままだが髪が異様に長く伸びる。髪はうねうねと興味のある異能を調べに行こうとする。
また髪は自在に操ることが出来るので、それを攻防に利用する。これが異能『墨に染める』。
イバラシティでは、己の興味がありそうな異能を察知して、つんつんとそのその方向に髪が引っ張られる・抜けた髪が相手についていく・しばらくの間であれば髪の居場所がだいたい分かる等、どうにもストーカー向きの異能。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー











































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [スキル]OK.



墨染ふみと稲井とわが出会ったのは、ふみがすでにアンジニティへ落とされた後だった。
ふみは何か強力な異能を持っているわけではないが、密かにアンジニティと外の世界を行き来していた。
アンジニティは正しく『強大な檻』だ。抜け出すことなど、ふみの能力程度では未来永劫かなわないだろう。
事実ふみは『抜け出していた』のではない。
ふみのわずかな一部が密かに染み出し、動きまわり、眺め回っていたにすぎない。
そのさなか、たまたま己の好みである状況に遭遇し、嬉しさのあまり、ほんの少しだけ手を出した。
だからそれは――ふみがとわに対してしたことは――どこまで行ってもふみの自己満足、言ってしまえば単なる独りよがりでしかないのだが、それがとわにとって得難い手助けであったこと、その後の『道』への間接的な手引きであったことも、また事実であった。
それらは、ふみにとってもとわにとっても、少しだけ楽しい記憶だ。――記憶だった。
それがいま。
そろってワールドスワップに巻き込まれたせいか、ふみの記憶もとわの記憶も見事改竄の憂き目にあった。
(ふたりの偽りの記憶に齟齬が生じていないことが何より恐ろしい、とふみは思う。)
イバラシティにおけるふみの記憶では、『異世界で新興宗教に軟禁されていたとわと知り合い、色々と調査に協力してくれたとわが逃亡する際、少し力を貸した在野の異能研究者』、それが己だ。
その後、謝礼代わりにとわの避難先であるイバラシティへ同行させてもらい(何しろいろんな異能がある世界と聞いたもので)、内心小躍りしながら地道な研究を続けている……、と思っていた。
イバラシティにおける、ふみの自己自認だ。
それがどうだろう。
ハザマに入り込み、アンジニティの記憶が戻れば、己はすでにずいぶん前から人ではなかった。
在野の異能研究者であることは、間違いではない。ふみは自分のことを常にそう思っている。
しかしその研究――というよりも好奇心のため、全てを捨て、引き替えて、人ならぬ罪と業の果てにアンジニティへと落ち、落ちた先でも変わらぬ自分がさらに裏道と禁忌を用いて、とわのいた異世界に偶然染み出していた存在だったことは、きれいさっぱり忘れていた。
初めてハザマでとわに対面したとき、何となくその旨を説明したところ、いささか驚かれたが――あの無表情のとわの目がまん丸になっていたし、そばにいた巨大なセキセイインコの青年の目も、いつもに増してまん丸になっていた――、ふみがとわたちに対して敵意がないことを示せば、まるでイバラシティにいるのと同じ態度で接してくれたことには、ふみの方が驚いた。
「いやあ、私、自分で言うのもなんだけど、随分な人でなしだと思うんだが」
「へえ、そう。でも、別に……。わたしには、あと、誠哉にも、酷いことをしてないから」
「とわがそういうなら、まあ、僕も……。実際、あのときは助かったしねえ」
「ねえ」
「これからも、僕たちやイバラシティに変なことをするつもりはないんでしょ?」
「ああ、ないよ」
「だったら、やっぱり、わたしは別に。……それより、ふみ、アンジニティにすんでいて、イバラの味方をしてしまって、良いの?」
「あ! そうだよ。良いの?」
「……君たち、私が言うのもおかしいけど、ハザマでは十分気をつけるんだよ……」
穏やかな会話だった。
ふみが置かれている――これからも置かれ続ける現状からすれば、嘘のように穏やかな会話だった。
イバラシティに戻れば忘れてしまうけれど、ハザマに戻るたびに思い出す会話だ。
これが、ふみがイバラシティ侵略に反対する理由では、決してない。ふみは最初から反対の立場をとっていた。
ふみはどこまで行っても身勝手で、異常で、今後も己の興味と好奇心のみを追求し、欲望を優先し、そのためなら恐ろしく底なしに何もかもを引き替えてしまうだろう。
ふみがイバラ侵略に反対するのは『普通の人に発現する異能が己の好みで、多元異世界等における多種多様な種族が強大な異能を保有し争い合っていることが当たり前の状態に興味がない』からだ。
だから、同じくイバラ侵略反対の立場をとったボルドールから声をかけられた時に頷いたし、侵略に嫌悪感を持っていたノーヴァルと併せて三人で組むことにも同意した。
ふみは、自分の欲望を優先し、イバラシティの侵略に反対している。



ENo.1386 ボルドール とのやりとり
| ▲ |
| ||
| |||
| |||



 |
ボルドール 「素材、マジで落ちてねーな……今回で拾えるか?」 |
 |
ノーヴァル 「…」 |





呪術LV を 5 UP!(LV10⇒15、-5CP)
装飾LV を 5 UP!(LV20⇒25、-5CP)
ノジコ(456) とカードを交換しました!
ノジコのおうえん! (デストロイ)

カース を研究しました!(深度0⇒1)
ダークネス を研究しました!(深度0⇒1)
タクシックゾーン を研究しました!(深度0⇒1)
闇の祝福 を習得!
◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!



ボルドール(1386) は パンの耳 を入手!
ノーヴァル(1387) は パンの耳 を入手!
墨染ふみ(1388) は パンの耳 を入手!
墨染ふみ(1388) は ねばねば を入手!
ボルドール(1386) は 羽 を入手!
ノーヴァル(1387) は 毛 を入手!



ボルドール(1386) に移動を委ねました。
チナミ区 J-4(道路)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 K-4(道路)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 L-4(道路)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 M-4(道路)に移動!(体調22⇒21)
チナミ区 N-4(草原)に移動!(体調21⇒20)






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
「おっくれまして―――ッ!!」 |

ノウレット
ショートの金髪に橙色の瞳の少女。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。
 |
ノウレット 「はぁい!はじめましてーッ!!私はここCross+Roseの管・・・妖精! ノウレットでーっす!!皆さんよろしくおねがいしまぁーっす!!」 |
チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。
 |
白南海 「・・・・・。管理用アバター・・・ですかね。」 |
 |
ノウレット 「元気ないですねーッ!!死んでるんですかーッ!!!!」 |
 |
白南海 「貴方よりは生物的かと思いますよ。 ドライバーさんと同じく、ハザマの機能ってやつですか。」 |
 |
ノウレット 「機能なんて言わないでください!妖精です!!妖精なんですッ!!」 |
 |
ノウレット 「Cross+Roseのことで分からないことは何でも聞いてくださいねーっ!!」 |
 |
白南海 「あぁ、どっちかというとアレですか。"お前を消す方法"・・・みたいな。」 |
 |
ノウレット 「よくご存知でーっ!!そうです!多分それでーっす!!!!」 |
元気よく両手両足を伸ばし空間を飛びまわる!
 |
ノウレット 「えーっとそれでですねーッ!!」 |
 |
ノウレット 「・・・・・あれっ 創造主さまからメッセージが!」 |
 |
白南海 「おや、なんでしょうね。」 |
・・・姿を現すことなく、女性のような声が伝わる。
 |
声 「――お疲れ様です御二方。役目を担ってくれて、感謝しています。」 |
 |
白南海 「担うも何も、強制ですけどね。報酬でも頂きたいくらいで。」 |
 |
声 「そしてハザマに招かれた方々、申し訳ありません。」 |
 |
声 「・・・・・・・・・」 |
 |
声 「このワールドスワップという能力は、招かれた方々全員が――ザザッ・・・」 |
 |
声 「――失われ、そう――ザザッ・・・――周期的に発動する、能力というより・・・」 |
 |
声 「制御不能な・・・呪いのよう。今までに発動した数度、自分への利は・・・ない。」 |
 |
声 「・・・・・・・・・」 |
ため息のような音が漏れる。
 |
声 「どうか、自らが自らであ―― ザザッ・・・」 |
 |
白南海 「・・・・・?」 |
 |
声 「――ザザッ・・・・・・・・己の世界のために、争え。」 |
声はそこで終わる。
 |
白南海 「何だか変なふうに終わりましたねぇ。」 |
 |
ノウレット 「そうですかーっ!!?そうでもないですよーっ!!!?」 |
 |
白南海 「どーも、嫌な予感が・・・ ・・・いや、十分嫌な状況ではありますがね。」 |
 |
白南海 「・・・・・ま、とりあえずやれることやるだけっすね。」 |
チャットが閉じられる――





ENo.1388
墨染ふみ



「……それはさておき、君のその『異能』。……調べさせてもらえないかなあ?」
墨染ふみ(すみぞめふみ)
男。30代。
ひょろりとした中背痩躯。
いつ散髪に行ったのか定かでない適当に伸びた黒髪。
手には小さなノートとペンがあり、いつも何かをメモしている。
自称、在野の異能研究者。
研究者というか単に『異能への好奇心を抑えられない変態』。
他者の異能を知りたくて堪らず、知る機会や方法があれば違法なことでも無視するタイプだった。
真も、善も、徳も、全て引き換えて。
結果、アンジニティに堕ちた。
アンジニティで初めて『普通の人に発現する異能』が己の好みであって、多元異世界等における『多種多様な種族が強大な異能を保有し争い合っていることが当たり前の状態』にはあまり興味がないことを自覚する。
それもありイバラシティを侵略することには反対の立場だが、染み付いた『己の欲望優先』気質は抜けていない。
《異能》
『墨に染める』
ハザマでの姿は、外見はほぼそのままだが髪が異様に長く伸びる。髪はうねうねと興味のある異能を調べに行こうとする。
また髪は自在に操ることが出来るので、それを攻防に利用する。これが異能『墨に染める』。
イバラシティでは、己の興味がありそうな異能を察知して、つんつんとそのその方向に髪が引っ張られる・抜けた髪が相手についていく・しばらくの間であれば髪の居場所がだいたい分かる等、どうにもストーカー向きの異能。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
20 / 30
43 PS
チナミ区
N-4
N-4





































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | ささべ | 武器 | 30 | 攻撃10 | - | - | 【射程3】 |
| 5 | かん | 防具 | 30 | 防御10 | - | - | |
| 6 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||
| 8 | パンの耳 | 食材 | 10 | [効果1]体力10(LV10)[効果2]幸運10(LV20)[効果3]活力10(LV30) | |||
| 9 | ねばねば | 素材 | 10 | [武器]衰弱10(LV25)[防具]強靭10(LV20)[装飾]耐狂10(LV20) | |||
[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 呪術 | 15 | 呪詛/邪気/闇 |
| 領域 | 10 | 範囲/法則/結界 |
| 装飾 | 25 | 装飾作製に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |
| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |
| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |
| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |
| カース | 5 | 0 | 50 | 敵:闇撃&束縛 | |
| リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |
| デッドライン | 5 | 0 | 100 | 敵列:闇痛撃 | |
| ダークネス | 5 | 0 | 100 | 敵列:闇撃&盲目 | |
| ガーディアン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+味傷:護衛 | |
| タクシックゾーン | 5 | 0 | 140 | 敵全:猛毒 |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |
| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |
| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |
| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |
| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |
| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |
| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |
| 闇の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:呪術LVが高いほど闇特性・耐性増 |
最大EP[20]





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 1 ]カース | [ 1 ]ダークネス | [ 1 ]タクシックゾーン |

PL / 白灰