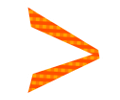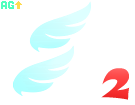<< 2:00>> 4:00




十手小町と黒須御月は小学生の低学年時より面識があり、よく遊んだり……とまでも行かないが
クラス替えまでの一時的な友人のような薄っぺらい縁でもなく、ごくごく当たり前のように過ごしていた仲だった。
御月は控えめで知的なようでいるのにどこか、特に同じくらいの子供達の傍から見れば奇妙な子供だった。
世間ずれしている。 この言葉で表すには相応しくないが狂っているというのもあまりに極端だ。
最初のうちは些細なちょっとした嫌がらせ程度の。 どうとでもないことだったのに
――4年前。 イバラシティのとある学校、御月と……十手小町の運命に大きく影響する出来事は起こってしまった。
ぱりん というつんざくような破壊音をその合図として。
苦痛の声、血 血 床と顔と手に鋭利な破片が突き刺さりその光景を広げてゆく。
だというのに程なく周りのがやの音がゆっくりな一瞬のうちに悲鳴をもみ消すのだ。
ざわざわ ざわざわ
席替え、席決めのくじ引き。
クラスの者がこみごみと一か所に集まっているときを狙ったように
花瓶が落ちて割れ、御月の顔はそこにたたきつけられた。
ざっくりと酷い傷……顔を抑え声にならない声をあげる御月はなんとか保健室へと運び込まれた。
一針二針、三針……十針十一針……
幸い目は無事ではあったが額から鼻周りを何針も、何針も縫わねばならなかった。
病院から戻った御月はとあるクラスメイトを指して、犯人だといった。
――誰も信じる者はいなかった。
十手小町は見ていた。 なのに、彼女が意を決してそれを証明しようども同じこと。
せっかちで早とちりがちでどじを踏みがちで素直で抜けている
そんな小町の言葉は親しいおかしな友人の妄想じみた狂言をかばうものでしかない。
大人というものはそう判断するし、子供というものは残酷だ。
以前からそのようなことがあったとて、大ごとになればどちらも不利で面倒くさいから。
彼らはなあなあにする。 それっぽい理由を見つけたり、あるいは真実を疑ったり捻じ曲げたり。
そんな中、啖呵を切ったのは御月自身だった。
御月を守ろうと不正を明らかにしようとしていた小町に対し、溜まっていた
重くてじりじりと焼けるような感情はひどく爆発した。
爆発して御月を内側から焼き尽くしてじりじりと溶かし尽くして。
御月がその感情のままに投げたものはひどくどしりと音をたてた。
小町はなにもいうことができず足がすくんでしまった。
"エリ"
その日を境に御月は学校に来ることはなくなり、御月の母である英里も程なくして倒れた。
十手小町は決意した。 このようなことを見過ごしたくない、起こしたくない。
率先して彼女は人の規律や和を仕切る立場であろうとするようになった。
あれから御月は人を信じなくなった。
ただ生きるために必要な仮面だけを残した冷たい亡骸のように、必要な時以外笑うこともない。
それでも十手小町は変わらず、寧ろ以前よりも御月に積極的に接し続けた。
相良伊橋高校への入学を進めたのも小町であった。
御月の親の経営していた店から比較的近いのもあり、比較的融通の利きそうな校風を掲げているのもあり。
入試に受かり、特進クラスへと行ったものの。 程なくして御月はぱったりとクラスへ顔を出さなくなった。
どうして と小町が問えば御月は残酷なことを口ずさむのだ。

小町は、制服のリボンを黄色に変え、同じように黄色のリボンで髪を留めるようになった。
私は小町、十手小町。 それを証明するためだけに……
あの悍ましい人の成れの果てを見た十手小町は足早にその場所を去っていた
ただその亡骸は丁寧に地に下ろし無惨な部分を覆って、手を合わせ……
そのくらいしか今の彼女にはしてやることができなかったが
そうせずにはいられない。 それが十手小町という人だ。
磔にされ苦痛にゆがんだような形相をしていた亡骸は心なしか安らかに横たわっていた。
それを物影でじっと眺める者が一人。
血のついた裁ち鋏をいかにもですと片手に持った人ならざる耳と目をもつその邪悪。
十手小町が去ったあと、彼女が優しく手をさしのべた亡骸を再び冒涜する。
クロノス……線の細い成人男性の姿を模った人ならざるもの。
彼こそ……黒須御月の正体。アンジニティへと追放された咎人。
亡骸を素材にして服を作るように、布を足したりなんかもしてそれを縫っていく。
愉快そうに口を歪ませている。
彼は仕立て屋。 服を作り繕う職人にして芸術家。
そして彼の種族を追害して殺した人間という種族が大嫌いだ。
悪魔は夜な夜な復讐という名の快楽殺人を行う。
作品を生み出すたび、過去の苦しみがほんのわずかの間薄れる……
この麻薬こそが彼をアンジニティへと誘った。
再び磔にされた"それ"は何も言えもできもしないのに悲痛さを訴えているようだった。
縫い合わされた口は苦痛の声をあげることはかなわない。
突き刺された腕からももう血が流れることもない。
はじめから何の音もなかった。
悪魔が去った後も変わらず磔の"作品"は静かな路地で人を待ち続けることだろう。
明日、悪魔の凶刃にかかるのはイバラシティのものかアンジニティのものか。



特に何もしませんでした。










具現LV を 5 DOWN。(LV10⇒5、+5CP、-5FP)
武器LV を 2 DOWN。(LV4⇒2、+2CP、-2FP)
使役LV を 2 UP!(LV3⇒5、-2CP)
解析LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
付加LV を 1 UP!(LV19⇒20、-1CP)
ItemNo.4 御用の十手 に ItemNo.9 白樺 を付加しました!
⇒ 御用の十手/武器:強さ20/[効果1]攻撃10 [効果2]活力10 [効果3]-【射程1】/特殊アイテム
レイナ(634) とカードを交換しました!
ブリーズエッジ (アイスバインド)

プリディクション を習得!
ヒンダー を習得!
クリエイト:ガトリング を習得!
ドローバック を習得!



チナミ区 F-10(森林)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 F-11(森林)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 G-11(道路)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 H-11(道路)に移動!(体調22⇒21)
撫子(347) をパーティに勧誘しました!






―― ハザマ時間が紡がれる。

花の香りと共に、Cross+Rose内が梅の花に囲まれた売店のある景色に変わる。
何か甘い香りが漂っている売店のほうを見ると――


静かに何かを作っているふたり。
榊の質問に、反応する。
そう言って焼いた団子を隣りに渡す。
団子にもっさりとアンコを乗せ、榊に手渡す。
両手でピースサインを出すカグハ。
ピースサインを下ろそうとするカオリ。
Cross+Rose内の景色が元に戻り、ふたりの姿も消える。
チャットが閉じられる――
















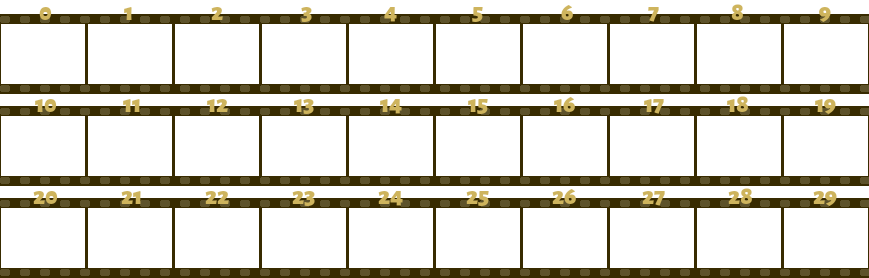





































異能・生産
アクティブ
パッシブ








[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



十手小町と黒須御月は小学生の低学年時より面識があり、よく遊んだり……とまでも行かないが
クラス替えまでの一時的な友人のような薄っぺらい縁でもなく、ごくごく当たり前のように過ごしていた仲だった。
御月は控えめで知的なようでいるのにどこか、特に同じくらいの子供達の傍から見れば奇妙な子供だった。
世間ずれしている。 この言葉で表すには相応しくないが狂っているというのもあまりに極端だ。
最初のうちは些細なちょっとした嫌がらせ程度の。 どうとでもないことだったのに
――4年前。 イバラシティのとある学校、御月と……十手小町の運命に大きく影響する出来事は起こってしまった。
ぱりん というつんざくような破壊音をその合図として。
 |
黒須御月 「ああああああああああああああ!!!!」 |
苦痛の声、血 血 床と顔と手に鋭利な破片が突き刺さりその光景を広げてゆく。
だというのに程なく周りのがやの音がゆっくりな一瞬のうちに悲鳴をもみ消すのだ。
ざわざわ ざわざわ
席替え、席決めのくじ引き。
クラスの者がこみごみと一か所に集まっているときを狙ったように
花瓶が落ちて割れ、御月の顔はそこにたたきつけられた。
ざっくりと酷い傷……顔を抑え声にならない声をあげる御月はなんとか保健室へと運び込まれた。
一針二針、三針……十針十一針……
幸い目は無事ではあったが額から鼻周りを何針も、何針も縫わねばならなかった。
病院から戻った御月はとあるクラスメイトを指して、犯人だといった。
――誰も信じる者はいなかった。
十手小町は見ていた。 なのに、彼女が意を決してそれを証明しようども同じこと。
せっかちで早とちりがちでどじを踏みがちで素直で抜けている
そんな小町の言葉は親しいおかしな友人の妄想じみた狂言をかばうものでしかない。
大人というものはそう判断するし、子供というものは残酷だ。
以前からそのようなことがあったとて、大ごとになればどちらも不利で面倒くさいから。
彼らはなあなあにする。 それっぽい理由を見つけたり、あるいは真実を疑ったり捻じ曲げたり。
 |
黒須御月 「もう……いいよ」 |
そんな中、啖呵を切ったのは御月自身だった。
 |
黒須御月 「どうにも、ならないんだよ…… 見苦しいよ……見苦しいだけだよ、無駄だよ……!!」 |
御月を守ろうと不正を明らかにしようとしていた小町に対し、溜まっていた
重くてじりじりと焼けるような感情はひどく爆発した。
爆発して御月を内側から焼き尽くしてじりじりと溶かし尽くして。
御月がその感情のままに投げたものはひどくどしりと音をたてた。
小町はなにもいうことができず足がすくんでしまった。
"エリ"
その日を境に御月は学校に来ることはなくなり、御月の母である英里も程なくして倒れた。
十手小町は決意した。 このようなことを見過ごしたくない、起こしたくない。
率先して彼女は人の規律や和を仕切る立場であろうとするようになった。
あれから御月は人を信じなくなった。
ただ生きるために必要な仮面だけを残した冷たい亡骸のように、必要な時以外笑うこともない。
それでも十手小町は変わらず、寧ろ以前よりも御月に積極的に接し続けた。
相良伊橋高校への入学を進めたのも小町であった。
御月の親の経営していた店から比較的近いのもあり、比較的融通の利きそうな校風を掲げているのもあり。
入試に受かり、特進クラスへと行ったものの。 程なくして御月はぱったりとクラスへ顔を出さなくなった。
どうして と小町が問えば御月は残酷なことを口ずさむのだ。

小町は、制服のリボンを黄色に変え、同じように黄色のリボンで髪を留めるようになった。
私は小町、十手小町。 それを証明するためだけに……
あの悍ましい人の成れの果てを見た十手小町は足早にその場所を去っていた
ただその亡骸は丁寧に地に下ろし無惨な部分を覆って、手を合わせ……
そのくらいしか今の彼女にはしてやることができなかったが
そうせずにはいられない。 それが十手小町という人だ。
磔にされ苦痛にゆがんだような形相をしていた亡骸は心なしか安らかに横たわっていた。
それを物影でじっと眺める者が一人。
 |
クロノス 「折角の僕の芸術を台無しにしてくれて」 |
十手小町が去ったあと、彼女が優しく手をさしのべた亡骸を再び冒涜する。
 |
クロノス 「折角の作品、こんなに醜くされちゃあ堪らない……」 |
彼こそ……黒須御月の正体。アンジニティへと追放された咎人。
亡骸を素材にして服を作るように、布を足したりなんかもしてそれを縫っていく。
愉快そうに口を歪ませている。
彼は仕立て屋。 服を作り繕う職人にして芸術家。
そして彼の種族を追害して殺した人間という種族が大嫌いだ。
悪魔は夜な夜な復讐という名の快楽殺人を行う。
作品を生み出すたび、過去の苦しみがほんのわずかの間薄れる……
この麻薬こそが彼をアンジニティへと誘った。
再び磔にされた"それ"は何も言えもできもしないのに悲痛さを訴えているようだった。
縫い合わされた口は苦痛の声をあげることはかなわない。
突き刺された腕からももう血が流れることもない。
はじめから何の音もなかった。
悪魔が去った後も変わらず磔の"作品"は静かな路地で人を待ち続けることだろう。
明日、悪魔の凶刃にかかるのはイバラシティのものかアンジニティのものか。



特に何もしませんでした。









具現LV を 5 DOWN。(LV10⇒5、+5CP、-5FP)
武器LV を 2 DOWN。(LV4⇒2、+2CP、-2FP)
使役LV を 2 UP!(LV3⇒5、-2CP)
解析LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)
付加LV を 1 UP!(LV19⇒20、-1CP)
ItemNo.4 御用の十手 に ItemNo.9 白樺 を付加しました!
⇒ 御用の十手/武器:強さ20/[効果1]攻撃10 [効果2]活力10 [効果3]-【射程1】/特殊アイテム
レイナ(634) とカードを交換しました!
ブリーズエッジ (アイスバインド)

プリディクション を習得!
ヒンダー を習得!
クリエイト:ガトリング を習得!
ドローバック を習得!



チナミ区 F-10(森林)に移動!(体調25⇒24)
チナミ区 F-11(森林)に移動!(体調24⇒23)
チナミ区 G-11(道路)に移動!(体調23⇒22)
チナミ区 H-11(道路)に移動!(体調22⇒21)
撫子(347) をパーティに勧誘しました!






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
榊 「・・・おや?何だか良い香りが。」 |

榊
黒髪に蒼い瞳、黒スーツ。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
花の香りと共に、Cross+Rose内が梅の花に囲まれた売店のある景色に変わる。
 |
榊 「香りまで再現、高機能な代物ですねぇ。」 |
 |
榊 「しかし香るのは、花の匂いだけではないような・・・」 |
何か甘い香りが漂っている売店のほうを見ると――

カオリ
黒髪のサイドテールに赤い瞳、橙色の着物の少女。
カグハと瓜二つの顔をしている。
カグハと瓜二つの顔をしている。

カグハ
黒髪のサイドテールに赤い瞳、桃色の着物の少女。
カオリと瓜二つの顔をしている。
カオリと瓜二つの顔をしている。
静かに何かを作っているふたり。
 |
榊 「ごきげんよう。それは・・・・・団子、ですか?」 |
榊の質問に、反応する。
 |
カグハ 「団子いっちょーう。180円。カオリちゃん、具。」 |
そう言って焼いた団子を隣りに渡す。
 |
カオリ 「はいはいカグハちゃん。はいアンコ奮発しちゃうよー!!」 |
団子にもっさりとアンコを乗せ、榊に手渡す。
 |
榊 「おお・・・これはこれは美味しそうな!ありがとうございます。」 |
 |
カオリ 「・・・・・って、チャットでやってもねー。無意味だねぇ!無意味っ!!」 |
 |
カグハ 「ホンモノ食べたきゃおいでませ梅楽園。」 |
両手でピースサインを出すカグハ。
 |
カオリ 「いやまだお店準備中だから!来てもやってないよー!! 材料創りはカグハちゃんなんだから自分で知ってるでしょ!!」 |
ピースサインを下ろそうとするカオリ。
Cross+Rose内の景色が元に戻り、ふたりの姿も消える。
 |
榊 「いただいた団子は・・・・・これは無味ッ!!味の再現は難しいのですかね。」 |
 |
榊 「まだ準備中のようですが、こんな世界の中でも美味しいものをいただけるとは。 いつか立ち寄ってみるとしましょう。」 |
チャットが閉じられる――







ENo.97
十手 小町



ジッテ コマチ 16歳 血液型 O 身長162cm)
相良伊橋高校 2年4組 風紀委員。
アンジニティの侵攻の件を受け、異変が起こっていないか
できる範囲でイバラシティ内をパトロールをしている。
風紀委員といえど堅苦しい形上の決まりよりも
義理や人としての正義を大事にしており、
通学途中で困っている人を助けたが故に
朝のHRに遅刻することもしばしばある。
困った人は捨て置けず非常に頑固で見て見ぬふりは以ての外。
納豆が好物で特に茶碗に盛ったフワフワに混ぜた納豆に
白米をかけた『ご飯かけ納豆』を好んで食す。
時折手に持っている十手は【異能:御用改メ】の具現化体。
これを振るうことで相手の行動に様々な制限を課すことができる。
現実世界では具現化体が現れないため、
できるのは相手をひるませたり瞬間的に動きを止めたりする程度。
【サブ】
店員(黒須 御月 -クロス ミヅキ 16歳 血液型 AB 身長167cm)
相良伊橋高校 2年1組 不登校、休学中。
入院した母親の代わりに洋菓子店を営業している。
十手小町とは高校以前からの長い付き合いらしく、
しょっちゅう尋ねられている。
【異能:ハウス・ワーカー】
家事に対する才能、あるいはそれを越したもの。
これをほぼ製菓に使用しているため、実質その類の異能のようであるが
掃除洗濯裁縫その他にも対応する。 無論、特化型の者にはかなわない程度のもの。
長い前髪の下には非常に大きな傷痕がある。
----というのがイバラシティ上でのカバーストーリー。
クロノス (身長167cm)
悪魔と呼ばれ追害された種族、魔族。
人間をはじめとした他種族への憎しみ、嫌悪はやがて彼を猟奇殺人へと駆り立てた。
昼の顔は服を縫う仕立て屋。 夜の顔は人を縫う仕立て屋。
被害にあった亡骸を自らの"作品"と呼称する。
相良伊橋高校 2年4組 風紀委員。
アンジニティの侵攻の件を受け、異変が起こっていないか
できる範囲でイバラシティ内をパトロールをしている。
風紀委員といえど堅苦しい形上の決まりよりも
義理や人としての正義を大事にしており、
通学途中で困っている人を助けたが故に
朝のHRに遅刻することもしばしばある。
困った人は捨て置けず非常に頑固で見て見ぬふりは以ての外。
納豆が好物で特に茶碗に盛ったフワフワに混ぜた納豆に
白米をかけた『ご飯かけ納豆』を好んで食す。
時折手に持っている十手は【異能:御用改メ】の具現化体。
これを振るうことで相手の行動に様々な制限を課すことができる。
現実世界では具現化体が現れないため、
できるのは相手をひるませたり瞬間的に動きを止めたりする程度。
【サブ】
店員(黒須 御月 -クロス ミヅキ 16歳 血液型 AB 身長167cm)
相良伊橋高校 2年1組 不登校、休学中。
入院した母親の代わりに洋菓子店を営業している。
十手小町とは高校以前からの長い付き合いらしく、
しょっちゅう尋ねられている。
【異能:ハウス・ワーカー】
家事に対する才能、あるいはそれを越したもの。
これをほぼ製菓に使用しているため、実質その類の異能のようであるが
掃除洗濯裁縫その他にも対応する。 無論、特化型の者にはかなわない程度のもの。
長い前髪の下には非常に大きな傷痕がある。
----というのがイバラシティ上でのカバーストーリー。
クロノス (身長167cm)
悪魔と呼ばれ追害された種族、魔族。
人間をはじめとした他種族への憎しみ、嫌悪はやがて彼を猟奇殺人へと駆り立てた。
昼の顔は服を縫う仕立て屋。 夜の顔は人を縫う仕立て屋。
被害にあった亡骸を自らの"作品"と呼称する。
21 / 30
97 PS
チナミ区
H-11
H-11





































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材・消耗の場合は詳細等) |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |
| 4 | 御用の十手 | 武器 | 20 | 攻撃10 | 活力10 | - | 【射程1】 |
| 5 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]敏捷10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) | |||
| 6 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV5)[効果2]活力10(LV10)[効果3]鎮痛10(LV15) | |||
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV5)[効果2]活力10(LV10)[効果3]鎮痛10(LV15) | |||
| 8 | 駄石 | 素材 | 10 | [武器]活力10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]器用10(LV20) | |||
| 9 | |||||||
| 10 | 駄木 | 素材 | 10 | [武器]体力10(LV20)[防具]防御10(LV20)[装飾]攻撃10(LV20) | |||
| 11 | 白樺 | 素材 | 15 | [武器]活力10(LV10)[防具]活力15(LV20)[装飾]活力10(LV10) | |||
| 12 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]加速10(LV25)[装飾]敏捷10(LV10) | |||
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 制約 | 10 | 拘束/罠/リスク |
| 具現 | 5 | 創造/召喚 |
| 使役 | 5 | エイド/援護 |
| 解析 | 5 | 精確/対策/装置 |
| 武器 | 2 | 武器作製に影響 |
| 付加 | 20 | 装備品への素材の付加に影響 |
アクティブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| ピンポイント | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |
| クイック | 6 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |
| ヒール | 5 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |
| リストリクト | 5 | 0 | 60 | 敵:DX・AG減(2T) | |
| クリエイト:タライ | 5 | 0 | 40 | 敵:攻撃&朦朧・混乱 | |
| ラッシュ | 5 | 0 | 60 | 味全:連続増 | |
| プリディクション | 5 | 0 | 60 | 味列:AG増(3T) | |
| クリエイト:チェーン | 5 | 0 | 60 | 敵3:攻撃&束縛+自:AG減(1T) | |
| ラテントパワー | 5 | 0 | 60 | 味傷:守護+重傷ならAT・DX増(1T) | |
| ヒンダー | 5 | 0 | 40 | 自:炎上・凍結・束縛防御増+次受ダメ減 | |
| クリエイト:ケージ | 5 | 0 | 60 | 敵:束縛 | |
| クリエイト:ガトリング | 5 | 0 | 110 | 味:貫撃LV増 | |
| ドローバック | 5 | 0 | 80 | 敵:痛撃&麻痺 | |
| キャプチャー | 5 | 0 | 70 | 自:束縛LV増 | |
| ワイヤートラップ | 5 | 0 | 140 | 敵:罠《ワイヤー》LV増 ※【被攻撃回避後】自5:精確攻撃(1回のみ) |
パッシブ
| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |
| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |
| 活力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |
| 体力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |
| 治癒 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |
| 幸運 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 | |
| 召喚強化 | 5 | 2 | 0 | 【常時】異能『具現』のLVに応じて、自身の召喚するNPCが強化 |



| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |
|
マリオネット (ブレイク) |
0 | 20 | 敵:攻撃 | |
| 決1 |
エキサイト (エキサイト) |
0 | 40 | 敵:攻撃+自:AT増(1T) |
|
ブリーズエッジ (アイスバインド) |
0 | 80 | 敵:水撃&凍結 |



| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |
| [ 3 ]クリエイト:チェーン | [ 3 ]イレイザー |

PL / めヰり屋