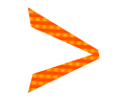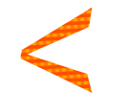<< 0:00>> 2:00




かつて、ヴァリシュワールは一人の人間の騎士であった。
幼い頃から騎士であった父に憧れていた彼は、成人になった頃には身体も精神も既に立派な騎士となっていた。
それは父親による厳しい特訓の成果でもあったが、それよりも大きかったのは幼馴染である花売りの少女「マナ」の存在であった。
彼と一緒に涙を流し、彼と一緒に笑ってくれる――彼の全てを包み込んでくれる「マナ」の優しさに励まされ、ヴァリシュワールは何度でも泥の中から這い上がることができた。
「今は弱っちいかもしれない……でも、こんだけ守って貰ってるんだ。弱いままじゃいられない。将来は絶対、俺がお前のこと守ってやるからさ」
ヴァリシュワールは、このことを口癖のように彼女に向けて繰り返した。それは彼女への約束であり、騎士の初めての「誓い」であった。
時を経て。
誰に対しても紳士的であり、それでいて父親似の豪快さも受け継いだ彼は、多くの人々から愛される騎士となった。
彼は、人間でありながら魔族の軍勢相手に一歩も引くことなく、一騎当千の活躍をする。そんな無双の騎士となっていた。
彼の国への忠義は厚く、想い人である「マナ」への愛は純粋なものであった。
大きな国への誇りと小さな女への愛が、彼の剣を輝かせるたった二つの信条であった。
彼の運命を変える一陣の風は、ある日何の前触れもなく吹き込んできた。
精鋭の騎士達を集め、当時の魔族の頭を討つ――国を守る為の最後の大きな戦いを終えた彼は、凱旋の途中で残酷な報せを受ける。
「城が魔族に攻め落とされ、騎士は全滅、王も討ち取られた。俺たちの国が滅んだ」と。
その報せは、またたく間に凱旋ムードの騎士達を絶望の淵へと追いやった。
残酷な仕打ちはそれだけに留まらなかった。
ヴァリシュワールの故郷の村も、魔族の軍の進行によって蹂躙され、生存者は皆無である、というのだ。
彼が人生最大の戦いに赴いている間に、彼の大事なもの全てが魔族の軍によって飲み込まれてしまったのだ。
この時、騎士達は皆地に伏して、目から赤い血の涙を流して悲しみに打ち震えていたという。
守るべきものも、帰るべき場所も、全て失ってしまったのだ。
皆がまだ立ち上がれない中、ヴァリシュワールは一人立ったまま空を見上げていた。
そうして、自らの故郷へ続く道を、よろよろと歩きだした。
理性では待ち人など居ないと理解していても、心が彼をそのように動かしたのだった。
自分の目で見なければ、信じることなどできなかった。
辿り着いた先は、瓦礫と肉塊の山であった。
ここに来て初めて、ヴァリシュワールは膝から崩折れて地に伏した。
彼が流した血の涙はその場に小さな水溜りを作るほどであった。
彼の胸に宿った黒い炎は、地を震わせ風を歪ませるほどであった。
ひとしきり涙を流した後。
顔を上げたヴァリシュワールは、その血溜まりに映る影を見た。
白い髪をした少女の姿をした影は言った。
「全てを失った哀れな騎士よ。
復讐の炎に身を燃やす剣よ。
愛すべき怨念を纏いし鎧よ。
気に入った。気に入った。
ここに契約を交わそうではないか。
私は冥府の女神。
お前の失った最愛の者をこの世に取り戻してやろう。
代わりに、お前には今日より1000年の間、私の為の騎士となって貰う」
と。
ヴァリシュワールは迷わなかった。
「黒き血を流す冷徹の女神よ。
愛すべきマナを今一度この世に呼び戻せるのであれば、俺は1000年だろうが2000年だろうが
地獄に落ちてやろう。どのような責め苦も受けよう」
ヴァリシュワールは立ち上がった。立ち上がり、長年握り締めてきた王国の騎士としての誇りを、地へと放った。
甲高くも鈍い金属音が所々砕けた石畳を打った。
「ああ。ああ。そうだろうな、お前は迷わずそう口にするだろう。
そう――だからこそ、気に入った」
女神はヴァリシュワールに微笑みかけた。その微笑みはどこまでも温情と愛に満ちていて、それでいてどこまでも冷たく歪んだそれであった。
女神は、ヴァリシュワールとマナに一夜だけ時間を与えた。
現世で共に過ごす最後の時間。全てを守りきれなかったことを謝罪するヴァリシュワールを、彼女はそれでも否定しなかった。
ただただ、涙と一緒に温かい微笑みを投げかけた。
国も剣も。
故郷も家族も。
誇りも栄光も。
全てを失ったヴァリシュワールだったが、生ある最後の時間に、目の前の――たった一握りの愛だけは、取り戻すことができた。
長い間、二人は語り合った。
全てを語るには一夜はあまりに短すぎたが、それでも別れを告げるには十二分であった。
どこまでも、穏やかな別れであった。
そうして、二人の最後の朝が訪れる。
「時間だ、ヴァリシュワール」
「待っていたぞ、冥府の女神よ」
彼の元に現れた女神は、大きな鎌を手にしていた。
彼女は歪んだ笑みを浮かべると、その鎌を大きく振りかぶり、ヴァリシュワールの首を切り落とした。
かつて無双を誇った騎士の首は、冥府の鎌を前に呆気なく落とされた。
――その日。
一人の輝ける王国の騎士が死に、一つの忌まわしき冥府の騎士が生まれた。
一片の慈悲なく、命を刈り取る魔の騎士。
正しく死を迎えさせる為に、全てを平等に切り捨て裁く死の化身。
老人も、若者も、女子供ですら。
それぞれに「定められた時間」と共に彼は現れて、その命を刈り取っていった。
次第に感情は枯れ果て、身も心も異形と化していった彼であったが、
一握りの愛だけは決して離すことがなかった。
そして今日も彼は、屍を踏み砕きながら伝承の闇を駆ける。
いつか血に塗れたこの鎧を脱ぎ去って、もう一度「マナ」に会う為に。
駆けて、駆けて、駆けて。
そうして、気づけば――――彼は、見知らぬ世界に居た。



特に何もしませんでした。








駄木(50 PS)を購入しました。
武術LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
呪術LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
合成LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)
ItemNo.5 不思議な石 に ItemNo.6 不思議な食材 を合成し、何か柔らかい物体 に変化させました!
⇒ 何か柔らかい物体/素材:強さ10/[武器]祝福10(LV20)[防具]鎮痛10(LV20)[装飾]防御10(LV20)/特殊アイテム
こがも(131) とカードを交換しました!
こわすぜ~! (ブレイク)

エキサイト を習得!
ダークネス を習得!
カースバインド を習得!
イレイザー を習得!
エナジードレイン を習得!
シャドウエッジ を習得!



次元タクシーに乗り『チナミ区 E-5:出発地』に転送されました!
チナミ区 F-5(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 G-5(草原)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 H-5(草原)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 I-5(道路)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 J-5(道路)に移動!(体調26⇒25)
シグ(712) をパーティに勧誘しました!
アルさん(595) をパーティに勧誘しました!
暁美(55) をパーティに勧誘しました!






―― ハザマ時間が紡がれる。

チャットで時間が伝えられる。
榊の前に1台のタクシーが止まり、窓が開く。

帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。
窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。
榊からのチャットが閉じられる――
























































異能・生産
アクティブ
パッシブ







[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.



かつて、ヴァリシュワールは一人の人間の騎士であった。
幼い頃から騎士であった父に憧れていた彼は、成人になった頃には身体も精神も既に立派な騎士となっていた。
それは父親による厳しい特訓の成果でもあったが、それよりも大きかったのは幼馴染である花売りの少女「マナ」の存在であった。
彼と一緒に涙を流し、彼と一緒に笑ってくれる――彼の全てを包み込んでくれる「マナ」の優しさに励まされ、ヴァリシュワールは何度でも泥の中から這い上がることができた。
「今は弱っちいかもしれない……でも、こんだけ守って貰ってるんだ。弱いままじゃいられない。将来は絶対、俺がお前のこと守ってやるからさ」
ヴァリシュワールは、このことを口癖のように彼女に向けて繰り返した。それは彼女への約束であり、騎士の初めての「誓い」であった。
時を経て。
誰に対しても紳士的であり、それでいて父親似の豪快さも受け継いだ彼は、多くの人々から愛される騎士となった。
彼は、人間でありながら魔族の軍勢相手に一歩も引くことなく、一騎当千の活躍をする。そんな無双の騎士となっていた。
彼の国への忠義は厚く、想い人である「マナ」への愛は純粋なものであった。
大きな国への誇りと小さな女への愛が、彼の剣を輝かせるたった二つの信条であった。
彼の運命を変える一陣の風は、ある日何の前触れもなく吹き込んできた。
精鋭の騎士達を集め、当時の魔族の頭を討つ――国を守る為の最後の大きな戦いを終えた彼は、凱旋の途中で残酷な報せを受ける。
「城が魔族に攻め落とされ、騎士は全滅、王も討ち取られた。俺たちの国が滅んだ」と。
その報せは、またたく間に凱旋ムードの騎士達を絶望の淵へと追いやった。
残酷な仕打ちはそれだけに留まらなかった。
ヴァリシュワールの故郷の村も、魔族の軍の進行によって蹂躙され、生存者は皆無である、というのだ。
彼が人生最大の戦いに赴いている間に、彼の大事なもの全てが魔族の軍によって飲み込まれてしまったのだ。
この時、騎士達は皆地に伏して、目から赤い血の涙を流して悲しみに打ち震えていたという。
守るべきものも、帰るべき場所も、全て失ってしまったのだ。
皆がまだ立ち上がれない中、ヴァリシュワールは一人立ったまま空を見上げていた。
そうして、自らの故郷へ続く道を、よろよろと歩きだした。
理性では待ち人など居ないと理解していても、心が彼をそのように動かしたのだった。
自分の目で見なければ、信じることなどできなかった。
辿り着いた先は、瓦礫と肉塊の山であった。
ここに来て初めて、ヴァリシュワールは膝から崩折れて地に伏した。
彼が流した血の涙はその場に小さな水溜りを作るほどであった。
彼の胸に宿った黒い炎は、地を震わせ風を歪ませるほどであった。
ひとしきり涙を流した後。
顔を上げたヴァリシュワールは、その血溜まりに映る影を見た。
白い髪をした少女の姿をした影は言った。
「全てを失った哀れな騎士よ。
復讐の炎に身を燃やす剣よ。
愛すべき怨念を纏いし鎧よ。
気に入った。気に入った。
ここに契約を交わそうではないか。
私は冥府の女神。
お前の失った最愛の者をこの世に取り戻してやろう。
代わりに、お前には今日より1000年の間、私の為の騎士となって貰う」
と。
ヴァリシュワールは迷わなかった。
「黒き血を流す冷徹の女神よ。
愛すべきマナを今一度この世に呼び戻せるのであれば、俺は1000年だろうが2000年だろうが
地獄に落ちてやろう。どのような責め苦も受けよう」
ヴァリシュワールは立ち上がった。立ち上がり、長年握り締めてきた王国の騎士としての誇りを、地へと放った。
甲高くも鈍い金属音が所々砕けた石畳を打った。
「ああ。ああ。そうだろうな、お前は迷わずそう口にするだろう。
そう――だからこそ、気に入った」
女神はヴァリシュワールに微笑みかけた。その微笑みはどこまでも温情と愛に満ちていて、それでいてどこまでも冷たく歪んだそれであった。
女神は、ヴァリシュワールとマナに一夜だけ時間を与えた。
現世で共に過ごす最後の時間。全てを守りきれなかったことを謝罪するヴァリシュワールを、彼女はそれでも否定しなかった。
ただただ、涙と一緒に温かい微笑みを投げかけた。
国も剣も。
故郷も家族も。
誇りも栄光も。
全てを失ったヴァリシュワールだったが、生ある最後の時間に、目の前の――たった一握りの愛だけは、取り戻すことができた。
長い間、二人は語り合った。
全てを語るには一夜はあまりに短すぎたが、それでも別れを告げるには十二分であった。
どこまでも、穏やかな別れであった。
そうして、二人の最後の朝が訪れる。
「時間だ、ヴァリシュワール」
「待っていたぞ、冥府の女神よ」
彼の元に現れた女神は、大きな鎌を手にしていた。
彼女は歪んだ笑みを浮かべると、その鎌を大きく振りかぶり、ヴァリシュワールの首を切り落とした。
かつて無双を誇った騎士の首は、冥府の鎌を前に呆気なく落とされた。
――その日。
一人の輝ける王国の騎士が死に、一つの忌まわしき冥府の騎士が生まれた。
一片の慈悲なく、命を刈り取る魔の騎士。
正しく死を迎えさせる為に、全てを平等に切り捨て裁く死の化身。
老人も、若者も、女子供ですら。
それぞれに「定められた時間」と共に彼は現れて、その命を刈り取っていった。
次第に感情は枯れ果て、身も心も異形と化していった彼であったが、
一握りの愛だけは決して離すことがなかった。
そして今日も彼は、屍を踏み砕きながら伝承の闇を駆ける。
いつか血に塗れたこの鎧を脱ぎ去って、もう一度「マナ」に会う為に。
駆けて、駆けて、駆けて。
そうして、気づけば――――彼は、見知らぬ世界に居た。



特に何もしませんでした。







駄木(50 PS)を購入しました。
武術LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
呪術LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)
合成LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)
ItemNo.5 不思議な石 に ItemNo.6 不思議な食材 を合成し、何か柔らかい物体 に変化させました!
⇒ 何か柔らかい物体/素材:強さ10/[武器]祝福10(LV20)[防具]鎮痛10(LV20)[装飾]防御10(LV20)/特殊アイテム
こがも(131) とカードを交換しました!
こわすぜ~! (ブレイク)

エキサイト を習得!
ダークネス を習得!
カースバインド を習得!
イレイザー を習得!
エナジードレイン を習得!
シャドウエッジ を習得!



次元タクシーに乗り『チナミ区 E-5:出発地』に転送されました!
チナミ区 F-5(道路)に移動!(体調30⇒29)
チナミ区 G-5(草原)に移動!(体調29⇒28)
チナミ区 H-5(草原)に移動!(体調28⇒27)
チナミ区 I-5(道路)に移動!(体調27⇒26)
チナミ区 J-5(道路)に移動!(体調26⇒25)
シグ(712) をパーティに勧誘しました!
アルさん(595) をパーティに勧誘しました!
暁美(55) をパーティに勧誘しました!






―― ハザマ時間が紡がれる。
 |
榊 「・・・60分!区切り目ですねぇッ!!」 |

榊
黒髪に蒼い瞳、黒スーツ。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。
整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。
チャットで時間が伝えられる。
 |
榊 「先程の戦闘、観察させていただきました。 ざっくりと戦闘不能を目指せば良いようで。」 |
 |
榊 「・・・おっと、お呼びしていた方が来たようです。 我々が今後お世話になる方をご紹介しましょう!」 |
榊の前に1台のタクシーが止まり、窓が開く。

ドライバーさん
次元タクシーの運転手。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。
イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。
 |
ドライバーさん 「どーも、『次元タクシー』の運転役だ。よろしく。」 |
帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。
 |
榊 「こちら、中立に位置する方のようでして。 陣営に関係なくお手伝いいただけるとのこと。」 |
 |
ドライバーさん 「中立っつーかなぁ・・・。俺もタクシーも同じのが沢山"在る"んでな。 面倒なんで人と思わずハザマの機能の一部とでも思ってくれ。」 |
 |
ドライバーさん 「ま・・・チェックポイントとかの行き来の際にゃ、へいタクシーの一声を。じゃあな。」 |
窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。
 |
榊 「何だか似た雰囲気の方が身近にいたような・・・ あの方もタクシー運転手が似合いそうです。」 |
 |
榊 「ともあれ開幕ですねぇぇッ!!!! じゃんじゃん打倒していくとしましょうッ!!!!」 |
榊からのチャットが閉じられる――







かみがかり
|
 |
狂人共の行軍記
|


ENo.1559
ヴァリシュワール



コンビニで酒を買っては飲んだくれている謎の外国人。
どうやら絵描きをしているらしいが、詳細は不明。
全てに絶望をしたような、暗い顔をしている。
そんな彼の異能は、【死を間近に迎える人間の顔が死後の顔に見える】というものである。
――――――――――――――――――――――――――――
彼の正体は、首無し騎士ヴァリシュワールと呼ばれる存在である。彼はイリュジオーム・スティッジと呼ばれる異世界の民間伝承に登場する存在である。
イリュジオーム・スティッジの多くの地域では、子供が親の言うことを聞かない時に「言うこと聞かないと、ヴァリシュワールが来てお前の首を持っていってしまうよ」と言い、言うことを聞かせているという。
親から子へ。そしてその子もやがて親になり、新たな子へ。悪い子供の首を持っていってしまうというヴァリシュワールの伝承は、このようにして数百年の間語り継がれてきた長い歴史がある。
また一部の地域では、老若男女関係なく無慈悲に首を潰して回る忌まわしい死神として恐れられてもいる。
実際の彼は、「定められた時間」を迎えた命を刈り取ることを仕事としている。
つまり、死すべき運命にある者に正しく死を迎えさせる、終わりの運命を告げる冥府よりの使者である。
運命通りの死を与える際には、障害となるあらゆる干渉を退けながら何処までも追跡し、確実に無慈悲な死を与えると言われている。
どうやら絵描きをしているらしいが、詳細は不明。
全てに絶望をしたような、暗い顔をしている。
そんな彼の異能は、【死を間近に迎える人間の顔が死後の顔に見える】というものである。
――――――――――――――――――――――――――――
彼の正体は、首無し騎士ヴァリシュワールと呼ばれる存在である。彼はイリュジオーム・スティッジと呼ばれる異世界の民間伝承に登場する存在である。
イリュジオーム・スティッジの多くの地域では、子供が親の言うことを聞かない時に「言うこと聞かないと、ヴァリシュワールが来てお前の首を持っていってしまうよ」と言い、言うことを聞かせているという。
親から子へ。そしてその子もやがて親になり、新たな子へ。悪い子供の首を持っていってしまうというヴァリシュワールの伝承は、このようにして数百年の間語り継がれてきた長い歴史がある。
また一部の地域では、老若男女関係なく無慈悲に首を潰して回る忌まわしい死神として恐れられてもいる。
実際の彼は、「定められた時間」を迎えた命を刈り取ることを仕事としている。
つまり、死すべき運命にある者に正しく死を迎えさせる、終わりの運命を告げる冥府よりの使者である。
運命通りの死を与える際には、障害となるあらゆる干渉を退けながら何処までも追跡し、確実に無慈悲な死を与えると言われている。
25 / 30
0 PS
チナミ区
J-5
J-5




































| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果等 |
| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]-【射程1】 |
| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |
| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |
| 4 | 不思議な牙 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV5)[防具]防御10(LV5)[装飾]器用10(LV5) |
| 5 | 何か柔らかい物体 | 素材 | 10 | [武器]祝福10(LV20)[防具]鎮痛10(LV20)[装飾]防御10(LV20) |
| 6 | ||||
| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV5)[効果2]活力10(LV10)[効果3]鎮痛10(LV15) |
| 8 | 駄木 | 素材 | 10 | [武器]体力10(LV20)[防具]防御10(LV20)[装飾]攻撃10(LV20) |
最大所持可能数[50]



異能・生産
| 名称 | LV | 説明 |
| 武術 | 10 | 身体/武器/物理 |
| 呪術 | 10 | 呪詛/邪気/闇 |
| 合成 | 20 | 合成に影響。 |
アクティブ
| スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| ブレイク | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 |
| ピンポイント | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 |
| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 |
| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 |
| ヒール | 5 | 0 | 20 | 味傷:HP増 |
| エキサイト | 5 | 0 | 40 | 敵:攻撃+自:AT増(1T) |
| ダークネス | 5 | 0 | 60 | 敵:闇撃&盲目 |
| カースバインド | 5 | 0 | 80 | 敵:闇撃&衰弱 |
| イレイザー | 5 | 0 | 150 | 敵傷:攻撃 |
| エナジードレイン | 5 | 0 | 160 | 敵:闇撃&DF奪取 |
| シャドウエッジ | 5 | 0 | 120 | 敵3:闇撃(対象の領域値[闇]が高いほど威力増) |
パッシブ
| スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |
| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 |
| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 |
| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 |
| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 |
| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 |
| 活力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 |
| 体力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 |
| 治癒 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 |
| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 |
| 幸運 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:運増 |





| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |

PL / 凉丘